| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年01月31日 日曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
99 |
15.10 | 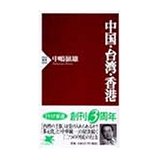 |
中国・台湾・香港 |
中嶋嶺雄 |
PHP新書 |
◎ |
序章 「三つの中国」から「二つの中国」へ 中国に対する日本人の錯覚 ・中国というと「古い国」というイメージを思い浮かべてしまいますが、実はまだ中国はようやく半世紀を経たばかりにすぎません。何百年もつづく王朝の間にいくつかの国々が興亡してきたように、長い中国の歴史からすると、まだまだ歴史の評価に耐え得る中国、すなわち中華人民共和国だとは言えないのです。 不安定な中国社会 ・一九八九年に起こった六・四天安門事件は、民主化を求め、鄧小平独裁という、まさに「人治(人が治める政治)」の体制に対して「法治(法に基づく政治)」を要求した、中国始まって以来の近代的政治意識に目ざめた学生や市民のデモが天安門広場を埋めていたのです。そしてこの建国四十周年の時期には、中国はまさに体制的危機によって、社会主義体制が崩壊するかもしれないという大きな危機に直面していたのです。 台湾に対する過敏な反応 ・中国は現在、江沢民体制の下で、「二十一世紀は中国の世紀」「中国は世界の大国」と言わんばかりに、ある種の覇権国家的な主張をつづけているように思われます。 ・それだけに、米ソ冷戦体制崩壊後の世界の大きな問題としての米中関係があり、米中間は戦略的パートナーシップだということを相互に言わざるを得ないように、米中関係は新しい時代の大きな対立構造だと私は見ています。 「国家と国家の関係」発言 ・日本人のなかには国連信仰が強いために、「国連」というと、すべての国際社会の運営を平等に行っている機関であるかのようにみなされていますけれども、そもそも戦勝大国としての安保常任理事国が拒否権をもっていること自体、今日の民主的な国際組織の運営とは完全に相反していると言えましょう。 第四章 台湾の発展 民主的な成熟した社会 ・蒋経国時代を継承した李登輝総統は、台湾本省人出身の初代総統ですが、あの長い伝統をもつだけに古い体質を備えた中国国民党を、よくもここまで変化させ、台湾全体をアジアでもっとも自由な社会の一つに育て上げたものだと思います。この功績については、歴史が将来、さらに大きな評価を与えることになるでしょう。 ・しかも、中国の統一政策の対象になっているとはいえ、二千二百万台湾民衆の民意はきわめて重くなりつつあり、そう簡単に中国によってコントロールできない社会をつくり上げています。 「二つの中国」 ・従来から李登輝総統の持論は「台湾は独立した主権国家であって、中華民国台湾はすでに主権をもって立派に存在している。だからいまさら台湾独立を宣言する必要もない」というものです。 ・むしろそうした中華民国台湾をいかに中身の濃いものにしていくか、豊かなものにしていくかというところに、台湾の政治改革、社会改革の大きな目標があるのです。 ・改めて考えてみますと、台湾は政治的にも民主主義の制度のもとにきわめて成熟した国家をつくり上げています。総統や副総統も民主的な直接選挙で選ばれる、という体制にまでなっています。 ・そして立法院などのいわゆる国会議員の選挙も、まさに 台湾海峡危機 ・最近の日米ガイドライン(日米防衛協力のための指針)が台湾海峡を含むのかとか、TMD(戦略ミサイル防衛構想)が中国をターゲットにするのではないか、という疑念を中国は表明しています。 ・これらはいずれも安全保障上の抑止の体制であり、中国自身が問題を武力で解決するという方針をやめさえすれば、問題は一切ないはずです。 ・つまり、武力による問題解決という立場をとりつづけている中国の姿勢そのものが問われているのだと言わざるを得ません。 ・とにかく国際社会の出来事を軍事的威圧や武力によって解決しようとする姿勢を転換しないかぎり、中国への信頼性は、本質的には固まらないのです。 第五章 アジアの中の中国 開発独裁による成長 ・経済は成長したけれども、例えばそれに伴って政治的民主化や市民社会的成熟が深まったわけではなかったのです。アジアはその多くが開発独裁であって、国民の知的自由や学問の自由、政治的自由、人権、環境への配慮などを考えてみますと、いずれもヨーロッパやアメリカに比して、きわめて多くの問題を残しています。 ・第一、アジアのなかに自由に言論が行使できる国はいくつあるでしょうか。アジアには多くの国が存在していますが、日本、台湾、インド、そしておくればせながら韓国ぐらいが、言論や民主主義が保証されている国であって、他のアジア諸国はほとんどが独裁体制を敷いてきています。 ・シンガポールやマレーシアも、ピカピカのビルは林立し、大きなハブ空港は次々に建設されるけれども、それはすべて開発独裁だからできるのであって、ここにアジアの大きな問題がある。 社会主義の兄弟国北朝鮮 ・日本がしばしば北朝鮮の脅威、北朝鮮の危険性を封じ込めるために、中国に頼って、あるいは北京をパイプとして北朝鮮を説得しようとしていますが、このような日本の外交姿勢は、根本的に間違っていると思います。 ・つまり、中国は日本の要請で北朝鮮を説得するようなことを絶対にしない、そういう関係としての中国と北朝鮮の関係があるのではないかと思うのです。 ・ここに日本外交の一つの問題があるような気がします。やはりアジアのなかの中国、その中国と北朝鮮はいわば主従関係だと考えなければいけないと思います。 第七章 日本にとっての中国 いい加減な中国の論調 ・原爆に関しては、わが国は実に立派だったと思います。あの原爆被災という凄まじくも恐るべき悲劇を、戦後の日本は反米ナショナリズムの根源には決してしなかったからです。 ・これは、日本人が戦争責任を感じていることの証です。「原爆を落としたのはアメリカだ。だから、アメリカはけしからん」という形で問題を立てていったのではなくて、むしろ日本の軍国主義、軍部の跳梁に対する反省と批判をもって、原爆の悲劇を直視しつつ、それを決して反米ナショナリズムや日本の戦後の対外政策のなかに位置づけてはいないところに、今日の日本の大きな意味、価値があるのです。これこそが重要な点であり、ここにわれわれが立脚すれば、歴史認識の問題は明確に整理できると思います。 謝罪よりもビジョンを提示すべき ・かつて中国で、中国の近代化の失敗の自己責任を問うた作家に、文化大革命のときに悲劇に陥った夏衍という劇作家がいます。中国人自身が一体、近代化にどう対処してきたのか、自らの責任はどうなのかということを問わずに、日本の侵略を主張することは、中国にとっても決して良くない、というのが彼の主張でした。 ・台湾の李登輝総統はかつて私にこう言いました。たまたまその時期は村山首相が東南アジアを訪問していて、ベトナムなどで日本の戦争責任を盛んに謝罪して回っていたときです。そのとき李登輝総統は、 「一体、あの村山首相の姿はなんですか、全く情けない。五十年も前の戦争のことを、アジアを歴訪して頭を下げて謝って回るなんてことは全く必要ない。いま日本にとって必要なのは、日本がこれからどういうビジョンで、どういうリーダーシップによってアジアのリーダーとして責任を取っていくのか、二十一世紀のアジアを日本がどのようなリーダーシップをもって導いていくのか、そういうビジョンこそ日本の首相に求められているのに、その点については何のビジョンももたず、全く哲学もなく、ただ頭を下げて歩いている。これが日本の首相の姿ですか」 と言って、親日的な心情から嘆いていました。 日中関係のタブー ・今回の小渕訪中でも、建国五十周年をお祝いするのは結構ですが、同時に天安門事件十周年であるにもかかわらず、あの悲劇を全くなかったように、一言も中国の人権問題に触れていません。 ・触れること自体がもうタブーになってしまっていて、とてもそんなことは触れることができない、恐る恐るでも言えないような雰囲気をつくってしまったところに、日中関係の大きな問題があるのです。 ・パッテン元香港総督やクリントン大統領は、一方で中国との友好関係を強調しながら、他方では人権問題を堂々と中国側に言っています。 ・何回も何回も繰り返して中国側に言っていかなければならないのです。そういうことさえ日中関係ではタブーになってしまったという日中関係の形成の仕方は、日本外務省、そしてとくに日本の政治家の責任だと思います。 ・台湾海峡が平和で安定していることは、日本にとって死活的に重要な意味をもちます。そして日米ガイドラインは、まさに先般の台湾海峡危機の発展として出てきた面があることはまぎれもない事実だと思います。 江沢民訪日の教訓 ・中国が一方で軍事力を増強しているのに、日本から援助を引き出すために高飛車になるということに対しては、日本政府はきちんとものを言っていかなければなりません。円借款のあり方についても根本的な見直しが必要だと思います。 ・日本が中国に言うべきことはきちんと言っていかないと、中国の指導者はますます日本を見下してしまいます。そもそも中華思想的な立場からすれば、日本は中国の属国ですから、そうした秩序観からすれば日本をほとんど評価していません。 あとがき ・解決が難しく思われる中国と台湾の統一の問題も、要は今日の中国が、台湾民衆にとって自らすすんで一緒になりたいような国になっていないところに最大のカギがあるのです。 ・中国に返還された香港は、大変残念なことに、その繁栄を中国自身の手で奪われ、損なわれつつあるように思われます。 |