| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年01月29日 金曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
103 |
15.10 |
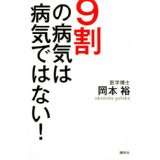 |
9割の病気は病気ではない |
岡本 裕 |
講談社 |
◎ |
そもそも……まえがき ・日本の医療は、“ウソの病気”には異常なほど寛容であるくせに、がんや難病などの“ホントの病気”に対しては非常に不親切なのです。 第一章 思いつきのように医者を増やしても? 医者が増えると病人も増える? ・医者が増えても、本当に必要な場所での医者不足の解消には決してつながらない。 ・医者が増えると、確実に医療費だけは増えることになる。 ・今までも、医者は一方的に増え続けています。しかし、みなさんご承知のように、病気は減るどころか増えるばかりで、病人は増えるいっぽうなのです。もちろん医療費は高騰し続けています。つまり、医者を増やして病気を減らすという目論見が、いかに机上の空論であるかを、歴史はすでに証明しているのです。 ・医者が増えると、医療費は高騰し、私たちの負担は増える一方。また、増えた医者の分だけパイ(分け前)も増やす必要がありますので、病人を増やさなければいけません。 ではなぜ、医者不足と世間では叫ばれているのか ・外来患者の10人に9人は、おしなべて来なくてもいい人たちです。救急外来の現場も例外ではありません。 ・しかし、医療側には来なくていい患者を断ることは出来ません。 ・一つには来るものは拒んではいけないという法律上の縛りが医者にはあるのです。まったくどうでもいいような、とうてい病気とは言えないような状態であっても、つまりどんな些細なことであっても、患者が診察を求めてくれば、医者はむげに追い返すことができないのです。それは医師法で厳格に規定されているルールなのです。 ・つまり、どうでもいい患者さんも診なくてはいけないこともあり、見かけ上、医者が不足しているように見えるだけなのです。 ・二つ目には、医者は「ウソの病気」をたくさん見なければ生活がままならないという、今の「診療報酬制度(今の日本の医療は、国が料金をすべて決めています。その価格を診療報酬点数といいます。1点=10円)の問題もあるのです。 ・つまり、一人の患者さんをゆっくりと診るということが許されないシステムになっているのです。じっくりとゆっくりと診ていては、とたんに経営する病院は破産の憂き目を見たり、勤務医なら病院をクビになったりしてしまいます。 ・なんのことはないのです。医者がホントの病気を丁寧に診るだけで十分生活ができるよう、報酬の仕組み(価格設定)を少し手直しすればすむことなのです。そうすれば、医者不足などはたちどころに解消されるのです。 ・もちろんそれと同時に、「ウソの病気」に関しては、報酬点数を削減するか、ゼロにする(要するに国民の税金で賄うのをやめる。そうすれば私たち国民の負担も軽くなる)か、とにかくなんとかしなくては国の財源がパンクしてしまいます。 第二章 恐ろしいニセ病 ウソの病気が多すぎる ・ウソの病気を改めて定義するとすれば、 「医者がかかわってもかかわらなくても自分で治せる病気」 のことを指します。 ・メタボリックシンドロームなどがその典型ですが、すこし知識と智慧があれば、実は誰でも十分自分の力で治すことが出来ます。したがって、「医者を必要としない病気」ということになるのです。だからニセ病です。 ・ホントの病気というのは、 「医者がかかわらなくては治らないか、医者がかかわると格段に治る確率が高まる病気」 のことを指します。その典型はがんや難病なのです。 ・言い方を換えますと、 ● ウソの病気とは――命になんらかかわらない病気 ● ホントの病気とは――ややもすれば命に直結してしまう病気 ・メタボリックシンドロームのそもそものはじまりは、内臓に脂肪がたまることです。 なぜ内臓に脂肪がたまるのか? 何も難しくありません。食べすぎて運動しないからです。それ以外に原因はありません。 ・だから、 「ただの食べすぎ+運動不足」 というネーミングにしておけば、誰も病気と錯覚することなく、 「だったら食べすぎをやめて、すこしは身体を動かさなくちゃ」 と思うだけで、すむのです。そうすれば、医者が忙しくなることもなく、医療費が高騰することもないはずです。 おいしい患者は命を縮める ・基本的には薬はすべて毒なのです。 ・「薬は常用するものではない」 ということが往々にして忘れ去られています。薬はできるだけ短期に限って用いるべきものなのです。それが薬の安全な使い方なのです。 ・薬はなべて免疫力を低下させます。つまり自己治癒力を低下させるということなのです。 ・依存心が高じると自己治癒力は低下してしまうのだと思います。 第三章 いざ、病気仕分け ホントの病気だけに仕分ける ・特に進行したがんから生還した人たちのほとんどは、3大治療(手術、放射線、抗がん剤)だけでは足りないと述べていますし、現に3大治療のほかにも、食事療法をはじめ、自然療法、中医薬、気功、ヨガ・・・・・・など、さまざまな治療法を併用しながら治癒率を高めているのが現状です。進行したがんで、3大治療だけで治った人は、私の知る限りでは極めてまれなのです。 診療報酬点数も仕分けよう ・国があえて皆保険制度を設け、診療報酬点数(公定価格)をつけたのは、本来は、ホントの病気になった場合に限ってセーフティーネットを設け、診療のチャンスを公平に、しかも低負担で国民に提供しましょうという崇高な理念があったからなのです。 ・しかしながら、ウソの病気にまで点数を割り当て、みんなで治療費を負担するというのは、その崇高な理念にはまったくそぐわないものです。ウソの病気にまで点数をつけ、みんながそれを負担しているために、医療費が高騰し、保険制度が崩壊しつつあるというのが現状なのです。 ・ふつうの人の気持ちとして、自分も負担しているんだから、元を取ろうという姑息な意識も働いてしまいます。自腹を切るならともかく、少ない負担で診療を受けることができるなら、医者にかかっておこうか、薬をもらっておこうかという心理も当然働くかと思います。 第四章 病気仕分けのメリット 「医原病」の恐怖 ・医原病とは、医者にかかったために、それが原因で病気になってしまうことを指します。 ・そもそも医療にはリスクが付き物です。そのリスクを承知のうえで、それでも得られるかもしれないメリットのほうが格段に大きいと見込まれる時にだけ、期間限定的に活用する「インフラ」が医療なのです。 ・つまり、医者は警察と同じように、すばらしいインフラだととらえるといいと思うのです。できれば一生お世話にならないほうがいいに決まっているけれど、それほど注意していたとしても、万が一ということも無きにしもあらず。そんな時のためのインフラなのだと位置づければ納得できるのではないでしょうか。 ・元気で長生きを望むならば、できるだけ自己治癒力を高めておいたほうが得策です。 ・自助努力を怠り、常に医者任せ、薬任せにしていると、自分の体の声が聞こえなくなってしまいます。 身体は折に触れ、私たちにイエローカードや、時にはレッドカードを発してくれます。 「疲れすぎていますよ」 「働きすぎですよ」 「運動不足ですよ」 「食べすぎですよ」 などなど、そんな身体の声に耳を傾ける時間も、時には必要だと思うのです。 薄利多売は矛盾 ・儲けを意識したとたんに、それは医療ではなくなる。 第五章 どこから先ががホントの病気? 「不定愁訴」はイエローカード ・身体がだるい、重い、頭が重い、すっきりしない、寝覚めが悪い、食欲がない、眼がかすむ、肩が凝る、腰が痛い、膝が痛い、眠れない、便秘が続く、お腹が張る、冷える、顔色がすぐれない、意欲が出ない、気分がすぐれない・・・・・・などなど。 これらは専門用語で ・不定愁訴は一言でいえば、私たちへのありがたいイエローカードなのです。身体が少し疲れていますよ、無理がかかっていますよ、あるいは自己治癒力が低下していますよという親切な警告なのです。 みんなが「がん患者」 ・厳密に言うと、みなさんはすでにがん患者なのです。 なぜなら、みなさんの身体では、毎日およそ数千個のがん細胞が生まれているとされているからなのです。 しかしみなさんは、がん患者という自覚などありません。 それは毎日、みなさん自身の自己治癒力のおかげで、日々生まれたがん細胞が、日々壊されているからです。 つまり、病人であるみなさんは毎日、病気が悪化しながらも、自己治癒力のおかげで日々、病気が持ち直して、事なきを得ているわけなのです。 第六章 ストレスと病気 もともと人間は病気になりにくい? ・私たちの身体には、変化を少なくしようとする、できるだけ日常の平穏を保とうとする大きな力が備わっています。これを医学の専門用語では「ホメオスターシス」と呼んでいますが、日本語では「恒常性」と訳されています。 その名のとおり、身体をいつも同じ状態に保っておこうとする力なのです。その力のおかげで、私たちはつつがなく命を長く保つことができるということになっているのです。 第七章 ストレス上手が命を救う 「NO WANT SOSO」 ・サバイバル(がんから生還した人)を果す人とそうでない人の差は何か・・・・・・。もちろん、生き方を変えた、生活習慣を変えたということがその答えになるのですが、もう少し突き詰めてみると、 「NO WANT SOSO」なのです。 ● 嫌なことはきっぱりと「NO」と言う。 ● 自分のしたいことをする。 ● 何事もあまり突き詰めない。 ・この、「NO WANT SOSO」は、一言で言うと過保護からの脱却、すなわち「自立」だと私はとらえています。もう少しくだいて言えば、 「これでいいのだ!」 ということになるのかもしれません。いい意味での開き直りの境地だと思います。 第八章 すぐできる、元気で長生き5つのポイント 侮れない生活リズム ・最初のポイントは「1日のリズム」です。 いい「1日のリズム」は、がん治療のすばらしい特効薬なのです。 「食べて動けて眠れれば人は死なない」 深呼吸(腹式呼吸)の効用 ・2番目のポイントは「深呼吸(腹式呼吸)」です。 浅い呼吸の弊害 ● 交感神経が優位になる。 ● 低酸素状態になる。 ● 血行不良になる。 ● 低体温になる。 プチ断食のススメ ・3番目のポイントは食生活です。 忘れてならない天然ベースサプリメント ・4つ目のポイントは、栄養を確保するために、ベースの「天然サプリメント」を活用するということです。 “オプティマヘルス”とは 健康志向の高い高い米国で広がっている健康観で、単に生命を維持するだけでなく、ベストな状態で維持しようというものです。簡単にいえば、「人生の坂道をできるだけ緩やかに使用」という考え方です。 薬は毒 ・5番目のポイントは、できるだけ薬をやめるということです。惰性で薬を飲んではいけないということなのです。 薬はすべて「毒」です。自己治癒力を顕著に低下させます。ですから、できるだけ薬は飲まないに越したことはありません。仮に飲むとしても、必要最低限、しかも期間限定で飲むようにするべきです。薬の常習は「NG」なのです。 ですから・・・・・・あとがき ・ウソの病気を仕分けて、少なくとも保険対象疾患から除外することで、今の日本の医療は再生します。 |