| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年01月25日 月曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
104 |
15/11 |
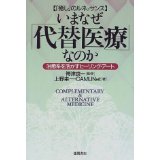 |
いまなぜ代替医療なのか |
上野圭一・CAMNet[著] 帯津良一[監修] |
徳間書店 |
☆☆ |
はじめに ・代替医療とは、英語の「オルタナティブ・メディスン(Alternative Medicine)」を直訳した語で、“近代西洋医学以外の医療法”ということになるでしょうか。 ・代替医療に共通する要素は、病気を治すのは人間のからだが本来そなえている力――<自然治癒力>というものであり、治療家の施術や使用するものは、その自然治癒力を活性化させるものである、という考え方が基本にあるところだ、といっていいかと思います。 ・近代西洋医学だけでは<複雑系>であるわたしたちのこころやからだやこころを治したり、癒したり、健康に保ったりすることにはもはや限界がきている、と考えているのです。 プロローグ 代替医療の可能性をめぐって。 帯津良一 vs 上野圭一 西洋医学と代替医療は使い分ければいい 帯津 ・目にみえる臓器の世界のことを、目にみえることを研究する「科学」というものが解明してきた――それが近代西洋医学です。 ・ところが、それで対処できないものが生命にはある。そのいちばん大きいものが <自然治癒> です。そういう自然治癒力みたいに目にみえない世界というものには、将来的にはどうあれ、西洋医学はまだ手をつけていない。 ・だから“わかること”つまり西洋医学でやれることは西洋医学でやっておいて、そうでない自然治癒力にたいしては、西洋医学が手が届かないといっているんですから、ほかのものをもってくる・・・・・・と、そういうふうな考え方です。 患者が医療を変えていく時代 ――“なぜいま代替医療なのか” 帯津 ・がんでもアトピーでも西洋医学だけでは治らなくなってきたからです。 ・結果に普遍性・客観性がなくても、患者さんに希望をもたせるような治療法を、それこそ魔術的なものもシャーマン的なものもふくめて豊富にもっているほうがいいにきまっているんです。患者さんの気持ちがグッと盛りあがってきますからね。それでけでも免疫力はかなりあがりますよ。 PART.1 なぜ、わたしたちはいま、「代替医療」だというのか。 「近代西洋医学」の限界と「代替医療」の可能性 いまだに鍼灸は「お医者さんごっこ」あつかい ・医学つまり「メディカルサイエンス」は“方法を研究する学問”であり、病気を治すことに直接かかわるものは「医学」ではなく「医術」である。 ・「医術」とは心身の病や傷を癒すための“わざ”、つまり「ヒーリングアート」「メディカルアート」であり、「学問」とは別の領域に属するものなのです。 ・「メディカルサイエンス」と「ヒーリングアート」が車の両輪のように車軸でつながり、回転しながら前進していくのが「医療」の本来のありかたです。 ・しかしいくら立派な車輪があっても、車輪だけではどこへいってしまうのか、その行方がわかりません。そこで、進行方向や速度をコントロールするハンドルとアクセル、減速や停止をするブレーキの役割をはたす「バイオエシックス」(生命倫理)がどうしても必要になります。 ・「バイオエシックス」のコントロールのもとに「ヒ―リングアート」「メディカルサイエンス」が息をあわせて回転し、前進していく。これがありうべき医療制度の基本的な構造だといっていいでしょう。 「代替医療」に共通するのは“癒しのわざ” ・わたしたちは現代医学を否定しているのではありません。現代医学の長所は大いに利用しながら、その短所を補う「代替医療」を最大限に利用したいと望んでいるのです。 「代替+医療」ということばが意味するもの 代替医療の四つの分類 ・①各国の伝統医学(伝統医療) ⇒ 中国医学、インド医学 ・・・ ②現代医学に対抗して生まれた比較的あたらしい医学体系 ⇒ ホメオパシー、カイロプラクティック ・・・ ③民間療法 ④その他の心身相関療法 ⇒ サイコセラピー、エネルギー療法、アロマテラピー ・・・ 日本におけるがんの「代替療法」 ・現代医学はがんを敵視し、外科手術で腫瘍を摘出したり、放射線で焼灼したり、化学療法で攻撃したりします。いわば、がんを「部分」の病気だと考え、病変部分を人工的に排除することで治療しようとするわけです。 ・それにたいして、「代替医療」はがんを「全身」の病気だと考えます。正確にいえば「全心身」の病気だと考えます。全心身のバランスがくずれた結果がんになったと考え、腫瘍の摘出よりも全心身のバランス回復をねらいとしてはたらきかけるのです。さまざまな方法でからだの化学的組成を変え、からだががんを異物として認識し、自然に排除するようにもっていくのです。 ・からだが自然に治癒的な方向に科学的組成を変え、異物を正しく認識し、不要なものを排除するはたらき――、そのはたらきの別名こそが「自然治癒力」なのです。 PART.2 もう欧米の医療先進国は「統合」へと動きだしている 多種多様な代替医療の宝庫アメリカ それは「ポピュラーヘルス運動」からはじまった ・現在、世界で「代替医療」の筆頭にあげられ、日本ではほとんど知られていない「ホメオパシー」(同種療法)は ・西洋医学は、たとえば発熱には解熱剤、便秘には下痢というふうに、症状とは反対の作用をもたらす対抗的な薬剤を使います(これを「アロパシー」 = “逆症療法”といいます)。 ・ホメオパシーはそれとは逆に、健康人がそれをのむと発熱するような薬剤で発熱を、便秘するような薬剤で便秘を治すところに特徴があるのです。 クリストファー裁判から「ホリスティック医学」へ ・「ホリスティックヘルス」は“健康とは病気でない状態”といった否定的で狭い健康観を大きく転換させ、“身体性・精神性・霊性のダイナミックな平衡状態”を健康ととらえる「全体論的健康観」のことをいいます。そして、その健康観から生まれたのが、「医のまなざし」を「医の内部」からふたたび「地上の風景」へ、さらに「天上」へと拡大させた「ホリスティック医学」なのです。 アメリカ人の代替医療費は年間二兆円以上 ・二十一世紀を目前にしたいま、アメリカは「統合医学」への道を歩みはじめています。成熟した「代替医療」と現代医学との統合をはかる段階に突入しつつあるのです。 医大から小クリニックまで広がる「統合医学」 ・アメリカでのホリスイティック・クリニックの例 最初に内科医が診断し、深刻な症状があれば即座に提携の病院に送り、なければ最適な代替療法家が適切な方法で非侵襲的な(心身に深刻な害作用がない)治療をほどこします。 ・たがいに異なる言語体系をもつ治療家たちの共通言語は「生命力」と「エネルギー」だそうです。 ・所長曰く、 「現代医学より代替療法のほうがいい。代替療法より現代医学がすぐれている。いつまでもそんな議論をしていてもはじまらない。両方に長所と短所がある。代替医療の内部にも競争があり、“おれが一番”という 「代替」ではなく「補完」の医療というイギリス 行動規範がきびしいイギリスのヒーラーたち ・西洋医学以外のさまざまな治療法が医療制度の中にとてもうまくとり入れられているという点で、イギリスは世界でもっともすすんだ国のひとつだといえるでしょう。 ・イギリスでは「代替医療」ではなく「補完医療」という呼び方で、ヒーリングやホメオパシー、アロマテラピーなどを総称しています。 ・つまり、現代の医療の主流である西洋医学にとって代わろう(代替)というのではなく、おたがいに不足しているところを補いあおう(補完)という発想で、種々の医療が共存しているのです。 ・たとえば、手かざしと祈りの医術である「スピリチュアル・ヒーリング」ですが、イギリスの西洋医学の医療現場でも、かなりの数の医師たちがそれを採用しはじめています。 ・イギリスでいちばん大きなスピリチュアル・ヒーリングの団体である「NFSH」(英国スピリチュアル・ヒーラー連盟)では、団体に所属するヒーラーに「補完」という意味でのヒーリングをひじょうに重要視した規約を順守するように指導しています。 ・ヒーラーは「患者への診断をおこなってはならない」とか、「主治医の指示にしたがう」とか、病院のスタッフへの配慮などもふくめて、こと細かに行動規範がつくられています。医師の立場を十分に゜配慮したうえで、その不足している部分を補っていこうとする態度が徹底しているのです。 ・イギリスの補完医療には資格制度がほとんどありません。 ・しかし、それでは治療をうける側としては危なくてしかたがありません。ですから、自分の身をまもるためにも、医療の消費者は必然的に賢くなければならないのです。 ・そして、医療消費者としての患者が治療家を選ぶときの目安として重要な基準になってくるものが、その治療家がどんな団体に属しているかということなのです。 ・イギリスでは、すべての国民が「GP」(General Practitioner)と呼ばれる開業医に登録することになっています。 ・GPは、イギリス人が病気になったらまず最初におとずれ、相談するところなのです。GPの合意なしには病院の専門医にかかることもできません。 ・そして、GPにかかったときの費用はすべて国の保険が負担します。また、GPの紹介をうけて専門医にかかるときも、国立の病院では無料です。 ・私立の病院にかかる場合は国の保険が適用されませんので、民間保険(保険会社の保険)を使います。 近代医学と自然医学が同居するドイツ 自然医学の歴史がいまだに息づく ・細菌の存在と発病との関係は因果論的にではなく、細菌の毒性と宿主の免疫力との相関関係のなかで相対的にとらえるのが妥当です。 ・医学における因果論と相対論のわか目は、つまるところ、生命力にたいする評価のちがいにあります。 ・生命力をかぎりなく信じる態度からは相対論が生れ、生命力に不信をいだく態度から因果論が生れるのです。 ・そして、因果論は還元主義的な医学の発展の動因となり、相対論は自然医学の発展の動因となっているといえます。 「健康士」という公的資格とシュタイナー医学 ・ドイツの医療制度では、病院はふつう外来診療はおこないません。 ・病院での外来診療は開業医(保険医)の紹介があった場合、救急の場合、それに退院患者のフォローの場合にかぎられるのです。 ・というのも、病院の九割が公立または公益病院で、ほんとうに病院での治療が必要だと判断された人だけを対象にしているからです。 ・ヨーロッパの多くの国と同じく、歴史的に「病院は私的なものではなく公共的なものである」という思想が徹底しているのです。 医療と宗教との再接近 「ホーリー」と「ヘルス」は語源が同じ ・“健康”を意味する「ヘルス」の語源は古代ギリシャ語で“全体”を意味する「ホロス」にあり、同じ語源からは“全体的” “完全な”を意味する「ホリスティック」、“神聖な”を意味する「ヒーリング」などが派生しています。 ・したがって、「ヒーリング」とは“人間を完全な状態にみちびく聖なるプロセス”であるとも考えられ、或る意味で、宗教的な響きをもったことばだということができます。 ・世界にはさまざまな癒しの系譜があり、病んだ人に健康を回復させるための多種多様な技法があります。そうした技法を発展させ、体系化したものが、いわゆる「伝統医学」です。 ・現代西洋医学もまた、ヒポクラテス以来の西洋社会における伝統医学の特異な発展型だということができます。 ・そして、いずれの伝統医学も、その起源をたどればシャーマニズムにいきつくのです。 ・シャーマニズムとは、その社会において特殊な能力をもつとみとめられた人(シャーマン)によっておこなわれる呪術的な行為の総称で、その呪術的行為には、現在でいう医療的行為、宗教的行為、教育的行為、政治的行為などがふくまれていました。 ・つまり、ひとりの卓越したシャーマンが医療・宗教・教育・政治などをすべてつかさどっていたわけです。 ・というより、ひとりのシャーマンがあつかっていた領域が分化し、専門化して、それぞれの領域に独立していったものが、現在でいう医療・宗教・教育・政治などの分野だということができます。 ・「ヘルス」や「レリジョン」の語源をたずねるまでもなく、医療と宗教はもともとひとつのものだったのでした。 ・ヒポクラテスは人間における「自然治癒力」(それは現代では白血球の抗菌力、リンパ球の免疫力などとして理解されている)の存在をみとめ、それが機能するかぎりにおいて病気が治る、と考えていました。 代替医療が医療と宗教のかけ橋に ・十七世紀にデカルトが「二元論」で人間を「こころ」と「からだ」に分けて以来、西洋の医学は自然科学に重点がおかれ、哲学や宗教からの離反にますます拍車をかけることになりました。 ・「精神」を神学や哲学にあずけて、精神とは別の次元だとされる「物質としての身体」だけに研究対象を限定した結果、西洋医学のテクノロジーは急速な発展をとげ、機会としての身体の故障を修理する「対症療法」が主流になっていきました。 ・また、ダーウィンによる「進化論」は医療と宗教の分離を決定的なものにするやくわりをはたしたのでした。 米医学界も「信仰の治癒力を再検討すべき」と ・『タイム』誌は「信仰は人を全体に回帰させるか」という記事で、アメリカの医学界が「信仰の治癒力を再検討すべきだ」と考えていることをつたえています。 ・祈りや霊的な行為が生理学的にも健康に寄与するという事実を容認しなければならないとして、信仰ある人たちの集団とそうでない人たちの集団との健康状態の比較をおこなっているのです。 ・その結果、二三二例の心臓手術のうち、宗教的な安心感をもつ人の集団の成功率がいちばん高く、その死亡率は信仰のない人の集団の三分の一以下であった。 ・瞑想や黙想をするだけで呼吸数・心拍・脳波がしずまり、筋肉が弛緩し、アドレナリンなどのストレス源的ホルモンの分泌が低下することがわかっています。 ・又、瞑想や心の平安がホルモンの機能や免疫系に好ましい影響をあたえることが証明されています。 ・また、リラクセーションと宗教的な経験が脳の中で同じ中枢にはたらきかけていることも、判明しました。 ・大脳生理学の発達によって人間のこころに科学のメスが入るようになってから、従来、宗教の世界ではとうぜんとされていながら科学には否定されていた数々の事実、たとえば瞑想や祈りの効用などが宗教と科学の共通の知識になりつつあるのは、じつに歓迎すべきことだと思われます。 「祈りの研究」と「手かざしの研究」 ・ドルー医科大学のマンドー・ゴーナム博士は「手かざし」の施術者と被術者の血液を採取し、免疫細胞であるNK細胞(ナチュラルキラー細胞)の変化と活性度をしらべるという方法で研究を開始しました。その結果は、研究を依頼した世界救世教の担当者の期待以上のものでした。「手かざし」をはじめると、被術者だけではなく施術者のNK細胞も優位にその数がふえることがわかりました。 PART.3 日本の「代替医療」にもやっと萌芽がみえはじめた。 「代替医療」ということばよりはじめよ 「代替医療」という共通項をつくるには ・多くの人はいまだに、「医療」といえば西洋医学がほぼ独占的におこなうものだと思いこんでいます。そして、どんな症状のときでもまずは西洋医学の治療をうけ、そこで効果がないとわかるとはじめて、代替療法に頼ったりすることになるのですが、その際にも、なんとなくうしろめたい気持ちをいだく人が少なくありません。 ・代替療法は多くの場合、プライマリー・ケア(一次医療)の一部として病気の初期に利用したときに最大の効果を発揮するものであるにもかかわらずです。 「ホリスティック」思想も導入された ・「ホリスティック」というのは、人間を部分ごとにみたり、部分の集合体としてみるのではなくて、“全体”としてながめていこうという態度のことです。 ・つまり、「胃にがんができれば胃をとってしまえばいいじゃないか」というのが現代の西洋医学ですが、ホリスティック医学では、「たまたま胃に症状があらわれているけれども、これはからだ全体になんらかの歪みがあって、それが現象化しているのだから、全体をチェックしなければいけない」という見方をします。 ・その患者の人間関係や食事など、日常の生活態度といったこと、あるいはどう生きているかという価値観にも目を向けていく必要があるという考え方です。 ・こうした考え方のうえに立った健康観を「ホリスティックヘルス」といい、医学・医療観を「ホリスティック医学」というのです。 ・「日本ホリスティック医学協会」の規定 1.ホリスティック(全的)な健康観に立脚する。 2.自然治癒力を癒しの原点におく。 3.患者みずから癒し、治療者は援助する。 4.さまざまな治療法を総合的にくみあわせる。 5.病への気づきから自己実現へ。 「 「こころの領域」が医学的研究の対象に ・一九七〇年代になって、アメリカでは盛んに「心身相関」ということがいわれはじめました。 ◎宇宙から帰還した宇宙飛行士の身体的・心理的ストレスを分析したところ、大気圏突入時に白血球が低下した。 ◎配偶者を失った人の血液を検査すると、免疫機能が低下していることがわかった。 ◎電気ショックというストレスをあたえたラットに腫瘍を植えつけたところ、ほとんどのラットに腫瘍の増殖と成長がみられた。 ・心身の相関関係は学問として成り立つようになってきたのです。 ・積極的に治療にとりくんだ人のほうが消極的な人よりもあきらかに治療効果が高かったのです。 “病気は悪者”の意識を変えなくては ・ひたすら病原菌を攻撃する医療は、いくら発展してもわたしたちを病気から解放してくれません。そんな現実にぶつかると、“病気は悪者だから撲滅すればいいんだ”という、従来の病気のとらえかたはまちがっているんじゃないだろうか? と疑問を抱かざるをえません。 ・そこで提唱されるようになったのが、“病気は悪者ではない、私たちの生活や生きかたに歪みがあったときにそれを修正すべく警鐘をあたえてくれているものだ。病気そのものが治ろうとするプロセスの表現なのかもしれない”というホリスティックな考え方でした。 ・そこから“病気になったら病気を治そうとするだけではなくて、その病気がどんな警鐘を鳴らしているのか、聞く耳をもとうじゃないか”と、つまり「気づき」と「癒し」をテーマにする医師たちが語りはじめました。 ・そして彼らは、“病気の意味”に気づくことができるような方法を治療法として選択し、その治療法をとおして“自然との共存”とは“人間が生きる”とは、“死ぬ”とはどういうことなのかを、患者が自分で感じられるような演出をしはじめたのです。 ・病気をしてさまざまな代替医療による治療法に出あったことによって、環境問題やエネルギー問題を真剣に考えるようなライフスタイルに変わったり、家族関係がより深まったり、毎日の生活に余裕をもてるようになったり、カネやモノへの執着が少なくなったり・・・・・・という具合に、生きかたや考えかたが変わったという患者が実際おおいのです。 ・病気をなくすことはできなくても、病気をただ忌み嫌うだけではなくて、わたしたちの“生きかたに重要なメッセージをあたえてくれているありがたい存在だ”と考えるような価値観の変革はできるはずです。こうした意識の変革が、人と病気との関係を変えていくのです。 「癒し」をテーマにする医師たち ・「癒し」をテーマに個性的な医療を展開している医師のその哲学をつきつめていくと、共通点がたくさん浮かびあがってきます。 1.人間を肉体だけの存在としてとらえない。 2.病気は悪いものではない、病気を「気づき」のチャンスとする。 3.人間を自然のなかのひとつの存在ととらえる。 4.人間は死んだら終わりではなく、生命は永遠であるというみかたをする。 5.みんなが癒す立場であり、癒される立場である。 6.医師の目的は病気を治すことではなく、病気のない生きかたへの提言である。 7.奇跡的な治療は起こりうる。 8.「癒し」は高い精神性をもった人のもとで起こる。 ・このようなかつてない現象が起こっているのは、“生命とは何か”を追求するひとつの段階として、医療が「治療」から「癒し」へと変化しているというみかたができるのではないでしょうか。 ・「生・老・病・死」は、だれにも避けられないステージです。それをなくそうというのも不自然だし、みないようにしようという態度は 日本の医療は、そんなテーマのなかで、大きく変貌しようとしているのです。 帯津三敬病院のホリスティックながん治療 帯津院長が提唱する「病を克服する家」 ・絶対的な治療法というものは、ひとつもありません。でも、どんな治療法にも可能性はあります。“だれも、いつかはかならず死ぬものだ”ということを前提に、いま、自分はどう生きたらいいのか、それをしっかりとみつめたうえで、気功や食事、そのほかの治療にとりくんでいただければ、それが治るか治らないかの結果をこえて、自分も家族も納得ができるのではないでしょうか。 おわりに――帯津良一 ・近代西洋医学陣営の医療者は、相変わらず「科学、科学」と口にします。しかし、彼らがいう科学は <単純系> の化学――つまり、単純な要素に分けられるものを対象にした科学なのです。ところが生命というものは <複雑系> であることがますます顕著になってきました。いくら分けていっても単純にはなりません。 ・いうならば、単純系の医学である近代西洋医学はこの“複雑系の生命のうちの単純系で処理できる部分”は立派に処理してきました。そして、いろんな意味で、生命の本質に向かって近づいてきました。しかし、いまや複雑系を前にして困惑している、というのが正直なところだと思うのです。 ・複雑系の生命の本質に迫るためには、ここで複雑系の医学をもってこなくてはだめなのですが、残念なことにまだ複雑系の医学はその姿を現していません。そして、将来の「複雑系の医学」こそホリスティック医学で、そのホリスティック医学に包括され、かつ複雑系の医学を先取りするかたちで存在するのが「代替医療」なのです。 |