| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年04月13日 水曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
16 |
15.02 |
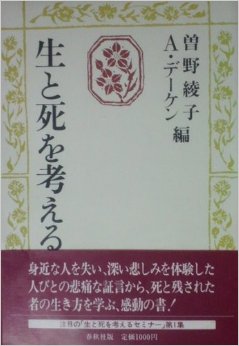 |
生と死を考える |
曽野綾子 A・デーケン |
春秋社 |
◎ |
序 曽野綾子 ・私はなんでも、隠して置かずに明るみに出すのが好きだ。隠しておくということは、いかなる意味でも解決にはならない。人間の悲しみも醜さも別離も、共に何か必要な面があったからこそ、存在したのである。 ・幸福も人間をふくよかにする。同時に死も人をみごとなものにする。病気は辛くもちろん避けたいものだが、苦しみを体験することによって、精神の成長を遂げた人がどれだけ多いかをみる時、死もまた同じだろう、いや、もっと効果的だろうと期待せざるを得ない。 1 臨床心理学の立場から――下山徳爾 死に臨む者とその家族 1 生命の中に潜む死 ・生と死というものをあまり二元的に考えない、つまり、生のうちには死があるし、死のうちにも生があるというわけです。人間は生きながら少しずつ死んでいくともいえますし、また、人間は絶えず小さな死と、小さな再生をくり返しているものだともいえるわけです。 ・しかし、私たちの人生を彩るのは、私たちが、小さな死をとげ、そして小さな再生をとげながら、われわれの人生というものを成熟させていくということになります。そういう意味では、死は厭うべきもの、生は誉むべきもの、そして生の断絶として死があるという考え方は、考え直すべきではないか。 2 死生観の文化差 ・有名な三輪山は普通、自然崇拝の山で、山そのものが御神体であるといわれている神社ですが、これも実は、民族学者によれば、あれは山そのものが御神体なのではなくて、山に集まってくる魂が御神体なのだ、つまり、人間の死後の霊を尊敬するわけです。なるほど、御神体などはないけれども、「三輪山縁起」によりますと、山の上には、元、神木で作った ・十五世紀のドイツの叙事詩『アッカーマン・イン・ベーメン』 この作品をみて感じることは、死に対し諦めたり、逃げたりしないで、真正面から死を見すえ、死と全力をもって戦う人間の強さです。これは、どんなに相手が強くても、訴えに訴え、真正面から死を見つめる姿勢というものだと思います。確かに人間の体はもろくても、人間性は死に屈することはないであろうという確信なのです。死に対する恐怖は、死に対するむしろ反発を呼び起こして、かえって生命力を呼び覚す結果を起しているということです。 4 人生の最期は人生の完成期 ・自分の命が長くないことを知ることによって、濃密な時間を生きることができる。 ・人間は最後の瞬間まで成長できるものです。 ・言葉というのは、患者さんに対しても、臨死の患者さんの家族に対しても、へたな励ましとか慰めをするのは、かえってマイナスのことが少なくありません。むしろむこうの嘆きや苦しみをそのまま受け取り、こちらも本当に同じフィーリングになってあげる、そして実際には、「おかげんいかがですか」などというのではなく、そばに座って黙って手を握ってあげたり、またいろいろなことを言われても、こちらが心からそこに座って聞いていてあげるということは、亡くなる患者さんに対しても、残された家族に対しても、必要なことなのです。 2 精神医学の立場から――土井健郎 親しい者との死別――その意味と影響 1 親しい者との「別れ」はなぜ悲しいか ・いったいなぜ、人間は親しい者と別れることがそんなにつらいのか? なぜいつまでも悲しむのか? 結局、「愛」の問題なのです。親しい者との死別が非常に悲しいということが謎である。心理学的に説明がつかない、ということは、「愛」というものは心理学的に説明がつかない、ということと実は同じなのです。 2 「悲しみ」の秘密は「愛」 ・何かに時間をかけた、ということで、そのものに対して責任が生まれ、愛情も生れるんだ。 ・悲しいのは、愛するからなんです。そして、すべてをそこで失ったわけではないんです。何かが残っているんです。 ・愛する以上は、何か残っているわけですね。・・・・・・思い出が残ります。そして思い出はむなしくない、 ‹それこそ、眼に見えるものよりもっと大事なんだ› ‹愛して、失ったほうがいい› と、サン=テクジュペリは言っているわけです。 ・日本のひとつの風習で、私が非常におもしろいと思うのは、親しい者を亡くしたときに、近所の人や友人たちが来て、「お悔み申し上げます」と言うことです。なぜお悔みですか? それは親しい者をなくしたときに、悔みが残らないという人は、少ないからです。 ・もし、親が死んだのなら、自分は親不孝だ、生きているときに、おとうさん、おかあさんにもっと尽してあげればよかった、と思います。あるいは、子供なら、なおさらですね。その悔みの感情をまわりがくんで、「お悔やみ申し上げます」と言うんです。要するに、日本の風習では、相手の人が親しい者を亡くしたときの同情の表現は、“悔む”ことです。あなたのために私は悔みます、こう言って同情を表すわけですね。悔みの感情に同情するわけです。それがないと、ますます悔みが募ってしまうわけです、独りで悔んでいると。 3 哲学の立場から――アルフォンス・デーケン 悲嘆のプロセス――苦しみを通しての人格成長 1 未解決の悲嘆とその危険 ・アメリカ・ロチェスター大学の医療チームは、肉親の死のような深刻な喪失を体験した直後の、無力感や絶望といった感情が、がんなどの悪性疾患を発生させる大きな要因であると解釈している。 ・アメリカの心理学者ローレンス・ルシャンも、がん患者に共通する基本的な心理傾向は「絶望」であると述べている。 ・近年、はなはだしい不安、抑鬱、失意などが身体の抵抗力を低下させ、がんなどの発生と進行を促すという心身相関現象がますます注目されるようになっている。 2 感情を発散させる必要性 ・感情の抑圧はけっして勧められるべき態度ではない。 ・悲しみの感情を自由に、また十分に発散させることこそ、悲嘆を乗り越える上で最も大切な要素なのである。感情を抑圧してしまうと、積極的に悲嘆という課題に立ち向かう道が閉ざされることになり、悲嘆は悲しむ人の心に内攻して深刻な害を及ぼすようになる。 3 悲嘆のプロセスの十二段階 (1) 精神的打撃と麻痺状態 (2) 否認 (3) パニック (4) 怒りと不当惑 (5) 敵意とルサンチマン(うらみ) ・近親者の中には、死別した患者の世話をしてくれた人々に敵意を示す人もいる。 ・残された人は、やり場のない感情をぶつける (6) 罪意識 ・過去における現実の、あるいは想像上の自己の過ちを悔やみ、自分を責める。あの人が生きているうちにこうしてあげれば死なずに済んだかもしれない、または逆に、あの時にあんなことをしなければよかった、などと考えて悔恨の念にさいなまれる。 (7) 空想形成、幻想 (8) 孤独感と抑鬱 (9) 精神的混乱とアパシー(無関心) (10)あきらめ――受容 (11)新しい希望――ユーモアと笑いの再発見 ・ユーモアと笑いは健康のために欠かすことのできない要素である。悲嘆の闇を貫いて新しい希望の太陽が最初の光を投げかける頃、忘れられていた微笑みが戻り、凍てついた心をとかしてあたたかいユーモアのセンスがよみがえる。ユーモアと笑いの再発見は、悲嘆のプロセスを上手に乗り切ったしるしでもある。 (12)立ち直りの段階――新しいアイデンティティの誕生 4 悲嘆における特殊な問題 ・子供は、空想の中で両親の死を思い描いたことがあるために、現実に両親の死に出合うと、自分の空想が死を招いたのだと思い込んでしまい、強い罪悪感を覚えるのである。子どもを対象とする、死と悲嘆の準備教育においては、子供に空想と現実とを区別させ、考えたり望んだりすることが死の原因になるのではないことを悟らせなければならない。 ・子供が父や母の死について話したいと思っても、残された片親がすぐに話題を逸らして、子供の関心を他のことに向けようとする場合があるが、これは誤った態度である。感情を自由に表現させ、死にまつわるいろいろの疑問を解いてやることは、子供の悲嘆における重要なプロセスである。逆にここで感情の抑圧を強いられたり、疑問を解明してもらえずに放置されたりすると、その歪みが将来、情緒障害や身体的疾患となって表面化するケースがきわめて多い。 ・父親が死んで、母親が嘆き悲しむ様子を目撃した子供は、母親にこれ以上悲しい思いをさせまいとして、しばしば死という話題を避けようとする。また母親の方も、子供に死の話をするのを意識的に避ける場合が多い。しかしながらこれも誤った配慮であり、正常な悲嘆のプロセスを阻害する危険を伴う。率直な対話と感情表現は、たとえその時点でどれほどつらいことであろうと、ぜひとも行われねばならない。長い目で見れば、残された親子の率直な対話は、心の傷を癒すためのはかり知れない助けとなるのである。 ・「男の子は泣いたりしてはいけません」といった小言もよくない対応の代表である。涙を流すというのは正しい健康的に態度であり、決して抑圧されてはならない。 ・仏教においてもキリスト教においても、一定の期間をおいて死者の追悼を繰り返す習慣がある。 こうした習慣は、悲嘆のプロセスの遂行のためにきわめて有意義である。 ・人間とは歴史的な存在である。人間は本質的に時間の流れの中で生きているのであり、時間という次元を除いて人生を語ることは不可能である。たとえある種の時間がたとえようもないほどの苦痛を伴うものだとしても、時間の流れに沿ってそれらをすべて経験し尽くさないことには、必要な悲嘆の仕事を達成できない。 ・残された人々は、こうした「苦しみの時」が、悲嘆のプロセスにおける人格成長のために積極的な役割を果たすことも知ってよいと思う。危険な時期を極端な抑鬱に陥ることなく過ごし、そうした特定の時間から来る苦痛の感情がノーマルなレベルに落ち着いたと自覚した時、悲嘆の仕事が成功のうちに達成されたことがわかるのである。「苦しみの時」をどのように過ごすかが、悲嘆のプロセスを乗り切ったかどうかの目安になり得ると言ってよい。 4 臨床看護の立場から――小林清子 苦痛に直面した人への臨床的対応 4 人間を人間らしく遇する ・日々の生活の営みの中で人を大切にするということ、その人に関心をもつこと、その人のことに一生懸命になるということ、その人の存在を認めて反応することが本当にできなければ、急に患者さんの前に行って援助することはできないのではないかと思います。 5 がんセンターの病棟から――小松玲子 死を看る場で思う 1 「告知」ということ ・人間は自分が「死ぬ」とわかってからも、その苦しみを見つめ、乗りこえ、自分で選択して自分らしく死んでいくことができると思います。そしてすべての医療者もそれを可能にするために関わっていかないと、本当に良い「死にゆく患者のケア」はできないのではないでしょうか。 3 ホスピスについて ・最も大切なことは、「各人が、必ず来る死に向かってどう生きるか」ということです。「明日がある」ではなく、「今日一日を納得して生きる」、そのような生き方をしてきた人にとっては、告知の問題も、延命についても、おのずから解決の道があるように思います。 6 経験者の立場から――川中なほ子 家族の死と残された者の生 1 残酷な体験 ・たとえ早く死んでも、本人の望むように自分の家で死なせてあげるべきてだったのではないでしょうか。本人の気持よりも、いつも医療が第一義的に考えられ、医学的延命のみが最重要視されてきたことへの反省、もっと人間らしい病人の最期の日々のために考えなければいけないという反省が、この時のものでした。 9 まとめ――平山正実 生と死を考える 1 死は隠されている ・「自分の死期をいつも眼前にたもち、毎日死ぬ心構えを怠らないものは祝福されたひとである」 死は、名将であり智謀にたけた優秀な戦略家であって奇襲作戦によって命を奪うことを好む。だからこそケンピス(ヨーロッパの神秘家。一三八〇~一四一七)は、死に不意打ちを食わされないように普段から準備しておくようにと警告したのだろう。 5 死はなぜ恐ろしいか ・人間が死を恐れる理由はいくつかある。まず第一に痛みに対する恐れである。がんの末期患者や心臓発作を起した患者は、痛みを訴えることが多い。そのために多くの人びとは、死は痛みを伴うものだと考えている。それだから死は恐ろしいのである。 ・日本でも昔は、仏教の教師が臨終の患者に対して善き導き手となり、三途の川を渡って仏道に入るための準備を行った。源信の書いた有名な『往生要集』には、この臨終の行儀について詳しく記されている。それによると、人びとは臨終を迎えると無常院という場所に移された。そこには救済のシンボルである金色の阿弥陀像が安置されており、導師は経文を読んだり、念仏を唱えるなどして、患者の精神の安定をはかったのである。 ・洋の東西を問わず、人類の歩んできた歴史を回顧すると、死にゆく人びとに対してきめ細かい配慮がなされてきたことは注目してよい。しかし、現代の日本では、宗教というものが全く風化してしまい、こうした臨終の行儀はほとんど行なわれなくなってしまった。そして、多くの人びとは高度な医療機械に囲まれて、独りで孤独と恐怖と戦いながら死んでゆく。こうした現状に対して、もう一度われわれは、反省してみる必要があるように思われる。 6 死に向けて成熟する ・人間には、『生るるに時があり、死ぬるに時がある』(旧約聖書、伝道の書三章二節)のであって、その時を人間が大幅に変更することは不可能である。それゆえ、より大きな力に委ねる覚悟をもち、どんな事態に陥っても他者配慮的な生き方ができる人こそ、真の意味における成熟した人間であるといえるのではないだろうか。人は生きてきたようにしか死ねないという。もしそうだとすれば、われわれは、毎日毎日の生の真っただ中において、人格の成熟への努力を怠ってはならないということになるだろう。 |