| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年07月25日 月曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
27 |
15.03 |
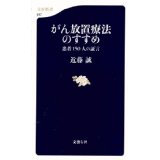 |
がん放置療法のすすめ |
近藤 誠 |
文春新書 |
☆ |
前書き ・進行がんでも縮小するケースがあると知れば、それだけで、がんに対するイメージが崩れるはずです。 放置患者の観察・分析から、がんが転移する時期も判明します。すべての癌は「本物のがん」か「がんもどき」のどちらかに属し、「本物」は初発がん発見のはるか以前に転移しているのです。他方、がん発見当時に転移がない「もどき」は、放置しても(初発巣から)転移が生じないことが確認できました。 1章 前立腺がん PSA(前立腺特異抗原)発見がんの九割以上は「もどき」 ・がんもどきというのは、病理検査で「癌」と診断されても、他臓器に転移していないため、放っておいても死なない癌です。これに対し「本物のがん」は、すでに転移が潜んでいるため、治療しても治らない癌です。「本物」は、ガン細胞が生じて間もなく転移するので、初発巣が発見できる大きさになったときには、転移巣は(潜んではいても)相当の大きさに育っている。それで初発巣を早期に発見しても、(転移巣を含め)がんを治すことができないのです。 症状が出てから治療しよう ・PSAが上昇したという一事で治療を始めるのは考えものです。前立腺がんの症状が出てQOL(日常生活の質)が落ちてから治療を始める方針ならば、PSA発見がんの九割以上は(他の病気で死ぬので)一生治療を受けずにすみます。またQOLが落ちてからなら、治療を受けて合併症が生じたときも、がんでQOLが悪くなっていたのだから(治療を始めたのは)仕方がなかったと、「無症状なのに治療を受けて合併症が出た場合より)得心しやすくなるでしょう。 2章 子宮頸がん 「本物のがん」である前提条件 ・がんが人を死に至らせるためには、重要臓器の機能を妨げる必要があります。たとえば肺がんが気管支を押しつぶし(肺に)空気が出入りできないようにするとか、肝がんが肝臓ほぼ全部を占めて肝不全にさせるというように、臓器の機能不全を引き起こす力がなければならないのです。その前提として、がんは腫瘤(細胞の塊)をつくる必要があります。 ただし、腫瘤であれば人を死なせる力が(必ず)ある、というわけではない。硬くて、周囲の正常組織から(触って)識別できなければ、人を死なせる力はないのです。 「もどき」でも治療したほうがいい場合がある ・がんを「本物」と「もどき」に分ける基準は、他臓器への転移の有無です。転移があれば治らない。 「放置」の意味は何より時間稼ぎにある ・乳がんのように他臓器転移のみが寿命を左右する癌では、がんを完全放置した場合にも、寿命は変りません。 ・がん放置療法といっても、寿命を延ばすためには、適当な時期に最低限の治療を受けることを前提としています。誰にでも共通する「がん放置」の意味は、時間を稼ぐ点にあります。多少の時間の余裕を得て、その間に、治療を受けるかどうかや、治療法の選択肢を検討する。あるいは、セカンド・オピニオン、サード・オピニオンを得るようにする。第一の目的はそこにあります。 ・放置してみたら、がんが増大しないことはいくらでもあります。それどころか、がんが縮小し、消失することさえある。そういう場合には、放置を続けるのが得策でしょう。それを続ければ、がんを一生放置することも可能になります。 3章 乳がん ・がんといえば「早期発見・早期治療」だと言われていますが、それはがんの成長過程から考えると無理であるようです。 転移時期は逆算できる ・がんは怖い、がんを放っておくと危ない、という社会通念は、転移時期に関する誤解によって生みだされた面があるからです。 非浸潤がんは転移しない ・非浸潤がんは生来的「がんもどき」といえます。 ・非浸潤がんは転移できないのですから、「がん」という名称は廃止すべきです。 マンモグラフィを受けてはいけない ・しこりや腫瘤がなくて、マンモグラフィでしか見つからなかった癌は「もどき」です。 ・二〇〇九年十一月、米国政府の予防医学作業部会は「マンモグラフィによる乳がん検診は四十代の女性には勧められない」と勧告しました。がんを検出する精度が低く、誤った診断で不必要な組織検査を受けさせられるなどでメリットが多いことが理由です。 ・マンモグラフィ検診中止は、死亡減少効果がないことを理由とすべきです。 ポリープがん化説と多段階発がん説 ・「がんと診断されてすぐに手術や抗がん剤治療などを受けたのに、助からなかった」と悔やむがん患者・家族はあまりにも多いのですが、それには、「早期発見・早期治療は正しい」とする「がん一元論」が広まっていることが関係しています。 すなわち、早期がんを放っておくと周囲への組織へがんが浸潤し、他の臓器へ転移する進行がんとなり、さらに末期がんとなって死に直面する、という考えがあるのです。いわゆる「多段階発がん説」で、これによれば、早期発見・早期治療が正しいことになります。 ・「多段階発がん説」では、まず粘膜から大腸の内腔=内側へ向かってキノコ状の腫瘍性ポリープ(隆起性病変)が発育。その後、ある一定の順番に従ってがん細胞の遺伝子変異が積み重なると、今度は一転し、粘膜より外側=大腸の粘膜下層、さらには筋層へと浸潤します。さらに遺伝子変異を積み重ね、大腸の周囲組織へ浸潤し、他臓器へ転移するとされています。これを「ポリープがん化説」ともいいます。 ・私は「多段階発がん説」と異なり、がんは発生当初から他臓器へ転移する「本物のがん」と、他臓器へ転移しない「がんもどき」の、性質が異なる二種類のがんがある、という「がん二元論」が正統と考えています。 ・「本物のがん」は他臓器転移を引き起こすためのがん関連遺伝子に変異が生じたがんであり、「がんもどき」は他臓器転移を起こすがん関連遺伝子に変異が認められない癌です。 転移を可能とする遺伝子変異の有無は、ガン細胞の発生時に決定されており、発生後に変わることはない、というのが、この考え方の根幹です。 がん幹細胞 ・ガン細胞にはいくつかの性質の異なった複数のものがあり、がん=悪性腫瘍をつくりだす大本のがん細胞の存在が明らかにされたのです。それが「がん幹細胞」です。 一個のがん幹細胞が発生すると、そのがん幹細胞の分裂・増殖によって、それと同じがん幹細胞と、分裂・増殖の激しい前駆(がん)細胞とがつくられます。さらに前駆細胞から分化(がん」細胞がつくられます。 4章 肺がん 胸部CTでのみ発見されるがんは「もどき」 ・(ひとつの塊として増大しないため)胸部レントゲン撮影で発見されない肺がんは、所詮、人間の命を奪う強いパワーを持ちません。がんが人の命を奪うには、正常組織を押しのけるパワーが必要です。がん細胞が塊をつくり、それが増大することで正常組織を押しのけ、臓器の機能を低下させて、命を奪うのです。 ・すりガラス状陰影の場合は、組織型が腺がんであっても、「もどき」なので、治療を受けないことが正解です。「がん」と言われて心配な人も、三~六ヵ月度様子を見て、改めてCTを撮って、大きくならないことを確かめるのが一法です。それをくり返しているうちに腹も据わるでしょう。 肺の検査にはご用心 ・がんが「本物」であればすでに転移があるため手術は徒労で、「もどき」であれば放っておいても命取りにならないため手術は無意味。結局、検診は受けないのが平和に長生きするコツなのです。 抗ガン剤の「繰り返し治療」でさらに縮命 ・抗ガン剤は肺がん患者の寿命を縮めます。それは他の固形がんでも同じです。一般に信じられているのと異なり、抗がん剤にあるのは(延命効果ではなく)「縮命効果」です。 ・乳がんに限らず、肺がん、胃がん、大腸がん等、縮命効果はあらゆる固形がんに妥当します。また縮命効果は、男性患者に一層強く出るはずです。男性は(タバコや酒などで)不摂生な生活を送ってきた人が多く、その場合、自覚症状はなくとも、心、肺、肝、腎などの重要臓器が水面下でボロボロになっているからです。 放射線治療も肺障害を起こす ・肺がんと診断された場合には、できるだけ慎重に判断・行動し、無症状であれば治療せず、何かQOLを落とす症状が出たときに、必要最低限の治療で症状を取るようにするのが、長生きを図るコツだと思います。 放射線治療の実際 ・残念ですが、現代医学は「本物のがん」を治す手立てを持っていません。しかし、抗がん剤等の無茶な治療を受けなければ、明るく前向きに、長生きすることも可能です。 食事療法で痩せるのは危険 ・コレステロールが減ると(がんを含む種々の病気の)死亡数が増えるのは、体の抵抗力が落ちるのが理由でしょう。抵抗力は(一般的には)免疫を含む概念ですが、がんの場合には免疫は(がんに)一度負けているので、免疫以外のがん発育を防止する力、と考えるのが妥当です。 ・転移がある人はもちろん、転移が潜んでいそうな人も、食事療法はしないことが、長生きするコツの一つになるでしょう。相撲取りのような太りすぎも寿命を縮めるので、メタボの入り口程度に押さえながら、エビ、カニ、ステーキ、トロ、イクラと、おいしいものをなんでも食べるのが、がん放置療法の要諦です。 5章 胃がん 未分化がんは本当にタチが悪いのか? ・逸見政孝さんのケースでは、治療に関して特筆すべき点が三つあります。 一つは、逸見さんが定期的に年に一度、内視鏡検査を受けていて、それで発見されたことです。担当医は早期胃がんと診断し、逸見さんに即刻告知し、手術を勧めました。しかし開腹すると、スキルス胃がんであることが判明。すでに腹膜に転移していました。 第二には、再発告白会見は、手術のわずか七ヵ月後であったことです。逸見さんは手術後まもなく腹部に再発したのです。 特筆すべき第三点は、告白会見後に東京女子医大病院で行われた手術で、残胃、膵臓、小腸、大腸など三キロに及ぶ臓器を摘出したことです。そのような大手術をしても治る見込みはゼロである、無謀な手術だ、との批判を浴びました。実際、逸見さんは再手術後すぐに再再発し、再手術から三ヵ月、初回手術から十ヵ月で亡くなられたのです。 ・未分化がんでも、スキルス胃がんに進行するものと、進行しないものとに分かれ、どちらであるかは、がん幹細胞の発生当初から定まっているのです。 他方、逸見さんのケースでは、内視鏡で早期胃がんと見えたものの、(開腹したら)腹膜転移が存在していたわけです。腹膜転移が一つでもあれば、治らないのは医学上の常識です。腹膜は胃のすぐ下にありますが、そこへの転移は(肺や肝など)臓器への転移と同義なのです(大腸がん、膵がん、卵巣がん等で腹膜転移がある場合も同じ)。逸見さんが治る可能性は、最初からゼロでした。 スキルス胃がんを放置して十年近く平穏に生きたケース ・もし担当医に勧められるまま手術を受けていたら、余命は一年か、もって二年程度だったと思います。スキルス胃がんの手術統計でも、五年生存率はほぼゼロです。 手術をするとがんが怒る? ・腸閉塞(イレウス)は、がんの腹膜転移が増殖して、小腸や大腸を狭めるために生じます(狭窄)。食べたものが通らないので、お腹が張って苦しく、食べたものを吐いてしまう。症状を軽減するため実施されるのがイレウス管。鼻からチューブを入れて小腸に通し、この管を通じて腸内容物を外に出します。イレウス状態は軽減されますが、腸の狭窄部位が広がるわけではないので、ずっと留置する場合がほとんどです。 ・これに対し、スキルス胃がんを放置した場合には、QOLはもっと良好なのです。 ・胃がん患者がイレウスで苦しむのは、手術のせいではないか、と疑う必要があります。手術をしたから、がんが余計に増殖し、腸管の狭窄を引き起こすのではないか、と。 実際にも、腹膜転移があるのに手術をすると、腹膜のいたるところに傷がつきます。当然ながらがん細胞は、その傷口に入り込みます。そして傷口は血管豊富で、ガン細胞が分裂するのに最適なので、手術をするとがん増殖が加速されるのです。 ・昔から外科医たちの間では、胃がんを手術すると、がんが急速に増大する事実がよく知られています。それで「がんが空気に触れると暴れだす」とか「手術すると、がんが怒る」と言われたものです。しかし、そうなる理由は以上のようなものですから、怒るのは癌ではなく、メスで傷つけられたからだが怒り、がんの増殖に手を貸したとみるべきでしょう。 胃の全摘や大幅切除は誤り ・私は、そもそも胃がんの手術で胃を全摘したり、大きく切除したりすることは原則として間違い(誤り)である、と考えるに至っています。 他の臓器に転移している「本物のがん」ならば、胃を全摘しても治りません。痛い思いをするだけ損です。他臓器へ転移しない「がんもどき」ならば、無治療のまま様子を見るだけでよいときも多いし、内視鏡治療など最小限のごく小さな手術で済む可能性もあるからです。 ・いずれにしても、胃の全摘や大がかりな胃切除などの胃がん手術によって、患者さんの体は甚大なダメージを被ります。食生活をはじめ、QOLが大きく損なわれ、本来の寿命を縮めてしまうことになるのです。 ・現在、がん治療における世界の大勢は、可能な限り臓器を温存する方向に向かっています。いたずらに拡大手術に走っても、がん患者の生存率向上に貢献しないばかりか、がん患者の生活の質も低下させてきたからです。 6章 腎がん ・転移がある本物のがんは治らないので、見つけるのが早くても、遅くても、本来の寿命は変らないのですから、検査をしないでおいて、何かがんによる症状が出てきたら検査するというのが、一番理論的な方法でもあります。症状が出てくると、残された時間が少ないのが欠点ですが、割り切れるなら、これが一番自然な方法です。、 7章 膀胱がん 膀胱全摘を拒否して放射線治療で対処したケース ・患者さんは、「手術を拒んで経過観察を選択したため、私はそれまでとまったく変らない日常生活を送れています。むしろ膀胱がんと診断されたことをきっかけに、年二回の海外旅行を四回に増やしたのは 膀胱全摘術の問題点 ・手術をしても成績が不良なのは、がんの性質が原因です。浸潤性膀胱がんは、肺、肝、骨等の他臓器に転移していることが多く、それが死因となります。膀胱の初発巣事態は(仮に放置後)増大しても、(それによって引き起こされるはずの)腎不全には対処法がいろいろあるので、放置した場合に初発巣が死因になる事はまず生じないのです。 ・そもそも、がんは転移がある「本物のがん」と、転移のない「がんもどき」のどちらかです。前者であれば、どういう治療をしても治らず、後者であれば、かりにがんを放置しても死なないので、結局、どういう治療であろうと、治る率に変りはないのです。だったら膀胱を残す方法を選ぶのが得策です。それで万一腫瘍が残存したら、そのとき手術を検討すればよい。初回治療としての膀胱全摘術は不要な時代になったといえます。 終章 がん放置の哲学 まずは様子を見よう ・がん放置療法の要諦は、少しの期間でいいから様子を見る、という点にあるからです。 その間に、がん告知によって奪われた心の余裕を取り戻すのです。そして考えましょう、がんの本質や性質を。 ・がんは老化現象です。年齢を重ねるなかで遺伝子変異が積み重なった結果が癌なので、年齢がたかくなるほど発がん頻度が上がるわけです。そして老化現象だから、放置した場合の経過が比較的温和なのです。 ただ、本物のがんの場合は、老化現象の究極として、いずれ死を呼び寄せます。しかしその場合も、なりゆきを癌に委ねれば、自然の摂理に従って人生を完結させてくれます。 ・大事なのは、がんは症状が出ても、緩和の方法が確立していることです。それゆえ(痛みに対し鎮痛剤ではなく抗がん剤を用いるがごとき)治療法選択の誤りをおかさなければ、QOLを回復させられます。 ・熟慮期間中には、手術や抗がん剤等で積極的にがんを治療する場合の不利益も考えましょう。 この点、がんを叩くための積極的治療を受ければ、心の安堵を得られることは確かです。が、人間の体は、医学とは無縁なままに進化してきたので、手術、抗がん剤、放射線等で治療されることには慣れていない。そのため、合併症や後遺症が生じるのです。 ・そもそも、がんは自分自身の一部です。それを叩こうとしたら、身体のほうが参ってしまうのは当然です。したがって治療法に数種の選択肢がある場合、なるべく負担の少ない方法を選ぶのが長生きするコツであるわけです。その場合、がん放置療法は有力な選択肢になります。 ・早期がんと言われた場合には、誤診が多いので、組織標本を別の病院でもう一度調べてもらうことを心がける。誤診と分かれば、治療そのものの必要性が消滅します。 ・もちろん進行がんの希な例外として、急速に増大するため(診断から死亡まで)数ヵ月というケースもあります。が、そういう癌は、ほとんどが最初から種々の症状があるので、ここでいう放置療法の対象ではない。放置療法は無症状の人を対象としているからです。 ・無症状であっても、急速に拡大する癌は、ほぼ全てに転移があるので、治療しても結果は同じです。積極的な治療を受ければ、合併症で苦しむだけなので、放置して緩和治療に徹することが妥当です。 ・少し様子を見るだけで、得することはたくさんあります。 様子を見る間に、万一がんに起因すると思われる症状が出てきたら、病院に戻ることを検討しましょう。しかし、戻ることが必須ではありません。人は、自分自身の主なので、たとえがんでっても、どう振舞おうと自由だからです。 ・がんを放置するのは愚かしい行為ではありません。それは、無神経で粗野な医者たちに人格や体が ・私からみると、身体のことに関しては患者本人が一番熱心に考えているのだから、質問されたとき以外は、他人がああだこうだ言うべきではないと思うのですが、個人主義が未発達のこの国では、なかなか難しいようです。 ・要するにがん放置療法は、患者だけで実行できる唯一の合理的な療法です。「患者だけ」というのは、原則として医者の力を借りずにすむからで、現代医療において医者たちに奪われた(自分の体に関しての)自己決定権を取り戻す究極の方法です。また、民間療法その他いかがわしい療法と異なり、科学的根拠を備えた「合理的な療法」であるわけです。 ・がん死亡が増えている現在、私たちは、がんやがん治療に対する考え方を根本から見直す必要があるでしょう。その際、がんの本質を見直すことはもちろんですが、もっと広く、人生観・世界観を がんと闘うことなかれ ・筆をとることにしたのは、患者たちが手術による合併症・後遺症や抗がん剤の副作用で苦しみ、治療のせいで亡くなった患者の家族が悲嘆にくれている現状があるからです。それらの治療が妥当でも必要でもなかったとしたら、それに気づいた専門家は、世に知らせる責任があると考えたのです。 ・人は夢や希望をもつことが大切、とよくいわれます。しかし、ことがんに関しては、それは当てはまりません。いやむしろ、夢や希望をもつことは有害とさえいえるでしょう。なぜならば、夢や希望にすがった結果、からだを切りきざまれ、たんなる毒でしかないものを使われてしまうからです。 ・人はいつか必ず死ぬのですから、宇宙の悠久の歴史からみれば、数年や数十年の延命などいかほどの意味もない、どういう治療をうけようが同じではないか、という見方も可能かもしれません。しかし、ひとつだけ大きな違いがあります。それは、医療の内容によって、あとで後悔するかしないかが違ってくる、ということです。 ・私は医療で一番大切なことは、だれ一人として後悔しないし後悔させないことだ、と考えています。せっかくよかれと思ってつらい治療をうけたのに、あとで後悔するのでは悲しすぎます。その場合、後悔したのは、現状認識や将来予測と治療の結果とが食い違ったためです。 ・これまで患者や家族が悲痛にあえいできたについては、がんと闘う、という言葉にも責任があったように思われます。つまりこれまで、闘いだから手術や抗がん剤が必要だ、と考えられてきたわけですが、そのために過酷な治療がおこなわれ患者が苦しんできた、という構図があります。 ・しかし考えてみれば、がんは自分のからだの一部です。自分のからだと闘うという思想や理念に矛盾はないのでしょうか。徹底的に闘えば闘うほど、自分のからだを痛めつけ、ほろびへの道をあゆむことにはならないでしょうか。また、逸見政孝さんの様子からも示唆されるように、患者が闘っていると思う相手はがんではなく、じつは手術の合併症・後遺症や抗がん剤の副作用と闘っているだけという可能性はないでしょうか。 ・がんは老化現象ですが、それはいいかえれば、“自然現象”ということです。その自然現象に、治療という人為的な働きかけをすれば、からだが不自然で不自由なものになってしまうのは当然です。どうやら私たちは、思想や理念のうえで、がんと闘うという言葉から脱却すべきところにきているようです。 ・治療で治せるがんはごく少数なのです。 ・肝心なことはがん治療に多くを望まない、ということのように思われます。がん治療には最低限、症状をとってもらうことを期待しましょう。ほかにメリットがありうるとしても、それはおまけ、なくてもともと、と考えるべきでしょう。またそのように腹をくくったほうが、専門家にすがって無理な治療をされてしまうより、長生きできることも多いものです。要するに、治らないことを率直に認めないと、長生きもできないし、楽にも死ねないわけです。 ・がん治療の将来にも、たいした夢も希望もありません。しかしそのことを悲観する必要はありません。なぜならば、私たちの人生にとって、がんやがん治療だけが大切なものではないからです。私たちにとって大切なのは、自由に生きる、なにものにもわずらわされずに生きる、ということではないでしょうか。そのためには死ぬまで、やまいからも解放される必要があるはずです。 ・しかし他方、やまいは気からというように、やまいは自然現象につけられた名称であって、私たちの頭のなかや観念のうちにしか存在しない、とみることも可能です。したがってもし私たちが、がんを自然現象としてうけいれることができるなら、がんによる死はふつう自然で平和ですから、がんにおいてこそ、やまいという観念から死ぬまで解放されることができるはずです。 後書き ・恐怖や不安という感情に対抗できるものは、知性や理性をおいてほかにない。 |