【最新更新日 : 2019年12月13日 金曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年12月13日 金曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
| 37 | 15.04 | 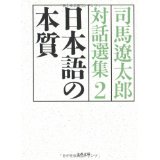 |
この国のはじまりについて2 | 司馬遼太郎 対談集 | 文春文庫 | ◎ | ・日本は歴史の発展の過程で、中国、朝鮮の影響を浴びるように受けている。たとえば奈良朝の仏教もそうですし、官吏になるためにも中国と同じように法律とか漢文学をやらなければならなかった。 ところが、菅原 ・明治になると、天皇をかつがないとどうしようもない。将軍を ・明治天皇までは一夫多妻で、大正天皇からはキリスト教徒のように一夫一妻になる。これは天皇史上はじめてのことです。 ・柳原二位局はあるとき、ご亭主の明治天皇が軍服を着て白い馬に乗っているのをみて、あんなことをしていれば天皇家の宮廷も滅びると、まわりの女官たちにいったそうですね。天皇とか公家というのは、ああいう武人の格好をしなかったからここまで持ってきたんだと。 ・現日本語は二音節。カタカナ二個であらわす言葉は、どうも縄文時代の完成された言葉じゃないか。 ・昭和二十一年には、当用漢字を千八百五十に決めてしまってるが、なんの根拠もないんです。 ・文化要素を自分で追い出して、これを使ってはいけないとか、使ってもいいとか、そんなこと言うのはおかしいと思いますね。こんなことをやっている国はないですよ。 ・その地方の人々が方言で喋ることを恥としない、あえて誇りと思わなくても、少なくとも恥としないところにしか地方文化はない。 ・地方の言葉を捨てて地方文化を守るのは不可能だと思うんです。 ・日本語にはいろいろ問題があるにしても、むつかしい哲学でも精密化学でも自国語で書ける。 ・若い人に対する場合、教える内容に教師自身が感動していなければ、伝わらない。 ・国語の時間は、いまの子どもたちにとって気楽なものでなく非常に苦痛な時間であるらしい。 ・国語の先生が、自分の教える古典と現代文を含めた日本の文章に誇りをもつことが少なければ、そういうことになるんじゃないでしょうか。 |
| 32 | 15.03 | 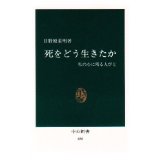 |
死をどう生きたか | 日野原重明 | 中公新書 | ◎ | 真摯に生き抜いた高橋敏雄さん 付添い婦との会話 ・人が生きるというのは、なにか目的があって、そのことのために生きる人生なら最高に幸せなんだね。 ・あきらめというか、悟りという言葉を自分のものにしたい。 ・なんとかしてこの不安な気持ちからぬけだしたい。もし病気で死ぬことになったとき、満足とまではゆかなくとも、なんとか自分で納得して、生きて来た意義をつかんでから死にたい。 ・明るい闘病 高橋さんの告白 ・多くの人のぎせいによって、今の私は生かされているのだから、そのことから考えても、真実を探り出して、より正しく生きねば皆に申し訳ないのだよ。 高橋さんの受洗 ・「〇〇ちゃん、いろいろありがとう、なにもしてあげられなくてすまなかったね」 石橋湛山前総理の闘病――その経済学、人生哲学 病室で語られた人生哲学 ・先生は戦後日本が領土をとられ人口過剰ということで、大部分の人が日本の将来はひじょうに暗いと考えたときに、「そうではけっしてない。海外の領土を失っても、日本に過剰といわれるほど良質な労働力をもてば、それが日本の再建の原動力となり、国の宝になる」といわれた。この「労働は富の源泉」「人こそよき資源」という経済原理は、日本の将来を正しく読みとることに役立ったのである。 『雨新者』のなかから ・「学問はなんでもそうだが、ただ本を読み言葉の上で理屈を知っただけでは、いわゆる畳の上の水練になり実際の役に立たない。それでは学問そのものも死んでしまう。本を読んだら、そこに書いてあることを絶えず実際の問題に当てはめ、自己の思考力を訓練し、学問を実生活に応用する術を習得しなければならない。医者は、遺書を読んだだけでは病人を治せない。本を読むとともに実習をする。経済学も同様である」 明日に生きた内藤豊次翁(エーザイ会長)――第四の人生に生きがいを 習慣づくりの人生 ・「若い時から、毎晩よく眠ることと、毎朝必ず便通をつけるという二つの習慣を身につけたのが、後年の健康に大きくプラスになったと思う。」 ・「毎朝食後に、自然に便を催すとはかぎらない。しかし便意があろうとなかろうと、朝食後のトイレ入りを日課の一つにして、出てくるまでガンバレば、やがて、いつも朝食が終わるや否や、からだのほうから便意を催促してくれるようになる」 癌とは告げられなかった福岡正一さん――司祭に真実をゆだねて 早期発見のむずかしかった癌 ・命は、長さではない、深さである。 恩師橋本寛敏先生の死に学ぶ――自然な死の姿 ・仕事を果して死にいく患者当人には、医師の治療よりも家人とナースによる看護ケアが、残された命の価値を深くさせる。 |