| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年04月20日 月曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き |
41 |
15.04 |
エゾの歴史 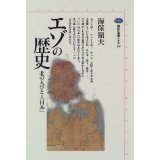 |
海保嶺夫 |
講談社選書 |
◎ |
はじめに 「技術的困難さ」から「政治的困難さ」へ ・近代になり「国境」が確定し、ために民族は分断され、人や物の交流に大きな制限が加えられた。 ・近代国家は、人を「国家」という檻のなかに閉じ込め、よほどの理由がないかぎり、檻の外へ長期的に出ることを認めない。 ・かかる体制の成立を、『近代」であるがゆえに「進歩」として肯定しなければならないのであろうか。 ・そのようなものがなかった時代のほうが、人ははるかに「自由」であった。 ・「自由」を時代の変化のメルクマールとすれば、「近代」はそれ以前より進んでいるとは言い難い。 ・「近代」とは機械文化がより高度化しただけでしかないのではないか。 第二章 エゾの登場 1 エゾと中世「日本」 最初のエゾ ・考古学的に言えば、続縄文文化人ついで擦文文化人、さらにはアイヌ民族へと、アイヌ民族が縄文段階より次第に変容した結果で、人種的には連続していることは明らかである。 第三章 エゾと擦文文化 1 文献史研究者の見た擦文文化 津軽と擦文文化 ・考古学的に見て、津軽は明らかに擦文文化の圏内にある。ようするに同時代の北海道本島の文化(オホーツク文化を除く)と同じであった。 ・また、和歌、中世軍記物語でも、共通してエゾは津軽と北海道本島(蝦夷が島)に広がっている。 ・前者は八世紀ごろから一三世紀ごろ、後者は一二世紀以後であり、両者は長期にわたり時間と場所とを同じくしている。 ・叙上の点から、筆者はエゾ=擦文文化人の意味であったと思う。この後、擦文文化人がアイヌ民族に変容するにともない、エゾは主としてアイヌ民族、さらには北方の人びと一般(アイヌ民族がほとんどのため)の意味に変化していったとかんがえられる。 3 北上する「骨嵬」 ・骨嵬はアイヌ民族とされている。 ・中国の勢力と最初に接触したサハリンの民族は、ギリヤーク族であって南部に住むアイヌ民族ではない。 第四章 波濤を越えて 2 「夷千島王」の謎 日本列島北部と朝鮮 ・日本列島北部(「夷千島」)と朝鮮方面との交流は現実に行われていた(十五・六世紀頃)。 ・一般的に考えられている以上に、北日本と朝鮮は日本海を横断する方式での交流があったようである。 ・この頃、日本列島北部と大陸との間に、直接交流のあったらしいことは考古学的にも推定される。 ・また、そういう前提がなければ、「夷千島王」(えぞがちしまおうとでも読むのであろうか)のごとき妙なものが朝鮮国王に「書契」を送ることなどありえなかったであろう。 第五章 未完の王権 1 エゾ地と権力 エゾと社会構造 ・北海道の歴史叙述は、明治以来官庁版が中心で、それは「開拓」を中心に記されている。したがって、その記述は中心的担い手である「和人」の活動が主で、アイヌ民族については簡単にすまされており、しかも偏見にみちたものとなっている。 ・「上からの近代化」=「開拓」の枠組みから抜け出せぬ北海道での、お役所の権威は現在でも他府県にくらべると強く、「開拓」時代=明治期のその権威の強力さは想像にかたくない。 開拓と民族 ・開拓=文化とし、開拓が出来るか否かで民族の優劣を判断し、「野蛮時代を脱しな」い「蝦夷」では不可能事で、なしうるのは「和人」のみであり、その移住こそが北海道の文化化の第一歩としている。このような和人優越論は、敗戦後も長く命脈を保ち、現時点でも顔を出すことがある。 2 渡党の場合 流通の都市 ・中世のエゾは基本的に三つ(日の本・唐子・渡党)に分かれていた。渡党は後の松前、箱館と推定される港を根拠地にして、津軽へ交易に来ると記されている。 第七章 底抜け鎖国体制――北からの道・北への道 2 中国の影 アイヌ民族と元 ・中国とアイヌ民族の最初の接触(記録上)は、一二六四年である。以後約半世紀の間、アイヌ民族(骨嵬)は元の大軍を向こうにまわして戦っている。 3 北方ルートでの交易 徳内の怒り ・松前藩は当初アイヌ民族の手を経て中国製品を輸入したが、そのやり方はアイヌ民族の犠牲の上にたつすさまじいものであった。 松田伝十郎の記録 ・松前藩はアイヌ民族より山丹人への借財返済の名目で、人売稼業の仲立ちをやっていたようである。 ・山丹人と直接取引をすれば松前藩の借財となることが分かっていたため、アイヌ民族を前面に押し立て、その犠牲の上に山丹品を入手していたのであろう。 ・幕府は山丹交易を中止させず継続させ、直接に交易するようになった。長崎方式を小型にした交易方法を導入したわけである。 ・松前藩は、北の物を南へ売り、また南の物を北へ売って生活していた藩であった。鎖国体制とは正反対のやり方をしなければ藩が立ち行かなかったのである。 ・松前藩は、「商人の藩」として理解するのが正しい。鎖国体制の底を抜いて藩を再生産させていたのである。 ・松前藩士は、たまたま、商人が帯刀していると考えるとよい。であっても、幕藩体制の一員として、松前藩はアイヌ民族などにたいし、藩権力を行使している。 第八章 エゾ地の閂 1 松前藩の役割――渡党の残影 蠣崎氏の役割 ・「日本」では、日本列島の北方に独立して生活し、「日本の言うがままにならない人びと、生活の仕方が大幅に異なる人びと」をほぼ一貫して蝦夷と表現している。 エゾ地=外国 ・エゾ地が幕藩体制の外と認識された理由は簡単には言えないが、エゾと呼ばれた人びとの生活が、主に狩猟漁撈と交易であって、土地(農耕地)の拡大をはかる本州以南の幕藩体制(石高制国家)と基本的に異なっていたことと、民族的相違などが原因であろうかと思う。 ・最北の藩(松前藩)の経済的基盤が交易であることも要因の一つであろう。 3 エゾ地の「門戸開放」――あきはじめる門 ネオ渡党 ・アイヌ民族への「同化」政策=固有文化の否定が強行されたが、強く拒否され、死をもって抵抗する人物のあったことが、松浦武四郎の『近世蝦夷人物誌』などに記されている。 終章 北方史研究私論――おわりにかえて 「日本」史の方法論と北方史 ・幕藩体制は、東アジアやヨーロッパ諸国に対してはたしかに「国を閉ざした」といえるかもしれないが、北および北東アジアに対しては、依然として大幅に門戸を開いている。 ・北方の前近代的なあり方を支えたのは、見かけは北方諸民族と「武士階級」であるが、実質はたまたま武士になってしまった冒険的商人である。 エゾ認識 ・エゾ表現はもともと俘囚文化圏で使用された言葉と思われる。いわゆる「日本語」への確実な出現は一二世紀中頃からで、まず和歌の世界や軍記物語に登場する。 ・地域的には、津軽と北海道本島方面をさし、時間的に考えて擦文文化人を意味したものであろう。 ・この表現は、擦文文化圏の隣国たる平泉政権の人びとから京都方面に伝えられたのであろう。プレ・アイヌ文化人をエゾと表現したわけである。 ・おおむね一三世紀に擦文文化はアイヌ文化に変容する。また、確実なところ一二世紀の末から鎌倉幕府はエゾ地を流刑地とし、これ以外の和人のエゾ地への北上もあり、この人びとは現地の風習や生き方を身につけ、現地人同様の生活をし、現地適応して ・「日本」では、一四世紀初頭のエゾは右の渡党と ・渡党エゾの統一者となった蠣崎氏は他二者からの圧力を軽減し、自己の政治的経済的地位強化のため、豊臣秀吉・徳川家康の統一政権にとびこみ、「和人大名」に変身した。松前藩の成立である。 ・これにより、エゾ=アイヌ民族のみの表現(アイヌ民族唯一説の確立)となり、方民はただひとつの意味となった。 ・幕藩体制は、近世エゾ(アイヌ民族)を体制外の人びとと明確に位置づけ、このあり方は、形式化しつつも、幕藩体制崩壊期までつづいた。 ・エゾ地であるかぎり、「日本」ではなかった。しかしながら、時代の進展にしたがいこの原則は崩れ、アイヌ民族は居住地ともども事実上幕藩体制の内に取り込まれるようになった。 ・エゾ地の北海道改称(明治二年)により、形式的にはエゾの歴史は終わる。 ・北海道全島の明治政府による開拓政策=本格的な「上からの近代化」が強力に推進された。 ・これは、アイヌ民族の生活を国家的レベルで否定することを意味した。 ・同時に、明治八年(一八七五)北方での国家領域が画定し、「日本」人すべての海外への自由な往来は遮断された。 ―― 完 ―― |