| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年04月13日 月曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き |
54 |
15.05 |
アジアの中の日本古代史 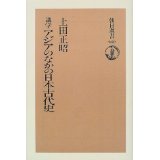 |
上田正昭 |
朝日選書 |
◎ |
序 アジアのなかの日本古代史 ・天皇という称号を日本ではいつごろから使うのか、いつから大王が天皇になったのか。 ・藤井寺市の野中寺に弥勒菩薩像があります。台座に「詣中宮天皇」の文言の有名な銘文があります。 ・法隆寺の薬師如来像の光背にも「天皇」という銘文があります。 島国史観を克服する ・越前の ・近畿という行政単位ができたのはそんなに古くない、一九〇三年(明治三十六)ごろからです。古代には畿内・近国という用語はあっても、近畿という用語はありません。 ・関西という用語がはじめてみえるのは、『吾妻鏡』の治承四年(一一八〇)の一〇月の条からです。 黒塚古墳の三角縁神獣鏡 ・大和の字は「養老令」で初めて使い、「大宝令」では「倭」の字を使っている。『古事記』や『日本書記』も倭です。 ・「養老令」が実施されたのは天平宝字元年(天平勝宝九・七五七)の五月です。古墳時代の四世紀や五世紀に大和などという字を使うのは適当ではありません。 ・「朝艇」というのは、厳密には ・宮中の部分ができただけでは朝廷とは言えない。王権があって政府の機構が出来て朝廷と言うべきです。 「魏志倭人伝」 ・『魏書』東夷伝倭人の条のことを、ふつう『魏志倭人伝』と言っていますが、これは『三国志』の一部です。 ・中国で後漢が滅んだ後に分立した王朝、魏、呉、蜀をあわせて三国と呼んでいます。この三国の歴史を、魏の後を受けて成立した西晋の歴史家(もとは蜀の役人)陳寿が書いた本が『三国志』です。 ・『三国志』が三世紀の後半に書かれた史書であることは間違いありません。 邪馬台国の外交 ・「詔書」や「伝送文書」、「上表」などの記事から、邪馬台国の外交は文書外交であったことが分かります。文書が読める人がいたということです。 ・邪馬台国は少なくとも五回、魏に使節を派遣しています。魏からの使節は二回来ている。 ・三角縁神獣鏡をめぐって、中国からの伝来の鏡という説に反対して、日本列島で作られた鏡だという方もあります。 ・日本で作られた鏡もたしかにあるんですが、その場合にも日本列島の在来の人だけでなく、渡来人の人びとの役割も考えておかなければなりません。 1 倭王権の成り立ち 「大和」「朝廷」「日本」という用語 ・「日本国」という名称はいつごろから使われるのか。七世紀後半からと考えてよい。論拠の一つは中国の文献(『 3 河内王朝 自立を強める倭王武 ・遣隋使も遣唐使もすべてが朝貢使です。いわゆる対等外交ではありません。しかし、遣隋使や遣唐使の場合は、中国王朝から爵号や軍号をいっさいもらっていません。隋や唐から朝鮮の国も ・そういう前提があったから、 4 大王から天皇へ 当時の朝鮮と中国 ・歴史を考えるときに、島国の中だけで考えていたのでは見えてこない。 ・倭国の場合は、いわゆる「東夷」のなかで「治天下」の大王としての独自性を保持していたことを軽視するわけにはまいりません。 ・倭王武の四七八年の遣使以後、六〇〇年の遣隋使の派遣まで、対中国外交は中断しますが、六〇〇年以後の遣隋使・遣唐使の場合は、中国王朝から軍号、爵号などを与えられてはおりません。 ・「治天下」の大王の自覚が、中国王朝中心の冊封体制からの自立をうながしていったと考えています。 5 飛鳥朝廷の内政と外交 冠位十二階の制定 ・冠位十二階以後、わが国の冠は布あるいは漆で固めた冠です。神主さんが被っておられる冠も漆で固めた冠です。 ・朝鮮半島などではまだ八世紀でも金銅の冠が使われているのですが、わが国は ・和魂漢才と申しますが、内なる文化と外なる文化を巧みに折衷して日本独自の文化を築いていくわけです。 十七条の憲法 ・私は現在の日本の精神的荒廃には、地域のコミュニティが急速に変貌し、われよしが先行して、家庭教育が崩壊したことが根本にあるというように考えているのですが。 遣隋使の持参した国書 ・外交というのは自信と勇気と決断と英知。その四つがないとまくいくはずはありませんが、飛鳥朝廷の外交は大成功であったと高く評価しています。その背後にはブレーンがいたわけです。飛鳥朝廷には渡来系の人材が多数いました。 6 飛鳥・天平の文化 ・雅楽がわが国土でどういうように具体化してきたか。 ・縄文時代にも音楽や舞がありました。縄文時代には明らかに神祭りの時に使ったと思われる土面や石面が出土しています。あるいは石笛も実際に出ていますし、土笛もみつかっています。 ・弥生時代から古墳時代になると、明らかに日本列島のなかで作られた琴、朝鮮半島の伽耶琴ではありませんで、日本列島に住んでいる人びとが造った琴が、つぎつぎに出土しています。 ・神を祭る、王者を慰める、あるいは葬送の時など、その時にお酒を飲むだけではなくて歌舞が行われたことは、『魏書』東夷伝倭人の条にもうかがうことができます。 ・日本列島在来の音楽や舞踊が古くから存在したことは事実ですが、これを大きく変えたのが海外から入って来た音楽や舞です。新しい楽器、あるいは新しい面や衣装などが伝わる。それらをわが国で集大成して、雅楽をつくっていくわけです。 ・「和魂漢才」は、十八世紀になって多くの人びとが使った「内なる和魂、外なる漢才」です。 ・幕末・維新期にはこれが和魂洋才になりますが、まさに雅楽は和魂漢才の文化です。内なるそれまであった歌舞に海外から伝わった舞や音楽をミックスして、わが国で集大成したものですね。 重視された雅楽寮 ・朝廷が神に位を贈ったのを ・皇族には ・神さまには失礼な話ですが、高くて正一位の神階、低いのには従七位などの例もありますが、日本の神さまは怒りませんね。 ・勅使が行って、「このたびあなたに従七位を贈ります」という祝詞をあげている勅使は従五位ぐらい、神様が下位だったりする場合もある。日本の神さまはおおらかです。品位を贈ったというのは重要です。 天武朝の七夕 ・少なくとも天武朝には始まっている七夕信仰は、今も日本人の暮らしの中に生きている。 8 長岡京から平安京へ 高野新笠の出自 ・天平文化を論ずるときに、たとえば大仏建立の立役者といってよい仏師の ・そして桓武天皇の母はまぎれもなく百済王族の出身です。 ・『続日本紀』は政府批判派が書いた歴史書ではなくて、天皇の命令を受けて編纂した歴史書です。そこにはっきり書いてあります。 13 天皇制と律令制 ・日本の律令制 律というのは、古代の刑罰法です。令というのは古代の根本の法律であって、現在で言いますと民法とか行政法とかにあたります。律と令によって土地、民衆を支配する仕組みを律令制度といい、そのような国家を律令国家と申します。 ・日本の近代政治は実態は古代とは異なりますが、律令制をモデルにスタートしたということも、ぜひ知っておいていただきたい。したがってこの律令制は、古代のアジアを考えるさいにも重要ですし、現代の日本を考える上でも重要な問題を含む。 ―― 完 ―― |