| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月12日 金曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
70 |
15.07 |
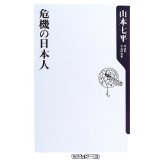 |
危機の日本人 |
山本七平 |
角川oneテーマ21 |
◎ |
【欧米人の見た日本】 ・十七世紀中ごろのオランダ人モンタス『オランダ使節日本紀行』 「日本人は、いかなる時にも己れの不幸困難を ・一六八九年刊行のフランス人イエズス会士J・クラッセ『日本 「日本人は物に堪え忍ぶ驚くべき美質あり。 日本人一般の気質として名誉を重んじ、自分が 日本人はその身分に準じ義務責任を怠らざるにより、不正の言語を発し人を 下賤貧困のもの その勇気の猛なること、忍耐力の強気琴は殆ど測るべからざるものとあり。まことに然り、彼らは災害にかかるもこれを悲しまず、平常の言語動作に於ても ただに悲しみにあいて痛苦することなきのみならず、非常な幸福に会うも歓喜の顔色をあらわすは ・一六九〇年(元禄三年)オランダ商館の医師として来日したE・ケムプエル『 「われはこの旅行に於て日本人より受けたる 「日本人は大胆または武勇と称すべき性質を有せり、ただし、ここにいわゆる武勇とは、敵の ・一七七五年(安永四年)医師としてオランダ商館に勤めたスウェーデン人K・Pツンベルグ『江戸参府紀行』 「 余はまたしばしば日本人の忍耐、親切、ことにヨーロッパ商人に対する親切を実体験したり。元来、勇猛なる民族たるに似もやらず、彼らはやさしく、温和なり。他の加うる脅迫に向っては動かざる山の如きも、友情に於ては 正義はこの地にては ・十八世紀、オランダ生まれのオランダ商館長イサーク・チチング『日本風俗図誌』 「日本人が、近代ヨーロッパの『国民』成立以前に於て、また彼ら(ヨーロッパ人)が未だ粗野不文明の束縛の下にありし時に於て、すでに文明開化したる民族たりしことを証明す。 大胆にして熟練せる水夫は勇気に於てインドの最も武を好む民族にも後れを取らぬ兵士に養成せられたるなり」 ・一八一一年(文化八年)ロシア海軍艦長、ゴローニン『ガローウニン日本 「概してこの民族は理解早く、直ちに受くる所を このように理解が早く、それを咀嚼して直ちに自分のものにする能力は何に基づくのであろう。彼はそれを教育だと見ている。 「日本人はこれをすべての国民に比するに、 ・一八五三年(嘉永六年)プチャーチンに提督秘書として同行した小説家ゴンチャロフの『日本紀行』 日本の自然が実に美しいこと、人びとは思慮があり、機敏で力強いこと、そして、「極東の諸国民中、その習慣の美なること、その社交の術を解する点において、日本の最も開化せるを悟れり」と記している。 ・一八五三年(嘉永六年)来航のペリー『日本遠征記』 日本人は個人的には怜悧・淡泊、正直で勇気があるけれども、幕府の役人となるとこれが一変して臆病で陰険で 吉田 「元来日本人は事々物々について疑念を起す人民であって、機会さえあればその ・一八五九年(安政六年)総領事として来日し、翌年全権公使となったオールコック『大君の都』 「物質文明について言わば、日本が東方各国民の第一位にするものなることは疑うべくもあらず。もし彼らにして応用科学に欠くることなく機械工業に進歩することあらば、彼らはヨーロッパ諸国民と優に競争するを得べきなり」 ・一八六〇年(万延元年)プロシアの条約締結使節に同行来日したマロン博士の『日本と中国』に記したグスターフ・シュピースの言 「婦人の地位は簡単 ・同上マロン博士の言 「日本人というものは、暴君のような父親から行儀よくおとなしく教育された児童のようだ。彼らは他人のものを盗むことがない、つまみ食いもしない、着物も汚すこともない、また一度でも だれひとりとして不平を称えるものもなく、なさねばならぬことは必ず実行しているが、それ以外の事は決して行わない。」 日本は専制君主の国といわれるが、その意味がヨーロッパと全く違うことを指摘している。たとえ将軍といえども、 彼が法律と見たものはむしろ「しきたり」とでも言うべきもののように思われる。いわば慣習のつみ重ねの中で法律のようになった「しきたり」は将軍といえども無視できない。 これは専制主義というより「しきたり主義」という方が適当であろう。 「国民にとって、あらゆる良いものの中でおそらく最上のものはパンであったろう。国民のすべてに十分なる糧食を与えるため、この国の全力は農業に注がれている」 この「しきたり主義」は奇妙な平等主義を生む。現在のわれわれは、将軍の食生活の貧しさとこの点では上下の階級差のないことに驚く。 「社会的関係におけるあらゆる日本人の、殆ど完全なるほどの平等は興味あるものであるが、われわれの習慣によっては殆ど理解できない。富と才能とはその所有主に対して決して特権ある階級を与えるものではない。百万長者といえどもその隣人と異った服装をすることは許されない。それゆえ生活上からは殆ど貧者と異なるところがない。貧しい人びとの日常食膳の上に見る魚、米、豆を、富んだ者も持っているが、それ以上のものを持ってはいない。日常品は豊富にしてかつ安価なるために、だれでも十分飽食するに足るほど持っている。階級とか特権とか人生の快楽とか、より高い知識階級でさえ決して金銭によって創造されることはない。社会的な階級を創造する条件は家柄と職業に他ならない」 ・安政二年(一八五五年)以降三度来日しているイギリス人セント・ジョン『日本沿岸航海記』 「日本人はいかに貧しくともその家は常に必ず清潔にして心地よし、余は田舎の人民によってしばしばその居宅に この種の記述、日本人は貧しくても清潔と整理・整頓を好み、ヨーロッパやロシアのような、無限に不潔で自堕落といった状態にならないといった指摘は彼以外にもある。 一方彼は日本人が必ずしも正直・率直でなく、その場に適合するように相手に口を合わせて、事実を言わない傾向のあることを鋭く見抜いている。 しかしこれは相手をだまそうという悪意から出たものではなく、この点、イギリスの下層社会より、まだよい状態であろうとしている。いわば相手の感情を損なわないように口うらを合わせたり、相づちをうったり、イエス・ノーをはっきり言わないという点にも現れている傾向である。 ・ザヴィエルが日本に来た一五四九年から、ルボンが来た一八八三年まで、約三三〇余年を通ずる欧米人の日本観の要約 まず、好奇心、探求心である。それは新しいことに興味をもち、これを理解しようと心掛けても、自らを絶対化して拒否することはしない。地動説でも進化論でも平気で受け入れ、きわめて記憶力にすぐれている。 ・・・ 実際に役に立つものには深い関心を示す。そして取り入れたものは日本化してしまう。またきわめて礼儀正しく、整然たる秩序を愛し、乱雑混乱を嫌って貧民でも清潔・整理・整頓を重んずる。ザヴィエルの時代でも盗みを嫌い、今と同じように泥棒は少ない。また詐欺を嫌う。 従って犯罪はきわめて少ない。大体において性質が温良で粗野な言葉や態度を嫌うが、実に勇敢な一面があり、また名誉を重んじ、これを生命より大切にする。親切だが喜怒哀楽の感情を表に出さず、相当な苦難に耐えて忍耐強く、自分の職務には精励し、上下の関係は礼儀によって厳格に守られている。災害にあっても別に悲しまず、すぐこれを克服しようとする。 正義を愛し温良であるとはいえ迷信・ 日本は科学技術の点でははるかにヨーロッパに劣るが、不必要な、人間を愚昧にする学者ぶりはないから、劣ったことは劣ったこととしてそれを克服する道を選ぶだろう。そうなれば、その好奇心・探求心、さらに活動的で生一本などの要因で軍事的にも経済的にもヨーロッパの恐るべき競争相手となるから、彼らを刺激しない方がよい。日本人は導入したものを必ず日本的に変えてしまって活用するから危険である。 日本人は個人的には怜悧・淡泊・正直だが、これが役人になると臆病・陰険・狡猾で、なんでも懸案を先にのばして決断をしない。また商人はその取引において決して さらに経済的にはきわめて合理性を重んじ、手形・小切手・倉荷証券等を古くから用いている。さらに社会のすべてが共同体的でそれぞれの中で合意を求めてから行われるから「強制」といった感じがなく、またそれぞれ共同体の中で相互扶助が行われている。そしてこれは労働者でも例外ではない。一般家庭では子供への身体的懲罰は行われず、根気の良い説得が行われる。婦人は、理想化もされず蔑視もされず、男性のよき相談相手、いわば女友だちだが、その活動は家庭内に限られている。 ・あらゆることに技能を競うことは、幕末から明治にかけて、しばしば欧米人を驚かした「職人芸」を生み出した。当時の欧米の機械類の多くは、職人の腕で模造できたのである。 【未来への課題】 ◎一貫して借金国だった日本 ・明治から一貫して日本の経済政策はおおむね、好感をもって迎えられた。 ・理由は、日本は外債を元利とも常に完全に期日通りに返済した唯一の国だったからである。日本は大変な資本輸入国であり借金国であったが、カントリー・リスクは皆無の国だったといってよい。この点では常に欧米の資本輸出国の優等生であった。 ・だがこれが日本にとって、どれほどの難事業であったか、理解している欧米人は殆どいないであろう。 ・安政五年(一八五八年)にアメリカが、悪名高い砲艦外交によって日本に押しつけた日米修好通商条約は、少なくともわれわれの目から見れば公正なものではない。日本は関税自主権を奪われ、一方的に、従量・従価はアメリカが都合のよい方を採用することで、最高五パーセントと定められていた。これは実質的には関税ゼロに等しい。 ・当時の日本には何の近代産業もない。そこへすでに工業化した先進国の製品が無関税でなだれ込めば、日本の伝統産業は壊滅するか、産業の近代化は不可能になる。後発の国は、保護関税で先進国に対抗して自国の産業を育成しようとする。現に、アメリカもドイツもこれをやっている。だが日本はそれを封じられた。その中で日本が近代化するのは、不可能といってよかった。過去において、こういう仕打ちをしたということは忘れないでほしい。 ・幸いに日本には絹があった。 ・一時は、日本国政府の予算の総額に匹敵したのである。日本は細い絹の糸にすがって近代化の道を切り開いたといっても過言ではない。 ◎論争をしない日本 ・ユダヤ人なら徹底して相手に論争を望むであろう。そして一つでも譲歩すれば、別の面で相手に何かを譲歩さす。だが日本人はそれをしない。またはっきり言って出来ない。相手の理不尽を相手の論理でつかむという術にたけていないからである。彼らはこれを反射的に行いうるが、それは伝統の違いであって、日本人にこのまねはできない。 ・しかし日本人は、言葉にはならなくてもカンは鋭いから、なんとなく納得できないという気持ちは抱いている。だがそれがしだいに蓄積して来ると、いつかは爆発する。日本人がよく口にする「今度という今度はがまんならない」が出てくるのである。 ◎「昭和の大失策」の遠因 ・当時は海軍国といえば英米日しかないわけであり、英米が対立して戦争状態になり、日本がキャスチングボートを握るという機会が来ない限り、日本海軍には出番がない。だが、そういった状態の現出はまず考えられない。とすれば日本は英米的秩序の中でそれを維持する役割を最低の負担で演じつつ国力を伸張させていくという方策しかなく、これが日本にとって最も有利な政策のはずである。そしてもしそれをせずに、海軍力の英米との対等を欲するなら、破産を覚悟で海軍力を三倍にする以外にない。だが破産をすれば、逆に、国際的影響力を失ってしまうからこれも意味はない。 ・それなのに日本は明確な決断もなく総合的プランもなく、英米体制を打破して、「東亜新秩序」なるものをつくるという方向に突っ走る、というより自らを追い込んで潰滅する。 ・冷静に考えれば英米に抑え込まれなくとも、これに対抗する軍事力を創設し維持しようとすれば日本は破産してしまうだけだから、意味のない行為である。 ・現在の環境を保持しつつその中で発展を策するか否かに基本があるはずである。だが、当時を振り返ってみると、このことを明確に国民に説明し、はっきりと国民の決断を求めた政治家がいなかったことに気づく。 これが、歴史的な「昭和の大失策」の遠因だ。 ・同じような現象は現在でもある。 |
69 |
15.07 |
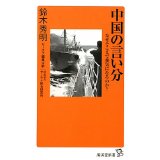 |
中国の言い分 |
鈴木秀明 |
廣済堂新書 |
◎ |
・そもそも日本人には、基本的にルールに従順という国民性があります。しかし、中国人にとってルールとは長い歴史を通じて、“お ・中国には、「上に政策あれば下に対策あり」という言葉があります。これは、国が規制のための法律を作ると、民衆はすぐその法の抜け道を考え出すということを意味しています。中国人には良くも悪くもルールを疑ってかかる傾向が強いのです。 ①領土問題 ・一度中国の領土であると声をあげたからには、たとえ海洋資源が大したことがなくても、振り上げた拳を引っ込めるわけにはいきません。そんなことをすれば、政府が国民から「かつての侵略国である日本に対して、今になっても弱腰だ」と突き上げられることは間違いないからです。 ・中国は資源の爲ではなく、国民へのアピールのために、尖閣問題を闘っている面があるのです。 ・中国は「沖ノ鳥島は島ではなく、ただの岩だ」と主張しています。2005年からは、沖ノ鳥島ではなく「沖島礁」という名称を用いるようになりました。 沖ノ鳥島が岩だとすれば、国連海洋法条約で「岩であれば排他的経済水域や大陸棚は認められない」と決められているため、その近海は日本の排他的経済水域ではなく、公海ということになります。 ・期を同じくして、中国は活発に沖ノ鳥島沖の海洋調査を行うようになりました。日本は排他的経済水域を侵害されたと抗議しましたが、中国は無視しています。「中国は一貫して沖ノ鳥島は岩であるという立場をとっており、日本の言い分は間違っている」と主張しているのです。 ・沖ノ鳥島には中国の軍事戦略問題が大きく関係しているのです。 ・中国はかねてから、第一列島線を戦略的防衛ラインと想定して、2010年までに第一列島線の内側の制海権確保を目指していました。2020年には第二列島線までの制海権を確保します。 ・さらに、2040年ごろまでには、米国による太平洋やインド洋の独占的支配を打破するとの構想です。 ・この計画を進めるうえでの障害のひとつになるのが、沖ノ鳥島の存在ということになります。 ・中国としては沖ノ鳥島を「島ではない」と主張し、日本の言い分を否定し続けながら行動することになります。国家としての「大戦略」にもとづくわけですから、沖ノ鳥島の解釈について、中国が簡単に諦めるとは考えられません。 ②政治・外交問題 ・靖国問題に関し、日本人の中には「死者には ・日中戦争を 特に、日本軍が上海に上陸して、南京に攻略の手を進めると、多くの日本人が熱狂しました。新聞なども、戦意を高揚させる“勇ましい記事”をこぞって掲載しました。極めて厳しい情報統制があったとことは事実としても、日本は“勝ち ・中国側が「侵略戦争の責任は、全日本人にある」と主張したのでは、日本との国交樹立は難しくなります。つまり、“軍国主義者”にすべての責任を負わせることは、中国側の立場では「日本人に逃げ道を残した」ことに他ならないのです。 ・中国側の政治指導者は立場上、「戦争責任はすべて“軍国主義者”に負ってもらうことにした。そのシンボルはA級戦犯だ。日本の政治家はどうして、こんなことを問題にしてしまうのか。避けようと思えば、避けられるではないか。政治センスのかけらもない」と考えていると思われる。 ・中国人は極めて政治的な人々だと言います。A級戦犯や靖国神社問題についても、「政治的に処理しろ」、「政治的に最善の結果をうみだす判断をしろ」と日本側に求めることになります。 ③中国人の意識 ・自己主張が旺盛で強引さもいとわない中国人の論法は、交渉の場では絶大な強みを発揮します。 ・はっきり言って「日本人が束になってもかなわない」ほど、交渉事にかけて中国人はタフです。 ・日本人は、世界でもっとも「温厚な人間関係を好む」民族のひとつと考えてよいでしょう。そのため、もめごとが発生すると「問題があること自体が問題だ」などと感じがちです。「けんか両成敗」という言い方もあるくらいです。交渉事がこじれると、それだけで大きな心理的負担を感じます。 ・中国人は違います。日本人とはむしろ対照的。交渉自体を「望ましくないもめごと」ととらえる感性はありません。むしろ、交渉事にはファイトをもやし、「できるだけの利益を得るためのよいチャンス」と考える傾向が強い。途中でどんなに紛糾しても、双方が本当に納得して合意すれば「にっこり笑って握手。これからは互いにうまくやりましょう」となるわけです。 ・中国人は、「相手に言い分を引っ込めさせるには、どのような方法が最も有効か」と冷静に分析しています。交渉は「正と邪」を決める場でなく「どのように得を取るかの過程だ」との意識が徹底しています。 ・中国人は現実的とよく言いますが、言葉を変えて言えば「状況が変化すれば、対応が変わってもおかしくない」との考え方が強いのです。そして、相手をじっくり観察します。大丈夫そうだと判断すれば、すでに契約したことでも「状況が変わった。もう一度話し合おう」と要求してくるのです。 ・中国人と交渉するときは、自分も中国人になりきって臨むことです。 ・交渉事で中国人が「原則」と言い出したら「これだけは、絶対に譲歩できない」という意志表明。 ・日本人は、主張が「議論の進行に流されてしまう」ことが多い。 ・中国人には絶対に譲歩できない「原則」と、譲歩可能な部分を、きっちりと分けて交渉に臨む天性のようなものがあります。 |
| 68 | 15.07 | 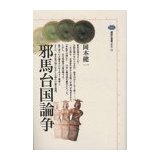 |
邪馬台国論争 | 岡本健一 | 講談社選書 | ◎ | ・南蛮人の渡来を促し、黒船に開国を迫られたのも、元はといえば、あの「黄金の国ジパング」伝説に由来する。 ――中国の東方の海に、「黄金の国」がある、「女王国」がある。 ・「黄金の国ジパング」伝説を一三世紀末のヨーロッパに伝えたのは、いうまでもなくマルコ・ポーロだ。 ・古代史家「三品彰英」 「吾々は、『魏志』の文を読むに当っては、陳寿時代の地理的知識に即して読むべきである。 「吾々は『魏志』が描いている通りに読めばよい。……特異な読方や解釈を試みたり、時には文字の訂正まですると、何時までも論争が尽きないのである」と主張した。 「われわれは今日の測量地図ではなく、撰者の脳裏に描かれていた地図を机上に想定して読まねばならない」 ・倭人は、距離ではなく日程によって、地域間の距離を表したとみられる。 ・「鬼道」は、 (1) の七点セットとして整理できる。 ・ |
| 67 | 15.06 |  |
日中国交正常化 | 服部龍二 | 中公新書 | ◎ | ・日中関係にはアメリカの影が常につきまとうのであり、そのことは今後も変わらないだろう。 ・日中国交正常化は、現代東アジア国際政治の原型となっただけでなく、政治家や官僚のあるべき姿を示唆しており、いまに生きる歴史なのである。 ・蒋介石氏、賠償請求を放棄してくれた。敗戦後日本が分割占領を免れて天皇制を残せたのも、大陸の敗残兵が引き揚げられたのも、蒋のお蔭にほかならない。 |
| 66 | 15.06 | 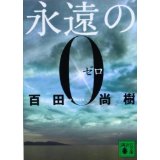 |
永遠のゼロ | 百田尚樹 | 講談社文庫 | ◎ | ・当時は試験の優等生がそのまま出世する。今の官僚と同じ。 ・戦争という常に予測不可能な状況に対する指揮官がペーパーテストの成績で決められていた。 ・かつての日本の軍隊について調べれば調べるほど、今の日本の官僚組織に通じるところがある。 ・彼らは作戦を失敗してもだれも責任を取らされなかった。 ・高級エリートの責任を追及しないのは陸軍も海軍も同じ。 ・代わって責任は現場の下級将校たちが取らされた。 ・責任を取らされないのは、エリート同士が相互にかばい合っているからだ。 ・当時の高級官僚は誰も責任を取らされていないばかりか、何人かは戦後、外務省の事務次官にまで上り詰めている。もしこの時、彼らの責任をしっかりと問うていれば日本人の『卑怯な民族』という汚名は ・名もない兵や将官たちは自分の任務を全うした。みんな国のために戦った。でも、日本の軍隊の偉い人たちは、本当に兵士の命を道具みたいに思っていた。 ・その最たるものが、特攻だ。 ・「大和」の出撃は絶望的なものでした。沖縄の海岸に乗り上げて陸上砲台として上陸した米軍を砲撃するという荒唐無稽な作戦のために出撃させられたのです。 ・負けることがわかってい戦いでも、むざむざ手をこまねいているわけにはいかず、それなら特別攻撃で、意地を見せるという軍部のメンツのために「大和」と数隻の軽巡、駆逐艦、それに数千人の将兵が使われたのです。 ・必ず死ぬ作戦は作戦ではありません。 |
| 65 | 15.06 | 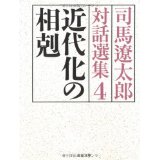 |
近代化の相剋 | 司馬遼太郎 対話選集 4 |
文春文庫 | ◎ | 日本人よ"侍"に還れ ・日本人はとことんまで対決しない。いい悪いは別にして、ともかく対決しないというか、ある点まで対決して、そのあとはサッと手をうつことによって、問題を解決していく。 ・他方、ヨーロッパの流儀はそうじゃない、とことんまでやる。しかし同時に忘れてならないのは、これは思想史の教科書によく書かれていることですが、思想の自由、異なった思想に対する寛容という態度が登場しはじめるのは、この三十年戦争のあたり、あるいはその渦中から、ということですね。 ・自分の宗教とか宗派に属さないものに対する追及、迫害、拷問などのすさまじさ、むごたらしさは、日本では考えられないほどものすごいもので、そういう時に使った道具などが、いまでもヨーロッパの博物館などに残っています。 ・つまり、ヨーロッパでは、精神や思想の問題で対決し、その勝ち負けの決着はつくものではないと、知識としてでなく文字通り、骨身にしみて知ったわけで、そこではじめて、異なった立場もありうるという認識、つまり寛容という結論に達したわけです。 ・その後も、フランス革命やロシア革命の例が示すように、とことんまで対決するという伝統は残りますが、それにもかかわらず、いや、逆にそれだからこそ、といえると思いますが、他の思想に対する本当の寛容な態度が、同時に養われていった、といえる。 ・ところが、日本の場合は、まずとことんまでやらない。やらないことが、逆に本当の寛容を生み出さない、そういう面がある。 ・一つの原理からででいる発想を改めさせることは、他の原理をもちこむ革命によらなければできないことですし、むろんそういう原理転換の革命は、容易にできるものではありません。 ・エジプトでピラミッドやスフィンクスあたりをラクダに観光客をのせてまわる案内人、彼らは強欲で旅行者から金をふんだくることしか考えていない、だから泥棒と同じだなどといいますが、それも彼らの原理から出ていることなんですね。旅行者は富める者だから ・日本人は、ある種の民族や国家について、枝葉のことでののしりますね。自分に原理がないものだから、原理にまで理解がとどかなくて、枝葉のことで生ずるつまらないアクシデントに猛烈に怒ったり、逆に猛烈に感心したりして。 ・朝鮮人には、一族というものについて特別な原理がある。だから場合によっては、親類を食いつぶしたっていいんです。食いつぶすというと、卑しい言葉ですが、向こうでは食いつぶすことが、極端にいえば原理に忠実なわけですね。こういう事例は無数にあります。 しかし、そういう国々の原理を無視して枝葉をとりあげて「朝鮮人はけしからん」と、民族の問題にしてしまいがちなんですよ、日本人というのは。 ・中国人は、日本には原理がないとみておりますから、日本をセッパ詰まらせるような所へ追いこんだら、破れかぶれのようにして、力をもってくると思っているはずです。 ・今の中国人は、日本人をこわがってはいませんよ。論理が一応通っていますからね。しかし、その論理が消えて行動が始まるということを、やはり警戒しているんじゃないでしょうか。 ・原理がある相手と交渉する場合は、ある程度の安心感がある。予測の可能性がありますからね。ところが特に日本のように原理のない国は、瀬戸際まで追いつめてはいけない。これは外交の一般原則でもありますけれど必ず逃げ道を残しておいてやらねばならない。もし日本をあまり追いつめたら……もう武力です。 ・いまの日本の商人たちを笑顔で迎えているのは、中国人の心の裏に、一抹の不安があるということで、彼らの洞察とそこから出てくる演技を、日本人は汲みとらなければいけない。 明治国家と平成の日本 ・立憲国家というものは、対立があって初めて動く。ところが日本では、必ずしもヨーロッパの王権対人民のような対立がなかった。だから、日本の人民というのは自分で世論をつくり上げ、自分が政治を動かしているという緊張感がない。 ・金権と、それから何か強硬論が出てくると、そっちのほうが格好いいからそっちに引きずられるという二点は、現代の日本でも心しなくちゃいけない。しかも、今の日本人は、いっさい言いわけできないんですからね。 ・主権者ですからね。 ・非常に重たい立場だと思いますね。そうであるだけに、非常に限定された制度の枠の中で、明治の先輩たちが一生懸命やっていたことを、やはり何度でも ・世界で天地鳴動の事件が起こっていても、国会で議論しませんよね。 とにかく、報道されるのは政局だけ。「政局」なんていうのは外国語には訳すことができない言葉ですよ。要するに限られた土俵の中で談合しているという状況です。政局があって政治がない。 ・鎌倉武士のプリンシプルは「名こそ惜しけれ」。十分にヨーロッパ的倫理と対抗できるものでしたが、いま、名こそ惜しけれという政治家がいるでしょうか。 ・現実にそうだったかはともかく、そういう規範が意識されているということ自体が大事なんですね。明治の人々が国民、国家をつくっていく。それに挑戦していったことは依然として私どもの課題なわけですね。その場合、明治の人と一つ違うのは、世界規模の公的なものへの寄与をしなくちゃいけないということです。 ・大事なことが起きているときに、国境の向こうだからといって傍観していいのか、人間の尊厳と生命がめちゃめちゃにされようとしているときに、それこそ「政局」だけでいいのかというのは、私たちにとっても大きな課題です。 ・とにかく日本は、世界の一員じゃないという意識でした。こんなに巨大になっても、まだあります。日本人は謙虚に自分自身を考えるべきです。 ・ともかく、何か問題が起こったら走っていって抱き起したり、お金が足りなかったらどうかこれを使ってくれといったりしなきゃ。ここまで経済がでっかくなったんですから。 日本がたとえ滅んだ後も、いい感じの国だったということを、あるいはいい感じの国民だったということを思われないと、何のために人間として生まれてきたのかと思いますよ。 |
| 64 | 15.06 | 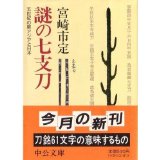 |
謎の七支刀 | 宮崎市定 | 中公文庫 | ◎ | ・古代においては、中国内部に大きな政変がおこるたびに、それが四方に波動を及ぼして、重大な影響をひきおこすのをつねとした。 このような現象はすでに古く、春秋戦国のころから見られたところであるが、とくに決定的であったのは、前漢五代の君主武帝の領土拡張政策である。 ・当時の日本人、いわゆる倭人は百余の小国に分れて地方に割拠していたという。その百余国のうち三十国ばかりが、これ以後、楽浪郡へ貿易に赴くようになった。 ・倭人百余国の中の奴国が、使を遣わして東漢の都洛陽に至って朝貢したのは、光武帝即位の三十三年目であり、帝から印綬を貰って帰ってきた。 ・後漢の中期、安帝の永初二年(一〇八年)に、倭国王師升という者が、使を出し、生口(奴隷)百六十人を献じて、天子に朝見を願ったことが『後漢書』に記されている。 その理由は、倭国王師升による、国内制覇が実現したためであるらしい。 ・従来のように三十余国が銘々勝手に楽浪郡へ出かけて朝貢し、貿易の利益をえて帰るのを止めさせ、倭国王の統制のもとに、秩序ある朝貢貿易を開始させた。この新体制を後漢の朝廷に認めさせる必要があって、さてこそこの年の朝貢が実現したものであろう。 ・滅亡に瀕した後漢王朝の大臣として、華北黄河流域一帯を斬り従えた曹操は、子の曹丕の代になって、漢の ・公孫氏の滅びたその年に、倭の女王卑弥呼の使者、難升米、および副使都市牛利らが帯方郡に渡って、魏の朝廷に赴いて貢献したいと申し出た。 ・魏の朝廷は久しぶりで帯方郡を恢復した効果が、このように早く現れたことに満足し、その年末に詔書を下し、女王を親魏倭王に封じ、金印紫綬を帯方郡をつうじて送り届けさせた。中国政府はひじょうに現金で、自分が招いたときには、せいいっぱい優遇する建前である。 ・義熙九年(四一三年)には、高句麗と倭国とが入貢して万物を献上している。ことに倭国の江南への朝貢はこれが初めてである。 ・秦始皇帝が治世の二十八年(前二一九年)に、斉人徐市(徐福)に命じ、童男女数千人をひきいて東海に入り、三神山に至って、そこの仙人について不死の薬を求めしたことは、『史記』「始皇本紀」に見えているから、伝説ではなく史実であった。しかしそれが不成功に終ったことも事実である。 ・宋の文帝の在位中、倭王讃が死して、弟珍が立った。讃は仁徳天皇、弟珍とは反正天皇に擬せられているが、これには異論もある。 ・宋朝廷の百済重視政策と、これに対して日本が、自国の実力伸張を理由として、あらたなる現実の認識によって、宋朝廷に日本重視への切りかえを迫った ・倭国からは、宋代にはいって初めて武帝劉裕の永初二年(四二一年)に朝貢使を派遣した。 ・当時の倭国は海上において、すでに対馬海峡を制圧していたので、半島南端の任那・泰韓・慕韓および新羅は、もし南朝に入貢したくても、倭国の同意、ないしは許可をえなければ、海上に船をだすことができない。おそらく当時これらの諸国は、倭国船に付随して、江南王朝に朝貢貿易を行なう恩恵にあずかっていたものであろう。 ・『三国史記』によると、当時の百済は連年北隣の高句麗と戦ったが、なんといっても高句麗は大国なので、しきりに敗北を重ねていた。そこで海をへだてた日本、当時の倭国に援助をもとめ、ときには太子を人質としてさしだしたりして、結好をもとめたりしていた。 ・百済の没落は、それに反比例して、日本勢力の上昇を結果した。その三年後、宋の後廃帝の後を嗣いだ順帝の昇明二年(四七八年)、雄略天皇と思われる倭王武が、自ら倭国王と称して、使を遣わして上表した。 |
| 63 | 15.06 | 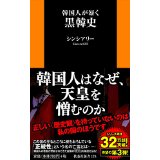 |
韓国人が暴く黒韓史 | シンシアリー | 扶桑社新書 | ◎ | ・韓国は反日思想によって生まれた国であると示している憲法前文の存在から、反共思想の弱体化による反日思想の強化、世代が変わるにつれて反日思想はさらに悪化していくだろうという話、さまざまな社会問題を精神的に抑えるためにも反日が必要で、本当は反日とは韓国内部の問題を映しているにすぎないという実態、そんな韓国とは基本的に距離を取る外交(擦り寄ることなく、基本だけに忠実な外交)を心掛ける必要がある。 ・「韓国語大辞典」によると、正統性とは<統治される人に、その権力支配を承認させ、体制を可能にしている論理的、心理的概念や根拠>になります。 ・韓国と日本においての「法意識」の差について 「日本は、合意の内容より『守る』ことを重視する。韓国では、道徳的に『正しいかどうか』の内容が重要で、正しくないなら事後的にでも正すべきだとなる」 ・正しさを追求する理由について 「近世までの朝鮮は、経済的に豊かではなく、軍事的に強大でもなかった。中国の儒教文化の強い影響下にあったこともあり、『何が正しいか』という名分論で自分たちの正統性を主張するしかなかった。それが『正しさ』を求める伝統を生んだのではないか」 ・「正しい」を「根拠」にしたデタラメな主張が、そのまま反日という「正統性<逆らえない根拠>」を作り出しています。そして、日本が従わないと、韓国は怒ります。「こちらに正統性があるのに、なぜ従わない!?」。言うまでもなく、日本から見るとそんなものは正統性でも根拠でも何でもありません。 ・正統性がちゃんとしていないほど、その集団(個人)は強権的になります。 言い換えれば、自分と違う意見(自分の正しさに一方的に同調しないこと)に耐えられず、よく怒ります。韓国がそうです。 ・日本の正統性を壊したいと思うのは、自分自身の正統性に自信がないからである。 ・歴代の朝鮮半島の国々は、自分の正統性を他国に頼り、それに邪魔となる過去の正統性を抹殺してきました。「不利な歴史は認めずに全否定する=自分から見て正しい歴史だけを受け入れる」の繰り返しでした。 ・『朝鮮經國典(一三九四)年』の記述 「前にあった国( ・朝鮮ほど土下座で一貫した国もなかったでしょう。 ・韓国人の儒教思想は違います。一般にいう「博愛」ではなく、何かの条件で制限された愛で構成されています。 ・儒教の判断基準は「差別」を前提とします。人の身分の尊卑を含め、天下万物には上下(尊卑)があることを肯定しているからです。そしてその序列に逆らってはいけないと説きます。 ・人々の精神世界を占領した「差別の宗教」の独裁は、「上」か「下」かでしか物事が決められない「二元論」的な考え方を人々に植え付け、恐ろしい階級社会を作り出しました。「勝つためには何をしても構わない」「負けたものへの配慮など無用」など、今の韓国社会にも影を落としている『ゆがんだ序列意識」の原型でもあります。 ・いくら頑張っても出世にはほど遠く、最大の権力は「生まれつき」、いわば血統でした。 ・「勢道政治」とは、朝鮮時代、王の親戚など一部の氏族が権力を握って、とてつもなく強い影響力を及ぼしていた政治の形を意味します。 ・勢道政治だけでなく、儒教社会の朝鮮で姓氏が持つ権力は何よりの憧れでした。 ・「私はこう生まれたからこのままで生きてこのまま死ぬしかない」 それを当たり前のものとして受け入れるしかない絶望が、「ハン(恨)」になりました。ハン(恨)は、「晴らすことができない悔しさ」という意味で、世界で韓国人にだけ存在する変わった怨みだと言われています。 最初から「悔しすぎて晴らすことができない」と決めつけているため、「解決」も「 ・一八六〇年、崔済愚(チェ・ジェウ)という人が立ち上げた「東学」という思想は、「人間は神聖で、人間は平等だ」を基本とします。詳しくは、「人乃天」、すなわち人は天である。天は神聖なものだ。人なら誰もがその天を持っている。だから、どんな人でも軽蔑や差別を受けてはならないという主張です。 ・東学は「天道教」という宗教になり、反日運動を主導していく民族主義勢力の1つになります。天道教は、勢力は弱くなったものの、韓国の民族宗教の一つとして今も機能しています。 ・誰もが天(神聖)を持っているというこ。それは、人には尊卑があるという儒教社会に対し、人は誰でも平等だという〈共産主義革命〉に他なりませんでした。そして、この「天」こそが、後に「民族」という概念へとつながっていきます。 朝鮮半島の民族主義が、今でも妙に共産主義っぽい側面を持っているのもそのためで、とくに北朝鮮のほうに強く残っています。 ・大日本帝国が日清戦争で勝利し、一八九五年、下関条約で朝鮮半島の独立が決まりました。 日本は最初から朝鮮半島を併合しようとしていたわけではありません。昔も今も、敵対する国と国境を合わせているのは得策ではありません。中国と日本の間に、独立国が必要だったのです。朝鮮半島の独立もそのためのものでした。 ・時代の変遷によって思想が変わるのは仕方ないとしても、朝鮮半島の思想はネガティブな側面だけが受け継がれ、肯定的側面は消えてしまいました。 ・例えば、「天」が人間の平等を謳ったものであるなら、身分制度を廃止し、頑張れば出世できる世の中を作ってくれた日本に対して牙を向けるのは、明らかに矛盾しています。 ・また、儒教の「差別」にあれだけ苦しめられた人たちが民族主義に走るのも矛盾です。民族主義は、他民族への差別でしかないからです。 ・また、歴史が長い(古い伝統が権威を持つ)、しかも単一民族(純血さ)を優秀さの基準とするのも、矛盾です。儒教的思考がバレバレです。 ・一九〇〇年代、儒教も天も民族も、肯定的にとらえられる側面はどこかへ行ってしまい、「自民族が嫌いなだけ」の否定的な側面しか知らない化け物へと変質してしまいました。大韓民国が神聖視している民族正統性は、その最終結果です。 ・この民族正統性を謳う朝鮮半島の民族主義は、大韓帝国が日本に併合(一九一〇年)されてからは、もはや限度を超えてしまいます。 日本が民族正統性を断ち切った! だから日本と戦わないといけない! あいつらは韓民族の誇りを奪おうとしている! 神性なる韓民族が、韓民族以外の別のものになってしまう! ……。 ・こうして、「朝鮮半島の『民族正統性』は『反日』とほぼ同じ意味として成立された」こと。 ・今でも韓国では、「親日」が「反日」と同じ意味でつかわれています。 ・植民地研究家のアレイン・アイランド氏曰く、「ダメになった大韓帝国こそが、むしろ日本にとって脅威だった」 「……二つの理由で朝鮮は日本の脅威になった。一つ目は、数世紀にわたる失政により、朝鮮国民がいくら望んだところで、自国が独立を維持できるほど十分な富と力を持った国に発展できる内部改革を期待できない状況にさらされていたこと。二つ目は、一つ目の理由によって、武力や策略を使ってロシアや中国が朝鮮半島を占有できるだろうし、そうなれば日本の国防を担当する個人や集団の誰もが黙認できない戦略的状況が招来されるだろうということだ……」 ・併合は日本の自衛でした。 ・日韓併合の全ての過程は、当時の国際法で認められた合法的行為であり、また、植民地ではなく、あくまでも「併合」でした。 ・韓国では、「国民感情が法律よりも上にある」とよく言われます。 ・韓国の憲法前文は臨時政府の正統性を明記(=「大韓民国は一九一九年三月一日に建立された」)したことで、併合時代は日本による違法占拠だと決めつけました。この意見に逆らうと、民族正統性を打ち切る大悪人になってしまいます。併合時代に日本に協力的だった人たちは「法的に」逆賊(反政府勢力)でしかなくなりました。彼らを「親日派」と言います。 ・さっそく一九四八年九月、「合法的反日」による大掃除が始まりました。「反民族行為処罰法」というものが制定されたのです。 ・その内容は、「日韓併合に積極的に協力した者は、死刑又は無期懲役に処し、その財産の全部または一部を没収する、というものです。 ・この時点からすでに「反民族」と「親日」が同じ意味で使われています。 ・「不遡及の原則(法律は成立する前の事案に対しては効力がないという近代法律の鉄則の一つ)に見事に違反します。 ・当時は朝鮮戦争が始まったせいで、この法律はうやむやになりましたが、二〇〇〇年代に別の形で復活し、韓国の反日思想を牽引することになります。 ・ケネディ大統領は、直属のタスク・フォースを作り、どうすれば韓国を親米国にできるのか≒経済成長に導くことができるのかを研究させます。一九六一年にメンバーたちが作った報告書に曰く、 「米国は、韓国で民主主義が成功するように力を注いできました。北の共産主義体制との直接的な競合だけがその理由ではありません。アメリカの威信がかかっています。軍事計画的にも、韓国の南半分の制御は、西太平洋の防衛、とくに日本の防衛のために極めて重要であります」 ・今でも韓国人は法というものについて「気に入らないやつを潰すための力」という認識を持っています。告訴、とくに ・韓国では、「謝罪」もまた人の上下を決める手段でしかありません。何かの重い事案で謝罪してしまうと、その人は「下」になります。少なくとも韓国人の考え方では、慰安婦問題においての日本の正統性<上に立てる正統性>は、河野談話で破壊されたのです。 ・何が恥ずかしいのかというと、何が悲しいのかというと、民主主義というのは、選挙結果で物事を決めるという「根拠」の上に立っています。民主主義こそが、「今」のこの国の正統性であり、そうでなければなりません。生まれからして正統性という言葉に命をかけてきたこの国が、民主主義を名乗って六十五年が経ってもなお、「未だ選挙一つまともにできないのか?」・・・・・・全身から力が抜けていきます。これで「過去」の半万年の正統性を謳ったところで、何の意味があるのでしょうか。 ・その上、韓国の憲法上の権利をなぜアメリカに訴えるのでしょうか(選挙の不正による再選挙を請願)。まだこの国の人たちには、「我が国の正統性は大国から決めてもらう」という思考が残っているのでしょうか。慰安婦問題などをアメリカに持ち込む人たちも含めて。 ・ ・韓国の言う真正性は、「こちらが正しいと思う事に一方的に合わせろ」という意味しかありません。韓国人にとって「自分の正しいこと」は「逆らえない根拠」。すなわち「私の出した正統性にお前も合わせろ」と同じです。だから、「こちらがやることは、寛容を施すことだ」と上から目線で言い切ることができるのです。「話し合いで意見を合わせてみよう」な態度ではありません。首脳会談の条件としてそんなものを要求するとは、完全に首脳同士の「上下を決める」、「日本は格下になれ」と言っているようなものです。 ・韓国は他の「正しい」を認めることができません。他の「正しい」を認めることで、自分の正統性が否定されると思っているのです。だから強権的になります。話を聞こうとしません。自分の聞きたいことだけを、自分を褒めることだけを求めます。 ・日本は韓国と外交をするにおいて、ただ隣国だから仲良くしないといけないという、「みんな仲良く」な理想に縛られて、擦り寄ってはいけません。例外や特例などを認めず、良いことは良い、悪いことは悪いと、とてもマニュアルな態度で、「基本」に忠実な外交を心掛ける必要があります。 すなわち、距離を置く外交関係をする必要があります。 ・日本に対しては千年経っても許さないという国が、なぜ中国にはあっさりと態度を変え、こうも「親中路線」に熱心なのか。そこには大まかに三つの理由があります。 その一は、反日です。 反日思想があまりにも強大になりすぎて、韓国の反日思想に同調してくれる中国を仲間だと思うようになったのです。日本の集団的自衛権などに賛成しているアメリカは、相対的に嫌われるようになりました。 その二は、経済的な問題です。 韓国は、国のGDPのほとんどを貿易に頼っています。そして、その貿易の最大の対象国が、中国です。 韓国は、経済と安保という二つの「現実」を、それぞれ中国とアメリカ、まったく違う二つの大国に頼っているわけです。 その三は、「反共思想」の強いはずの保守勢力が、親中路線への牽制にならなかったことです。 この韓国の親中路線は、韓国という国への信頼と、朝鮮半島問題で中国に頼る姿勢において、アメリカに大きな危機感を与えました。 ・韓国人は「(自分で)正しい」という主観的な判断を正統性、すなわち「根拠」にしています。そして、その「正しい」を確固たるものにするために求めるものがあります。それが、「正しくない」存在、すなわち絶対悪です。絶対悪の反対になることで、自分が絶対善になれます。 ・韓国にとって、その絶対悪は日本です。民族正統性そのものが反日から始まったからです。自分たちに有利な要素ばかりで、考古学的根拠などは無視されています。併合時代を前後しての法的手続きにも矛盾しています。それでも、嘘をついてでも「日本」を絶対悪とすることで、民族正統性は絶対善として成立しています。それを受け継いだ(と主張している)のが大韓民国です。 ・しかし、そんなやり方で「自分」を見つけることはできません。自分が見つけられないから過去ばかり気にすることになります。いずれ動揺します。自分が見下されていると思い込み、強権的になります。これは韓国人が命より大事にしている「体面(面子、プライド)」とも関わっています。そうやって、どんどん、どんどん、「自己肯定」の仮面を被った「自己否定」の沼にハマっていきます。 |
| 62 | 15.06 | 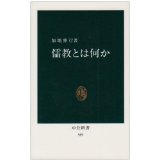 |
儒教とは何か | 加地伸行 | 中公新書 | ◎ | ・仏式の葬式で、参列者のほとんどの人が拝み方をまちがっている。 ・参列者のほとんど百パーセントの人は、葬儀場に安置されている死者の ・仏教徒であるならば、その寺院の本堂中央に安置されている本尊をこそ拝むべきである。死者の柩は真正面でなく、かたわらに置いてもいい。なぜなら、仏教では、仏を、ひいては ・では、人々はなぜ柩を拝むのか。これは実は、仏教ではなく儒教のマナーである。厳密に言えば、儒式争議の一段階なのである。 ・本尊に読経し死者を導いた導師が、出棺前に柩をそのままにして、さっさと先に退場してしまい、なぜ出棺に立ち会わないのか。 その理由は簡単である。仏教では、死者の肉体は、もはや単なる物体にすぎないからである。死者は成仏したのである。あるいは、成仏しない場合、その霊魂は生の時間から、(「 ・しかし、儒教は違う。儒教では、その肉体は、死とともに ・儒教では、死者になると、それを ・儒教的には、死者の肉体は焼くべきではない。かつては遺体をそのまま土葬することが多かったが、それは儒式である。仏教は火葬にする。死者の肉体には仏教的意味が認められないからである。 ・仏式葬儀の中に、儒式葬儀の儀礼が取りこまれているのである。 ・死者の 序章 儒教における死 一 <女の姓を返す>儒教 ・結婚後の改姓の点である。明治まで日本にはこんな改姓という習慣はなかった。少なくとも姓を有していた人々の間では。なぜなら、儒教では、その人の持つ姓を最も重んじて同姓不婚(同じ姓の者とは結婚しない)という理論を立てており、夫婦別姓を守ってきたからである。 ・儒教に基づいて、現代でも中国・朝鮮では、結婚後も実家の姓を名乗る。 ・日本人の祖霊感覚は実は仏教よりも儒教に、より近いのである。 二 仏教における死 ・仏教は、この世を苦しみの世界とする。これが大前提である。 ・人には必ず死が来て、その生涯が終わる。 ・さて、肉体の死とともに、霊魂は浮遊する。肉体は ・一方、成仏しないかぎり、霊魂は、肉体の死とともに、 ・さて、どこへ生れ変るのか。これにはランクが六つある。最高界は天上界で、神に生れる。その次は人間界であって、人間として生れ変る。というふうになり、六番目の最下界は地獄である。その他にたとえば四番目は畜生界であり、そこは人間以外すべての動物の世界である。 ・なにしろ生は苦しみなのであるから、この生れ変るということは、実は再び苦しみが始まることなのである。転じ生れて、そこにおいて生・老・病・死の苦しみを再びくりかえすということである。このように霊魂が転じ生れる。つまり ・このように、くりかえしぐるぐると、何度も何度も循環するわけであるから、丁度車の輪が ・しかし永遠に輪廻転生していたのでは救いがない。そこで、この束縛から、なんとか解き放され、苦しみの世界から脱したいという願いになる。解き脱す、すなわち解脱である。解脱するとは、仏と成れることである。解脱し仏と成れば、ついに苦しみから逃れられる。 ・結局のところ、解脱して成仏するのか、それても輪廻転生して苦しみ続けるのか、そのどちらかということになる。すると、成仏の場合は別として、輪廻転生するとすれば、理論的に言えば、霊魂は天界から地獄までの六つの世界のどこかに生れ変っているわけであるから、中陰の時期を除いて、霊魂はどこにも存在しないことになる。 ・仏教はみごとなことばを述べている。「形アル者ハ、必ズ滅ス」と。霊魂は別離し、肉体は ・墓は仏教と7は関係ない。 三 中国人の死生観 ・風土的に言って、南アジアのインドは酷烈な環境である。「生きていること自身が苦しみである」ということばには実感がある。仏教のみならず、インド諸宗教が、共通してこの世の苦しみから救済を、解脱を求めたのは当然であろう。 ・風土の酷烈さと言えば、インドよりも、砂漠の中近東一帯(西アジア)はいっそう厳しい。とすれば救世主を求め、天国を夢想し、生きてゆくためにあれこれと選択する余地なく、唯一神を信ぜざるをえない感覚も分る気がする。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教などがそれである。 ・中国、朝鮮、日本――これらの国は、西アジアの中近東や南アジアのインドよりもはるかに住みやすい上に、多神教の国々である。その代表である中国の人々は、インド流のこの世は苦しみの世界であるなどということは絶対に考えなかった。ましてキリスト教のような、人間は原罪を持つなどという考え方は、まったくなかったのである。 ・それどころか、中国人は、この世を楽しいところと考えたのである。ここが、インド人や、中近東の砂漠の人々と決定的に異なるところである。 ・中国人は、五官(五感)の快楽を正しいと認めるのである。眼、耳、鼻、味覚、触覚――五官(五感)の快楽、それは活きている人間の喜びとするのである。 ・仏教ではどうか。そのような五官(五感)の快楽を否定する。それは煩悩であるとして。 ・中国人の思考は、漢字ならびに漢字を使った文章によってなされる。とりわけ漢字が重要である。この漢字は本質的には表意文字である。その表意とは、物の写しのことである。物の写しであるから、まず先に物があり、それに似せた絵画的表現として漢字の字形が生れる。とすると、なによりもさきに、物体(自然的存在)があるということになり、物の世界が優先する。「はじめにことば(神)ありき」ではなくて、「はじめに物ありき」なのである。だから、形而上的世界よりも形而下的世界に中国人の関心が向かうようになる。こういう構造から、中国人はものごとに即して、事実を追って考えるという現実的発想になったのである。現実とは何か。それは物に囲まれた具体的な感覚の世界である。このため、感覚の世界こそ中国人にとって最も関心のある世界とならざるをえなかったのであ。 中国人が現実的であり、即物的である、ということの根本的理由はここにある。だからこそ、中国人は、現実に密着する五官(五感)の世界をこそ最優先するのである。 ・五官(五感)の世界――これはこの世のものである。美人を見たい、いい音楽を聴きたい、よい香りをかぎたい、おいしいものを食べたい、気持ちのよいものにさわりたい――この現世の快楽を とすれば、中国人は、快楽に満ちたこの現世にたとえ一分でも一秒でも長く生きたいと願わざるをえないではないか。来世とか、天国とか、地獄とか、そのような現実感のないフワフワとしたものは、中国人にとって信じがたい虚構の世界であった。 しかし、いくら現世の快楽をつくそうとも、いずれ必ず死が訪れる。現世をこそ最高とする中国人にとって、これはたいへんつらいことである。インド人やキリスト教徒のように来世や天国を信ずることのできる者にとっては、この世は仮の世にすぎないから、死もまたその過程の一つにすぎない。神仏のおぼしめしと思えば、死の不安も恐怖もない。しかし、現実のこの世しか世界はないと考える中国人にとって、死はたいへんな恐怖である。とすれば、その死を 四 儒教における死 ・中国人は現実的・即物的である。この世に徹底的に執着する。特に金銭への執着はものすごい。こうした感覚の中国人といえども、彼らに死が必ず訪れる。当然、現実的・即物的人間として納得のゆく死の説明を求めることとなる。その説明は可能か。 可能である。いや、可能な説明をしようと努力した集団があった。それが<儒>である。彼らは後に儒家という思想集団になった。 ・中国人は、この現世に一秒でも長く生きていたいという現実的願望をもっているから、やむをえぬ死後、なんとかしてこの世に帰ってくることができることを最大願望とせざるをえない。そこで、死後、再び現世に帰ってくることができるという方向で考える。生と死の境界を交通できると考えるわけである。 ・しかし、現実には、死後、肉体は腐敗して骸骨となるだけである。そこで<儒>はこう考えた。人間を精神と肉体に分け、精神の主宰者( すなわち、肉体の呼吸停止が始まると(脳死ではなくて、心臓死を意味する)一致していた魂と魄とが分離し、魂は天上に、魄は地下へと行く。これが死である。 ・すると理論的に言えば、逆に、分離していた魂と魄とを呼びもどし、一致させると<生の状態>に成るということになる。ただし、どこに呼びもどすか、という点が問題である。 最もふさわしいのは、死者の肉体であるが、時が経っており、ただ白骨が残るのみである。そこで、白骨化した骸骨の内、頭蓋骨が特殊な意味を持っていると考えられるので、この頭蓋骨を残しておく。残りの骨は、後に埋葬するようになり、それが発展して墓となってゆく。 ・一般にお ・こうした儀礼を続けるうちに、 ・儒は、世界共通の招魂儀礼を基礎にして、一大理論体系を作っていったのである。ここが、儒教と他の招魂儀礼宗教と決定的に異なる点である。 ・招魂儀礼とは、祖先崇拝そして祖霊信仰を根核とする。 ・当然、祖先を これを肉親の関係で言えば、 祖先 ・・・・・・ 祖父母 ―― 父母 ―― 自己 ―― 子 ―― 孫 ・・・・・・(一族) ということになる。整理すると、(一)祖先との関係(過去)、(二)父との関係(現在)、(三)子孫・一族との関係(未来)、を表している。 ・そこで、儒は、この関係をばらばらのものとしないで、一つのものとして統合する。すなわち、(一)祖先の祭祀(招魂儀礼)、(二)父母への敬愛、(三)子孫を生むこと、それら三行為をひっくるめて<孝>としたのである。 ・ふつう、孝といえば、(二)の「父母への敬愛」だけのように考えやすいが、それは誤りである。(一)「祖先の祭祀」、(三)の「子孫を生むこと」、この二者もまた孝としたのである。儒の言う孝とは、そういう内容である。 ・孝を行なうことによって、子孫を生み、祖先・祖霊を再生せしめ、自己もまたいつの日か死を迎えるのではあるけれども、子孫・一族の祭祀によってこの世に再生することが可能となる。儒は、「〔我が〕身は親の ・その結果、ここに一つの転換が起る。自己の生命とは、実は父の生命であり、祖父の生命であり、さらに、実は遠くの祖先の生命ということになり、家系をずっと遡ることができることになる。すると、いまここに自己があるということは、実は、百年前、確かに自分は生きていたことでもある。いや、百年はおろか、千年前、一万年前、十万年前にも、ひいては生命のもとであったところにまで遡って自己は確かに存在していたことになるのだ。それは、<血脈>あるいは<血の鎖>と言っていい。それと対照的に、一方では子孫・一族があり、百年先、千年先、一万年先と、もし子孫・一族が続けば、自己は個体としては死ぬとしても、肉体の死後も子孫の生命との連続において生き続けることができることになる。 ・孝の行ないを通じて、自己の生命が永遠であることの可能性に触れうるのである。そう考えれば、死の恐怖も不安も解消できるではないか。永遠の生命――これこそ現世の快楽を肯定する現実的感覚の中国人が最も望むものであった。これは韓民族に対する死の説明として最もよく整ったものとなっているのである。 ・そしてこの死の理論は、逆に言えば、永遠の生命を認めようとする生命論となっているのである。 ・生命論――これが孝の本質である。儒は、招魂儀礼という古今東西に存在する呪術を生命論に構成し、死の恐怖や不安を解消する説明を行なうことに成功した。この生命論のとしての「死の説明」を受け入れた者こそ、一般の中国人(漢民族)であったのである。 ・この生命論としての孝を基礎として、後の儒教はその上に家族倫理(家族理論)を作り、さらにその上に、社会倫理(政治理論)を作ったのである。後世になり十二世紀の新儒教になると、さらにその上に宇宙論・形而上学まで作るようになった。 第一章 儒教の宗教性 二 宗教の定義 ・ ・すなわち、多神を統合するため、東北アジア人はこう考えた。或る最高の神的実在があるとする。たとえば真言宗では、それを ・こうして、東北アジア人は最高神(最高実在)といったものを八百万の神や仏に解体して、すべての神仏を統合している。もっとも最高神のことはあまり念頭になく、あいかわらず多神教的感覚で眼前に据えたてまつった八百万の神や仏を拝んでいる。あえて言えば、最高実在など関心の外であり、どうでもいいという統合のしかたなのである。 ・諸神諸仏(キリスト教の神も含めて)を通じて、或る最高実在に向かおうとする。それはやはり一神教の感覚である。東北アジア人は、逆に最高実在を多神(諸神諸仏)に解体し吸収し、諸神諸仏を創る事へと向かうのである。 三 儒教の宗教性 ・その民族の民族性に適合した死ならびに死後の説明をなしえたとき、それはその民族の国民的宗教となる。 ・宗教とは、死ならびに死後の説明者である。 第二章 儒教文化圏 一 いまなぜ儒教なのか ・第二次大戦後、日本ではいわゆる近・現代国家たるべく、個人主義を唱える日本国憲法を<神>のように崇め、個人を重視し、家族共同体やその理論である儒教を批判してきた。しかし世界的には、共同体の再評価とともに、その理論である儒教を再び評価しようとしているのである。 二 儒教文化圏の意味 ・儒教文化圏を歴史的に継続せしめて来た根本は、儒教の宗教性にある。 ・その儒教の宗教性とは、現世を快楽とする東北アジア人の現実感覚にふさわしい死ならびに死後の説明理論である。そしてそれは、具体的には祖先崇拝として存在する。この、祖先崇拝と結びつく宗教性に基づく儒教の政治的・文化的影響を、有史以来、今日に至るまで受けている中国・朝鮮・日本を一つの文化圏と考えることができる。このように<孝とりわけ祖先崇拝を核とする儒教によって歴史的・宗教的に一体化されている文化圏>というのが儒教文化圏の概念である。 第三章 儒教の成立 一 原儒――そして原始儒家 ・体系を持った理論・思想という意味で、儒教が孔子から始まったとするのは正しい。けれども、孔子とて儒教思想のすべてを独創的に造り出したわけではない。 ・或る思想、或る理論体系が登場するとき、必ずその母胎、あるいは先駆的なものがある。孔子に始まる儒教、理論体系を持った儒教が登場する前、その母胎があった。それを原儒と名づけておく。 ・原儒の本質はシャマン(天上の神・魂など神霊なものと地上の人間とをつなぐ能力を持つ祈禱師)である。 ・世界のシャマンのほとんどは、まさに祈禱それだけの任務に終っており、俗言的水準にある。 ・しかし、儒教は原儒のシャマニズムを基礎にして、孝という独自の概念を生み出し、この孝を基礎にして家族理論を造り、さらにその上に政治理論を造り出し、一つの体系的理論を構成したのである。 ・儒教では、祖霊への宗教的行事を筆頭に、家において冠婚葬祭を行なうので、いわゆる教団宗教の行為に比べて日常的であり、人々には宗教と気づかれないできたのである。 四 孔子の孝と礼制と ・後に仏教がはいってきたとき、儒教が仏教を批判した一つの理由は、僧侶が ・喪に服する期間の意識は、現代日本において今も生きている。それは学校や官庁・会社において認められている忌引という特別の休暇制度である。それは儒教の喪制の考え方に基づくものである。 五 儒教の成立 ・需給の考え方では、死生の上に孝を置き、孝の上に礼を載せている。この礼が社会の規範(それを延長すると最後は政治理論となる)であることは言うまでもない。そして、その礼の基準の役割を果しているのが、親の葬儀を中心にしている喪礼である。 八 道徳と法と ・ 儒家 → 道徳第一(共 同 体 的) → 慣習法重視 → 徳治 法家 → 法律第一(中央集権的) → 成文法重視 → 法治 これが法治や徳治といわれるものの真相である。 第五章 教学の時代(下) 一 儒教・仏教・道教――三教 ・仏教・道教ともに、後漢時代から魏晋南北朝時代、そして隋唐時代へという、七、八百年の間、中国において盛んであり、その間、はじめは儒・仏・道の三教が争い、やがて融和してゆくという歴史があった。 ・死――その恐怖の解決方法の説明こそ、宗教にとって最大の課題である。 仏教は輪廻転生を説き、儒教は招魂再生をいう。道教は不老長生を説く。 ・儒教――子孫の祭祀による現世への<再生>――招魂再生 道教――自己の努力による不老<長生>――――不老長生 仏教――因果や運命に基づく輪廻<転生>―――輪廻転生 終章 儒教と現代と 一 現代における儒教 ・日本人はお彼岸やお盆には祖先の墓参りをする。仏教においては、墓を建てることはもとより、墓参りなどあり得ないのに、日本人はそれを行なう。すなわち、墓参りは本来儒教であり、その日をお彼岸やお盆の日に選ぶのは日本仏教である。 ・ホテル家族(家をただ寝泊りに使うだけで精神的つながりの乏しい家族形態)となる大きな理由の一つは、おそらく仏壇や墓に対して関心がなかったり、法事や墓参りをしない家庭であろう。 ・家族における精神的つながりを、各家庭において持っていること、それは家庭という空間を安定させるとともに、過去(祖先)から未来(子孫)にかけての時間という儒教風の永遠を求める意識を養っている。そこから、現実の己の生死を越えて広い世界を見る眼も生れてくる。 ・もし儒教風の永遠をこの世に求めるとすれば、社会や地球に対して、 ・義務に力を入れず、ただただ個人の権利の主張を突出させるだけという行きかたもそぐわない。常にいま自分とともにある家族という共同体と運命を共にするというのが、儒教文化圏の人々の心情なのである。すべては、ここから始まる。 ・儒教文化圏の人々には、キリスト教的な唯一神の 二 儒教と脳死・臓器移植と ・各思想・宗教において死に対する観念はさまざまである。しかし、死後、肉体は土に帰り、魂は肉体から脱けでて存在するという観念は非常に古くからあり、また世界各地に見られることはいうまでもない。さらに、この魂を現世に招いて再生させる招魂儀礼もまた古くから広く行われてきた。いわゆる祖先(祖霊)崇拝はその典型である。 ・儒教は、①一族が亡き祖先を追慕して祭ること、すなわち招魂再生儀礼、②生きて親につくすこと、③祖先以来の生命を伝えるため子孫を生むこと、この三者を合わせて「孝」と称し、儒教理論の根本とした。 ・孝とは、祖先という過去、親という現在、子孫という未来にわたって生命が連続することに基づく思想なのであって、現在の親だけを対象とするものではない。 三 儒教と教育と――そして自然科学的思考の基盤 ・中国には儒教以外の思想も存在してきた。その代表が老荘思想である。 ・老荘は、儒教が<人工・人為>を重視したことを徹底的に批判し、逆に自然を尊重した。 ・儒教の立場では、自然的世界は未開・野蛮なものであり、人間の手が加わった人工・人為的世界(それは礼の世界)こそがすぐれたものだった。だから人々に聖人の作った礼を「教」え、道徳による「感」化をしてゆき、その華やかな「文」の恩恵を与えてゆくこと、つまり「教化・感化・文化」してゆくことが大切である、と儒教は主張したのである。逆に老荘は、儒教のもつ人工的性格、人為性を批判したからこそ、嬰児讃歌のような考え方をとることになった。 ・今日、小・中・高校において生徒が義務として掃除をするのは、おそらく儒教文化圏における学校のみではなかろうか。 四 儒教と政治意識と ・明治二年の版籍奉還、明治四年の廃藩置県は、秦王朝の郡県制に酷似している。中央集権国家をつくるために、このような疑似郡県制を布いた明治政府が、秦王朝の法治政治よろしく、法律を最大の自分の武器としていこうとしたことは言うまでもない。 ・現代日本の政治において「政治倫理」なるものが強く求められている。すなわち、政治家的力量や行政官僚的能力よりも清潔な道徳家であることを求めるわけであるが、これは伝統的な儒教的お ・こうしたお上に対して、べったりと甘えてぶらさがるのが、われわれ儒教的民衆である。たとえば、ふだんはエゴむきだしで、政府は国民のすることに対して干渉するなと言いながら、社会においていったんよろしくない事件が起ると、政府は何をしていたのか、なぜきちんと対策をとらなかったのか、と声高に責める。つまり、本質的には政府の御指導と御加護を乞い願うという姿勢が抜けきらない。 儒教文化圏においては、民衆は、官僚層の指導と管理とを否定する自信などない。 |