| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月12日 金曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
70 |
15.07 |
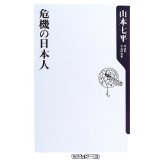 |
危機の日本人 |
山本七平 |
角川oneテーマ21 |
◎ |
【欧米人の見た日本】 ・十七世紀中ごろのオランダ人モンタス『オランダ使節日本紀行』 「日本人は、いかなる時にも己れの不幸困難を ・一六八九年刊行のフランス人イエズス会士J・クラッセ『日本 「日本人は物に堪え忍ぶ驚くべき美質あり。 日本人一般の気質として名誉を重んじ、自分が 日本人はその身分に準じ義務責任を怠らざるにより、不正の言語を発し人を 下賤貧困のもの その勇気の猛なること、忍耐力の強気琴は殆ど測るべからざるものとあり。まことに然り、彼らは災害にかかるもこれを悲しまず、平常の言語動作に於ても ただに悲しみにあいて痛苦することなきのみならず、非常な幸福に会うも歓喜の顔色をあらわすは ・一六九〇年(元禄三年)オランダ商館の医師として来日したE・ケムプエル『 「われはこの旅行に於て日本人より受けたる 「日本人は大胆または武勇と称すべき性質を有せり、ただし、ここにいわゆる武勇とは、敵の ・一七七五年(安永四年)医師としてオランダ商館に勤めたスウェーデン人K・Pツンベルグ『江戸参府紀行』 「 余はまたしばしば日本人の忍耐、親切、ことにヨーロッパ商人に対する親切を実体験したり。元来、勇猛なる民族たるに似もやらず、彼らはやさしく、温和なり。他の加うる脅迫に向っては動かざる山の如きも、友情に於ては 正義はこの地にては ・十八世紀、オランダ生まれのオランダ商館長イサーク・チチング『日本風俗図誌』 「日本人が、近代ヨーロッパの『国民』成立以前に於て、また彼ら(ヨーロッパ人)が未だ粗野不文明の束縛の下にありし時に於て、すでに文明開化したる民族たりしことを証明す。 大胆にして熟練せる水夫は勇気に於てインドの最も武を好む民族にも後れを取らぬ兵士に養成せられたるなり」 ・一八一一年(文化八年)ロシア海軍艦長、ゴローニン『ガローウニン日本 「概してこの民族は理解早く、直ちに受くる所を このように理解が早く、それを咀嚼して直ちに自分のものにする能力は何に基づくのであろう。彼はそれを教育だと見ている。 「日本人はこれをすべての国民に比するに、 ・一八五三年(嘉永六年)プチャーチンに提督秘書として同行した小説家ゴンチャロフの『日本紀行』 日本の自然が実に美しいこと、人びとは思慮があり、機敏で力強いこと、そして、「極東の諸国民中、その習慣の美なること、その社交の術を解する点において、日本の最も開化せるを悟れり」と記している。 ・一八五三年(嘉永六年)来航のペリー『日本遠征記』 日本人は個人的には怜悧・淡泊、正直で勇気があるけれども、幕府の役人となるとこれが一変して臆病で陰険で 吉田 「元来日本人は事々物々について疑念を起す人民であって、機会さえあればその ・一八五九年(安政六年)総領事として来日し、翌年全権公使となったオールコック『大君の都』 「物質文明について言わば、日本が東方各国民の第一位にするものなることは疑うべくもあらず。もし彼らにして応用科学に欠くることなく機械工業に進歩することあらば、彼らはヨーロッパ諸国民と優に競争するを得べきなり」 ・一八六〇年(万延元年)プロシアの条約締結使節に同行来日したマロン博士の『日本と中国』に記したグスターフ・シュピースの言 「婦人の地位は簡単 ・同上マロン博士の言 「日本人というものは、暴君のような父親から行儀よくおとなしく教育された児童のようだ。彼らは他人のものを盗むことがない、つまみ食いもしない、着物も汚すこともない、また一度でも だれひとりとして不平を称えるものもなく、なさねばならぬことは必ず実行しているが、それ以外の事は決して行わない。」 日本は専制君主の国といわれるが、その意味がヨーロッパと全く違うことを指摘している。たとえ将軍といえども、 彼が法律と見たものはむしろ「しきたり」とでも言うべきもののように思われる。いわば慣習のつみ重ねの中で法律のようになった「しきたり」は将軍といえども無視できない。 これは専制主義というより「しきたり主義」という方が適当であろう。 「国民にとって、あらゆる良いものの中でおそらく最上のものはパンであったろう。国民のすべてに十分なる糧食を与えるため、この国の全力は農業に注がれている」 この「しきたり主義」は奇妙な平等主義を生む。現在のわれわれは、将軍の食生活の貧しさとこの点では上下の階級差のないことに驚く。 「社会的関係におけるあらゆる日本人の、殆ど完全なるほどの平等は興味あるものであるが、われわれの習慣によっては殆ど理解できない。富と才能とはその所有主に対して決して特権ある階級を与えるものではない。百万長者といえどもその隣人と異った服装をすることは許されない。それゆえ生活上からは殆ど貧者と異なるところがない。貧しい人びとの日常食膳の上に見る魚、米、豆を、富んだ者も持っているが、それ以上のものを持ってはいない。日常品は豊富にしてかつ安価なるために、だれでも十分飽食するに足るほど持っている。階級とか特権とか人生の快楽とか、より高い知識階級でさえ決して金銭によって創造されることはない。社会的な階級を創造する条件は家柄と職業に他ならない」 ・安政二年(一八五五年)以降三度来日しているイギリス人セント・ジョン『日本沿岸航海記』 「日本人はいかに貧しくともその家は常に必ず清潔にして心地よし、余は田舎の人民によってしばしばその居宅に この種の記述、日本人は貧しくても清潔と整理・整頓を好み、ヨーロッパやロシアのような、無限に不潔で自堕落といった状態にならないといった指摘は彼以外にもある。 一方彼は日本人が必ずしも正直・率直でなく、その場に適合するように相手に口を合わせて、事実を言わない傾向のあることを鋭く見抜いている。 しかしこれは相手をだまそうという悪意から出たものではなく、この点、イギリスの下層社会より、まだよい状態であろうとしている。いわば相手の感情を損なわないように口うらを合わせたり、相づちをうったり、イエス・ノーをはっきり言わないという点にも現れている傾向である。 ・ザヴィエルが日本に来た一五四九年から、ルボンが来た一八八三年まで、約三三〇余年を通ずる欧米人の日本観の要約 まず、好奇心、探求心である。それは新しいことに興味をもち、これを理解しようと心掛けても、自らを絶対化して拒否することはしない。地動説でも進化論でも平気で受け入れ、きわめて記憶力にすぐれている。 ・・・ 実際に役に立つものには深い関心を示す。そして取り入れたものは日本化してしまう。またきわめて礼儀正しく、整然たる秩序を愛し、乱雑混乱を嫌って貧民でも清潔・整理・整頓を重んずる。ザヴィエルの時代でも盗みを嫌い、今と同じように泥棒は少ない。また詐欺を嫌う。 従って犯罪はきわめて少ない。大体において性質が温良で粗野な言葉や態度を嫌うが、実に勇敢な一面があり、また名誉を重んじ、これを生命より大切にする。親切だが喜怒哀楽の感情を表に出さず、相当な苦難に耐えて忍耐強く、自分の職務には精励し、上下の関係は礼儀によって厳格に守られている。災害にあっても別に悲しまず、すぐこれを克服しようとする。 正義を愛し温良であるとはいえ迷信・ 日本は科学技術の点でははるかにヨーロッパに劣るが、不必要な、人間を愚昧にする学者ぶりはないから、劣ったことは劣ったこととしてそれを克服する道を選ぶだろう。そうなれば、その好奇心・探求心、さらに活動的で生一本などの要因で軍事的にも経済的にもヨーロッパの恐るべき競争相手となるから、彼らを刺激しない方がよい。日本人は導入したものを必ず日本的に変えてしまって活用するから危険である。 日本人は個人的には怜悧・淡泊・正直だが、これが役人になると臆病・陰険・狡猾で、なんでも懸案を先にのばして決断をしない。また商人はその取引において決して さらに経済的にはきわめて合理性を重んじ、手形・小切手・倉荷証券等を古くから用いている。さらに社会のすべてが共同体的でそれぞれの中で合意を求めてから行われるから「強制」といった感じがなく、またそれぞれ共同体の中で相互扶助が行われている。そしてこれは労働者でも例外ではない。一般家庭では子供への身体的懲罰は行われず、根気の良い説得が行われる。婦人は、理想化もされず蔑視もされず、男性のよき相談相手、いわば女友だちだが、その活動は家庭内に限られている。 ・あらゆることに技能を競うことは、幕末から明治にかけて、しばしば欧米人を驚かした「職人芸」を生み出した。当時の欧米の機械類の多くは、職人の腕で模造できたのである。 【未来への課題】 ◎一貫して借金国だった日本 ・明治から一貫して日本の経済政策はおおむね、好感をもって迎えられた。 ・理由は、日本は外債を元利とも常に完全に期日通りに返済した唯一の国だったからである。日本は大変な資本輸入国であり借金国であったが、カントリー・リスクは皆無の国だったといってよい。この点では常に欧米の資本輸出国の優等生であった。 ・だがこれが日本にとって、どれほどの難事業であったか、理解している欧米人は殆どいないであろう。 ・安政五年(一八五八年)にアメリカが、悪名高い砲艦外交によって日本に押しつけた日米修好通商条約は、少なくともわれわれの目から見れば公正なものではない。日本は関税自主権を奪われ、一方的に、従量・従価はアメリカが都合のよい方を採用することで、最高五パーセントと定められていた。これは実質的には関税ゼロに等しい。 ・当時の日本には何の近代産業もない。そこへすでに工業化した先進国の製品が無関税でなだれ込めば、日本の伝統産業は壊滅するか、産業の近代化は不可能になる。後発の国は、保護関税で先進国に対抗して自国の産業を育成しようとする。現に、アメリカもドイツもこれをやっている。だが日本はそれを封じられた。その中で日本が近代化するのは、不可能といってよかった。過去において、こういう仕打ちをしたということは忘れないでほしい。 ・幸いに日本には絹があった。 ・一時は、日本国政府の予算の総額に匹敵したのである。日本は細い絹の糸にすがって近代化の道を切り開いたといっても過言ではない。 ◎論争をしない日本 ・ユダヤ人なら徹底して相手に論争を望むであろう。そして一つでも譲歩すれば、別の面で相手に何かを譲歩さす。だが日本人はそれをしない。またはっきり言って出来ない。相手の理不尽を相手の論理でつかむという術にたけていないからである。彼らはこれを反射的に行いうるが、それは伝統の違いであって、日本人にこのまねはできない。 ・しかし日本人は、言葉にはならなくてもカンは鋭いから、なんとなく納得できないという気持ちは抱いている。だがそれがしだいに蓄積して来ると、いつかは爆発する。日本人がよく口にする「今度という今度はがまんならない」が出てくるのである。 ◎「昭和の大失策」の遠因 ・当時は海軍国といえば英米日しかないわけであり、英米が対立して戦争状態になり、日本がキャスチングボートを握るという機会が来ない限り、日本海軍には出番がない。だが、そういった状態の現出はまず考えられない。とすれば日本は英米的秩序の中でそれを維持する役割を最低の負担で演じつつ国力を伸張させていくという方策しかなく、これが日本にとって最も有利な政策のはずである。そしてもしそれをせずに、海軍力の英米との対等を欲するなら、破産を覚悟で海軍力を三倍にする以外にない。だが破産をすれば、逆に、国際的影響力を失ってしまうからこれも意味はない。 ・それなのに日本は明確な決断もなく総合的プランもなく、英米体制を打破して、「東亜新秩序」なるものをつくるという方向に突っ走る、というより自らを追い込んで潰滅する。 ・冷静に考えれば英米に抑え込まれなくとも、これに対抗する軍事力を創設し維持しようとすれば日本は破産してしまうだけだから、意味のない行為である。 ・現在の環境を保持しつつその中で発展を策するか否かに基本があるはずである。だが、当時を振り返ってみると、このことを明確に国民に説明し、はっきりと国民の決断を求めた政治家がいなかったことに気づく。 これが、歴史的な「昭和の大失策」の遠因だ。 ・同じような現象は現在でもある。 |