| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年11月14日 火曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
64 |
15.06 |
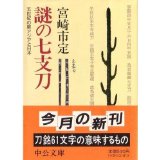 |
謎の七支刀 |
宮崎市定 |
中公文庫 |
◎ |
序章 日本古代史のなかの不思議 私の七支刀研究 ・歴史学とは、本質的に他人の眼を通して見たものを史料として検討するにある。 ・しかも他人の目を通して観察しながら、結果において渦中の当事者自身よりもよく事実の真相を把握する、それが歴史学の本領ではないか。 第三章 七支刀銘文の影響 銘文研究の態度 ・現在の段階ではまだまだ資料が不足で、どの読み方がぜったい正しいとか、間違っているとか、断定することはできない状態にある。すべては、どちらがベターかということができるに止まる。それさえ意見の違いはいかんともしがたいのである。 ・学者は野球の監督ではない。勝った、負けたという観念を学問の世界にもちこむと、それが理性を曇らせる原因になる。勝ち負けを念頭におくと、自然に党同伐異の風がおこる。派閥の合意が研究の出発点となれば、それは学問の自由を自ら放棄することを意味する。 補修という名の破壊 ・遺跡の発掘は破壊である。 ・そんな破壊に手を貸した以上は、それを償うだけの学問への貢献が責任となる。調査、研究、発表とともに、遺物を長く世に残して、後世の学者の研究の資料とせねばならぬ。 ・考古学という学問は、最初から矛盾を内蔵した学問なのである。破壊しなければ研究ができず、研究のためには破壊しなければならぬ。そこで破壊を最小限に止め、一方、研究成果を最大にすることが、せめてもの償いということになってくる。 第五章 五世紀東亜の形勢 漢代の倭人 ・古代においては、中国内部に大きな政変がおこるたびに、それが四方に波動を及ぼして、重大な影響をひきおこすのをつねとした。 このような現象はすでに古く、春秋戦国のころから見られたところであるが、とくに決定的であったのは、前漢五代の君主武帝の領土拡張政策である。 ・当時の日本人、いわゆる倭人は百余の小国に分れて地方に割拠していたという。その百余国のうち三十国ばかりが、これ以後、楽浪郡へ貿易に赴くようになった。 ・倭人百余国の中の奴国が、使を遣わして東漢の都洛陽に至って朝貢したのは、光武帝即位の三十三年目であり、帝から印綬を貰って帰ってきた。 ・後漢の中期、安帝の永初二年(一〇八年)に、倭国王師升という者が、使を出し、生口(奴隷)百六十人を献じて、天子に朝見を願ったことが『後漢書』に記されている。 その理由は、倭国王師升による、国内制覇が実現したためであるらしい。 ・従来のように三十余国が銘々勝手に楽浪郡へ出かけて朝貢し、貿易の利益をえて帰るのを止めさせ、倭国王の統制のもとに、秩序ある朝貢貿易を開始させた。この新体制を後漢の朝廷に認めさせる必要があって、さてこそこの年の朝貢が実現したものであろう。 三国魏と倭女王 ・滅亡に瀕した後漢王朝の大臣として、華北黄河流域一帯を斬り従えた曹操は、子の曹丕の代になって、漢の ・公孫氏の滅びたその年に、倭の女王卑弥呼の使者、難升米、および副使都市牛利らが帯方郡に渡って、魏の朝廷に赴いて貢献したいと申し出た。 ・魏の朝廷は久しぶりで帯方郡を恢復した効果が、このように早く現れたことに満足し、その年末に詔書を下し、女王を親魏倭王に封じ、金印紫綬を帯方郡をつうじて送り届けさせた。中国政府はひじょうに現金で、自分が招いたときには、せいいっぱい優遇する建前である。 東晋と百済 ・咸安二年(三七二年)正月七日辛丑の日に、初めて百済王の使者が、南方林邑国の使者と共に入庁して朝貢した。 ・入庁した百済の使者は、破格の優遇をうけた。六月使者の帰国にさいし、東晋の使者が同行し、百済王余句を拝して鎮東将軍に任じ、楽浪太守を領せしめた。 倭国の朝貢 ・義熙九年(四一三年)には、高句麗と倭国とが入貢して万物を献上している。ことに倭国の江南への朝貢はこれが初めてである。 ・秦始皇帝が治世の二十八年(前二一九年)に、斉人徐市(徐福)に命じ、童男女数千人をひきいて東海に入り、三神山に至って、そこの仙人について不死の薬を求めしたことは、『史記』「始皇本紀」に見えているから、伝説ではなく史実であった。しかしそれが不成功に終ったことも事実である。 宋と倭の五王 ・宋の文帝の在位中、倭王讃が死して、弟珍が立った。讃は仁徳天皇、弟珍とは反正天皇に擬せられているが、これには異論もある。 ・宋朝廷の百済重視政策と、これに対して日本が、自国の実力伸張を理由として、あらたなる現実の認識によって、宋朝廷に日本重視への切りかえを迫った ・倭国からは、宋代にはいって初めて武帝劉裕の永初二年(四二一年)に朝貢使を派遣した。 倭と三韓 ・当時の倭国は海上において、すでに対馬海峡を制圧していたので、半島南端の任那・泰韓・慕韓および新羅は、もし南朝に入貢したくても、倭国の同意、ないしは許可をえなければ、海上に船をだすことができない。おそらく当時これらの諸国は、倭国船に付随して、江南王朝に朝貢貿易を行なう恩恵にあずかっていたものであろう。 ・『三国史記』によると、当時の百済は連年北隣の高句麗と戦ったが、なんといっても高句麗は大国なので、しきりに敗北を重ねていた。そこで海をへだてた日本、当時の倭国に援助をもとめ、ときには太子を人質としてさしだしたりして、結好をもとめたりしていた。 倭王武の上表 ・百済の没落は、それに反比例して、日本勢力の上昇を結果した。その三年後、宋の後廃帝の後を嗣いだ順帝の昇明二年(四七八年)、雄略天皇と思われる倭王武が、自ら倭国王と称して、使を遣わして上表した。 ・その中に先祖以来の功業を述べて、 「東は毛人を征すること五十五国、西は衆夷を服すること六十六国、渡りて海北を平ぐること九十五国」 という有名な文句がある。 ・彼はこうして自国の武威を誇り、ついては高句麗が無道で、百済や倭国の入貢の航路を妨害しているので、これを征伐して暴虐を懲らす許可をえたいと請い、さらにそのために、かりに開府儀同三司の位を名乗っているので、これを承認してもらいたいと吹きかけた。 ―― 完 ―― |