| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月12日 金曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
65 |
15.06 |
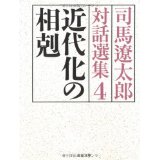 |
近代化の相剋 |
司馬遼太郎 対話選集 4 |
文春文庫 |
◎ |
日本人よ"侍"に還れ ・日本人はとことんまで対決しない。いい悪いは別にして、ともかく対決しないというか、ある点まで対決して、そのあとはサッと手をうつことによって、問題を解決していく。 ・他方、ヨーロッパの流儀はそうじゃない、とことんまでやる。しかし同時に忘れてならないのは、これは思想史の教科書によく書かれていることですが、思想の自由、異なった思想に対する寛容という態度が登場しはじめるのは、この三十年戦争のあたり、あるいはその渦中から、ということですね。 ・自分の宗教とか宗派に属さないものに対する追及、迫害、拷問などのすさまじさ、むごたらしさは、日本では考えられないほどものすごいもので、そういう時に使った道具などが、いまでもヨーロッパの博物館などに残っています。 ・つまり、ヨーロッパでは、精神や思想の問題で対決し、その勝ち負けの決着はつくものではないと、知識としてでなく文字通り、骨身にしみて知ったわけで、そこではじめて、異なった立場もありうるという認識、つまり寛容という結論に達したわけです。 ・その後も、フランス革命やロシア革命の例が示すように、とことんまで対決するという伝統は残りますが、それにもかかわらず、いや、逆にそれだからこそ、といえると思いますが、他の思想に対する本当の寛容な態度が、同時に養われていった、といえる。 ・ところが、日本の場合は、まずとことんまでやらない。やらないことが、逆に本当の寛容を生み出さない、そういう面がある。 ・一つの原理からででいる発想を改めさせることは、他の原理をもちこむ革命によらなければできないことですし、むろんそういう原理転換の革命は、容易にできるものではありません。 ・エジプトでピラミッドやスフィンクスあたりをラクダに観光客をのせてまわる案内人、彼らは強欲で旅行者から金をふんだくることしか考えていない、だから泥棒と同じだなどといいますが、それも彼らの原理から出ていることなんですね。旅行者は富める者だから ・日本人は、ある種の民族や国家について、枝葉のことでののしりますね。自分に原理がないものだから、原理にまで理解がとどかなくて、枝葉のことで生ずるつまらないアクシデントに猛烈に怒ったり、逆に猛烈に感心したりして。 ・朝鮮人には、一族というものについて特別な原理がある。だから場合によっては、親類を食いつぶしたっていいんです。食いつぶすというと、卑しい言葉ですが、向こうでは食いつぶすことが、極端にいえば原理に忠実なわけですね。こういう事例は無数にあります。 しかし、そういう国々の原理を無視して枝葉をとりあげて「朝鮮人はけしからん」と、民族の問題にしてしまいがちなんですよ、日本人というのは。 ・中国人は、日本には原理がないとみておりますから、日本をセッパ詰まらせるような所へ追いこんだら、破れかぶれのようにして、力をもってくると思っているはずです。 ・今の中国人は、日本人をこわがってはいませんよ。論理が一応通っていますからね。しかし、その論理が消えて行動が始まるということを、やはり警戒しているんじゃないでしょうか。 ・原理がある相手と交渉する場合は、ある程度の安心感がある。予測の可能性がありますからね。ところが特に日本のように原理のない国は、瀬戸際まで追いつめてはいけない。これは外交の一般原則でもありますけれど必ず逃げ道を残しておいてやらねばならない。もし日本をあまり追いつめたら……もう武力です。 ・いまの日本の商人たちを笑顔で迎えているのは、中国人の心の裏に、一抹の不安があるということで、彼らの洞察とそこから出てくる演技を、日本人は汲みとらなければいけない。 明治国家と平成の日本 ・立憲国家というものは、対立があって初めて動く。ところが日本では、必ずしもヨーロッパの王権対人民のような対立がなかった。だから、日本の人民というのは自分で世論をつくり上げ、自分が政治を動かしているという緊張感がない。 ・金権と、それから何か強硬論が出てくると、そっちのほうが格好いいからそっちに引きずられるという二点は、現代の日本でも心しなくちゃいけない。しかも、今の日本人は、いっさい言いわけできないんですからね。 ・主権者ですからね。 ・非常に重たい立場だと思いますね。そうであるだけに、非常に限定された制度の枠の中で、明治の先輩たちが一生懸命やっていたことを、やはり何度でも ・世界で天地鳴動の事件が起こっていても、国会で議論しませんよね。 とにかく、報道されるのは政局だけ。「政局」なんていうのは外国語には訳すことができない言葉ですよ。要するに限られた土俵の中で談合しているという状況です。政局があって政治がない。 ・鎌倉武士のプリンシプルは「名こそ惜しけれ」。十分にヨーロッパ的倫理と対抗できるものでしたが、いま、名こそ惜しけれという政治家がいるでしょうか。 ・現実にそうだったかはともかく、そういう規範が意識されているということ自体が大事なんですね。明治の人々が国民、国家をつくっていく。それに挑戦していったことは依然として私どもの課題なわけですね。その場合、明治の人と一つ違うのは、世界規模の公的なものへの寄与をしなくちゃいけないということです。 ・大事なことが起きているときに、国境の向こうだからといって傍観していいのか、人間の尊厳と生命がめちゃめちゃにされようとしているときに、それこそ「政局」だけでいいのかというのは、私たちにとっても大きな課題です。 ・とにかく日本は、世界の一員じゃないという意識でした。こんなに巨大になっても、まだあります。日本人は謙虚に自分自身を考えるべきです。 ・ともかく、何か問題が起こったら走っていって抱き起したり、お金が足りなかったらどうかこれを使ってくれといったりしなきゃ。ここまで経済がでっかくなったんですから。 日本がたとえ滅んだ後も、いい感じの国だったということを、あるいはいい感じの国民だったということを思われないと、何のために人間として生まれてきたのかと思いますよ。 |