| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月09日 火曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
72 |
15.07 |
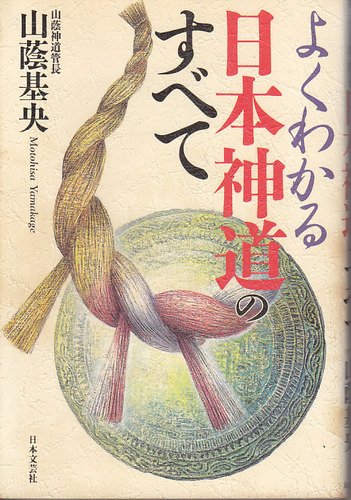 |
よくわかる日本神道のすべて |
山蔭基央 |
日本文芸社 |
◎ |
・日本での植林計画が文献に見えるのは三世紀からである。以来この方、日本は国土の危機管理を治山治水においてきた。その“気の長い”未来への贈り物が植林と育樹である。 ・とにかく「日本神道」には何もない。 「教祖がない、教義がない、戒律がない、 というのが神道である。 ・『魏志倭人伝』には、古代日本人の生活態度が立派だと讃美し、“東海の君子国”だと紹介している。これは、教祖がいなくても人倫の道が立つことを証明している。 ・しかし、当時の大文明国(中国)の文化思想に抗することはできず、社殿を それが奈良時代以降の神道である。 ・太古の日本では刑罰を行なっても、それを ・儒教や仏教の洗礼を受けた人々は“見直し、聞き直し、言い直して、水に流す”ということができなくなっていたのである。 これはまさに、全日本人の悲劇である。 ・神社は斎場であって“神霊の住居”ではない。 【水こそ神の ・近代科学の結論によると、生物は海の中から発生したとされているが、古代日本語の「ウミ」は、漢字を借りると「生み、 ・日本語の海についての認識が明らかになれば、 ・大自然の神霊が姿を現わすときは「水」が最初であるとして、水源を ・すべてのものがことごとく差別ある姿をしていることを正当なことだと観ることを“妙観察智”というが、まことにそれは、古神道において八百万神として崇める思想と同じである。 ・神は最初に「水」として顕われ、後に、万物の姿をとったのである。“万物は神の化身”なのである。その化身の筆頭がと出るという神話は正しい。 ・由緒ある古大社では、正月の元旦祭では「井戸の水神祭」がすべての祭祀に先行する。つまり、水神は、その神社の「 【氏神と鎮守と産土の違い】 ・中国宋代になると周代の郷が「鎮(小都市))」となった。元来そうした地域守護の神が「鎮守社」であったのが、日本では、城・寺院・小村落の守護神として祀られ、それを鎮守と呼ぶようになった。 ・もともと産土神とは、その土地に鎮まっている元来の神であって、ある場合は“水神”であり、ある場合は“火神”であった。そうした土地の宗主(地主)を産土といい、別名を「 ・氏神とは、その土地に入植した一族の大元祖(氏の祖先)のことをいう。藤原氏は春日大社を氏神とし、源氏は八幡宮を氏神とした。だから、それぞれの家系の大元祖が氏神である。だから郷邑の鎮守に祀って氏神とした場合もある。 ・その昔、神社には建造物(ヤシロ)はなかった。だから、祭礼の度に“神迎への儀”を行なってお祭りし、それが終わると“神送りの儀”を行なった。ある場合、臨時祭場の建物を造る神社もあったが、それは祭儀が終われば だから巨岩のことを「 ・古代の人々は、この神聖な岩を扉として、神々は ・「鳥居から中は正中を通ってはならない。右か左かどちらかを通ること」と、よくいわれるのは、真ん中は“神の道”となっているからだ。 拝殿に到着しても、やはりどちらかに寄って礼拝すべきものである。神主が中央で拝むのは“神の憑代”であるから。 ・神社は斎場であって、“神霊の住居”ではない。 【なぜ土俵で塩を撒くのか】 ・もともと相撲とは、神事に伴う“占”であったのだから、その“占の 【なぜ神様へのお供物に塩が必要なのか】 ・日本人の心には、“塩は海神(祓戸大神)の化身”として、一切を浄めてくださる 【「水に流す」とは何を流すのか】 ・ ・古来、日本には「水はすべてを浄めてくれる」という信仰がある。まさに“ ・「 【水商売の“水”の意味】 ・古代日本語では、蛇のことを「ミズチ」という。又、霊のことを「ヒ」、「ミ」、「チ」、「タマ」、「モノ」というが、その中の「チ」がついた「ミズチ」とは「水の霊」ということになる。 そこに蛇信仰が生まれる理由がある。 水商売の人は「ミーさん」と称して蛇を祀る。その心は“ミイリ=収入”がよくなるという意味につながっている。だから、水商売の水は、“ 【死水とはどういう水なのか】 ・「死に水」とは「末期の水」のことである。 末期とは、死の寸前のことで、この最後のとき唇をしめらせてあげる水のことを「死水」という。 そのことを「死水を取る」というが、転じて、「死の最後まで世話をする」意になっている。 【祝いに使う「水引」の意味】 ・「麻などを水に浸しておいて皮をはぐ」ことを水引というとあり、進物用の品を飾るためにしばる紙紐を「水引」というが、案外それは、その贈り物を浄めるための ・西洋にも贈り物にリボンを飾るという風習があるが、その感覚は「水引」とは異なる。 なぜなら、「水引」は、包装紙の上にさらに白紙をかけて、それに紅白や金銀の水引をかけるのだから、やはりそれは“浄める”の意がある。 【相撲の「水入り」とは】 ・相撲は神事の一つで「 疲れた者は“気が枯れて”いる、そうした衰えを“汚れ”と見た。そうした“気枯れ”を復活させるために“水入り”という休憩を与え、気力を整えさせてから、再び「塩祓」の上で相撲の取り直しをさせたのである。 つまり、“水入り”の原意は「汚れを浄める」ためであった。 【祝儀事は神社、不幸はお寺 この分担の意味は?】 ・おそらく仏教が人間救済の教えであると宣布した一方で“地獄の恐怖”を流布したので、それを解除する“呪術”を考案しなければならなくなったからではないか。 ・そうしたとき、唐の善導が唱えた「浄土教」なるものが渡来し、「いかなる罪人でも阿弥陀如来の御名を唱える者には極楽往生を保証する」との呪術を法然が紹介し、親鸞がそれを継承して、仏教地獄の救世主になった。 ・仏教は全国に広まり、鎌倉時代には庶民の世界にまで普及していたから、法然・親鸞の救いが必要になったわけで、それにより死者の「安心立命」は、念仏往生として確立し、「葬儀は仏教へ」となった。 ・さらに江戸時代における「キリシタン禁制」のために設けた檀家制度を活用して、仏教僧にキリシタンを監視させ、“葬儀、追善供養”はことごとく仏教に一任されることになった。 【なぜ天照大御神に絵や像がないのか】 ・それは、天照大御神は ・日本の神道には神々の偶像は作られておらず、あるのは「神楽仮面」だけである。 ・神々を造形しなかった英知は、偉大であったというしかない。 なぜならば、神霊のお姿を人間の考える低次元の容相に固定することは、自由にして偉大なる神霊を限定した枠に閉じ込めることになるからだ。 【 ・祝詞は、一般的には神様に奏上する詞であるが、経文とは、教祖から信者に対する教諭の言葉である。 【元気を出せの“元気”とは何?】 ・これは中国語で、道教の用語である。 ・辞書には、「万物の根本精気、天地生成の気、人の精気」などとあり、ひいては活動力の源泉となるわけで、人が生まれながらに持つ生命力のことである。 ・その元気の吸引は、なんとしても呼吸法にある。 ・元気は呼吸法によって吸引され、人びとの体内にある元気(風空の気)と合体して偉大な活力を増幅する。 ・だから呼吸すること自体が元気を出すことになるわけで、簡単な方法は“吐く”ことから始まる。 ・空気は吸えば入るというものではなく、まず吐かねばならない。要するに出せば入るのである。とにかく出すしかないのである。腹の底からしぼり出すように吐き出すことである。そうすれば、その反動で空気は吸引され、感情的に停滞している気は吐き出されて、新しい気が入ってくる。 ・また「笑え! 笑えば新しい気が入ってくる」と言う。まったく、その通りである。 また、高笑いする声には、 【天地神明に誓うのと聖書に誓うことの違い】 ・「神明」という語は、天照大神のことをいう。 ・「天地神明」という日本の神々は、宇宙普遍の神を中心とするあまたの神々のことなのだが、日本人にとっては正義の根源になる神々のことでもある。 ・これらの神々は人類普遍の創造主を中心にする組織的な神である。したがって、キリストをも含み、儒教の天はもとより、道教の天皇大帝をも包含する神である。もちろん、仏教で説く諸仏も包括する神である。 ・しかし日本神道の神々には、微に入り細にわたった「教誡・戒律」がない。だから真理とされ、正義とされる言語を持っていない。 そのために、いままでは幼稚で未開で原始的な宗教だと軽蔑されてきた。 ・しかし だから教義の神に誓うことは普遍性がない。 ・一人の神を信じることは、他の神に反する誓いを立てたことになるわけである。キリスト教とイスラム教の神では永遠の対決となる。 ・だから「天地神明」という“無教義の神”にこそ“普遍の誓い”があるといえる。 |