| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月09日 火曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
78 |
15.08 |
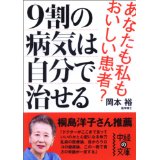 |
9割の病気は自分で治せる |
岡本 裕 |
中経の文庫 |
☆ |
・私の周りでは、高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満症、痛風、便秘症、頭痛、腰痛症、不眠症、自律神経失調症などは総称して「喜劇の病気」と呼ばれています。 理由は簡単です。なぜなら、それらの疾患は悲劇のヒロインの病気にはなりえないからなのです。 ・「喜劇の病気」は原則として自らの力で治すことができますし、仮に医者の力が必要な場合でも、ほんのわずかなアドバイスで事足ります。 ・日本には「おいしい患者」が実に多くいます。 「おいしい患者」とは、言うまでもなく、医者にとって非常にありがたい患者さんだという意味です。 文句も言わずに定期的にずっと通院してくれること。 その上、黙って薬をのみ続け、検査を受け続けてくれます。そうなれば、儲けも確実に見込めて、とてもありがたいはずです。 さらに、これが非常に重要なポイントになるのですが、命にかかわることもなく、さりとて完全に治らないことが、重宝するのです。 ・命にかかわらない患者さんを診る場合は、やりがいという点でははなはだ疑問がありますが、なんと言っても気楽に対応できますので、非常にありがたいのです。しかも完全には治らないというのもおいしい点です。いくら気楽な病気でも、すぐに治ってしまってはリピーター(顧客)になることがありませんので、まったくおいしくありません。 ・みなさんが自ら強くなって意味のない通院をやめることは、長期的にみれば、薬と検査漬けのマニュアル化された医療の現状を是正することにもなります。 ・日本の医者一人が、年間に診察する患者数はおよそ8500人、それに対してOECD平均は2421人です。 ・外来患者一人当たりの診察料の平均が、日本が7000円なのに対して、米国は6万2000円、スウェーデンはなんと8万9000円で、日本は極端に低いのです。 ・日本の医者は、日本の医療システムが薄利多売構造になっているために、多数の患者さんを診なければやっていけないのです。 ・日本の医者も欧米の医者も報酬はほぼ同じですから、結局は日本の医者は非常に忙しい思いをしているということになります。 ・50~60人くらいは診ないと経営が成り立たないのも、日本の医療現場の厳しい一面です。 ・私がいなくても治る人は治っていた ・私がいても治らない人は治らなかった ・病気の状態(病態、疾患)をおおまかに分類してみると、次の3つのカテゴリーに分けることができます。 カテゴリー1 医者がかかわってもかかわらなくても治癒する病気 カテゴリー2 医者がかかわることによってはじめて治癒にいたる病気 言い換えると、医者がいないと治癒に至らない病気 カテゴリー3 医者がかかわってもかかわらなくても治癒に至らない病気 ・開業医や市中病院の医者が日常診療で遭遇する疾病のほとんどは、カテゴリー1にあたります。その比率は、少なくとも70%以上、多ければ90%以上だと思います。 ・医者にかからなくてもい人をかからなくていいと断定することも大切な仕事ですが、そのことは今はあまり重要視されていません。 ・今の社会風潮は、高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満などは「しっかりと治療を受けなくてはいけませんよ」という空気です。これは、医療機関の経営者にとっては、とてもありがたい追い風です。その風は自然にふいたのではなく、政府が吹かし、メディアがあおっているような気がします。 ・定期的な検査も、患者さんをつなぎとめる非常に有効な手段です。簡単な血液検査も項目を適当に増やせば、大抵はなんらかの異常値が見つかるものです。脅す材料にはこと欠きません。 ・政府の論理は、病人が増えれば医療費支出が増加し国の財政を圧迫することから、予防措置として、合併症を併発する糖尿病や高血圧の基準値を下げることで警告を鳴らしているのだと思います。しかし、医療の世界が経営の安定化を重視するあまり、その警告を逆に利用して、安易な方向に走っているのではないか。 ・米国では昨今、あまりにも医療訴訟が多すぎて、医師への希望者そのものが減る傾向にあるようです。 命がけで命を救うことは、まさに命がけなのです。 ・命にかかわる疾患と向き合う医者が、もう少し快適に、第一線に長くいられるような、そんな環境を整えなければいけないはずです。 ・がんをはじめとする慢性疾患、免疫疾患は西洋医学の考えだけではなかなか治りません。西洋医学、東洋医学、補完代替療法の枠にこだわらずに、それぞれのいい部分を取り入れ、病気の根本原因を解消し、もともと備わっている自己治癒力を増進させることによって治癒を目指すのが、最も理にかなう。 【高血圧】 ・日本人の5人に1人が高血圧症患者というのは、いくらなんでも、高血圧の定義そのものがおかしいと考える方が自然でしょう。 ・薬で血圧を下げるというのは根本的な治療ではなく、あくまでも対症療法なので、薬の服用は限られた期間に限定すること。そしてその限られた期間に生活習慣を是正して、体重を減らしたり、ストレス負荷を和らげる工夫をしたりという努力を優先して行うこと。 ・血圧が低くても脳出血は起きます。また、血圧が高くても脳出血が起こらないこともあります。 ・血圧の上の値(収縮期血圧)が常時200mmHgを超えるほどの極端な場合は別として、血圧の値と脳出血が直接相関しているという印象はありません。 ・むしろ、血圧の値の急激な変動、生活習慣の乱れ、栄養の偏り、肥満、考え方、過度なストレス負荷などの方が、脳出血とより密接に相関しているのではないか。 ・降圧剤をのみはじめて、かえって調子が悪くなる方は少なくありません。特に高齢者の場合、上の血圧(収縮期血圧)を150~160mmHg以下に急激に下げてしまうと、何かしら不定愁訴(元気がなくなった、もの覚えが悪くなった、頭がぼうっとする、集中力がなくなる、寝起きがすっきりしない、手足が冷たくなった……)を訴える人が多くなります。 ・老人ホームなどでは、降圧剤を服用している人の方が、服用をやめた人に比べて、認知症の進行が早いという報告もあります。 ・「NIPPON研究」によりますと自立度が著名に低下するとされています。 ・血圧が高くなるのは、それなりにちゃんとした理由があるからです。つまり、身体の適応であることを理解しなくてはなりません。血圧を高く保つことによって、生体の機能をうまく維持しているわけです。だから、何の脈絡もなく薬で血圧を無理やり下げてしまっては、体にいいわけはありません。 ・上の血圧値が180mmHgくらいまでは、脳卒中になる可能性が高くなるという明確な根拠もありません。 ・「ヨーロッパ高齢者高血圧研究会」が行った調査によると、高齢者にとっては、むしろ血圧が高ければ高いほど、総死亡率が低くなるという結果も出ています。 ・血圧が高いことと白血球数が多いことは、元気なご老人の共通点なのでした。 ・自律神経の1つである交感神経は、運動をしたり精神的に緊張したりしてドキドキしたときに活動する神経で、心拍数や血圧を上げるなど、全身の活動力(エネルギー)を高める方向に働きます。 ・体重が増えたりストレス負荷が強くなったりすると血圧が上がりますが、これは身体のエネルギー需要を確保するために必要なのです。より血圧を高めることが、心身に有利なために高くなっているのです。 ・“根本的な解決”とは、血圧が高くなった原因そのものを是正することです。血圧の値だけを無理やり薬で下げてみても、なんら解決にはならないということなのです。多くの方は“根本的な解決”をなおざりにするせいで、かえって薬をのみ続けなくてはいけない破目に陥るのです。それこそ本末転倒です。立ち直りを不可能にするために降圧剤をのんでいるようなものだと思います。 ・生活習慣をそれなりに是正し、ストレス負荷を軽減する工夫をして、それでも家で測った血圧値が、上が200mmHGを超え、下が100mmHGを超えるほどでなければ、さほど心配することはない。 【糖尿病】 ・空腹時血糖値が140mg/㎗くらいであれば、すぐに合併症が起きるほどの血糖値ではありませんので、あわてて服用する理由もないはずです。まずは生活習慣の改善を優先すべきです。 ・血糖降下剤の服用が問題なのは、対症療法にすぎないからなのです。 ・血糖降下剤を服用することによって、見かけ上は、血糖値やHbA1c(ヘモグロビンA1C)の値は改善されます。 しかし、それは治ったということではありません。逆に、生体の自律(自己治癒力)を損なう危険性を多分にはらんでいます。血糖降下剤のために生体の調整機能、すなわち自己治癒力はいよいよ衰退していきます。 ・ついには、自律機能がまったく機能しなくなり、インスリンを補うよりほか、手立てがなくなってしまいます。そうなればまさしく、一生薬漬けになってしまうでしょう。 ・さらに本人も、薬さえ服用すればこと足りると変に安心して、いよいよ薬に依存するようになります。そうすればますます生活習慣を改める努力もおろそかになり、自律能はいよいよ低下するばかりです。 ・日本糖尿病学会は1999年に、糖尿病の基準値を140mg/㎗から126mg/㎗にいきなり改定しました。そのおかげで、新たに数百万人もの方が、はれて血糖降下剤を服用する資格を得ることになりました。 ・ある老人ホームでは、入所して2カ月もたつと、糖尿病と診断されたお年寄りのほとんどが治ってしまうことでも有名です。ホームの“食”へのこだわりが功を奏しているのか、玄米菜食と日本の伝統食を給食の基本にしていることがキーポイントではないか。 【コレステロール】 ・日本動脈硬化学会は、治療が必要なコレステロールの値を220mg/㎗以上としています。 ・実は、コレステロールが220~280mg/㎗の範囲の人が一番長生きしています。 ・「NIPPON研究」でも、コレステロールの値が低いほど、がん死亡率が高くなり、自立度が低下するという結果が出ているのです。 ・コレステロールが高くなればなるほど、心筋梗塞だけは、ごくわずかですが発症しやすくなるのは確かです。しかし、すべてにおける死亡率や、あるいはがんの死亡率は、圧倒的にコレステロールが低いほど、高くなるのも事実なのです。 ・したがって、常識的に考えてみてどちらが得かという話になれば、スタチン剤はやめるべきでしょう。 ・コレステロールは細胞の膜の材料になったり、ホルモンの材料になったりと、非常に大切なものです。悪者呼ばわりなど、お門違いもいいところだと思います。 ・スタチン剤をのめば、もちろん大切なコレステロールが不足してしまいます。また、コレステロールが作られるときに一緒にできるはずのコエンザイムQ10もできにくくなります。 ・コエンザイムQ10は、生体活動のエネルギー源を作るために必要な物質で、非常に重要な働きを担っています。 ・コレステロールが不足しますと、細胞そのものが弱体化しますので、当然、生体の自己治癒力(防衛力)は著名に低下します。つまりスタチン剤によって、生体の維持が危うくなるということなのです。 ・したがって、あえて悪玉と言うのであれば、コレステロールよりもむしろスタチン剤を悪玉と言うのが、正しい言葉の使い方になるかと思います。 ・スタチン剤をのむということは、小さく得して、大きな損をする典型とも言えます。 ・スタチン剤には、重篤な副作用として、がんや横紋筋融解症の誘発が挙げられる。 ・コレステロール低下剤をのむ人は、今や1000万人近くに上るといわれています。 【肥満】 ・○○ダイエットのように、同じものばかりを食べると、当然のことながら栄養が偏ってしまい、自己治癒力が低下します。 ・また栄養が偏ってしまうことで、体重は減少します。何も画期的な方法ではありません。極めて当たり前の話です。 ・さて、炭水化物を極端に減らすとどなるのでしょうか。 炭水化物はもちろんエネルギーの源ですので、当然の結果としてエネルギー不足に陥ります。そのため、炭水化物のかわりにタンパク質にエネルギー源としての動員がかかります。つまり炭水化物(糖類)がエネルギー源として利用できないので、たんぱく質(アミノ酸)からわざわざ糖(炭水化物)を作ってエネルギー源を確保しようとするのです。 ・もちろん生体は、タンパク質をほとんど筋肉として備蓄しているわけですから、タンパク質がエネルギー源として必要となれば、筋肉が解けていき、もちろん自己治癒力も著名に低下していきます。 ・いずれの手法も体調を損ね、その結果として体重が減っているのです。言い換えれば、命がけのダイエットなのです。早い話が、病気になって痩せてくるという当たり前の原理なのです。 ・健康を維持しながら減量(ダイエット)する方法は、結局は栄養素を減らさないで、カロリーを減らすしか方法はありません。つまり食べる量と運動のバランスを調整するしか方法はないのです。 ・太りやすいという体質は、生物学的にはより進化しているということなのです。いつも飢餓にさらされていた人類にとっては、太りやすいということは究極の進化体、つまり超好燃費体なのです。 ・少し太り気味の方が本当は長生きなのです。 ・体重を減らすのに必要なアイテムは体重計です。ただそれに尽きると思います。 ・体重計に乗るくせをつけることです。あとはその値とにらめっこしながら、向こう1日や2日、間食を減らすか、アルコールの量を減らすか、あるいは脂っこい物、甘い物を減らすか、はたまた、エレベーターやエスカレーターに乗らないか、自問してみることに尽きます。 ・5キロを超えると少し努力が要りますが、1~2キロであれば、ほんのちょっとした心がけだけで、誰でも容易に減量できます。 少し面倒なことを1カ月もやれば、ほぼ間違いなく、少なくとも2~3キロは減量できるはずです。2~3カ月続けることができれば、数キロはダイエットできます。そのコツを掴めば、自信もつくかと思います。 ・よくある質問が、食べる量は減らさないで、運動するだけで減量するという手法があるのでは? というものです。 確かに理論的には可能です。しかしそれは現実的ではありません。なぜなら、運動だけで減量できるほど立派な自制心の持ち主であれば、きっとはじめから肥満にはなりません。 ・果物はダイエットの敵とされる向きもあるようですが、むしろダイエットに適した食物といえるかと思います。 【メタボリックシンドローム】 ・メタボリックシンドロームは、カテゴリー1の「医者がかかわってもかかわらなくても治癒する病気」の代表選手です。 ・メタボリックシンドロームを一言で言うと、ただの食べ過ぎ、運動不足で、それ以上でもそれ以下でもありません。 ・本来はそれほど大騒ぎするものではないことを、社会゛教える必要があるのですが、政府もメディアも、こぞってメタボをあおるばかりです。その風潮に乗じて、儲けてやろうという ・1つだけ、メタボブームをよしとする点を挙げるとすれば、健康への意識が低い人たちに、生活習慣の見直しを喚起したことだと思います。 ・このメタボブームで、国民が未病に関心を持つきっかけになれば、それは好ましいことでしょう。未病は自分で治す! という社会的なムーブメントを巻き起こすことができれば、メタボブームも、うまく軟着陸できるかもしれません。 【便秘】 ・便秘の人は野菜や果物、発酵食品の摂取量が極めて少ない。 ・便秘によって腸内環境が非常に劣悪になっていて、ひいては免疫力(自己治癒力)を低下させることにもつながり、場合によってはさまざまな病気の元になったり、そしてなによりも肌の老化が早まったりします。 ・また、安易に薬剤に頼りすぎると、次第に薬も効きにくくなってしまいます。 ・腸は脳からの指令ではなく、原則として、自分で考えて機能しています。 ・腸にある神経細胞(ニューロン)の数は1億以上で、この数は脊髄全体に存在する神経細胞の数より勝っています。つまり腸は立派な神経器官とて言ってもいいくらいなのです。 ・腸が自立して機能しているということは実にすごいことなのです。なぜなら、外界から入ってくる(侵入してくる)すべての物質を体内に取り入れるべきか、排除すべきか瞬時に判断して機能しているわけなのですから。 ・全身のリンパ球の約60%は腸で働いています。そして抗体の60%は腸で作られています。つまり、腸は私たちの免疫を ・実は花粉症、気管支ぜん息、アトピーなどのアレルギー疾患のなりやすさは、腸の環境に大きく左右されることが明らかになっています。 ・がんをはじめとする慢性疾患のほとんども、おそらくは腸の環境のいかんが、その発病率や治癒率に大きく影響するものと思われます。 ・腸では数多くの神経細胞や、免疫細胞が機能しています。その上、腸管内には100種類以上もの微生物が ・したがって安易に抗生物質などで腸管をきれいにしてはいけないのです。抗生物質によってはほとんどの腸内細菌は死滅してしまいますので、心身へ及ぼす悪影響は少なくないはずです。 ・脂肪の摂りすぎ、動物性たんぱく質の摂りすぎ、野菜・果物の摂取不足、薬ののみすぎ、発酵食品の摂取低下が、腸の機能を低下させている主な要因となっています。 ・それは、アレルギー、がんをはじめとして、多くの慢性疾患が増えている現状ともみごとに符合します。 ・このスゴい腸の機能を適正に保つためにはもちろん食習慣を是正することが最優先なのですが、安易に薬剤に頼るよりは、プロバイオティクス(※1)やプレバイオティクス(※2)をうまく活用することも、非常に賢明な考えだと思います。 (※1)プロバイオティクス 消化管内の最近叢を改善し、宿主に有益な作用をもたらしうる有用な微生物など(ex. 乳酸菌など)。 (※2)プレバイオティクス 有用な微生物の増殖促進物質など(ex. オリゴ糖、繊維質など)。 ・微生物は昔からよくBRM(生体応答調整物質)(※3)の宝庫だと言われています。しかも微生物や発酵の分野は、日本がもっとも得意とする研究分野の1つでもあり、今までに私たちの先輩が築き上げてきてくれた膨大な英知が蓄積されています。このすばらしい英知を利用しない手はありません。 (※3)BRM ⇒ 最適な健康状態を推進する有機化合物のこと。 【腰痛】 ・一般的には腰痛は腰の筋力の低下や、交感神経の過緊張で起こる。したがって、血流を止めてしまうように働く湿布薬や消炎鎮痛剤、そしてコルセットは、一時的には症状を軽快させるかもしれないけれども、根本的な治療にはならない。 ・腰の血流を改善させること、腰の筋力を高めること。 ・具体的には、まずは前かがみの姿勢を意識して是正すること、同じ姿勢を長時間続けないこと、ストレッチ運動をすること、ときどき腰を反ること、できれば腹筋を鍛えること。 ・薬を処方するということは、すなわち毒を盛るということです。 ・薬剤すべてに言えることですが、薬剤の連用で、一番に懸念されるのは自己治癒力を低下させることです。 ・具体的に述べますと、リンパ球の機能低下をもたらすということです。そうなればがんが発生しやすくなります。 【対症療法ではなく、根本治療を】 ・具体的な方法がどうであれ、根本治療(自己治癒力を高め、根本的に治すことを主眼におく)にこだわることが、慢性疾患の治療の必須条件です。しかも実際、ほとんどのケースは自己治癒力を高める手立てを個々に考えることによって、十分に治りうるのです。 ・根本治療を優先させたうえで、それでも、その効果が現れるまでの時間稼ぎが必要な場合には、薬をはじめとする対症療法が本領を発揮するのではないでしょうか。 ・外来受診する約9割の人たちは、根本治療を優先させれば、それだけで治る。 ・もちろん薬を用いることが必要な方もいらっしゃると思いますが、それはほとんどの場合が、期間を限定したものであるはずです。 【健康と病気の境】 ・みなさんの体の中では、毎日がん細胞が発生しているといわれています。しかしみなさんは、がん患者ではありません。それはなぜでしょうか。それは発生したがん細胞が、うまく成長することができないからです。つまりがん抑制遺伝子が働いて、正常な細胞にひき戻されるか、そうでなければリンパ球やマクロファージ(※)によって、ことごとく処理されてしまうからなのです。 (※)マクロファージ ≒ 単球・・・・・・白血球の一種。 免疫システムの一部をになう細胞で、生体内に侵入した細菌、ウイルス、はたまたごみや細胞の死骸まで、なんでも食べることを生業とする奇特な奴。 ・みなさんの1年前の細胞は、神経細胞などごく一部を除き、すべて入れ替わっています。原子や分子レベルの話になれば、完璧にすべてが入れ替わっています。 ・1年前のあなたを形作っていた細胞、原子、分子は、今はまったく存在しないのです。常に古い細胞が死んで、新しい細胞が生まれながら、全体としては何も変化していないように見えるだけなのです。 ・これを“恒常性(ホメオスターシス)”が保たれていると言います。 ・この恒常性、あるいは健全性を保とうとする力を「自己治癒力」と呼んでいるのです。 【「未病」を直せば「病気」にならない】 ・「未病」とは、恒常性が崩れかけていて、そのままほうっておけば完全に崩れてしまうような危うい状態を指します。 ・「未病」を軸に、体の状態を要約すると、 状態1 恒常性が健全に保たれている状態・・・・・・健康 状態2 恒常性が崩れかけている状態・・・・・・未病 状態3 恒常性が崩れ、そのままでは元に戻らなくなっていて、悪化している状態・・・・・・病気 ・中国医療で「未病」と診断されるのは、検査で明らかな異常がなく、明らかな症状もないが、少し調子の悪い状態で、病気になる前段階の心身の微妙な変化を指します。この大事な変わり目を早急にとらえ、速やかに改善を図れば未然に発病を阻止することができるのです。 ・西洋医学では、未病を見過ごし、発病してはじめて治療に取り掛かります。すなわち、検査で異常が発見されるか、明らかな症状が出るようになるまでは病気とみなしません。 ・例えば、がんの場合、いったん発病してしまいますと、治療に多大なエネルギーを要するようになります。したがって、西洋医学のように発病するまで待っていて、発病したら対処しようという考えはあまり得策とは言えません。中医のように、未病の段階で、微細な異常を的確に察知し、自己治癒力を高めて早く対処しておこうという考えが重要です。 ・“待つ”のが西洋医学とすれば、重篤な病には悠長すぎる考えと言えます。それに対し、事前に対処する中医は“攻め”の考え方と言えるのではないでしょうか。 ・「中医」の考えは自己治癒力を高めることで、病気や「未病」を治そうというもので、非常に理にかなった考えです。 ・漢方とは日本の伝統医学を、「中医」とは中国の伝統医学を意味するのです。 ・最近中国では、西洋医学と中医のいいところをうまく組み合わせた手法を中医結合医療と呼び、がん治療など慢性疾患の治療の主流になってきています。西洋医学で初期治療を行ない、そのあとを中医を用いて養生していくという非常に賢明な考え方なのです。 ・がん治療の場合、西洋医学が主流の日本では、手術や抗がん剤治療などの初期治療のあとは、基本的に放置するのみです。生活指導ももちろん、中医をすすめることもありません。ただただ再発・転移を待つのみです。 そのためでしょうか、実際に半数の人が再発・転移で亡くなります。積極的に再発・転移を抑えていれば、結果は大きく異なるはずだと思うのですが、いまだに西洋医学一辺倒なのが、日本の悲しいがん医療の現状です。 ・薬をのむと最初のうちは容易に血糖値が下がりますので、みなさんは治ったのではないかと錯覚してしまいます。ついつい油断して、食生活の是正や運動習慣の取り入れなどの話は、完全に忘却のかなたにいってしまいます。つまれ薬さえのんでいれば、節制などくそ食らえという、大きな気もちにとらわれてしまうのです。 ・本来ならば運動や食習慣の是正、ストレス対処などをうまくやりこなすことで自己治癒力を高め、インスリンの分泌能、もしくはインスリンの感受性を改善させなければいけないところを、まったく逆のことをやっているわけです。いくら薬をのみ続けても、治るどころかどんどん悪くなるのが道理です。 【自己治癒力を高めよう】 ・自己治癒力とは恒常性を保つ力であって、自己修復脳力、元に戻る力と言ってもいいでしょう。 この自己治癒力は、人が潜在的に持っているすばらしい能力です。 ・医者は病気を治せないのです。 どんな名医でも無のなものは無理なのです。 医者ができることは、ただ、患者さんが治るきっかけを作るだけです。 適切なきっかけを作ってあげ、あとは患者さんの自己治癒力が病気を治すのです。したがって、適切なきっかけを作ることができるのが名医だということになるでしょう。 ・風邪をひいて、不要な解熱剤を用いたり、抗生物質をのんだりすると、自分で治す力が著名に妨げられます。そのあげくが、治りが遅くなったり、治りが悪くなったりしてしまうのです。医者が余計なことをしないほうが、風邪はずっと治りがいいのです。 ・一般的に、西洋医学(現代医学)は対症療法の医学・医療ととらえていい。今ある症状をすみやかに解消させることを主な目的とします。 ・西洋医学は救急救命、再建手術、そして画像診断などにおいてはすばらしい力を発揮しますし、他の手法の追随をゆるさないところです。 ・糖尿病で使用する約85%を占める治療薬は、いずれも糖尿病を根本的に治す薬ではありません。単に対症治療として血糖値を下げるだけで、インスリンの分泌を担う膵臓β細胞の機能を戻す働きはありません。 ・特にSU剤などは、無理やり膵臓β細胞をむち打ってインスリンを絞り出しているのですから、非常に手荒な治療法と言えなくもありません。そのせいか、いずれはβ細胞も疲弊してしまいついにはインスリンを分泌しなくなってしまいます。そうなるといよいよインスリンで治療をしなくてはならなくなってしまうのです。 ・がんでも同じことが言えます。がん組織そのものが免疫力を抑えますので、がん組織を手術や放射線で取り除くことは確かに意味のあることです。ただしこれは根本治療ではなくて、対症療法です。なぜなら、がん組織はがんの結果であって原因ではないからです。 ・したがって慢性疾患の場合には根本治療を優先させなくてはいけません。 考え方、栄養、血行、自律神経バランス・リズムの是正をまずは行ない、もしそれで不十分な場合には、やむを得ない選択肢として薬剤や手術、あるいは放射線などの攻撃的治療(侵襲的治療)を、期間を限定して用います。 ・糖尿病や高血圧の場合も、まずは食事をはじめとした生活習慣を是正することを奨め、多くはそれだけで大きく改善し、治癒します。仮にそれでも改善が見られない場合にはやむを得ず短期間に限定して、並行して薬剤の投与を行なう場合もあるかもしれません。薬剤の使用とはそれくらいのものなのです。 ・薬剤は基本的には異物です。薬剤は言い換えれば毒物ですので、ずっと処方しつづけるのは避けるべきです。どうしても必要な場合に、必要な期間に限り、用いるべきです。 ・現在の診療報酬制度では、生活習慣の指導や、見極める技量はほとんど点数査定されません。 ・現在の診療報酬システムでは、できるだけ薬を少なくして治癒へ導こうという医師の努力は報われることがなく、何も考えないでただただ毒をたくさん投与した医師が報われるという非常におかしなシステムなのです。しかも毒性のある薬の処方が多いほど、多く点数加算されるのです。 ・薬は自分で病気を治すというすばらしい力を、時には壊してしまうことがわかりました。 ・日本は少なくとも世界でダントツ薬が多い国であることに間違いありません。現に外国からは、日本人は異様に薬を好む民族だとみられています。 ・しかし、これほど膨大な数の薬剤の中で、自己治癒力を高めることが証明されている薬剤は、残念ながらいまだかつて聞いたことがありません。 ・薬剤は基本的には復元力のじゃまはすれども、貢献することがないということになります。 ・しかもどんな薬にも100%もれなく副作用は付いてきます。副作用のない薬はこの世に存在しません。 ・薬剤というのは「毒を以て毒を制する」という考えで用いるのが基本ですので、よほどメリットが見込まれなければ安易に用いるべきものではないはずです。薬剤を用いるのは他の選択がなくなった際の最終手段と言ってもいいと思います。 ・薬を用いる場合というのは、症状がどうしても我慢できなくて、リスクを勘案してみてもメリットが大きいと判断される場合、あるいはこの薬でないと命を救う可能性がないという場合の、2つに限られると思います。 ・「薬」と「検査」は、患者さんをつなぎとめておく最強のアイテムです。 ・薬処方もなく、定期的な検査の予定もなければ、おそく人はなかなか真面目に通院しないのが現実ではないでしょうか。 ・検査は顧客を囲い込むにとても有効な手段です。検査のため、結果を教えるためと、最低2回は来院が見込めます。 ・CTもMRIも薬剤と同じく、検査件数も機器の台数も世界中で断トツ1位です。それもけた外れの多さ(世界中の3分の1)なのです。 ・これほどまでにCTやMRIが日本で稼働していれば、確かに医療費も被曝も大きくなるはずです。 ・たとえば60歳も過ぎれば、CTやMRI検査で多くの方に、ごくごく微細な脳梗塞が見つかります。 ・そうして微細な脳梗塞は、実はほとんどが何の問題もなく、薬で治療する必要もありませんし、治療効果もありません。 ・薬を短期間に限ってのむ分にはそれほど心配する津要はありませんが、数カ月以上、あるいは年単位にわたって薬をのみ続ければ、確実に自己治癒力を損ないます。しかものみ続けるほどに薬への依存が強くなり、ついには薬からの離脱が不可能になってしまいます。 ・医者への依存心そのものが自分で治す力を低下させます。 ・依存が自立を凌駕すると、とたんに病気は治りにくくなってしまいます。 ・40歳を超えると、自己治癒力は急速に低下していきます。したがって、40歳を超えたら、自己治癒力を意識した考え方、生き方をするかどうかで、病気になるかどうか、ひいては健康寿命が大きく左右されます。 ・責任感の強い人、義務感の強い人、我慢強い人、遠慮深い人、周りを気にしすぎる人は、自身のストレス負荷を過小評価する傾向にあります。 また、ストレス負荷そのものについても、大きな誤解があります。それは「我慢できるストレス負荷は、それほど大したことはない」というとらえ方です。これはまったくの正反対です。 ・がん患者さんにおけるデータですが、いわゆる「いい人」は長生きできない傾向があります。 ・ストレス負荷ががん発症の大きな要因になっていると思われるケースがとても多いのが現状です。おそらく、生きる姿勢が受け身で、考え方が消極的だという側面が、かなり影響しているのではないかと推測されます。 ・あまり「NO」と言わない人は、実はストレス負荷が大きく、心身への負担は思ったよりも大きいのです。 ・衰えを感じる年になってからの我慢、忍耐、根性、がんばり、競争などはすべて身体には悪く作用します。また、義理、約束、責任感、義務なども同じく、自己治癒力を低下させます。 ・嫌な感覚を大切にすることの裏返しが、WANT(したい)の気持ちを大切にすることです。どうしてもMUST(ねばならない)の考えを重視する人が、がん患者さんには多いのです。 ・このMUSTの発想を、WANTの発想に変えることが、自己治癒力を高め、がんを治療に導くには必要な作業なのです。 ・嫌なことは極力避ける、そしてやりたいことを優先してやる、その姿勢に自分が慣れ、相手にも認めることが、自己治癒力を高める重要なポイントです。そうすれば、お互いにストレスがすくなくなり、お互いの自己治癒力が高まるのではないでしょう。 ・自己治癒力を高める、もう1つの大切な感覚が“いい加減さ”です。 ・「嫌(NO)」「したい(WANT)」「いい加減(SOSO)」、この3つのかんかくをうまく取り入れた方は、治りが明らかにいいようです。 ・がんになる方の性向を見てみますと、ほとんどが、何事も生真面目に取り組み、完璧にそして徹底的に、とことんやらないと気がすまないタイプの人たちです。つまりいい加減さを知らない人たちです。そのような姿勢は立派には違いありませんが、往々にしてがんになりやすく、そして治りにくいのです。 【自己治癒力を高める14の方法】 1.前かがみの姿勢をやめる 2.ときどきゆっくりと深呼吸 3.食にこだわる 4.便秘にはくれぐれも気をつけよう 5.ベースサプリメントを上手に用いる 6.気がついたら、ときどき爪モミ 7.ついでにツボ刺激! 8.温冷浴を習慣にしよう 9.血流をよくする「ふくらはぎマッサージ」 10.「 11.1日に6000歩、歩こう! 12.屋時間睡眠のすすめ 13.自己治癒力を高める『海外旅行」と『読書』 人がカルチャーショックを受け、それがその人の考え方や生き方に変容を与えるほどのものであればあるほど、リンパ球数は増加します。すなわち、自己治癒力が有意に高まります。 このような事実を踏まえて、がん患者さんにはもちろん、慢性疾患の方、あるいはストレス負荷の多い方には、読書や海外旅行をお勧めしています。 14.薬は控えめにする 【賢い医者の活用法】 ・“患者”の立場にまで、自分の身を ・みなさんが素直に“患者”になりきってしまいますと、それはまさに医者の思うツボです。 ・医者と患者の立場がはっきりしている限り、医者としての建前が前面に立ちはだかり、まさに医者主導の、建前通りの治療が展開されることになってしまいます。 ・相手の土俵で相撲を取るのはやはり不利です。 ・医者に接するときに、“患者”という立場はすこぶる不利になります。 ・理想は“友人”、そうでなくても最低限“クライアント”という立場を崩してはなりません。 ・そもそも、自分の命のあるじは自分自身なのですから、自分の命の責任は自分自身が持つべきです。 ・最終決定は自分でするべきだということです。なんでもかんでもすべて医者任せというのは、いただけないことです。 【みなさんが日本の医療を変える】 ・おいしい患者さんをそのままにしておきながら医療費を抑制しようとしても、かえって日本の医療がますます荒廃するばかりです。 ・それはどういうことかと言いますと、医療費を抑えようと、診療報酬を削減すればどうなるでしょうか? ・そうすると新たに病人をつくったりして、さらにおいしい患者さんを確保するように動くでしょう。そして、7確保したおいしい患者さんを目いっぱい活用する手立てを模索するはずです。 ・結局は医療費の無駄遣いを助長することになるだけでなく、本来、治してあげなければいけない患者さんたちが、ますますなおざりにされてしまいます。 ・先進国と比較してみても、日本の医療費は非常に少ないことは世界的にはよく知られている事実です。 ・医療費そのものは国の安心度を測るいい物差しだと思います。医療費にこそお金をかけなければ、どこにお金をかけるのでしょうか。不必要な公共事業、無能な公務員や政治家にお金をかける方が、よほど無駄というべきではないでしょうか。 ・ちなみに日本の公共事業費は、先進各国と比べても異常なほど巨額で、このことは世界的にも有名です。 ・政治の世界でもそうです。国会の動き、社保庁問題など、常識では起こりえないことが実際に起こるのは、「おいしい選挙民」が数多くいるからだと思います。衆愚政治とまでは言いませんが、それに近いのが今の日本の現状ではないでしょうか。うまい言葉につい乗せられて選んでしまう、ムードで選んでしまう、ちょっとした便宜に義理を感じてしまう、握手されたから選んでしまう、つき合いで選んでしまう、見た目だけで選んでしまう、有名だからというだけで選んでしまう・・・・・・など、でたらめな理由ででたらめな代議士を選んでいるから、でたらめな議会、政府が出来上がってしまうのです。そしてでたらめな政策によって、結局は無垢で「おいしい選挙民」は、自分の首をしめることになってしまうのです。 ・結局は、「おいしい選挙民」が数多くいる限り、社会は変わらないということになるかと思います。 ・医療費を削減する必要はないというのが私の意見ですが、「おいしい患者」がいなくなれば、少なくとも現在の33兆円の半分以上は不要になります。 ・自己治癒力で十分治る喜劇の病気に医者がかかわるのは、非常に無駄だと思います。まさに社会的共通資本の無駄遣いです。 ・喜劇の病気に対して医療費が無駄遣いされているために、本当に必要な医療費が ・治さなくてはいけない疾患にお金を使うべきであり、容易に治る疾患にお金を費やすこともないと思います。どうしても治したい疾患にお金を使うことが、生きたお金の使い方ではないでしょうか。 ・私たち一人ひとりが自立した考えを持つことが、今こそ必要です。まさに私たち一人ひとりの自立が、社会の動向を決定付けるキャスティング・ボートなのです。 ・私たち一人ひとりが「おいしい人」にならないという自覚から、社会が変わる風潮は芽生えると思います。もちろん医療、医学も例外ではないと思います。 |