| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月05日 金曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
82 |
15.08 |
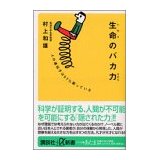 |
生命のバカ力 |
村上和雄 |
講談社+α文庫 |
☆ |
・外的な刺激などによって、私たちの遺伝子のはたらきは、ONになったりOFFになったりします。ちなみに、ONになったとは、ゼロが百になったということではなく、遺伝子の稼働率が数十パーセント程度アップしたという意味です。 ・なんらかの物理的刺激がDNAレベルにまで影響を与えていること、遺伝子のはたらきをONにさせたり、OFFにさせたりしていることが、はっきりと目に見えるかたちでわかったのです。 ・私たちが実際にもっている遺伝子は、いっときの休みもなく ・私たちの身体が人間の形状をしているとか、 ・遺伝子が刻々と活動していることによって、生命は持続されている、つまり、遺伝子こそが生命のもととも言えるのです。遺伝子が動かなくなったら、一巻の終わり、生体は死んでしまいます。 ・私たちは遺伝子によって、人間としての過去の歴史を受け継いでいるだけでなく、現在を人間として生き、そして、未来にそれを伝えていく役割を ・私たちがもっている遺伝子は、一分一秒の休みもなくはたらいているものの、常時使っているのは全遺伝子情報のせいぜい三パーセント程度、どう多く見積もっても、一〇パーセントは超えない。 ・私たちがもっている遺伝子は、けっして固定されたものではなく、条件しだいではたらきが変わる。変えられる余裕をもっているということです。 ・「火事場のバカ ・最近の遺伝子研究のめざましい進歩によって、生命体の生命体たるゆえんは、まさに、「子が親に似る」という現象の中にこそあるのだということがしだいにわかってきたのです。 ・絶えることのない生命の材料をつくりながら、さらにそのつくの方を、情報として次の世代へ伝えていくのが遺伝子です。 したがって、遺伝の謎を解くことは、とりもなおさず、生命の謎と神秘に迫ることにつながっていきます。 ・もとは、お父さんとお母さんから受け継いだたった一個の細胞(受精卵)だったものが、お母さんの胎内にいる ・細胞は、その一つ一つに核があり、核の中にある染色体にDNAという物質が収納されています。だから、六十兆個の細胞をもった人間なら、六十兆個のDNAのコピーをもっていることになります。このDNAこそが遺伝子の本体です。 ・DNAは、糖とリン酸というごくありふれた、構造的にも簡単な物質が交互につながった二本の長い鎖でできています。 ・この二重らせんのはしごに書かれている分子の文字は、地球上のすべての生物に共通していて、A(アデニン)、T(チミン)、C(シトシン)、G(グアニン)という四つの塩基によってあらわされています。 ・人間の場合、すべての遺伝子が核の中の四十六個の染色体の中に、それぞれ折りたたまれて収納されています。人間の染色体には ・子どもは父親と母親から一セットずつを受け継ぎますが、一ゲノムのDNAをすべてつなぎあわせると、約一・八メートルの長さになります。 ・一つのゲノムのもつ情報量は、約三十億のA、T、C、Gの組み合わせからなっており、これは一ページに千字ある千ページの本で約三千冊分に相当します。三十億の情報が書きこまれたDNAのテープが、人体中には約六十兆存在し、その六十兆のDNAは、みな同じ遺伝情報をもっているのです。 ・六十兆の細胞にはそれぞれにまったく同じ遺伝情報が組みこまれているから、人間のどこの細胞をとってきても、そこから一人の人間のクローンをつくりだすことのできる可能性があるということになります。 ・DNAは、じつは私たちの身体を構成するすべてのタンパク質をつくるための設計図だったのです。 ・いつ、どこに、どんなタンパク質を、どのくらいつくるかを指示しているのが遺伝子で、その指示によって、人間なら人間の身体が形成されているわけです。 ・酵素があるおかげで、糖や脂肪もつくられ、細胞がつくられていって、人間なら人間の身体になり、活動ができ、人間として生きていけるわけです。 ・最近の研究で、ある遺伝子はダイナミックに変化していることが明らかになってきました。 ・たとえば、生体はありとあらゆる異物に対して ・生体内では、私たちが知らないあいだにも、そのときそのときの必要に応じて遺伝子組み換えが自然に行われているのです。 ・これほど遺伝子の研究が進んでも、遺伝現象にとってもっとも初歩的な疑問である「カエルの子はなぜカエルなのか」という基本的な謎も解けていないし、カエルならカエルという種を決定する遺伝子についても、まったくわかっていません。 ・二〇〇一年になって、人間のタンパク質をつくっている遺伝子の数が約三万二千個ほどであることもわかりまのした。 ・このことは、少ない遺伝子数でも、部品化、連携、共生などによって、多様で複雑な仕事をこなしていることを裏づけます。 ・これらの遺伝子はじつにみごとな調和のもとではたらいています。ある遺伝子がはたらきだすと、ほかの遺伝子はそれを知って仕事の手を休めたり、作業ピッチを上げたりすることで、うまく全体のはたらきを調整しているのです。 ・こうした作業がいっときの休みもなく行われているから私たちは生きていられるわけです。 ・六十兆個の細胞の中にある人間の遺伝子の情報はみな同じでありながら、なぜ心臓の細胞は心臓にしかならず、髪の毛の細胞は髪の毛にしかならないのか。 ・私たちの身体は、もとはたった一個の受精卵です。父親と母親からワンセットずつのゲノムをもらって一対とし、両方の遺伝子を受け差ぐわけですが、この一つの細胞が倍々と分裂を繰り返し、多くの器官を、そして身体全体をつくっていきます。 ・もとは一つの細胞から出発したのに、増殖が進むと、途中で血球や臓器など、まったく別の細胞に分化していきます。分化しても、細胞の核のDNAは同じです。それなのに、なぜまったく違う器官ができるのでしょうか。 ・細胞が分化すると、そこで不要になった大多数の遺伝子が休眠状態に入ってしまう、つまり、OFFの状態になるからだと考えられています。 ・身体のどこの細胞をとってきても、その核のDNAには全情報が書かれています。けれども、すでに分化が進んだあとなので、ほかのはたらきはOFF状態になっています。これが、ある特殊な環境とか刺激のもとに置かれると、OFFになっていた遺伝子のスイッチが入って、たった一つだった最初の受精卵と同じはたらきをよみがえらせ、細胞分裂をはじめて、最終的に羊なら羊の身体をつくり、羊として生かしていくようになるわけです。 ・このように遺伝子にはON・OFFの仕組みがあり、ある種の刺激や環境によってスイッチが入ったり切れたりするのです。 ・はたらいている遺伝子と眠っている遺伝子との違いは、ひとことで言えば、タンパク質をつくることができるか否かです。同じ遺伝子でも、眠った状態では、タンパク質をつくることができないということです。 ・人間の思いや行動とはかかわりなく自律的にON・OFFが行われている場合と、なんらかの刺激や環境の変化によってスイッチが入ったり切れたりする場合があるということです。 ・心臓は自律的にはたらくけれども、外部からの刺激によってもはたらきが変化することが分かります。 ・身体の中には、一定の時間が経過するとスイッチが入るタイマー式の遺伝子があって、これらも心や気持ちの持ち方とは関係なくはたらきはじめますが、環境や外部からの刺激などによって、早くなったり遅くなったりすることもあります。 ・「病は気から」という言葉があります。気持ちの持ちようで病気を予防したり、健康を損ねたりするという意味ですが、これはけっして「気のせい」という意味ではなく、私はこのことにも遺伝子が関係していると考えています。 ・なんらかの方法で、休眠している免疫性を高めるための遺伝子のスイッチをONにすることができれば、病気を予防したり、病気にかかっても、そこから早く回復することができるわけです。 ・ガンにかかった人でも、「絶対に治るんだ」と思っている人と、「もうダメだ」と思っている人とでは、ガン細胞の増殖速度に違いが出てきます。 ・遺伝子の中には、ガンを起こす遺伝子と、ガン化を抑制する遺伝子とがありますが、たとえガン遺伝子をもっていたとしても、それがOFFの状態になっていれば発病しません。 ・たとえガンにかかっても、生きることに前向きな精神状態でいるときには、ガンを抑制する遺伝子がONになって、その増殖を遅らせることができるでしょう。ときには、ガン遺伝子をOFFにしてしまって、ガン細胞を消滅させたりすることもあります。 ・心とか気持など、精神活動の遺伝子に与える影響についての正確なメカニズムまでは解明されていませんが、そういうことを示す状況証拠、臨床データは、かなり以前から多数報告されています。 ・遺伝子のレベルで見るかぎり、人間の遺伝子暗号は誰のものでも九九.九パーセントが同じです。 ・つまり、人間の能力は誰も似たようなもので、ほんのわずかな部分で個性が表現されているにすぎないのです。 ・言い換えれば、誰にだって天才になれる可能性があるということです。 ・ほんのちょっとの差でも、私たちの目には大きな違いとなって表面化するわけですが、こうした差が出てくるのは、私たちにとって都合のいい遺伝子をONにでき、都合の悪い遺伝子をOFFにできるかどうかの違いではないかと考えられます。 ・遺伝のON・OFFが、ある程度、意識的にできるようになったら、私たちの人生にとって、新しい可能性が展開される大きなチャンスと言えるのではないでしょうか。 ・心や気持ちのもち方で遺伝子のはたらきが違ってくるというのは、人間の遺伝子の多くの部分がOFFになっていることと関係があるのではないでしょうか。遺伝子のまだわかっていない九七パーセントの部分に、心と強く反応する遺伝子があるのではないでしょうか。そして、必要に応じてONになり、必要がなくなるとOFFになるというような活動をしているのではないでしょうか。 ・多くの競技者が、試合でよい結果を出すための秘訣として、不断の練習のほかに、集中力を高めるなど、異口同音に精神面での影響の大きさを口にしています。 ・すでに人間の精神活動と遺伝子の関係についての研究が行われていますが、これからはこの部分が大きなウエートを占めるようになると考えています。 ・心のもち方、つまり、心が好ましい状態に置かれると、眠っていた遺伝子が目覚めるきっかけになることは、ほぼ間違いないでしょう。 ・遺伝子のONの効果がもっともはっきりあらわれるのは、思いきって環境を変えたときでしょう。 環境を変えると、身も心も新たな刺激を受け、それが意識の変化となって、遺伝子のON・OFFにかかわってくるはずです。 ・言い換えれば、人間は環境や経験しだいでいくらでも能力をのばすことができるし、飛躍したいと思うなら、自分から積極的に環境を変えていくことも必要だということです。 ・食べ物や栄養成分も遺伝子を左右する重要な環境要因の一つで、血糖値を一定に保つために、胎内にグルコースがあまれば分解し、不足すれば合成するというじつに合理的なはたらきをしていますが、それを自動的にコントロールしているのが関連遺伝子のON・OFF機能です。 ・すぐれた発見、発明の多くは、雲をつかむような話から生まれているのですが、日本人はこうした自由な発想の芽を摘んで、全員の能力を均質化させようとする傾向が強い。 ・いまの日本に求められているのは、組織力より発想力です。それだけに、みずから進んで環境を変えたり、自分が動きやすい環境を構築する努力をしなければ、いつまでたってももてる能力をONにすることはできないでしょう。 ・正常でない遺伝子は、生まれたときには作動していなかったのに、ストレスとか外的刺激といった環境の変化によってスイッチが入ってしまうと、それがガンや糖尿病などさまざまな病気の引き金になるわけです。 ・つまり、病気とは、DNAのはたらきがバランスを失って恒常性を保てなくなり、病気の因子をもっていた遺伝子のはたらきがONになることを言うのです。 ・いまでは、高血圧も、糖尿病も、ほとんどの病気に遺伝子が関係していたり、もしくは原因になっていたりしていることがわかっています。 ・アメリカの心理学者アブラハム・マスローは、人間の可能性を阻害する要因として、次の六つをあげています。 ①いたずらに安定を求める気持ち ②つらいことを避けようとする態度 ③現状維持の気持ち ④勇気の欠如 ⑤本能的欲求の抑制 ⑥成長への意欲の欠如 これらはいずれも遺伝子の目覚めを阻害する要因と考えてもいいでしょう。 ・いつも常識を旨としていれば、トラブルの少ない人生を送ることができるかもしれません。しかし、自分の中にひそんでいる才能を引き出すのは、むずかしいでしょう。 ・自分の仕事への至誠とか人生に対する態度が、常識の範囲内だけにとどまる様では、人にぬきんでた創造性を発揮することはできません。 ・好ましい遺伝子をONにして生きるには、自由闊達さを失わず、熱中し、持続する気持ちや姿勢が必要です。 ・遺伝子に書かれていないことは、どんな天才にもできません。しかし、遺伝子に書かれていることなら、どんな凡人にも可能です。その潜在能力を、なんらかのきっかけでONにすることができるなら。そして、その可能性は、誰もが等しくもっています。 ・私たちの能力とは、新しく身につけるものというよりも、もともともっているもので、問題は、それをいかに目覚めさせるかだと思います。 ・人間の遺伝情報には、まだ九〇~九七パーセントもの不明部分があるのだから、どんな潜在能力が眠っているか、想像もできません。無限に近い力が、私たちの内部には眠っているはずです。 ・環境の変化や外からの刺激だけでなく、心のもち方や精神的な作用によっても、眠っていた遺伝子を目覚めさせることができます。 ・遺伝子には、ONにしたほうがいい遺伝子と、OFFにしたほうがいい遺伝子があります。好ましい遺伝子をONにし、都合の悪い遺伝子をOFにすることができれば理想ですが、その最大の秘訣は、ものごとをいつもいいほうに、いいほうにと考えることです。 ・プラス発想の効用は、医学の分野でも、自然治癒力の強化としてあらわれてきます。「病は気から」と言いますが、これを逆に、「病を気で治すことができる」ととらえることもできるでしょう。 ・ある病気にかかった場合、「自分は絶対に治る」と信じているのと、「自分はもうダメかもしれない」と思っているのとでは、ゝ治癒をするにしても、早さが違ってくるし、くよくよしているとほかの病気まで併発し、さらなる免疫力の低下を招いて、どんどん重くなっていくこともあります。 ・私たちがごく自然に「死ぬのはいやだ」と思うのは、遺伝子の「生命を持続させる」スイッチがONになっているからです。 ・遺伝子は放っておけば自然に「生きる」方向に向かって作用しているものなのです。言い換えれば、いま作動している遺伝子は、基本的にプラス発想だということです。 ・人間は心の中に大きな力を秘めています。その力をうまく引き出すには、ときに自分を追い込むことも必要です。 ・ふだんはOFFの状態で休眠している遺伝子が、苦しい状況に追い込まれたとき、ONの状態になって、隠れていた能力を引き出すのです。 ・日本の ・お医者さんの役割は、あくまでもヘルプです。もちろん、ヘルプは必要だし大切なものですが、ヘルパーはヘルパーであって、オールマイティではありません。 そこで、いまの西洋医学にはなにか抜けているものがあるのではないかと考えたとき、思いあたったのが、心とか気持の部分です。 ・化学の助けを借りなくても、心が身体に大きな影響を与えることは誰でも知っているはずです。同じ量のエネルギーを使っても、おもしろいことをやっているときには疲れないし、いやなことをやらされていたら疲れます。このことは、科学的にも証明してもらわなくても、みんながわかっています。 ・ホルモンや酵素ももとをただせばタンパク質です。免疫力をつけるためには免疫タンパク質が必要です。そうしたタンパク質を、いつ、どこに、どれだけつくるかを指示しているのが遺伝子なのです。 思いとか心のもち方が遺伝子に影響を与えるかどうか、与えるとしたら、どのように作用するか、ここがわかれば、遺伝子をはたらかせたり休ませたりすることが、ある程度、意識的にできるようになるのではないか・・・・・・。 ・漫才を聴いておおいに笑ってもらったあとで血糖値を測定したところ、患者さん全員、上がり方が極端に落ちて七十七ミリグラムしか増えず、なんと前日と平均で四十六もの差が出たのです。 ・あとでそれぞれの患者さんに、漫才がどのくらいおもしろかったかを聞いているのですが、よく笑った人ほど効果があったのです。 ・たんなる治癒力が上がったというような漠然としたものではなく、血糖値の低下という明確なデータとなって効果があらわれたことがとても重要だと思います。 ・笑うことにより病気が軽くなる事実は、前に述べた以外にも、いくつか報告されています。高血圧、脳卒中、動脈硬化、心臓病、ガンなどの生活習慣病だけでなく、ボケ、うつ、風邪、肺炎にいたるまで笑いがよい効果をあげると言われています。 ・笑いは脳細胞に新鮮な血液を送り、脳卒中を予防する効果があると言われています。事実、笑いは脳、とくに左脳の血流量を増加させることや、脳の中でも記憶や感情をつかさどる脳深部のはたらきを刺激すると報告されています。 【恋愛感情とセロトニン】 ・人間の潜在能力、つまりOFFになっている部分をなんらかの作用によってONにできる可能性は、誰もが等しくもっています。その意味で能力とは新しく身につけるものではなく、もともともっていた力を目覚めさせる性質そのものだと言えます。 ・しかも、人間の遺伝情報にはまだ九七パーセント以上もの不明部分がありますから、なにが潜在能力としてひそんでいるかは想像もできません。それこそ無限に近い力が私たちの内部には眠っているはずです。 ・いま眠っている遺伝子も、周囲の環境や外からの刺激によって、目覚めさせることができます。つまり、DNAのはたらきは変えられるのです。しかも、この環境や刺激には、当人の心のもち方や精神的な作用も含まれているということが、しだいに明らかにされつつあります。 ・最近、意識が遺伝子のON・OFF機能に作用することを裏づける有力な実験結果が発表されています。 恋をすると、あるタンパク質の量に変化があらわれるという事実が、科学的に確かめられたのです。 ・遺伝子のはたらきはタンパク質をつくることですから、そのタンパク質の量が変動するということは、遺伝子のON・OFF機能に変化があったことを示しています。その量的変化の引き金になったのは、恋愛感情という心の領域に属するものだったのです。 ・心のもち方が身体のはたらきに影響を与えることなら、私たちは昔から経験的によく知っています。 ・たとえば、「恋をすると女性の肌がきれいになる」。恋愛のわくわくした気分が肌を美しくするホルモンを分泌させ、さらにホルモンをつくるはたらきをたかめるからです。 ・「惚れて通えば千里も一里」と言いますが、好きな人に会いに行くための一キロの道のりと、嫌いな人に会わなければならない一キロの道のりとでは、後者のほうがずっと疲れるし、遠く感じられるでしょう。これも、たんなる気のせいだけではなく、体内でなんらかの化学反応が起きている可能性があります。 ・遺伝子とはけっして固定されたものではなく、遺伝子のON・OFF機能には後天的な柔軟性があって、環境の変化や心の在り方でそのはたらきが変わってくるのであれば、トレーニングや節制や心がまえしだいで、眠っていた遺伝子のはたらきをONにして、健康や能力の開発につなげていくことも可能になります。 ・こうして私たちは遺伝子に、遺伝を決定する、生体活動を恒常的に支えるというはたらきのほかに、あらゆる能力や可能性の源としての側面を見いだすことができるでしょう。 ・遺伝子は、生まれつき変えることのできないファクターではなく、能力や生き方の幅を広げるための可能性の因子でもあるのです。 ・細胞は脳の指令によってもはたらきますが、同時に細胞そのものが一個の独立した生命体として生きています。遺伝子のON・OFF機能を考えるとき、このことはとても重要です。 ・笑うことも同じですが、感動するとき、遺伝子はけっして悪い方向へははたらきません。なにかに感動したときの心地よさは、誰でも経験しているところでしょう。 ・感動することで、悪い遺伝子を眠らせ、よい遺伝子をONにすることができると思っています。 |