| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月05日 金曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
84 |
15.08 |
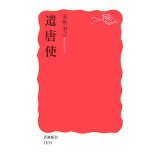 |
遣唐使 |
東野治之 |
岩波新書 |
◎ |
・第二回の使節(六〇七年)がもたらした国書をめぐって、大きな外交問題を引き起こした。 「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。 ・中国王朝の皇帝は、天から委任された唯ひとりの人として、文化の中心である中華と、その周辺の蛮人たちに君臨している建前である。その蛮人の一つである東夷の倭が、天子を名乗ることは、儒教的な秩序(礼)に背く「無礼」なことだった。隋との対等関係を打ち出した倭の姿勢が煬帝の怒りを買ったわけである。 ・「日出づる処」「日没する処」は仏典の『 ・煬帝は倭のこういう姿勢を見て、倭の国情を知る必要を感じたと思われる。 ・現在で言えば外務省にあたる ・その裴世清が伝えた煬帝の書は、「皇帝、倭皇を問う」で始まり、倭王を完全に臣下扱いしたものであった。 ・中国に学んで中央集権体制を築くという構想が、本格的に具体化するのは、隋からの帰還者がふえてからではなかったか。 ・一口に遣唐使といっても、二百年以上にわたる歴史があるから、唐、日本、あるいは東北アジアの情勢に応じて、様々な変化があった。 ・第一期は、六三〇年の第一次から、六六九年の第七次までである。 ・そのころの朝鮮半島では高句麗・百済・新羅の三国が対立しており、この情勢を背景に、朝鮮半島を直接支配しようとする唐と、朝鮮諸国に対する影響力をこれまでどおり維持したい倭との間に、深刻な対立が生じてくる。やがて新羅と結んだ唐が朝鮮半島に出兵、百済を滅ぼす中で、それは唐との直接軍事衝突にまで至った。 ・六六三年、倭は唐・新羅の連合軍に完敗し、ついに朝鮮半島から撤退する。さらに同様にして高句麗が滅ぼされるにおよび、倭は唐に対し、恭順の意を表明する使いを送った。六六九年の遣唐使である。 ・第二期は三十年の空白を隔てて、七〇二年に始まり、七七七年までである。 ・唐の高宗の后、 ・この方針転換は、もちろん先の敗戦を受けたものであって、従来の「倭」を捨てて「日本」国号を使用するようになるのも、これと関連する動きだった。 ・聖徳太子は、その神秘的な力で、前世に慧思だったころ所持していた法華経を、遣隋使を派遣して取り寄せさせたという伝承も生じ、ひいては太子こそ、列島に初めて法華経をもたらした人物という信仰が、奈良時代末の日本では定着した。 ・天台宗は法華経を根本の教えとする宗派だから、慧思・聖徳太子は、日本の天台宗の開創に連なる重要人物にもなるわけである。 ・唐の張守節が七三六年に著した『史記正義』を見ると、 「又倭国は、武皇后、改めて日本国と曰う。」 とあるのが目に付く。則天武后が、日本の国号を倭から日本に改めたという伝えのあったことがわかる。 ・国号を則天皇后が決めたように書かれていることには、違和感があるが、それは皇帝が中華世界の主として、臣下の国の名を公認する権限を持つと考えられた結果であろう。 ・ふつう国号は、蕃夷の君主が皇帝から授けられる称号の中に含まれる。 ・国号の変更は皇帝の許可のもとになされねばならなかったはずである。 ・実際は倭国のほうがその称を嫌い、日本に改めようとしたのだったが、唐側に立てば、皇帝が国号を改めたことになるのである。 ・倭は日本と改号し、唐に仕える形をとって唐との円滑な関係を築こうとした。日本の真意は第二期の始まりと同時に完成した大宝律令によく現れている。 ・そこでは天皇は皇帝・天子と位置づけられ、朝廷の威の及ぶ範囲は中華とされた。唐や新羅などの外国は、みな蕃夷である。 ・同じく律令制度を取り入れたといっても、この点は新羅や渤海などとは全く異なるところで、これらの諸国では君主は皇帝の臣下の「王」であり、その命令も詔・制や勅ではなく、「教」であった。日本のようなダブルスタンダードが維持できたのは、いうまでもなく、日本が地理的に大陸から遠く、唐の目が届きにくかったからである。 ・なお、第二期に限らず、遣唐使に皇族が加わった例はない。これも、皇族があからさまな形で、中国皇帝の臣下として扱われるのを避ける意図が働いていたのだろう。 ・第二期に入り、大宝の使節(七〇二)以降になると、一回につき四~五百人あまりの編成で、船は四隻という形が定着する。 ・住吉大社に祭祀される ・遣唐使船に設けられた祠の主神には、住吉大社を祭祀する家柄として有名な ・日本の場合、国内統治のために中国王朝の権威を借りる必要がなく、複数の外国勢力に脅かされて、外交努力をしなければならないような条件がほとんどなかった。外交使節の主な使命は、文化的なものに限られていたと言える。 ・日本は唐文化を自らのフィルターで濾過し、文化摩擦をほとんど起こさずに摂取したが、その効率的な受容のありかたは、九世紀半ばまでに、独自の文化を作り上げるためのものを、受け入れ終わっていたと言えるのではないだろうか。 ・日本の対外関係の歴史をながめていて感じるのは、それが他地域の歴史と比べ、極めて異色の特徴を持っていることである。 ・たとえば遣唐使の時代の前半に定まった「日本」国号が、千三百年を経て現在まで続いているのは、世界に例のないことである。 ・国際社会での「ジパング」という国号は、「日本」の漢字音を訛ったものである。 ・「日本」が持続したのは王朝交替がなかったからである。 |