| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月05日 金曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
89 |
15.09 |
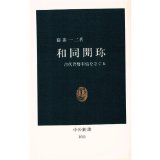 |
和同開珎 |
藤井一二 |
中公新書 |
◎ |
・和同開珎が貨幣として誕生した意義は、国家によって、もっとも普遍的な交換手段ないし流通手段が保証されたことにあるといってよい。 ・貨幣としての基本的な機能を発揮するためには、交換価値を法的に保証し、それを維持することが不可欠であった。 ・和同銭は律令制下における徴税体系と流通機構の中に組み入れられ、共通の価値基準として、給与、支払い、価格表示、貯蓄、運搬、消費、貸借などに有効な機能を果すことができた。 ・和同銭一枚(文)の価値は、単純換算でも当時、役人に支給された一日の食糧米を上回る量に相当していたに相違ない。貨幣の最小単位としてはきわめて高い価値が与えられていたのである。 ・奈良時代の政府は、和同開珎の使用と流通を図るために、交換手段の前提である価値への関心を高めるとともに、銭貨使用について多様な方策を講じている。 まず第一に、和銅四年(七一一)一〇月、役人に与える給与としての 第二は、一定の貯金をした人々に位階を授ける 第三は、旅行する人の必需品としたことである。つまり銭を費用に充てることを奨励した。和銅五年(七一二)一〇月のことである。 第四は、税制の中に銭貨を導入したことである。 第五に、和銅六年(七一三)三月のこと、税の輸送にあたる「 第六に、政府は、土地の売買に和同開珎の使用を命じる施策を打ち出した。やはり和銅六年のことである。 以上によって、律令政府の多面的な貨幣流通政策は、ほぼ完了したことになる。 ・和銅四年(七一一)一〇月のこと、銭(和同開珎)を蓄えた人に位階を与えるという「蓄銭叙位令」が出された。 ・蓄銭叙位令はほとんどの階層を対象に含むこととなった。地方に住む無位・無官の農民でも、一定額の蓄銭によって律令官人への道が夢ではなくなった。 ・しかし、この法令の特質は、流通を前提とする貯蓄の奨励にあったのではない。 ・本来、庶民の貨幣利用の便宜を図るという名目はあったが、実際は制約付きの叙位と引き換えに、蓄銭額を政府が合法的に吸収するという点に究極の目的があった。 ・国中の銅を結集して像を造り、大山を削って堂を構える夢・・・・・・。一枝の草、1把の土をもって造像への貢献を呼びかけたのは、天平十五年(七四三)一〇月、聖武天皇が発した「 ・豪族を初め多数の人々が大量の銭貨の寄進している。大量の財貨の寄進に銭貨が適したのであり、また同時に、大仏・大仏殿の建立資金として、和同開珎が十分に機能したことを物語っている。 【私鋳銭】 ・元明天皇の時期、銀銭発行は和銅元年(七〇八)五月、銅銭は同年八月のことだが、翌年の正月には、すでに私鋳銭の弊害と対策についての詔が出されている。 ・発行からずか半年余のことであった。 ・大宝律に、銅銭の私鋳に対する罪刑が定められていた。 ・和銅四年(七一一)の一〇月、政府は威信にかけて徹底して厳しい態度に出た。その内容は、私鋳銭者は |