| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月03日 水曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
89 |
15.09 |
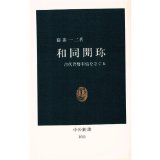 |
和同開珎 |
藤井一二 |
中公新書 |
◎ |
・和同開珎が貨幣として誕生した意義は、国家によって、もっとも普遍的な交換手段ないし流通手段が保証されたことにあるといってよい。 ・貨幣としての基本的な機能を発揮するためには、交換価値を法的に保証し、それを維持することが不可欠であった。 ・和同銭は律令制下における徴税体系と流通機構の中に組み入れられ、共通の価値基準として、給与、支払い、価格表示、貯蓄、運搬、消費、貸借などに有効な機能を果すことができた。 ・和同銭一枚(文)の価値は、単純換算でも当時、役人に支給された一日の食糧米を上回る量に相当していたに相違ない。貨幣の最小単位としてはきわめて高い価値が与えられていたのである。 ・奈良時代の政府は、和同開珎の使用と流通を図るために、交換手段の前提である価値への関心を高めるとともに、銭貨使用について多様な方策を講じている。 まず第一に、和銅四年(七一一)一〇月、役人に与える給与としての 第二は、一定の貯金をした人々に位階を授ける 第三は、旅行する人の必需品としたことである。つまり銭を費用に充てることを奨励した。和銅五年(七一二)一〇月のことである。 第四は、税制の中に銭貨を導入したことである。 第五に、和銅六年(七一三)三月のこと、税の輸送にあたる「 第六に、政府は、土地の売買に和同開珎の使用を命じる施策を打ち出した。やはり和銅六年のことである。 以上によって、律令政府の多面的な貨幣流通政策は、ほぼ完了したことになる。 ・和銅四年(七一一)一〇月のこと、銭(和同開珎)を蓄えた人に位階を与えるという「蓄銭叙位令」が出された。 ・蓄銭叙位令はほとんどの階層を対象に含むこととなった。地方に住む無位・無官の農民でも、一定額の蓄銭によって律令官人への道が夢ではなくなった。 ・しかし、この法令の特質は、流通を前提とする貯蓄の奨励にあったのではない。 ・本来、庶民の貨幣利用の便宜を図るという名目はあったが、実際は制約付きの叙位と引き換えに、蓄銭額を政府が合法的に吸収するという点に究極の目的があった。 ・国中の銅を結集して像を造り、大山を削って堂を構える夢・・・・・・。一枝の草、1把の土をもって造像への貢献を呼びかけたのは、天平十五年(七四三)一〇月、聖武天皇が発した「 ・豪族を初め多数の人々が大量の銭貨の寄進している。大量の財貨の寄進に銭貨が適したのであり、また同時に、大仏・大仏殿の建立資金として、和同開珎が十分に機能したことを物語っている。 【私鋳銭】 ・元明天皇の時期、銀銭発行は和銅元年(七〇八)五月、銅銭は同年八月のことだが、翌年の正月には、すでに私鋳銭の弊害と対策についての詔が出されている。 ・発行からずか半年余のことであった。 ・大宝律に、銅銭の私鋳に対する罪刑が定められていた。 ・和銅四年(七一一)の一〇月、政府は威信にかけて徹底して厳しい態度に出た。その内容は、私鋳銭者は |
88 |
15.08 |
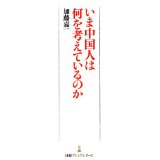 |
いま中国人は何を考えているか |
加藤嘉一 |
日経プレミアシリーズ |
◎ |
・地方の政府はとことん面子にこだわる。中央政府や外国人から「どう見られるか」を異様に気にするのである。中国を理解するうえで、中国人と付き合っていくうえで、この「面子文化」を理解しておくことは必要不可欠である。 ・接待の席においては、おごる人間がケチだと思われるのを極端に嫌がるため、とにかくたくさん注文する。お客さんが「もう食べられない」と降参する。料理はたくさん残っている。接待者はその状態を確認して、初めて面子が保たれる。 ・かつてないほど外国との交わり、関わり合いが深まっている中国社会。国内は荒れている。インターネットという武器を手に入れた中国人は、すでに一方的に統治される愚民としての人民では決してない。「物言う市民」になってきたのだ。中国は民主主義的意義における選挙権を持たない。しかしそれは、中国に有権者がいないことを意味しない。 【毒入りギョーザ事件】 ・毒入りギョーザ事件で2年後、突然容疑者逮捕のニュースが流れた時、日本の鳩山首相や岡田外務大臣は「感謝」「評価」のコメントを返した。中国メディアは「待っていました」のごとく、「日本の首相が中国側に謝意表明」「日本側が中国政府の努力に敬意を表した!」などのタイトルで、3月27日、トップページの目立つ位置を飾った。 ・それに対し、ネットでの中国人の反応の40%は、「中国人として恥ずかしい。もっと早く罪を認めるべきだった」「日本の首相は感謝する必要なんてない。中国政府を甘やかすな」であった。 ・事件に対する民衆の不満 「中国人だけが被害者だったらここまで犯人捜しをしただろうか。政府は国のメンツがかかった大事には真剣になるが、人民の健康・衛生といった小事には見向きもしないじゃないか!」 ・これら一般民衆のコメントの背景にあるのは、呂容疑者と同じく「日頃の待遇・賃金への不満」という政府・企業当局への「報復心」ではないだろうか。 ・中国の人はとにかく「南京大虐殺30万」にこだわる。家庭内で、学校でそう教えられるのだ。さもなければ「政治的に不合格」になり、中国では生きられなくなってしまう。中国人にとって、歴史認識とは「保身」の意味も含んでいるのだ。 ・中国人にとって、南京や自国史(たとえば文化大革命、天安門事件)を含めた「歴史観」とは、歴史にどう向き合うかではなく、今をどう生き抜くかという起点なのだ。 ・この背景を理解せずして、我々日本人は、歴史認識をめぐって、中国人とまともにコミュニケーションを取ることはできないと考える。 ・私たち日本人は知る必要がある。限られた政治環境、特殊な政治体制の中で、リスクを背負ってでも、戦う中国人がいる。 【日本について】 ・「日本の首相はなぜここまで頻繁に替わるのか?」 ・私たち日本人はこの質問に的確な答えを見出せるだろうか。そもそも、日本の首相が1年前後という周期で替わるという趨勢に、海外の人たちが関心を持ち、疑問を抱いているという現状をまともに認識できているのだろうか。 ・「日本は変わった国だ」と外国人から思われていることを日本人はそもそも自覚しているのだろうか。 ・白洲次郎の随筆集『プリンシプルのない日本』で語っている。 「私が政府であるならば、私は国民にいうだろう。安保を廃止して自分のふところ勘定で防備をすれば、いくらかかる。この費用は当然国民の税金から出てくるのだから、国民の所得税は〇〇パーセント増加、物品税は〇〇%増加、云々と。なぜもっと具体的に数字で、というより、自分で防備をやったらいくら税金が増えると国民に説明しないのか。 税金が増えて、我々の生活がいまよりぐっと苦しくなっても、なお外国の軍隊を国内に駐留さすよりもいいというのが国民の総意なら、安保など解消すべし。安保の賛成派も反対派もヒステリー女の喧嘩みたいな議論はやめるべしと私は思う」 ・中国の日本専門家たちは、「首相は1年以内に替わるけれども、国民の政治生活は何も変わらない。独立した官僚システムが安定しているからだ」と、自国民に説明している。 ・「日本が政治主導になる事はあり得ない。政治家が無能すぎて、官僚が狡猾すぎるからだ」 ・「頻繁換相」の根本的な理由は、「日本人が国家の目標を自らの背丈と器に適したカタチで設定できていないからだ」 ・「国家の構造」・「戦略的目標」・「国民の意識」が三位一体となって、初めて、「頻繁換相」に待ったをかけることができる。 ・若者の引きこもりが気になる。自宅に引きこもるなどという生易しいものではない。若者全体が外に目を向けない、日本の中に引きこもるという意味だ。「世界の中の日本」という視点で己を客観視しないということだ。 ・「自分さえよければいい」と威張るのであれば、なおさら海外に目を向けるべきだ、信念を持って。 そこに日本の未来があるのだから。 【日中ジャーナリスト交流会議】 ・中国ではポスト社会主義のイデオロギーとして、ナショナリズムが台頭している。5億人に及ぶネット利用者の情緒的世論が、外交政策を決めてしまうというような事態が見られる。 ・日本にとっては、主体的に米中間のバランサーとしてのポジショニングができればベスト。受け身でもどちらかと仲良くできれば合格点。最悪のシナリオは孤立することだ。 ・現地中学生との交流会での女の子の質問 「日本の政治家は主権とか領土とかあまり気にしないんですか? 興味がないんですか? 日本は海洋国家ですよね? 政治家がリーダーシップを持って、国民の主権・領土に対する意識を高める事。安全保障って、そこから始まるんじゃないんですか? 日本の政治家が日頃何に忙しくしているか興味があります。教えていただけませんか?」 ・言葉もなかった。地方の一中学生にここまで本質をつかれるとは、思ってもみなかった。年齢は12歳だった。 ・12歳の日本少年・少女は国家の安全保障の先行きを憂いているであろうか。 ・領土をめぐる紛争は対中国、ロシアというバイラテラル(二国間)のみの問題ではない。北東アジアという「ポスト金融危機時代のバルカン」ともいえる地域における、日本、ロシア、中国、そして米国間の地政学的なパワーゲームが激化したことを意味する。各プレーヤーの同地域における戦略、国益への執念、国際間の共有の利益に対する協調性が試されている。 ・メドベージェフ大統領は、漁船衝突事件をめぐる日中摩擦を上手に利用した。国内選挙向けに「近日中に北方領土を必ず訪問する」と公言していた。有言実行でポイントを稼いだ。前回中国を訪問し、胡錦濤国家主席と会談した際も、歴史問題をめぐる対日政策での協調政策を戦略的に際立たせた。「胡錦濤国家主席がロシアを訪問した際にロシアサイドと交わした合意には、対日政策に関して歴史・領土問題で歩調を合わせていくことが含まれている」 【中国はもはや中央集権国家ではない!】 ・「反日」を装ったデモは本質的には中国の内政問題である。このことを一番理解しているのは中国政府自身なのだ。 ・昨今の中国共産党は毛沢東時代の「革命党」ではなく、正真正銘の「執政党」である。社会主義というイデオロギーは保ちつつも、市場経済で国家運営を進める「与党」なのだ。 ・選挙という「手続き」さえ踏めば、結果を保証する必要のない民主主義とは異なり、自らのパフォーマンスをもって結果を示さなければ、政権自体が崩壊するシステムなのである。 ・経済が発展し、生活水準が向上しさえすれば、中国人民は沈黙し、我慢する。しかし、その前提が崩れれば、彼ら・彼女らは暴れる権利を授かる。 ・中国4千年の偉大なる歴史を見れば、明らかである。常に統一と崩壊の繰り返しなのだ。中華民族・文明の根本は何も変わっていない。 ・少数民族は引き続き、国家と民族という矛盾の中で生きていく。 ・国家が最良の統治方式だと信じて疑わない事、これほど危険な思考回路はないのかもしれない。 ・「ダライラマも含めて独立を主張しているわけではありません。ただ私たちの伝統・文化に立脚した、より良い自治を望んでいるだけです」 ・チベット内部における漢族とチベット族間の矛盾、意見の衝突も顕著であるという。「我々はより良い自治を主張する。漢族は漢化政策が現実的で、そのほうがこの地区が物質的に豊かになると主張する。コミュニケーションにならない」 |
87 |
15.08 |
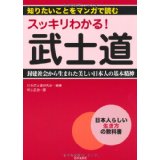 |
知りたいことをマンガで読む |
日本武士道研究会 編著 井上正治 画 |
日本文芸社 |
◎ |
・知識より叡智(知識だけあっても意味はない。学問や知識はあくまでも人間的成長や徳を促すための道具であって、決して目的となってはいけないのである) ・知行合一(武士とはすなわち行動の人) ・新渡戸稲造は言う。 「名誉」の真実の意味は、境遇から生じるものではなく、それぞれが自己の役割を、精いっぱい努める事にある。 武士の若者が追求しなければならない目標は、富や知識ではなく、名誉である。 恥となる事を避け、名を取るために、武士の息子はどのような困難も甘受し、肉体的、精神的苦痛の厳しい訓練に耐えたのだ。 ・「名誉」とは、常に「世間の目」というものを強烈に意識する武士としての誇りの問題だった。 ・「武士道とは死ぬことと見つけたり」の意味 あたかも死を美化し、礼賛し、ひたすら死ぬことを願望するかのような解釈は、決してこの言葉を正しく理解しているとは言えない。 いつも死ぬ気でいれば、武士道が身につき、足を踏み外すことのない生涯を送り、奉公しおおせるのである。 ・コケの一念。愚直でも誠実が一番。 ・管理の要諦 細かいことまであらゆることを知った上で、人に任せることだ。干渉せずにそれぞれの担当に自主的にやらせ、聞かれれば明確に指示する。わかっているが細かく追及しない、穏やかだが野放図にさせない、そうすれば役人も人民もよく治まる。 ・時代に翻弄されず、自分のやるべきことを誠実にこなすこと。後ろ向きにならない人は、いつか必ず浮かび上がってくるのである。 |
86 |
15.08 |
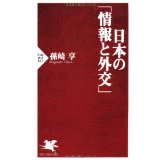 |
日本の『情報と外交」 |
孫崎 亨 |
PHP新書 |
◎ |
・ここでいう「情報」は、ニュースで受動的に見聞きするような「インフォーメーション」のことではなく、外交や軍事面での行動を前提として能動的に集められる「インテリジェンス」を指している。 ・国際社会では、すべての人が平和と安定を目指しているわけではない。ほどよい緊張が望ましいと思う人も多い。 このことは、指導者層が国内的基盤を固めるため、意図的に緊張状態を求める可能性を示している。それは日本でもけっして無縁な現象ではない。 ・スパイの役割は「現場に行け、現場に聞け」である。 ・第二次大戦終結直前、米国はドイツ、日本の町を徹底的に空爆した。なぜ、普通の都市を破壊したのか。それは、終戦後、資源を非軍事の復興に集中させるためである。 ・戦争は人道目的で行っているのではない。すべての軍事行動の是非は、軍事目的の観点で判断すべきである ・米国社会は多様な価値観から成り立っている。重大な外交・安全保障政策は、世論の支持がなくては実施できない。面白いことに米国では世論を、世間一般の世論と、指導者層の世論とに分類している。時の政権は仮に世間一般の支持を取れなくとも、最低限、指導者層の世論の支持を得る必要がある。 ・世界の多くの指導者が対米関係で失敗するのは、自分をあれだけ重用したではないか、自分は米国の利益に大変な貢献をした。だから米国は自分を切ることはない、との思い込みである。 ・米国とのディール(取引き)は、それが米国大統領とであっても、米国の一個人とのディールである。同じポストを引き継いだ人は、前任者のディールに縛られる義務は感じない。彼には白紙の委任がある。この点が、多くの非米国人が誤解する点である。 ・米国の情報関係予算は、軍関係を除いても、日本の外務省予算の一〇倍弱にのぼる。この米国の情報機関の中心になっているのがCIAである。 ・CIAの上を行く米国国家安全保障局(NSA)の雇用者数は約三万人、規模・予算ではCIAの三倍以上ともいわれている。 国家安全保障局の主たる任務は盗聴である。 ・米軍が日本軍に対して比較的容易に勝利したのは、盗聴のおかげである。対日戦争では盗聴が決定的役割を果たした。 ・元CIA長官アレン・ダレスは『諜報の技術』で次のように言う。 「真珠湾攻撃があった一九四一年ごろまでに、米国の暗号解読者たちは日本海軍および外務省の重要暗号のほとんどを解読していた。結果としてアメリカは、太平洋戦争で次の日本の作戦の証拠をしばしば事前に入手していた」 「日米開戦後における重要な問題は、アメリカが日本側の暗号を解読するのに成功した事実をいかに隠し通すかであった。ときどきこの事実が漏れたが、日本側は明らかにまったくこれに気がつかなかった。 ・孫子は、情報分野を軽視する者は「民衆を統率する将軍とはいえず、君主の補佐役ともいえず、勝利の主宰者ともいえない」としている。 ・残念ながら日本は、情報の分野を最も軽視してきた。国際社会での戦いで勝利の主宰者になりえない。そもそも今日日本では、安全保障や外交で「勝利を得るには・・・・・・」の発想すらないのではないか。 ・ナイ教授は講義で「戦争はいかなるときに起こるか。それはナンバーワンがナンバーツーに追い抜かれる危惧を感じたときである」と述べたときには、明確に日本を意識していた。 ・冷戦終結後、米国は国家の意思として、日本を主たる標的として経済スパイ活動を展開した。 ・米国はこの時期、日本のすべての省庁に内通者を確保したといわれる。内通者は交渉相手ではない。脅迫や金銭提供等、非正規な手段によって協力者となった者である。 ・スパイ活動は非合法を手段とする。この時期、CIAのみならず、米国国内を拠点とするFBIも活動している。女性を使い相手国にスパイを獲得する手口、ハニー・トラップ(蜜の罠)も適用されている。ときに売春婦や年少者も利用されている。 ・一九九〇年代は明らかに日本が標的であった。 ・日本は情報分野では、建物もしかり、人間もしかり、組織や人が存在しないに等しい。 ・日本では自衛隊に対して文民統制、シビリアン・コントロールが説かれているが、大学で軍事・安全保障に特化した講座はまずない。このなかで、シビリアンがどうして国際水準に達する安全保障の知識を得られるのか。 ・戦後解体されて復興しないものに情報機関がある。 ・国家の組織で対外活動をするのは、軍事と外交がある。情報は、軍事と外交の場で行動を起こすことを前提とする。要は、この部門で日本がどこまで独自の外交と、独自の軍事を展開する意思があるかにかかる。独自の軍事政策、外交政策を追求すれば、独自の情報が必要となる。日本の軍事政策と外交政策が米国依存なら、独自の情報機関は不要である。 ・通常、政策は次の過程をとる。「情報入手」 → 「情報分析」 → 「政策決定」。しかし、イラク戦争参加はまず対米関係の観点から決められた。イラク情勢の客観的分析からは始まっていない。 ・国際情勢の分析にはグローバルな視野がどうしても必要である。地域情勢は、地域の専門知識ですべて分かるものではない。 ・AとBに同じ内容の情報が伝えられたとしよう。この意味合いをどう理解するかは、人により異なる。国際情勢の歴史の理解や、各国情勢の理解の度合いで、同じ情報でも、その情報に与える価値が異なる。さまざまな情報に対して的確な判断をするには、長い勉強が必要である。 ・個々人が努力するのはよい。しかし、同時に組織として情報に特化した部局を強化する必要性がある。情報の専門家を育てる必要がある。しかし残念ながら、今日の外務省は逆コースを歩んでいる。情報の当然の論理すら理解されない事態を招いてしまった。 ・「わが国が他に脅威を与えなければそれでよし」が、日本および国際社会の認識であった。この状況の下、われわれは物質的豊かさを求めればよく、それはアメリカとの緊密な関係で可能であると、ほとんどの日本人は考えてきた。 ・対外政策で「日本は自ら悪はしない。安全確保はアメリカの手で」という考え方の中で、情報分野が育つはずがない。 ・国際化が進む中で「我が国はこう生きていく」という鮮明な意志を有する国のみが強力な情報機関を築く。だからこそ、日本を除くほとんどの国が、守るべきものがあると判断して、強固な情報機関を育てている。 ・日本の外交政策は今、アメリカの政策との調整をできるだけ最優先にするという方針になっています。いくら質の良い情報が政府に集まってきても、“アメリカの政策を支持する”という日本の基本政策がそれで変わることは考えづらいのです。 ・独自の政策を検討するからこそ必要とされるのが情報だと思います。基本的にアメリカと同じ政策を選択するという前提ですと、それなら情報もいらないということになります。 ・情報機能を実際に実のあるものにするには、日本独自の外交を考える必要があります。そこで本当に考えていただきたいのは、“日本の国益は何か”ということです。 ・「わが国独自の国益があるのか」――この認識が、国家の情報部門を必要とするか否かの一番の決め手である。 ・米中の狭間にあって、日本の安全保障政策のかじ取りは難しい時代に入る。否応なしに、独自の情報能力が問われる時期が来る。ほんとうはその日に備え、日本は情報機能を強化すべき時期に入っている。 【リーダーは「空気」を読んではいけない】 ・山本七平著『「空気」の研究』より <至る所で人々は、(日本における)何かの最終決定者は「人でなく空気」である、と言っている。> たとえばこうだ。 <「ああいう決定になったことに非難はあるが、当時の会議の空気では・・・・・・」 「議場のあのときの空気からいって・・・・・・」 「あのころの社会全般の空気も知らずに批判されても・・・・・・」 「その場の空気も知らずに偉そうなことを言うな」・・・・・・> ・その場の「空気」が、場合によっては、人命や国の行方さえも決定することを、同書は明らかにした。 ・あの、戦艦大和の最後となる沖縄海上特攻作戦を決定したのも、また「空気」だった。 「全般の空気よりして、当時も今も(大和)の特攻出撃は当然と思う」(軍令部次長)という発言がでてくる。 ・大和の出撃を無謀とする人びとにはすべて、それを無謀と断ずるに至る細かいデータ、すなわち明確な根拠がある。 ・だが一方、当然とする方の主張はそういったデータ乃至根拠は全くなく、その正統性の根拠は専ら「空気」なのである。 ・大和の特攻は、参謀自身が「作戦として形を為さない」と考えている「作戦」だった。しかし、「論理・データ」と「空気」が対決した結果、「空気」が勝利をおさめ、大和は悲劇的な最後を遂げることになる。 ・これに対する最高責任者、連合艦隊司令長官の戦後の言葉はどうか。「戦後、本作戦の無謀を難詰する世論や史家の論評に対しては、私は当時 ・空気が、すべてを制御し統制し、強力な規範となって、各人の口を封じてしまう現象、これは昔と変わりがない。 ・米英が強行したイラク戦争当時のことを思い起こしてみよう。戦争の火蓋がきって落とされるや否や、小泉純一郎首相は外務省が想定していた「理解」を超えて「支持」を表明。 ・以後、国内世論は「同盟国なのだから支援するのは当たり前」「米国に言われたらついていくしかない」という「空気」に支配されていく。 ・イラク戦争への疑念を述べた者はほとんど ・さらに不思議なのは、米英が開戦理由の第一に挙げた「大量破壊兵器の存在」などまったくの嘘だったことが満天下に明らかになった後でも、日本では、淘汰された者は淘汰されたまま、地位を確立した者もそのままということだ。 ・対して、「大量破壊兵器の存在」を「錦の御旗」に押し立てた米英では、事実が明らかになった後、英国では、ブレア首相とMI6長官が退陣、辞任に追い込まれた。 ・米国でも、ブッシュ政権第一期の国務長官を務めたコリン・パウエルは、長官退任後、当時国連安保理で列挙した「イラクが大量破壊兵器を保有していることの証拠」が誤認にもとづくものだったことを認め、「人生最大の恥」と深い反省の言葉を述べている。 ・この違いはどこから来るのだろうか。 やはり、米英では「人」が決定しているのに対して、日本では「空気」が決定しているからではないだろうか。 ・人が具体的な根拠を挙げて決定すれば、結果がどうあろうとも、事後に検証し総括することができる。しかし、「空気」に押し流された決定であれば、根拠があいまいなので総括のしようもない。「あの場の空気ではやむをえなかった」の一言で、いくらでも責任逃れがきく。 ・つまるところ、日本ではいまだに、客観的な情報に目を向けることよりも、「空気」といっしょにいることが重んじられているのである。 ・これは外交政策にかぎらない。どのような政策決定を行なおうが、問われるのは、その判断が事実に照らして適切だったかどうかではなく、空気といっしょにいたかどうかなのである。 ・いちばん恐ろしいことは、自分にとって都合の悪い情報をシャットアウトすることだ。確実に視野を狭めることになる。 ・外交においては、正確な情報分析に失敗し、相手の動き・変化を見落とし、身内の「空気」にのみ身を浸すことになる。そうなれば、後は身の破滅あるのみだ。 ・国際社会全体を見渡しながら、長期的な視野に立って日中関係を考えている政府首脳は皆無ではないだろうか。 ・ヒラリー・クリントンは国務長官時代、安全保障問題について日本首脳と語らうことに喜びを見出せなかった。なぜなら、日本政府の要人と会えば、出てくる言葉はフテンマ(普天間)ばかり。普天間基地移設問題は、国務長官が語るべき話題ではなく、「不動産屋かハウスキーパーの話題」と思っているはずだ。 ・一方、中国首脳には歴史や国際社会全体を見渡した雄大なスケールで話をできる人材が多かったらしい。 ・尖閣問題をめぐって、中国の民衆は「空気」に押し流され暴動に及んだ。しかし、日本の民衆の間に、そのような未熟な行動は見られなかった。一方、首脳レベルを比較すると、 ・「空気」に押し流されず、歴史に学び、冷徹なまなざしで事実を見つめ発進しつづけるリーダーが、一人でも多く育ってくれることを願ってやまない。 |
85 |
15.08 |
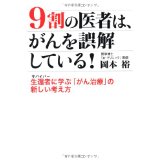 |
9割の医者はがんを誤解している |
岡本 裕 |
飛鳥新社 |
◎ |
・胃がんは胃の病気ではなく、全身の病気と言ったほうがよさそうです。現象として、結果的に胃に病変が現れているだけなのです。 ・そもそも、がんに対する根本的な誤解は、現象として現れたがん(塊)そのものを、がんのすべてだと思ってしまうことです。いわゆるがんは、がんの枝葉末節にすぎません。主犯格はもっと別に控えています。 ・がんは単なる臓器だけの病気ではなく、全身の病なのです。全身の免疫力(自己治癒力)、栄養が低下した状態です。 ・がんに最終的に打ち勝つためには、患者さん本人の体力・免疫力が大事になりますから、これらを高めることを、並行して行うことが不可欠なのです。 ・考え方をはじめ、食などの生活習慣そのものを根本的に是正しながら、免疫力を向上させ、血のめぐりや「気」の流れを改善させ、自律神経のリズムを整え、その上にさじ加減を加えながら、慎重に3大療法(手術、放射線治療、抗がん剤)を選択することによって、初めて打ち勝つことができるものなのです。 ・自分が主体になって、上手に医者と付き合っていく姿勢こそが大切です。 ・進行したがんを治したサバイバー(生還者)のみなさんが、がんが治った理由は医者ではないと言っているにもかかわらず、多くの人たちは、医者ががんを治してくれると信じているのです。 ・病気の根本原因の是正をはかり、本来人間に備わっている自己治癒力を呼びさまし、増進することにより、完全治癒を目指すのが、本来の医療の姿だと考えます。 ・がんは本来、医者や民間治療で治してもらうものではなく、医者や民間治療を活用しながら自分自身で治すものです。 ・がんは治りうるものであり、自分で治すものだと気付くことが、がんを治す唯一の方法なのです。 ・他に依存することをやめ、自分で治そうと決めた瞬間が、がん完治のスイッチが入る瞬間なのです。 ・がんは、今までの生き方のズレが大きな原因であり正体です。 ・がんが際限なく増殖していくように見えるのは、考え方をはじめ、今までの生活習慣のゆがみが改善されず、あるいは免疫力を低下させる対症治療(3大治療)のみに依存してしまうから、結果として自己治癒力が損なわれ、がん細胞のさらなる増殖を許す結果となっているにすぎない。 ・自己治癒力というものは、本来とてつもない力なのですが、年齢とともに、そしてストレスによっても低下してしまうという事実には留意する必要があります。 したがって、ある年齢を超えれば(およそ40歳くらい)、自らの努力で自己治癒力を高めていくことも必要になってくる。 ・がんによる直接死というものは、基本的にはありません。 ・がんで人が死ぬのは、がんが増殖し、急激に大量の栄養を独り占めすることによって、正常な細胞が急速に栄養不足を引き起こしてしまうからなのです。 ・がんが自然に退縮してしまう患者さんには、いくつかの共通点があります。 それは、「治ると信じていること」「よく食べること」「リンパ球(白血球の一種)」が多いこと」「身体をよく動かしていること」「夜はぐっすり眠れること」です。 ・全身の細胞に命令するのは自分自身(脳)なのですから、その司令塔(脳)がしっかりと自分自身の意思を持つことが、免疫力(復元力)を高めるのに不可欠なのではないでしょうか。人間の心と身体は、みなさんが思っているよりはるかに密接に連動しています。 ・余命告知の意味は、少なくとも3大療法という限られた枠の中だけの話です。それもその医療機関での、限定された枠の中での話です。その上、身体の環境整備をまったくしていないケースの話であり、その中でも考えられる最悪のケースの話なのです。 ・余命告知のもう1つの意味合いは、安請け合いをしてしまって、あとから苦情がくることを避けたいという主治医の思惑だと思います。 ・3大治療がひとまず完了したから、患者さんは治った、したがって生活習慣や仕事も元のままでいいというのは大きな勘違いなのです。 とんでもありません、それでは元の ・3大療法で治療しても、目に見えない「がん幹細胞」は生き残っています。 そしてこの細胞は、攻撃されればされるほど強くなり、新たな分子を生んでまた攻撃される・・・・・・。このような、いたちごっこを繰り返すことになるのです。 ・現在、がんの医療現場で当たり前に行われている3大療法は、副作用(毒性、後遺症)が非常に気になる手法ではありますが、用い方によってはすばらしい力を発揮しますので、かたくなに否定するのは得策ではないと思います。 ・3大療法のメリット(意義)は即効性です! ・3大療法は、いうなれば、「毒を ・がんは、ある臨界点を超えてしまうと爆発的に成長が早くなってしまいます。この時期を「プログレッション」と呼び、目に見えて体重が減り、一気に身体が衰弱していく過程です。 ・自らの自然治癒力がまったく枯渇してしまった状態なのです。 ・プロモーションの最後の段階で、綱引きをしていた、がん細胞軍(反乱軍)と免疫細胞軍(防衛軍)との拮抗が一気に崩れてしまいます。 ・さらに、この臨界点を超えてしまいますと、免疫細胞自体のはたらきそのものにも抑制がかかってしまい、よけいに崩壊のスピードが増していくのです。 ・この拮抗がくずれる患者さんの血液をよくみてみますと、たいていリンパ球がとても少なくなってきているのに気付きます。がんを攻撃する免疫細胞というのは、ほとんどがリンパ球ですから、これはたいへん由々しきことです。 ・しかも反対に、ストレスがかかると活性酸素(※)を放出する顆粒球という細胞がやたらと増えているのです。つまり、栄養障害にストレスが加わると一気にがんは進行していくのだと考えられます。 (※)活性酸素 酸素分子中の電子が、ペアを探そうと必死になった結果できてしまう、はなはだ不安定な化合物。細菌などをやっつけたりもしてくれて重宝なのですが、糖質、脂質、アミノ酸などを酸化したりして、胎内に悪影響を与えてしまうお騒がせ者。老化や動脈硬化、そしてがん化にも、この活性酸素が大いに一役買っています。ちなみに食べすぎ、運動のしすぎ、がんばりすぎで活性酸素は増大するので留意する必要があります。特にストレスは、活性酸素の大放出となるので、ストレス対処は長生きの必須条件! ・医者を信用しなくて不幸になった人よりも、医者を信用したばっかりに不幸になった人のほうが圧倒的に多いのは皮肉なものです。 ・西洋医学はがん治癒(完全治癒)を保障してくれないのですから、西洋医学の枠の中でしか治療を考えない医者に依存しすぎることが、命取りになるというのは、しごく当然のことです。 ☆がんで「死ぬ人」 ・考え方を変えない人 ・生活習慣を変えない人 ・自立できない人 ・医者のいいなりになる人 ・がん特効薬や特効治療があると思っている人 ・努力しない人 ・意志の弱い人 ・投げやりな人 ☆がんで「生きる人」 ・考え方を変えた人 ・生活習慣を変えた人 ・努力を惜しまない人 ・感謝の気持ちのある人 ・自立心のある人 ・生きがいを持っている人 ・夢のある人 ・意志の強い人 ・治ろうと思う人 ・死生観のしっかりした人 ・万が一、環境整備ががん細胞の増殖のスピードに追いつかない場合には、直接がん細胞をやっつける手段も必要であるということを決して忘れないようにして下さい。その場合はつまり、手術や放射線、抗がん剤などの武器(3大治療)が、一定期間必要になるということなのです。 ・がんに負けてしまうその大きな原因は、がんそのものが進行し、転移したことよりも、食べることができなくなって栄養失調に陥ったり、動く気力が ・「セルフ治療」とは、 「24時間のリズム」を整える + 1.メンタル(考え方とストレス対処) 2.栄養(食生活やサプリメント) 3.運動(血行、自律神経、気) ・西洋医学は、「生命は物質であり、物質ですべてが説明できる。だから病気も物質(物理的)として説明でき、したがって物質で治すことができる」と考えます。 ・いっぽう中医学(中国伝統医学)は、「生命には、物質の他に気(生体エネルギー)が不可欠であり、病気は気の不足や滞りととらえ、したがって気の不足や滞りを改善することで病気は治る」と考えます。つまり、中医学には物質だけでなく、もう1つ、気(生体エネルギー)という考え方が必要になってくるのです。 ・江戸時代に蘭方医学(いわゆる西洋医学)が日本に導入された際に、もともと日本にあった医学を、漢方(当時は、中国の漢の時代の医学を取り入れていたため)と称したのが、「漢方」という名前のはじまりといわれています。 ・漢方と中医の違い 主に病院などで処方される漢方は、基本的には症状と病名から治療(処方)がスタートします。したがってある意味、対症療法とも言えます。 いっぽうの中医は、病名などにこだわらず、今の身体の状態を診て(脈や舌の状態、さらに気の量や流れなど・・・・・・)、元々の体質「証」といわれるものを勘案しながら、本来の健全な状態に戻すことを治療ととらえます。したがって、身体の根本治療ということもできます。 |
84 |
15.08 |
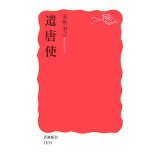 |
遣唐使 |
東野治之 |
岩波新書 |
◎ |
・第二回の使節(六〇七年)がもたらした国書をめぐって、大きな外交問題を引き起こした。 「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。 ・中国王朝の皇帝は、天から委任された唯ひとりの人として、文化の中心である中華と、その周辺の蛮人たちに君臨している建前である。その蛮人の一つである東夷の倭が、天子を名乗ることは、儒教的な秩序(礼)に背く「無礼」なことだった。隋との対等関係を打ち出した倭の姿勢が煬帝の怒りを買ったわけである。 ・「日出づる処」「日没する処」は仏典の『 ・煬帝は倭のこういう姿勢を見て、倭の国情を知る必要を感じたと思われる。 ・現在で言えば外務省にあたる ・その裴世清が伝えた煬帝の書は、「皇帝、倭皇を問う」で始まり、倭王を完全に臣下扱いしたものであった。 ・中国に学んで中央集権体制を築くという構想が、本格的に具体化するのは、隋からの帰還者がふえてからではなかったか。 ・一口に遣唐使といっても、二百年以上にわたる歴史があるから、唐、日本、あるいは東北アジアの情勢に応じて、様々な変化があった。 ・第一期は、六三〇年の第一次から、六六九年の第七次までである。 ・そのころの朝鮮半島では高句麗・百済・新羅の三国が対立しており、この情勢を背景に、朝鮮半島を直接支配しようとする唐と、朝鮮諸国に対する影響力をこれまでどおり維持したい倭との間に、深刻な対立が生じてくる。やがて新羅と結んだ唐が朝鮮半島に出兵、百済を滅ぼす中で、それは唐との直接軍事衝突にまで至った。 ・六六三年、倭は唐・新羅の連合軍に完敗し、ついに朝鮮半島から撤退する。さらに同様にして高句麗が滅ぼされるにおよび、倭は唐に対し、恭順の意を表明する使いを送った。六六九年の遣唐使である。 ・第二期は三十年の空白を隔てて、七〇二年に始まり、七七七年までである。 ・唐の高宗の后、 ・この方針転換は、もちろん先の敗戦を受けたものであって、従来の「倭」を捨てて「日本」国号を使用するようになるのも、これと関連する動きだった。 ・聖徳太子は、その神秘的な力で、前世に慧思だったころ所持していた法華経を、遣隋使を派遣して取り寄せさせたという伝承も生じ、ひいては太子こそ、列島に初めて法華経をもたらした人物という信仰が、奈良時代末の日本では定着した。 ・天台宗は法華経を根本の教えとする宗派だから、慧思・聖徳太子は、日本の天台宗の開創に連なる重要人物にもなるわけである。 ・唐の張守節が七三六年に著した『史記正義』を見ると、 「又倭国は、武皇后、改めて日本国と曰う。」 とあるのが目に付く。則天武后が、日本の国号を倭から日本に改めたという伝えのあったことがわかる。 ・国号を則天皇后が決めたように書かれていることには、違和感があるが、それは皇帝が中華世界の主として、臣下の国の名を公認する権限を持つと考えられた結果であろう。 ・ふつう国号は、蕃夷の君主が皇帝から授けられる称号の中に含まれる。 ・国号の変更は皇帝の許可のもとになされねばならなかったはずである。 ・実際は倭国のほうがその称を嫌い、日本に改めようとしたのだったが、唐側に立てば、皇帝が国号を改めたことになるのである。 ・倭は日本と改号し、唐に仕える形をとって唐との円滑な関係を築こうとした。日本の真意は第二期の始まりと同時に完成した大宝律令によく現れている。 ・そこでは天皇は皇帝・天子と位置づけられ、朝廷の威の及ぶ範囲は中華とされた。唐や新羅などの外国は、みな蕃夷である。 ・同じく律令制度を取り入れたといっても、この点は新羅や渤海などとは全く異なるところで、これらの諸国では君主は皇帝の臣下の「王」であり、その命令も詔・制や勅ではなく、「教」であった。日本のようなダブルスタンダードが維持できたのは、いうまでもなく、日本が地理的に大陸から遠く、唐の目が届きにくかったからである。 ・なお、第二期に限らず、遣唐使に皇族が加わった例はない。これも、皇族があからさまな形で、中国皇帝の臣下として扱われるのを避ける意図が働いていたのだろう。 ・第二期に入り、大宝の使節(七〇二)以降になると、一回につき四~五百人あまりの編成で、船は四隻という形が定着する。 ・住吉大社に祭祀される ・遣唐使船に設けられた祠の主神には、住吉大社を祭祀する家柄として有名な ・日本の場合、国内統治のために中国王朝の権威を借りる必要がなく、複数の外国勢力に脅かされて、外交努力をしなければならないような条件がほとんどなかった。外交使節の主な使命は、文化的なものに限られていたと言える。 ・日本は唐文化を自らのフィルターで濾過し、文化摩擦をほとんど起こさずに摂取したが、その効率的な受容のありかたは、九世紀半ばまでに、独自の文化を作り上げるためのものを、受け入れ終わっていたと言えるのではないだろうか。 ・日本の対外関係の歴史をながめていて感じるのは、それが他地域の歴史と比べ、極めて異色の特徴を持っていることである。 ・たとえば遣唐使の時代の前半に定まった「日本」国号が、千三百年を経て現在まで続いているのは、世界に例のないことである。 ・国際社会での「ジパング」という国号は、「日本」の漢字音を訛ったものである。 ・「日本」が持続したのは王朝交替がなかったからである。 |
83 |
15.08 |
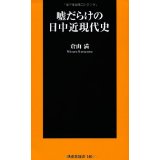 |
嘘だらけの日中近現代史 |
倉山 満 |
扶桑社新書 |
◎ |
・共産党に支配された中華人民共和国の寿命があとどれくらいなのかわかりません。ただ、彼ら中国人は絶対に生きることをあきらめないでしょう。肉食動物は、より弱い生き物を食べて生き抜きます。もし中国が崩壊したとき、隣国の草食系国家ともいうべき日本が餌食にされないと誰が言えるでしょうか。 ・歴史の基本は政治史です。人間同士の生々しい営みのほうが重要なのです。 ・中国を理解するにもやはり「政治」を理解しなければなりません。というか、中国では個人レベルでも人間関係が壮絶なのですから、彼らにとっての「政治」が何たるかを知らなければ、話は始まりません。 ・新しい王朝を打ち建てた皇帝がまっ先にすることは、功臣の粛清です。それまでの功労者を殺すのです。しかも、一族皆殺しです。なぜならば、自分の地位を脅かす能力があるからです。 ・中国人の間では力がすべてなので、「自分より強くなりそうな相手は弱いうちにつぶしておけ」が掟なのです。 ・中国は強力なコネ社会です。能力よりも情実が優先します。知り合いの「質と量」こそが、その人の能力です。どこの国でも多かれ少なかれそうう面はありますが、 中国の人脈競争は世界一苛烈です。 ・明にお伺いを立てて従った国は朝鮮だけです。 ・台湾に逃れた明の遺臣である鄭成功は何度も江戸幕府に助けを求め、日本も本気で援軍を検討していました。母親が日本人である鄭成功は、近松門左衛門のの人形浄瑠璃「国姓爺合戦」で人気を博します。 ・清国にも愛国者はいました。その筆頭が林則徐です。彼はアヘンを取り締まる欽差大臣に任命されるや、違法なアヘンを焼き払ってしまいます。これにイギリスが怒って仕掛けてきたのが、アヘン戦争です。一八四〇年のことです。 ・戦争でどちらかが一方的に善だの悪だのということは、まずありえません。少なくとも、負けた責任は負けた国の政府にあり、負けるだけの理由も存在するのです。 ・隣国の日本は、東洋の大帝国の清が西欧列強から理不尽な戦を仕掛けられて一方的な敗北を喫したことで、「次は自分の番だ!」と深刻な危機感を抱きます。 ・清国は屈辱的な大敗を喫しながら眠り続け、一方の日本は明治維新という血を流す改革を断行したのです。 ・ホンタイジ以来、清国は朝鮮を自分のものだと思っています。満州人にとっては、蒙漢回蔵のほかの民族は対等だという建前でも、朝鮮は名実ともに格下です。日本がその朝鮮を対等に扱ったら、清のメンツが丸つぶれになります。この時期の明治政府に清国を挑発したり戦争をしたりする気などありませんから、対等条約を結んだ清より格下の朝鮮には不平等条約でなければ国際問題になるのです。これでもって日本人が朝鮮人を差別したというなら、当時の事情を顧みない後世の後知恵にすぎません。 ・日本にとって目と鼻の先の朝鮮半島に敵国が勢力を伸ばすならば、もはや戦争しかないのです。ほかの国に取られるならば先に自分のものにしてしまわなければわが身が危ないという戦国時代の論理で国際社会は動いているのです。 ・関東軍にとって幸運だったのは、国内世論が支持してくれたことです。 腐敗した政党内閣、・・・ 関東軍が事変を断行したことは閉塞感を打破するかのように、国民世論は感じたのです。 ・第一次世界大戦の外交を取り仕切り、大日本帝国を世界の大国として認めさせた外務大臣の石井菊次郎は、「宣伝にかけてはわが日本ほど遅れた国はない」と慨嘆していました。 ・中国は国際連盟の小国を味方につけて日本の非道をプロパガンダします。 ・満州事変で結果的に日本は国際連盟を脱退し、国際的孤立という外交的敗北に陥るのですが、これは歴史的必然でも何でもなく政策の失敗なのです。 ・アメリカで問題だったのは、東海岸のメディアが反日親中を煽りまくったことです。 ・もし、ここで日本がまともに国策を統一し諸外国に真っ当な説明をしていれば、中国は世界の嫌われ者として放逐されていたでしょう。 ・要するに日本は、何も言わなくても日ごろの行いがいいのでみんながわかってくれるという態度です。残念ながら国際社会はそんなに甘くないですし、中国人のプロパガンダ能力をナメすぎです。 ・在欧の各大使から宣伝の必要性を具申され、外務大臣幣原喜重郎もようやく事態を認識してくれるのですが、それでも「支那側は御用宣伝屋のみならず政府の代表者迄が殆ど常識上考えられざる捏造説を平然流布し居り我方としては一々反駁するの価値すらも認めざる次第なるが」との感覚で、具体策も「貴地方面の情勢に鑑み必要ありと認めらるるに於ては概括的に何等声明を公表せらるる様致度し」といった程度です ・嘘でも信じ込ませれば価値という中国人と、真逆の態度です。 ・満州事変が起こった背景を思い出してください。閉塞感を打破したいという空気が大きかったこと、そして政党政治そのものへの不信が強かったということを。満州事変が開始されるや、大正デモクラシー的な言説は吹っ飛び、「強くて清廉で純粋な軍人さんならば、この腐った世の中を何とかしてくれる」という空気が蔓延します。こういう風潮は朝日新聞と婦人雑誌が先導(扇動)します。 ・問題は、日本のマスコミや世論が公表された報告書の内容を部分的に取り上げて、「こんな報告書など受け入れられるか」と激昂したことです。『リットン報告書』は、実質的に日本の権益をすべて認めているのです。蒋介石のほうが屈辱に耐えながら苦渋の決断をしています。それなのに日本は、暴走した世論と一緒になって過激な政策を採用していきます。 ・満州事変から満州国建国にかけて、日本は道徳的に避難されるようなことはしていません。むしろ生まじめすぎたのです。ただし、政治と外交においては、あまりにも稚拙だったと言うべきでしょう。 ・第二次世界大戦を戦った大国(ソ連、ドイツ、アメリカ、イギリス)は一九三三年から四五年まで一人の独裁者が政治を指導しています。 ・日本だけはこの十三年間に十三代の内閣で十一人の総理大臣が交代しています。英米ですら独裁者に匹敵する指導者を選んで戦争を行なおうとしている時代に、日本政治は不まじめすぎたというべきです。 ・世界は三つの陣営に分れます。一つは英米のような憲法を奉じる自由主義国、ドイツのような民族主義を鼓吹するファシズム、ソ連のような共産主義を広げようとするファシズム。 ・現実の日本は、自由主義を擁護しようとする勢力と、ナチス・ドイツのファシズムにシンパシーを持つ勢力と、日本を共産化しようとする勢力との三つ巴でした。どの勢力も決定的な権力を握れず、内政と外政が複雑に絡み合っていたのです。 ・予算権限を最終的に握るのは衆議院ですが、この頃の日本の世論は「時代の閉塞感を打ち破った軍人さんのやることはなんでも信じられる」ですから、代議士は選挙で当選するために軍拡と対外強硬論を陸海軍以上に主張するようになります。そこへ新聞・ラジオといったメディアが「支那人に制裁を」と煽るのですから、この流れを止めるのは至難となります。ポピュリズムここに極まれりです。 ・大日本帝国を滅ぼしたのは、近衛文麿とその側近たちです。彼らが中華民国との泥沼の戦いに日本を引きずり込み、それだけでは飽き足らずに対米開戦を仕組んだのです。 ・中国人にとって、対外関係など政治の道具です。いついかなるときでも内輪もめのほうが大事なのです。外国に迷惑をかけようが、人民がひどい目に遭おうが、そんなことは権力闘争に勝つことに比べれば何でもありません。 ・一九三七年七月二十九日には二百人以上の日本人居留民が虐殺された通州事件が発生します。 ・こうした事実が報道されるや、日ごろからただでさえ中国に反感を抱いていた世論は止まらなくなり、「暴支 ・そこに近衛文麿首相が戦いを嫌がる参謀本部に対して「世論がこんなに怒っているのに、なぜ参謀本部は戦おうとしないのだ」と圧力をかけます。部長と首相では勝負になりません。「昭和の日本は、軍部独裁」という先入観で判断してはいけません。 ・宣戦布告の有無は重要です。宣戦布告があって戦争がなされるのであって、なければ事変です。 【南京大虐殺】 ・第一に、「大虐殺」と言うからには、「大」とは何人からを言うのでしょうか。 ・第二に、「大虐殺」と言うからには、最低何人が虐殺されたのでしょうか。 ・第三点、虐殺肯定派の言っていることは、数が合わないのです。二十万人しか住民がいなかった南京でどうやってそんな数の人間を殺すのでしょうか。 ・第四点、南京攻略は一九三七年(昭和十二年)十二月ですが、その直後に人口は増えています。 ・第五点、日本と国民党の戦いを監視していた第三国の委員会から、日本が立派に国際法を守ったと感謝状までいただいています。 ・第六点、「南京事件」は別名「レイプ・オブ・ナンキン」などとも呼ばれます。中国人女性が大量に強姦されたから、こういう呼び名になるとのことです。では、一年後の南京には、日中混血の私生児が大量に生まれたのでしょうか。 ・第七点、日本の「残虐行為」が糾弾されるのはなぜか南京だけなのです。日本軍は南京攻略までは軍規正しく、南京だけ羽目を外して、南京攻略が終わるとまた軍規が正しくなったのでしょうか。 ・第八点、日本が南京を攻略した際、Massacre(虐殺)はあったのでしょうか。立証された議論を拝見したことがありません。ここで重要なのは「理由もなく」です。 「虐殺」の定義(四つの次元の異なる言葉) ① Genocide (民族殲滅) ② Holocaust (ユダヤ教の宗教用語。ヒトラーのユダヤ人虐殺に関してしか使わない) ③ Atrocity (都市破壊) 当時の国際法では「軍事目標主義」と言って、軍事施設ではないことを明確にしている都市に対して攻撃を加えることをAtrocityと言いました。その行為によって非戦闘員が殺されたら虐殺になります。ここで注意すべき点は、あいまいな場合は攻撃していいので虐殺には当たらないこと、むしろ都市の側に責任が発生すること、攻撃側も明らかな非戦闘員への殺傷意思がある場合にのみ虐殺と認定されることです。 ④ Massacre (虐殺) 理由なくむごたらしく殺すこと ・第九点、中華民国軍には、捕虜になる資格があったのか、国際法を守って戦ったのかが問題です。中国軍は便衣兵と呼ばれるゲリラを多用しました。軍服を着ていないので民間人と見分けがつきません。民間人の格好をして日本兵に攻撃を仕掛けてくるのが便衣兵です。疑わしきは殺しても良しの原則によれば、便衣兵と見分けがつかずに民間人を日本兵が殺しても責任は中華民国軍にあります。しかも、漢奸狩りといって、中華民国軍は見境なく見方をスパイ呼ばわりして殺して回りました。 また、中国大陸の戦争では敗残兵が盗賊のごとく略奪・暴行・強姦・殺人を繰り広げるのが通例です。督戦隊といって、後退する味方の兵士を射殺することを専門にした部隊もいます。降伏という国際法で認められた行為をさせないための舞台です。 ・中華民国軍には国際法を守る意思と能力があったか、極めて疑わしい。これで日本にだけ国際法を厳密に適用して批判するのはフェアではありません。 ・支那事変に対して、齋藤隆夫代議士は有名な反軍演説で「国際政治は空理空論ではなく、徹頭徹尾、力の論理で動いている」と演説して議会を除名になりました。しかし、現実は齋藤代議士の言った通りでした。世界は結局のところ軍事力で動いているという現実は今も何ら変わっていないのです。 |
82 |
15.08 |
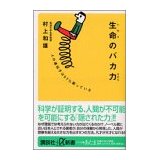 |
生命のバカ力 |
村上和雄 |
講談社+α文庫 |
☆ |
・外的な刺激などによって、私たちの遺伝子のはたらきは、ONになったりOFFになったりします。ちなみに、ONになったとは、ゼロが百になったということではなく、遺伝子の稼働率が数十パーセント程度アップしたという意味です。 ・なんらかの物理的刺激がDNAレベルにまで影響を与えていること、遺伝子のはたらきをONにさせたり、OFFにさせたりしていることが、はっきりと目に見えるかたちでわかったのです。 ・私たちが実際にもっている遺伝子は、いっときの休みもなく ・私たちの身体が人間の形状をしているとか、 ・遺伝子が刻々と活動していることによって、生命は持続されている、つまり、遺伝子こそが生命のもととも言えるのです。遺伝子が動かなくなったら、一巻の終わり、生体は死んでしまいます。 ・私たちは遺伝子によって、人間としての過去の歴史を受け継いでいるだけでなく、現在を人間として生き、そして、未来にそれを伝えていく役割を ・私たちがもっている遺伝子は、一分一秒の休みもなくはたらいているものの、常時使っているのは全遺伝子情報のせいぜい三パーセント程度、どう多く見積もっても、一〇パーセントは超えない。 ・私たちがもっている遺伝子は、けっして固定されたものではなく、条件しだいではたらきが変わる。変えられる余裕をもっているということです。 ・「火事場のバカ ・最近の遺伝子研究のめざましい進歩によって、生命体の生命体たるゆえんは、まさに、「子が親に似る」という現象の中にこそあるのだということがしだいにわかってきたのです。 ・絶えることのない生命の材料をつくりながら、さらにそのつくの方を、情報として次の世代へ伝えていくのが遺伝子です。 したがって、遺伝の謎を解くことは、とりもなおさず、生命の謎と神秘に迫ることにつながっていきます。 ・もとは、お父さんとお母さんから受け継いだたった一個の細胞(受精卵)だったものが、お母さんの胎内にいる ・細胞は、その一つ一つに核があり、核の中にある染色体にDNAという物質が収納されています。だから、六十兆個の細胞をもった人間なら、六十兆個のDNAのコピーをもっていることになります。このDNAこそが遺伝子の本体です。 ・DNAは、糖とリン酸というごくありふれた、構造的にも簡単な物質が交互につながった二本の長い鎖でできています。 ・この二重らせんのはしごに書かれている分子の文字は、地球上のすべての生物に共通していて、A(アデニン)、T(チミン)、C(シトシン)、G(グアニン)という四つの塩基によってあらわされています。 ・人間の場合、すべての遺伝子が核の中の四十六個の染色体の中に、それぞれ折りたたまれて収納されています。人間の染色体には ・子どもは父親と母親から一セットずつを受け継ぎますが、一ゲノムのDNAをすべてつなぎあわせると、約一・八メートルの長さになります。 ・一つのゲノムのもつ情報量は、約三十億のA、T、C、Gの組み合わせからなっており、これは一ページに千字ある千ページの本で約三千冊分に相当します。三十億の情報が書きこまれたDNAのテープが、人体中には約六十兆存在し、その六十兆のDNAは、みな同じ遺伝情報をもっているのです。 ・六十兆の細胞にはそれぞれにまったく同じ遺伝情報が組みこまれているから、人間のどこの細胞をとってきても、そこから一人の人間のクローンをつくりだすことのできる可能性があるということになります。 ・DNAは、じつは私たちの身体を構成するすべてのタンパク質をつくるための設計図だったのです。 ・いつ、どこに、どんなタンパク質を、どのくらいつくるかを指示しているのが遺伝子で、その指示によって、人間なら人間の身体が形成されているわけです。 ・酵素があるおかげで、糖や脂肪もつくられ、細胞がつくられていって、人間なら人間の身体になり、活動ができ、人間として生きていけるわけです。 ・最近の研究で、ある遺伝子はダイナミックに変化していることが明らかになってきました。 ・たとえば、生体はありとあらゆる異物に対して ・生体内では、私たちが知らないあいだにも、そのときそのときの必要に応じて遺伝子組み換えが自然に行われているのです。 ・これほど遺伝子の研究が進んでも、遺伝現象にとってもっとも初歩的な疑問である「カエルの子はなぜカエルなのか」という基本的な謎も解けていないし、カエルならカエルという種を決定する遺伝子についても、まったくわかっていません。 ・二〇〇一年になって、人間のタンパク質をつくっている遺伝子の数が約三万二千個ほどであることもわかりまのした。 ・このことは、少ない遺伝子数でも、部品化、連携、共生などによって、多様で複雑な仕事をこなしていることを裏づけます。 ・これらの遺伝子はじつにみごとな調和のもとではたらいています。ある遺伝子がはたらきだすと、ほかの遺伝子はそれを知って仕事の手を休めたり、作業ピッチを上げたりすることで、うまく全体のはたらきを調整しているのです。 ・こうした作業がいっときの休みもなく行われているから私たちは生きていられるわけです。 ・六十兆個の細胞の中にある人間の遺伝子の情報はみな同じでありながら、なぜ心臓の細胞は心臓にしかならず、髪の毛の細胞は髪の毛にしかならないのか。 ・私たちの身体は、もとはたった一個の受精卵です。父親と母親からワンセットずつのゲノムをもらって一対とし、両方の遺伝子を受け差ぐわけですが、この一つの細胞が倍々と分裂を繰り返し、多くの器官を、そして身体全体をつくっていきます。 ・もとは一つの細胞から出発したのに、増殖が進むと、途中で血球や臓器など、まったく別の細胞に分化していきます。分化しても、細胞の核のDNAは同じです。それなのに、なぜまったく違う器官ができるのでしょうか。 ・細胞が分化すると、そこで不要になった大多数の遺伝子が休眠状態に入ってしまう、つまり、OFFの状態になるからだと考えられています。 ・身体のどこの細胞をとってきても、その核のDNAには全情報が書かれています。けれども、すでに分化が進んだあとなので、ほかのはたらきはOFF状態になっています。これが、ある特殊な環境とか刺激のもとに置かれると、OFFになっていた遺伝子のスイッチが入って、たった一つだった最初の受精卵と同じはたらきをよみがえらせ、細胞分裂をはじめて、最終的に羊なら羊の身体をつくり、羊として生かしていくようになるわけです。 ・このように遺伝子にはON・OFFの仕組みがあり、ある種の刺激や環境によってスイッチが入ったり切れたりするのです。 ・はたらいている遺伝子と眠っている遺伝子との違いは、ひとことで言えば、タンパク質をつくることができるか否かです。同じ遺伝子でも、眠った状態では、タンパク質をつくることができないということです。 ・人間の思いや行動とはかかわりなく自律的にON・OFFが行われている場合と、なんらかの刺激や環境の変化によってスイッチが入ったり切れたりする場合があるということです。 ・心臓は自律的にはたらくけれども、外部からの刺激によってもはたらきが変化することが分かります。 ・身体の中には、一定の時間が経過するとスイッチが入るタイマー式の遺伝子があって、これらも心や気持ちの持ち方とは関係なくはたらきはじめますが、環境や外部からの刺激などによって、早くなったり遅くなったりすることもあります。 ・「病は気から」という言葉があります。気持ちの持ちようで病気を予防したり、健康を損ねたりするという意味ですが、これはけっして「気のせい」という意味ではなく、私はこのことにも遺伝子が関係していると考えています。 ・なんらかの方法で、休眠している免疫性を高めるための遺伝子のスイッチをONにすることができれば、病気を予防したり、病気にかかっても、そこから早く回復することができるわけです。 ・ガンにかかった人でも、「絶対に治るんだ」と思っている人と、「もうダメだ」と思っている人とでは、ガン細胞の増殖速度に違いが出てきます。 ・遺伝子の中には、ガンを起こす遺伝子と、ガン化を抑制する遺伝子とがありますが、たとえガン遺伝子をもっていたとしても、それがOFFの状態になっていれば発病しません。 ・たとえガンにかかっても、生きることに前向きな精神状態でいるときには、ガンを抑制する遺伝子がONになって、その増殖を遅らせることができるでしょう。ときには、ガン遺伝子をOFFにしてしまって、ガン細胞を消滅させたりすることもあります。 ・心とか気持など、精神活動の遺伝子に与える影響についての正確なメカニズムまでは解明されていませんが、そういうことを示す状況証拠、臨床データは、かなり以前から多数報告されています。 ・遺伝子のレベルで見るかぎり、人間の遺伝子暗号は誰のものでも九九.九パーセントが同じです。 ・つまり、人間の能力は誰も似たようなもので、ほんのわずかな部分で個性が表現されているにすぎないのです。 ・言い換えれば、誰にだって天才になれる可能性があるということです。 ・ほんのちょっとの差でも、私たちの目には大きな違いとなって表面化するわけですが、こうした差が出てくるのは、私たちにとって都合のいい遺伝子をONにでき、都合の悪い遺伝子をOFFにできるかどうかの違いではないかと考えられます。 ・遺伝のON・OFFが、ある程度、意識的にできるようになったら、私たちの人生にとって、新しい可能性が展開される大きなチャンスと言えるのではないでしょうか。 ・心や気持ちのもち方で遺伝子のはたらきが違ってくるというのは、人間の遺伝子の多くの部分がOFFになっていることと関係があるのではないでしょうか。遺伝子のまだわかっていない九七パーセントの部分に、心と強く反応する遺伝子があるのではないでしょうか。そして、必要に応じてONになり、必要がなくなるとOFFになるというような活動をしているのではないでしょうか。 ・多くの競技者が、試合でよい結果を出すための秘訣として、不断の練習のほかに、集中力を高めるなど、異口同音に精神面での影響の大きさを口にしています。 ・すでに人間の精神活動と遺伝子の関係についての研究が行われていますが、これからはこの部分が大きなウエートを占めるようになると考えています。 ・心のもち方、つまり、心が好ましい状態に置かれると、眠っていた遺伝子が目覚めるきっかけになることは、ほぼ間違いないでしょう。 ・遺伝子のONの効果がもっともはっきりあらわれるのは、思いきって環境を変えたときでしょう。 環境を変えると、身も心も新たな刺激を受け、それが意識の変化となって、遺伝子のON・OFFにかかわってくるはずです。 ・言い換えれば、人間は環境や経験しだいでいくらでも能力をのばすことができるし、飛躍したいと思うなら、自分から積極的に環境を変えていくことも必要だということです。 ・食べ物や栄養成分も遺伝子を左右する重要な環境要因の一つで、血糖値を一定に保つために、胎内にグルコースがあまれば分解し、不足すれば合成するというじつに合理的なはたらきをしていますが、それを自動的にコントロールしているのが関連遺伝子のON・OFF機能です。 ・すぐれた発見、発明の多くは、雲をつかむような話から生まれているのですが、日本人はこうした自由な発想の芽を摘んで、全員の能力を均質化させようとする傾向が強い。 ・いまの日本に求められているのは、組織力より発想力です。それだけに、みずから進んで環境を変えたり、自分が動きやすい環境を構築する努力をしなければ、いつまでたってももてる能力をONにすることはできないでしょう。 ・正常でない遺伝子は、生まれたときには作動していなかったのに、ストレスとか外的刺激といった環境の変化によってスイッチが入ってしまうと、それがガンや糖尿病などさまざまな病気の引き金になるわけです。 ・つまり、病気とは、DNAのはたらきがバランスを失って恒常性を保てなくなり、病気の因子をもっていた遺伝子のはたらきがONになることを言うのです。 ・いまでは、高血圧も、糖尿病も、ほとんどの病気に遺伝子が関係していたり、もしくは原因になっていたりしていることがわかっています。 ・アメリカの心理学者アブラハム・マスローは、人間の可能性を阻害する要因として、次の六つをあげています。 ①いたずらに安定を求める気持ち ②つらいことを避けようとする態度 ③現状維持の気持ち ④勇気の欠如 ⑤本能的欲求の抑制 ⑥成長への意欲の欠如 これらはいずれも遺伝子の目覚めを阻害する要因と考えてもいいでしょう。 ・いつも常識を旨としていれば、トラブルの少ない人生を送ることができるかもしれません。しかし、自分の中にひそんでいる才能を引き出すのは、むずかしいでしょう。 ・自分の仕事への至誠とか人生に対する態度が、常識の範囲内だけにとどまる様では、人にぬきんでた創造性を発揮することはできません。 ・好ましい遺伝子をONにして生きるには、自由闊達さを失わず、熱中し、持続する気持ちや姿勢が必要です。 ・遺伝子に書かれていないことは、どんな天才にもできません。しかし、遺伝子に書かれていることなら、どんな凡人にも可能です。その潜在能力を、なんらかのきっかけでONにすることができるなら。そして、その可能性は、誰もが等しくもっています。 ・私たちの能力とは、新しく身につけるものというよりも、もともともっているもので、問題は、それをいかに目覚めさせるかだと思います。 ・人間の遺伝情報には、まだ九〇~九七パーセントもの不明部分があるのだから、どんな潜在能力が眠っているか、想像もできません。無限に近い力が、私たちの内部には眠っているはずです。 ・環境の変化や外からの刺激だけでなく、心のもち方や精神的な作用によっても、眠っていた遺伝子を目覚めさせることができます。 ・遺伝子には、ONにしたほうがいい遺伝子と、OFFにしたほうがいい遺伝子があります。好ましい遺伝子をONにし、都合の悪い遺伝子をOFにすることができれば理想ですが、その最大の秘訣は、ものごとをいつもいいほうに、いいほうにと考えることです。 ・プラス発想の効用は、医学の分野でも、自然治癒力の強化としてあらわれてきます。「病は気から」と言いますが、これを逆に、「病を気で治すことができる」ととらえることもできるでしょう。 ・ある病気にかかった場合、「自分は絶対に治る」と信じているのと、「自分はもうダメかもしれない」と思っているのとでは、ゝ治癒をするにしても、早さが違ってくるし、くよくよしているとほかの病気まで併発し、さらなる免疫力の低下を招いて、どんどん重くなっていくこともあります。 ・私たちがごく自然に「死ぬのはいやだ」と思うのは、遺伝子の「生命を持続させる」スイッチがONになっているからです。 ・遺伝子は放っておけば自然に「生きる」方向に向かって作用しているものなのです。言い換えれば、いま作動している遺伝子は、基本的にプラス発想だということです。 ・人間は心の中に大きな力を秘めています。その力をうまく引き出すには、ときに自分を追い込むことも必要です。 ・ふだんはOFFの状態で休眠している遺伝子が、苦しい状況に追い込まれたとき、ONの状態になって、隠れていた能力を引き出すのです。 ・日本の ・お医者さんの役割は、あくまでもヘルプです。もちろん、ヘルプは必要だし大切なものですが、ヘルパーはヘルパーであって、オールマイティではありません。 そこで、いまの西洋医学にはなにか抜けているものがあるのではないかと考えたとき、思いあたったのが、心とか気持の部分です。 ・化学の助けを借りなくても、心が身体に大きな影響を与えることは誰でも知っているはずです。同じ量のエネルギーを使っても、おもしろいことをやっているときには疲れないし、いやなことをやらされていたら疲れます。このことは、科学的にも証明してもらわなくても、みんながわかっています。 ・ホルモンや酵素ももとをただせばタンパク質です。免疫力をつけるためには免疫タンパク質が必要です。そうしたタンパク質を、いつ、どこに、どれだけつくるかを指示しているのが遺伝子なのです。 思いとか心のもち方が遺伝子に影響を与えるかどうか、与えるとしたら、どのように作用するか、ここがわかれば、遺伝子をはたらかせたり休ませたりすることが、ある程度、意識的にできるようになるのではないか・・・・・・。 ・漫才を聴いておおいに笑ってもらったあとで血糖値を測定したところ、患者さん全員、上がり方が極端に落ちて七十七ミリグラムしか増えず、なんと前日と平均で四十六もの差が出たのです。 ・あとでそれぞれの患者さんに、漫才がどのくらいおもしろかったかを聞いているのですが、よく笑った人ほど効果があったのです。 ・たんなる治癒力が上がったというような漠然としたものではなく、血糖値の低下という明確なデータとなって効果があらわれたことがとても重要だと思います。 ・笑うことにより病気が軽くなる事実は、前に述べた以外にも、いくつか報告されています。高血圧、脳卒中、動脈硬化、心臓病、ガンなどの生活習慣病だけでなく、ボケ、うつ、風邪、肺炎にいたるまで笑いがよい効果をあげると言われています。 ・笑いは脳細胞に新鮮な血液を送り、脳卒中を予防する効果があると言われています。事実、笑いは脳、とくに左脳の血流量を増加させることや、脳の中でも記憶や感情をつかさどる脳深部のはたらきを刺激すると報告されています。 【恋愛感情とセロトニン】 ・人間の潜在能力、つまりOFFになっている部分をなんらかの作用によってONにできる可能性は、誰もが等しくもっています。その意味で能力とは新しく身につけるものではなく、もともともっていた力を目覚めさせる性質そのものだと言えます。 ・しかも、人間の遺伝情報にはまだ九七パーセント以上もの不明部分がありますから、なにが潜在能力としてひそんでいるかは想像もできません。それこそ無限に近い力が私たちの内部には眠っているはずです。 ・いま眠っている遺伝子も、周囲の環境や外からの刺激によって、目覚めさせることができます。つまり、DNAのはたらきは変えられるのです。しかも、この環境や刺激には、当人の心のもち方や精神的な作用も含まれているということが、しだいに明らかにされつつあります。 ・最近、意識が遺伝子のON・OFF機能に作用することを裏づける有力な実験結果が発表されています。 恋をすると、あるタンパク質の量に変化があらわれるという事実が、科学的に確かめられたのです。 ・遺伝子のはたらきはタンパク質をつくることですから、そのタンパク質の量が変動するということは、遺伝子のON・OFF機能に変化があったことを示しています。その量的変化の引き金になったのは、恋愛感情という心の領域に属するものだったのです。 ・心のもち方が身体のはたらきに影響を与えることなら、私たちは昔から経験的によく知っています。 ・たとえば、「恋をすると女性の肌がきれいになる」。恋愛のわくわくした気分が肌を美しくするホルモンを分泌させ、さらにホルモンをつくるはたらきをたかめるからです。 ・「惚れて通えば千里も一里」と言いますが、好きな人に会いに行くための一キロの道のりと、嫌いな人に会わなければならない一キロの道のりとでは、後者のほうがずっと疲れるし、遠く感じられるでしょう。これも、たんなる気のせいだけではなく、体内でなんらかの化学反応が起きている可能性があります。 ・遺伝子とはけっして固定されたものではなく、遺伝子のON・OFF機能には後天的な柔軟性があって、環境の変化や心の在り方でそのはたらきが変わってくるのであれば、トレーニングや節制や心がまえしだいで、眠っていた遺伝子のはたらきをONにして、健康や能力の開発につなげていくことも可能になります。 ・こうして私たちは遺伝子に、遺伝を決定する、生体活動を恒常的に支えるというはたらきのほかに、あらゆる能力や可能性の源としての側面を見いだすことができるでしょう。 ・遺伝子は、生まれつき変えることのできないファクターではなく、能力や生き方の幅を広げるための可能性の因子でもあるのです。 ・細胞は脳の指令によってもはたらきますが、同時に細胞そのものが一個の独立した生命体として生きています。遺伝子のON・OFF機能を考えるとき、このことはとても重要です。 ・笑うことも同じですが、感動するとき、遺伝子はけっして悪い方向へははたらきません。なにかに感動したときの心地よさは、誰でも経験しているところでしょう。 ・感動することで、悪い遺伝子を眠らせ、よい遺伝子をONにすることができると思っています。 |
81 |
15.08 |
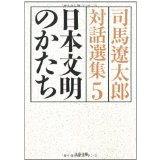 |
日本文明のかたち |
司馬遼太郎対話選集 |
文春文庫 |
◎ |
【日本人と日本文化】 (ドナルド・キーン) ・日本人は、八百万の神とかいろいろな可能性を認める――絶対的なことより相対的なことを考えやすい。日本語の場合、「でしょう」とか「であろう」とかと文末を結ぶように・・・・・・。 (司馬) ・日本語は断定を嫌って、語尾をあいまいにしてまわりの様子を見ます。 (キーン) ・西洋人として聞きたがるのは、「である」か「でない」かのどちらかです。「であろう」という場合は何パーセントの推測なのか、それを聞きたいところですが、日本人としては、それほぼかすことが日本語そのものだと思っている。はっきりしない言葉はフランス語ではない、といいますが、日本語の場合は、はっきりしている言葉は日本語ではないと言えます。日本語では、はっきり線を引いて、これは悪とか善とか、あまり言いたくない。 (司馬) ・「ないこともない」とか。 (キーン) ・日本人の生活が、まず清潔であることに、ヨーロッパ人は驚きました。ある宣教師が手紙のなかで、日本の家のなかが清潔でありすぎるから、どこでつばを吐いたらいいかわからないと書いています。ヨーロッパでは、きっと家のなかで平気でつばを吐いていたにちがいないと思います。また、当時のヨーロッパの食堂では、床の上に (司馬) ・神道は教義も何もないんですが、清潔ということだけが教義なんです。だから、日本はおそらくずいぶん古い時代化から清潔だったのでしょう。 【アメリカから来た日本美の守り手と】 ・アレックス・カー(作家。一九五二年アメリカ生まれ) 時に伝統を顧みない日本人に警鐘を鳴らしながら、日本の伝承文化の保存と継承に力を注いできた。 【日本人とリアリズム】 (司馬) ・当時の高級軍人には本当の意味での愛国心はない。これはちょっとまずいんじゃないか、という冷静な人もいたはずですが、それを公式にいうと出世がとまる。うかうかすると、殺される。亡国へころがってゆくときは、仕方がないものですね。 ・鎌倉政権が出来て、江戸期が始まるまでの間は、日本史はヨーロッパよりもヨーロッパ的かもしれません。織田信長の思想も、ヨーロッパよりもっと尖鋭なリアリズムを持ってるし、堺の商人たちも、やはり地球を意識した。 ・やっぱりぼくらが市民であって、人民であってという意識がきちっとなかったらダメだと思うんですよ。その人民というのは、生きる権利を持ってて、うるさいやつで、お上はそう自由にできるもんじゃないんだというね。 ・ところがわれわれのうるささというのは、隣の人間に対するうるささなんですよ。隣の人がちょっとゴミ箱をおれのところにやったといったら、血相を変えて喧嘩する。なぜ国家とか、自治体に対してうるさくないのか。もっと違ううるささっていうものがわれわれのなかで成長してくると、ちょっといいんじゃないかと思うんですけどね。 ・結局、われわれは自分自身を改良していくしかない。人類の仲間たちに貢献し、自分自身の社会にも被害を与えない。 (山本七平) ・それをはっきりと自覚することが、過去の繰り返しに陥らない唯一の道でしょう。 (司馬) ・勝海舟の有名な話がありますね。 咸臨丸でアメリカへ行ってみてきて、江戸の殿中に呼び出される。若年寄や老中がならんでいるところで「アメリカはどういう国だ」ときかれたら、「アメリカは日本とさかさまでございます。偉い人が賢うございます」 ・大阪の人間ばかりに内閣を組織させていたら、太平洋戦争はやらなかった、ということははっきりしている。 ・大阪の人間は、アメリカという国が強いんだから戦争しちゃダメだ、とすぐ考えるんです。ところが、弥生式時代以来の純農地帯から出てきて高等文官の試験通った連中とか、陸大へ行った連中は、貨幣経済が作りあげた意識を持っていない。貨幣経済がなければ、合理主義はなんにも生まれないんですがね。合理主義は紙の上じゃないんですものね。そこから出てきたやつが、天皇制のもとで、異常な愛国心だけで出世していこうという。暗記ものと天皇制と異常な愛国心だけで出世してきた連中だから、太平洋戦争なんかすぐはじめちゃいますよ。 |