
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年01月31日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
102 |
16/12 |
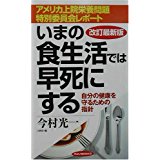 |
いまの食生活では早死にする |
今村光一 |
リュウブックス |
◎ |
まえがきに代えて――健康と新しい医学を考える最高の原点 ●アメリカ上院栄養問題特別委員会(M委)レポート ・M委員会の結論 (1)ガン、心臓病、脳卒中など先進諸国に多い病気の多くは、先進国の食事や栄養のとり方の間違いが根本的な原因になっている “食原病” である。この “食原病” には予防が第一であり、そのためには先進国風の間違った食事や栄養のとり方を健康的なものに改める必要がある。 (2)従来の薬や手術を主体とした医学は、栄養や食事のことに盲目な “片目の医学” であった。(それゆえに医学界はいまいったような病気と食事・栄養の関連に気づかずにきた)この医学は、片目の医学であるために、治療のうえでも効果の上がらない医学になっていて、医学革命が必要であり、医者の再教育も必要である。 プロローグ M委が実証した現代病と食生活の相関関係 ●栄養に盲目な従来の医学は頼りにならない 自分の健康は自分で守れ ・成人病には二つの大きな特徴がある。それはカゼその他のようなウイルス性の病気と違って長い間の食事の間違いによって起こる “食原病” だということが一つ。 ・もう一つは、少なくとも従来の医学では原則的に治せない病気であり、予防によるしか手がない病気だということである。 ・つまり成人病は自分で防ぐのが一番いい、それしか手段はないということである。 ・一人一人が自分の健康に責任を持って自分で気をつけていく以外にない。 第二章 日本でも急増した食原病 ●食事欧米化の危険は警告されていた 大腸、食道、膵臓、前立腺のガンが目立ってきた ・ガンの九〇%は食べものないしは体に入る化学物質によるといわれる。 ●日本の現状をどう見るか 平均寿命のトリック ・平均寿命というのは、ゼロ歳児があと何年の余命を期待できるかという数字である。 ・リー博士(カリフォルニア大学健康政策教授)曰く、 「平均寿命が延びたかに見えるのは、ただ新生児死亡が激減したからに過ぎない。それにわれわれは幻惑されている。だから、新生児の平均寿命は伸びたが成人の場合には一九四〇年から数十年の間で、たとえば二〇歳の男子で二年強、女子で六年強しか延びていない」 ・アメリカでは数十年で数年、日本では明治以来の一〇〇年余りで一〇年余りの延びというのが成人の場合なのだ。 ・しかも新生児の場合だって平均寿命なんてのは彼らに全く関係のない他人の数字を計算上無理に当てはめてつくられた数字マジックなのだ(そうしなければこの統計はつくれない)。 ・多くの人は平均寿命が延びたといわれると、では健康になったのかと錯覚する。そして一方では有病率(人口当たりの病人の率)は年々上昇し医療費も増大する一方である。さらに、平均寿命世界一なんてばか騒ぎをしている日本は、世界一寝たきり老人や要介護老人の多い国で、アメリカの四倍もの高率なのだ。 破れて死ぬか詰まって死ぬか、脳出血と脳梗塞の教訓 ・脳の血管が破れる日本型脳卒中の脳出血は確かに激減しており、昭和二六年に比べ五八年頃には半減、平成一〇年ではそれよりさらに二五%ほど減った。これに対し脳の血管が詰まる欧米型脳卒中の脳梗塞は、昭和二六年から平成一〇年の間に数で二五倍にも増えた。 ・脳出血にも脳梗塞にもならないという一番いい道は、塩の多さだけを別にすれば、基本的には日本型食生活を守りつつ穏健な栄養改善を進める道だ。 ・脳出血は減らしたがそれ以上に脳梗塞を増やしたのは、食事が欧米化と栄養の過剰の道を同時にたどったからである。 ・破れるほうの脳出血は一口でいえば栄養不足で起きる。蛋白質の不足などで脳の血管が弱ければ破れるからだ。 ・これに対し詰まるほうの脳梗塞は、過剰な栄養が脳の血管を詰まらせて起こる。 ・破れもせずつまりもしないためには、要するに過剰にも不足にもならない “腹八分の栄養” がいい。 ・コレステロールもそのレベルが高過ぎれば詰まるし、低過ぎれば血管はもろくなって破れるといわれるように、高過ぎず低過ぎずがいいのと同じである。 ・脳出血は国民全般の栄養水準の向上の中で激減した。しかし、その減少以上に脳梗塞を増やしたということは要するに過度な欧米化、過度な栄養改善の結果である。 ・これに対し日本型食生活の中で穏健に、つまり腹八分に栄養改善が進んでいたら、われわれは破れも詰まりもしないでこられたにちがいない。 ・脳出血が多かった昭和二〇年代はご存知の食糧難の時代だった。これに対し脳梗塞の多い現在は飽食の時代である。栄養は腹八分のバランスが大切ということを、減った脳出血と増えた脳梗塞がよく教えてくれる。 第三章 信じられないほどのビタミン・ミネラル不足 ●文明の進歩で病気が増えるのはなぜか 十九世紀までは盲腸炎もなかった ・M委証言の中にきわめてわかりやすい事例があった。 ・「盲腸炎という病名が医学の中に初めて登場したのは一八八六年で、それまでこんな病気はなかった。そしてそれは、小麦粉をふるう ・目の細かいふるいだと製粉カスのふすまもたくさんすくい取られ、小麦粉のほうにはあまり残らない。つまり小麦粉はそけだけ白くなる。そして、これは知らぬ間に人間のとる繊維の量を減らすことになった。繊維はふすまの中に多いからだ。 ・そして腸の働きをよくする繊維が少なくなったために、腸の働きの悪さが原因になる新しい病気、盲腸炎も病気のニュー・フェースとして登場したという。 現代人の「生命の鎖」は弱くなっている ・ウリリアムズ博士の「生命の鎖」理論と博士の半健康人の定義 われわれの健康、つまり生命の維持のためには五〇種ほどの栄養素がバランスよくとられていることが不可欠なことを明らかにし、これらの栄養素が体の中で協力し合って生命活動を維持している様子を「生命の鎖」という表現で示した。 この鎖全体の強さ、つまり生命力の強さは一つ一つの輪の強さ次第である。仮に五〇の輪が一つ一つ繋がって全体の鎖をつくっているとする。この全体の輪は、四九の輪がどんなに強くても一つでも弱い輪があれば、その弱い輪の所で切れてしまう。全体の鎖の強さは、だから弱い輪のレベルで決まってしまう。 ・つまり弱い輪が一つでもあれば全体としての鎖は、その弱い輪のレベル以上に強くなることはできない。ビタミンCの輪が極端に弱くなれば、他の輪が強くても壊血病になるといったのもそういうことである。 ・生命の鎖の強さ、つまり健康のレベルは、体に不可欠な栄養素がどれもバランスよくとられていなければ高い水準には維持できない。他の栄養素がいくら十分にとられていても、一つでも不足していれば、全体の健康レベルはその不足したもののレベルにまで低下してしまう。 ・生命の鎖を構成する栄養素は八種類の必須アミノ酸、一六種類のミネラル、二〇種類のビタミンなどとした。 ・体に不可欠なタンパク質は二〇種類のアミノ酸の組合せでできているが、このうち八種類は人間が体の中でつくることができない。そこで食物からどうしてもとり入れなければならないので ・一六種類のミネラルは鉄、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、マンガン、ヨウ素、セレニウム、クロムなどといったものである。二〇種類のビタミンとはビタミンA、B類、C、Eなどである。 ・これらのどれにも絶対必要水準というものがあり、このうちのどの一つがその水準以下になっても生命の鎖の強さ、つまり健康水準は低下したり、病気になったりするということだ。 ・これらの栄養素のそれぞれが、 “個人プレー” をしているのではなくて全体の鎖の一つ一つの輪となることで “チーム・プレー” をしている。 ・アルコールが直接的に肝臓を悪くするわけではなく、アルコールの長期的常用が体内の亜鉛を食い荒らして亜鉛不足を起こし、それが肝臓へのダメージになるのだということがわかっている。 “血の疲れた” 人間を増やすビタミン、ミネラル不足 ・肝臓では一〇〇〇以上の酵素がつくられている。そしてこれらの酵素がなければ汚れた血液はきれいにもされないし、失くなった分の再補給もされ得ない。要するにわれわれは生き続けられなくなる。 ・ではこういう酵素を肝臓の細胞はどうやってつくっているのかといえば、それはアミノ酸、ミネラル、ビタミンなどを原料にしてつくっている。これらの栄養素がそのまま酵素の材料だからだ。 ・ではこれらの栄養素の供給が不十分だとどうなるか。肝臓の細胞は与えられたものの範囲でベストを尽くす。しかし、それでも血液は十分にきれいにはならない。 ・いまのような状況下では、血液中には軽度の有害物質が残り、その結果として、われわれはいろいろな種類の軽い症状に悩まされることになる。体の中のどんな器官も組織も血液中の有害物質の悪影響からは逃れられない。 ・その結果として、われわれは元気がなくなって "血が疲れた" 感じになり、頭痛や気持ちの滅入り、消化不良、軽度の痛みなどに見舞われる。 ・つまりはこれらは肝臓の栄養不良が根本の原因になって起きるのだ。 ・有害物質の解毒工場として肝臓が万全の働きをしてくれないとその害は身体の全ての器官に呼ぶのだから、いろいろな症状が出てきて当然だろう。 ・そしてそれは、はっきりした病気として形に現われるずっと以前に起きる状態である。半健康人のかなり多くは、たぶん博士の言う "血の疲れた" 人々なのだと解釈してよさそうである。 ・ "血の疲れた" 状態、それは「生命の鎖」を構成する一つ一つの輪のうちのどれかが弱くなるような、バランスの崩れた栄養のとり方が原因だ。 ・一般的にいえば、現代先進国では蛋白質などの不足は少なく、むしろ過剰なくらいである。しかし、ビタミンやミネラルは絶対必要水準も満たしていない人が多いというのがだいたいの状況である。 国際栄養会議でも日本人学者が同じことを指摘 ・国際栄養会議で、日本栄養・食糧学会の井上五郎会長はいった。 「現代は過栄養と低栄養が共存するという矛盾した状況になっている」 ●ビタミン・ミネラル不足の起きる理由 (1)食事の内容的なバランスの悪さ ・脂肪や動物性蛋白質が増え、でんぷん質が減ったのが日本を含めた先進各国での食生活の内容的変化の特徴だ。 ・また、同じでんぷん質でも穀類や野菜といった自然な食品でとるでんぷん質を減らし、砂糖を増やしたことが繊維摂取量を激減させた。 ・そしてこういう変化は実はビタミンやミネラルという微量栄養素の不足も起こすものだった。 ・二つの提言 「砂糖の消費を減らして微量栄養素源である野菜や果物をもっととれ、それも自然な形でとれ」 「緑黄色野菜、豆類をいまの二倍とれ、果物は五〇%増やせ、根菜類はいまの二倍にし、じゃがいもは二五%増やせ、油脂類は二五%減らせ、砂糖、菓子類、清涼飲料は二五%減らせ」 ・今日の食生活は、カロリーのわりに基本栄養素の少ない食生活になっている。 ・動物性蛋白質や脂肪が増えれば、大きさに限度のある胃袋に入るでんぷん質(植物性食品)は減り、これだけでも微量栄養素は減る。そのうえ同じでんぷん質でもビタミンなどの多い穀類、野菜、果物を減らして砂糖を増やしたのでは、当然豊かな凹凸社会(カロリーなどが凸で微量栄養素が凹である、過栄養と低栄養の共存する凹凸社会)になる。 (2)食品をきれいにし過ぎる ・「一物全体食」とは食品を生きたままの全体として食べることで、生きた栄養、つまり生命をとり入れることを教えたものであり、現代の栄養学の立場からもその正しさが立証されている教えである。 ・アンズならば実も種もというのが一物全体食である。 ・玄米を白米にすればどれだけ重要な栄養成分が減ってしまうか。 ・スーパーで売っているじゃがいものように、ゆでて冷凍したのだとすぐ料理ができて便利である。しかし、これはじゃがいもを自分で切ってみそ汁に入れるのと比べればはるかに栄養的な価値は低い。捨てられたゆで汁と一緒に大量の栄養成分が捨てられているからだ。 ・高血圧予防に、じゃがいもをゆでてゆで汁を飲むだけでも効果が高いという学者がいる。 ・ゆで汁の中には、じゃがいもの中の豊富な高血圧予防成分であるカリウムが半分は流れ出るので、ゆで汁だけでも十分だという。 ・しかも、問題はカリウムだけでなくその他のビタミン、ミネラルにしてもそうである。 ふすま味噌の知恵を忘れた現代人 ・ふすま味噌とは、小麦の製粉かすのふすまを原料にしたものである。 ・かつて、小麦は精白してもそのかすのふすまは活用していた。これなら小麦の「一物全体食」になる。 ・米や麦を精白すれば大事なものがなくなる。その代わり、かすのほうにはいいものがたくさん入っていることになる。 ・皮つきのじゃがいもだと皮をむく場合に比べ、たとえば糖尿病予防のうえで注目されるクロムといったミネラルもたっぷり含まれている。 ・魚の腹わたも食べる一物全体食の食習慣の土地のほうがはるかに健康だ。 ・ "白くてきれいな" 食べものばかりを好む現代風の人々が捨てている部分こそ微量栄養素の宝庫なのだ。 ・調理済み食品の利用頻度の高い家庭ほどビタミンなどの不足が目立つ。 (3)体内のビタミン、ミネラルを食い荒らす要因の増加 ・食事からとる微量栄養素が少なくなっている時代に体内でこれらの栄養素が食い荒らされたり、何らかの理由によって体から追い出されたりしている。 ・大気汚染が問題になるような先進国では汚れた空気だけによってもそうなっている。 ・鼻毛の伸びが速いような環境ではビタミンA がかなり食い荒らされているに決まっている。ビタミンAは呼吸器官の組織の細胞を守ったりする効果のとくに高いものだからで、肺ガン予防の効果がよく指摘されるのもこういうビタミンAの働きのためである。 ・タバコでビタミンCが減るのは常識になっているが、ビタミンAも同じように減るのはタバコが個人レベルの大気(小気?)汚染だからである。 ・PCB、DDTなどに限らずどんな生体異物だってそれは体にとっての異物であるだけに、それとの戦いのために、ビタミンや有用なミネラル類は食い荒らされる。 ・そしてそういう生体異物が増加しているのも先進国である。 ・他にも食品添加物、汚染された大気や土壌の中の公害物質などさまざまな原因によって体内のビタミンやミネラルを食い荒らされている。 ・また、カルシウムの敵リンのように、本来は生体異物でなく体に必要なものでありながらも食品添加物の中に過剰に含まれているために、他のミネラルとのバランスを崩してカルシウムの敵になっているものもある。 ・さらに過剰なリンはカルシウムだけでなく、鉄分なども体から追い出す鉄分の敵にもなっている。 ・こういう鉄分不足は貧血の他にも疲れやすさ、だるさ、頭痛、めまい、食欲不振などなど多くの半健康人症状を起こす。 ・現代ではさまざまな生体異物や生体異物まがいのものが体内でビタミンやミネラルを食い荒らしたり、その必要度を高めているのだと知る必要がある。 ・ビタミンCを体内でつくれないのは人間その他ごく少数の動物だけである。 (4)食品そのものを劣化させる現代の農業 ・化学肥料と農薬で土壌中の大切なミネラルがみな流出してしまった。また土壌中の有機質もなくなった。 ・作物は土壌中の養分を吸って育つものである。だからこのようにやせた土壌では、たとえ形は同じ作物ができても重要な栄養分を失ったやせた作物にしかならない。そしてそれを食べる人体も・・・・・・ということになる。 ・「身土不二」という古い言葉がある。土と人体は結局は一つの者だという意味である。 劣化した食べものでは病気も治せないと嘆いた天才ゲルソン ・セレニウムというミネラルのガン予防効果が注目されるきっかけになったのは、土壌中にセレニウムの多い土地ではガンが少ないというアメリカや中国での調査からだった。有名な中国の調査では、セレニウムの豊富な土地では少ない土地より肺がんにかかる率は八分の一の低さだった。 ・先進国での肺ガンの急増は、化学農業が土壌中のセレニウムを食い荒らしたり流出させたことが有力な原因の一つでなかったとは誰にもいえないだろう。 第四章 “異常現象”も多い現代の食事、健康状況 ●からみ合う複合原因が “異常現象” を起こしている ビタミンB6不足の貧血と高校生の脚気 ・鉄分不足と考えられやすい貧血だが、比較的軽度の貧血を調べてみると鉄分不足でなくてB6不足の場合が多いという。B6は鉄分から血色素をつくるのに不可欠なビタミンなので、鉄分は十分でもB6が不足すれば貧血になるわけだ。 ・では麦飯を食べればそれでいいのか? ・現代のB6不足の貧血の背後には実は脂肪、蛋白質の過剰もからんでいて、脂肪などを余計にとると、B6はその分だけ必要になるビタミンだからだ。 ・中・高校生に頻発して何年か前に話題になった脚気、この時は、甘いものの過剰が砂糖の体内代謝のために必要なビタミンB1の消費を増大させて脚気を起こしたのだろう。 牛乳を一日一リットル飲んで起きたカルシウム欠乏症 ・牛乳を一日一リットル飲んでいたのにひどいカルシウム欠乏症になった青年のケース。 野菜はほとんど食べず甘いものが大好きだった。 カルシウムをいくらとったって、それを体の中で活用するのに不可欠なマグネシウムという別のミネラルがなくてはカルシウムも役には立たない。しかし野菜や豆類や海草も嫌いというのでは、マグネシウムは完全に不足する。もう一つはカルシウムの敵の砂糖をたくさんとっていたことも原因だった。 ・現代のカルシウム不足の原因 第一にカルシウムそのものの摂取不足、つぎにカルシウムの敵の砂糖や食品添加物からのリンの過剰、さらにカルシウムの味方のマグネシウムなどの不足などである。 ・リンそのものは必要な栄養物質だが、過剰になれば体からカルシウムを追い出す。 ・しかし今では多くの食品添加物などのなかに、これがイヤというほど入っている。 ・又、食事全体のバランスの悪さがカルシウム欠乏を招いている。 ・肉食の過剰はカルシウム不足の原因になる。肉の中の過剰なリンがやはりカルシウムの敵になるからだという。 ・菜食主義者のほうが骨多孔症など骨の病気が断然少ない。 国民病になったアレルギーと “奇病” エイズの本当の原因 ・アレルギーの原因は、食生活の変化や過剰栄養、食品添加物、環境汚染物質、ストレスの増加などが考えられる。 ・カゼのような病気は、もし病原菌だけが本当の原因になって起こるとすれば全部の人が病気にならなければおかしい。そこでよく考えてみると、確かに病原菌は病気の一つの原因ではあってもむしろ抵抗力の強弱のほうがより大きな問題であって、抵抗力の低下のほうがより大きな原因だとわかる。 気づかれないままに低血糖症はわが国でも増えている ・低血糖症はそれとは逆の高血糖症である糖尿病の前駆症状なので、糖尿病の増加が著しい今のわが国で増えているのは常識でもわかる。 ・消化吸収のよ過ぎる食物のためにインスリンを何とか無理して大量に生産していた膵臓は、やがて疲れてしまう。そしてついに必要なだけのインスリンも出せなくなる。こうなるとインスリン不足病の糖尿病になるというわけだ。 ・繊維が十分にとられていれば糖尿病にならないことは今では常識になっている。このことから考えても低血糖症が糖尿病の兄弟であるのはわかろう。 "麻薬" になることもある砂糖のこわさ ・昭和五七年の日教組全国教育研究集会では、「非行に走る子には食生活の乱れが目立つ」という発表があり注目された。そしてそういう子は「甘い菓子や清涼飲料水のとり過ぎで成長期に必要なタンパク質、カルシウム、ビタミン類が完全に不足だった」という。 ・マクガバン博士は、実験でネズミの脳の中のドーパミンという物質のレベルを調べた。すると砂糖を大量に与えられたネズミはドーパミンが極端な不足状態になることがわかった。ドーパミンは神経刺激の伝達物質なので、これの不足は当然神経の働きをおかしくする。 ・砂糖はさらにもう一つの意味でも麻薬になっているのは確実と見ていい。それは低血糖症→アドレナリンの過剰分泌→麻薬という経路を通じてである。 ・砂糖は血糖の乱高下を起こして低血糖状態も起こす。すると体は低血糖状態からくるエネルギー・ショックに対処するためにアドレナリンというホルモンを分泌させて血糖レベルを正常レベルに引き上げようとする。ところがこのアドレナリンが体内で分解されてできるアドレナクロムという物質は、実は麻薬メスカリンの中の薬効成分(つまり麻薬成分)と同じ物質なのだ。 ・そしてアドレナクロムが精神分裂症の原因物質だというのは、精神分裂症の原因に関する説のうちでも有力な説になっているものなのだ。 ・そして砂糖は、低血糖症の一因になることでアドレナクロムの "原料" になるアドレナリンを過剰に分泌させるものとすれば、砂糖自身は麻薬でなくても麻薬を体の中でつくらせるものだという理屈になってくる。 ・テレビの暴力番組が子どもに悪影響を与えるというのは一見本当そうだが、あまりにも通俗的な解釈。それより悪いのは、甘い菓子などのコマーシャルのほうだ。 アルミニウムや鉛の害も見逃せない ・異常行動をする子どもや学習不能児は、体内に普通の子の二・五~八・五倍も高いレベルのアルミニウムがたまっていた。 ・精神的に不安定な子どもの中には、鉛が体内に蓄積しているケースが多い。 「17歳」やキレる子どもの乱れた食事 ・キレる子どもやADHD児(注意欠陥・多動性障害)の症状や行動は、・・・低血糖症の犠牲者であるのは間違いない。 ・その原因は、低血糖症、ビタミン、ミネラルなどの微量栄養素の欠乏、食品ケミカル、脳アレルギー、有害金属などであるのも確かである。 分析と部分に振り回される科学的思考方法 ・部分には明るくなる、しかし全体のことには暗くなるのが科学的分析的な思考法の弱点だといわれる。しかし科学も科学技術も神にしたに二〇世紀は、化学的分析的思考のそういう弱点に気づかず、化学的分析的思考とは、全てに明るくなることだと錯覚した。 ・ワラビには発ガン物質があるとは以前からいわれてきた。しかし、ワラビなどアクの強いものの中には、アク抜きすれば発ガン抑制効果の高い別の物質もかなり多い。 ・科学的、部分的に見て発ガン物質があるというのも発ガン抑制物質があるというのも事実なのだろう。 ・問題はこれらの研究に対してどう対処すべきかということである。しかし、発ガン物質があるというのでワラビを全く食べないのも、抑制物質があるというのでワラビばかり食べるのも、どっちもおかしな態度である。 ・科学的思考を神にしたわれわれは “部分” に振り回されて、どっちかに傾いた行動ばかりしてきたのが本当である。 大きく育つとガンになる? ・部分的、分析的な思考に傾き過ぎた科学を神にした現代では、現代に特有の感覚や好みや価値観などもつくり出し、これらが互いに結びついたり、ごちゃごちゃになったりした不思議で “狂った社会” をつくり出している。 ・黒っぽい本物のふすま味噌はイヤだという消費者の好みもそんな現代的嗜好の一つである。そのため醸造会社は大豆の煮汁を産業廃棄物として栄養成分とともに捨てる。しかも、この “廃棄物” の処理のために設備や消費電力に大金をかけ、それが製品価格に転嫁される。 ・本当は高くて栄養不足の味噌を買っているだけなのである。 第五章 病気を起こさないための食事作戦 ●先進国の食事の欠陥を是正するための具体的指針 穀類は精白しないほうが好ましい ・穀類はなるべく未精白ないし精白度の低い形でとるのがビタミン、ミネラル、繊維などの点から見て望ましい。 ・穀物の繊維は精白度を高めれば高めるほど減ってしまうものだし、精白度を高めれば、ガンを防ぐ効果の高いことが立証されているセレニウムや他のミネラルもビタミンも何分の一にも減ったりゼロにさえなる。 ●健康的な長寿食とはどんな食事か 実証的な研究が結論づけた近藤式五項目 ・近藤正二博士の健康長寿食五項目のポイント (1)動物性蛋白質にせよ植物性蛋白質にせよ、蛋白質は必要なだけはとらねばならない。 (2)動物食が過剰になるいわゆるゼイタクな食事は心臓病を招き、若死にを招く。 (3)いも類は、でんぷん質を穀類ばかりでとるより、カサがあって早く満腹感を起こさせるのでカロリーのとり過ぎを防ぐという効果もある。 (4)野菜はいろいろな種類のものを十分にとる必要がある。 (5)穀類も米偏重でなく多種類のほうがいい。 ・大豆は成長期の子どもの伸長を伸ばす効果はない。しかし弱点はその一点だけであり、大豆の蛋白質は他の点で動物性蛋白質に十分代わりうる。 ・子どもはある程度動物性蛋白質をとれ、しかし大人になったらそれは減らす方向にし、蛋白質不足を起こさないために大豆をとれ。 ・古い言葉で「五穀豊穣」という言葉も五穀があってはじめて健康になれるということを示した先祖の教えに他ならない。 バランスを失えば悪い食べものになる ・食べものの中にいい食べもの、悪い食べものなんてない。どんな食べものも全体のバランスのなかでバランスよく食べればいい食べものになるし、バランスを失えば悪い食べものになる。 ・現代の食生活はいろいろな点でバランスが崩れているということなのだ。 食事の間違いは万病のもと ・M委はアメリカの六大死因はみな食原病だったといった。この指摘は日本をも含めた先進国にそのまま当てはまる。 ・心臓病、ガン、糖尿病、脳卒中などと病名は違ってもそれは表面化して現れる症状が違うだけで、これらの病気の背後では現在の先進国の食事のもつ同じ欠陥が原因になっているという意味ではどれも “一つの病気” である。 ●ガン予防とガンをめぐる議論 ガン予防のための幾つかのポイント [NCI] (1)脂肪を減らす (2)野菜をもっととる (3)腹八分目に食べる (4)繊維をもっととる (5)ビタミン類は十分に (6)亜鉛とセレニウムは適切量を維持する (7)ヨーグルトなど有用菌を利用する [アメリカ科学アカデミー] (1)脂肪を減らせ (2)過度のアルコールと塩分を減らせ (3)果物、野菜、未精白穀物をよく食べよ (4)とくに人参などの緑黄色野菜やミカン類などのビタミンA、Cの多いものはよく食べよ [日本のがんセンター] (1)いろどり豊かな食卓にして、バランスのとれた栄養をとる (2)ワンパターンではありませんか? 毎日、変化のある食生活を (3)おいしい食べ方をしましょう。食べすぎをさけ、脂肪はひかえめに (4)健康的に楽しみましょう。お酒はほどほどに (5)吸いたい気持ちはわかりますが、たばこを少なくする (6)緑黄色野菜をたっぷり。適量のビタミンと繊維質のものを多くとる (7)胃や食道をいたわって。塩辛いものは少なめに、熱いものはさましてから (8)突然変異を引きおこします。焦げた部分はさける (9)食べる前にチェックして。かびの生えたものに注意 (10)太陽はいたずら者です。日光に当たりすぎない (11)いい汗、流しましょう。適度にスポーツをする (12)気分もさわやかに。体を清潔に ・同じ蛋白質でも魚の蛋白質のほうが胃がんになりやすいという結果が出ている。これは胃がんの発ガン物質ニトロソアミンを魚の蛋白質のほうが肉の蛋白質より余計につくるからだ。 ・魚とともに大豆や種類も量も豊富な野菜をちゃんととっている人の場合には、やはり胃がんの発生率はずっと減少する。 ・食品にはどれもそれ一つで完璧なものなどない。どれにも長短はあり、それをバランスよく組み合わせることで短を打ち消し長を伸ばすようにするのが食生活の知恵というわけだ。 ・魚の蛋白質がつくるニトロソアミンもビタミンCを加えた場合には何十分の一にも減ったという。種類も量も豊富な野菜や大豆の中にはビタミンCもその他の発ガン物質抑制物質もあるということがわかってきている。 脂肪やコレステロールに関する新研究 ・『第六次改訂、日本人の栄養所要量』(厚生省、平成一一年) 「多価不飽和脂肪酸の過剰摂取は体内で過酸化物を生成し、動脈硬化症疾患やガンなどさまざまな健康障害をもたらす」 ・ここで多価不飽和脂肪酸といっているのは、「指針」が動脈硬化を予防するとしている植物性の脂肪や魚類の脂肪に他ならない。 ・反対のことをいっているわけだが、これは植物油の代表のようにいわれてきたリノール酸の過剰摂取のことをいっている。 ・しかし、これは本当はリノール酸の過剰の害よりも間違った製造法でつくられている現代の植物油のリノール酸の中にたくさん含まれるトランス脂肪酸という危険な脂肪酸の害を指摘しているものである。 ・欧州各国ではトランス脂肪酸を基準以上に含む食用油やマーガリンは販売禁止になっている。 ・トランス脂肪酸を大量に生じさせるような現代風製油法の中ではリノール酸とは別のオメガ3系列の脂肪酸は姿を消してしまう。リノール酸より “敏感” な脂肪酸だからである。 ・そして、この系列の脂肪酸の不足が現代の健康問題やキレる子どもを生むなどの社会医学的な問題も生じさせている。 第六章 ガンもビタミンで治る! 新しい医学に目を開こう ●栄養療法医学への医学革命が必要 まずわれわれ自身が新しい医学へ目を開こう ・食物繊維の働きを重視した新しい糖尿病治療食は、糖尿病治療食の革命といわれるものです。 ・この新しい治療食は、悪くしないのが精々で治すことはできないといわれてきた糖尿病を治すのだから、確かに糖尿病治療食の革命である。 ・一方、栄養に盲目でない医学が従来の医学にとって代わるようにまだなっていない。 ・これが本当の新しいシステムとして定着するには代替療法を健保でカバーするといった制度上の大きな変革も必要だ。 ●パスツールから狂った二〇世紀の医学 肉体の持つ自然な抵抗力の強化が大切 ・傷ひとつだってそれを治すのは体自体の持つ自然治癒力である。 ・この自然治癒力の強弱は要するに「生命の鎖」の強弱であり、バランスのとれた栄養で肉体がいい状態にある人とない人では、傷ひとつにしてもその治り方に大差があるものである。 ・抵抗力の強い人は病菌に出会っても病気にはならない、病菌のことを問題にするより抵抗力の強弱、つまり「生命の鎖」の強弱のほうがより大事な問題だということである。 ・病菌は病気の原因になるとしてもそれはむしろ第二原因に過ぎない。本当は抵抗力の低下している時に病菌に出会うと病気になりやすいと理解すべきで、病気の第一原因は抵抗力の低下なのだ。 ・抵抗力も自然治癒力もほとんど栄養とイコールだ。 ・栄養に盲目な医学になった。ここに医者や薬、手術が病気を治すという幻想が当然生まれることとなった。 ●ガン治療も栄養療法の時代へ 増殖のペースをゆるやかにしてやればガン細胞も正常細胞にもどれる ・セレニウムを十分とっていればガンにならないのはなぜか? ・セレニウムは細胞の増殖(分裂)のペースを時間的にゆるやかにするということである。 ・そこでセレニウムを与えると狂った細胞のガン細胞も分裂のペースがゆるやかになる。ゆるやかになればガン細胞も自分の中の狂い(遺伝子の狂い)を自分で修繕して正常細胞に戻る時間が稼げる――ガンの栄養療法家たちが治療にセレニウムを使っているのはこういう理由による。 ・健康人の場合も体内では、いつも細胞のガン化という現象は起っているに違いない。しかし、それは自然にその狂い(つまりガン化)が修繕されているので発病しない。セレニウムがガン予防に効果があるのも修繕の時間的余裕を細胞に与えるからで、それは同時に治療にも役立つというわけだ。 ・ガン細胞はすべて狂った細胞であってもその狂い方がまちまちだ。 ・一つのガンの腫瘍が一〇〇〇のがん細胞でできているとすれば、それぞれの細胞はそれぞれ一〇〇〇通りの違う狂い方をしていると考えた方がいい。 |