
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年12月09日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
104 |
16/12 |
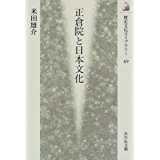 |
正倉院と日本文化 |
米田雄介 |
吉川弘文館 |
◎ |
正倉院宝物 正倉院宝物のなりたち 数十万点の宝物の由来 ・天平勝宝八歳(七五六)、光明皇后は六〇種の薬物を廬舎那仏に献上している。そのときの献上品目録が「種々薬帳」である。 ・献上した薬物のうち、もし病人の治療に用いることができるものであれば、僧綱の許可を得て使用してもよい。それらの薬によって、人々が苦しみを解除し、諸悪を絶つことができ、その人々が廬舎那仏の住む蓮華蔵の世界へ往生できるようにと願っていると記されている。 ・皇后は 称徳天皇の東大寺行幸 ・正倉院に収納されている宝物は、献物帳を伴っての献上品で、その献物帳によって宝物の材質や技法、法量や数量などが確認できるのである。正倉院宝物が少なくとも一二〇〇余年も前の記録に合致するということは世界史的に見ても稀有なことといわざるをえない。 ・正倉院宝物は、宝物自体に付けられている付箋、木牌、あるいは墨書・朱書などによって、それがいつ、どのような儀式に用いられたか、時には儀式の内容などを確認することができる。宝物に記されている銘文によって、宝物の価値自体が明らかになるとともに、これまで知られていなかった事実が、客観的な文言で確認できるのである。 宝物の点検 宝物の移納と点検――平安時代末から江戸時代 寛文六年の点検 ・古くは宝庫の開扉は朝廷の専決事項であった。ところが鎌倉時代の初め、源頼朝が宝庫の開扉にかかわって以来、勅封倉を開扉するための鍵は朝廷が掌握しているが、宝庫を開けさせる権限は武家が把握しているのである。 ・武家の許可なくして宝庫の修理・宝物の点検が行えないのは、武家の経済力に依存せざるをえなかったためであろう。 ・このように鎌倉時代以来、宝庫の開封・点検にあたっては武家に経済的支援を求めており、皇室または東大寺の宝庫管理の権限が武家に把握されている。 |