
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年12月21日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
105 |
16/12 |
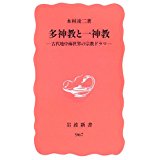 |
多神教と一神教 |
本村凌二 |
岩波新書 |
◎ |
第1章 「死すべき人間」と神々 ― メソポタミアの宗教 ― 最古の叙事詩に見える超自然への畏怖 ・脳が肥大化した人間には、いつのころからか畏怖という感情がめばえていた。おそらく自然の天変地異と人間の死はこの畏怖という感情の萌芽におおいに力があっただろう。 ・太陽がかがやき、月に照らされ、星がまたたく。風がふき、雨がふる。雷鳴と雷光ととともに嵐がくる。日が翳り大地がゆらぐ。自然界の激変は目にみえる世界の向こう側に何か得体のしれない力のあることを感じさせる。 ・さらにまた、生命ある人間の死、とりわけ慣れ親しんだ身近な者の死はその生命の死滅を認めたくないという気持ちをおこさせる。肉体を離脱した霊魂は目に見える世界の向こう側に今も生きつづけるという思いがしてならないのだ。 ・この目に見える世界の向こう側にある超自然的な世界に人々は恐れおののくのである。目に見ることも手でふれることもできないが、たしかに人間を脅かす力というものがある。それを感じるとき、「恐ろしい」という思いをいだかざるをえない。 まばゆく光り輝く神々のイメージ ・これらの畏怖する人々は神々をどのように思い描いていたのだろうか。 ・そこには光り輝くまばゆいばかりの存在があり、目がくらんで頭がふらふらし身震いしてしまうのである。神そのものが光に満ち満ちており、神の衣装からも装身具からも光がきらめくのである。その輝きあふれる閃光は周りを照らし出し、その明るさのために目眩をおこしそうになる。そのきらめきは言葉にならないほど心ときめくものであり、それとともに恐ろしいものでもあった。 ・この眩惑と畏怖とが一つに融合した光源こそが神という存在をそのほかのものから際立たせるのであり、それはメランムとよばれている。 ・そこにあっては光や輝きがあたかも「存在」を指す表意文字として考えられていたかのようであった。 ・そのことはメランムとの同義語がいくつもあり、それらもまた「きらめく輝き」とともに「畏れ」「おののき」をこめた感情をよびさますものであったことからもわかる。神々をめぐる人びとの感情はからみあって複雑であり、いわく言い難いものがあった。 ・神々を表現するにあたって、人々は驚愕も讃美も畏怖もどれもが同時に喚起されるような修飾語句をちりばめた。 ・自然現象では大洪水も嵐も増水も山もあり、獰猛な動物なら野牛あり獅子ありドラゴンありの恐怖をよびおこす表現が用いられた。 ・メソポタミアの人々の神々への思いは、文書に記された彼らの個人名にも反映している。 ・これらの個人名のなかには、輝き、閃光、荘厳、権威などとともに、崇敬、畏れとおののき、賞讃などが入り混じった感情がこめられていたのである。 最古の神々の階層序列 ・先史時代の太古までさかのぼれば、神なる観念はまず天空の神であった。 第2章 来世信仰と一神教革命 ― エジプトの宗教 ― 冥界に復活する死者たち ・エジプト人の来世信仰はなんとも不思議としか言いようがない。彼らの信じるところでは、人間が死ぬとその人の霊魂は肉体を離れるのだが、いつの日かふたたび肉体を必要とするという。自分の亡骸が土に戻ってしまえば、霊魂はどこへ行ったらいいのか、わからなくなってしまう。 ・そこで亡骸を保存する方法が開発されるわけである。心臓以外の内臓を取り去った遺体に香油と植物汁をすりこみ、長い包帯でぐるぐる巻いてしまうのだ。内臓は別の壺におさめられた。こうして亡骸は腐らないまま保存され、それはミイラとよばれている。このミイラはまず木製の棺によこたえられ、その棺は石の棺におさめられ、それから墓室に入れられた。 ・この来世信仰に結びついて名高いのがオシリス神にまつわる物語である。オシリス神はもともと穀物を育てる豊穣の神としてあがめられていた。それとともにエジプトを治める神であり、善政をしき絶大な人気があった。だが、これを妬む弟神セトに謀られて殺害され、遺体はエジプト全土にバラバラにして投げ捨てられた。妻でもある妹神イシスはくまなく探し、身体のひとつひとつを見つけ出して拾い集めてしまう。やがて遺体をつなぎ合わされたオシリスはイシスにより生命の息を吹きこまれて復活する。しかし、それはこの世ではなくあの世であった。こうしてオシリスは冥界の王として永遠に生きつづけることになる。 ・ミイラを包帯でぐるぐる巻きにするのはこの神話に由来するという。というのも、イシスはバラバラの身体をつなぎ合わせた後で、ふたたび身体がバラバラにならないように包帯をほどこしたからである。 アクエンアテンの一神教革命 ・ギリシア人の価値観の基本には、真、善、美がある。 第3章 神々の相克する世界 ― 大文明の周縁で ― バビロン捕囚とユダヤ教の成立 ・辛く苦しい経験をくぐりぬけながら、ユダヤ教が成立し、ユダヤ人の国家が形成される。 ・ユダヤ教は神を天地万物の創造主とする「創世記」やモーセにまつわる伝承などを聖典として編纂していくのだが、それは後に旧約聖書とよばれるようになる。この旧約聖書の成りたちはヘブライ人がイスラエルの民として自覚を深めるところにある。 ・しかし、このとき皮肉にも、ユダヤ教は民族宗教や国家宗教の次元を超えつつあった。 ・このために、民族国家を存続しようとする運動とともに超越神の信仰へと向かう動きも広がりつつあった。双方の勢いは両立しがたく、むしろその間にある溝は深まるばかりであった。 世界観の改革の時代に ・前一千年紀半ばのユーラシア大陸といえば、ギリシア、オリエント、インド、中国が先進文明地域であった。これらの地域においては、宗教や思想が国家や民族という枠のなかだけにとどまらない段階にいたっている。 ・ギリシアではホメロスから自然科学者を経て、ソクラテス、プラトンが現れている。インドではウパニシャッド哲学が出現し、仏陀が稀ている。中国では孔子と老子が生まれ、諸子百家が雷鳴をとどろかせた。 ・なぜこのような類似した現象がほぼ同時代の各地で出てきたのだろうか。 一つは文字の発明から二千年以上を経て、それらの文字が簡素化されながらある程度の広がりをもって普及したことがあげられる。 もう一つ、交易がさかんになり広い範囲での情報が交感されるようになったことも無視できない。 第4章 敬虔な合理主義者たち ― ギリシアの宗教 ― ギリシア人は神話を信じていたか ・前五世紀の叙情詩人ピンダロスは、この世に存在するものとして、神々、英雄、人間という三つの区分を示している。 ・神々は不死なる存在であり、ゼウスを筆頭としたオリュンポス十二神が主たる大神である。 ・ほかにも数多の神々がいたが、民衆にとっては恩恵をあたえる善意の神々と不幸をもたらす悪意の神々が区別されていた。 ・英雄は人間として死すべき運命にあるが、そのきわだった創造活動において歴史に記憶される。 ・死すべき人間の運命ははかないものであるが、死すべきものであっても英雄はその名を永遠に刻みつけることにおいて不滅である。彼らは地域社会のなかでとりわけ半神として人々の信仰をあつめていた。 人間の限界を自覚する ・ギリシア神話に描かれた神々には人間味があふれている。喜怒哀楽をあらわにし、ほかの神々に嫉妬したり、人間を愛したりもする。 ・しかし、だからといって、人間の側から気安く接することができる存在ではなかった。不死なる神々と死すべき人間との間には越えがたい溝があり、まったく異なる別々の種族なのである。 ・だからギリシアの知者たちはくりかえし「汝の限界を自覚せよ」「人間たることに甘んじよ」「汝みずからを知れ」と警告する。 ・人間が己を自覚することの核心はみずからの ・あらかじめ割り当てられたモイラの限界と人生のはかなさ。このことについての意識はギリシア人の念頭から消え去ることはなかった。これでは悲観を通り越し絶望の淵にも立つことになりかねない。 ・しかし、ギリシア人はそうならなかった。というのも、死すべき人間として定められた生き方の枠さえ超えないかぎり、神々は人間を罰することがないのだから。 卓越の徳をもつ英雄たち ・神々が人間に限界を越えることを許さないのであれば、その限界すれすれまで自分を高めることができるはずだ。このようにして卓越という徳がことさら重んじられることになる。 ・その理想が、ヘラクレス、テセウス、アキレウスら数多くの英雄伝説として花開いたのである。 ・卓越という理想への意識がある人々にめばえ、ギリシア人に広く受け容れられていった。それはあの輝かしいギリシア文化の創造にひとかたならぬ役割を果たしたにちがいない。このことは歴史のなかの驚異ではないだろうか。 ・ギリシア人の信仰心は思いのほか深かったことは想像にかたくない。数多くの神々の物語や英雄の伝説が成立し、多種多彩なギリシア神話として語りつがれてきたのも、彼らの信仰心の表われであるかもしれないのだ。 ソクラテス――魂の発見 ・今でこそソクラテス(前四七〇 ― 三九九)はギリシアを代表する哲学者のごとく言われている。しかし、同時代、前五世紀アテナイの人々からすれば、ソクラテスの語ることはまったく理解できなかった。 ・そのころのギリシア人は人間の外にある自然界にしか目がいかなかったからである。その自然界には空も陸も海もあり、それらは人間と切り離しても意味があり法則がある、と考えられていた。 ・そのような雰囲気のなかで、ソクラテスは人間の内面には精神あるいは魂がある、と説くのであった。 ・人生で配慮するに値するのは、富で地位でも名誉でもない。それは精神であり魂であるのだ。 ・ソクラテスにとって、「魂はすべて不死なるもの」ということになる。さらに「魂は人間の形の中に入る前にも、肉体から離れて存在していたのであり、知力を持っていた」ということにもなる。 ・このようなソクラテスの言動は弟子プラトン(前四二七 ― 三四七)によって後世に伝えられている。 ・肉体と物質世界ははかなく朽ちやすい。しかし、魂には「純粋で、永遠で、不死で、同じように有るもの」がある。肉体はわれわれを閉じこめる監獄であるから、死は「魂の肉体からの解放」であるのだ。だから、人生の目的は、来世で神々とともに生きるために、魂を磨き浄化することにある。そのためには「知恵と共に売買されるならば、勇気、節制、正義、知恵を伴ったすべての真実の徳が生ずる」ことが大切である。 第5章 救済者として現れる神 ― ヘレニズムの宗教 ― 文字というメディア ・ギリシア人の世界にアルファベットが導入されたのは、ソクラテスより四百年ほどさかのぼる。 ・楔形文字、ヒエログリフなどと異なり、わずか二十数文字ですべての言葉が表現できるようになった。 ・しかし、つづく数百年の間、読み書き能力のある人間はごく少数の人々にかぎられていた。 ・前六世紀末にはホメロスの叙事詩が書きとめられたが、それは朗誦用のテキストでしかなかった。 ・世間の中心はあくまでも音声言語のメディアであり、文字言語のメディアになれ親しむ人は少なかった。その音声メディアを駆使して青少年を教育しようとしたのがソクラテスであった。 ・人間の精神や魂に注目すれば、知性や認識が重きをなすだろう。人間はまず思考する存在であり、感情も意欲も行動も脇役でしかなくなってしまう。 ・古来、人間はすべての経験をもろもろのイメージを結びつけながら韻律をもつ詩句にのせて語ってきた。ホメロスの口承叙事詩はその大傑作である。韻律をもつことで記憶しやすくもあり、説得しやすくもなるのだ。 ・しかし、皮肉にも、ソクラテスが求めるところは概念による思考を磨きあげることになる。そこから忠実な弟子プラトンは文字メディアの人としてあざやかすぎるほどに変身する。 ・ヘレニズム時代とはこのような読み書き能力をそなえた人々がだんだんと増えつつあった時期なのである。 第6章 普遍神、そして一神教へ ― 神々はローマ帝国にそそぐ ― 普遍神としてのイシス女神 ・多神教社会にあっては多産と豊穣こそが人々の願いであり、さらに再生への希望であった。それらを生みだすものはなによりも女性であった。女性だけが自然の営みで生命を創造することができる。女性原理こそがこの世に共通する根源である。そのことを古代人は熟知していた。 救済宗教・キリスト教の成功 ・キリスト教徒は抑圧された貧者に手を差し出すことによって、圧倒的な大衆を受容する潜在力をもった。 |