
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月08日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
13 |
16/02 |
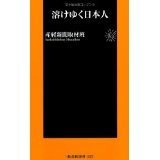 |
溶けゆく日本人 |
産経新聞取材班 |
扶桑社文庫 |
◎ |
第一章 モラル破壊の惨状 第二章 過保護が生む堕落 (二)シュガー社員 ツケを払うのは会社 ・「かわいがる」「甘やかす」の区別ができない親が多い ・「失敗してもねばり強く取り組む力」「チームで働く力」――。経済産業省の研究会が平成十八年に初めて提議した「社会人基礎力」だ。 ・いまや家庭も学校も本当に必要なしつけはすべて先送り。そして、会社がお金を出して研修する。過保護のツケを企業が払わされているのだ。 (七)「安全」という保身 成長阻む逃げの姿勢 ・「何か(気に入らないことが)あったら、お母さんに頼ってしまう。そして文句を言って“解決”する。子供たちにとって悪循環を招かないですかね?」 ・汚いからと子供に触らせない、辛いことはさせたくない――と、子供が歩む道を、つまずかないように先回りし、平たんにならそうとする親や大人の姿がある。 第三章 人間関係の不全 (一)消える「長幼の序」 新人議員、先輩に“ため口” ・「長幼の序」を重んじる心、それは「敬語の使用」や「還暦の祝い」といった数々の日本固有の文化を生み出してきたことを忘れてほしくない」。 ・「長幼の序の崩壊。それは日本文化そのものの危機です」。 (二)みんな平等 指導の手段を失う教育現場 ・「大人がやってもいいことは子供もやっていい」・・・・・・そんな意識の子供が多く、「大人には許されても、子供はまだダメ」というかつての論理は通用しにくくなった。 ・行きすぎた平等主義 『指導』を『支援』と言い換えたり、教壇も取っ払ったりして、教育やしつけに欠かせない上下関係を自ら放棄してしまった。ルールを教えることは軽んじられ、個性や自主性ばかり重視される。 ・文科省所管の「日本青少年研究所」他が平成十六年、四カ国の高校生千人に行った意識調査 ◎「先生に反抗する」ことを「よくない」と回答したのは、 韓国(八一・一%)、中国(六八・七%)、アメリカ(五四・三%)、日本(二五・一%) ◎「(先生に反抗することは)本人の自由」という回答は、 日本(五一・四%)、アメリカ(三〇・一%)、中国(一八・二%)、韓国(一一・四%) (五)乱れる性行動 「間が持たぬ」と相手かえ ・「温かくて頼れる人間関係の心地よさを感じられるように育ててほしい。それを知らないと、ほかの人間関係もうまく築けない」 ・批判が広がる「性行動の乱れ」、潜在・陰湿化する「いじめ」・・・・・それらは親子関係を基本とした「人間関係構築」の習得不全の“象徴的な表れ”であるということを、親は認識したほうがいい。 (六)向き合わぬ親子 親指だけの“会話” ・メールは連絡を密にする効果はあるが、それは決してコミュニケーションを深める効果はない。 ・なぜ気兼ねし合うような“不自然”な親子関係が出来上がるのだろうか。「昔に比べて、親子関係が対等になりつつある」から。 ・「縦」の関係なら踏み込める領域が、「横」のつながりになることで、関係を壊さないような遠慮が生じる。いわば友人関係の延長だ。「家庭内では、ある程度のヒエラルキーがあったほうが子どもに安心感を与える。 ・聞こえのよいことを報告し合うだけの家族は「家族」とはいえかい。けんかをしても、言い争っても縁が切れない、それが親子のいいところ。「語り合う」――親子はそれが大切だ。 (七)衝突避ける家庭 癒やすのは自分だけ ・今の社会は「誰かや何かの犠牲になるのはいけないこと」という共通認識がある。 ・子供がつらそうな顔をしていたら、いち早く気づいて、当たり障りない話をしながら、つらかったことを聞き出して心を癒すのが家族の役割。ところが、そういったエネルギーを使いたがらない親がいる。 ・「がまんするのは精神衛生上よくない」「楽しめるときに楽しもう」と言ってもらえると、気が楽だ。だが、それは容易に「好きなことだけする」「いやなこと、面倒なことはしない」に転換する。 (八)崩れたコミュニティー ご近所よりネット ・現代社会は、自己愛の充足に最大限の価値観を置く「自己愛型社会」と呼ぶ。家や共同体(国)の繁栄を目的とした伝統的価値観が崩壊した結果、唯一の価値が自分になったのだ。 ・先人が道徳や礼儀を奨励したのは、社会に秩序と安定をもたらすための知恵でした。しきたりや礼儀は確かに面倒くさいが、「個人の生きづらさ」が極限までいかないよう歯止めをかける役割も果たしてきた。今、自己愛だけで結びつく便利な(自分に都合の良い)人間関係が広がるが、そこからは「確かな絆」は築けないのです。そこに、この社会のアキレス腱がある。 第四章 快適の代償 (二)“怪物”患者 「治らない」と暴力、暴言 ・人間ドックを受けて異常がなかったから払わないという人もいます。 ・日本は皆保険制度で、誰もが医療を受けられるが、それが逆に「治療は受けて当たり前」の意識につながり、診察に対して感謝の気持ちがなくなっている気がする。 (四」出来合いの食 誰も彼も容易に ・子供は親とともに料理を作ることで料理の楽しさを知り、料理を覚えるのです。さらに自分で料理すると食べ物を大切にするようになります。 (六)姿勢が悪い 三十分間まっすぐ座れず ・背中を丸めた状態は、内臓機能を低下させるうえに、血液の循環を悪くする。とくに右手を多用する環境では、背骨のゆがみの原因にもなる。 ・姿勢を改善するために発達したのが武道や茶道などの“道”でした。 ・軍国教育への反動は「束縛からの自由」「規律からの自由」となり、便利で快適な社会の追求は「子供にできるだけ、気楽な思いをさせること」へとつながっていった。 ・豊かになった社会では、大人が意図的に“鍛える”場を用意しないと、子供が健やかに成長することはできない。 (十一)機器の魔力 便利さが自分を見失わせる ・子供がひきこもりになったとき、「子供の生活環境を快適にしてはだめ」。学校にも行かず、働きにも出ないのであれば、トイレ掃除や洗濯、浴槽掃除などの家事をやらせるようにする。 ・生活に負荷をかけることで、「家にいても家事をしなければだめだし、学校に行くほうが楽だ」と考え、引きこもりから抜け出した子もいます。逆に、親が腫れ物に触るように対処し、快適な状態をつくり上げると、容易に脱出できない。 |