
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年03月07日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
14 |
16/02 |
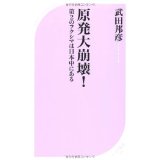 |
原発大崩壊! |
武田邦彦 |
ベスト新書 |
☆ |
第1章 事態は「想定内」で進行中 原発の電源は失われる可能性がある ・今まで作られてきた原子力発電所は、「原子炉の安全」(これは、チェルノブイリのような大きな核爆発を起こさないという意味での「安全」)にばかり目がいって、周辺設備の安全を想定していませんでした。原子炉は震度6や7に耐えても、電源などの周辺施設の耐震強度は低いのです。これは日本中にある、あらゆる原発がそうなっています。 ・また、「原発は事故を起こさない」という安全神話を信じ込んで、「事故を起こした場合、国はどのように対処し、地方自治体はどのように対処し、電力会社はどうするか」という、周辺地域の住民を守るための計画を誰も想定していませんでした。 フクシマを教訓に私たちが考えるべきこと ・「なぜ起きたのか」については、2つの方向について検討する必要があります。 ▼地震をきっかけに、今までどんなことが起こってきたのかを分析し、「なぜ」このような事故が起こったのかの物理的な理由を考えていくこと。 ▼「なぜ」この地震で壊れるような原発をつくることを許してしまったのかという、社会的な構造を考えていくこと。 ・科学的な視点と社会的な視点。理科系と文科系の両方の目で、「なぜ起きたのか」を考えなければならないのです。 原発を襲った地層について考える ・4月7日に東北地方で起きた最大震度6を記録する余震で、青森県の東通原発と六ケ所村の再処理施設の電源が切れ、ディーゼル発電の非常用電源を使うに至ったという事実があります。ディーゼル発電機が動くということは「耐震設計を越えた地震に見舞われた」ということです。 ・気象庁の発表ではなんと震度4(!)でした。またこのときは、停止中の女川原発も通常電源が止まり、予備電源に切り替わりました。 原発が利用している「原子力」とは何か ・失敗から知識や教訓を取り出し、世代を超えて次につなげていける動物種は地球上に人間しか存在しません。この原発事故もごまかさずにしっかりと考えることで人類の次に生かしていく必要があります。 「軽水炉」は暴走しにくいタイプの原子炉 ・核分裂反応が起きれば、原子核が爆発して2つの原子核に別れるのだから、それはどんなに小規模のものでも核爆発です。原発の専門家、関係者は「核爆発」とは言わず、「臨界」と言います。 ・核爆発と言うとあまりに刺激的だからもう少しやわらかい名前で言おう、という考えがそこにはあります。事故が起きても、核爆発事故とは言わず、臨界事故と言う。それが今度の事故の一因にあると思います。 ・いろんな言葉を使い分けているうちに、核分裂反応もなにかマイルドな反応であるかのように、自分たち関係者も錯覚してしまうのでしょう。 ・原子力発電所というものは、核爆発を制御しながら継続的に起こして、そのエネルギーを取り出すというものなのです。 福島原発が爆発する可能性はあるのか? ・チェルノブイリは、日本だと考えられないほどの教育不足や連絡不足、規則違反があり、「人間の操作ミス」で爆発したのです。 ・作業員たちが、大したことはないだろうと勘違いして、ちょっと手を抜いたのですが、手を抜いたというか、制御棒を抜き過ぎた。そうしたら出力が上がり過ぎた。慌てて制御棒を差し込んだのですが、黒鉛炉は一気に制御棒を差し込むと、瞬間的にさらに出力が上がる場合があります。それが起こって大爆発につながってしまいました。 ・黒鉛炉に比べると、軽水炉は暴走時に自動停止する方向に向かうから安全だという理由で日本では軽水炉を選んできました。世界中のほとんどの専門家の意見が「非常時に自分で停まる軽水炉では、チェルノブイリみたいな核爆発は起こらない」となったので、ほとんどの原発が軽水炉になりました。 ・もう原発は大丈夫、爆発することはないと、世界中のほとんどの原子力関係者が考えていました。 ・残念なことにそれが今度の事故の原因にもなった。誰もが爆発(核爆発)すると思っていなかったということが、今度の爆発(水素爆発)につながってしまったのです。 第2章 すべての原発は地震で壊れる 責任逃れをする人間は原発に関係してはいけない ・原子力関係者の多くは、役所、電力会社出身問わず多くが官僚的です。 ・事故の影響が大きいので、原子力関係者は、責任逃れの官僚的態度ではダメなのです。 ・私が宮崎の施設で所長だったとき、場内をときどき見回ったのですが、運転後半年ほど経って変な配管をみつけてしまいました。 ・いち早く適正な配管に直さなければいけないと思い、当時の科学技術庁の担当者に連絡して、事情を話して配管の再工事願いを申し出ました。 ・すると、「国が認可をした施設に再工事はまかりならん」という返事が来ました。 ・「国ではなく私が間違ったということで、私が始末書を書くから配管を直させてくれ」と粘りましたが、「これは国が認可を出したから国が正しいんだ」と、最後まで認めてくれませんでした。 ・交渉が終って担当者に話を聞いたら、「いや、あれは『武田さんが勝手にやってくれ』という意味なのですよ」というようなことを言われました。 ・認可したことは正しいままにしたいから、役所は再工事は認めません。 ・武田が勝手にやったことは知らない。逆に再工事で事故が起こったら、勝手にやった武田さんの責任だから国は関係ない。武田が悪いと言えばいい。これが官僚的発想なのです。 ・普通のサラリーマンタイプの所長だったら、役所と話したあと、「役所が許可出さないならしょうがないな」とそのままにしてしまうかもしれません。 ・現実にも直されるべきものが直されていないというようなことが結構あるのではないかと思います。 ・覚悟の決まった人を発電所の所長にしないといけません。不当なクレームにも官僚的嫌がらせにも非常時の対応にも毅然と対応できる能力が必要だということです。 ・原発規模の施設は、ひとつ間違うとものすごい人数に影響を及ぼしてしまうからです。 ・日本の全ての原発は、人事構造でも非常に危険なのではないかと感じます。 「原子炉至上主義」というガラスの幻想 ・たき火でも発生する「ダイオキシン」は猛毒だとそれています。人類は昔からたき火をしているし、現在ダイオキシンによる患者さんはいない。では、なぜ猛毒とされているのでしょう。「ダイオキシンが猛毒だ」とテレビが言ったからです。 ・ある事実があるのに、その事実と180度正反対のことを言っても、事実よりも言ったことのほうが優先される。伝播力を持つマスコミが言ったり、権力がある国や権威ある学者が言ったから、それはそうなんだろうということになってしまう。それが今の日本の社会です。 ・「原子炉が安全なら原発は大丈夫だ」という思い込みによる奇妙な原子炉安全至上主義と、地震学者にも責任を負わせる仕組みが組み合わされて、それに加えて「想定外の場合住民は著しい被ばくをする」と書いておけばすべての免責が完成する、という、どんなことが起きても責任を取りたくない官僚にとって、素晴らしいシステムのもとですべて日本の原発は動いているわけです。 ・原発も地震では倒れないと国や電力会社が言うから、みんながそう思っている。だから、原発が地震で倒れるなんて言ったって、誰か変な学者が言ってるに過ぎないというふうに受け取られるわけです。 ・人間には、事実よりも信じたいものを信じてしまうという癖があります。 ・「原発は原子炉を守れば安全だ。そもそも原発が壊れるほどの地震は来ない。もし仮に来たら周辺住民の被ばくは仕方ない」というガラスの幻想を国と電力会社と御用学者が組み立てて、その上に巨大技術を乗っけていたというわけです。 ・お金を東電が出して、権威を学者から調達して、国家権力がお墨付きをあたえるという仕掛けです。 偏西風を考えた防災対策が必要 ・地震に対しては新旧全ての原発は危ない。 1つは原子炉の耐震性です。想定外の事態には全部、付近住民が被曝するという構造の設計になっています。 2つ目の危険性は電源系とかその他の付帯設備の耐震強度が一般家庭並みであるということ。 3つ目の問題がいちばん大きな問題なのですが、住民の保護政策がないことです。 ・現在の「30キロ非難区域」というのも悪例ですが、風向きを考えていない避難計画はほとんど意味がありません。どっちに風が吹いているかわからないなら、とりあえず事故が起きたら80キロ圏外に出るというアメリカのやり方は意味があります。 ・名古屋市は敦賀原発に最も注意を払う必要が出てきますが、北陸電力と関西電力が「風向きにまでは責任を持てません」と言ったら、今度は質問の対象は政府になるでしょう。 ・被ばく防止を担当する国の機関は、多分、現在はないのではないかと思います。強いて言えば厚生労働省でしょうか。 ・北陸電力と関西電力に「敦賀原発に吹く風が四季ごとにどうなっているか教えてくれ」と言ったら、「私たちにはそういう義務はないんです」と現状では言われそうです。 ・あなたのところから飛んでくる放射性物質で私たちは傷つく可能性があるのだから、自治体として対策を立てるためにも、どうしても教えてください」と押し込んだらどうでしょう。 「法律がないからやらない。原発の事故に対して、自治体の領域は関係ない」と頑張るのじゃないかという気がします。 第3章 私たちはどうすればいいのか 自治体は原発に対してどのように向き合えばいいか ・原子力発電所は、放射能漏れで被ばくするリスクのある周辺住民が申し出る「条件」を満たすことができなければ、運転(建設)してはいけない。 ・原子力安全・保安院はあくまで法律やルールに沿って、それが進められているかを確認するだけの事務的なことしかしません。自分たちの判断で、安全かどうかをチェックするつもりもないし、その能力もありません。 ・だったら、地方分権ではありませんが、被ばくする住民を多く抱える地方自治体が「安全」ということを厳しく原発と電力会社に迫る必要があります。 原発(政府)は周辺住民にどのような対策と責任をとるのか ・基準を超えたアクシデントが起きた場合の対策と責任の所在を明確にすべきだ。 ・放射能漏れが起きた場合、原子力発電所(政府)は周辺住民が被ばくしないためにはどのような対策をとるのか。避難シミュレーションも合わせて提示できなくては、運転(建設)してはいけない。 ・日本の原子力政策は、施設から放射能漏れが起きた場合、「安全対策」についてなんの決定権もない周辺住民が「著しい被ばくをする」というリスクを被るという非常に不公平な仕組みになっています。 ・東京電力という一企業が引き起こした事故です。社会一般の常識ならば、東京電力側が迅速に車両を用意し、避難を誘導し、迷惑がかからないような滞在先を用意するのが筋です。 ・原子力発電所が最低限用意しておくべきもの 1.住民を避難させるための緊急車両・オートバイ。移住先の住宅の手当、仕事の斡旋 2.放射能漏れが起きたら周辺住民に配布するヨウ素剤 3.季節や風向きによって放射能汚染物質がどのように飛散するのかを示したハザードマップ 4.放射能漏れの程度や周辺の環境に及ぼすシミュレーションの公開 ・これらに加えて、放射能漏れをシミュレーションした避難訓練を定期的に行うこと。 ・緊急事態には速やかに避難先となる宿泊施設などをあらかじめ準備する必要があることも当然です。 ・住民を被ばくの危険から守るためにありとあらゆる備えをする、というのは原子力発電所を有する電力会社の責任として、ごく当たり前のことだ。 ・「福島第一原発でもし爆発が起きたら、逃げる時間があるでしょうか?」 一般市民の安全というのはこういうところが肝心なのです。 ・ところが、日本にはその時間を計算する人もいなければ、そのような避難計画を立てる人もいない。本来であれば、原子力発電所を持つ電力会社が進んで計算をしなくてはいけないことなのです。 ・「事故が起きて放射能漏れが起きました。ご迷惑をおかけしていますが、そのうち政府からいろいろ避難指示とかあるでしょうから、それに従ってください」 このような態度でただ頭を下げているだけという方が、企業としてはよほどおかしくないでしょうか。 原発は絶対に安全だから、備えなど必要ないという理屈 ・飛行機というものは、公共交通機関ということで国の指示のもと「安全」を厳しく求められていますが、残念なことに非常に稀に事故が起きてしまいます。そこで、緊急脱出用の酸素マスクやライフジャケットを備えることが法律によって義務づけられ、不時着時の姿勢や緊急脱出経路の説明を客室乗務員がしなくてはいけません。 ・航空会社のスタンスをわかりやすく言うと、 事故は絶対に起こしてはいけない。しかし、事故が起きることもあるので、乗客の命を守るためにあらゆる備えをしなくてはいけない ・ところが、原子力発電所のスタンスは、 事故は絶対に起こしてはいけない。しかし、事故が起きることもあるので、住民は著しく被ばくする ・被ばくする、マル、で終わってしまい、「備え」が一切抜け落ちているのです。 ・この根底には、「原発は絶対に安全だ」という硬直した考えがあり、備えなど必要ないという理屈があります。 ・不測の事態が起きたら、客室乗務員は乗客の安全を守るためにあらゆることをします。 ・ところが原子力発電所の場合、放射能漏れという不測の事態が起きても、周辺住民の安全を守るための備えもなければ、訓練もありません。 第4章 原子力・エネルギー政策はどこへ向かうのか 政府がデマや風評の発信元になっている ・政府がまずすべきは「事実」をしっかりと国民に伝え、希望的観測や「福島の人たちが可哀想だ」という感情によって生み出されるデマや風評を極力抑えることです。 ・政府には正確な情報を流して、自国民の生命・財産を守る義務があります。「原発は安全だ」とか「被害はたいしたことない」などという感情や希望的観測ではなく、科学的事実を直視した正確な情報を流さなくてはいけないのです。 汚染を拡げないために直ちにすべきこと ・最善の方法とは原発の近くに処理工場をつくってしまうことです。そこで汚染物質をすべて処理する。 ・未曾有の災害を乗り越えるために日本人が求められているのは、科学的合理性と事実を見つめるという勇気です。 「原子炉を守る」から「住民を守る」政策へ ・その次に政府が行うことは、これまでの「原子炉を守る」という原子炉至上主義を改めて、「住民を守る」という住民至上主義に徹底的に見直すことでしょう。 ・原子炉(圧力容器)は格納容器、建屋という順番で覆われていて、電力会社はこれを「三重防御」と呼んでいます。 ・この「防御」は私たちを被ばくのリスクから守るのではなく、原子炉を守るためのものなのです。 原発はトイレのないマンション ・現在、日本には「核燃料廃棄物の最終的な貯蔵所」というものが存在しません。原発が「トイレのないマンション」と言われるのはこのためです。 ・「使用済み核燃料」が搬入されている青森県六ケ所村の施設も「高レベル放射性廃棄物中間処理施設」で、建前としては「最終処理じゃありません」というスタンスです。 ・なぜこういうことになるのかというと、日本全国の自治体が「核燃料廃棄物」が危険だとして受け入れを拒否しているからです。 ・原発も危険なのだから、その廃棄物だって危ないに決まっている。「住民を被ばくのリスクから守る」のを最優先にするというのだから、当たり前の対応じゃないか。 きっと多くの人がそのように思われるのでしょうが、私から言わせれば、これは全くナンセンスな話です。なぜなら「核燃料廃棄物貯蔵所」は原子力発電所とは全く次元の違う施設であって安全だからです。 「核燃料廃棄物貯蔵所」は安全だ ・「高レベル放射性廃棄物」は、基本的には「すでに冷えた放射性物質」なのです。 燃えカスなので水をかけなくても温度は上がりません。何もしなくていいし、どんな最悪な事態となっても、今の福島第一原発から放出される放射線量の数億万分の一以下です。 ・「高レベル」や「低レベル」の安全判断はあくまで言葉の響きにひっぱられたイメージによって左右されているだけで、科学的根拠に基づいたものではないのです。 ・科学よりイメージ。これが「日本の原発は安全」という全く根拠のない神話をつくりだしてきた遠因ではないか。 ・日本の原子力政策の根本を見直すには、まずこのような「印象操作」を止めることが重要ではないでしょうか。 「安全神話」のもうひとりの共犯者 ・原子力が科学よりもイメージが優先されるようになってしまった「犯人」は、もちろん「原発は安全です」と根拠なく繰り返してきた国や電力会社ですが、実はもうひとり「共犯者」がいます。 それは、なんとも皮肉な話ではありますが、「原発反対運動家」なのです。 ・彼らは、原子力施設の構造的な欠陥や安全対策の不備を攻撃することなく、「とにかく危険だ」「角砂糖1個ほどのプルトニウムで日本が滅びる」という感情や恐怖をメインにして運動を進めてきてしまいました。その結果、日本の原発の根本的な問題を指摘することができませんでした。 ・そこでさらに事態を悪化させたのは、攻撃の矛先を「放射性廃棄物」に向けてしまったことです。 ・「放射性廃棄物」は、原発に比べたら何千倍も安全にもかかわらず、攻撃対象として手軽なため全国で放射性廃棄物貯蔵所ができなくなりました。 ・原発は「トイレのないマンション」などとたとえられますが、これは反対派のみなさんが「トイレをつくるな」と運動してきたからなのです。 ・これは原発の安全性について何の関係もない運動でした。彼らが安全な施設を「危険だ」「被ばくする」と騒いでいる間に、役人と電力会社と御用学者で「周辺住民不在」の原子力政策を粛々と進めていたというわけです。 ・安全なものを危険だと思い込んでいると、本当に危険なものがわからなくなる。科学的合理性よりも「感情」が先走ってしまったのが、日本の原発反対運動なのです。 ・彼らは「電気より命が大事です」というプラカードを掲げていました。もうそうなってくると宗教観というか人生観なので、これでは「安全」の議論はできません。 ・この空気は何かに似ているなとよくよく考えたら、「とにかく原発は安全だ」と言い続け、「放射能漏れ事故」からひたすら目を背けてきた政府や原子力委員会の空気にそっくりでした。 ・日本に原発ができて40年、気がつけば推進派も反対派も合わせ鏡のようになってしまっていたのです。 ・結論としては、これは原子力が持つ「架空性」の賜物ではないかということです。 ・直感での理解を越えた「イメージの世界」というのは宗教や迷信と同じです。そこに科学や合理性は通用しません。「神はいるか」という議論と同じく、「原発は安全か、危険か」という極論にしかならず、結果として、とんでもないウソや、とんでもないデタラメがまかり通るのではないでしょうか。 ・原子力は人類の手に負えないエネルギーだという人がいますが、手に負えないのではなく、「想像力を超えてしまっているエネルギー」というところが正確だと思います。 エネルギー問題はウソがまかり通る ・我が国のエネルギー政策を考えていく上での重要なポイント (1) 良質の石油や石炭はおよそ1000年分はある (2) 太陽光・風力・水力などの「自然エネルギー」は自然を破壊する (3) 日本の原発はすべて危険だが、日本には「安全な原発」をつくる技術はある ・「原発は安全だ」というのはウソだらけですが、実はエネルギーに関しても同じ構造があって、とんでもないウソの上にさらにウソを重ねて、国民をペテンにかけているのです。 ・その代表的なものが、「石油石炭の化石燃料はあと40年で枯渇する」というものと「自然エネルギーを利用するのは地球に優しい」という「常識」です。 ・原発事故は不幸中の幸いで、「原発が安全だ」というウソが取っ払われました。ただ、この2つのウソも取っ払わないことには、日本のエネルギー行政に未来はありません。 「石油は40年で枯渇する」というウソ 1970年代も「石油は40年で枯渇する」と言われていた 2010年にも「石油は40年で枯渇する」と言われている ・「40年」というのは油田や鉱山を発見者が買い取る埋蔵量の目安なのです。 探査をするには掘らなきゃいけない。そこで資源が見つかったら誰かが欲しがります。だから見つけた人は横取りされないように土地を買わなくてはいけません。つまり、地下資源の調査とは「土地買収」とワンセットになっているのです。 ・この原則が地下資源の調査に「40年」という限界を設けました。手当たり次第に石油を見つけてしまうと、それだけ「土地買収費用」がかさむからです。 ・そもそも、尖閣諸島の下に1500億バレルの石油があるといわれています。日本の石油の年間消費量が15億バレルだからここだけでも100年分あります。 40年で枯渇するほど希少な資源が、奇跡的に尖閣諸島にあったのでしょうか。確率的に言ってもそんなわけはありません。世界にはまだ油田が山ほどある。 ・国連だってどんなに少なく見ても1000億バレルあるとしているので、70年分にあたります。それがなぜ「40年分しかない」ということにしなくてはいけないのかというと、それは投資側の都合なのです。 ・70年分あるということにしたら、尖閣諸島のような「未来の資源」を石油メジャーが買って寝かせておかなくてはいけません。今から70年先まで土地を所有し続けるなんて、あまりにも投資効率が悪い。そこで、「40年ぐらいなら先に土地を買っても資源で儲けられる」と試算し、「40年で枯渇」ということにしているのです。 ・石油会社の社長の身になってみれば、200年先に生産できる石油を掘り当てて、そこを買収しても、 1.200年分の金利がかかり、売り上げか生じるのは200年後 2.石油はいくらでもあるということになって、値段が下がる というこことですから、直ちに社長を解任されるでしょう。そんなことを社長がするはずはありません。 ・地下資源は常にこのような状態にあります。石油だろうが石炭だろうが鉄鉱石だろうが、地下資源は面白いように30年から50年で枯渇ということになっている。 ・化石燃料が40年で枯渇するというのは資源の話ではなく、経済理論の話なのです。日本の資源エネルギーを考えるには、このようなペテンに惑わされず、石油・石炭は十分にあることを認めることからはじめるべきなのです。 「自然エネルギーは地球に優しい」のウソ ・「太陽光・風力・水力という自然エネルギーを使うのは地球に優しい」という話ですが、これもデタラメで実はまったく優しくありません。 ・これも原子力同様、科学よりもイメージが先行してしまった悪しき例といえましょう。 ・「自然エネルギー」とは何か。 大原則ですが、人間というのはエネルギーを生み出すことはできません。石油も石炭もウランもすべて自然界にもともと存在するエネルギー源、いわば自然エネルギーです。 ・理解されていない大事なことがもうひとつあります。風力や水力をはじめとする自然エネルギーといわれているものはもともと「太陽エネルギー」であるということです。 ・「風力」 風というのは高い気圧から低い気圧のところに流れます。では、このような気圧のばらつきはなぜ起こるのかというと、これは場所によって太陽光の照射され方が異なることで生まれる。 つまりは太陽エネルギーの偏在によって引き起こされる現象が「風」なのです。 ・「風はムダには吹いていないよ」 風が吹けば桶屋が儲かるという言葉がありますが、すべての現象には因果関係があります。特に自然界ならばなおさらです。 ・風が吹いているから、花粉が移動して果実ができます。風が吹くから葉の表面からの蒸散がさかんになり木々の生長が促進される。私たちの身の回りでいえば、風が吹くから洗濯物だって乾くのです。 ・その風のエネルギーを100として、風力発電で50のエネルギーを使って電力に変えるとしましょう。すると風力発電所の風下にある場所では風は50%弱くなります。 ・「風から電気を取ると風が弱まるなんて、ウソだ」 今から10年ほど前には多くの人が私に文句を言いましたが、最近では風力発電所周辺では、風邪が弱くなったというのは常識となりました。これもイメージではなく「エネルギー保存の法則」という科学に照らし合わせばすぐにわかることです。 ・つまり、太陽エネルギーを使うということは、それでうまく回っていた太陽エネルギーの循環から奪うわけです。これで自然が破壊されないなんて、そんな虫のいい話はありません。 「水力発電は環境を破壊しない」のウソ ・水力も代表的な「太陽エネルギー」です。 ・まず太陽が海水面を照らす。海水が蒸発し、水蒸気が上空にあがって冷えて雲になる。その雲が山にぶつかって雨や雪となり、やがて河川になるわけです。 ・つまり、河が上流から下流に流れるエネルギー(高さのエネルギー)というのは太陽が生み出している。 ・「水力発電」 河川の流れでタービンで発電するというもので、環境破壊をしない理想的な自然エネルギーとされていますが、とんでもありません。 ・河の流れを100の太陽エネルギーとしましょう。そこにダムを建設して川の流れをせき止めて電力をつくる。できる電力のエネルギーを20としますと、電力を作るときに損失するエネルギーがおよそ30ですから、川は50のエネルギーを失います。ダムができる前の川のエネルギーが50%もダウンします。 ・どういう結果を招くかということをなかなか理解してもらうのは骨が折れますが、簡単に言えば水が淀むのです。 淀んだ河はやがて水が腐ります。そこに棲む生物にとってみれば大問題で、水質が変わったことで死滅する生物も出てくるでしょう。 ・具体的に言えば魚と樹木です。河の流れにって新しい水が来ることで、魚や樹木は生きることができるのです。ほかにも、河底の砂利が流れるのでセメントができる。河川のエネルギーは無限ではなく、必要としている者たちが有効活用しているのです。 ・これに加えて問題は電力の「生産効率」です。電気というのはエネルギー源のだいたい3分の1しかできません。発電はどんなものでも3分の1は電気になりますが、3分の2は「熱」になります。 ・だから原子力では、熱くなった冷却水を海にどんどん流さなくてはいけないのです。 ・実はこれは水力発電も然りで、奪った水力の3分の1で発電し、残りの3分の2は「熱」となってしまいます。だから、正確には水力発電所の下流は温かい水が淀んでゆっくり流れるということです。 ・それで「脱ダム宣言」が出ました。 ・日本は過去に多くのダムを建設しており、このような自然破壊は身をもって経験しました。結果として「実験」を繰り返すことになった日本では、全電力の8%程度を水力発電所にあてるのがふさわしいという結論をだしています。 生物を死に追いやる自然エネルギーの正体 ・スウェーデンは全電力の50%が水力発電ですが、忘れていけないのは人口密度が日本の17分の1ということです。一人の人間が使える「自然エネルギー」が17倍ということですから、自然破壊をしても被害は17分の1。水力発電を日本の6倍ぐらい進めたところでなんの問題もないのです。 ・自然の破壊というのは、自然エネルギーと人間の生活で消費されるエネルギーのバランスが崩れたときに引き起こされます。 日本でも江戸時代の前まではエネルギーと生活のバランスが取れていました。 ・このバランスを著しく崩すのが、実は「自然エネルギー」でもあるのです。 ・例えば、佐世保市で使用する電力の8%を太陽光発電でまかなおうとして、これを推進すると、市周辺の野生生物が大量に死にます。 ・太陽光発電というのはすべての生物や植物に平等に降り注ぐ太陽光を奪っているのです。 ・当たり前の話ですが、ソーラーパネルの下は「日陰」になります。人間も含めて生物は太陽がなければ生きていけません。膨大な数のソーラーパネルを敷きつめれば、膨大な土地が太陽を奪われた「死の世界」になるのは自明の理なのです。 ・そもそも、ソーラーパネルが置ける平地でなおかつ南向きなんて条件のいいところは、だいたい人間が家を建てていたり、豊かな自然がある。つまり、多くの野生生物が生きている。生態系に影響を与える場所ということです。 ・環境に影響を最低限に抑える空地だけではなく、民家の屋根はもちろん、道路や線路の脇、ありとあらゆるスペースにソーラーパネルを敷きつめて最大で全電力の8%。 ・少ない電力とひきかえに生物を死に追いやる。これが「地球に優しいエネルギー」の正体なのです。 私が「安全な原発」を主張してきた理由 ・どうしても「自然エネルギー」を使いたいのならば、 まず、山を削って埋め立てる。沿岸部も埋め立てる。つまり、平地を広げていく。太陽光発電、水力発電しかり自然エネルギーを利用するには平地が必要不可欠なのです。 ・日本は森林面積が66%で世界3位。これはどういうことかというと、自然エネルギーに利用できない山地だらけで平地が異常に少ないということです。つまり、日本というのは「自然エネルギー」を使うには不適切な国なのです。 ・現在の人口密度の3分の1くらいまで少なくなれば、北欧のような自然接続社会ができるはずです。 ・国土面積と国民総生産で言うと、アメリカと日本は40倍、ドイツとは5倍の開きがあります。「土地の広さ」に関係ある「自然エネルギー」のものに手を出しても欧米に勝てないというのは、農業でもう懲りているはずです。 ・逆に言えば、この土俵に乗らなかったので、日本の電力事業が繁栄してきました。原子力発電や石油発電というのは面積が小さくても大きなエネルギーを確保できる。そういう意味では、非常に日本向きなのです。 ・私たちがとるべきエネルギー政策 (1)良質の石油や石炭はおよそ1000年分はあるが、日本にはないので外国から買わなくてはいけない (2)太陽光・風力・水力は自然破壊とのバランスで今の技術では全電力の10%程度しか賄えない (3)日本の原発はすべて危険だが、日本には「安全な原発」をつくる技術はある ・こう見てみると、自前で化石燃料を供給できない日本が自然を破壊することなく安定した電気を生み出していくというのはやはり「安全な原発」をつくっていくしかないことがわかります。 これからの「エネルギー改革三原則」 ・政府やすべての日本人がエネルギーについて考えていくための心得というか、精神の大原則。これまでの日本のエネルギー政策に欠けている視点です。 (1)常に科学的に合理的に判断をする (2)感情に流されず、勇気を持って現象をきちんと正面から見つめる (3)ウソをつかない ・これらができなかったため、近隣住民よりも原子炉が大事というような原子力政策を進めたり、自然を破壊する「自然エネルギー」を「地球に優しい」と喧伝してみたり、と日本の資源エネルギー政策はおかしな方向へ舵をきってしまったと言っても過言ではありません。 ・原発もダメ、自然エネルギーも環境破壊するとなると、私は石炭発電がもっとも有望と思っています。 ひとつ目の理由は「合理的」だからです。 ・石油産地が偏っていることもあり、投機マネーの流入で高騰したりしますが、それに比べたら石炭は世界にまんべんなくあります。 ・さらに日本とは地理的に近いオーストラリアが最適だと私は思います。 ・クイーンズランド州のボウエン盆地には1000年分の埋蔵量があると言われています。 ・なによりオーストラリアには自国に石炭発電も少なく、石炭採掘の技術もありません。つまり、技術と資金のある日本と資源のあるオーストラリアが話をまとめて安定供給する仕組みをつくればいいのです。 ・そしてもうひとつ「科学的」にも石炭発電はメリットがあります。CO2が出るので温暖化が進んで、食物がより穫れるからです。 ・実はCO2が出て温暖化が急激に進んでいるというのは真っ赤なウソです。CO2は地球の誕生のときは大気中に90%あったのです。 ・科学的かつ合理的に判断をすれば、日本の現実的なプランとしては、石油石炭の火力発電を推進するということなのです。 ・その間に、今ある原子力発電所を安全にする。それをやっているうちにいろいろな知恵も出てくるから、もう一度日本のエネルギー政策を根本的に見直すということでしょう。 ・間違っても、自然エネルギーなんか進めたらダメですし、バイオ燃料なんかデタラメなものに手を出したら日本は取り返しのつかない衰退がはじまってしまいます。 本気で低エネルギー社会を作るには? ・「感情に流されず、勇気を持って現象をきちんと正面から見つめる」というのが実は一番難しい。 ・人間というのは感情に流される生き物です。だからこそ、科学的でも合理的でもない行動を取るし、それが美徳でもありますし、問題でもあります。 ・福島第一原発事故の後、エネルギーが少なくてすむ社会に変えようということで芸能人やタレントのみなさんがAC(公共広告機構)でこのように訴えました。 「使わないコンセントは抜いておこう」 「無駄な通話やメールは控えましょう」 ・被災地のために自分ができる範囲のことをしようという精神は正しいし、これぞ日本人の美徳だと思うのですが、残念ながらこれを徹底したところで、せいぜい1,2割の削減。みんなの心がけでこれだけ減りましたという美談というか、自己満足にはなりますが、「低エネルギー社会」はつくれません。 ・「コンビニの深夜営業は必要か」「パチンコの電気はムダだ」などと問題視している政治家がいました。電気が煌々とついているのでそう思ったのでしょうが、実は深夜コンビニやゲームとしてのパチンコは電気効率は非常にいい。 ・家の冷蔵庫が深夜に消費している電気屋テレビを使ったゲーム機の方がはるかに多いのです。 ・本気で低エネルギー社会を考えるのなら、「コンセントを抜こう」とか「無駄を省こう」とかではなく、「田畑では灌漑用水はポンプで汲み上げるんじゃなくて計画的に高い土地から落とす」とか、「高速道路を真っ直ぐにする」とか、社会の構造を変えなくてはいけないということです。 ・感情論としては「コンビニは深夜営業をやめろ」というのが先にたちますが、これは科学的でも合理的でもありませんし、たいして省エネにならないという「現実」があります。まず、これに向き合うことが大切です。 ・日本人は特にこの「現実と向き合う」ということが苦手です。 ・現実を直視するというのは精神力がいります。これをもつことができるか否かが、大げさではなく日本人の命運を分けると私は考えています。 原発の責任者は戦艦大和の艦長クラスでないと務まらない ・国民の安全よりも私利私欲を優先してウソをつく――。このような人が多いのは、論理的に考えれば、やはり日本の戦後教育が間違っていたと言わざるを得ません。それはつまり現在の「教育基本法」です。 ・要するに「個人が幸せならばそれでいい」という基本精神が書かれています。家族も社会もすべて抜かして、自分の幸せを追求する。人間にはその権利があるのだから、そのように教育しなさいというのです。 ・これでは自分のためには平気でウソをつき、事故が起きても周辺住民のことなど知るかという人間ができあがるのも無理はありません。 ・私はひとつの案として、戦前の教育指針である「教育勅語」の復活を挙げたいともいます。 ・戦前の軍部がこれを悪用したため、なにやら教育勅語が悪いような印象になってしまいましたが、教育理論としては右も左もありません。 ・しかも、「教育勅語」には「教育基本法」に欠けているものがちゃんと含まれています。 それは「個人と公」という思想。個人がおり、家庭があって、友人や地域社会があって国がある。こういう教育だと、「社会のために尽くそう」「国のために全力を注ごう」という人が多くなります。 ・「教育基本法」で育った「自分と家族さえ幸せならいい」という人達が大多数でもいいのですが、やはり2割ぐらいは「社会のため」という意識が強い人がいてくれないと、原子力施設のようなものは制御できないと思うのです。 ・つまり、フランスに原発視察に行くといいながら高級ワインばかり飲んでいる「御用学者」とか、霞が関で安全よりも法律どおりにつくられているかのチェックしかしない官僚が原子力政策を進めるのではなく、「公」に自分を捧げられる人たちにやってもらうのです。 ・もっとわかりやすく言うと、原子力発電所の責任者は、大東亜戦争の最初の海戦、マレー沖海戦のときに沈んだ大英帝国の旗艦プリンスオブウェールズや日本が世界に誇った戦艦大和の艦長のような人でないと務まらないということです。 ・艦が沈む時、士官に「艦長、そろそろ退避してください」と言われても彼らの多くは「いや、私は最後まで艦と共にある」と乗員たちを見送ったのです。 ・周辺住民が被ばくしても知らん顔で、会見だけしているような電力会社や原子力安全・保安院の人たちにこの「覚悟」を求めるのはそもそも無理でしょうが、原子力発電所を動かすというのは、実はそれぐらいの責任があることなのです。 後書き ・ここ20年来、日本社会は「環境、環境」を連呼していました。特にNHKなどは数時間おきに「明日のエコでは間に合わない」と連呼していました。 ・その一方で、NHKのCO2の増加率は1990年比で80%も増えていたのです。 NHKだけが「言っていることとやっていることが違う」のではなく、極端に言うと日本の指導層の人の多くが、言動不一致だったのです。 ・環境問題を研究していた私は、「補助金をもらうための環境問題」はやがて破綻し、私たちの子供たちに災厄をもたらすことになるだろう、環境とは将来を見据えたことなので、もっと誠実に正直でなければならないと感じていました。 ・それが、原発事故のような形で表面化するとは思っていませんでしたが、起こってみるとまさに「誠実さを失った日本社会の必然的結果」とも言えます。 ・「原発は日本に必要だから、原発は安全だ」という発言に見られるように、東電の甘さを全くチェックしていなかったというお役所の無責任体質が第二原因でした。 ・いまこそ私たちは事実を見る勇気、科学を尊重する意識、そしてウソをつかない誠実さを取り戻して、明日の子供たちのために「額に汗して」社会に貢献する行動を取り戻したいと思います。 |