
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月16日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
15 |
16/02 |
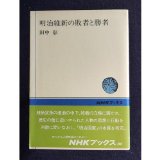 |
明治維新の敗者と勝者 |
田中 彰 |
NHKブックス |
◎ |
第一章 明治維新の政治と思想 尊攘・討幕運動の思想と論理 ・明治二十四~五年(一八九一~九二)刊の竹越与三郎の『新日本史』はいう。 「幾百年間英雄の割拠、二百年間の封建制度は、日本を分割して、幾百の小国たらしめ、小国をして互ひに藩屏関所を据えて、相 「世直し」と「王政復古」と ・竹越の『新日本史』は、 尊王や攘夷や、佐幕や討幕や、はたまた公武合体などは、「唯だ是れ此の大変革の波濤の上に浮かびたる雑木浮草に過ぎず」という。 「是等政治的戦争の闘はるゝ間に、社会の根底に於ては、人知らぬ間に、絶大の潮流は混々として流れつゝありし也」と彼はみるからである。 ・「絶大の潮流」とは何か。それは封建制度を内から崩壊させる「民権の勢力」であり、それを彼は「町村都邑の庄屋名主中」の台頭のなかに見いだしていた。 ・この「乱世的革命」であり、「社会的革命」たる維新の変革の基底にある思想が、「世直し」の思想であり、その思想を形成する階級矛盾は、「世直し状況」ともよばれる。この「世直し状況」は慶応二年(一八六六)の百姓一揆・打ちこわしでひとつのピークに達する。 ・その背後には、「農民(民衆)の『福・禄・寿』の人生観に起因する、『平等』・『生存』・『自由』の要求」があり、それあるがゆえに、農民(民衆)は「不服従の行動」をとりえた。 ・慶応三年(一八六七)の「ええじゃないか」もそうした理想世、つまり「ミロクの世」=「世直し」の到来を幻想した民衆が、幕府倒壊の決定的瞬間に集団乱舞のかたちをとって、みずからの期待と予感と不安を噴出させた姿だとみてよい。 維新の政治と思想 ・維新の政治は確かに民衆の「世直し」のエネルギーを組み込むことによって展開した。しかし、「王政復古」の思想による新しい権力の構築は、民衆の「世直し」の志向とはめざすところを異にしていた。その維新の政治と思想の実態を見抜いた民衆は、再び自己の論理の組み直しのなかで、激しい抵抗運動を試みはじめたのである。 ・それはある時は「血税」一揆や地租改正反対一揆の高揚となり、ある時は士族反乱と不即不離の関係を保った。そして、やがて「維新の精神」を国会開設要求と重ね合わせて、自由民権運動の奔流で明治政府の足もとをゆさぶっていくのである。 ・維新の政治と思想とは、幕末維新の激動期、「外から」の圧力のなかで、明治天皇制国家の創出とその支配の思想をうち出す「上から」の力と、その支配の思想と論理を逆に自己の論理に組み込みつつ、民衆を真の主体たらしめる政治をつくり出そうとする「下から」の力との、激しいたたかいと論理の相克にほかならなかった、といえるのである。 第二章 吉田松陰とその人間像 2 吉田松陰と女囚高須久子 松陰と久子と明治維新と ・松陰には、すでにしいたげられる者、差別されるものを、同じ人間とみるヒューマニズムがあった。 ・アイヌの人びとを同じ人間とみて奸商を批判し、被差別部落民へのわけへだてのない発想に立っていた松陰であった。。 3 吉田松陰の変遷 『身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし大和魂』 第三章 維新のなかの敗者と勝者 3 奇兵隊の人びととその末路 ⅱ 尊攘志士・高杉晋作 高杉晋作の上海行き ・長崎を出帆して上海に向かったのは文久二年(一八六二)四月二十九日である。 ・高杉が上海についたのは五月六日。 その彼が上海をたってふたたび長崎へと向かうのが七月六日なのだが、このまる二ヵ月のあいだに上海の地で高杉がみたものは、半植民地化の危機に直面した中国の姿であった。 ・きょうの中国があすの日本の姿なのかもしれないという危機感が、ひしひしと彼らにはせまっていたのである。高杉が上海から長崎に帰り着くや、独断でオランダの汽船購入を約束したのもそのためであった。 御殿山公使館焼き討ち ・高杉はかつて安政五年(一八五八)に、吉田松陰あての手紙に「人びとはわたくしの議論をさして鎖国論といっておりますけれども、そうではないのです。わたくしはただ安易に開国するのを恐れるのみです。」といっている。 ・半植民地化した中国、中国のなかの異国ともいえる上海の地を、その目でつぶさに見てきた彼の心には、いっそう安易に開国すればこと足りるとする開国論には、なんとしても 奇兵隊創設 ・中国の地、上海で目のあたりにみた民族的危機が、いま馬関海峡の現実となろうとしたとき、高杉の危機感をゆさぶって彼の決断と実行力が伝統的な幕藩体制の枠を一歩つき破ったとしても不思議ではあるまい。 ・そして、一たび破られたその枠は、旧い体制をのりこえていく。奇兵隊を皮切りにつぎつぎと新しい軍事力が編成され、数多くの諸隊や農(商)兵隊が誕生していったのである。 ⅲ 諸隊の苦悶 遊撃軍 ・吉田稔麿によって、身分外の身分の部落民であろうとも、「つよいものをえらび、軍の御用に立候様」と、軍事力登用の口火が切られたのである。 ・藩が部落民の軍事登用令を出したのは、その三日後の文久三年七月十日、一村およそ百軒に五人という割り合いではあったが、帯刀胴服着用を許して、「 ・部落民の「解放」が、こうした長州藩諸隊という新軍事力編成の過程で第一歩がふみ出されていることは見落としてはならない。そこには明治四年(一八七一)の穢多・非人の称を廃止した、いわゆる解放令の前提が形成されつつあった、といえる。 第四章 朝廷と幕府のなかの人びと 4 勝海舟 ・慶応四年(一八六八)三月十五日は、江戸城総攻撃の予定日だった。 ・すでに予備折衝は旗本山岡鉄太郎(鉄舟)によってなされていた。 ・この会談で、勝は西郷に向かい、いまインドや中国の二の舞をふみ、「皇国の首府」たる江戸で一戦を交え、「国民」を殺すような事態をひきおこすことは、一徳川氏という「私」のためにもならず、徳川慶喜自身もけっして考えているところではないから、どうか公平な処置によって、「皇国化育の正しき」ことを全国および海外におよぼしてほしい、と述べた。そうすれば、「国信一洗、和信益々固からむ」というのである。これに対し、西郷は、これは自分ではきめかねるので、明日出立して総督府に伺いを立てる。よって明十五日の江戸城総攻撃は延引の命を下そう、といったというのである。 ・だが、この会談にはさらに内幕がある。当時、旧幕府支援のフランス公使ロッシュに対抗して薩長側を支持していたイギリス公使パークスは、江戸が戦火にさらされることによって横浜貿易に影響がおよぶことを極度におそれていた。だから彼は、新政府軍の江戸城総攻撃には反対だった。 ・このパークスの反対意向を知るや、西郷は心中ひそかに江戸城攻撃の中止を決意して勝との会談に臨んだ。 ・一方、勝は西郷よりさきにパークスの意向をキャッチしていた。いや、知っていたがゆえに、パークスの影響力を利用して新政府軍の強硬方針をおさえようとしたのである。 ・それだけではない。この勝、西郷会談の背景には、二月中旬以後、関東とその周辺におこっていた一揆、打ちこわしの高まりがあった。江戸の戦乱によってこれがいちだんと激化することを、勝も西郷もいちばんおそれていた。 ・新政府側にしても、この一揆、打ちこわしの高まりや、イギリスの反対をおしきってまで江戸城総攻撃を強行する自信はなかったから、総攻撃が中止され、慶喜をはじめとする徳川氏の処分が寛大となったのは当然だったといえよう。そのようにしむけ、それを演出したのがまさに勝海舟だった。 ・維新の二人の英雄の腹芸で江戸を戦火から救ったという世に喧伝された美談の背後には、明治維新という日本近代の出発点において、国際勢力の圧力と国内の階級的な矛盾が深刻にからみあい、そのなかでの東西両軍の息づまるようなきびしい政治の現実があったのである。それを勝は読みぬいて手を打ったのだ。 5 最後の将軍とその晩年 ・幕府の文久改革は、政事総裁職松平慶永を中心に実施された。第一は、参勤交代制の緩和であり、第二は軍制の改革である。歩騎砲三兵制やオランダからの軍艦購入、留学生派遣などが行なわれた。第三には、学制改革がなされ、洋学の導入が一段とすすめられた。第四には、京都守護職が置かれ、会津藩主松平 ・禁裏守衛総督を辞した直後の慶応二年(一八六六)八月二十二日、慶喜は徳川宗家を継いだ。自分の思うように改革を行なうということと引換えに承諾したのである。そして、八ヵ条の基本方針を打ち出して改革にふみきった。 ・慶喜は第二次征長の失敗によって失墜した幕権を、内政、外交、軍事、経済などのあらゆる面にわたって改革することによって、新たな徳川統一政権の樹立の基礎を築こうとしたのである。 ・これまでの老中月番制は、慶喜を補佐する専任老中板倉勝静を中心とした国内事務、会計、外務、陸軍、海軍の五局制に改められ、官僚機構化がはかられた。人材登用もいっそうすすめられようとした。 ・また、積極的に新税の賦課や殖産、貿易の振興、鉱山の開発などが計画され、財政の充実がめざされた。 ・軍政の改革も、文久改革の矛盾を克服しようとし、銃隊編成、旗本、御家人の兵賦、軍役の金納化による傭兵性が企図された。 ・フランス軍事教官団がその指導に当たり、横須賀製鉄所の建設もすすめられた。財政不足はフランスからの借款によろうとした。さらに、三井以下の特権有力商人との結びつきも強化され、「商社」による商品流通の掌握も計画された。 ・この慶喜による慶応改革の諸政策は、実は若干の修正をみながらも、多くはのちの維新政権に引き継がれているのである。その意味では、慶喜政権と維新政権との間には、幕府の廃絶をはさんで“非連続の連続”とでもいうべき関係があった、といってよい。 |