
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年03月04日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
19 |
16/02 |
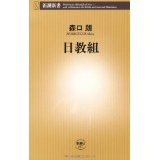 |
日教組 |
森口 朗 |
新潮新書 |
◎ |
序章 ある平凡な日教組教員の日常 ※教職員組合は基本的に都道府県単位で存在し、日教組はその連合体にすぎない。県教組の下に地域ごとの支部があり、そのまた下に学校ごとの分会がる。支部には通常支部長、書記長、会計の三役がおり、かつては分会にも三役がいた。 ・民主的な学校運営をするためには、最初が肝心だ。分会長は校長が変るたびに日教組の教職員全員を連れて校長室に乗り込み「校長着任交渉」を行った。 ・そこで、「授業内容については教師の教える自由(要するに日教組が推奨する教材を使うこと)を尊重すること」「主任等に逐一仕事を命じないこと(主任教諭を実質的にヒラと同一に扱うこと)」「夏休みの自宅での研修を認めること(夏休みは全部休ませろということ)」「その他の重要事項(卒業式や入学式での日の丸掲揚・君が代斉唱など)は校長と組合が話し合って決めること」などを認めさせた。 ※校長着任交渉とは、組合の言いなりになりますと校長に宣誓させることに等しい。今でも日教組系の組合が強い北海道では校長着任交渉が行われている由。 日教組の強い道県として北海道・広島・大分が挙げられる。 ※文部省は二〇〇〇年の学校教育法施行規則改正で、職員会議を校長が主催する補助機関と位置づけた。何でも多数決で決めるのが民主的という日教組的な思考に校長自身が侵されているため、放っておくと職員会議が学校の意思決定機関になってしまうのである。 ・日教組の本部役員になれば事実上組合の仕事一筋になるから、学校に籍をおきながら教育研究所に研修に行くという名目で一切の授業を免除される。 ※「ヤミ専従」は決して組合単独ではできない。公務員社会にヤミ専従が横行している場合、必ずその役所と組合の間には馴れ合いの関係が存在する。これは教員世界も含めてすべての官公庁に当てはまる事実である。 教職員組合に限らず多くの官公労では幹部クラスの専従職員に管理職公務員と同等の報酬を保証している。 ※北朝鮮の日本人拉致問題を題材とした『めぐみ ― 引き裂かれた家族の30年』やアニメ『めぐみ』を学校で上映する県は埼玉県や新潟県などいくつか存在する。しかし、日教組系組合の幹部達はこれを妨害しようと試みている。 日教組系組合員が上映に反対する際の根拠は、①在日朝鮮人児童がかわいそうである、②日本も過去に強制連行した、の二点である。 二点目については、秘書給与の流用事件で逮捕された元社民党の辻本清美も同様の主張をしていた。 * * * ・日教組役員には、①専従職員、②ヤミ専従職員、③学校に勤めながら組合役員をやっている教員、の三種類の人間がいます。 ・①は日教組の組合員が支払う組合費から給与が出ている。 ・②は最も悪質です。日本全体で十六億四五〇〇万円です。不当支出として見逃すには大きい額です。 ・③のタイプは、雑務と言われる授業以外の、仕事をせずに組合の仕事ばかりしている教員はどの学校にも一人や二人はいます。 日本には小中学校併せて三万以上の学校がありますから、少なくとも三万人の③タイプがいると考えられます。 彼らの労働力の三割が日教組のために使われているととして計算すると、六三〇億円ものお金が無駄に使われていることになります。 ・日教組の悪名は天下にとどろいています。今では日教組を称賛するメディアなど、ほとんどありません。それでも日教組の組織率は少しずつしか減りません。 ・それは、日教組の何がいけないのかを自覚できないからです。日教組に所属している大多数の人たちは、自分たちの所属する組織の歴史も基底に流れる思想も何ひとつ知らないのです。 ・「日教組はかつてほど過激な左翼団体ではない」という一般メディアの多数説に対し、保守言論の世界では「過激な性教育」や「反日思想に彩られた歴史授業」など極端な授業を取り上げ、日教組の教員すべてがそのような授業をしているかのごとき主張をする方がいます。 ・これらの授業は確かに日教組の体質を表してはいるのですが、現場の教員からすれば、「学校現場を 第一章 「日教組」の誕生 すべては「新教育指針」から ・戦後、教職員組合を造ったのは文部科学省の前身である文部省です。より正確にいうならば、GHQ(連合国総司令部)の方針に屈服し、恭順の意を表すために文部官僚が学校に教職員組合を造らせたのです。 ・GHQから出された「教育に関する四つの指令」は、後に出される「新教育指針」とともに日本の戦後教育のあり方を決定づけます。 ・最初の指令により、軍事教練が廃止され、戦争協力者とされた教員やGHQに逆らう教員は ・四つの指令と教育使節団の報告により、生半可な改革では許されないことを悟った文部省は、四七年五月一五日、「新教育指針」という教師用の手引書を新たに全国の学校に配布します。この新教育指針によってわが国の戦後教育はスタートしました。 「押し付け=悪」の原点 ・新教育指針は、GHQの四つの指令と教育使節団報告書の内容を具体化するために出されたものです。 ・「はしがき」 【国民の再教育によって、新しい日本を、民主的な、平和的な、文化国家として建てなほすことは、日本の教育者自身が進んではたすべきつとめである。マッカーサー司令部の政策も、この線にそって行なはれており、とくに教育に関する四つの指令は、日本の新教育のありかたをきめる上に、きはめて大切なものである】 ・新教育指針はマッカーサーの意図には沿っているけれども、それはGHQに「押し付け」られたから出された文書ではないと弁明しているのです。 ・新教育指針は続けて言います。 【「本省(文部省)は、ここに盛られてゐる内容を、教育者におしつけようとするものではない」「むしろ教育者が、これを手がかりとして、自由に考へ、ひ判しつつ、自ら新教育の目あてを見出し、重点をとらへ、万法を工夫せられることを期待する」「かうした自主的な、協力的な態度こそ、民主教育を建設する土台となるのである」】 ・押し付けはすべて悪という思想は戦後教育の負の側面だと思いますが、その原点はここにあります。 ・当時の学校の体質から考えて、学校現場が文部省の文書に従わないはずがない。それをわかった上で「おしつけようとするものではない」と言って責任を逃れているわけです。 敗戦をどう捉えたか ・新教育指針の見解は、【連合国軍が占領しているのは、未だ軍国主義や極端な国家主義がはびこっているからであって、戦争する力がなくなれば独立できるのである。現在はその過渡期の状態だ】という訳です。 文部省の驚くべき日本人観 ・新教育指針は主張します。 ①日本はまだ十分に新しくなりきれず、旧いものがのこってゐる。 ②日本国民は人間性・人格・個性を充分に尊重しない ③日本国民はひはん的精神にとぼしく権威にもう従しやすい。 ④日本国民は合理的精神にとぼしく化学的水準が低い。 ⑤日本国民はひとりよがりで、おほらかな態度が少ない。 ・今時日本人をここまで悪し様に言うのは、時代についていけないオールド左派か、中国や韓国のネット中毒者か、北朝鮮の国営放送くらいでしょう。しかし、当時は文部省がこんな日本人観を提示したのです。 民主的修養としての組合のすすめ ・新教育指針はさらに続けて、以下のような教育環境が民主主義を実現すると説きます。 ①教育制度を民主化すること ②教育の内容に民主主義を取りいれること ③生徒の人格を平等に尊重し、個性に応ずる教育を行なふこと ④自主的・協同的な生活及び学習を訓練すること ⑤教師自身が民主的な修養を積むこと 学校経営において、校長や二、三の職員が決めるのではなく、すべての職員が参加して、自由に十分に意見を述べ協議したうえで事をきめること。 そして全職員がこの共同の決定にしたがい、各々の受け持つべき責任を果たすこと。 教職員組合を造ることも教師の民主的修養にとっては重要である。 教師といえども政治に関心をもつべきであり、偏らぬ立場にありながら、諸政党の動きには十分注意をはらい、よいことはよい悪いことは悪いとする有力な意見を述べ、政治を正しい方向に指導しなければならない。 教員組合がこうした意味で勢力を増してゆくことが健全な発達であって、それはただ教育者だけの降伏ではなく、国家のために大きな奉仕をすることになる。 以上が、文部省から出された新教育指針の概要です。 教職員組合の爆発的拡大の果てに ・一九四七年三月八日に初めて結ばれた文部省と教職員組合の労働協約には、 「争議中または争議発生のおそれがある場合、組合の運動に対抗する処置を業務命令で行ってはならない」 「組合員の政治活動に妨害をあたえない」 という、今の日教組幹部が見たら泣いて喜ぶような文言が盛り込まれていました。 ・一九四七年六月八日、日本教職員組合(日教組)の結成大会がひらかれました。 戦後民主教育の申し子 ・「日教組はまさに戦後民主教育の申し子である」というのは歴史的事実です。 ・「日教組は子どもたちに自虐史観を押し付けるからけしからん」という人がいます。 とんでもない。封建時代にまでさかのぼって日本を断罪し、日本人は劣っているから教師はそれを自覚して生徒を導かなければならないと言い出したのは文部省です。 日教組は文部省から手渡された「新教育指針」という手引書によって誕生し、その手引書の教えを愚直に守って来たに過ぎません。 ・「先生は聖職者だ。それを労働者とする日教組はけしからん」という人がいます。 お門違いです。批判したいのならば、教職員組合と労働協約を結んだ文部省をまず批判すべきでしょう。労働協約を結んだ教員が自分たちは労働者だと考えたとして、どこに問題があるのでしょうか。 ・「日教組は教育をそっちのけにして政治活動をするからけしからん」という人がいます。 八つ当たりです。新教育指針には、教師は政治を正しい方向に指導しろと書いてあります。それに文部省と教職員組合が最初に結んだ労働協約には「組合員の政治活動に妨害をあたえない」と書いてあります。後になって協約を ・「日教組が体罰を禁止したから子どもがダメになった」という人がいます。 ウソです。体罰は戦前から法律で禁止されていました。実際には体罰が横行していましたが、それは日教組の教員も同じです。彼らは戦後の一時期まで法を犯し、ビシビシと体罰に励んでいました。 ・多くの日教組批判は言いがかりです。日教組は、少なくとも外見上は戦後民主教育を当初の形どおり行ってきたに過ぎません(幹部の本音は別のところにあった)。 ・日教組を批判したいのであれば、戦後民主教育も同時に批判すべきなのです。 ・では、戦後民主教育を推進してきたのは誰か。それは戦後ほぼ一貫して政権を担ってきた自民党とその前身政党です。あるいは文部省です。彼らを批判せずに日教組だけを批判するのは、不公平というものです。 ・日教組は戦後民主教育の一貫として誕生し、表面上は、それをほぼ愚直に推進してきただけの団体です。 所業① 一九四七年「六・三制完全実施」 所業② 一九四九年「レッドパージ反対」声明 ・一九四九年の中華人民共和国の誕生に危機感を覚えたGHQは、共産党を目の敵にするようになります。 ・そもそも獄中にいた共産党員を釈放して彼らを軍国主義と戦ったヒーローにしたのはGHQですが、この時期になると戦略ミスに気づいて急激に方向転換します。 ・GHQ自身の指令としてではなく、政府に、共産党員とその同調者の教職員を追放するよう口頭で指示を出しました。政府は直ちに全国教育長会議を開催し、GHQの意向だからすぐに処置するようにと各都道府県に伝えました。 ・このレッドパージで追放された教員は一七〇〇人程度と言われています。 所業③ 一九五一年「教え子を再び戦場に送るな」 ・一九五一年にサンフランシスコ講和条約が結ばれて日本が独立を回復すると政府からは戦後民主教育を見直そうという動きが出てきました。 ・これに対し、日教組は戦後民主教育を守る合言葉として「教え子を再び戦場に送るな」というスローガンを採択します。 ・さらに、このスローガンを実りあるものにするためには、「戦争に行きたくない」という子どもを育てる教育方法を確立する必要があると考え、第一回全国教育研究大会を開きます。 ・平和教育を扱った分科会では、赤十字運動やユネスコ運動、国連に対する理解を深めることで平和を守る子供を育てようという意見が出され、教育の力で戦争を喜ぶ人間をなくし、人種的偏見を取り除き、平和のための歴史を教えることで平和は守られるという結論に落ち着きました。 ・この大会は、その後「教育研究全国集会(略称・教研集会)と名称を変え、日教組最大のイベントとして毎年開催されることとなりました。 所業④ 一九五三年~五五年「偏向教育批判」批判 ・一九五三年に山口県教組が平和教育の自主教材として編集・発行した『小学生日記』『中学生日記』の欄外の記述が偏向していると保護者が訴えて、社会問題になりました。 ・これがきっかけとなり日教組の平和教育が偏向しているという批判が高まりました。日教組に対する世間の目も徐々に厳しくなっていきます。 ・これら一連の動きの中で、教師の政治的中立を義務付ける法律が可決されました。 所業⑤ 一九五六年~五九年「勤評闘争」 ・日教組の歴史の中で最も激しい運動が、勤務評定の実施に反対した「勤評闘争」です。 ・一九五〇年に成立した地方公務員法は任命権者による勤務評定の実施を義務付けていましたが、全国の教育委員会は教員の勤務は評定になじまないとして実施していませんでした。 ・ところが、一九五六年に愛媛県教育委員会が県下市町村の教育委員会に勤務評定の実施を厳命したことで逃走の引き金が引かれます。翌年には勤務評定の実施が全国化し、教員だけでなく、児童生徒や保護者、さらには地域住民まで巻き込んだ大闘争に発展しました。 ・日教組側の言い分は、当初は教職員だけの視点から「差別昇給反対」でしたが、大衆運動に発展させることを意図して「教育の権力支配のための勤評」に反対するというように変化していきました。 ・違法なストライキがうたれて、約六万人の教職員が何らかの処分を受けます。勤評闘争に反対する世間の評価は分かれ、この争いが日教組の組織率が低下するきっかけとなりました。 所業⑥ 一九五九年~六〇年代「高校全入運動」 所業⑦ 一九六一年「学力テスト」反対運動 所業⑧ 一九七三年「主任制度」反対運動 文部省との和解 ・文部科学省のスポークスマン寺脇研氏はゆとり教育のはじまりは臨教審にあるといい、ミスター日教組槙枝元文氏は日教組がゆとり教育をはじめたと主張している。 ・槙枝元文氏は、最も尊敬する人物として北朝鮮の故金日成氏をあげ、一九九一年には北朝鮮から親善勲章第一級を授与されており、日教組を象徴している人物と言っても過言ではないでしょう。 第二章 「教団」としての日教組 なぜ教師が「聖職者」なのか ・戦前の日本において教師は明らかに聖職者でした。それについては、教師聖職者論を真っ向から否定した日教組自身が認めているところです。 『日教組60年』は戦前の教師について「教職員は、天皇=神に仕える身として『聖職者』とされた」と記しています。 戦後民主主義の布教者 ・戦後、教師は聖職者の地位からすべり落ちました。それまで神様だった昭和天皇自身が「人間宣言」をするのですから仕方ありません。奉る神が否定された聖職者ほど惨めなものはありません。 ・しかし、彼らには次の神様が用意されていました。 新教育指針は「民主主義」を広めるという新しい役割を教師に与え、そのうえ教職員組合という「教団」を造ることさえ奨励したのです。これにより神を失い茫然自失となっていた聖職者は元気を取り戻します。 ・教師は戦前戦後を通じて聖職者でした。 それは日教組や左派文化人が主張しているように押しつけられたものでは決してありません。彼ら自身が聖職者であり続けることを望んだのです。 ・彼らは神を「天皇」から「民主主義」に変えることで聖職者の地位にとどまることを許されたのです。そして、ほぼ唯一の教職員組合であった日教組は、教職員組合であると同時に民主主義の布教集団=教団的様相を呈するようになっていきます。 ・もちろん、ここでいう「民主主義」は封建時代にさかのぼってまで過去の日本を断罪し、日本人を西洋人よりも劣ったものとみなし、多数決だけを正義とする「戦後民主主義」であって、本来のデモクラシー原理ではないことは言うまでもありません。 ・日教組が、何故、布教の過程で平和教育を重視したのか。 彼らにはそうしなければならない事情があったのです。その事情とは「第二次世界大戦中、日本の教師は教え子を戦場に送り続けた」という紛れもない事実です。 ・日教組が大戦中の教師を「教え子を戦場に送る教育」をしたと評するのは、あまりに自分自身や先輩達に厳しすぎるというものです。忠君愛国がいけないのであれば、親だって地域社会だってみんな罪人です。みんなで若者を戦場に送ったというべきでしょう。 ・軍国主義の世の中で一般論として軍国教育を行った教員を非難することは間違いだと思います。 ・教師の本当の罪は軍国教育をしたことではありません。 ・大戦中の教師たちは教育の枠を越えて積極的に教え子を戦場へと駆り立てていたのです。 満蒙開拓青少年義勇軍と教員 ・満蒙開拓青少年義勇軍は、青少年を満州に送り込んで訓練し開拓と国防に当たらせようとするもの。 ・募集により、最終的に二万四三七四人が訓練所(送り込む前の事前の訓練)に入所しました。 ・この満蒙開拓青少年義勇軍は選挙区が悪化したのちも続けられ、年を追うごとに政府から都道府県、都道府県から学校、学校から生徒・父系への入所圧力は強くなっていきました。 ・一九四二年に入所した青少年の応募動機の内訳 教師の勧め 九三九〇人 父兄の勧め 一三三三人 講演 五八三人 友人の勧めむ 三二九人 ⠇ 教師は嬉々として戦場に教え子を送った ・満蒙開拓青少年義勇軍。そこに教え子を送り続け、開墾と国防を担わせて、内地の日本人よりもはるかに高い確率で死へ導いたのは戦前の教師です。しかも彼らは嬉々として胸を張って生徒を戦場に送ったのです。 ・その現実を直視することから逃げ、罪の意識から逃れるために過激な戦後民主教育の宣教師となるしかなかった。それが戦争直後の教師の心理構造だったのではないでしょうか。 ・満蒙開拓青少年義勇軍は貧しく成績が芳しいとは限らない子どもたちがターゲットでした。募集人数も多く各校への割当もきつかったのです。だから、教師達は時に本人や親を「非国民」と脅し、時に広大な土地が手に入ると甘言を弄して、教え子を戦場へと送り出したのです。 体罰禁止は明治時代から ・保守系言論人の教育論を読んでいると「戦前は子どもが悪いことをしたら教師は迷わず体罰をしたものだ。ところが戦後は体罰が禁止されて、悪いことをした子どもも放りっぱなしになった。これでは子どもに道徳心が育つはずがない」「体罰を復活させろ」などと平気で主張している方がいます。中には「日教組のせいで体罰がなくなって日本の教育はダメになった」といったデタラメなことを主張する人もいます。 これらは二重に間違った意見と言わなければなりません。 ・間違いの第一は戦後すぐに体罰がなくなったわけではない点です。 ・体罰が学校から急激に減少したのは戦後教育が二周目(親も戦後教育世代)に入った一九七〇年代のことであって、それまでは日教組の加入非加入にかかわらず日常的に体罰が行われていました。 ・もう一つの間違いは、日教組が組織されるはるか以前、つまり戦前から日本の法律は一貫して体罰禁止だったという点です。 新たな経典の誕生 ・一九五二年、日教組は第九回定期大会で「教師の倫理綱領」を採択し発表しました。 教職員自らが決めた教師の指針です。 ①教師は日本社会の課題にこたえて青少年とともに生きる。 ②教師は教育の機会均等のためにたたかう。 ③教師は平和を守る。 ④教師は科学的真理に立って行動する。 ⑤教師は教育の自由の侵害を許さない。 ⑥教師は正しい政治を求める。 ⑦教師は親たちとともに社会の ⑧教師は労働者である。 ⑨教師は生活権を守る。 ⑩教師は団結する。 ・保守系の政治家や文化人は八番目の「教師は労働者である」という部分に反発しましたが、実際には四番目の「科学的真理に立って行動する」という条項こそが最も日教組幹部の性質を現す条項でした。というのは、ここに言う「科学的真理」とは当時「科学的社会主義」を自称していた共産主義を指しているからです。 ・つまり、「教師の倫理綱領」制定により日教組幹部は、日教組という団体を共産主義団体だと明確に規定したことになります。 第三章 「ムラ」としての日教組 勤務評定を拒否した校長たち ・勤務評定実施の目的は、信賞必罰を導入して教員の職務精励を促すためでなく、日教組弱体化だったと考えれば、一九五八年から文部省が日教組の組織統計を取り始めた理由も分かります。 ・行政統計調査の目的は、政策立案の根拠か、政策効果の検証のいずれかしかありません。ただなんとなく行政統計調査を始めることなど絶対にないのです(不必要になった行政統計調査をただなんとなく続けることは多々ありますが)。 ・日教組の組織率を見て政策を立案するとは考えにくいので、効果測定と考えるのが素直な解釈です。 あとがき ・日教組思想 「勉強のできない子を競争させるのはかわいそうだといって低学力のまま社会に放り出す」 「校内犯罪の加害者を出席停止もせずに『いじめっ子も被害者だ』とかばう」 「教室内で自衛隊や米軍を罵倒する教師が、中国や北朝鮮の軍拡には批判さえしない」 「人権と言う言葉を聞くと思考停止に陥り、その言葉を濫用する人のいいなりになる」 ・こういったことを以上だと感じる人たちがようやく増えてきました。 ・巷間言われる「教育の正常化」とは、この異常性を正す営みに他なりません。 |