
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年03月16日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
25 |
16/03 |
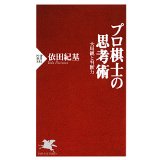 |
プロ棋士の思考術 |
依田紀基 |
PHP新書 |
◎ |
第1章 「正しいか」より「新しいか」でものを見る ――大局観と判断力 何が大局観を準備するか ・大局観とは、勝つための判断力である。 ・勝つため、勝ち続けるためには、大局観を準備する大切な要素がいくつかある。 ・プロが勝ち続けるための八つの要素 どれも頭文字が「か行」であることから、私はこれを「勝ち続ける八つのK」と称している。 「心技体」でいえば、一~四は「技」、五~八が「心」と「体」にあたる。 ・一つめは、「感動」だ。 これはすばらしい、と感動する。こんないい手を自分も打てるようになりたいと思う。そうしたら、その棋譜を、自分で並べてみるのだ。 「こんないい手を打ちたい」と念じて、くり返し並べていけば、必ずその人間に近づいていくと信じている。 ・二つめは、「繰り返し」である。 同じことでも何度も勉強することだ。 わからないと「わかる」ことも大切な進歩 ・三つ目は、「根本から考える」ことだ。 ・四つめは、「工夫を加える」ことだ。 トップに立つ近道は、古いことに工夫を加えて新しいものを創り出すことだと考えている。「温故知新」、まさにそれである。 いつも、真剣に工夫をしていくことによって、自分が磨かれていく。ほかの人が自分の工夫した手の上を歩けば、新しい道となっていく。 必ず勝つには長く戦うことだ ・五つ目は、「感謝」である。 ・六つ目は、「健康」だ。 ・七つめは、「根気」である。 ・八つめが「 「虚仮の一念」とは、愚か者でも一心に一つのことをやれば、目的を達せられるというほどの意味である。 勝負はなんでも、相手がある。「勝った」[負けた」は、つまり相対的なものだ。だから、虚仮の一念のような強い心があるかどうかが、ぎりぎりのところで勝敗を分ける。 負けが込む人の共通点 ・判断ができない人、つまり負けが込む人は、判断基準を持っていないのではないかと私は思っている。心の根本のところに、「こういう方向に行く」「ここで行動する」という定まった基準がないのではないか。 ・根本のところがあいまいであれば、判断はふらつく。自信も持てない。少なくとも、碁ではそうである。だから、人生やビジネスでも同じだろうと考えている。 ・判断する力は、継続して勉強していけば、必ず得られる。 「実利」と「厚み」と実社会 ・厚みは、実社会に置き換えれば、目に見えにくい人脈、信用などになる。国に翻訳すれば、潜在的な軍事力と考えることもできる。 ・「厚みを地にするべからず」 ・地という現実の利得にしようとすると、せっかくの潜在力が損なわれてしまう。 碁は考える力をつける ・「厚みに近寄るな」 ・「厚みは攻めに活用すると力を発揮する。だから、あまり近寄ると攻められて危険だ」 これなどは、まさに軍事力に近い。 ・自分の厚みに近寄り過ぎると、厚みがダブって、石の効率が悪くなるのである。 ・こう考えると、碁は、縦横十九の盤から飛び出して、現実社会の応用力を養う空間になる。さまざまな局面が現れるが、状況を読み解き、状況ごとに、よい手を考えていく。よい手を打てば優勢になり、勝ちにつなげられる。 定石という「部分」を全体と結ぶ ・碁の基本的な考え方は、価値の大きいところに石を置くということに尽きる。非常にシンプルである。 ・大事なのは、どこが価値が大きいかを判断する力だ。1つ1つの石の意味と、石の力を考えることだ。それを怠らなければ、碁も上達するし、考える力が格段についてくる。 読みとはイメージを広げること ・読みとは、置いていない石が盤に置いてあるように、形をイメージすることである。だから、自分が打って、相手が応じてといった連続した石のつながりは、意味を成さない。 ・まず、どのような形がよいのか、どのような形を自分は望むのかをイメージする。それができなければ、いくら相手の手を予想しても仕方がない。 ・第一手は、読みようがない。 局面が広すぎ、どこに打ってもよいのだから、打ち方は無数にある。そのわからない中でできるのは、形をイメージすることだけである。イメージを盛り上げていくことが、非常に大切になってくる。 ちょっと外れた場所にいい発想がある ・なまじ定石の知識があると、ほかの手が浮かばなくなることを心してほしい。決めつけようと思わなくても、自然に決めつけてしまうのだ。 心が「これしかないんだ」と思い込むと、それは現実のものとなってしまう。心には、そういう力がある。決めつけのこわさである。 自由はあなたの視野を広げる ・既成概念がすぐ胸に浮かぶようでは、縛られてしまう恐れがある。束縛は、新しい手を生み出す障害になる。ここはこう打つものという決めつけが、よいイメージを損なってしまうからだ。 ・決めつけがない。こだわらない。自由である。そういうことが碁では大事だ。 いい「布石」の条件 ・大局観は最初から振りかざすものではなく、自分のしたいこと、すべきことを一つひとつ深めていくところから、おのずから生まれてくるものなのだと思う。 少なくとも、そのほうが、ほんものである気がする。 第2章 不安な手イコールだめな手とは限らない ――劣等感と深く考える力 潜在能力は「べき」より「好き」で伸びていく ・子どもはすごい潜在能力を持っていると断言できる。 ・興味を持ち、好きになって、集中すると、底知れぬエネルギーとパワーが出てくる。好きだから、楽しい。楽しいから、続けられる。 ・どんな分野でも、一人前になるには何年もかかるが、好きなことなら必ず長続きするものだ。 子どもの「興味」や「好き」を見つけてやるのが、大人の役割だと思う。 ・だから、子どもが興味を持ち、好きになりかけたことに対して、大人は、まずほめてやる。それが大切だ。 酒と博打と女がそろう ・情報には、「知っておかなくてはならない」「知らないほうがいい」の二つがある。 心が勝ち負けを決めている ・心の持ちようは、現実を左右するほど大きなものだ。 ・それまでの私は、「碁は技術」と考えていた。だから、技術が上の者が勝つと決めつけていた。そうではないのだ。碁も「心の持ちよう」なのだ。心が勝ち負けを決めている。心が大切だった。 頭でイメージせず心でイメージせよ ・碁とは、イメージなのである。 それは分かっていたが、「頭」で考えたイメージであった。「心」という考えがなかった。心で読み、心でイメージする。 したがって、いつも心の状態が大事になる。 第3章 「どうあっても!」は知恵の宝庫である ――捨石法と発想力 逃げさせて得をする ・捨てようとしたら、その石の強弱を見きわめる。 弱い石なら捨てさせない。逃げさせて得をする。 これも碁の技のおもしろさである。 第4章 希望に向かう船にはどんな風も順風に働く ――メンタル管理と勝負強さ 悪手がよい手になるのはなぜ? ・いま、世の中は理屈っぽくなっていて、感情の重大さを見逃しがちな気がする。だが、自分、相手、周囲それぞれの感情が一体となって大きな作用をもたらすことを忘れてはならない。 安全に勝とうとするから負けるのだ ・碁は感情の戦い、感情の交換でもある。 ・人間は感情の動物なのだ。心で戦っている。だから心の向きをちょっと変えるだけで、弱い人間が強くなることもある。 ・勝ちたいと思いすぎると、のびのびした手が打てなくなるのだが、そのさらに真因を探ると、「安全に勝とう」とする心がある。 ・冒険をしないのだ。自分を信じていないわけである。 第6章 自分を進めることは世界を少し進めること ――先手をつかむ私の提案 学問には「正解」があるが社会にはない ・学校で能力、才能というと、学業成績ばかりが話題になる。 元劣等生から言わせてもらえば、先生も子どもも親も、学校の勉強ができないことを、人間として劣っていることだと思っているふしがある。 まったくの誤解だ。あるいは妄想といってもよい。 社会に出てからは、学校の成績なんて、たいした意味を持たない。 ・学校の勉強は、答えがあることをやっている。 だが、社会に出たときには、正解のないことをする。 ・「勉強の才能がない」 子どもがやらないのは、それ自体、才能がないということなのである。勉強の才能がないと認めることは、人間的に劣っていると誤解しているから、言うのが怖いのであろう。 ・勉強が好きで好きで仕方ない子どもは、勉強の才能があるのだろうから、大いに勉強を続ければいい。しかし、勉強が嫌いな子どもに無理じいさせることはない。無理やり、嫌いなことをさせるから、いじめやその結果として自殺に追い込まれるようなことが起きてしまう。 ・むしろ、好きなことを発見させて、それに打ち込ませればいいのである。それが社会に役立つことであれば、もっといい。子どもは好きなことであれば長続きする。そちらに力を振り向けてやれば、すごいパワーを発揮するのだ。 |