
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年04月18日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
34 |
16/04 |
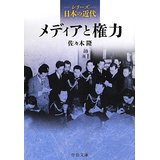 |
メディアと権力 |
佐々木 隆 |
中公文庫 |
〇 |
1 メディアの創生 新聞事始 日本最初の新聞『バタヒヤ新聞』 ・日本人が最初に発行した新聞は、文久二(一八六二)年正月に ・『官板 バタヒヤ新聞』は東インド(現インドネシア)のバタヒヤ(現ジャカルタ)にあったオランダ総督府の機関紙を翻訳・抄録したもの。 幕末の情報公開 ・為政者・権力者が独占してきた情報をすすんで公開・開示するのは、なんらかの体制の危機・国家の危機に直面して他の指示を取りつける必要があるときが多い。 ・開国・開港論と ・危機が進行してからの情報公開は、体制内の分裂や士気の低下を誘発したり、 ・そもそも情報独占を捨てざるを得ないほどに深刻化した危機は、にわか 明治十四年政変と 『官報』 の誕生 新聞紙条例強化と正誤権 ・明治十六(一八八三)年、正誤文掲載要求権(正誤権)が初めて登場した。 ・関係者から記事に訂正要求があった場合、日刊紙なら翌日か翌々日に訂正要求文または訂正記事を載せなければならないというものである。 ・正誤権は新聞の攻撃対象となることの多い政府が反論を行ないやすくするために設けた規定と考えられる。 2 スキャンダルとキャンペーン 誰が森有礼を殺したのか 内村鑑三不敬事件 ・メディアによるステレオタイプ化した人間把握が ・ある人物(政治的、社会的な存在感のある人物)についてプラス・マイナス(ほとんどはマイナス)の価値判断を加えて類型化・単純化したうえで記事を連発すれば、ある意味で政治キャンペーンになるわけだし、小新聞的読者にとっては一つの娯楽である(世にいう「他人の不幸は蜜の味」)。 4 日露戦争と新聞の変貌 報道戦争と日比谷焼打ち事件 講和反対を煽った新聞 ・非講和論に 日比谷焼打ち事件顛末 ・国民新聞社は、五千といわれる群衆に襲われた。 ・九月六日、戒厳令が施行されて ・日露戦争の勝利はしばしば「辛勝」あるいは「惨勝」と表現される。極限までの動員を行い、戦費を遣い尽くしての危うい勝利だったというのだが、戦争目的を考えれば、実は日清戦争以上の「完勝」であった。 ・日清戦争の戦争目的であった朝鮮半島の勢力圏編入はいったん成功したものの、ロシアの進出と朝鮮(韓国)の内政の変動によりたちまち損なわれてしまったが、日露戦争の結果、朝鮮半島は日本の勢力圏に入り、日本の独立を危うくする本土への脅威は消滅した。明治三十九年、 ・しかも、戦争によって勢力圏が確定し日露間の紛争要因がなくなったため、ロシアは敵国からイギリス以上の友邦に ・当時の戦争形態は勢力圏接触部の陣取りであり、よほど互いが接近していないかぎり、首都の占領や敵国の覆滅、政体の変更などはもともと期待されていなかったのである。 ・しかし日本が得た国際政治上の利益は、領土のように可視的でもなく、戦時賠償金のように即物的でもなかった。つまり「わかりにくかった」のである。それは湧き起こるナショナリズムと愛国心をすぐに満足させられるものではなかった。 ・一般国民は外交官でも軍事評論家でもない。目に見える形でのナショナリズムの充足を望んでいたのである。 5 平民宰相のメディア = コントロール 原敬暗殺と第二次護憲運動 原と記者クラブ ・日本で最も古い記者クラブは明治二十四年に発足した同盟新聞記者倶楽部である。 6 昭和の動乱と新聞の“転向” 陸軍の「番記者」たち 情報幕僚としての親軍記者 ・新聞の親軍的記事は、すべてが強制ないし暗黙の強制によるものではないということである。誘導の効果はいくらかあったかもしれないが、もともと親軍的な記者、軍シンパシーを抱く記者、誘導を受け容れる 7 昭和十九年の情報公開 記者クラブの完成 情報カルテルとしての記者倶楽部 ・一連の紛糾(有田外相のラジオ演説に対する新聞論評から起こった問題)は、政局の主導権掌握を念頭において、新聞を利用した外務省・陸軍省の牽制合戦だったと考えられる。この過程ではしなくも露呈したのは軍部に迎合的な記者クラブの姿であり、取材対象と同化・一体化している記者クラブの姿であった。 ・それは抜け駆けを許さぬ情報カルテルであり、取材対象の利害を反映しがちな今日の記者クラブの弊害とされるものをすでに用意していたといえる。 ・戦時期の新聞統制は経営上の秩序のみならず、記者クラブのあり方にも今なお大きな影を落としている。 ・日本の政治・経済・社会のシステムが戦時体制を引きずっているとは新聞がよく指摘することだが、それは新聞界も例外ではないのである。 エピローグ 独立新聞というユートピア 政府系新聞の類型 ・近代日本の新聞は政府・権力と危うく微妙な間合いを取ってきた。独善的・専制的な政府と、これに反対し異議を申し立てる新聞の物語として綴られることの多い日本新聞史だが、現実には、主要な新聞で政府と “密接な関係” “特別な関係” を持ったことのない新聞は皆無といってよいほどである。 ・政府系の新聞・新聞人は常に相当の割合いをもって存在し、それはべつだん強制・強要によってその ・政府と政府系新聞・新聞人の関係 ⑩組織体としての新聞社が政府と関係しているわけではないが、幹部・有力記者(主幹・主筆・論説委員・編集委員・古参記者・有力記者)などが政府や 新聞と政府の関係変遷早わかり ・軍部や政府による誘導や強制はあったかもしれないが、満州事変以降の新聞が対外膨張を支持したのは新聞自体にも内発的要因が存在したといわねばなるまい。 ・戦後の新聞は基本的に⑩のパターンが受け継がれている。反政府的と見られる新聞の中に政府系・与党系の記者(いわゆる番記者)が含まれているのはよく知られているし、記者クラブの官庁との蜜月ぶりもよく知られている。新聞社の敷地が多くは国有地(あるいは払下げ地)であり、放送局が新聞社の系列化したとき国が果たした役割りも何やら示唆的である。 戦時体制が制度化した記者クラブ ・十六年十二月、記者クラブ(記者会)は一官衙一記者会と定められ、記者単位ではなく新聞社単位に改められた。このシステムは基本的に戦後の今日まで受け継がれているのである。 ・現在、記者クラブについては官庁の情報隠匿を抑止する機能、取材の効率化を評価する一方で、取材や記事化の相互規制、排他性、施設の無料利用、消耗品の無償提供などの取材対象からの便宜供与の常態化などの弊害が指摘されている。 ・こうした慣習は数十年をかけて形成されてきたものだが、それを制度化・統一化したのは戦時体制であった。 「木鐸」の持つ二重の意味 ・政治を報道する新聞は必然的に権力や政府と接触・同化する契機を持っており、大多数の新聞がなんらかの形で政府と特別の関係を持ったことがある。つまり政府系紙だった過去を持つという、いたって散文的な現実であった。 ・新聞の中にはもともと権力や政府に対して求心的な要素と遠心的な要素が共存・混在していて、常にきわどいバランスをとっているということなのである。 |