
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年04月19日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
36 |
16/04 |
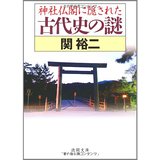 |
神社仏閣に隠された 古代史の謎 |
関 裕二 |
徳間文庫 |
〇 |
法興寺 ・飛鳥寺、本元興寺などの名がある。 ・法興寺は「仏教を日本に普及させたい」という蘇我氏の願いと共に、新たな技術を朝鮮半島から学び、建設されたものであったことがわかる。ただし、すべてが渡来系の技術と思想で造られたのかというと、そうとばかりもいい切れない。 ・というのも、「木工」に関しては、すでに縄文時代以来、日本列島には技術の蓄積があって、法隆寺や東大寺でも、大いに日本的な知恵が生かされたとされている。法興寺でももちろん、いくつもの文化と技術が融合していたに違いない。 ・さらに、これは発掘調査によってはっきりとしたのだが、寺院の心臓部ともいえる塔の礎石に埋められた「舎利」が、極めて「日本的」だった。 宇佐神宮 ・日本列島それぞれの地域にそれぞれの信仰形態があって、それぞれの心の中に「太陽神」がいたのであって、『日本書紀』にいう天照大神だけが、日本人の太陽神ではないのである。 おわりに ・神道は、縄文人のアニミズムに渡来系の文化や信仰が折り重なって醸成された多神教世界だ。大自然の前では人間は無力だという諦観が、この信仰を支えている。したがって、人々はひたすら神(大自然、森羅万象と括ることができようか)を持ち上げ、暴れ回る神をなだめすかそうと考えた。そうすれば、神は豊饒をわれわれにもたらすという発想である。 ご先祖様たちは、大自然を畏怖し、一方で日々の豊饒に感謝することで、満たされていたのである。これほどの達観が、どこにあるというのだろう。 ・これに対し、一神教はいたずらに正義(独善)を振りかざし、傷つけ合う。だから救われないのである。正義と救済は裏腹の関係にあり、人間の独りよがりに過ぎない。 |