
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年05月16日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
42 |
16/05 |
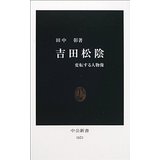 |
吉田松陰 |
田中 彰 |
中公新書 |
◎ |
第一章 「革命家」松陰像の浮き沈み――明治期の松陰像 2 松陰伝の定型 ・松陰が読書 ・「史料」所収にみられる松陰伝の定型は明治十年代後半に出来上がっている。 ・ここでの松陰伝では、世界の大勢を察し、海外に心を馳せ、「下田韜晦」を決行した松陰像は描かれているが、とくに愛国者松陰像のようなものはない。 ・また、教育者松陰像もないことは、松下村塾の名すら登場していないことに象徴的である。 ・われわれは歴史を、あとからつくられた枠組みのみでみてはならない。 第三章 教育者松陰像から「松陰主義」へ――昭和期の松陰像(一)敗戦まで ・田中義一内閣の山東出兵(一九二七~二九年)という三度にわたる中国山東省への軍事力行使によって始まった昭和は、以後、「満州某重大事件」( ・それは日本の天皇制ファシズム化、大陸侵略の進展、超国家主義の 第四章 復権、そして多彩なアプローチ――昭和期の松陰像(二)敗戦以後 ・奈良本達也著『吉田松陰』 秩序の中に進歩がなく、破壊の中にそれが保障されている。それは、まさしく歴史の危機であった。人は歴史を作る。そして、より以上に危機は人を作る。 第五章 人間・吉田松陰 1 外国人のみた松陰像 ペリー側からみた松陰 ・ペリー監修、F.L.ホークス編『ペリー日本遠征記』に記されたペリーの感想 「この事件は、厳しい国法を犯し、知識をふやすために生命まで 「日本人の激しい好奇心をこれほどよく示すものは他にはあり得ない」 「日本人のこの気質を考えると、その興味ある国の将来には、何と夢にあふれた広野が、さらに付言すれば、何と希望に満ちた期待が開けてていることか!」 ・ペリーは松陰と金子の二人のなかに、日本人の旺盛な好奇心や命をも賭けての世界に対する貪欲な知識欲をみてとり、そこにこの国の将来性のある希望を読みとろうとしていたのである。 2 松陰の人間平等観 松陰の囚人観 ・相手の立場にわが身をおき、相手の心になってわが身を考えようとするのが松陰である。それは決して同情ではない。相手の喜怒哀楽を松陰自身の喜怒哀楽にしようとしていたのである。松陰は老若男女を問うことはなかった。それは相手がつねにみずからと同じ人間であるという考え方を根底にもっていたからである。 高須久子の入獄理由 ・高須久子は、長州藩萩城下、高三百十三石のれっきとした ・久子は陽気な性格で三味線好きだった。その趣味が高じて、浄瑠璃や京歌、チョンガレなどに凝りはじめた。三味線から「 ・このような芸能は、被差別部落の人びとが主として ・夜は酒食でもてなし、遅くなると翌朝まで泊まらせることもあった。 ・これらのことは幕藩制身分社会での社会規範からいえば、破天荒の行為であった。 このことが親類中に露見するや、一族は久子乱心と称して閉じ込め、やがて藩の取調べがなされた。嘉永四年(一八五一)のことである。 共鳴する久子と松陰 ・この取調べに際して、注目すべきことは、久子が被差別部落の人々とのつき合いを「 ・藩は彼らとのつき合いを、「密会」「密通」と決め付けようとしたが、彼女は「 ・藩は先例を勘案し、嘉永六年(一八五三)二月、久子に野山獄入りを命じた。 ・江戸・伝馬町獄から安政元年(一八五四)十月、萩・野山獄に送り込まれた松陰は、獄中でこの久子と ・松陰はここで「獄中座談会」をやり、「読書会」を行なった。周知の『 ・松陰と久子をここまで近づけたのは、男と女であったことは否定できない。しかし、松陰は、久子が被差別部落の人々と「平人同様」につき合ったのだ、という態度に共鳴したからではないか。 ・そうした久子の心が、すべての人間を同じ人間としてみようとする松陰の琴線に触れたからであろう。 「討賊始末」と私要因と久子 ・「討賊始末」とは、 ・文政四年(一八二一)、浪人 ・登波は夫幸吉の諒解のもとに仇討ちを思い立った。 ・彼女は、藩へ仇討ちを願い出た。 ・やがて、藩は、九州 ・この登波復讐事件は、長州藩安政改革の過程でクローズアップされ、仇討ちは孝道・節婦の行為とすりかえられて、安政三年(一八五六)、登波は表彰された。 翌年、当時 松陰の肖像 ・門人松浦松洞の描いた松陰の肖像 問題はその顔立ちだが、いずれも一様に老成化して描かれている。齢三十前の青年の顔とはとても思えない。弟子筋からみると、それほどに松陰はかけ離れて老成した人物に思えたのか、あるいは長期間の獄中や幽室生活で、そのようにみえるほど変貌していたのか。 ・いずれにせよ、この老成化した松陰の面貌は、松陰亡き後の松陰イメージとして一人歩きし、大きな影響を与えた、と思われる。青年松陰のイメージはいつの間にか遠くへ追いやられ、老成化したこの松陰イメージが、松陰聖域化と二重写しになっていったのである。 ・松陰が登波へ異常なほどの力を入れた契機 松陰は、宮番が差別されていたにもかかわらず、「彼の幸吉夫妻の所為は、 「解放」のための建碑 ・登波は「良民」に列せられた。だが、碑を建てることは見送られようとしていた ・松陰の思いは、登波のみの「良民」化であってはならないのだ。「建碑」によって登波個人にとどまらず、被差別の人々の「解放」が広く一般化されなければならない。それはすべての人間を差別なく等身大にみようとする松陰の主張でもあった。 ・そして、それは久子への思いとも重なる。「解放」が実現すれば、久子の釈放にも連なるであろう。 ・ちなみに、「烈婦登波碑」と大きな字で刻まれた石碑は、松陰の「討賊始末」起草よりほぼ六十年後の大正六年(一九一七)、登波の実家屋敷跡に建てられた。碑の裏側には松陰の碑文が刻み込まれている。 3 松陰のまなざし 幕藩体制下の社会的芽生え ・すでに十八世紀の中頃には、安藤昌益のように人間を社会的には平等にみようとする考え方があった。 ・十八世紀から十九世紀にかけての画家司馬江漢(一七四七~一八一八)は、「上天子将軍より、下士農工商非人乞食に至るまで、皆以て人間なり」という有名な一文を述べている。 ・備前岡山藩では、安政三年(一八五六)、いわゆる 松陰とアイヌのアイヌの人々 ・嘉永四年(一八五一)から五年にかけての東北行で ・松陰が松下村塾で、門人、熟生の出身や身分にかかわらず、個性を尊重しつつ一人ひとりに対応したことは、周知のことである。 実弟敏三郎のこと ・敏三郎は杉家の三男として、弘化二年(一八四五)に生まれた。松陰とは十五歳も年がはなれていた。 ・彼は生まれながらにして ・敏三郎の日常生活は、普通の人と少しもちがうところはなかった。みずからの機能の欠陥を自覚していたがゆえに、人の読書を熱心に見習って、字の意味を理解しようとしたが、ついに読んで言葉を通ずることはできなかった。 松陰の苦悩 ・碧瑠璃園著『吉田松陰』の一節 「あはれ此の児、不運不孝なるこの唖の児・・・」 ・このいい知れぬ苦悩こそが、松陰をして「人間とは何か」という根源的な問題へと思考を深めさせたのではなかったか。その思考の深みからあらためて目を開いたとき、人間に対する優しい目線をもつようになる。 ・弱者を弱者としてみるとうより、ひとりの人間として見直し、すべての人間をそれぞれの個性をもった等身大の人間としてみる目線でもある。それは人間をあらためて平等にみつめるまなざしといってもよい。 松陰の目線 ・松陰が松下村塾で、周知のように出身や貴賤にかかわらず、一人ひとりを個性のある人間として台頭に扱ったのはなぜなのか。 ・獄中の人々は罪は「疾」のごときもので、治せばよいのだと、性善説の上に立って獄中教育をし、彼らの釈放に尽くしたのはなぜか。 ・なぜ、被差別の人たちを「平人同様」に扱った廉で入獄していた久子に、心を通わし、共鳴しえたのか。 ・そしてまた、それとからんで、「討賊始末」に全力を傾注し、登波の「解放」を志向したのはなぜなのか。 ・これらを松陰のもっとも深いところで規定していたのは、身内のなかのこの「唖弟」敏三郎の存在ではなかったか。 ・敏三郎を巡っての、「彼の蒼なる者は天にして、一視同仁なり」という松陰の言葉。 それが松陰の内なる契機としての彼のヒューマニズムを発酵・成熟させ、外なる幕末期の政治・社会状況への危機感と結びつき、松陰の思想や行動を律したのではないか。 ・家族のなかの「唖弟」敏三郎の問題を真正面に見据えて、松陰の人間観、家族観、社会観、政治観、世界観などを見直してみたとき、松陰を長い間聖域に閉じ込めようとする松陰像とはまったく無縁な、疾風怒濤の幕末に、命を賭して生きぬいた |