
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年06月21日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
46 |
16/05 |
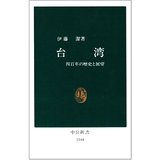 |
台 湾 |
伊藤 潔 |
中公新書 |
◎ |
序章 大航海時代の波しぶき 麗しき島・Ilha Formosa ・台湾は西太平洋で活躍するポルトガル人によって、「発見」された。 ・それは台湾付近の海域を航行中の船員が、縁したたる美しい島影を目のあたりにして、「Ilha Formosa!(イラ・フォルモサ!)」と感嘆の声をあげたことに始まる。 ・現在のところこの「発見」は、ポルトガル船の種子島漂着の翌年、つまり一五四四年のことと推定されている。 ・今日ではフォルモサは台湾をさす固有名詞となっており、とくに欧米諸国では台湾をTaiwanではなく、フォルモサと呼ぶこともしばしばである。 倭寇・海賊の巣窟 ・倭寇とは、室町幕府の統制力の衰退と戦国時代の混乱に乗じて、東アジア海域を荒らしまわった、九州、四国、瀬戸内海を根拠地とする「武装強制貿易集団」、要するに海賊のことである。 ・この集団には、かなりの朝鮮人や中国人が加わっていたことから、東アジア海域の「連合武装勢力」ともいわれており、中国の明王朝が国力を傾注して、倭寇退治に臨んだものの、ほとほと手を焼いたほどに、その勢力には凄まじいものがあったようである。 ・明王朝の衰亡の原因の一端は、ほかでもないこの倭寇掃討にあったとされる。 ・もとより中国は同じ時期に、中国人を中心とした海賊が存在したことは肯定するが、倭寇に中国人が加わっていたことは認めない。「倭」は日本人の蔑称、「寇」は盗賊のことであり、倭寇すなわち日本人盗賊団だという解釈からである。 ・倭寇と海賊は、活動の舞台が交錯していたばかりでなく、民族的にも混淆しており、両者の厳密な区別は難しい。いずれにしても、台湾が倭寇や海賊の格好の巣窟であったのは事実である。 先住民と高山国 ・ポルトガル人が「発見」した十六世紀半ばの台湾には、わずかの漢族系の移住民のほかに、先住民(今日の台湾では高山族という)と総称される、マレー・ポリネシア系の人々が先住していた。 ・先住民が「高砂族」と称されたのは、一九二三年に昭和天皇が摂政として、台湾を視察したときのことである。 ・しかし、多部族に分かれていたため、ついに台湾は先住民による統一した政権や、王権が樹立されないままに外来の民族に押されて、少数民族への道をたどるようになったのである。 タイワンの由来 ・第二次世界大戦後に台湾を支配することになった中華民国の国民党政権は、日本の統治時代に名づけられた「高砂族」を「高山族」に改めた。 ・高砂族にしろ高山族にしろ、いずれも「先進民族」と自認する日本人や中国人が、一方的に命名したものである。けっしてその民族みずからが名のったものではなく、その根底には、先住民を「未開、野蛮」としか見ず、「 ・そして台湾を支配してきた外来政権のオランダ、鄭氏政権、清国、日本、国民党政権のいずれもが、「蕃人」対策のいわゆる「理蕃政策」のもとで、先住民を漢族系の移住民から隔離し、「分割支配」の策を弄してきた。そればかりでなく、先住民の「蛮性」を意図的に印象づけてきたのである。 ・台湾の先住民の場合は大航海時代以来、今日にいたるまで常に抑圧されつづけ、近代文明から遠ざけられてきたため、独自の文化と伝統を発展させ、洗練させる環境に恵まれなかった。あまつさえ平野部から山岳地帯という、僻地に押しやられているのである。 ・もともと「タイワン」とは、かつて台南付近に居住していた先住民のシラヤ族が、外来者あるいは客人を「タイアン」または「ターヤン」と称していたのが訛って、「タイワン」となったものである。 ・「台湾」と慣用されるようになったのは、明王朝の万暦年間(一五七三―一六二〇)のことである。 ・タイワンの名の由来から見ても、先住民にとって移住民や外来者は、「客人」でしかなかった。それがいつの間にか「客人」によって「理蕃政策」の対象とされ、「蛮人」扱いされることになったのである。 台湾海峡の波高し ・インドネシアのジャカルタ(オランダ人はバタビアと改名)に本拠をおくオランダ艦隊が、台湾海峡に連なる澎湖列島をめざし、その主島である澎湖島に上陸したのは一六〇三年のことで、これが西ヨーロッパ勢力が台湾の地に足を踏み入れた最初であった。 ・一六二四年、明王朝はオランダ艦隊の澎湖列島撤退を条件に、オランダの台湾占領を認めるとともに、オランダとの貿易に同意するという停戦協定を提示した。 ・明王朝がかくも簡単に、オランダの台湾占領と領有に同意したのは、もともとこの地を領土とは見なしてはいなかったからなほかならない。 第二章 鄭氏政権下の台湾 鄭成功と反清復明 ・鄭芝龍は日本の平戸に滞在中に日本人女性の田川氏と結ばれ、一六二四年に長男の鄭森(一六二四 ― 一六六二)をもうけた。鄭森は母と弟とともに一六三一年に中国に渡った。 ・二一歳の鄭森は隆武帝に拝謁し、「朕はそなたの妻として与える娘のないことが残念である。朕を忘れず、忠義を尽くせ」との言葉と、明王朝の姓(国姓)である「朱」を授かり、名前も「成功」と改められた。これが「国姓爺・鄭成功」の由来である。 ・明王朝の最期の皇帝ともいうべき永暦帝は、各地を転々と追われる一六五三年に、鄭成功を「 ・鄭成功がオランダの台湾支配を覆し、台湾に移ったのも明王朝再興の実現のためで、台湾に新たな運命を運ぶことになったのである。 開発と誅求 ・鄭氏政権が台湾に発足するとともに、先住民は否応なしに漢族系の移住民に支配されるようになり、その生活習慣やおかれた環境のゆえに人口がさほど増えず、少数民族への道をたどらざるを得なかった。台湾を舞台とする歴史の推進力は、移住民に委ねられることになり、先住民はその脇役に押しやられたのである。 第四章 台湾民主国 台湾民主国の独立宣言 ・日清講和条約は、一八九五年四月十七日に調印された。清国政府はこの重大なできごとを、ついに台湾の官民に対して事前に知らせることはなかった。 ・一八九五年五月二十三日、「台湾民主国独立宣言」が布告された。 ・二十五日には独立式典が行われた。その独立宣言には、「 ・かくしてアジア最初の共和国が、ここに誕生した。ただし、諸外国の承認を得られぬまま日本軍の進撃により、ほどなくして消えたのである。 日本軍の台湾占領 ・日本政府は日清講和条約の締結後、台湾の不穏な動きに加え、外国の介入を恐れ、台湾の受け渡しと占領を急いだ。 ・台湾の領有権は、国際法的に清国から日本に移った。 ・一八九五年六月十七日、樺山総督は元台湾巡撫衙門(役所)で始政式を行なった。その後、日本が台湾を放棄するまで、毎年この日を「始政記念日」として式典を催している。 ・ちなみに、この巡撫衙門は台湾民主国の独立式典の会場でもあり、日本統治下で台北公会堂に改築され、さらには第二次世界大戦に敗戦した日本の、中華民国国民党政権に対する降伏式の式場となった。 ・日本の降伏式は国民党政権の台湾始政式でもあり、その後、台北中山堂と改名されて今日にいたっている。この建物こそ台湾の変遷のあれこれを眺めつづけて来た、物言わぬ歴史の「証人」であろう。 台湾民主国の崩壊 ・劉永福の脱出で中心的な指導者はいなくなり、ここに台湾民主国は崩壊したのである。一八九五年五月二十五日の建国から、わずかに一四八日間の台湾民主国ではあったが、激動のなかに生まれ、悲壮な戦いのなかに消えた共和国として、台湾の歴史に痛哭の一章を記している。 第五章 日本統治の基礎づくり 土匪の抵抗 ・日本の台湾統治は、台湾人の武力抵抗に対する鎮圧から始められた。 国籍の選択 ・日清講和条約の第五条には、二年間の猶予期間を設けて、台湾住民に対し、台湾にとどまり日本国籍を取得して日本国民となるか、それとも所有の財産を売却して台湾を去るか、のいずれかを選択する自由を与えている。 ・日清講和条約は一八九五年五月八日に批准交換された、 ・この第五条は、講和会議において日本側が提案したもので、当時、台湾の住民は割譲に反対し、徹底抗戦の構えを見せており、独立国家を模索する動きもあった。日本政府としては、住民の抵抗もなく平穏理に台湾を領有するため、割譲に反対する者には、あえて台湾にとどまり、日本国民となることを求めなかったのである。 ・しかし、実際に台湾を退去した者は約四五〇〇人とも、六五〇〇人ともされている。いずれにしても人口の一%にもおよばず、住民の台湾定着度の高さを示している。 後藤新平の生物学的植民地経営 ・台湾人の阿片吸飲は、オランダ統治時代からの悪習であった。 ・日清講和会議の席でも台湾の阿片問題が話題にのぼり、阿片吸飲対策は台湾人の武力抵抗の鎮圧とともに、日本の台湾領有の当面の重要課題になっていた。 ・後藤新平の阿片漸禁政策と専売制度は、阿片吸飲者の漸減をはかる行政目的、アヘン専売収入をはかる財政目的に加え、各地の台湾人をアヘンの仲売人と小売人に指定することで、抵抗する「土匪」の対策に協力させる治安目的にも資し、一石二鳥どころか、実に一石三鳥もの効果をあげている。 ・後藤は持論である「生物学的植民地経営」を実践していった。 ・「比良目の目が一方に二つ付いているのは、生物学上その必要があって、付いているのだ……政治にもそれが大切だ……だから我輩は、台湾を統治するときに、先ずこの島の旧慣制度をよく科学的に調査して、その民情に応ずるように政治をしたのだ……これを理解せんで、日本内地の法制を、いきなり台湾に輸入実施しようとする奴等は、比良目の目をいきなり鯛の目に取り替えようととする奴等で、本当の政治ということの解らん奴等だ」 ・後藤はこの生物学的な原理にしたがい、台湾に就任すると「土匪」の鎮圧に従事する一方、台湾旧慣調査会や中央研究所などを設立し、土地および人口の調査を実施した。 ・そしてこれらの調査と研究を基礎に、台湾統治の政策と法制を立案した。 ムチとアメの併用 ・植民地経営は人類愛にもとづく「慈善事業」ではない。軍事力という物理的な措置で領土を獲得すれば、当然に武力による抵抗を招く。その抵抗を抑えるために、またしても武力を行使することになり、抵抗が激しいほど弾圧も強化されて行く。後藤新平の「土匪」対策は、徹底したアメとムチの併用であった。 ・総督府の意向を住民に徹底させるため、「匪徒刑罰令」を布告し、「土匪」「匪徒」に対して厳罰で臨んだ。 ・後藤の就任から一九〇二年までの五年間に処刑された「土匪」は、三万二〇〇〇人にも達しており、当時の台湾人口の一%を越えている。 ・「治台三策」 台湾人の弱点を利用しての統治 ①死を恐れ、高圧的な威喝に弱い。 ②銭を愛し、利益誘導に弱い。 ③面子を重んじ、虚名と虚位で篭絡しやすい。 ・八〇歳以上の高齢者は「饗老典」に招いてもてなし、読書人には詩作や詩吟の集いの「揚文会」を催し、名望家や士紳には気前よく「紳章」を授けた。 ・投降を奨励した。投降者には刑を免除するほかに、更生資金と職業を与えた。今日も使用されている、台北から宜蘭にいたる急峻な道路は、投降した「土匪」らの手で建設されたものである。 調査事業 ・まず一八九八年に土地調査が始められ、「台湾地籍規則」と「台湾土地調査規則」が布告された。 ・この調査で台湾の耕地は、調査前に予想した三〇万甲をはるかに越して、約六二万甲となり、地租徴収の基礎となった。 ・清末の劉銘伝の清賦事業において整理できなかった耕地の二重所有形態も、大租戸に補償金を支払うことで解消し、小租戸を地主とする近代的な土地所有制度を確立した。 ・土地調査に際しては、日本国内でもまだ用いられていなかった、最新の三角測量法が採用され、台湾と付属諸島の面積と地形の測定、ひいては正確な地図の作成に役立っている。 インフラ整備 ・一八九九年七月に台湾銀行を設立、九月に開業した。 ・一九〇四年にいたり、台湾銀行券が発行された。 ・台湾総督府は一九〇一年に「台湾公共 農業振興のための水利灌漑施設の整備に関する規則であり、あわせて新たな耕地の開拓に資するものであった。 ・水利灌漑事業は、台湾の農業生産に飛躍的な効果をもたらし、地租の増収にも貢献している。 ・コメの品種改良も積極的に行なわれ、新種の「 ・台湾総督府は一九〇二年に「台湾糖業奨励規則」を布告した。 ・日本資本に対する「優遇」といってよく、土地調査で「無主」とされた官有地を無償で企業に譲渡し、砂糖の製造には補助金を提供した。 ・製糖技術と設備の近代化で、砂糖の品質と生産高は大いに高まり、税収の増加に大きく貢献した。 ・後藤新平は台湾総督府に必要な人材に対しては、異例あるいは破格とも言える条件で、多くの優秀な人材を集めている。 ・インフラの整備は、台湾領有の直後に着想されてはいたが、後藤新平のもとで本格的に着手され、その退任後も継続的に推進された。もっとも基幹的な事業として、港湾の増改築、鉄道の敷設、道路の改修と延長、通信網の整備、公衆衛生事業の推進が挙げられる。 基隆港と高雄港を増改築。 基隆と高雄の間に縦貫鉄道を敷設して、港湾と鉄道を連結。 縦貫鉄道と隋所の道路を結び、陸上交通網の整備に努めた。 日本本土との通信設備を整え、台湾各地に郵便局と電信局を開設した。 いちはやく台湾医学校を開校して医者を養成。 伝染病患者の隔離を徹底させ、住民に種痘と伝染病の予防注射を強制した。 ・これらの台湾総督府によるインフラの整備は、台湾の産業の振興と住民の健康の改善に大きく役立った。 ・交通網や通信網の整備は、台湾人の生活圏と経済圏の拡大と深化をもたらした。しかし、清国と隔離され、日本人に差別されるなかで、台湾人意識をいっそう強めさせてもいる。 第六章 日本植民地下の近代化 武力抵抗から政治運動へ ・異民族による植民地統治は、支配される民族の伝統的な文化を破壊し、政治的な従属を強制し、経済的な圧迫を加えるため、必然的に支配される民族の抵抗運動を惹き起こす。日本の台湾統治も例外ではなかった。 ・抵抗運動には武力抵抗と政治運動があり、台湾の場合は一九一五年の「西来庵事件」の前後を境に、「非合法」の武力抵抗から合法的な政治運動へと移行して行った。 台湾議会設置請願運動 ・全台湾規模で展開された台湾議会設置請願運動を通じて、幾多の台湾人の政治指導者が排出され、植民地下とはいえ台湾人が近代的な市民としての自覚に目覚め、日本人官憲の弾圧を受けるなかで、台湾人としての意識がより強められたことの意義は大きい。 教育の充実 ・一九四四年の児童の就学率は、九二・五%という驚くべき高さであり、戦闘要員の要請が急務の戦時体制下とはいえ、各国の植民地の教育状況と比較しても、台湾は格段に教育の普及に力を注いでいたことが窺える。 ・台湾ではすでに科学分野でノーベル賞の授賞者( ・確かに、後藤新平が懸念したように教育の充実は台湾人の民族意識を高め、植民地支配への抵抗運動を助長した。しかし、日本の台湾統治の最大の「遺産」は、インフラ整備におけるソフト面としての教育であり、これなくしては台湾人の近代的な市民としての目覚めは、大幅に遅れたであろう。 ・今日の台湾人年配者に多く見られる親日感情は、日本人教師の存在に負うところ大である。 ・日本が台湾を放棄した後、新たな支配者となった国民党政権は、日本植民地下の教育を「奴隷化教育」ときめつけているが、それは近代的な市民意識に対する認識を欠く為政者が、みずからの独裁と腐敗の政治を隠蔽し、責任を転嫁するための口実に過ぎない。 産業の新興 ・台湾総督府は一九三五年十月に、「台湾始政四〇周年記念大博覧会」を台北で開催した。このとき中華民国国民党政権は福建省と厦門市の幹部を中心とする視察団を派遣し、博覧会はもとより日本統治下の台湾の施政を、つぶさに視察させた。 ・視察団は帰国後の一九三七年に、『台湾考察報告』なる報告書を刊行した。この報告書は、日本の台湾統治に最大級の賛辞を惜しみなく呈しており、いわく「他山の石」「日本人にできて中国人になぜできないのか」「わずか四〇年の経営で、台湾と中国の格差は驚くばかり」と評して、日本帝国主義の台湾支配を批判するどころか、その成果に驚愕し絶賛している。 霧社事件 ・一九三〇年十月二七日の朝、中央山脈の中部にあたる ・この襲撃で日本人一三二名が殺害され、二一五名が負傷した。 ・日本人の殺害だけを目的としたところに、この事件の特徴がある。 ・霧社事件は日本の台湾統治が軌道に乗り、先住民への教化も進み、「理蕃政策」の成功が謳われていた頃のことであり、それだけに衝撃も大きかった。 ・霧社事件の発端として、日本の統治に対する不満、なかでも討伐や強制労働、官憲の傲慢な態度、権勢を笠に着ての婦女誘惑などに対する怒りの爆発が指摘されている。 ・しかしながら、先住民に対する日本語教育の普及率は、漢族系台湾人よりも高く、今日でも先住民の部族間の共通語となっているほどであり、また、太平洋戦争に突入した後、先住民だけで編成された「高砂義勇隊」が、東南アジア戦線で日本国のために勇敢に戦ったことはつとに知られる事実であり、先住民に対する日本の教化や政策を、霧社事件ゆえに一概に失敗と断じ切るのは、いかがなものであろうか。 第七章 日本戦時体制下の台湾 戦時体制下の台湾人 ・三万余の台湾人犠牲者をはじめ、負傷した軍人、軍属、軍夫は戦後、日本国籍を失ったことを理由に、なんらの補償も受けていない。 ・同じ「日本兵」として戦地で血を流しながら、戦後における日本人と台湾人の処遇には雲泥の差がある。 ・また、アメリカやイギリス、フランスなど宗主国として植民地の民を戦場に送った国々は、手厚い戦後補償をほどこしている。この彼我の違いを見れば、台湾人にたいする「一視同仁」や[皇民化」の同化政策は、ただの統治の手段に過ぎないと批判されても、いたし方あるまい。 第八章 虐殺と粛清の二・二八事件 台湾省行政長官公署と台湾警備総司令部の設置 ・国民党政権は戦勝国とはいえ、米軍の全面的な支援を得ての台湾占領であった。このときの国民党軍の低い士気とわびしい身なり、劣悪な装備を目のあたりにした多くの台湾人は、日本軍とのあまりの違いに驚愕し、日本が中国に敗れたとは、とても信じられなかった。 ・そして「日本はアメリカには負けたが、中国に負けてはいない」という噂の正しかったことを確信したのである。国民党軍への驚愕と失望は、「祖国復帰」に一抹の不安を抱かせ、期待と喜びに微かな影を落とすものであった。 祖国復帰と敵産の接収 ・一九四五年十月二十五日、台北公会堂(現在の台北中山堂)で「中国戦区台湾地区降伏式」が行われた。 ・陳儀行政長官は「今日より台湾は正式に再び中国の領土になり、すべての土地と住民は中華民国国民政府(国民党政権)の主権下におかれる」との声明を発表した。 ・この声明は台湾の領有権の変更のみならず、台湾人の意思にかかわらず一方的に、その国籍を日本から中華民国に変更するものであった。この点、日清戦争後の台湾割譲にともない、台湾住民には二年間の猶予期間が与えられ、国籍の選択が認められたのとは、著しい違いであった。 ・この日から台湾人の国籍は中華民国となり、「本省人」と称され、中国から新たに渡ってきた中国人を「外省人」と称して区別した。そしてこれ以降、十月二十五日は「 ・日本の降伏を受けて、敵産(日本企業)の接収も始まった。 ・一九四七年二月までに、土地を除き接収された財産は、一〇九億九〇九〇万円であった。当時の貨幣価値からすれば膨大な資産である。 ・接収の過程で官僚の私腹も肥やされたのである。国民党政権の官僚の貪官汚吏ぶりは、枚挙にいとまがない。 ・日本の教育が浸透し、法治国家の市民に成長していた台湾人の目には、「祖国」の官吏の公私混同と腐敗ぶりは、これまた驚嘆すべきものに映った。 接収された日本企業のその後 ・接収された主な公営および民営企業はその後、国民党政権のもとで国営、または台湾省営の公営企業となっている。 ・国民党政権はいわば「棚ボタ式」の台湾占領により、領土と莫大な財産を掌中にした。これは数年後の政権の台湾移転、台湾人のいう「祖国の台湾逃亡」を助けて余りある、国民党政権にとっての恩寵であった。 土皇帝と統治機構 ・国民党は「レーニン式の一党独裁」に近い政党であり、「 ・国民党政権は特務機関と称される治安情報組織をその統治の支柱としており、日本の敗戦直後に特務人員を台湾に潜入させ、いたるところにその組織網を広げて行った。。 ・国民党政権は台湾に移転する前から早々と、「党(国民党)」「政(行政)」「軍(軍隊)」「特(特務機関)」からなる独特の統治体制を整えていた。 ・日本統治末期の台湾総督府本庁の人員は約一万八三〇〇名であったのに対し、長官公署は約四万三〇〇〇名であった。 ・国民党政権は重要なポストや管理職のほとんどを外省人で独占した。しかも学識や経験、能力に劣る者が多かったため、台湾人の不満を募らせた。 経済破綻と社会混乱 ・国民党政権は台湾を占領し接収するとともに、台湾と日本の関係を断った。 ・台湾のあらゆる産物が不当な低価格で、中国に移出または密輸されたため、早くも一九四六年早々には、著しい物資の欠乏とインフレの昂進の二重苦に台湾人は直面していた。 ・経済状況の悪化に加えて、失業者の急増による社会的な混乱も深刻化しつつあった。 ・わけても国民党政権の意図的な台湾人排除により、就労機会は極端に減少し、三〇万人以上もの台湾人失業者が巷に溢れた。治安も急速に悪化し、日本統治時代の「法治国家」から一転して「無法地帯」になった。 長官公署に批判の声 ・国民党軍兵士の強奪や狼藉、官吏の腐敗と貪欲ぶりには目に余るものがあった。 ・台湾人は、「犬(日本人)去りて豚(中国人)来たる」とまで嘆くようになった。要するに、日本人はうるさく吠えても番犬として役立つが、中国人は貪欲で汚いというのであるが、そこには台湾人は日本人や中国人とはちがった存在であるという、潜在的な意識があることに注目したい。 二・二八事件 ・台湾人の不満が鬱積していた一九四七年二月二十七日の夕暮れどき、台北市の ・長官公署の高官やその関係者は、大量のタバコを密輸して稼いでいた。いわば密輸タバコの元締めを放置しながら、末端の街頭小売人ばかりが摘発されることに、日ごろから台湾人は不満を抱いていた。 虐殺と粛清 ・一九四七年三月八日午後、中国から派遣された憲兵第四団(連隊)二〇〇〇名と、陸軍第二十一師団一万一〇〇〇名の増援部隊は、基隆港と高雄港から上陸し、そのまま手あたりしだいに台湾人に向けて発砲した。 ・殺戮には機関銃が使用されたほか、鼻や耳を削ぎ落とした上に、掌に針金を通して数人一組に繋いだり、麻袋に詰めて海や川に投げ捨てるなど、きわめて残虐なものであった。 ・無実の罪で逮捕処刑された張七郎の妻の訴冤状 「日本の統治は独裁とはいえ、なお呉越同舟が可能であり、法にしたがいみだりに逮捕したり、処刑したりはしなかった。今日、民主の美名のもとで生命の保障がなく、官憲はしたい放題である。官が法律や綱紀にしたがわないのに、どうして民に法が守れようか」 ・台湾人の悲劇は、日本統治下で体得した「法治国家」「法の支配」の精神を、国民党政権にも期待し、幻想を抱いたことである。 ・知識人の多くは「治安警察法違反事件」(一九二三年)を経験しており、政府を批判したり抵抗しても、「悪法」とはいえ法にしたがって裁判と処罰を受けている。 ・ところが「祖国」には、「法の支配」の概念のかけらさえなく、ただあるのは、批判や抵抗する者を容赦なく「鉄砲で裁く」ことであった。 ・台湾人にたいする過剰なまでの鎮圧と殺戮は、国際社会とくに米国の厳しい批判を招いた。 二・二八事件のその後 ・「二・二八事件」に関連して、一ヵ月余の間に殺害された台湾人は、国民党政権のその後の発表によれば約二万八〇〇〇人を数える。 ・しかも知識人が粛清の標的であっただけに、台湾人の指導者のほとんどが殺害され、または「粛奸」「清郷」の名で検挙されて、長期にわたり投獄されたため、その後ながらく台湾人社会に指導者の空白が生じている。 ・国民党政権は台湾人の政治改革の要求を正面から対処することなく、虐殺と粛清で封じ、それが外省人と台湾人の対立をもたらした。今日、台湾人(本省人)と外省人の対立、つまり「 第九章 国民党の強権政治 国民党政権の台湾移転 ・中国における内戦は国民党の形勢不利がますます顕著となり、国民党政権は台湾への移転に向けて本格的な準備を進めていた。 ・一九四八年、蒋介石の腹心である ・同時に蒋介石の長男の ・また、次男の ・陣誠主席は、一九四九年一月に戒厳令を施行した。この戒厳令は、一九八七年七月十五日に解除されるまで、実に四〇年に迫る世界一長い戒厳令となった。 ・一方、中国大陸では中国共産党と中立勢力の反対を無視して、国民党政権は一九四七年一月に「中華民国憲法」を布告し、翌年の三月に第一期の国民大会が招集され、蒋介石を総統に、 ・しかし、戦局はますます悪化し、蒋介石の下野を要求する声が高まるなかの一九四九年一月に、蒋介石は国民党総裁のまま総統を辞任、下野した蒋介石はその後台湾に渡り、一九四九年八月一日に台北近郊の陽明山に「中国国民党総裁弁公庁」を開設し、ここから国民党総裁として諸機関を指揮し、命令を下した。 ・この頃、頼みの綱である米国政府の国民党政権に対する失望は高まり、八月五日に発表された『中国白書』は、国民党政権の失敗の原因は腐敗と無能にあり、「不信の政権」と断定して、国民党政権を見限ろうとしていた。 ・そして十月一日、中国共産党が中華人民共和国の建国を宣言し、国民党の敗北はいよいよ決定的となった。 ・国民党政権は台湾に移転した後も、一貫して中国共産党の中華人民共和国を認めず、中華民国こそ「唯一の中国」、国民党政権こそ「中国の正統政府」であることを固持している。 ・いわゆる「二つの中国」または「一つの中国、一つの台湾」の問題の原点はこにあり、その後の国際社会における台湾の立場を困難に陥れている。 朝鮮戦争と米国の軍事保護 ・国民党政権に追い撃ちをかけるかのように、米国のトルーマン大統領は一九五〇年一月五日に、「台湾海峡不介入」を声明した。つまり中国の共産党軍(中国軍)の台湾侵攻に、米国は関与しないことを意味する。 ・米国にまさに見放されようとしていた国民党政権にとって、「救いの神」ともいうべき朝鮮戦争が、六月二十五日に勃発した。 ・トルーマン大統領は六月二十七日に、一転して「台湾海峡の中立化」を声明し、これより以後、台湾は米国の軍事保護下におかれ、冷戦構造下の西側陣営の一員となる。朝鮮戦争の勃発は、国民党政権ならびに台湾人の運命を左右する重大なできごとであった。 ・一九五一年一月には、米国政府は国民党政権に対する軍事援助を復活、一九五四年十二月には「米華共同防衛条約」を締結した。 ・その後、国際情勢の変化により、一九七九年一月の米中国交正常化を境に、台湾と米国の国交はなくなったが、米国は同年四月十日に「米華共同防衛条約」に代わる、国内法の「台湾関係法」を制定して、台湾を「政治的な実体」と認め、実質的な関係を維持し、台湾の防衛に必要な武器を有償で提供しつづけてきた。 ・国民党政権は米国の保護下の台湾で生き延び、体制づくりに専念することができたのである。 一党独裁と蒋家の支配体制 ・国民党の性格は共産党とほぼ同じで、革命が成就、つまり「三民主義」(孫文の主張する「民族主義」「民権主義」「民生主義」)が、全中国に実現するまで「革命」をつづける「革命政党」であり、党首(蒋介石のときは総裁、その後は主席)に絶対的な権力を集中させた。 ・蒋経国は一九六五年一月に国防部長に就任、蒋介石は一九六六年五月に第四期の総統に就任、その後蒋経国は一九六九年六月に副院長に就任した。 ・一九七二年五月に蒋介石と ・そして一九七五年四月に蒋介石が死亡すると、国民党の党首には蒋経国が就任した。 ・それから三年後の一九七八年五月、党主席の蒋経国が第六期総統に就任すると、党主席と総統を兼ねることになり、いわゆる「蒋家王朝」が実現したのである。 国民党と蒋介石父子の軍 ・中国の政治文化には「投票箱から政権が生まれる」という発想はない。毛沢東が言ったように「鉄砲のもとで政権が生まれる」のが、中国政治の真髄である。 ・国民党政権は中国大陸奪還をめざして、「一年準備、二年反攻、三年掃討、五年成功」の「反攻大陸」のスローガンを掲げ、長きにわたり喧伝してきた。しかし、いつの間にか「反攻大陸」のスローガンは消え、逆に中国の武力侵攻に備える「専守防衛」の国防体制に変わっている。 第十章 奇跡の経済発展 幣制改革と土地改革 ・国民党政権は、一党独裁の強権政治体制を構築する一方、経済の再建と復興を最優先させた。これがいわゆる「開発独裁」である。そして経済の再建と復興にとどまらず「奇跡」といわれるほどの成長を成し遂げた今日、台湾の「開発独裁」は「台湾経験」(台湾モデル)として、開発途上国の範とさえされている。 ・中国共産党関係者の潜入を防ぎ、かつ人口の過剰流入を抑制するため、警備総司令部は一九四九年二月から、許可された者以外の台湾入境を認めなかった。 ・中国と台湾の貨幣の関係を断ち、従来の四万台湾元を一新台湾元(NT$、これ以後の台湾元はすべて新台湾元)とする、デノミネーションを断行した。 ・翌一九五〇年六月に朝鮮戦争が勃発するにおよび、トルーマン米大統領の「台湾海峡中立化」宣言により、台湾と中国の関係は完全に分離したのである。 台湾経済の問題点 ・中国のマーケットに過度に依存することは、台湾経済が中国に左右され、中国経済に吞み込まれる危険性をはらんでいる。明らかに中国政府には、台湾経済を中国依存に仕向ける意図が窺え、当面は経済的な緊密化をはかり、将来的には政治的な「統一」をめざしている。中国マーケットの拡大に、喜んでばかりはいられない。 第十一章 急テンポで進む民主化 李登輝の民主化政策 ・李登輝の政治スタイル、政治信念 ①党が国家の上位にあってはならない、 ②軍は「党の軍」ではなく、「国家の軍」でなければならない、 ③民主政治は政党政治であり、一党独裁であってはならない、 ④国際社会で孤立してはならず、実務外交を推進すべきである、 ⑤中国政府・中共政権と対立してはならない、 ⑥政治犯の存在は政治的な開発途上国であり、民主国家の恥である、 あとがき ・一八九五年に始まる日本の統治時代には、後藤新平の「生物学的植民地経営」にもとづく旧慣調査の一環として、台湾の史料調査と整理も行なわれ、台湾総督府は一九二九年から『台湾関係史料』を刊行している。 ・一九四五年に始まる国民党政権の統治においては、台湾関係史料の整理どころか、「中国唯一の正統政府」を固持し、その台湾支配を正当化するために、「台湾は中国の固有の領土」であると教え、台湾の歴史を恣意的に歪めてきた。台湾において永らく台湾史の研究と教育が阻害されてきたのは、政権の正当性の矛盾を衝かれることを警戒したからにほかならない。 ・四〇〇年に近い台湾の変遷を振り返って見れば、ことに半世紀におよぶ日本の統治は、善きにつけ悪しきにつけ、今日の台湾の基礎を築き上げたといえよう。 ・少なくとも台湾は、日本の統治で「植民地下の近代化」を成し遂げたことは事実であり、わけても教育制度の整備と普及は、大書特筆すべきものである。国民党政権が台湾を「接収」すると同時に、義務教育を施すことができたのもその恩恵といえる。 ・台湾の歴史は「外来政権」の支配の歴史であり、物理的な武力装置による「帝国主義」支配の歴史でもある。それゆえに私は、日本の台湾統治における「植民地下の近代化」を強調するのである。 ・日本の台湾統治に対して最大級の賛辞を呈したのは、ほかでもない中華民国政府(国民党政権)が、一九三七年に刊行した『台湾考察報告』なる報告書である。 ・『台湾考察報告』があるにもかかわらず、戦後、国民党政権は日本の台湾統治を否定し、日本による教育を「奴隷化教育」ときめつけている。 ・台湾人に対する虐殺と粛清である一九四七年の「二・二八事件」は、この「奴隷化教育」による知識人の一掃をはかったものであり、公的な発表でも二万八〇〇〇人が殺害された。 ・今日、国民党政権による公式な謝罪こそないが、民主化の流れのなかで、犠牲者への国家賠償条例の制定と、責任の追及がなされようとしている。そして、この「二・二八事件」をはじめ、国民党政権が恣意的に歪めてきた歴史の書き換えも始まろうとしている。 ・いずれ日本統治の台湾史における位置づけも変わり、「植民地下の近代化」にも光があてられるであろう。 ・李登輝総統・国民党主席が掲げる中国との統一の条件 ①政治の民主化 ②経済の自由化 ③社会の公平化 ④軍隊の国家化 |