
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年06月27日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
49 |
16/05 |
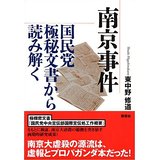 |
南京事件 国民党極秘文書から読み解く |
東中野修道 |
草思社 |
☆ |
第一章 極秘文書発掘 ……… プロローグに代えて ・蒋介石の国民党は当初から軍事的に劣勢であったため、昭和十二年(一九三七)十二月十三日の南京陥落の直前から宣伝戦に総力を挙げていた。 ・「現代の戦争は武力を用いることを除けば宣伝もまた勝敗を決する一つの要因である」と考えていた中央宣伝部は、「宣伝は作戦に優先す」を合言葉に、宣伝戦で日本を ◆現在の南京大虐殺の根拠となった『戦争とは何か』 ・長いあいだ、大部分の人のあいだで南京大虐殺が話題にのぼることはなかった。教科書に記載されることもなかった。あたかも南京大虐殺は有名無実であるかのごとくであった。 ・ところが、今ではわが国のすべての教科書に掲載されている。 ・その それから一年後の昭和四十八年(一九七三)に、大虐殺はあったのだと主張する人々によって英語版の『戦争とは何か――中国における日本軍の暴虐』が発掘され、大虐殺の根拠として提示される。 ・この本は、上海にいた英国の『マンチェスター・ガーディアン』紙中国特派員ハロルド・ティンパーリ記者が南京在住の欧米人(匿名)の原稿を編集して、昭和十三年(一九三八)七月にニューヨークやロンドンで出版したものであった。 ・この『戦争とは何か』の評価が一躍高まったのは、その後になって、匿名の執筆者がマイナー・ベイツ教授と宣教師のジョージ・フィッチ師であると判明したからであった。 ・この『戦争とは何か』を典拠として、それから次々と南京大虐殺を主張する本が出た。 ◆『戦争とは何か』は宣伝本ではなかったかという疑惑 ・近年の研究により、南京大虐殺が歴史的事実と決め付けられないことは誰の目にも明らかになっている。 ◆極秘文書『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』を手にして ・探し求めていた中央宣伝部の史料は、台北の国民党党史館に眠っていた。 ・中央宣伝部には九つの機関があった。そのなかの国際宣伝処の資料の一つが『戦争とは何か』に関係がある『中央宣伝部国際宣伝処工作概要 一九三八年~一九四一年四月』であった。冒頭に「極機密」の印が押されている極秘文書は、見るのも手にするのも初めてであった。 ・極秘の『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』は、国際宣伝処の各部門が「一九三八年から一九四一年まで」の三年間にいかに宣伝工作をしてきたか、その工作内容を秘密報告した極秘文書であった。 ◆やはり『戦争とは何か』は対敵宣伝本だった ・私が中央宣伝部の史料を探し求めたのは、『戦争とは何か』が国民党の「宣伝本」ではないのかという推測の可否を確定するためであった。 ・それは極秘文書中の「対敵課工作概況」のなかの「(一) ・単行本の内、『外人目撃中の日軍暴行』は英語版『戦争とは何か』の漢訳版であった。ティンパーリ編『戦争とは何か』は、中央宣伝部が編集制作した二冊の宣伝本のうちの一つであった。 ・『戦争とは何か』は中央宣伝部の製作した「宣伝本」だったことが確認された。長いあいだ南京大虐殺の根拠となっていた『戦争とは何か』とその巻末に収録された資料は、戦争プロパガンダの視点から見直さねばならなくなったのである。 ◆戦争プロパガンダの視点から新たな検証へ ・『戦争とは何か』が中央宣伝部の製作した宣伝本だからと言って、それがただちに南京大虐殺はなかったということを意味するものではない。 ・ところが、第一回の訪台で入手した極秘文書を見直しているうちに、ふと不思議なことに気づかされた。『戦争とは何か』には「度重なる殺人」といった描写が頻出するにもかかわらず、「対敵課工作概要」を読んでも『戦争とは何か』を要約した記述のなかに「虐殺」はおろか「殺人」という言葉すら見当たらないではないか。誰が『戦争とは何か』を要約しようが、この本には「虐殺」「殺人」が描写されていると要約されて当然であったのではないか。 ・『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』という極秘文書の特徴 まず第一に、これは同時代の記録であった。中央宣伝部があらゆる手段を駆使して掴んだ日本軍の動向にもとづいて、中央宣伝部国際宣伝処が展開した三年間の宣伝工作を総括していた。 次に、これは個人的な回想とか日記とは違って、当時わが国と戦っていた中央宣伝部が総力をあげて総括した公的な記録であった。 第三に、これは決して外部に漏れないよう秘密裏に記された、ということは内部向けに報告された極秘報告であった。 第二章 国際宣伝処ができるまで 一九三七年(昭12)十一月十二日の上海陥落後、蒋介石は首都南京の死守を決定したものの、国民党軍の敗北は誰の目にも明らかであった。しかし蒋介石は、広大な国土を武器として日本軍を大陸の奥深く引き込みさえすれば、勝てなくても負けないという長期消耗戦の戦略に立っていた。 そしてもう一つ。蒋介石は「宣伝は作戦に優先す」という「世界戦略」の宣伝戦に乗り出していた。その本格的な展開のため、南京戦の直前、第二次国共合作のもと、国民党員と共産党員が結集した国民党中央宣伝部のなかに、国際宣伝処が組織される。 ◆第二次上海事変の勃発から日中全面戦争へ ・蒋介石は日中全面戦争となることには慎重であった。上海南京戦区司令官の ・しかし、それにもかかわらず張治中将軍は蒋介石の命令を無視して攻撃をつづけ、八月十八日、事態は日中全面戦争へと進んでしまった。 ・日中全面戦争のきっかけを作ったのは、ほかならぬ張治中将軍であったという。彼は国民党の中枢に潜んでいた共産党のスパイであった。 ◆国際友人を使っての宣伝活動 ・一九二八年(昭3)に中国へ渡り、一九三六年(昭11)夏には延安を訪れて、外国人としては初めて毛沢東や朱徳ら中国共産党の幹部と会見したアメリカ人ジャーナリスト、エドガー・スノウは、現在、北京大学構内の墓に眠っている。つまり、スノウは毛沢東の中国共産党とは深い関係にあった。 ・国民党と共産党は第二次国共合作下によって同盟関係にあったものの、根深い敵対関係にあったことも垣間見られる。 ・共産党はアメリカ人スノウを使い、国民党もアメリカ人の学者や教会関係者を使って非難の応酬を繰り返していた。しかし彼らはともに反日の国際宣伝を支える国際友人であった。 ◆外国人記者の記事にたいする厳格かつ綿密な検査 ・国際宣伝処は、中国駐在の記者が発進した電報を各国の新聞が載せれば、「極東情勢に注目している国際人にはそれを重視する」と判断していた。彼らが国民党政府の見解と相容れない見解や、中央宣伝部に不利な事柄を徹底的に検閲していた。 ・厳格で綿密な検閲こそ、国際宣伝をスムーズに展開するうえで最も重要なことであった。 ◆対敵宣伝の狙い ・外国人を動かして行う宣伝活動とは、中央宣伝部の宣伝と見破られないよう、国際団体、国際友人、外国人記者を動かして英語、フランス語、ロシア語などで行う宣伝工作のことであった。 ・それにたいして、「対敵宣伝」は、読んで字のごとく、敵である日本軍と日本人を対象とする情報戦であった。 ・極秘文書中の「対敵課工作概要」の対敵宣伝についての記述 「対敵宣伝は、文字、絵画、放送などがあり、中国にいる敵軍、敵国内の人民、及び海外の世界各地に居住する敵国の人間にたいして、幅広く宣伝をし、敵の軍閥の残酷なることと、必ずや失敗するという真相を暴き、厭戦感情をあまねく盛り上げる」 ◆国内外の日本人にたいする対敵宣伝 ・中央宣伝部の撮影課は一九三八年(昭13)から本格的に、人の目に訴えるニュース用写真や映画用写真を、宣伝工作の一環として作成し始めていた。そして、一九三九年(昭14)になると、世界に出回る中国関係の写真の九五パーセントは、中央宣伝部直属の中央通信社の提供するものとなった。 第四章 南京大虐殺が報じられるまでの序曲 ◆ラーベ委員長の周辺・その二・・・・・・中国軍将兵を匿う事態に ・中立的立場であるべき国際委員会のメンバーが中国軍将兵を匿うという行為は、安全地帯への中国兵「立ち入り」を禁ずるという公約を、ラーベ委員長みずから破るものであった。 ◆ラーベ委員長周辺・その三・・・・・・中国軍将兵は何のために残されたのか ・安全地帯に潜んだ中国兵が悪事を働き、日本軍のせいにしていた事例は、南京の同盟通信が二月二十六日に配信した「皇軍の名を ・それによれば、南京憲兵隊は、安全地帯内で日本軍の名を騙って掠奪暴行のかぎりを働いていた ・この十一名はもともと警官であった。 ◆中国兵を武装解除し安全地帯のなかに入れてしまう ・十二月十二日二十時、城門陥落の数時間前に、狭い出口が唯一開いていた ・城門で日本軍と戦っていた中国兵のあいだにパニックが生じたのは当然のことであった。そして、それぞれが次のような行動に走った。 ・一つは、城内から城外に脱出することであった。 ・ところが挹江門の前には、命令どおり中国軍の督戦隊が待ちかまえていて、戦線から離脱しようとする有軍兵士に発砲し、射殺していた。 ・しかし、危機的状況はやがて督戦隊も感知するところとなった。督戦隊が逃げ出すと、つづいて多くの兵士が狭い脱出路に殺到した。 ・日本軍の ・しかし、これは、友軍の督戦隊に射殺されて死んだ兵士か、一度に狭き門に殺到したため圧死した兵士か、いずれかの死体であった。 ・二つ目は、挹江門から逃げられないと判断した兵士たちは、城壁の上からロープを降ろして城外に脱出しようとした。 ・三つ目は、武器を投げ捨て軍服も脱ぎ捨てて市民になりすまし、安全地帯に潜伏して南京の避難民のなかに紛れ込むことであった。 ・城内から城外への脱出が明らかに不可能と判明するにつれ、この第三の道が唯一残された方策となった。 ・兵士と市民を区別することは最低限の義務だと、国際委員会は、はっきりと認識していた。明らかに知っていながら、そうはしなかった。 ・つまり積極的に市民と兵士の区別に努めるどころか、武装解除したと称して、軍服を脱いだ中国兵を市民の中に野放しにしていた。軍服を脱いだ兵士と市民の混在、これはどこの国の軍隊にとっても危険な状態にほかならない。 ・陥落後、南京に入ってきた日本軍がその危険な状態をどのようにして、市民だけが存在する普通の状態に戻すか、すなわち市民と兵士を区別するために兵士を摘発し、それに付随して処刑に及ぶであろうことは、国際委員会も当然予測していたであろう。 ・要するに、日本軍による摘発と万が一の処刑という軍事行動は、国際委員会の作り出した兵民混在という状況を解消するには必要不可欠であった。日本軍は国際委員会の大失態の後始末を余儀なくされたのである。 第五章 アメリカの新聞記事も中央宣伝部の宣伝戦だったのか ◆南京占領を高価にする別の計画があった ・蒋介石は唐生智将軍を南京防衛司令官にして南京死守を宣言したが、将軍は南京を放棄して敵前逃亡した。これは許されざる行為であった。 ・したがって蒋介石政府が唐将軍の逃亡から六日後の十二月十八日に「軍事裁判の結果(唐生智将軍に)死刑を宣告」した。 ・ところが、唐将軍は処刑されていなかったのである。 ・唐将軍は一九四九年(中華人民共和国成立の年)に国民党を捨てて共産党に走り、戦後も共産党政権下で ・唐生智処刑という重大発表は蒋介石政府しか流せないから、その発信源は蒋介石の中央宣伝部しか考えられない。そうなると、蒋介石政府は唐将軍を処刑したというウソをついたことになる。 ・なぜ蒋介石は背信行為を犯した唐生智将軍を処刑しなかったのか、なぜ将軍は敵前逃亡しながら不問に付されたのか。 ・その答えとしては、唐生智逃亡はあらかじめ蒋介石も承認していた。蒋介石政府の南京死守は表向きの宣言であり、唐生智逃亡は最初から織り込みずみだったのではないか。 ・唐生智将軍逃亡は南京攻防戦の幕引きであり、中国情報戦の幕開けであった。 ◆アメリカの新聞記事に反応はなかった ・「南京大虐殺物語」がアメリカの新聞に出たとき、怒りを表明して日本に抗議し続けるべきだったのは国民党政府であったことだ。しかし実際は、中国外交界のの大立者の顧維鈞が、国際連盟で演説しただけであり、それはそのときかぎりであった。 ◆中央宣伝部は「南京大虐殺物語」を虚報と認識していた ・国民党政府がアメリカの新聞記事を根拠にして、「南京大虐殺」を世界に向けて公言したのは、国際連盟における顧維鈞の演説が最初にして最後であった。このことは、アメリカの新聞に載った「南京大虐殺物語」が虚報であると、中央宣伝部が認識していたからだ、としか言いようがない。 第六章 宣伝本『戦争とは何か』を改めて検証する ◆検証2――『戦争とは何か』の第二章 ・注意すべきは、当時、南京大学附属病院に行き、日本軍に暴行されたと申告さえすれば、無料で治療を受けることができたということである。 ・焼き払われたと言われる南京の繁華街は陥落後直ぐに日本人街〔日本人が買い物や飲食のできる街〕に指定されている。 ・誰かから聞いた話を、あたかも目撃したかのように書いている。 ◆検証4――『戦争とは何か』の第四章前半 ・ベイツ教授やフィッチ師の言う「度重なる殺人」を突き詰めていくと、それは陥落後三日間の掃討の際の処刑でしかない。 第七章 中央宣伝部は南京大虐殺はなかったと考えていた ◆戦時国際法から見た陥落後の中国兵 ・人を殺すことは平時においては罪であるが、戦争においては合法である。戦争とは敵を殲滅して、どちらかが降伏して初めて終わる。 ・戦場は生きるか死ぬかの場であるが、しかし敵を殺し合う戦争にも一定のルールがあった。それが戦時国際法の交戦法規である。 ・一九三七年(昭和12)当時の現行法はハーグ陸戦法規で、それは「交戦者の資格」として次の四条件を定めていた。 ①部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト ②遠方ヨリ認識シ得ヘキ固着ノ特殊標章ヲ有スルコト ③公然兵器ヲ携帯スルコト ④其ノ動作に付着キ戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト ・法を守る者は法に守られ、法を破る者は法に守られない。日本軍が南京に入ったとき、安全地帯にいた中国兵はハーグ陸戦法規の定める四条件を守っていたであろうか。そして捕虜と認定されるための法的資格を有していたであろうか。 ・①の指揮官について言えば、南京では ・中国兵は明らかに右の三条件を破り、ハーグ陸戦法規の起草者が夢想だにしなかった ◆今も変わらない鉄則 ・安全地帯に潜伏した中国兵は当時の戦時国際法から見て、交戦者の資格を失っていた。これは、交戦者が敵の手に落ちたとき、捕虜となるための資格を失っていたことを意味する。この「交戦者の資格」がいかに重要か。これは今日においても変わらない。 ・二〇〇二年(平14)一月、キューバのグアンタナモ米軍基地に、アルカイーダやタリバンの兵士が拘束された。一月十二日付の『朝日新聞』は、ラムズフェルド国防長官が「戦時捕虜〔戦争捕虜〕の待遇を定めたジュネーブ条約は(抑留者には)適用されないとの見解を表明」したことを伝えていた。 ・ラムズフェルド長官は、戦闘員は捕らえられたとき、四条件の全てを満たしていて初めて戦争捕虜として遇されると言う。 ・これは「捕虜の待遇に関する一九四九年八月十二日のジュネーブ条約(第三条約)」に立脚する見解であった。 ・第三ジュネーブ条約(捕虜条約)の「第四条(捕虜となるもの)」に ①部下について責任を負う一人の者が指揮していること ②遠方から認識することができる固有の特殊標章を有すること ③公然と武器を携行していること ④戦争の法規及び慣例に従って行動していること これはハーグ陸戦法規の第一条「交戦者の資格」と本質的に同じである。 ・ラムズフェルド長官は、人はみな四条件を満たして戦闘に従事しなければならないと強調している。戦闘員は、軍服を着て、武器を見せて、組織的作戦について初めて合邦戦闘員とみなされる。そして合邦戦闘員であって始めて、敵の手に落ちても助命という最高の保護を与えられる。したがって、これらの条件を満たさない不法戦闘員は、この助命という最高の保護を享受できないというのである。 ・今日の鉄則から見ても、また当時の鉄則から見ても、南京の中国軍将兵はこの四条件のうちの一つすら満たしていなかった。彼らは戦争捕虜ではなく、「不法戦闘員」の範疇に分類されよう。 ◆軍服を脱いだ中国兵をどう見るか ・中国軍の将兵が軍服を脱ぎ捨て、市民になりすまして潜伏している状況下で、日本軍はどうすればよかったのか。そのままに事態を放置しておいてよいのかどうか。 ・南京は陥落したが、中国軍は降伏して来なかった。私たちは戦争がまだ終わっていなかったことを頭の中に入れておかねばならない。戦闘は次の戦場へと続いていた。南京戦はこの連続する戦闘の一部であった。 ・戦闘が続くなか降伏もせず、巨大な城壁に阻まれて脱出できない中国兵が勝手に軍服を脱いだところで、日本軍としてはそれを直ちに降伏と認めることはできなかった。 ・降伏とは敗者が勝者に屈服する際の「一つの契約」であったにもかかわらず、南京防衛軍司令官は日本軍の降伏勧告を拒否したうえ敵前逃亡し、中国軍の誰も日本軍との契約を結んでいなかったからである。 ・それどころか、南京では、放置しておけば危険な事態が十分に考えられた。 ・戦闘員が非戦闘員のようにみせかけて不意に反撃に出るという事態が南京で生じることも、完全には否定できなかった。日本軍がそれを考慮に入れるのは当然であった。なぜなら、中国軍は全軍揃って降伏しなかったから戦闘中であるとみなされ、日本軍もまた戦闘中であったからだ。 ・したがって、たとえ中国兵が軍服を脱ぎ市民のように見えたとしても、戦っている日本軍からすれば、城内に潜伏する中国兵は「市民」でも「元兵士」でもなく、戦闘中の兵士以外の何ものでもなかった。敵の兵士が安全地帯にいるかぎり、戦闘は続いていると認識するのが当然である。 ・では日本軍はどうすればよかったのか。戦闘に終止符を打つためには、本当の市民と軍服を脱いだ兵士とをまず区別するのが、その第一歩であった。それが掃蕩戦の際の摘発である。そして次に反抗した兵士にかぎって処刑する。これは戦時においては自然の流れであった。 ・その処刑の対象となった「中国人」「男」「元兵士」というのは、軍服を脱いで安全地帯に潜伏していた中国兵だったのである。 ・軍服を脱げば兵士でなくなるかと言えば、そうではない。いったん兵士になった者は除隊しないかぎり、いつまでも兵士であり続ける。 ・今になって思えば、中国兵が軍服を脱がずに指揮官の指揮のもとに、進んで降伏していたならば、また国際委員会が武装解除と称して一部の中国兵に軍服を脱がせていなかったならば、中国兵は日本軍に捕らわれても捕虜の資格を得ることができたであろう。 ・日本軍とても、軍服を脱いで市民になりすまし、武器を隠し持った中国兵がどのような行動に出るかという猜疑心にとらわれることなく「交戦者と非交戦者の区別」を難なく行って、残敵掃蕩は困難を極めなかったであろう。ひいては、兵士の摘発の際に市民が間違って摘発されたのではないかとの疑念が湧く余地もなかったであろう。その後の掃蕩にまつわる問題も起きなかったであろう。 ・兵士の軍服着用は、戦闘員として守るべき最低限の条件であり、鉄則であった。日本軍は所与の状況を鑑みながら、「残敵ヲ掃蕩シ以テ南京城占領ヲ確実ナラシムル」ため、国際法にもとづいて作戦を展開したまでのことであった。 ◆中央宣伝部はベイツ教授の二文を削除する ・中央宣伝部は英語版の『戦争とは何か』と同時に、その漢訳版の『外人目撃中の日軍暴行』編集印刷を進めていた。 ・ところが中央宣伝部はそのとき、一方では英語版に次のベイツ教授の二文を印刷しながら、他方では漢訳版からはそれをそっくり削除していたのである。 ・削除された二文とは、ベイツ教授が『戦争とは何か』の第三章に書いていたAとBの二文であった。 A「埋葬隊はその地点には三千の遺体があったと報告しているが、それらは大量死刑執行の後、そのまま並べられたままか、あるいは積みかさねられたまま放置されていた」 B「埋葬による証拠の示すところでは、四万人近くの非武装の人間が南京城内または城門の付近で殺され、そのうちの約三〇パーセントはかつて兵隊になったことのない人びとである」 ・中央宣伝部は『戦争とは何か』の草稿を念入りに点検したであろう。そこにこの二文が目についた。それは「妥当性に欠ける」として問題になったと思われる。中央宣伝部の情報戦にとっては、捨てがたい二文であったが、だからと言って二文を削除しないまま出版することは、中央宣伝部にはできなかった。その苦悩の結果、中央宣伝部は次のような選択に出る。 ・つまり、アメリカやイギリスなどで出版された欧米向けの『戦争とは何か』には、読者が「極東情勢」の実情に疎いため、二文をそのまま載せることにした。『戦争とは何か』は、第三者的立場の外国人が戦争の悲惨さを訴えるため独自に出版した形式となっていたため、中央宣伝部の関与した痕跡は認められず、批判は出てこないと呼んでいたのであろう。 ・しかし、南京の実情に精通した人々が多くいる中国向けの漢訳版(『外人目撃中の日軍暴行』)では、この二文の削除が無難と判断した。事情通がこの二文を嘘と非難したなら、すなわち、この二文の是非をめぐって正式に調査がなされたにらば元も子もなく、かえって危険だ、と中央宣伝部は用心したからだ。もしそうなれば、二度と「南京」を情報戦に使えなくなる。そのことを恐れた中央宣伝部は、これまでの努力が水の泡になるよりも、それを削除する無難な道を選んだのである。 ・いずれにせよ、中央宣伝部がベイツ教授の婉曲的な「日本軍(四万人)不法処刑説」を削除したのは事実であった。 ◆ベイツ教授自身も「日本軍(四万人)不法処刑説」を否認していた ・埋葬証拠が示す「公称四万」の埋葬体のなかに、戦死体が少なからず含まれていた。残るは処刑によって生じた死体であろう。ベイツ教授の言う「非武装の人間」〔武器を投げ捨て、軍服を脱ぎ捨てた兵士〕にたいする処刑は不法だったのかどうか。そのなかに「かつて兵隊になったことのない人々」〔非戦闘員〕がいたのかどうか。その証拠はあったのかどうか。 ・この問題を、中央宣伝部と国際問題研究所は国際法と南京の実情から検討していた。その結果としてベイツ教授の一文を「妥当性に欠ける」と判断し、削除を了解するよう求めたものと思われる。 ・ベイツ教授は国際法の何たるかを知っていた。そして、日本軍の処刑は戦時国際法に照らして合邦であることも知っていたのであろう。だからこそ削除に抗議もせずに同意したとしか考えられない。 第八章 極秘文書は玉手箱だった ◆戦争プロパガンダの視点に立って ・まず初めに「対敵宣伝本」を作るという中央宣伝部の計画があった。そして、そのためにさまざまな工作が行われた。そうしてできあがったのが『戦争とは何か』であった。『戦争とは何か』は、中央宣伝部の宣伝工作の総決算であったから、それが目的達成の成果として極秘文書には報告された。したがって『戦争とは何か』は中央宣伝部が総力を挙げて取り組んだ、ないものをあるかのように見せかけた巧妙な拡大宣伝の精華であった。あれもこれも、すべては、『戦争とは何か』の作成という目的に向かって |