
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年06月27日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
54 |
16/06 |
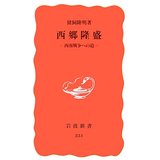 |
西郷隆盛 |
猪飼隆明 |
岩波新書 |
〇 |
Ⅰ 幕末動乱の主役として 二 王政復古から武力討幕へ 三職制の性格とは ・「王政復古の大号令」は、前半で「摂関・幕府」を廃して「 Ⅱ 「有司専制」の成立 一 新たな権力機構樹立の模索 藩と絶縁することの難しさ ・藩主あるいは藩首脳と対立しつつ尊攘・倒幕に奔走して、ついに御恩・奉公という封建家臣団にとってのもっとも大事な関係、中世というもっとも重要な封建的倫理を捨てるにいたる行為、これが脱藩だが、この結果、自藩という狭い視野を克服して、国家レベルの視野を獲得するという重要な資質が、その人物に賦与されることになるのである。 二 「有司専制」への途 ・のちに自由民権派が、中央政府を「有司専制」と非難したことは有名である。 ・有司とは官吏のことだから、本来の意味は官吏独裁ということになろうか。 ・この「有司専制」は、「藩閥政府」と同じ意味でつかわれることもあるが、わたしはまったく違ったものであり、それどころか正反対の意味さえもちと考えている。 版籍奉還と徴士制度改革 ・中央集権化の起点としてまず注目すべきは、一八六九(明治二)年の版籍奉還である。版とは土地台帳、籍は戸籍簿のことで、すなわち領土と人民を朝廷に返還するというのである。すべての土地と人民は天皇に属するという、王土王民思想を具現するものであった。 「有司専制」にとっての天皇 ・形式上、天皇の裁可が絶対であり、それをみずからの正当性の根拠とする以上は、次のことが満たされねばならない。 ・一つは天皇への上奏権をもつものを有力な一員としていること、いま一つは天皇がその上奏に対して拒否したりしない、また重要な修正を要求しないということである。 ・天皇は有司専制を正当化し、権威あらしめる存在として、またその役割のみが期待されるのである。 ・そのことによって、はじめて権力内の権力として有司専制が機能した。 ・天皇への上奏権をにぎっていることの強みは、重大な政変をもたらした征韓論争の場において、遺憾なく発揮されることになる。 Ⅲ 征韓論争 一 「使節を暴殺に及び候」 強硬な談判を主張する議案 ・一八七三(明治六)年夏のある日、、外務省から太政官に朝鮮問題についての議案が提出された。朝鮮の「非礼」を糺すため、出兵をも辞さない強硬な談判を行なおうというものである。 ・新政府発足以来、朝鮮との国交は樹立しておらず、政府にとっての重大な懸案事項の一つとなっていた。だが、「非礼(修好書受取拒否、「草梁倭館」問題他)」は、事実かどうかにおいてすでに問題があり、仮にそうだとしても、朝鮮との間に緊張関係をもたらしたのは、日本の強引な態度であった。 ・「 だが日本政府は、七二(明治五)年、廃藩置県による対馬藩消滅を期に、一方的に外務省管轄のものとして接収した。この行為が朝鮮政府を刺激したことは想像に難くない。 しかも、この「倭館」を拠点に日本商人の密貿易が始められる。正式の国交が樹立されないままの、こうした行動に朝鮮が硬化するのは、理の当然であった。 四 「征韓論」の系譜 ・征韓論争で争われたのは、「征韓」そのものの是非ではない。征韓派といい、非征韓派というが、政治の表舞台で衝突した論点は、時期であり方法であった。どちらも征韓そのものを不可としたわけではないのである。 朝鮮側の修好拒否理由 ・新政府はまず、朝鮮に対して王政復古を通告するよう対馬藩に命ずるとともに、その書契に押す「図書」を新印にかえる措置をとった。 ・六八(明治元)年九月末に、対馬藩朝鮮方頭役の川本九左衛門が、王政復古を通告する大修大差使(特使)が派遣されることを予告するため、藩主名義の「先問書契」を携えて釜山におもむいていたが、この予備交渉段階ではやくも暗礁にのりあげた。慣例に異なる点が多い年て、朝鮮は予告書である「先問書契」の受理すら拒否したのである。 ・「先問書契」について朝鮮が問題としたのは、名義が「日本国左近衛少将対馬守平朝臣義達」とあって従来と異なること、「大差書契」には図書(「義達」)にかわって新印(「平朝臣義達章」)を用いることを通告していること、そして最も問題だったのは、文中に「皇」「勅」の字がでてくることであった。 ・東アジアの冊封体制にあっては、「皇」「勅」の字は宗主国である中国の皇帝のみが使用できるものだったからである。「先問書契」には「政権一帰皇室」とあったのだが、「大差書契」にいたっては、「皇祚連綿」「皇上誠意」などと「皇」の字がちりばめられていた。 ・朝鮮側で折衝にあたった安東唆は、禁字である「皇」字を使用するのはやがて朝鮮を臣従させようとする奸謀にちがいない、と語ったという。 木戸孝允の征韓論議 ・歴史を点検してみると、幕末維新期にかぎらず、変革期とくに分散・割拠から新たな統一に向かうときには、きまって征韓論が生まれ、朝鮮半島への侵略が試みられている。いずれも朝鮮に原因があるのではなく、日本国内の事情によるのである。 ・わたしは、このような歴史について、日本人としてみすえなければならない問題が多々あると思う。なぜこのような傾向が生まれるのか、また各時代の違いは何なのかを明らかにする責務が、とりわけ歴史研究者には課せられていると思う。 西郷の期待は何であったか ・わたしは西郷の望んだものは、「有司専制」を克服し、立憲的形態を許容しながらも、限りなく天皇専制に近い国家形態と考える。 ・自ら権力の中にいながら、権力の行使を実感できないもどかしさとはがゆさ、そのもどかしさとはがゆさの原因を「有司専制」に求めながら、かれらが天皇を掌中におさめているがゆえに、直接かれらに向けられない刃を朝鮮に向けようとしたのである。 ・そして、それに代わる新たな国家をそれぞれに思い描き、「征韓」がその国家の実現につながることを期待したのであった。そしてここには、「征韓」を手段化するという、日本近代の重大な問題が孕まれていたのである。 |