
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年01月12日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
6 |
16/01 |
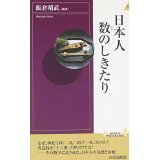 |
日本人 数のしきたり |
飯倉晴武 |
青春出版社 |
〇 |
「五」のしきたり ▼いまに残る五節句の由来と意味 ・七月七日(七夕節句)――旧暦の七月七日は現在の八月上旬にあたるため、現在でもその時期に七夕祭りを行う地域も多い。 「六」のしきたり ▼「どっこいしょ」の語源となった「六根清浄」 ・六根とは、眼根(視覚)、耳根(聴覚)、鼻根(嗅覚)、舌根(味覚)、身根(触覚)、の五感に意根(心)を加えたもの。私たち人間は五感を通してさまざまな事物に触れますが、そこに我欲が付着すると心に迷いが生じます。六根こそ我欲の世界に根を張る煩悩の象徴です。「六根清浄」の掛け声は、そうした我欲から六根を浄めようとするものなのです。 ・修験道の行者たちは、この「六根清浄」を唱えながら厳しい修業を行いましたが、それが一般化して登山者にも広まると、本来の意味を離れて登山中の無事と山を汚さないための掛け声になっていきます。さらに、「ろっこんしょうじょう」の音を耳にするうちに、一休みするときの一声「どっこいしょ」になったといわれています。 「七」のしきたり ▼七福神――七神とはいったい何者なのか ・七福神は、じつはいくつもの国の神様の集合体です。 ・七福神信仰は室町時代に始まり、江戸時代には一般にも広がり、各地にそれぞれの神を祀った ・この風習は、現在でも初詣として受け継がれています。 「八」「九」のしきたり ▼二月と十二月の八日が、なぜ「針供養」の日? ・二月八日は事始め、十二月八日は事納めという厄日に当たるため、針仕事を休んで張りの供養をするようになりました。 ・日本には、すべてのものに霊が宿っているという考え方があり、折々にそうしたものに感謝して霊を慰めようという風習があります。針供養もその一つで、万物を慈しむ日本人の豊かな心情が繁栄された行事といえるのではないでしょうか。 ▼村八分――十分ではないもっともな理由 ・一般に共同体内の交際には、冠、婚、葬、追善、出産、建築、旅行、火事、水害、病気の交際十種があるといわれていますが、このうち、葬儀と火事ははずして、残り八つに関して仲間はずれにするので、村八分といわれます。 火事は個人の家にとどまらない事態に発展する恐れがあり、葬儀は人の死に関する厳粛な事柄なので、この二つだけは手助けするということになっていたのです。 「十」以上のしきたり ▼皇室の紋はなぜ「 ・菊が皇室の紋とされたのは、平安末期から鎌倉初期にかけて在位した ・皇室の紋章は「十六葉八重菊形」ですが、親王・内親王は十四葉の菊花です。 ▼還暦のお祝いはなぜ赤ずくめなのか ・数えで六十一歳になると「還暦」を迎えます。十干、十二支の干支が六十年で一巡し、六十一年目にまた生まれた年の干支に戻ることから、「暦が還る」という意味で還暦と呼ばれているのです。 ・さらに、還暦が「 「百」「千」「万」「億」のしきたり ▼「指切りげんまん」の「げんまん」とは? ・「指切りげんまん」の指切りは、遊女が客に不変の愛を証明するために小指を切ったことに由来するといわれます。 また、「げんまん」は、「拳万」と書き、約束を破ったときは その上でさらに「針千本」を飲ませるわけですから、裏切り者には徹底的な報復を加えると宣言しているに等しいのです。 ・この「指切りげんまん」の約束は、江戸時代から子供たちの間で使われていました。 ・これは、子供の遊びの中で約束を守ることの大切さを具体的に学ばせる、昔の人々の知恵だったのかもしれませんが、なかなかシビアな誓いです。 ▼自然万物に神が宿った「八百万の神」の考え方 ・元来、日本人は森羅万象あらゆるものに「神」の存在を感じてきました。古代には、山や川、海、動物、植物などの自然物、さらに風、雨、雷、火などの自然現象の中に ・自然は生きる そのようなとき、私たちの祖先は神々の怒りに触れたと考え、怒りを鎮めるために収穫物を供え、崇め奉ったのです。 ・そして、それが日本人の精神性を形づくってきたといってもいいでしょう。 ・あらゆるものに神が宿ると考えてきたからこそ、異国の宗教である仏教やキリスト教も寛容に受け入れてきました。 ・この寛容性こそが日本人の特性であり、また半面では「あいまいさ」と揶揄されるところでもあります。 |