
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年08月14日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
68 |
16/08 |
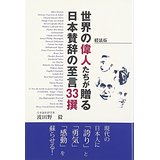 |
世界の偉人たちが贈る 日本賛辞の至言33選 |
波多野 毅 |
ごま書房 |
◎ |
プロローグ ・日本人は、貪欲なほど好奇心に溢れ、創意工夫の精神に 第一の言葉 アルバート・アインシュタイン 近代日本の発展ほど世界を驚かせたものはない。 一系の天皇を戴いていることが、今日の日本をあらしめたのである。 私はこのような尊い国が世界に一ヵ所ぐらいなくてはならないと考えていた。 世界の未来は進むだけ進み、その間、幾度か争いは繰り返されて、 最後の戦いに疲れるときが来る。 そのとき人類は、まことの平和を求めて、世界的な盟主をあげなければならない。 この世界の盟主なるものは、武力や金力ではなく、 あらゆる国の歴史を抜きこえた最も古くてまた尊い家柄でなくてはならぬ。 世界の文化はアジアに始まって、アジアに帰る。 それには、アジアの高峰、日本に立ち戻らねばならない。 我々は神に感謝する。 我々に日本という尊い国をつくっておいてくれたことを ・日本は、技術などの「物」は西欧化させ、「心」は、日本人を保持するという、困難で稀有な成功を収めました。 ・これを見て、ようやく他のアジア諸国も、「西欧」を導入しはじめました。「西欧」を取り入れても、自国の民族性が保てる、「西欧」にならなくて済むやり方がわかったからです。 ・今でこそ、多くの国で西欧の取り入れは抵抗なく行っていますが、当時はできえなかった事で、唯一日本のみが、相当の覚悟で行いました。その先駆的働きは大きな意義があるでしょう。 ・中国の正史、「宋史」の日本伝では、一千年前の宋の国王太宗が、日本を ・これと同様のことを、一千年の時を経て言う人がいました。 アインシュタインです。 「一系の天皇を戴いていることが、今日の日本をあらしめた」 ・日本は一系が続く平和な国家、尊い国であるというものです。世界が戦争で興亡を繰り返し、断絶する歴史であるなかに、ただ日本のみが、日本として変わることなく連綿と続いているという永続性に、平和の秘訣を見たのでしょう。これは日本人が容易に気づかない、または発言しない鋭い指摘です。 第二の言葉 フランシスコ・ザビエル この国の人々は今までに発見された国民のなかで最高であり、 日本人より優れている人びとは、異教徒のあいだでは見つけられないでしょう。 彼らは親しみやすく、一般に善良で、悪意がありません。 驚くほど名誉心の強い人びとで、他の何ものよりも名誉を重んじます。 大部分の人びとは貧しいのですが、武士も、そうでない人々も、 貧しいことを不名誉と思っていません。 ・ザビエルを驚嘆させたのは「大部分の人は読み書きができる」ということです。識字率は少なくとも自国のスペインの民よりは高そうだし、今まで接してきたインド、中国の人よりも一般日本国民は読み書きができる、ということに驚いた事でしょう。 ・インドの首相ネルーは、この時期の日本についてこう述べています。 「むしろかれらが、ヨーロッパとはほとんど交渉がなかったにもかかわらず、宗教という羊の皮をかぶった帝国主義の ・このようにして、西欧の恐るべき植民地化の罠から脱した日本は、世界史的にも特筆すべき長期の平和な江戸時代を築きました。 第三の言葉 エドワード・シルヴェスター・モース 外国人は日本に数ヶ月いた上で、徐々に次のようなことに気がつき始める。 即ち彼は、日本人にすべてを教える気でいたのであるが、驚くことには、また残念ながら、 自分の国で人道の名に於て道徳的教訓の重荷になっている善徳や品性を、 日本人は生まれながらにして持っているらしいことである。 衣服の簡素、家庭の整理、周囲の清潔、自然及びすべての自然物に対する愛、 あっさりして魅力に富む芸術、挙動の礼儀正しさ、他人の感情に就いての思いやり・・・・ これ等は恵まれた階級の人々ばかりでなく、最も貧しい人々も持っている特質である ・「盗み」をしないことは、古くから日本の美点として称えられ、世界の偉人たちは一貫してその点に感心しています。「盗み」がないことが、よほど不思議なのでしょう。しかし、それこそ日本人には、逆に不思議に感じます。日本ではあたり前の行いも外国ではすばらしい称讃の的になります。 ・民衆がお互い手を助け合う姿勢を見て、「手をよろこんで『貸す』というよりも、いくらでも『 第四の言葉 シーボルト 生気に満ちた緑の丘と耕やかされた屋根が前景を飾り、 その背景には鋭い輪郭で青みを帯びた山の峰がそそり立っている。 あちこちにある暗い岩が鏡のような海を中断し、 近くの海岸のけわしい岩壁は朝日に照り映えて、多種多様な色彩に輝いていた。 近くの島の段丘状の畑、きらめく白い家や二、三の寺院の屋根、 浜や入り江に沿って杉の木の間から顔を出したたくさんの大きな家や小屋は、 まことに魅力的な光景であった。 (中略)おだやかな海と晴れ渡った空とが一つになって、 この地を輝くばかりに美しくみせていた。 心地よい住居のある、なんと魅力的な開眼であろうか! なんと実り豊かな丘、なんと神々しい神苑であろうか! ・武士は藩校で、庶民も寺子屋で勉強をしていました。日本全国で寺子屋の数は、1万4千もあります。平均しても、一都道府県当たり、300軒もあるのです。 当時の人工は3千万人程度ですが、現在の小学校の数は、人口ははるかに増えているものの、2万3千校程度です。いかに寺子屋が普及し教育が行き届いていたかがわかります。 ・当時、日本の識字率は、おそらく世界一ではなかったかと思われます。 第八の言葉 魏志倭人伝 婦人淫せず、 ――婦人の貞操観念は堅く、ねたんだりしない。 盗みをする者も少なく、訴えごとも少ない―― ・魏志倭人伝では、「盗まない」ことが特筆されています。「盗まない」ことに驚いています。 ・1550年頃のザビエルは、「それがキリスト教信者の地方であっても、そうでない地方であっても、盗みについてこれほどまでに節操のある人々を見た事がありません」と言っています。 ・明治維新前後に来た外国人達もこの点に驚き、西欧も、日本にかなわないと自ら認めています。 ・この「盗まない」ということについては、約2000年もの長きにわたり、日本の素晴らしい特徴として、他の国から羨望されつづけてきたのです。 第九の言葉 レヴィ・ストロース 民族学者、文化人類学者として私が非常に素晴らしいと思うのは、 日本が、最も近代的な面においても、 最も遠い過去との絆を持続し続けていることができるということです。 私たち(西欧人)も自分たちの根があることは知っているのですが、 それを取り戻すのが大変難しいのです。 もはや乗り越えることのできない溝があるのです。 その溝を隔てて失った根を眺めているのです。 だが、日本には、一種の連続性という絆があり、それは、おそらく、 永遠ではないとしても、今なお存続しているのです。 ・現代の西欧社会は、古代ギリシャ・ローマ時代を精神的故郷と感じてはいますが、しかし今の西欧文明とは本質的に別の社会・文化であり、過去との継続性が無く大きな溝があります。 ・それに対し日本は、神話時代からの長い歴史の継続があり、民族文化が今なお生き続けていて、過去と現在が繋がっている、と言い、そのことに驚き、感嘆しています。 第十の言葉 サミュエル・ハンチントン 一部の学者は日本の文化と中国文化を 極東文明という見出しでひとくくりにしている。 だが、ほとんどの学者はそうせずに日本を固有の文明として認識し、 中国文明から派生して西暦100年ないし400年の時期にあらわれたと見ている ・「日本は大文明の一つ」 ・西欧や中華文明、イスラム文明だけが世界の大文明と思うことなかれ、日本は古来からの大文明のひとつだったのです。 ・他の文明は、ひとつの文明のなかに複数の国が入っていますが、日本は一つの国で独立した一つの文明という、世界に類を見ない唯一の国であるといいます。 ・他の文明としては、中華文明・ヒンドゥー文明・イスラム文明・西欧文明・ロシア正教文明・ラテンアメリカ文明・アフリカ文明の八つが挙がっています。 ・日本は、最初に近代化に成功した最も重要な非西欧の国でありながら、西欧化しなかった点が特徴であり、アメリカと日本は全く異なった国だと指摘します。 ・個人主義と集団主義、平等主義と階級性、自由と権威、契約と血族関係、罪と恥、権利と義務、競争と協調などがその相違点としてあげられます。 ・「日本の文明が基本的な側面で中国の文明とは異なる。それに加えて、日本が明らかに前世紀(19世紀)に近代化をとげた一方で、日本の文明は西欧のそれとは異なったままである。日本は近代化されたが西欧にはならなかったのだ。 第十一の言葉 シュリーマン この国には平和、行き渡った満足感、 ゆたかさ、完璧な秩序、 そして世界のどの国にもまして よく耕された土地が見られる。 ・高潔さ、自己の欲望を考えない武士道は、私を捨て、国のことを思い、幕末の最後に日本を救います。自ら武士という特権を放棄し、明治維新を成し遂げたということです。 ・英国の歴史学者トインビー曰く、 「彼らはほとんど崇高といってよいほどの、高い自己抑制の境地に到達した。すなわち、もはやその外に超然としていられなくなった西欧化された世界の環境のなかで、日本が独立を維持してゆくためには、自分たちが犠牲をはらわなければならないと確信し、みずから進んでその特権を放棄したのである」 ・通常特権階級にある人間はそれを手放したくないために 第十七の言葉 ジャワーハルラール・ネルー アジアの一国である日本の勝利は、 アジアのすべての国々に大きな影響をあたえた。 わたしは少年時代、どんなにそれに感激したかを、 おまえによく話したことがあったものだ。 たくさんのアジアの少年少女、そしておとなが、 おなじ感激を経験した ・一九〇四年~一九〇五年に、日露戦争はありました。その頃の世界地図は、恐ろしいことに、地球上のほとんどすべての場所を、欧米白人列強が植民地化してしまっています。アフリカや東南アジアは、分捕り合戦でズタズタです。一八七八年には地球の67%を、一九一四年には地球の84%を西欧が支配することになります。実質的に植民地支配をまぬがれていたのは、日本とタイぐらいなものでした。 ・日本もロシアがドンドン南下してきたため、大国ロシアと争いたくはありませんでしたが、やむを得ず乾坤一擲の戦いに至りました。苦難の末、勝利した日本は白人の植民地化をまぬがれます。 ・一方、西欧に植民地化されたり、抑圧された人々は、アジアの名も知らぬ小国である日本が、西欧の一員である巨大国ロシアに勝ったので狂喜乱舞しました。 ・支配されるのが当然と思っていた植民地の人々に、「小国をもっての大国を打ち破れるなら、自分たちにできないことは無い」、と独立運動に目覚めさせることになりました。 ・黒人の解放運動にも火がつきました。独立運動は、日露戦争の日本の勝利が1つの大きな原動力となっています。他方、西欧側は、有色人種の独立運動が活発になり、植民地化、奴隷化することは、もはやできなくなっていきます。 ・欧米は日本の勝利を機に、白人の世界制覇を断念せざるを得なかったといえます。このように日露戦争は、世界の歴史において、非常に大きな意味を持っています。 第十八の言葉 李 登輝 私はね、二二歳まで日本人だったんですよ、 岩里政男という名前でね。 私は日本人として、非常に正当な日本教育を受けた。 後に中国の教育も受け、アメリカにも学びましたが、 私の人生に一番影響を与えたのは、 この日本時代の教育だったんです。 ・「日本の『武士道』は素晴らしいのであり、天下無比のパワーを秘めているのです。このような『不言実行』あるのみの不文律を築き上げてきた民族の血を引く日本人は、もっと自信と誇りを持って、積極的に『国際社会のリーダー』の役割を果たしていくべきではないでしょうか」 ・「私は、このような『日本精神』、すなわち、『義』を重んじ、『誠』をもって、率先垂範、実践躬行するという『大和魂』の精髄がいまなお脈々として『武士道』精神の中に生き残っていると信じ切っているからこそ、日本および日本人を愛し、尊敬しているのです」 ・「この『大和心』こそ、日本人が最も誇りに思うべき普遍的真理であり、人類社会がいま直面している危機的状況を乗り切っていくために、絶対に必要不可欠な精神的指針なのではないでしょうか」 第二十六の言葉 マルコ・ポーロ ジパングは東海にある大きな島で、 大陸から2400キロの距離にある。 住民は色が白く、文化的で、物質に恵まれている。 偶像を崇拝し、どこにも属せず、独立している。 黄金は無尽蔵にあるが、国王は輸出を禁じている。 しかも大陸から非常に遠いので、商人もこの国をあまりおとずれず、 そのため黄金が想像できぬほど豊富なのだ ・二回の元寇があったのが、1274年・1281年ですから、ちょうどポーロも元に滞在していた頃です。 ・元軍の火力に悩まされた日本でしたが、二回とも「神風」と言われる暴風雨などで撃退できました。その火力は西欧に伝わり、めぐりめぐってそれが火縄銃となって1543年種子島に伝わります。そして、あっという間に国中に広がり、日本は戦国時代後期には多くの銃を持つ大軍事国家となりました。 ・一方西欧も、武器開発にいそしみ軍備拡張していきます。しかしながら植民地獲得などで西欧同志の戦争状態が続いていくのに、日本は江戸時代に入り、パタッと鉄砲などの火力を捨ててしまい、軍縮してしまいます。 ・ヨーロッパが軍拡に走るなかで、一方の軍事大国日本は軍縮していくという、不思議な構図が生まれました。無論戦争がなくなったため武器が必要なくなったという点は考えられますが、戦争を 第二十七の言葉 小説「八十日間世界一周」 ・明治政府は藩閥政府といわれて、薩長土肥が牛耳っていたように思われがちですが、実際には結構実力主義であり、高級官吏は、四藩出身者よりその他の藩の出身者のほうが圧倒的に多かったのです。 ・実力のある人を抜擢していたのです。 ・実はこれが他国にはなかなか出来ない事で(汚職などがはびこり私欲に走る国が多いこと)、たまに見せる日本の大胆な決断でした。 まとめ ・現在、世界の土地面積に対し、森林の占める割合は30%です。これに比べ日本は、国土の64%もが森林です。しかし、アメリカは25%しかなく、中国も実は18%しかありません。 ・日本人に接して分かったのは、日本人の道徳性の高さや、文化の高さ、頭のよさや善良な品性などで、むしろ先哲偉人はこの点に圧倒された感があります。そのような一般的な民度の高さに大変驚嘆しています。礼儀、道徳もすべて高い水準で備わっていた。 ・「自国で道徳的教訓の重荷になっている善徳や品性をすでに日本人は生まれながらに持っている」とモースは脱帽しています。 ・アインシュタインは、「日本人以外にこれほど純粋な人間の心を持つ人はどこにもいない。この国を愛し、尊敬すべきである」といい、ザビエルは、「日本の人々は慎み深く、また才能があり、知識欲が旺盛で、道理に従い、その他様々優れた素質がある」と称讃しました。 ・「盗まない」ことについても、魏志倭人伝の時代から2000年近くも外国から特筆された長所です。 ・史上の偉人の言葉をよく噛み締めると、日本人の良さ、美風がよくわかります。「己」がわかり、自分の長所、強み、美風がわかれば、それが誇りに感じられますし、自信にもなります。また、それを失いたくはないでしょうから、維持し、守る努力をするでしょう。そうなれば、長所を上手に活用していくことができるはずです。そしてさらには、日本の進むべき道をも見えてきます。 一方で伝統を大事にし 一方で健全な進取の気風がある これが先哲外国偉人がわれわれ日本人へ送る、重要なメッセージであり、日本人が大切にしたい指針といえましょう。 |