
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年8月23日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
70 |
16/08 |
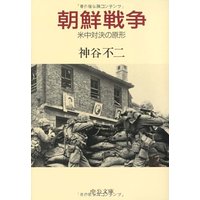 |
朝鮮戦争 米中対決の原形 |
神谷 不二 |
中公文庫 |
◎ |
Ⅰ 開戦前史 朝鮮の分割 連合国の構想 ・一九四五年八月、太平洋戦争の終結にさいして、朝鮮は三八度線を境として米ソ両軍によって分割占領され、同じ民族が南北にわかれてまったく異なった道を歩きはじめた。 南北両政府の成立 南朝鮮の分離選挙 ・一九四八年八月十五日、大韓民国は独立を宣言した。 ・北朝鮮も八月二十五日に最高人民会議の総選挙を行ない、九月八日正式に憲法を採択し、朝鮮民主主義人民共和国の成立を宣言した。そして同九日、金日成が首相に選ばれた。 米・ソ両軍の撤兵 ・ソ連は、すでに一〇月一九日から撤兵を開始していた。 ・アメリカの撤兵計画がはじめて公にされたのは、十二月二八日の歩兵一個師団撤退の発表であった。 ・二日後、モスクワ放送はソ連の撤兵完了を報じた。 ・六月八日、アメリカは正式に撤兵を発表し、同月二九日、約五〇〇名の軍事顧問団をのこして撤兵を終了した。 ・一九四九年の夏は、過去半世紀以来、朝鮮半島に朝鮮人だけがいた最初の夏であったが、南北朝鮮の境界には不穏なものがただよっていたのである。 アメリカの基本戦略と開戦 李承晩への経済援助 ・結局のところ一九四九年七月から一九五〇年六月までの経済援助として最初トルーマンが提案した一億五千万ドルのうち、朝鮮戦争勃発までに支出されたのは六千万ドルにすぎなかった(開戦後の分をくわえても四千万ドル減の一億一千万ドルにとどまった)のである。 アメリカの軍事援助 ・朝鮮戦争勃発までに実際に韓国へ到着した武器・装備はわずか一〇〇〇ドル分たらずであり、アメリカから発送ずみの分をあわせても三五万ドル分にすぎなかった。 ・一九五〇年六月一五日、アメリカ軍事顧問団は「南朝鮮は中国にふりかかったと同じ悲運におびやかされている」とワシントンへ警告したが、当時ソウル・東京・ワシントンを通じて、アメリカは朝鮮の内戦を切迫した問題とは考えないことで意見が一致していたのであった。 ・アメリカの対韓軍事援助および韓国軍の実情は、このように、一九五〇年六月二五日に朝鮮で戦争をひきおこすだけの準備をまったく欠いていたといってよい。 民族解放戦争としての朝鮮戦争 ・前年における中共の大陸制覇に大きな刺激と激励をうけながら、この見通しのもとに北から南にたいして民族解放戦争として開始されたのが、まさに朝鮮戦争であった。 ・もちろん、六月二五日に南北どちらが先に発砲したかは水かけ論に終っている。 ・しかし、当時の韓国軍には、北にたいして大規模な攻撃を行なうだけの装備がなかった。 ・これに反して、開戦後の北朝鮮軍が飛行機・戦車などの攻撃用重装備を駆使してきわめて急速に南下した事実は、その攻撃が「十分計画され整備された全面的な南朝鮮侵攻」を意図したものであったことを物語るといわねばなるまい。 ・ここで注意すべきことは、一九四八年ころからアジアの諸地域で、共産党がいっせいに武力蜂起を行なったという事実である。 開戦の決定者 ・一九四五年から五〇年までのあいだ、ソ連は、占領国および同盟国として北朝鮮に数々の指導や統制、助言や協力を行ない、北朝鮮をほとんど衛星国化していた。 ・平壌のいかなる決定も、事実上モスクワとの事前協議なくして行なわれたとは解しにくい。一九五〇年六月の開戦決定も、おそらくはソ連の助言ないし勧告を得た上での決定であろう。つまり、北朝鮮がリードをとった形で、実質的にはソ連との共同決定に近いものではなかったかと推定されるのである。 ・これにくらべて、のちに「抗美(=米)援朝」に決起した中国は、共産政権成立以前はもとより、その後も北朝鮮にたいしてソ連よりもはるかに小さい影響力しかもっていなかった。 ・当時の中国にとっては、主要な軍事目標は台湾とチベットの「解放」であり、中国中・南部の「平定」であった。 ・中国は一九五〇年六月の攻撃に大きな関心をもっていただろう。しかし、その開始および結果については、ソ連と異なって直接の責任をもたない立場にあったと考えられる。 Ⅱ 「解放」と「統一」 統一の日きたる? "北進"決行の背景 ・アメリカは、参戦のときと同様、すでに実施にふみきっていた三十八度線突破について国連の追認を得た。ただし、このときの「国連」とは、安保理事会ではなくて総会であった。八月以来安保理事会にソ連が復帰したため、訴えてもソ連の拒否権がある以上無意味である。そこで総会が舞台に選ばれたのである。 ・国連のとる強制措置は、安保理事会の議決によってなされるのが本来の建前である。それを勧告という形で総会――そこでアメリカ支持国が多数を占めるのは明らかであった――に肩がわりさせることによって、アメリカはひきつづき自国の政策に国連の衣をきせようとしたのであった。 Ⅲ 「まったく新しい戦争」 中国参戦の背景 台湾への関心 ・朝鮮開戦後の三ヵ月間にみられる中国の関心は、朝鮮よりもむしろ台湾にあった。 アジアにおける中国の地位 ・北京にとって、朝鮮の「公正な」平和はそれ自体が目的ではなく、それに関する他の政策目標を達成するための手段であったといえよう。 ・その政策目標とは、簡単にいえば、アジアにおける中国の地位の問題であった。 Ⅳ 休戦 板門店の隘路 アイゼンハワー登場とスターリンの死 ・北朝鮮の南朝鮮への進撃を認めたのは、スターリンの大きな誤算であった。このことは、一九五三年はじめまでには、すでにクレムリンでも明らかになっていただろう。しかし、スターリン存命中は、彼はあくまでも「誤りをおかすことのない」存在でなければならなかったのであろう。 ・一九五三年三月五日のスターリンの死はその障害を取りのぞき、休戦会談再開への大きな転機になったと考えられる。 李承晩の抵抗 急戦は“国家的死刑” ・朝鮮の真の悲劇は、その運命があまりにしばしば朝鮮人以外の者によって決定されてきたことだろう。 ・朝鮮戦争の場合も、本来それは南北朝鮮の民族的統一の問題として企画されたはずであるにもかかわらず、その後の事態は、朝鮮人、ことに南朝鮮の国民および指導者の意向におかまいなく進行した。 ・北進統一をシャニムニ念願としていた李承晩にとっては、アメリカがマッカーサーを解任し、戦前状態への復帰で休戦にふみきったことは、まことににがにがしく、憤懣やるかたないことであった。 ・アメリカの軍事力の傘から出されたならば、韓国の命運は決する、それは敵(中国・ソ連・日本)に包囲されている、内部から崩壊するおそれも多分にある、アメリカ軍がひとたび朝鮮のもつれから身をひいてしまえば、それをふたたび呼びもどす手段はないであろう、これが李承晩の深甚な危惧であった。 ・休戦が韓国にとって“国家的死刑”を意味するという恐怖であった。 Ⅴ 朝鮮戦争の意義 世界政治の流れのなかで 冷戦の基本図 ・開戦の決定が実質上平壌とモスクワの共同決定に近いものであったにせよ、朝鮮戦争の本来の性格は武力による全朝鮮統一をめざす北朝鮮の民族解放戦争であり、ソ連はこの北朝鮮の意図とその成功の見通しを、極東における日米連携の強化に対抗するために利用しようとしたのであった。 ・アメリカはそれを、「ソ連による世界の軍事的征服計画の第一着手にすぎないとする見解」をとった。 ・チェコのクーデター(一九四八年二月)、ベルリン封鎖(一九四八年六月 ― 四九年五月)、アジアの諸国における共産系勢力の暴力行動(一九四八 ― 四九年)、中華人民共和国の成立(一九四九年一〇月)に続いて朝鮮戦争をむかえるにおよんで、アメリカは、それらを個々の事件ではなくて、クレムリンに源を発する一つのドラマの一幕ずつであると受けとるにいたったのである。 ・こうして、アメリカは、三八度線の破綻を局地的次元においてではなく、 ・戦争の性格をそのように受けとるならば、反応は必然的に朝鮮での参戦だけにはとどまらない。すなわち、アメリカは朝鮮への派兵と同時に、台湾海峡を「中立化」し、フィリピンとインドシナへの軍事援助の拡大をも決定したのである。 ・それとともに、一見逆説的にも、アメリカは朝鮮に深く介入すればするほどヨーロッパへの配慮を増大し、統一NATO軍の創設を実現したのであった。 ・ダレスの「力による平和」路線――反共軍事同盟網による共産圏包囲政策――は、朝鮮戦争に起因するところが大きい。 ・同様に、それは日本および西ドイツの再軍備を促進することになり、それによって、いわば冷戦の基本図を礎定することになったのである。 戦後日本の歩みのうえで 単独講和と日米安保体制 ・朝鮮戦争は戦後日本の歩みとどのようなかかわりあいをもったであろうか。 ・第一に、朝鮮戦争は日本の「単独」講和と日米安全保障体制を決定的なものにした。 ・早期・単独講和が決定的となり、日米安保体制が樹立されたのは、朝鮮戦争がわが国にもたらしたもののうち、第一にあげるべきことであろう。 ・「朝鮮戦争は、日本の安全保障問題を全面的に、根本から変えてしまった。非武装化され、軍事的に中立化された日本という夢はもはや消え去った。」この戦争によって、わが国は、決定的かつ明示的にアジアにおける反共軍事体制の中核たる地位を占めることになるのである。 ・ダレスは日本の再軍備をもとめたが、吉田首相は、わが国には本格的な再軍備に耐えるだけの経済力がないとの理由で消極的な抵抗を行ない、警察予備隊をなしくずしに「漸増」すること以上に出ようとしなかった。 ・一九五一年二月二日、ダレスはつぎのように演説した。いわゆる「真空戸じまり論」がこれである。すなわち、日本には軍備がないので、講和後占領軍が撤退すればそこに軍事的「真空」が生じ、共産主義者の侵略をまねくおそれがある。したがって、それを防ぐために「戸じまり」をする必要がある。アメリカ政府は「もし日本が希望するならば、日本国内およびその周辺にアメリカ軍を維持しておくことを好意的に考慮する」というのがその趣旨であった。 ・吉田首相はこれにたいして、 「朝鮮において共産勢力が仮借ない侵略に出ている現実に直面して、ダレス特使は、日本本土とその周辺にアメリカ軍を駐留させ、軍備のない日本をまもるためにアメリカとのあいだに安全保障にかんする取決めを結ぶよう要請された。政府と国民大多数はこれをよろこび迎えるものである」 との談話を発表した。 ・今日にいたる日米安保体制は、このとき事実上決まったのである。 特需ブーム ・朝鮮戦争がわが国にもたらした第二のものとしては、経済面におけるいわゆる「特需ブーム」の到来をあげねばなるまい。 再軍備はじまる ・第三に、国家警察予備隊の名のもとに日本の再軍備がはじめられ、今日の自衛隊の基盤ができたのは、まさに朝鮮戦争のためであった。 解説 阪中友久 ・一九五〇年六月二五日、北朝鮮軍の南下で始まった朝鮮戦争は、第二次世界大戦後の国際関係に決定的な影響を与えた事件であった。 ・すでに当時、ヨーロッパで東西の冷戦は始まってはいたが、朝鮮戦争の勃発は「ヨーロッパの冷戦」を「世界にわたる冷戦」に変えた。 ・アメリカはこの戦争を共産主義勢力の世界にわたる軍事的挑戦の開始と認識して、アメリカの本格的な再軍備と全世界にわたる反共「封じ込め」のための軍事同盟の形成を急いだのであった。 ・アメリカは朝鮮戦争によって、戦後の世界的な責任を認識して「真の意味での政治・軍事面での超大国となった」のであった。 ・現在ではソ連も中国も、この戦争が北朝鮮の南下で始まったことを非公式には認めている。 ・しかし本書の初版が刊行された一九六六年二月ごろ、わが国では、社会主義は平和勢力であるという「社会主義神話」がまかり通っていた。神谷教授の「朝鮮戦争は北の侵攻」という見解は、当時の論壇や学界において少数派ないし異端として捉えられて、いわゆる進歩派から多くの批判・非難を浴びた。 |