
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年01月26日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
8 |
16/01 |
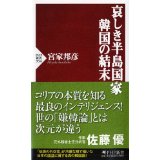 |
哀しき半島国家 韓国の結末 |
宮家邦彦 |
PHP新書 |
〇 |
第2章 「事大主義」と「小中華思想」の本質 ❖北東ユーラシアを知るための必須概念 ・事大主義とは、「小」が「大」に ❖「事大主義」と「小中華思想」は表裏一体 ・小中華とは、中華文明圏のなかで、非漢族的な政治体制と言語を維持した勢力が、自らを中華王朝(大中華)に匹敵する文明圏であっさて、中華の一部をなす者(小中華)と考える一種の文化的優越主義思想である。 ・十七世紀以降、コリア半島の指導者たちは女真系の清を徹底的に蔑む一方で、事大主義に基づいて、その夷狄・禽獣に朝貢を行なって冊封関係に入るという矛盾した世界観と行動様式を維持してきた。 ・この屈折したコンプレックスの塊とも思えるコリア半島の住民の民族性は、李氏朝鮮以降、事大主義という劣等感と小中華思想という優越感を、心中で巧みに均衡させることによって維持されてきたのではないだろうか。 ❖必要なのは「基軸」ではなく「バランス」 ・自然の要塞のない中小大陸国家の住民は、外国人を基本的に信用しない。自らがその地域の覇権を握る可能性は低いが、特定の列強だけに依存すれば、いずれ他の列強の反発を買い、中長期的には自らの安全そのものが危うくなるからだ。 ・そのような国家の外交に「基軸」は不要である。逆に必要とされるのは、隣接する列強の力関係に関する「バランス感覚」。特定の列強に過度に依存しないことこそが生き残りの秘訣だからだ。 ・コリア半島の住民にとって現在の中国、ロシア、日本、米国はいずれも信用できない大国である。ロシアにはどうしても信頼が置けず、そもそも日本とは格が違うと思っている。米国は唯一の域外国だが、しょせんはコリア半島にとっては新参者に過ぎない。 ・とくに、中国との関係は複雑だった。潜在的に最大の脅威でありつづけた漢族中華王朝に対する憧憬と劣等意識、非漢族王朝に対する反発と優越意識。この二種類の(実際にはコインの裏表でしかない)コンプレックスを併せ持つのが、コリア半島の対中観の特徴なのである。 第3章 チャイナタウンの存在しないソウル ❖高句麗をめぐる中華歴史論争 ・高句麗とは紀元前一世紀ごろから六六八年まで続いた国家であり、最盛期の ・ところが、中国社会科学院は中国東北地域(旧満州)にあった高句麗と 中国の教科書によれば、朝鮮史の始まりは六七六年の統一新羅からとなっているらしい。 ・中国の昔の民族「高夷」が先祖である高句麗は朝鮮ではなく、中国東北部に存在した少数民族による「中国の地方政権」に過ぎないのだそうだ。 ❖学問的な論争は不毛なだけ ・韓国はこれまで高句麗を当然「朝鮮の王朝」だと考えていたが、最近になって中国側が「朝鮮民族は新羅人を中核に形成されたため、高句麗人とは違う民族であり、高麗王朝は新羅系の王朝であって高句麗とは何の関係もない」と主張し始めた。 ・この問題は学術的疑問ではなく、政治そのものだ。 ・韓国の専門家はコリア半島の排外的な民族感情を「 ・恨とは文字どおり「恨み」である。 ・ハンとは「伝統規範からみて責任を他者に押しつけられない情況の下で、階層型秩序で下位に置かれた不満の累積とその解消願望」なのだ。 ・同時に、ハンは時の権力者や異民族による支配に服従を余儀なくされた屈辱感だけではなく、ときにはそうした支配者に対する「憧れや悲哀や妄念など」を表す朝鮮半島独特の感情だとする説もある。 第4章 中華でもコリアでもない地域の民族たち ❖中華にとってウイグルはいまだ「西戎」 ・ウイグル問題の第一の本質は、「農耕民族」と「遊牧民族」との戦いである。 ❖ウイグル自治区は中華圏の外にある ・ウイグル問題の第二の本質は、「一神教イスラム」と「伝統的祖先信仰」との衝突だ。 ・ウイグル人は中東を源とする一神教のイスラム教徒である。 ・ところが、中華には「神との契約」という概念がない。漢族の世界では昔から「神」よりも「人間」のほうが偉い。 ・だから漢族の中国は、「法治」ではなく「人治」の国なのだ。 ・善悪の判断を「神」に委ねるウイグル族と、その判断を「祖先」と「賢人」に委ねる漢族とは本質的に相容れない。 ❖「共産主義」対「信仰の自由」 ・ウイグル問題の第三の本質は、「共産主義」対「信仰の自由」である。 第9章 日本のコリア半島戦略 日本の戦略と戦術 ・将来の韓国政府は、現在の政府と同様、対日譲歩に反対する世論に対抗する意思と能力を欠くというのが、悲しい現実である。 |