
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年09月25日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
81 |
16/09 |
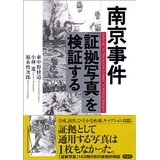 |
南京事件 証拠写真を検証する |
東中野修道 小林 進 福永慎次郎 |
草思社 |
◎ |
第一章 南京戦とは何だったのか 日本軍を大陸の奥深く引き込む ・一九三〇年代の中国大陸は、今日の中華人民共和国のように一つの統一された国ではなく、多くの軍閥が乱立する内乱状態にあった。 ・当時の大陸でもっとも強い勢力を誇っていたのが蒋介石の国民党であった。蒋介石は武力による天下統一に乗り出した。それが昭和二(一九二七)年から始まった「 ・毛沢東は、蒋介石の攻撃の矛先を共産党から日本に向けさせようと必死であった。 ・ところが、事態を変える突発事件が起きる。昭和十一(一九三六)年十二月十二日、中共軍討伐作戦を督励のため ・それから七ヵ月後の昭和十二年七月七日、日本が日中戦争の泥沼に入り込むきっかけとなる盧溝橋事件が起きる。 ・北京近郊の盧溝橋で、日本軍はいつものように実弾ではなく空砲を使って演習していた。ところが、昭和十二年七月七日二十二時四十分、日本軍が発砲される。 ・この盧溝橋事件につづいて北京では広安門事件(北京の邦人二千人を保護すべき日本軍兵力はわずか二個中隊であったため、支那駐屯兵第二連隊第二大隊が北京城内の三個旅団の当局と約束のうえ、北京の広安門から入城しようとしたところ、中国兵が閉門して猛射を浴びせた事件)が、通州では通州事件が起きる。とくに通州では日本人居留民二百余名が中国軍に殺害された。 ・盧溝橋事件から通州事件にいたる一連の事件の処理をめぐって、日本は中国側と八月九日に上海で和平交渉を行う予定であった。日本は不拡大政策をとっていたのである。 ・ところがその和平交渉の当日、上海で中国の保安隊が大山勇夫海軍中尉と部下一名を殺害したことから、第二次上海事変〔第一次上海事変は昭和七年〕が勃発してしまう。こうして戦火は北支から上海へ移っていく。 ・上海では英米仏伊の外国軍がフランス租界や共同租界に駐留しており、いきおい日本と中国の戦いを観戦する形になった。蒋介石の狙いどおり、上海での日中衝突は国際的な注目を引き、欧米諸国を反日へと誘導していくことになったのである。 ・日本軍は三ヵ月間の戦闘の末、多大な死傷者〔累計九万八〇〇〇〕を出して、ようやく十一月十二日に上海を陥落させた。 ・しかし中国軍は降伏することなく、南京へと逃げる。蒋介石はドイツ軍事顧問団の助言に基づき、「空間を武器として」活かすという観点から、広大な大陸を武器として、日本軍を大陸の奥深くに引き込みさえすれば、勝てなくても負けないという消耗戦の戦略に立っていたのである。 ・日本軍は逃げる中国軍を南京へと追撃していった。戦争は、一度始まると、どちらかが降伏しないかぎり終わらないからだ。 ・逃げる敵軍も武器を持ち、日本軍の殲滅をはかりながら南京へと向かっていたのである。それが戦争であった。 ・激戦のさなかの十二月十二日、国際委員会は三日間の休戦協定を中国軍に提案した。しかし中国軍はこれを拒否し、通常の軍隊ではあり得ない動きに出た。 ・その一つは、十二月十二日二十時、南京防衛軍司令官の唐生智が、日本軍に降伏の意思表示をすることなく、ただ一つ開いていた挹江門(北門)の狭い通路から逃亡したことである。 ・二つ目は、唐生智の逃亡後、中国兵が軍服を脱ぎ、市民のための中立地帯である安全地帯に逃げ込んだことである。 捕虜となり得なかった不法戦闘員の中国兵 ・一度起こった戦争はどちらかが降伏の意思を表明しないかぎり、終わったことにはならない。 ・中国軍は城門が陥落しても降伏して来なかった。そのなかには、依然戦闘の闘士を秘めた兵士がいたであろう。どちらか決められない兵士もいたであろう。 ・このような状態では、いつ戦闘状態になるかわからない。これは日本軍にとっても住民にとっても安心できる状態ではない。 ・中国兵が組織的に降伏してこない以上、いずこの軍隊も行うように、日本軍も、逃げる敵には追撃戦を、潜伏中の敵には掃蕩戦を展開した。 ・大虐殺を主張する人たちは、これをもって虐殺行為と言うが、追撃戦は古今東西の戦場の常識である。また、掃蕩戦は自軍と市民の安全確保のためにも不可欠である。 ・三・八六平方キロの安全地帯は非戦闘員の市民で「スシ詰め」で、そこに二万と推定される兵士が市民になりすまして潜伏していた。安全地帯内の中国軍の高射砲陣地は撤去されないまま残っており、武器を隠し持っている兵士も多数いた。 ・日本軍は、古今東西いずれの戦場でも行われる残敵掃蕩を、各部隊ごとに担当地域と責任を決めて、展開したのであった。 ・この安全地帯での掃蕩戦の結果、日本兵は多くの中国兵(不法戦闘員)を摘発した。そして白昼、反抗的な数千人にかぎって揚子江岸で処刑を実行した。これは事実である。 ・問題は、日本軍の行った処刑が合法か不法かである。捕虜となった合法的戦闘員は法に守られ、違法なことをしないかぎり、処刑されることはない。とくに理由もなく捕虜が処刑されたならば、それこそ不法な「虐殺」である。 ・しかし、安全地帯で摘発された中国兵はじつところ「捕虜」となる資格はなかった。彼らは明治四十(一九〇七)年のハーグ陸戦法規の定める戦闘員の資格四条件をことごとく踏みにじっていたのである。 ・軍服を着用し戦争法規を守っている戦闘員は、戦争法規に守られて「捕虜の資格と身分」を与えられるが、しかし軍服を脱ぎ捨てた兵士は不法戦闘員となる。 ・戦闘員の資格四条件を守った合邦戦闘員はその報償として、捕らえられても捕虜となり命を保証されるが、不法戦闘員はその報償を得られず捕虜にもなり得ないのである。 ・当時、南京在住の欧米人の誰ひとりとして、「日本軍が捕虜を処刑」と明言したことはなかった。それは東京裁判においても同様であった。 ・ベイツ(国際委員会)が日本大使館宛てに提出した「市民重大被害報告」は、のちにルイス・スマイスの手で「安全地帯記録輯」としてまとめられたが、その「事例一八五」の「注」には、「われわれには日本軍の合法的な処刑について講義する権利はない」と記録されている。 ・「事例一八五」が書かれたのは、城門陥落から約一ヵ月後の昭和十三(一九三八)年一月九日で、国際委員会は「日本軍の処刑は戦時国際法の原則に合っている」と判断していたことになる。 ・平和な時代から見ると、兵士が軍服を脱げば、「普通の市民」と認めてよいのではないかと思われるかもしれないが、兵士は軍服を脱いでも除隊しないかぎり兵士なのである。 「日毎加わる親密さ」 ・日本軍は、十二月二十八日現在、外国大使館や建物から中国軍の将校二三名と下士官五四名、兵卒一四九八名を摘発した。 ・安全地帯に潜伏していた将校が安全地帯の中国兵に攪乱工作を命じていたのであった。しかも、南京の欧米人のなかには将校を匿うという違法行為を行う人もいた。 ・「ある女性が今朝病院に入ってきた。一ヵ月以上も前に城内南部に連れ出されたという。日本軍兵士たちが彼女を毎日七回から九回もレイプして、ついに彼女は使えなくなったので赦免された。・・・しかし、勿論日本軍はこのようなことはしないし、これらの嘘をでっち上げて中国人を元気づけるのは我々外国人なのだ」(南京の聖パウロ聖公会教会の宣教師アーネスト・フォースター師の手紙)。 検証なしに記された「被害報告」 ・「市民重大被害報告」の九五パーセントが伝聞であった。周知のように、伝聞は証拠となり得ない。 ・ドイツ大使館のパウル・シャルフェンベルク事務長は、公刊されたジョン・ラーベの日記、『南京の真実』(二月十一日)が引用するように、「日本軍の暴行といっても、すべて中国人から一方的に話を聞いているだけではないか」と批判している。 第二章 初めて世に出た「証拠写真」 「証拠写真」のルーツをたどれば、2冊の本に行きつく。 「日寇暴行実録」と「外人目撃中の日軍暴行」――「証拠写真」の源流 ・中国国民政府軍事委員会政治部編『日寇暴行実録』 ・ハロルド・ティンパーリ編『外人目撃中の日軍暴行』 ・小山栄三『戦時宣伝論』より 氏は、戦前から戦中にかけては厚生省人口問題研究所の調査部長として、戦後は国立世論調査所所長や立教大学教授を歴任している宣伝戦に関する専門家でもあった。 「各国の通信員はいづれも意識すると、しないとに拘らず其の国の利益代表者であるか、又はセンセーショナルなニュースを探し廻ってゐる人々であって、甚だしきは支那人以上の捏造ニュースを彼ら自身が作るのである」 「支那側は事々に自己の敗戦による悲惨さを誇大化して泣訴し、第三国の対日干渉を誘発せんとしてゐるのだ。この種の「 斬首、生き埋め ・敗戦につぐ敗戦の蒋介石とその国民党宣伝部は、 ・至近距離から撮影された公開処刑の写真は国民党宣伝部が『外人目撃中の日軍暴行』に載せるために演出した写真ではなかったのか。 ・ちなみに、日本国内で公開処刑の慣習があったかどうか調べてみたが、明治以降の日本には公開処刑は認められないようだ。慣習がないのに南京でおこなえるはずもない。 合成、演出、ひそかな転載、キャプション改竄 ・この二冊に掲載された写真は、国民党宣伝部ないしは国民政府が敵国日本の名誉を貶める目的で、写真の改竄も演出も辞さないという方針にたって、まさにプロパガンダの写真をも投入して編集した宣伝写真であった。 第三章 趣向を凝らした追加写真 さまざまなところから持ち寄られた写真 ● ・明治以降の日本国内には ・中国では一九三〇年代になってもこの習慣があった。 ●「日本軍の放火」写真? ・ジョン・ラーベが十二月十二日二十時の日記に「南の方角は一面火の海だ」と書いている。 ・十二日の夜といえば、まさに南京陥落直前の前夜にあたる。十二日の夜八時、中国軍の南京防衛軍司令官唐生智がまず逃亡し、つづいて中国軍の敗走が始まったが、中国軍は敵に一物も残さないという古来からの戦闘方法「 第四章 「撮影者判明」写真はどのように使われているのか 欧米人撮影の写真(一) ジョン・G・マギー師〔米国聖公会伝道団宣教師〕 ●なぜ東京裁判に写真を提出しなかったか ・師は大正元(一九一二)年から昭和十五(一九四〇)年まで南京に在住した。 ・マギー師は東京裁判に証人として出廷し、日本軍の組織的な「殺戮行為」を証言し、その証拠はみずから撮影した写真にあると述べている。 ・ところが、そのような写真を撮ったと言いながら、彼は東京裁判にフィルムを証拠として提出していなかったのである。 ・「マギーフィルム」は、南京陥落後の光景のほとんどが戦傷者と病院の光景であった。その他の光景も、マギー師が述べたような「信じられないほど恐るべき状態」ではなかった。南京大虐殺を示す決定的な光景はどこにも見出せないのである。だから、東京裁判にも証拠写真として提出されなかったのではないか。 ●字幕の追加で「フィルムに活気が出る」 ・今日私たちが「マギーフィルム」と呼ぶものは、マギー師の無声フィルムに、ティンパーリ記者が字幕説明を挿入して加工したものと考えられる。 ・マギー師のフィルムからこれまでよく使用されてきた四つの光景を静止画として取り出し、後年、『ザ・レイプ・オブ・ナンキン』が説明を付けている。 欧米人の写真(二) アーチボールド・スティール記者〔『シカゴ・デイリーニューズ』紙特派員〕 ●日本軍の放火写真 ・「南京特務機関報告3」(一九三八年三月)が記録するように、日本軍特務機関の編成した消防隊は一月から三月までのあいだに一〇一回も出動している。あまりに中国兵の放火が多かったからこそ、日本軍は消防団を新設して消化に努めていたのである。 ・この煙は中国軍による焼き払い作戦(清野作戦)後の燻りと考えられる。 日本人撮影の写真(四) 村瀬守保氏〔兵站自動車第十七中隊二等兵〕 ・私たちが肝に銘じておかねばならないことは、戦争には必ず多くの死体が発生するということである。否が応でも死体が目につき、撮影者の関心に応じて、死体がカメラの被写体になることにもなろう。 ・今日言われるように、日本軍が南京に入城するや、手当たり次第に市民を殺しまくっていたのであれば、そのような死体の写真があっても当然であった。 ・ところが、マギー師はそのような写真は撮っていない。 ・撮影者判明の写真は、日本軍が市民を殺しまくってなかったことの、むしろ傍証となっているように思われる。 エピローグ 「証拠写真」として通用する写真は一枚もなかった 完全な検証への決め手を求めて ・発掘された国民党宣伝部の極秘文書『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』のなかの「撮影課工作概況」に見られる秘密報告で、宣伝処が、プロパガンダ写真をつくるため「撮影工作」に本格的に乗り出したのは、一九三八(昭和十三)年春だったことがわかった。 ・つまり、一九三八年七月に出た宣伝本、 ・それにしても、なぜ国民党宣伝部は南京大虐殺が生じたと言われる真冬の季節に注意を払わなかったのか。 その決定的な理由は、国民党宣伝部が「南京で虐殺」という認識をもちあわせておらず、ただたんに抽象的な戦争プロパガンダを展開していたということにあった。 ・今でいうエキストラを動員して、海外向け宣伝用短編映画や写真が宣伝部を中心にして作られていたのである。 「親中反日」の国際世論を創出せよ ・国民党宣伝部が撮影工作を中央通信社撮影部に一本化したのが一九三八年春であった。それから中央通信社撮影部が鄺光新聞撮影通信社となった。 ・外国人記者の「名義」で全世界の新聞雑誌に掲載された中国関係のニュースの九五パーセントが、鄺光新聞撮影通信社の「撮影工作」した「抗戦用写真」であった。 ・抗戦用写真が外国人記者の名義で全世界の新聞雑誌に出るよう、国民党宣伝部は必死の努力をつづけていたのである。日本に反対するアメリカの中国支援こそ国民党の死活問題と見ていたからである。 ・そのため、「アメリカの新聞雑誌にウソをつくこと、騙すこと・・・・・・アメリカを説得するためなら、どんなことでもしてよい」という政策が、「中国政府唯一の戦争戦略」になっていた、と回想するのは、後年の著名なジャーナリスト、セオドア・ホワイトである。大学を出たばかりの彼は白修徳という名で国民党宣伝部の「顧問」となっていた。 ・日本も世界も、国民党宣伝部のプロパガンダ写真に惑わされ、七十年前の戦争プロパガンダに今にいたるも完敗しているのである。 憎悪の感情の連鎖反応を断ち切るために 結論 ・一つは、日本軍が南京で六週間にわたって、大量虐殺、強姦、放火、掠奪をしたという「証拠写真」は一枚もなかったということである。 ・私たちは「虐殺があったか、なかったか」を検証しようとしたのではない。あくまでも南京大虐殺の証拠に使われている写真が、はたして証拠写真として通用するものなのかどうかを検証したのである。 ・二つ目は、今日流布する南京大虐殺の「証拠写真」なるものは、 ・この二冊の本に少なからず出てくるのは、自国民とアメリカを反日親中に向かわせる抗戦用写真として収集、盗作ないしは撮影工作されたプロパガンダ写真であった。 ・三つ目は、この二冊の宣伝本をもとに、こんどは中国共産党の新たな情報戦が一九七〇年代から始まったということである。 ・中国共産党の時代になっても写真の修正など「日常茶飯事」であり、それは現代までつづいている。 ・一九七二(昭和四十七)年に出版された本多勝一『中国の日本軍』中の掲載写真も、国民党のプロパガンダ写真に、改竄された説明を付したものをふくんでいた。 ・ウソを取り払おうとする努力を妨げようとする人こそ、日中関係の真の構築を妨げているのである。このウソが取り除かれなければ、ウソによって作りだされた憎悪の感情が、中国における嫌中の悪しき連鎖反応を生み出していく。 ・このウソが取り除かれるとき、はじめて真の日中友好が始まるであろう。 |