
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年10月28日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
85 |
16/10 |
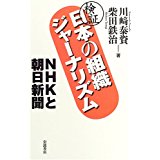 |
検証 日本の組織ジャーナリズム ―NHKと朝日新聞 |
川崎泰資 柴田鉄治 |
岩見書店 |
◎ |
対談 なぜNHKと朝日新聞なのか ――弱体化する組織ジャーナリズムを考える 川崎 ・イラク戦争の取材で日本の新聞・テレビなどの組織ジャーナリズムは、戦争が始まる前に全員バグダッドから引き揚げてしまった。外国メディアはみんな踏みとどまっているなかで、日本のジャーナリストで現地に残ったのはフリーだけだった。 柴田 ・日本の組織メディアがいかにジャーナリスト精神を失ってしまったか、それを如実に示す象徴的な出来事だった。命がけで取材にあたったベトナム戦争の時とは大違いだった。 川崎 ・放送についていえば、英国もフランスも、公共放送や国営放送の取材陣はみな現地に踏みとどまって報道している。NHKが全員引き揚げてしまったことは、公共放送の責任を果たしていないことだ。 ・自衛隊を派兵したサマワからも、非戦闘地域だったはずなのに、危険だからと放送も新聞も記者を撤退させている。 ・今の組織メディアには、ジャーナリストというのは足で稼ぐことだし、地を這う仕事だという意識が希薄だ。ジャーナリズムというのは命がけでやる仕事だということが忘れられているのではないか。 ・BBCとNHKでは、ジャーナリズム精神に雲泥の差がある。イラク戦争でも、BBCはブレア政権批判をがんがんやっており、米国寄りで政府べったりのNHKとは基本的に異なる。 ・本来、新聞は権力を監視し、批判するところに本領がある。 ・有事法制が成立したのは、朝日新聞の読売化によるものだといわれている。 【私見 : これはどう見てもおかしい。一新聞の論調の変化がが法律を作るなど、驕りも甚だしい。国民はそんなにアホではない。事実、朝日の慰安婦問題等の一連の錯誤報道も、化けの皮が剥がれて世論を誘導できなかったではないか】 ・日本の報道界で「朝日の読売化、NHKの国営化」が進んだら、日本はお先真っ暗だ。 【私見 : 問題はそこではなく、ジャーナリスト精神が無くなったことにあると言っていたのではないのか。真っ暗なのは、論調とかスタンスではなく、取材能力の劣化(敵前逃亡、負け犬の遠吠え)、記者クラブ制度などにある】 第Ⅰ部 漂流する公共放送―――NHK 第3章 イラク戦争報道とNHK 2 「従軍記者」という名の米軍広報 ・戦争になると最初の犠牲者は「真実」であるとは、第一次大戦後にアメリカの上院議員になったハイラム・ジョンソンが残した名言である。これは真実を隠すことによって戦争は遂行されるということにもつながる。 3 逃げ出した日本のメディア ・今回のイラク戦争での日本のメディアの珍事といえば、戦争の取材にイラクに出掛けながら、アメリカのバクダッド攻撃の前に、放送も新聞もフリージャーナリストを除くマス・メディアの記者やカメラマンが全社いなくなったことである。 ・しかし世界の各報道機関は新聞社や通信社はもちろん、テレビ・メディアもかなり多数がイラクに踏み止まり、テレビではアメリカの各放送局、イギリスのBBC、ITN、フランスの国営放送、ドイツのZDFなどの大手の放送局のジャーナリストは残った。 ・フランスの国営放送の記者は「国民の血税で番組を作る国営放送が国民のために、今この大事なときに取材をしなかったら国民は受信料の引き上げを認めないだろう。イラクに派遣するスタッフの生命保険料が膨大な金額に上るのは承知の上だ。それを含めての受信料である」と言い切ったという。 ・この発言は、イラクからの報道が報道機関が代償を払う価値のある仕事だというコンセンサスがフランス国民の間にはあることを示している。またこれは国営なり公共放送という公的な役割を果たさなければならない機関の責務は、私企業とは異なるという見識を示すものであり、ここからはジャーナリズムが成熟している西欧の風土をうかがい知ることができる。 ・視聴者に充分な情報を提供することこそ本来、「あまねく」全国に放送を行なうNHKの使命であり、自社取材の重要性を主張するのなら、当然、現地に要員を残すべきであった。フランスの国営テレビやイギリスのBBCのように、受信料で運営する企業にはそれだけの責務があるという気概を持つことが当然なことであろう。 4 報道規制 ・NHKのイラク報道が、アメリカや日本政府の言い分そのままだというのは、今や定説になっている。 ・有事法制の中の「国民保護法制」では「指定公共機関」を設けて、政府の指示どおりの報道をすることが義務付けられる。報道機関にとっては死活問題であるのに、NHKは「指定公共機関」を当然のことのように受けとめているようだ。 【私見 : 有事における報道規制は混乱を避けるためにも必要であり、それをNHKが担うことも構わないと思う。問題は、コントロールされた情報の中身を他のメディアやジャーナリズムがきちんと検証して国民に伝える牽制機能があるかどうかが問題だ。戦前、大本営による情報操作はあったろうが、メディアがよってたかって国民世論に迎合し戦意高揚を煽ったことも事実だ。】 ・戦前の日本で唯一の放送機関であった社団法人の日本放送協会が、大本営発表で偽りの放送を続けて戦意高揚に一役も、二役も果たした過去が教訓として何も生きていない。 ・サマワから日本の新聞、放送などの組織ジャーナリズムがほぼ一斉に撤退した後、自衛隊員自身が撮った現地での隊員の交替式の映像などを、何のクレジットも入れずに放送で使っている神経が不思議だ。これでは大本営発表の再来ではないか。 第Ⅱ部 萎縮するリーディング・ペーパー―――朝日新聞 第5章 新聞論調の二極分化のなかで 2 二極分化は八〇年代から ・戦前・戦中の日本の新聞は、政府の厳しい弾圧と新聞側の自粛との繰り返しによって、しだいに政府批判の勢いを失い、一九三一年の満州事変あたりを境にジャーナリズム機能を喪失した。その後は、報道規制のさまざまな法律と検閲によって、戦争批判どころか、戦争推進に協力し、国民を戦争に駆り立てるばかりの報道機関になってしまったのである。 【私見 : 著者は、政府側の弾圧を強調し、被害者的論調で書いているが、政府にとって都合の悪い情報は統制されただろうが、国威発揚や国民感情を煽って、逆に軍や政府をけしかけたのは、むしろ新聞の方ではないのか。満州事変がいい例だ】 ・こうした戦前・戦中の報道を深く反省して、どの新聞も「二度と過ちを繰り返さない」と誓って戦後の再出発をした。そのため、戦後の新聞は、だいたい六〇年代ごろまでは政府に対する姿勢も厳しく、「野党精神」もこぞって旺盛だった。 【私見 : 報道に必要なのは「野党精神」ではないと思う。真に必要なのは事実を明らかにして、何が正しいのかを国民の前に示すことであって、単なる批判や反対論はかえって国民を不安に陥れるだけだ。報道に求められるのは、事実を見抜く力と、その事実を把握し判断する能力だ。】 渡辺恒雄氏の論説委員長から大転換 ・八〇年代に入って読売新聞が大転換する。 ・八三年の元旦社説で「日本は西側の一員」と強調し、米レーガン政権と中曾根政権を支持する路線を明確にした。そしてさらに八四年の元旦社説で、名指しこそ避けたものの、はっきり分かる形で朝日新聞を攻撃して、ここに、朝・読対決を中心とする「新聞論調の二極分化」と呼ばれる状況が生まれたのである。 ・八四年の元旦社説 「両翼の偏向思想が、マスコミを侵す危険がないとはいえない。特に警戒すべきは左翼偏向である。今日の左翼偏向派は、決して自ら「左翼」と称することはしない。平和とか軍縮とか反核といった大衆の耳に快くひびく言葉の中に、それを隠そうとする」「大部数を発行する新聞は、どっちつかずのあいまいな国際的無責任、進歩を偽装した保守的、観念的中立主義に耽溺することは許されないと考える」 3 読売・朝日の憲法対決 ・この二極分化をいっそう際立たせたのが九一年の湾岸戦争である。 ・読売・産経新聞の主張 「日本だけ平和であればいいという「一国平和主義」では世界の孤児になる。憲法も改正して、日本も軍事的な国際貢献に参加できるようにすべきだ」 ・これに対して、朝日・毎日新聞などはこう反論した。 「日本がすべき国際貢献は非軍事面でいくらでもある。冷戦が終結して日本の平和憲法が輝きを増しているとき、改憲なんてとんでもない」 【私見 : 湾岸戦争で、日本は巨額の資金を拠出しながらも、世界平和のためには一滴の血も流さないのかと糾弾された。金以外のことは普段からやっているしやるべきことで、一朝有事の際に何を今さらという感じもするが】 ・九四年十一月の読売改憲案 自衛力の保持を明記し、現憲法では禁じられている集団的自衛権(同盟国が攻撃されたとき出動できる権利)の行使も含めて、国際協力のため海外派遣もできるとしている。その一方で、軍事大国化への歯止めとして、大量破壊兵器の禁止、徴兵制の禁止、文民統制なども盛り込んでいる。 「普通の国」対「非軍事に徹する特殊な国」 ・朝日新聞は九五年五月の憲法記念日に、「護憲大社説」を発表した。内容は、 ①現憲法は、依然としてその光を失っていない。改訂には益よりもはるかに害が多く、反対である ②日本は非軍事に徹する。国際協力にあたっては、軍事以外の分野で、各国に率先して取り組む 【私見 : ②は、日米安保条約に完全に頼るということ。でなければ、結局自前で軍隊を持たなければならなくなる。中国、北朝鮮の動きに、丸裸でどう対処しようというのか】 の二点に要約されるとしている。そのうえで「あえて比喩的にいえば「良心的兵役拒否国家」を目指そうというのである」と記している。 ・読売新聞が「軍事貢献もできる普通の国」を目指そうというのに対して、朝日新聞は「非軍事に徹する特殊な国」を目指そうというのである。 ・この対立は、かねてから日本国民を二分する最大のテーマなのだから、本来なら政党が担うべきものであり、この対立軸をもとに政界の再編制がなされてもいいはずなのである。ところが、正当がそうならないので、新聞がその代役を務めているような形なのだ。 【私見 : 日本では、護憲派は野党勢力として成り立たたなかった。民進党は党内が統一されていない。共産党と社民党だけでは、護憲勢力といっても世論を二分できない。国民の大勢が普通の国を目指そうという選挙結果になっているのに、朝日は、それでも少数意見を押し通すのか。マイノリティーとしての意見と言うことならば理解できる】 第6章 有事法制と朝日新聞 戦後の日本は軍事優先を認めない社会 ・有事法制の制定は、その社会が軍事優先の思想を容認することを意味する。戦後の日本社会は、戦前の反省から世界でも珍しい「軍事優先の思想を認めない社会」としてやってきたのではなかったか。 【私見 : 有事法制を作ることと軍事優先の思想とは全く異なる。元々、日米大戦で負けて軍備を取り上げられたが、東西冷戦で日本を東側諸国の盾にすべく安保条約の締結とともに日本に対して自衛隊を持たせることになった。有事法制下では、文民統制をきちんと機能させることが大前提。軍事優先にはしてはいけない】 4 「ウィングを広げるために」と言うが ・現行法を守りながらの戦いなんてありえないから、万一、有事となったら超法規的な行動をとるようになることは認めざるを得ない。しかし、それと、外国からの武力攻撃など考えられない平時に有事法制を制定して「軍事優先の思想を認める社会をつくること」はまったく別のことなのである。 【私見 : ①予め超法規的な判断と行動を時の政権に委ねる事こそが問題。結果的に無制限の軍事行動を許すことになる。平時の時こそ、いざという時の備えを可能な限り想定して準備し、時の政権が勝手に超法規的な行動をとれることがないように法整備しておくのは当然。 ②外国からの武力攻撃など考えられないというのはナンセンス。今でも危機は目前に迫っている】 第7章 北朝鮮、中国報道のトラウマ 5 中国文革報道の誤り ・中国当局の顔色をうかがって、事実の報道をためらった中国報道の誤りも重大だが、その誤りをきちんと検証せず、誤りだったと総括していないことは、さらに重大だろう。 朝日新聞の北朝鮮・中国報道が、いまだにトラウマを引きずっている原因も、まさにそこにあるといえる。 ・ジャーナリズムは常に過去の報道の検証ををくり返し、そこから教訓を汲み取って先へ進んでいかなくてはならない。 第8章 時に迷走する論調、歴史認識 ・「言論の自由」「報道の自由」に関わる規制は、どんな些細なものでも認めるべきではない。最初は些細なものでも、いったん規制が始まると、どんどん拡大されていくのが報道規制の特徴であり、戦前の教訓である。 第12章 歪められる世論調査報道 2 設問を操作して誘導する ・イラク戦争をめぐって開戦の前後に行なわれた読売新聞の世論調査で、結果は、当然一二%、やむを得ない六四%、納得できない二二%という数字が出た。中間的な選択肢を大半の人が選んでしまった。 ・この設問の場合、「やむを得ない」と答えた人の心理を分析すると、「日米同盟があるからやむを得ない」「北朝鮮問題があるからやむを得ない」と考えた人が相当数含まれていることは間違いなかろう。しかし同時に、まったく逆の「本当は納得できないのだが、起こってしまったことはしかたがない」という意味でこの選択肢を選んだ人がかなり含まれといることも事実である。 ・この調査結果を二〇〇三年三月二五日付の一面で、「イラク戦争 政府の米支持「当然」「やむなし」七六%」と報じた。「当然」と「やむを得ない」を一つにくくって「容認派」だとしたのである。 ・「やむを得ない」が即「容認」でないことは、いうまでもなかろう。むしろ、「反対だが、しかたがない」という点で、反対派に近い人が大勢含まれていることは明らかだ。それは、開戦前の同紙の世論調査で「国連決議なきイラク攻撃」には九一%が反対していた事実と重ね合わせると、いっそう明白である。 我田引水の読売社説 ・にもかかわらず、読売新聞はこの調査結果をもとに、その日の社説で「イラク戦対応、「正しい決断」と評価した世論」という見出しを掲げたのである。「やむを得ない」が、ついに「正しい決断と評価」にまで「昇格」してしまったのだ。 ・読売新聞は、二〇〇一年一〇月の米国のアフガン攻撃の時にも、同じ手法を使って報じている。世論調査の設問に、「やむを得ない」という選択肢をつくって質問し、それを加えて「容認」という見出しまで掲げたのだ。 ・一般に、報道機関は、自社の主張と世論の動向が一致していることを望むものである。しかし、必ずしもそうなるとは限らない。そのときは、なぜ、世論と違う主張をするのか、その理由を詳しく丁寧に説明することだ。 ・世論の動向と異なる論調を主張することは、報道機関にとって決して恥ずかしいことではなく、世論調査の設問を操作して自社に都合の良い結果を出そうとするようなことこそ、真に恥ずべき手法だといえよう。 提言 これからどうすべきか [組織ジャーナリズム全体に望むこと] タブーと記者クラブをなくせ 川崎 ・日本のジャーナリズム全体のあり方として、タブーと記者クラブをなくすことだ。 ・かつて菊(皇室)・星(自衛隊)・鶴(創価学会)が三大タブーだといわれたが、鶴のタブーはいまだに続いているし、広告代理店「電通」なども含め今や強大化したマス・メディア自身がタブーになりつつある。メディアの相互批判がもっと必要だ。 柴田 ・もともと記者クラブはメディアが一致協力して権力と対抗するために生まれたものだが、今やメディアの取材力を弱める作用ばかりが目立ち、メリットよりデメリットのほうが大きくなっている。 川崎 ・記者クラブの閉鎖性、排他性は日本独特のもので、とくに若い記者がここから出発することが問題だ。 ・発表ジャーナリズムと酷評されるような官庁の広報まがいの記事の氾濫は、足で稼ぐべき記者の本質を歪めている。 ・各種の報道規制を安易に受け入れるのも記者クラブの存在があるからだ。 柴田 ・権力に対する監視役どころか、権力側がメディアをコントロールするための道具にさえなっている。 ・報道規制は、どんなに小さくとも許してはならない。必ず拡大解釈して規制を強める方向に進んでいくからだ。それが戦前の教訓でもある。 ・また、政府は、電波の管理権を武器に新聞へのコントロールを強めようとねらっているので、新聞の批判力を高めるためにも、新聞とテレビの系列化はやめるべきだ。 川崎 ・放送について総務省が監督官庁になっているのは世界の先進国のあり方からみてもおかしい。戦後の放送民主化で短期間だけ実現したような、政府から離れた独立の行政委員会に戻す必要がある。 [組織メディアの幹部に望むこと] まず社内言論を活発に 柴田 ・社内の自由な言論を封殺しているような組織に、健全なジャーナリズムが育つはずがない。 ・組織メディアの幹部は、まず社内で自由にものが言える空気をつくりだすこと。間違っても箝口令を敷くような組織にしてはならない。 川崎 ・それには、幹部に相応しい人材を起用することだ。NHKの隠蔽体質、物言えぬ空気、箝口令などはもってのほかだ。 柴田 ・ジャーナリズムの組織では、幹部は、記者ひとり一人の志を大切にすることが何よりも大事だ。そして外部からの圧力があれば、記者を守ってそれをはね返す役を幹部がになうべきなのだ。現状は、組織防衛ばかりが優先され、その逆になっていないか。 川崎 ・幹部がはね返さずに、内部に責任をとらせるような風潮は、ジャーナリズムの機関として失格である。 ・また、社会に対して「説明責任」をしっかり考えることも幹部の仕事だ。まが隠そうとする幹部が多すぎないか。 ・不祥事が起きた場合、幹部は自らがしっかり責任を取ることだ。組織防衛的な、形式的な対応ではだめで、「トカゲの尻尾きり」などは論外である。 [記者一人ひとりに望むこと] 志を自らに問い直せ 柴田 ・報道の自由が失われた社会は、どれほど人権が損なわれるか、戦前の日本社会や、あるいは戦前の日本とそっくりな今の北朝鮮の状況などから類推して、ジャーナリズムの役割を再認識することだ。 川崎 ・常に使命感を持つことであり、権力の誘惑に屈しないこと。「権力に愛されるのはジャーナリストではない」「権力に憎まれることを恐れてはならない」 あとがき ・ジャーナリズムの仕事は、日々の出来事の報道ではあるが、それは歴史に残るものであり、一過性のものと考えてはならない。常に過去の報道を検証し、過ちがあれば、それを正していく勇気が必要である。それが、国民の信頼を得る道にもつながるのだ。 ・このところ新聞やテレビに、チェック機能のみならず特ダネやスクープもなくなっているように感じる。 ・その点では、記者クラブに依存しない週刊誌などの雑誌ジャーナリズムのほうが、タブーへの挑戦も、スクープも目立って、ずっと元気なように見える。 |