
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年10月24日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
87 |
16/10 |
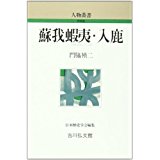 |
蘇我蝦夷・入鹿 |
門脇禎二 |
吉川弘文館 |
◎ |
はしがき ・蘇我「 ・しかしながら、いったいかれらを ・それは、蘇我「蝦夷」「入鹿」の死後、短くみても約一世紀も経た時期の、そして五百数十万~六百万の古代日本人のうち一〇〇人にも足らない古代貴族のうちの書記編者の史観であった。かれらが、それなりの「蝦夷」「入鹿」の人物像を描出するのは、『日本書紀』の国史としての性格からいって当然である。 ・けれども、それをすべての古代人が、まして二〇世紀の後半を生きるわたくしどもまでが、そのような人物像に同調する必要はないだろう。 はじめに ・主な史料となる『日本書紀』は、かれらの生きた宮廷の制度や人物像を、八世紀以降の律令制下の制度や観念で述作しているから、それらをまず七世紀前半のものにもどして理解していく必要がある。 ・わたくしどもはこの時代を、余りに『日本書紀』の描出したとおりに教えられすぎてきたし、いまの中学校や高校の教科書でもなおそれを踏襲している。 ・一〇〇年近くおこなわれてきた近代の教育・文化政策のもとで培われた国家観や歴史意識が社会通念化していることによって、すでに固定してしまった七世紀の歴史像は容易に崩れない。 1 『日本書紀』について 諸資料と『日本書紀』 ・『日本書紀』は客観的な記録集でも実録でもない。つまり、その編述者たちのめざした述作の目的にそって、かれらの史観・思想性、教養などにもとづき『日本書紀』じたいが、特定の歴史的所産として、特定の歴史的性格をもつものである。 『日本書紀』の成立年代 ・『日本書紀』は、ながいあいだ奈良時代の養老四年(七三〇)に完成したと教えられてきた。 『日本紀』と『日本書紀』 ・しかしながら、『日本書紀』が養老四年に成立したとの誤った理解のもとになっている『続日本紀』養老四年五月癸酉条に記されているのは、明らかに『日本紀』であって『日本書紀』ではない。 ・ここにいう『日本紀』と『日本書紀』は同じものが異称されているだけなのか、それともほんらい別ものなのか、あるいは両者の内容はどう関連するのかなどについて、論議は、未だに決着がついていない。 ・また、『日本書紀』という呼び方そのものからしておかしいことも、つとに指摘されている。書は紀伝体の歴史を、紀は編年体の歴史を示すのが通例であるから、 ・『日本紀』は、『続日本紀』の条文いらいつぎの『日本後記』以下の国史ではみな「日本紀」と記し、いくつかの太政官符でも同様に記される。 ・しかし一方、『日本書紀』は、非官撰のものの記事・私記・仏書などにみえてくる書名である。 ・こうした大勢をおさえてみれば、やはり国史や官符などにおける正式の称は『日本紀』であったように思う。 ・なお、『源氏物語』『紫式部日記』『大鏡』あるいは『愚管抄』などにも、いずれも『日本紀』とでてくるのであって、『日本紀』と『日本書紀』とは混用されたようなものではない。 ・中世初期までは、貴族たちには『日本紀』というのがほんらいの署名として一貫して意識されていたように思える。 『日本書紀』と『日本紀』 ・『日本書紀』という書名は、「公式令集解」の古記の用例がもっとも古い。古記の成立は天平十年(七三八)のこととされるからである。 ・これと関連して、『正倉院文書』の天平二十年六月十日写章疏目録にみえる「帝紀二巻 日本書」という記事が、とくに気にかかる。 『日本紀』と『日本書』 ・『日本書紀』とか『日本書』という呼び方が、天平中期から後期にかけてみえはじめていた。 ・それも、『日本書紀』は公式令についての法家の古記説に、『日本書』は僧侶の写章疏目録にみられたように、当時にあってはもっとも漢籍の高い人びとの書きもののうちにであった。 『日本紀』から『日本書(紀)』へ ・『日本紀』がもとで、『日本書』や『日本書紀』の称が天平中~後期に生じ、しだいに『日本紀』と『日本書紀』が混用されるようになったと理解している。 ・ことに古代貴族が没落した中世以後には、元来の正称たる『日本紀』の観念が失われていったと思われる。 ・『日本紀』が真の「紀」に非ずとされた以上、単にその呼称にとどまらず、真の「紀」からさらには真の「書」にまで整えゆくべき努力のあともまた古くからあった筈である。 ・事実、現在の『日本書紀』にみえる「内臣」の官や歌謡のうちには、養老四年(七三〇)後の官や歌謡の反映とみられるものがあることが指摘されている。 ・あるいは高句麗の国号などもすべて高麗で統一されているようなこともある。 ・また中世以後の写本にさえ記事の変改・略補の例があるという。 ・したがって、七世紀に生きた蘇我「蝦夷」「入鹿」とかれらの生きた時代の動向を述べる『日本書記』の記述のうちにも、そうした作業のうちに生じた修飾・略補・改変のあとがあるとみなければならない。 2 七世紀の宮廷制度 古代貴族の天皇観 ・そもそも、日本古代の歴史思想は、天皇観と不可分に結びついているのであるが、天皇はかならずしも最高の有徳者たるが故に君主とされたのではない。 ・その点、儒教的な徳治主義の精神や天命思想にもとづいてみられた中国の古代帝王とはちがう。 ・むしろ、皇位の決定にあたってより重視されたのは、天皇の血統性とその尊重性とであった。 第二 「大臣」蘇我大郎鞍作 ・蘇我氏じしんが、がんらい百済の貴氏八姓のうちの木氏の、木(羅)満致の渡来に発した。 |