
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年4月21日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
93 |
16/11 |
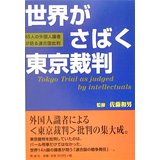 |
世界がさばく東京裁判 |
佐藤和男 監修 |
明成社 |
☆☆ |
序 東京裁判を裁判せよ 初代国際連合大使 加瀬俊一 ・かねてから私は「東京裁判を裁判せよ」と主張し、歴代首相にもその必要を説いた。 ・要するに、勝者の敗者に対する一方的断罪であった。日本の立場を完全に無視しており、パル・インド判事の明言を借りれば、「歴史の偽造」なのである。 ・それに、「法律なければ犯罪なし」の原則に反する。しかも、わが国民は戦勝国の世論操作によって洗脳され、いまだに裁判の真相を理解していない。これを是正せぬ限りわが民族の精神的独立は回復しがたい。 ・日ソ中立条約に違反して満州に侵攻し、虐殺掠奪をほしいままにしたソ連には明らかに日本を裁く資格は皆無である。 ・また、六十六都市を無差別爆撃して四十万の非戦闘員を殺戮したうえ、日本が終戦を模索していることを知りながら、原爆を投下したのは、天人ともに許さざる重大な国際法違反である。 レーリンク判事の ‹東京裁判› への総括的批判 ―― はしがきに代えて ―― 佐藤 和男 ■東京裁判史観の克服のために ・戦後、日本社会に巣くってその骨髄をむしばみ、健全な国民精神を頽廃させてやまないもの、いわゆる東京裁判史観を凌ぐものはないであろう。 ・昭和の初期から二十年(一九四五年)に至るまでの日本の対外軍事行動を、ことごとく「侵略」の一語をもって否認し去ろうとする戦勝連合国側の史観は、昭和二十一年~二十三年に占領軍によって強行された極東軍事裁判所によるわが国の戦時指導者の裁判(東京裁判と通称されるもの)によって、敗戦によって意気消沈する日本国民の前に、鳴物入りで喧伝された。 ・日本国民は、あたかもそれが厳正な司法裁判であるかのごとく錯覚し、爾来、多くの者が祖国の歴史を誇りを持って顧みることを忘れ、甚だしきは国家を呪詛するに至った。 ■注目すべき文献『東京裁判とそれ以後』 ・東京裁判を国際法の視点から批判を行なった『東京裁判とそれ以後』 著者の一人は、東京裁判にオランダ代表判事として参加されたベルト・レーリンク博士である。 ■レーリンク博士の学問の特徴 ・東京裁判を境にして専門的研究分野を刑法学から国際法学に変更したレーリンク博士は、第二次世界大戦を契機として実現を見たアジア・アフリカ諸国の解放という歴史的事実の重要な意義に着目して、それに関連して、日本の遂行した大東亜戦争が世界史の中で果たした積極的な役割を非常に重視するに至るのである。 ■東京裁判とレーリンク博士 ・GⅡ(占領軍総司令部・参謀第二部)の長であったウィロビー将軍は「東京裁判はは、有史このかた最悪の偽善であった」語った。 ・ウィロビーがいわんとしたのは、日本が開戦直前に置かれたような状況にもしアメリカが置かれたなら、アメリカとても日本と同様に戦争を遂行したであろうし、その結果敗戦したら重要な責任ある地位にあった軍人が戦争犯罪人として裁かれるというのは、許しがたいということであった。 ・レーリンク博士は、開戦前の日本への連合国側による石油輸出禁止措置に言及し、日本にはその石油事情からして二つの選択肢しかなかったこと、すなわち、戦争を回避し、自国の石油ストックが底をついて、自国の運命を他国の手に委ねるか、あるいは、戦争に打って出るかの二者択一を迫られていたことを指摘し、その結果遂に日本は開戦に踏み切ったのだ。 ・ウィロビーが語ったのは「自国の死活的利益がこのようなかたちで脅かされる場合には、どこの国でも戦うだろう」――日本が戦ったのは自存自衛のためだったことを含蓄する言葉――ということだったと結んでいる。大東亜戦争に突入した日本のやむを得ざる事情について、レーリンク博士は正確に理解していた。 ・レーリンク博士は、「侵攻戦争の犯罪性についていえば、侵攻の罪〔平和に対する罪〕が敗戦国にだけ適用されたことは、明らかだ。しかし、検察官は、自身が目下適用している法は、現在は裁判官の席にいる諸国をも拘束するものである」ことを、公然と語っっている。 ■国際法における戦争 ・国際法(慣習法および条約)では、戦争は諸世紀を通じて合法的制度とされてきたが、日本国民のうち特に戦後教育を受けた世代は「戦争はすべて悪」としか考えない傾向が強く、世界の通念に背反している。 ・近世以降、諸民族国家が併存する国際社会で、各国家は基本的に自国民の安寧と福祉を求めて内外諸政策を実施してきたが、他の国家と利害関係が衝突して、平和的手段では紛争を解決できない場合に、戦争という最後の手段に訴えてきたのであり、国際法も戦争をその規律対象のなかに包容してきた。 ・往昔、騎士や紳士の相互間で、男の名誉や意地のために決闘が行なわれたが、人格的に平等の立場にあって闘う両者については、いずれが悪いとは断定しがたいものがあった。 ・国際法は国家間の戦争をそのような決闘になぞらえて、軍隊と軍隊との間で行われる戦争そのものは合法と認めてきた。 ・そして、国家は慣習国際法上、重要な権利の一つとして戦争権を持つものと認められ、戦争権は開戦権と交戦権のかたちにおいて具体的に行使された。 ・国際法では、国家は戦争遂行に際して「交戦法規」(戦争法規、国際人道法と呼ばれるものもある)を遵守しなければならない。 ・交戦法規の具体的内容(主なもの) ①一般住民(市民、民間人)ないし非戦闘員を攻撃・殺傷してはならない(戦うべきはあくまでも軍隊と軍隊である)、 ②軍事目標とされるもの以外の民間物や非防衛都市を攻撃・破壊してはならない、 ③不必要な苦痛を与える残虐な兵器を使用してはならない、 ④捕虜を虐待してはならず、原則的に食物・衣料・寝所につき自国将兵と対等な扱いをしなければならない、 ・日清・日露の両役で日本軍が国際法学者を法律顧問として従軍させてまで交戦法規を厳守した徹底ぶりには、全世界が賞讃を惜しまなかった。 ・しかし、大東亜戦争中に連合国側がこういう戦争法規の重大な侵犯を行った事例は、枚挙にいとまがない。 ・たとえば、日本国内の多数の都市への無差別――軍事目標と民間物を区別しない――爆撃、広島・長崎への原子爆弾の投下、民間人・非戦闘員への暴行(特に満州での日本人婦女子に対するソ連軍の暴虐は言語に絶するものがある)、捕虜(戦犯容疑者を含む)の虐待、等々である。 ・ちなみに、交戦法規に違反する行為が、国際法上で伝統的に認められてきた戦争犯罪であって、違反者は戦争中に敵側に捕えられれば軍事裁判にかけられて処罰される(第二次大戦後には、自国の軍事法廷でも裁かれる傾向が強くなった)。 ・もちろん、交戦法規に違反して、民間人の服装でテロ行為をするいわゆる便衣兵は、捕虜の待遇を与えられることなく、処断される。また、武器を捨てても自軍に加わる意志を持って逃走する敵兵は、投降したとは認められないので、攻撃することができる。 ・圧倒的優位を誇る軍事力を恣意的に行使して、実定国際法を蹂躙した第二次大戦中の連合国側の責任は決して不問に付されてよいものではない。 ・国際法的に厳密にいえば、戦争は特定の「法的状態」であり、またそのような状態のもとでの諸国による交戦権の行使でもある。 ・国家は「開戦権」を行使して、一方的な宣戦布告(開戦宣言――戦争意思の相手国への伝達)により、相手国との間に正式な「戦争状態」を創出できるものとされた。こうして交戦国となった国家は、国際法により「交戦権」の行使を許容されることになる。 ・交戦権とは、平時ならば禁止されている以下のごとき諸行為を、戦時に合法的に遂行できる権利である。 ①敵国との通商の禁止、 ②敵国の居留民と外交使節の行動の制限、 ③自国内の敵国民財産の管理、 ④敵国との条約の破棄、またはその履行の停止、 ⑤敵国兵力への攻撃・殺傷、 ⑥軍事目標・防守地域への攻撃・破壊、 ⑦敵国領土への侵入とその占領、 ⑧敵国との海底電線の遮断、 ⑨海上の敵船・敵貨の拿捕・没収、 ⑩敵地の封鎖、中立国の敵国への海上通商の遮断・処罰、 ⑪海上での中立国の敵国への人的物的援助の遮断・処罰、 等。 ・⑦に関連して、アメリカ、イギリス、オランダなどの敵国の植民地――その国の領土の一部である――であったフィリピン、ビルマ(現在はミャンマー)、東インド諸島(インドネシア)等への日本軍の進攻は、合法的な交戦権の行使であって、 “侵略” などではないことは自明である。 ・オランダとの関連でいえば、昭和十七年に今村均将軍の率いるわが第十六軍がスマトラ島南部やジャワ島に進攻して、オランダ軍は全面的に降伏している。 ・日本軍は占領行政を敷くと同時に、現地の独立運動の闘士であったスカルノやハッタ博士を獄中から救い出して、彼らを中心にしてインドネシア人民に将来の独立達成のための諸準備をさせたが、わけてもペタ(郷土防衛軍)を育成して青壮年に軍事教育を行ったことは、後のインドネシア人民の旧宗主国に対する独立戦争の勝利に大きく貢献したことが認められている。 ・なお、国際法の意味における「戦争」(戦争状態)が終了するのは、原則として交戦国間に締結された平和(講和)条約が発効する時点においてである。したがって、大東亜戦争が法的に終結したのは、日本と連合国との間のサンフランシスコ講和条約の発効の時点(昭和二十七年四月二十八日)においてであり、日本国民が一般に考えているように昭和二十年八月十五日ではない。連合軍は、戦闘段階終了後の占領段階において、連合国の利益にかなった日本社会の改造計画を、戦争行為(軍事行動)として推進したのである。 ■不戦条約の解釈と東京裁判 ・戦争は久しきにわたって攻撃戦争(侵攻戦争)――国家が不当な動機に基づいて他国に攻撃を仕掛ける戦争――も、防衛戦争(自衛戦争)――他国による不当な攻撃に対して、本質的に自国の権利を守るために行なう戦争――も、ともに合法とされてきた。 ・一九二八年にフランスとアメリカの主唱によってパリで締結された「戦争放棄一般条約」(不戦条約と通称)は、上の二つの戦争を区別して、侵攻戦争を違法化(犯罪化ではない)したものと認めらてれいる。(違法化していないとする学説は、締結当時にも、また現代においてもアメリカの学者などの間で見られる)。 ・不戦条約の眼目ともいうべき第一条において、締約諸国は「国際紛争の解決のために戦争に訴えることを非難し、相互関係において国策の手段としての戦争を放棄する」ことを誓約した。 ・「国策の手段としての戦争」は「侵攻戦争」を意味するものと、また「国際紛争を解決するための戦争」は「侵攻戦争」に該当するものと、締約諸国の間で了解され、以後、この二つの表現は国際社会で――特に外交場裡で――この意味で慣用されることになった。 ・重要なのは、戦争が「侵攻戦争」であるか「自衛戦争」であるかを誰がいかなる基準に拠って判断するのかであるが、アメリカ国務長官ケロッグが言明したように、実際には各国家が「自己解釈権」を行使して、みずから判断するものとされた。 ・また、「侵攻」(その原義は、挑発されないのに行う攻撃)の国際法的定義は未確定で、国際社会で曲がりなりにも一般的な定義が作成されたのは、戦後の一九七四年十二月のことであった。 ・こういう国際法的状況にもかかわらず、一九四六年~一九四八年に行われた東京裁判が、不戦条約によって「侵攻戦争」は犯罪――平和に対する罪――にされているとの連合国側の独断的な主張を認め、日本の遂行した戦争が(少なくとも日本の自己解釈権の行使においては)「自衛戦争」と認められるにもかかわらず、杜撰な歴史認識のもとに「侵攻戦争」――翻訳係が “侵略戦争” と悪訳した。現在では、外務省の国際法関係の要職にある人も、 “侵略” アグレッションの正確な訳語ではないことを認めている――であると強弁し、東條元首相以下の戦時指導者個人に、いわゆるA級戦犯としての戦争責任なるものを追及したが、このようなことは、かつて前例がなく、また実定国際法の許容するところではなく、東京裁判自体が悪質な国際法侵犯の事例として非難されることになった。 ■若干の重要問題に関するレーリンク博士の見解 ・日本に開戦を決意させ、ハワイを攻撃させることになる一九四一年十一月二十六日のハル・ノートについての氏の見解 「(日米交渉に関連して)日本の見地からして、アメリカ(イギリス・支那・オランダ)側のとった行動のうち最も重要なものは、石油禁輸であり、・・・それは、日本がインドシナおよび支那から撤退することが経済的譲歩の代償とされるというものであった。しかし、日本政府としては、そのような代償をを支払う意思も能力も持てなかった」 「ハルが提示した諸条件は端的に戦争を意味しており、そのことをハルは知っていた」 「アメリカ政府は戦争が始まることを確信していたが、それが日本よって開始されることを熱望していた」 「 “われわれは、あまり多くの危険がもたらされないようにしながら、日本を操って最初の第一撃を発射するようにさせなければならない” と、確かにハルは言った」 ・ハル・ノートの原案を作成したのが財務次官補ハリー・D・ホワイト(ソ連のスパイであったことが後に判明している)であったことが確認されており、ルーズベルト一味の対日挑発計画はソ連の世界赤化戦略に副うものであった。 ・ルーズベルト大統領と数名の閣僚は真珠湾に迫る軍事的危機を知っていながら、真珠湾の防衛責任者たるキンメル海軍大将やショート陸軍中将にその情報を知らせず、二千有余のアメリカ人将兵を犠牲にしたのである。 ・レーリンク博士は、日本政府が実質的に正式な開戦宣言に相当するものを、真珠湾攻撃に先だってワシントンに通告する意図を持っていたことを認めており、真珠湾へのだまし討ちなる罪科は、法的には十分な根拠があるとは決していえない。 ・連合国側の戦争犯罪行為についても、レーリンク博士は厳しい批判をしている。 「日本の諸都市に対する連合軍の爆撃は違法である」 「原子爆弾の投下は、一般住民への攻撃であって、軍事目標に向けられたものではなかったから、違法です」 「今日、国家の政府は自国民――特にデモクラシー諸国では、国民は権力を持つ地位にある――の世話をすることを期待されている。この状況が、国民を攻撃することによって最終的には政府に降伏するよう圧力をかけられるという理論を生み出した。これが脅迫戦争理論であって、それは、一般市民に対する戦争が、敵国軍隊に対する戦争よりも費用が安く効率が高い」と主張する。 「このようにして勝利の達成が可能なことは否定できない。広島と長崎への原子爆弾投下は、この種の戦略に基づいていた」 「十万人を殺すことにより、自分は数百万というアメリカ人および日本人が日本全土での死闘で殺されるのを防いだというのが、トルーマン大統領の主張であった。それは脅迫戦争観念にアピールする議論である。すなわち、幾百万人もの死を阻止するために、通常の常態においては犯罪と考えられる仕方で、十万人を殺さなければならなかった、というものである」 「しかし、日本の降伏の史実から見て、幾百万人ものアメリカ人および日本人の死は、原子爆弾がなくても、日本側の条件である国体の護持を容認するだけで、阻止できたであろう。広島と長崎の破壊は、ドイツ降伏のしばらく前のドレスデン空爆と同様に、不必要だったのだ」 「アメリカが、日本との戦争を終わらせるためでなく、自国の新しい力をソ連に印象づけるために、原子爆弾を使用することを、どの程度望んでいたか。原子爆弾の使用を厳しく批判したのがイギリスのブラケットという人で、彼は早くも一九四六年に、広島と長崎に落された原子爆弾は第二次世界大戦の最後のそれではなく、第三次世界大戦の最初の原子爆弾であると書き、アメリカは非常に腹を立てた」 「私は、これらの爆撃が戦争犯罪であったと、固く信じている。それは、一般国民が政府に対して降伏を強く促すように、戦争を耐えがたいまでに苦痛に満ちたものにする目的で、一般国民を恐怖に陥れていた。それは恐怖戦術・脅迫戦術であって、交戦法規によって禁止されていたことは確かである」 「カッセーゼ教授は、チャーチルが彼の書いた第二次世界大戦史の中で、原子爆弾の使用は、ソ連が日本を占領してそこに自国の影響力を及ぼすのを阻止するために必要であったと強調している」 「あらゆる都市に軍事施設はあるものだ。広島と長崎への攻撃は、両都市内の軍事目標を破壊する意図に動機づけられていたことを証明しようとする努力がアメリカでされていたことは、容易に理解できる」 「こういうのは、アメリカ人の良心の呵責を和らげ、かつ世界の他の諸国を欺こうとする作り話なのだ。私は歴史がこのことを見抜いて肯定すると思う」 ・カッセーゼ教授は、日本政府が広島への原爆投下に対して、それは不必要な苦痛を与える非人道的兵器の使用を禁ずる国際法原則に違反するとの理由で、スイス大使館を通じてアメリカ政府に抗議を行った。 ・レーリンク博士は、国際法や軍事裁判に対するアジア人の視点からする見解に特に考慮を払い、それを尊重する態度が顕著であった。 ・東京裁判においてインド代表判事・パール博士が、日本は問題の戦争において国家として犯罪行為はしておらず、平和に対する罪などというものは実定国際法上存在していないとの見解に立脚して、日本人被告全員の無罪放免を主張したことは、東京裁判の法的正当性に対する疑念を全世界に印象づけ、戦勝連合国の政治的企図に奉仕した同法廷を震撼せしめた。 ・パール判事の個別反対意見の中に展開された理路整然たる東京裁判批判は、占領軍当局の関係者を恐怖に陥れ、彼らは卑怯にも裁判所条例のいう公正の趣旨に反して、パール判事の意見書の法廷における朗読を、許さなかった。被占領期の日本では、その反対意見書の出版も許されなかった。 ・パール判事は、植民地関係について本当に憤慨していた。 ・日本が “アジア人のためのアジア” というスローガンを掲げて、ヨーロッパ系諸国からアジアを解放しようとした今次の戦争は、真実、彼の心に共鳴を呼び起こした。 世界がさばく東京裁判 【第2章】 戦犯裁判はいかに計画されたか ――国際法違反の占領政策 ■国際法違反の “精神的武装解除” 政策 ・“重大戦争犯罪人”という奇異な考え方が一体いつ、誰によって提唱されたのか。 ・この裁判の着想の原点は、第二次世界大戦中の一九四一年(昭和十六)八月、米大統領ルーズベルトと英首相チャーチルによって発表された「大西洋憲章」に求めることができる。 ・この憲章で表明された思想は、次のような “ «[無条件降伏政策は]この戦争の最終目標をドイツ、イタリア、及び日本の無条件降伏に求めることであり、無条件降伏はこれら三国の人民の破砕を意味するものではなく、他国の征服と屈従に基礎をおく、これら三国の哲学そのものを破砕することである。» ・つまり、“無条件降伏”政策は、敵国に賠償金や領土割譲というペナルティーを課すだけでなく、敵国の政治制度の抜本的改革、さらに進んで敵国の「哲学の破砕」すなわち「 ・「無条件降伏」政策には四つの柱があった。 第一は、敗者の発言権をすべて奪い去ること。勝者が何でもできる権利を確保すること。 第二に、敵国の長期無力化、半永久的武装解除を行なうこと。 第三には、今後戦争を起こすことができないようにその国の社会的基盤を完全に破壊すること。そして、敵国を新しい国家として改造する。 第四に、これらの政策を実行するために長期占領して占領下で徹底した改革を行なうこと。 ・これらのことを実現するための国際法上の名目として、相手国の無条件降伏が必要だと連合国は考えたのである。 ・この“無条件降伏”政策の本質を、チャーチル首相は、“無条件降伏”は第一にナチ、ファシスト、日本の「抵抗力が完全に打破され、彼らがわれわれの審判と慈悲に、絶対的に従うことを意味する」と述べたのである。 ・連合国の「審判」に「絶対的」に従うよう国家改造を行なうとは、簡単に言えば、連合国の意のままに動く従属政権を作るということだろう。そのために日本を占領統治したGHQは、日本の伝統精神の基盤である神道を徹底的に弾圧し、一国の基本法たる憲法の改正さえ辞さなかった。これは、「占領地の法律を尊重すること」等を謳ったハーグ陸戦条約の規則を完全に蹂躙している。 ・連合国側が戦犯裁判について正式に言及したのは、カサブランカ会談後の一九四三年(昭和十八年)二月十一日、チャーチル首相が “無条件降伏” に関連して「罪ある人々に対して法の裁きが加えられなければならない」と下院で述べた演説が最初である。 ・その二日後、今度はルーズベルト大統領がやはり “無条件降伏” に関連して「罪ある野蛮な指導者層に刑罰を加える方針である」と演説した。 ・すなわち “戦犯裁判” は、ドイツ、イタリア、日本の現存する政府を否認するとともにこれを抹殺し、その後に従属政権を樹立するという “無条件降伏” 政策の不可分の一環として、だんだんと成長してきたのである。 ■「戦勝国の戦争犯罪も裁かれるべきだ」(ケルゼン博士) ・一九四三年(昭和十八年)十月三十日、連合国はドイツを対象とした「モスクワ宣言」を発表した。同宣言には、国際法に規定された「通例の戦争犯罪」を犯したドイツ軍将兵、ナチス党員をその犯罪がなされた国に引き渡し、その国の裁判によって処罰する旨が明記されていた。 ・しかし、この宣言にはある致命的な欠陥があった。連合国側の戦争犯罪人をどうするかについて全く言及していなかったのである。 ・常設国際司法裁判所(PCIJ)規程作成のため一九二〇年、オランダのハーグに合同した法律家諮問委員会は、「戦争の法規慣例に違反したかどで訴追されるものを裁判するにあたっては、戦勝国も戦敗国も、ともに公平な裁判所においてこれを裁判しうるものでなければならない」という “希望” を表明していた。にもかかわらず、第二次世界大戦において連合国は、敵国の戦争犯罪人だけを裁く意向を表明し、連合国側の交戦法規違反者については全く口を閉ざしてしまったのだ。 ・米カリフォルニア大学のハンス・ケルゼン教授は指摘する。 「被害を受けた国が、敵国国民に対して刑事裁判権を行使することは、犯罪者側の国民からは、正義というよりはむしろ復讐であると考えられ、したがって将来の平和保障の最善策ではない」 「戦争犯罪人の処罰は、国際正義の行為であるべきものであって、復讐にたいする渇望を満たすものであってはならない」 「戦敗国だけが自己の国民を国際裁判所に引き渡して戦争犯罪にたいする処罰をうけさせなければならないというのは、国際正義の観念に合致しないものであ」 ・戦犯裁判が「将来の平和保障のため」であるならば、「戦勝国もまた戦争法規に違反した自国の国民にたいする裁判権を独立公平な国際裁判所に進んで引き渡す用意があって然るべき」であったのである。 ・一九四五年(昭和二十年)二月四日から十一日までソ連領クリミア半島ヤルタにおいて開かれた「ヤルタ会談」(米大統領ルーズベルト、英首相チャーチル、ソ連首相スターリン)で、「すべての戦争犯罪人を正当かつ迅速に処断する不動の方針」が明らかにされたが、この「すべての戦争犯罪人」にももちろん連合国の戦争犯罪人は含まれていなかった。 ■「戦犯裁判は負けることを犯罪とした」(モントゴメリー子爵) ・後から勝手に作った法律で、その法律ができる前の行動を犯罪とされてはたまったものではない。 ・このため、法治主義を採用した近代国家においては、国内法上、遡及的立法の禁止は刑法の基本原則の一つとなっている。 ・連合国は、この事後立方禁止の原則をいとも簡単に踏みにじったのである。 ・また、ロンドン会議では一九四三年(昭和十八年)十月の「モスクワ宣言」以来受け継がれてきた方針――敗者のみを裁き、勝者たる連合国側の戦争犯罪はすべて免責する――を公式に採用した。 ・勝者も敗者も、権力者も一般庶民も何ら区別することなく、等しく適用されるから「法」は「法」たり得るものであって、敗者にしか適用されないのではそれは「法」とは呼べない。 ・イギリスの子爵モントゴメリー元帥は声明で言った。 «ニュルンベルク裁判は、戦争をして負けることを犯罪とした。» ・GHQ参謀第二部部長のC・A・ウィロビー将軍も言っている。 «この裁判は歴史上最悪の偽善だった。こんな裁判が行われたので、自分の息子には軍人になることを禁じるつもりだ。[なぜ東京裁判に不信感を持ったかといえば]日本が置かれていた状況と同じ状況に置かれたならば、アメリカも日本と同様戦争に訴えたに違いないと思うからである» ■「国際法という文明は圧殺された」(パール判事) ・連合国はロンドン会議において、ドイツの指導者を裁くための新しい犯罪概念「平和に対する罪」と「人道に対する罪」を導入したニュルンベルク条例を定め、一九四五年(昭和二十年)十月二十日、ドイツでニュルンベルク裁判を開廷した。 ・開廷された国際軍事裁判は、「世界平和のため」と言いながら、あくまで「審判と慈悲に、絶対的に従う」政権を相手国に樹立するという連合国の “無条件降伏政策” の遂行という政治目的が色濃く反映されたものであり、おおよそ次のような特徴をもっていた。 ①裁判の基本目的は、戦勝国(連合国)の「正義」と戦敗国(枢軸国)の「邪悪」とを明確にし、第二次大戦を連合国の「聖戦」として示すことにある。 ②このため、裁判を敗戦国の言い分を宣伝する場としてはならない。 ③裁判では、戦勝国の戦争責任は追及されてはならない。 ④裁判の理論的根拠は国際法、刑法の批判に耐えうるものでなければならないが、「連合国の正義に基づいた国際秩序」確立のためにも戦勝国は立法する権限をもつ。 ⑤相手国が無条件降伏をした以上、戦勝国はオール・マイティの権限を有する(何でもできる)。戦勝国は、無条件降伏をした戦敗国を国際法上の一種の禁治産者とみなし、国際法を適用しない。 ・東京裁判はニュルンベルク裁判の「太平洋版」とも呼ばれ、以上の基本骨格は東京裁判にもそのまま当てはまる。 ・インド代表のラダビノッド・パール判事は総括した。 «勝者によって今日与えられた犯罪の定義に従っていわゆる裁判を行うことは敗戦者を即時殺戮した昔とわれわれの時代との間に横たわるところの数世紀にわたる文明を抹殺するものである。・・・本件において見るような裁判所の成立は、法律的事項というよりも、むしろ政治的事項、すなわち本質的には政治的な目的にたいして司法的外貌を ■連合国の許しがたい背信行為 ・ポツダム宣言を日本政府が受諾した直後から、連合国側、特にアメリカ政府の様子がおかしくなってくる。 ・九月二日、米戦艦ミズーリの艦上で、政治的宣言であるポツダム宣言を条約化することによって法的拘束力のあるものとする「 ・日本政府は「ポツダム宣言」を受諾し、「日本国軍隊の無条件降伏」を一条件に休戦することに合意したのだから、調印したのは国際法上厳密に言えば「休戦協定」である。それを連合国側は意図的に「降伏文書」と名付けたのである。 ・「降伏文書」にサインし、日本側が武装解除を始めた途端、アメリカは対日姿勢を急変させた。 ・「日本政府は無条件降伏をしたのだから、占領政策を遂行する上で、日本政府の権利に配慮する必要など全くない」と言い放ったのである。正式な国際条約を踏みにじる許しがたい背信行為といえよう。 ■「ポツダム宣言」違反の検閲 ・GHQは九月十九日、検閲指針を示した「日本に対するプレス・コード」を発令した。 ・以後、占領終了まで約七年間、「ポツダム宣言」に「言論の自由の尊重」が謳われていたにもかかわらず、GHQは以下のような指針に基づき、連合国批判、東京裁判批判につながる意見の一切を原則的に検閲で封じ込めてしまったのである。 1.SCAP(連合国最高司令官または占領軍総司令部)批判 2.極東軍事裁判[東京裁判]批判 3.SCAPが日本国憲法を起草したことに対する批判 4.検閲制度への言及 5.合衆国に対する批判 6.ロシアに対する批判 7.英国に対する批判 8.朝鮮人に対する批判 9.中国に対する批判 10.他の連合国に対する批判 ・全部で三十項目からなる検閲指針は、「検閲制度への言及」を厳禁した上で実施されるという、極めて周到かつ隠微な形をとって行なわれた。 ・日本は、アメリカの植民地フィリピンを開放し、アメリカの年来の国家目的である太平洋一元支配を阻んだという意味で「脅威」であった。 ・アメリカは、「アジアによるアジア」という理想を抱いて「アメリカによるアジア支配」を覆そうという意図や能力を持たないようにすること、そのために「米国の目的を支持する」従属政権を日本に確立すること、それがアメリカの対日戦後処理の究極の目的とされたのである。 ・アメリカ政府は「ポツダム宣言」に伴い「無条件降伏」政策が変更を余儀なくされていることを承知しながら、日本政府が休戦に応じた途端、「日本は無条件降伏をした」と悪質なデマを流し、なおかつ検閲によって日本側の「発言権」を奪って反論できないように追い込んだ上で、「ポツダム宣言」を大きく逸脱して実質的な「無条件降伏」政策を日本に強要したのである。 ・連合国、特にGHQの政策を主導したアメリカという国が、自国の政治目的を達成するためには、国際条約(「ポツダム宣言」の内容を条約として法的拘束力のあるものとした休戦協定・連合国側が「降伏文書」と名付けたもの)さえいとも簡単に反故にした歴史的事実を、私たちは後々まで忘れてはならないであろう。 ■裁判の偽善性に悩んだソープ准将 ・GHQ対敵情報部長エリオット・ソープ准将は言う。 «戦争を国策の手段とした罪などは、戦後につくりだされたものであり、リンチ裁判用の事後法としか思えなかった。» ・GHQは、十月二日、さらなる “精神的武装解除” の方策を打ち出した。 ・「ウォー・ギルト・インフォーメーション・プログラム(戦争犯罪周知宣伝計画)」を開始したのである。 ・日本側の戦時指導者が逮捕され、日本が犯罪国家として裁かれることについて、日本人に納得させるように徹底した宣伝を行ない、日本人をマインド・コントロールしようとしたのである。 ・「ウォー・ギルト・インフォーメーション・プログラム」は、東京裁判が「倫理的に正当」であることを示すとともに、「侵略戦争」を行った「日本国民の責任」を明確にし、日本国民に戦争贖罪意識を植えつけることを「目的」としていた。 ・GHQは開戦記念日の十二月八日、日本軍の残虐行為を強調した「太平洋戦争史」の新聞各紙への掲載を始めさせ、翌九日にはラジオ番組「真相はかうだ」の放送も開始(十週連続)させるなど、あらゆる日本のメディアを動員して、「広島、長崎の原爆投下も、無差別爆撃も、すべて日本が戦争犯罪を犯した罪であって、悪いのは日本の方だ」と宣伝し、日本人自らがそう思うように巧妙な心理操作を加えていったのである。 ■「極東軍事裁判所条例は国際法に基づいていない」(モーン卿) ・「平和に対する罪」などが当時の国際法に基づいたものではなく、また、戦勝国がそうした新たな罪を事後的に設けて敗戦国を裁くという権限が当時の国際法で認められていない以上、連合国に事後立法に基づいて国際軍事裁判を行う権限はなかったはずなのである。 ・いずれにせよ、マッカーサー司令官が定めた「極東軍事裁判所条例」に対して、それが当時の国際法に照らして適法か違法かを審議し、もし違法ならば、そのような条例に基づく国際軍事裁判は「ポツダム宣言」違反だと断固拒否する権限を、ほかならぬ日本政府は有していたはずであった。 ・しかし、マッカーサーの日本「国」無条件降伏説にたぶらかされていた日本政府や、検閲によって一切の言論活動の自由を奪われていた日本国民は抗議するすべもなかった。 ・昭和二十一年五月三日、東京・市ヶ谷台に極東国際軍事裁判所が一方的に開廷された。 ・アメリカ人の首席検事ジョゼフ・キーナンは起訴状を朗読した。 「彼らは、文明への宣戦布告をしたのであって、検察側の役目は、将来また戦争が日本によって起こされぬよう阻止することであって復讐や報復という低劣な目的ではない」 ・この裁判が(「ポツダム宣言」を国際法化した国際条約[降伏文書と名付けられたもの]と国際法一般を蹂躙指定にもかわらず)「文明の裁き」だと称したのである。 ・欧米諸国は「文明」をどのような意味で使ってきたか。 ・十九世紀末から二十世紀初頭にかけて、欧米諸国はアジア・アフリカを植民地化していくにあたって、自らを普遍的「文明」の担い手と称し、異文化を「野蛮」とみなし、それらの「文明化」を自らの神聖なる使命と呼んできた。 ・キーナン検事がいう「文明」とは、欧米植民地支配を正当化するイデオロギーにほかならなかった。 ・言うなれば、欧米の植民地支配を正当化した「文明」に逆らったことが、日本の「罪」だったのである。 ・なるほどそれは欧米から見れば「罪」だったかも知れないが、アジアから見てそれは果たして「罪」だったのだろうか。 【第3章】 追及されなかった「連合国の戦争責任」 ――裁判の名に値しない不公正な法手続き ■ハンキー元英国内閣官房長官の憂慮 ・法手続上、極東国際軍事裁判所は公正な裁判所ではなかった。 ・つまり連合国側の戦争責任を不問に付して日本人のみの罪を問うたことは、最も大きな問題であった。 ・戦犯裁判が「将来の平和保障の最善策」たるためには「戦勝国もまた戦争法規に違反した自国の国民にたいする裁判権を独立公平な国際裁判所に進んで引き渡す用意があってしかるべきである」と述べた世界的な国際法の権威、ケルゼン教授の主張に、連合国側は耳を傾けるべきであった。 ・しかし、ニュルンベルク・東京の両裁判で裁かれたのは常に敗者であった。 連合国にとって裁判の目的が、戦勝国の「正義」と敗戦国の「邪悪」とを明確に区別し、第二次大戦を連合国の「聖戦」として示すことであった以上、それは当然の帰結であった。 ・もっとも連合国側にも、自分たちの戦争責任を不問に付したまま敵国だけを裁く――その欺瞞性に煩悶した公正な識者たちが少なからずいた。彼らは「なぜ被告席に座るのが敗戦国のドイツ人や日本人だけなのか。裁く自分たちの手は汚れていないのか」という問いを発することで、戦争裁判が掲げた「正義」、つまり連合国の、勝者の「正義」に強い疑問を投げかけたのである。 ・例えば、内閣官房長官、枢密院書記官長などの要職を歴任し、第二次大戦中は無任所の閣僚であったイギリス政界の重鎮ハンキー卿は当初から戦争裁判に反対し、一九四九年(昭和二十四年)著書『戦争裁判の錯誤』の中で表明した。 「不戦条約その他の国際条約を侵犯し、隣国に対し侵略戦争を計画し、準備し、遂行し、占領地域の一般住民を虐待し、奴隷労働その他の目的のためにその土地から追放し、個人の財産を略奪し、軍事上の必要によって正当化されない都市村落の無謀な破壊を行うような罪を犯したことが一見明かな同盟国の政府(例えばソ連)および個人にたいしても同じような裁判を行うつもりか。 このような裁判をやらないとすれば(もちろん、やるはずはない)、ニュルンベルクの政策は、敗者に適用する法律は勝者に対するそれとは別物だということを示唆していないか。哀れなるは敗者である!」 ・イギリスのフランシス・S・G・ビゴット少将は『戦犯裁判の錯誤』序文で述べた。 「[ハンキー卿]は上院において、また新聞紙上、その他において、戦犯裁判制度そのものに対し断乎たる攻撃を行うなかで、憎悪と復讐の念を払拭すべきだという点を絶えず強調してきた。元陸軍参謀総長、元帥ミルン卿が亡くなる前に私と最後に会った時の話は、彼がいかに勝者による敗者の裁判に反対していたかを示した。」 ■日本空爆計画を暴いたトンプソン教授 ・真珠湾攻撃を時のルーズベルト大統領が「卑劣な騙し討ち」と非難して以来、「先に仕掛けたのはジャップの奴らだ。ジャップは皆殺しにされても当然だ」という論理で、米軍は投降した日本軍兵士を殺害し、都市部を無差別爆撃し、最後には原爆投下にまで踏み切った。 ・確かに大々的な「先制攻撃」を仕掛けたのは日本であった。しかし、それは「挑発を受けない」先制攻撃であったのだろうか。 ・ルーズベルト大統領が対独参戦のためにしきりにドイツに挑発行動を仕掛けていたが、それは日本に対してはもっと露骨であった。 ・アメリカは一九三七年(昭和十二年)に支那事変が始まると、中国国民党の蒋介石政権に借款を与え、武器を売却するなどして、日本に対する非友好的行動を続けた。 ・更に一九四〇年(昭和十五年)初めには一個の義勇航空隊(フライング・タイガース)を対日抗戦中の重慶政権に派遣し日本軍と交戦させた。 ・これらの行為が局外国としては国際法違反であることは明らかであり、アメリカは一九四〇年(昭和十五年)初頭には既に実質的に対日開戦をしていたといわれても仕方がないだろう。 ・アメリカ南カロライナ大学のロバート・トンプソン教授曰く、 「旧日本軍による真珠湾攻撃の一年前から、米国が当時の蒋介石政権に多数の爆撃機を供与し、工業地帯を中心に日本空爆をひそかに計画していた」 として、アメリカは外交・軍事両面であらゆる手段を使って日本を戦争に引きずりこむ方針だったと断定している。 ■ローガン弁護人の「アメリカの戦争責任」論 ・アメリカ人のウィリアム・ローガン弁護人は一九四七年(昭和二十二年)、冒頭陳述の「太平洋段階第二部・日本に対する連合国の圧迫」の中で、 「対米戦争だけは何とかして避けたいと日本政府側が懸命な交渉を続けていた一九四一年(昭和十六年)七月の段階で、アメリカ軍部首脳とルーズベルト大統領は、さらなる対日経済制裁が日本の南進を促すことになることを承知していたにもかかわらず、それでも制裁に踏み切った」 というのである。 ・更に、ローガン弁護人は一九四八年(昭和二十三年)三月十日、最終弁論・自衛戦論において、パリ不戦条約の草案者の一人である国務長官ケロッグが当時の一九二八年、経済制裁、経済封鎖を戦争行為として認識していた事実を紹介し、今次戦争を挑発したのは日本に非ずして連合国であることを詳しく論証した。その内容は「アメリカの戦争責任」を徹底的に追求したものとなっている。 ・アメリカ政府から対日戦争行為に匹敵する経済封鎖を受けておきながら、それでも忍耐強く平和的解決を図ろうとした日本政府の態度は「永遠に日本の名誉」だと、ローガン弁護人は堂々と法廷で訴えたのである。 ・アメリカ人でありながらローガン弁護人は 「日本には二十年間一貫した世界侵略の共同謀議なんて断じてなかったことに確信を持つにいたった。したがって起訴事実は、当然全部無罪である。」 ・ローガン弁護人が案じた通り、パール判事らを除いて検事も裁判官も、最後までローガン弁護人の段階には達しなかった。そればかりか ■ルーズベルトの開戦責任を問うリットルトン英国軍需生産相 ・英国の軍需生産大臣オリバー・リットルトンは、一九四四年、言った。 «日本がアメリカを戦争に追い込んだというのは歴史の狂言である。真実はその逆である。アメリカが日本を真珠湾に誘い込んだと見るのが正しいのだ» ・合衆国前大統領ハーバート・フーバーも当時、発言している。 «若し吾々が日本人を挑発しなかったならば決して日本人から攻撃を受ける様なことはことはなかったであらう» ・アメリカの黒人ジャーナリスト、J.A.ロジャースは、イギリスやフランス、オランダによる植民地支配や、アメリカのハワイ、フィリピン支配を批判して、当時、アメリカの新聞に書いた。 «そもそもヨーロッパやアメリカがこれらの地域を植民地支配しなければ、日本との戦争は起こり得なかった。真珠湾はなかったはずだ。» ・欧米諸国がアジア地域を植民地にし、自由貿易に反して排日的なABCD経済包囲網を形成したから、日本は戦争をせざるを得なかったのであり、アジア諸国が独立国家であるならば日本は自由貿易を行い、戦争に訴える必要もなかったのだというのである。 ・イギリスのラッセル・グレンフェル海軍大佐は一九五二年(昭和二十七年)に指摘した。 «ルーズベルト大統領が戦争を欲していたことは疑う余地はないが、政治的理由から、最初の攻撃が相手方から加えられることを望んでいた。そのため自尊心を持つ国なら、いかなる国でも武力に訴えるほかない地点にまで日本に圧力を加えたのである。日本はアメリカ大統領によってアメリカを攻撃することにされていた» ・アメリカの歴史家ハリー・エルマー・バーンズは、指摘している。 «一九四一年六月の、日本の経済的扼殺で始まった戦術の切り換えを除いては、戦争への道はまったく直線的であった。全局面を通ずる戦争工作の建築家であり大指揮者だったのはフランクリン・デラノ・ルーズベルトだ。» ・アメリカ人のカーチス・B・ドール大佐はルーズベルト大統領の長女の夫でありながら、一九六八年(昭和四十三年)暴露した。 «ルーズベルト大統領および彼の側近たちの戦略は、平和を維持し保障することではなく、事件を組み立て、あるいは引き起こさせて、アメリカを日本との戦争にまき込むという陰謀にもっぱら関わっていた。これは「裏口」からヨーロッパの戦争に入ることを可能にする計略でした。» ・中華民国政府の行政院僑務委員会顧問で、国際汎太平洋私学教育連合会の副会長を務めている許國雄・東方工商専科大学学長は一九九五年(平成七年)に、日本だけが批判される風潮に異議を唱えた。 «国際戦争は個人の喧嘩と同じく、誰が先に手を出したのかを問うのではなく、誰が喧嘩を売りつけたかを問わなければならない。このような意味で、米国を主とするA、B、C、D(米、英、支、蘭)諸国は、日本を生き埋めにしようとハル・ノートで喧嘩を売りつけたのである。 戦後、米駐日大使グルーは「戦争のボタンが押されたのは、日本がハル・ノートを受け取った時点だというのが私の確信である」と証言し、英駐日大使クレーギーも同様の証言をしている。日本は喉元に刺された ・一九四一年十二月、真珠湾攻撃の翌日、アメリカ政府は全国民に向け声明を発表した。日本軍の攻撃は「この十年間における国際的背徳の最高のものである」。この日までにアメリカは「日本と平和の状態」にあり、「日本側の懇請によって、太平洋の平和維持をめざして日本政府と会談中であった」。そしてルーズベルト大統領は「平和に向かって考えられるあらゆる限りの努力を尽くした」。しかるに日本政府は、その間に慎重に計画しつつ「巧妙にも合衆国を欺こうとしていた」。そして日本の海軍が交渉中にハワイの攻撃を開始した。このような「日本側の言葉と行動が明白に歴史的記録として残され」ている以上、「正直な人ならだれでも、日本の軍事独裁者どもが犯した裏切り行為に対し憤激と憎悪の念を今日、いや今後幾千年もの間、禁じ得ないであろう」と。 ・しかし、真実を踏まえるならば、日本は次のように声明を出すべきだろう。 ・真珠湾攻撃の数年前から事実上「アメリカと日本は戦争状態にあったが、「日本側の懇請によって、太平洋の平和維持をめざしてアメリカ政府と会談中であった」。そして日本政府は「平和に向かって考えられるあらゆる限りの努力を尽くした」。しかるにアメリカ政府は、エドワード・ミラー著『オレンジ計画』によれば、日露戦争直後の一九〇四年(明治三十七年)から対日戦争計画を研究・立案し、その間に慎重にその計画を実行に移しつつ「巧妙にも日本を欺こうとしていた」。そして一九四〇年から正規兵を義勇兵と偽って対日戦闘に参加させ、更に戦争行為と見なされても仕方がないほどの経済制裁、軍事的圧力を加えた。このような「アメリカ側の言葉と行動とが明白に歴史的記録として残され」ている以上、「正直な人ならだれでも、アメリカの軍事独裁者どもが犯した裏切りに対し憤激と憎悪の念を今日、いや今後数千年もの間、禁じ得ないであろう」と。 ・米国下院での共和党D・ショート議員の演説 «真珠湾攻撃に関するすべてのいきさつと真実が語られ、白日の下に ■ブレイクニー弁護人の「原爆」発言 ・マサチューセッツ州立大学のリチャード・マイニア教授は一九七一年に刊行した著書『勝者の裁き』の中で、 «アメリカも「人道に対する罪」を犯した疑いがきわめて強かった。極東国際軍事裁判所条例は「人道に対する罪」を、「一般市民に対する非人道的行為」と定義した。この定義は、広島や長崎に対する原爆投下にも適用されないのであろうか。» と疑問を投げかけている。 ・アメリカのベンブルース・ブレイクニー弁護人は、一九四六年(昭和二十一年)五月十四日の法廷で、、広島・長崎への原爆投下という空前の「一般市民に対する非人道的行為」を犯した国(アメリカ)の人たちが日本人を裁く資格があるのか、と追及したのである。 «戦争での殺人は罪にならない。それは殺人罪ではない。戦争は合法的だからです。つまり合法的な人殺しなのです。殺人行為の正当化です。たとひ嫌悪すべき行為でも、犯罪としての責任は問はれなかったのです。» «キッド提督の死が真珠湾爆撃による殺人罪になるならば、我々は広島に原爆を投下した者の名を挙げる事ができる。投下を計画した参謀長の名も承知してゐる。その国の厳守の名前も我々は承知してゐる。彼等は殺人罪を意識してゐたか。してはゐまい。我々もさう思ふ。それは彼等の戦闘行為が正義で、敵の行為が不正義だからではなく、戦争自体が犯罪ではないからである。» «何の罪科で、いかなる証拠で、戦争による殺人が違反なのか。原爆を投下した者がゐる! この投下を計画し、その実行を命じこれを黙認した者がゐる! その者達が裁いているのだ!» ・この ■「原爆投下を我々は悔む」(『ナッシュビル・グローブ』紙) ・戦後、アメリカ政府指導者たちは、戦争を短期に終わらせるために原爆投下が必要だったと釈明に努めた。そして更に、百万人のアメリカ人将兵の命を救うためには、二十万以上の日本人が殺されてもやむを得なかったのだと、原爆投下を正当化した。 ・その「釈明」を真正面から批判したマスコミが、当時のアメリカには存在した。ハンプトン大学助教授等を経て現在、神田外語大学で教えるレジナルド・カーニー助教授は次のように紹介している。 «[『ナッシュビル・グローブ』紙はいう。]「日本との戦争で、かつてない非人道的な武器である原子爆弾を使用したことを、われわれは少なからず恥じ、また悔やんでもいる。こんな形で勝利を迎えても、けっして素直に喜ぶことはできないのだ」。そして、こう問うている。「何万人と言う人びとの命を奪った原爆。われわれアメリカ人の心には、本当に一点の曇りもないのか」、「キリストの教えを踏みにじった」というのに・・・・・・。» ・『ユナイテッド・ステイツ・ニューズ』編集長のデービッド・ローレンスも一九四五年(昭和二十年)十月五日、同誌で問いかけた。 «もし原爆を使う権利が容認されるなら、いわゆる安楽死を行なう兵器――ブーヘンバルトのガス室なみに手っとり早く即効性のあるもの――を開発する権利も容認されるはずだ。・・・・・・合衆国は何においても原爆を非難し、それを使用したことについて日本に謝罪すべきだ。陸軍航空軍のスポークスマンは、原爆投下はいずれにせよ必然性はなく戦争はすでに勝利していたと言っている。原爆が落ちる何週間も前に日本が降伏しようとしていたとする確たる証言がいくつもあがっている。» ・実は、戦時中のアメリカの軍人たちは「原爆投下は不必要」と考えていた。 ・原爆実験に初めて成功し、原爆投下の是非を検討した一九四五年(昭和二十年)七月十六日の統合参謀本部の会議において、キング海軍作戦部長は「海上封鎖だけで日本は飢えて降参し、戦争にトドメをさせる」と主張、アイゼンハワー連合軍欧州最高司令官は「原爆投下は全く不必要だ。もはやアメリカ兵の生命を救う手段としては必須ではなくなった。この恐怖の兵器を使えば、世界に反米世論を巻き起こすだけだ」と注意を促していた。 ・明治学院大学の加藤典洋教授は指摘している。 «戦争終結時にはどうしても戦争勝利者としての「フリーハンド」を持っていることを至上目的とし、しかも一方的に敵を裁き敵からは裁かれない地歩の獲得を眼目のうちに含んだ政策が、実は、原子爆弾使用を彼らに可能にさせるための不可欠の条件として、彼ら連合国の指導者に必要とされていたのではなかったか» ・もし、国際法を楯に日本から裁かれるような事態となればどうなったか。連合国の首脳は原爆使用をもって国際法違反として裁かれることを覚悟しなければならなかった。 ・ルーズベルトやチャーチルが無条件降伏という「フリーハンド」政策を敗戦国に適用しようとした理由は、このような告発からどのようにして身を守るか――その方途を考え抜いた結果でもあった。 ・その方途とは、まさしく「敵を裁き敵からは裁かれない地歩」に立って、①連合国側の戦争責任を追及しようという発想そのものを封じ込め、②戦犯裁判などを通じて日本人に罪の意識を植え付け、「日本の指導層が侵略戦争を行なったのだから、原爆を投下されても仕方がない」と思い込ませ、③最終的に連合国の「審判と慈悲に、絶対的に従う」ように日本人の精神を改造すること――であった。 この狙いは見事に成功した。 ・原爆投下後、「自らの名と全人類と文明の名」においてアメリカ政府を糾弾した日本は戦後、その抗議とは全く正反対の趣旨の、「安らかに眠って下さい/過ちは/繰り返しませぬから」という文面を刻んだ原爆慰霊碑を広島に建立するに至ったのである。 ■「原爆投下を反省すべきはアメリカだ」(ガザリー元外相) ・一九五二年(昭和二十七年)十一月、広島を訪れた国連国際法委員会委員で、元東京裁判判事のラダビノッド・パール博士はこの文面を眼にして、「ここにまつってあるのは原爆犠牲者の霊であり、原爆を落としたのは日本人でないことは明白である。落としたものの手はまだ清められていない。原爆投下者にこそ罪悪を知らすべきだ」と批判し、その直後の世界連邦アジア会議で次のように述べた。 «彼らは口実として、もし広島に原爆を投下せねば多数の連合軍の兵隊が死ぬことを強調した。原爆投下は日本の男女の別、戦闘員、非戦闘員の区別なく無差別に殺すことである。いったい、白人の兵隊の生命を助けるために幾十万の非戦闘員が虐殺されることはどういうことなのか。彼らがもっともらしい口実をつくるのは、このような説明で満足する人々があるからであ。» ・このパール発言に対して、同年十一月十日、原爆慰霊碑文を作った雑賀忠義広島大学教授は、次のような抗議文(?)を出した。 «広島市民であるとともに世界市民であるわれわれが過ちを繰り返さないと霊前に誓う――これは全人類の過去、現在、未来に通じる広島市民の感情であり、良心の叫びである。 "広島市民が過ちを繰り返さぬといっても外国人から落とされた爆弾ではないか。だから繰り返さぬではなく、繰り返させぬであり、広島市民の過ちではない" とは世界市民に通じないことばだ。そんなせせこましい立場に立つ時は過ちは繰り返さぬことは不可能になり霊前でものをいう資格はない» ・この碑文作成者は、日本人としての立場から連合国の戦争責任を追及するよりも、連合国=国連=国際社会=世界市民という「立場」に立つことで、結果的に「過ちを犯した日本が悪かったから原爆も投下されたのだ」という連合国=東京裁判の「論理」を受け入れることを選択したわけである。 ・しかし、パール判事のような「アジア」の立場から見れば、連合国=国連=国際社会=世界市民という「立場」はあくまでアジア・アフリカへの侵略を正当化してきた欧米諸国の「立場」に過ぎない。 ・日本が過ちを犯したから原爆を投下されたのだ」という「アメリカの口実」を繰り返し、自らを責めるだけの「反戦平和運動」こそ、アジアにとっては「せせこましい」ものと映ったに違いない。 ・マレーシアのタンスリー・ガザリー・シャフェー元外務大臣も一九九三年(平成五年)十一月に来日した際、この原爆慰霊碑について次のように語っている。 «以前、広島を訪れた時、小学校の先生が原爆慰霊碑の前で子供たちに「日本は昔悪いことをした。これはその記念碑だ」と教えていたのを見ました。それで広島市長に「原爆慰霊碑と原爆資料館は日本人が見るべきではありません。ワシントンに持っていき、アメリカ人に見せて、アメリカ人に反省させるべきではないでしょうか。原爆資料館がここにあるのは不適切だと思います」と言ったところ、広島市長は真っ青になってしまったが、やがて彼らも私の意見に賛同してくれました。 それにしても日本人はなぜアメリカに対して異様なほどおびえているのか。敗戦国心理から早く脱却するべきではないだろうか。» ・まず何よりも原爆を投下したアメリカの責任を追及すべきであった戦後の我が国の平和運動は、日本人としての立場も、パール博士やガザリー元外相のような「アジアの視点」も見失ったまま、連合国側が東京裁判で掲げた「正義」に擦り寄ってしまった。 ・そして、いまなお我が国の反戦平和運動家やマスコミ、社民党(旧社会党)らは自国の戦争責任ばかりを執拗に追求することで、東京裁判の背景にある「再び日本を米国の脅威たらしめないこと」という占領政策の究極目的の達成を補完し続けているのである。 ■原爆投下を懺悔したキリスト教会連邦協議会 ・一九四五年(昭和二十年)八月、『クリスチャン・センチュリー』紙の論説 «原爆を使用したことにより、我が国は道義上弁護の余地のない立場に立たされた、と我々は考えている。» ・後に国務長官を務めたジョン・フォスター・ダレスは、八月十日付『ニューヨーク・タイムズ』紙に声明を発表した。 «いま私たちに開かれた選択肢の一つは、人類の想像を超えるような大量殺戮を直ちに停止することである。このような大量殺戮は、老若男女を問わず、罪ある者も罪なき者も無差別に、確実に抹殺してしまう。彼らが、私たちを攻撃し、私たちに深い怒りを植えつけた国の一員であるというだけの理由で。いやしくもキリスト教徒である私たちが平気で、このような形での原子力の使用を認めてしまえば、いつ他の人たちが同じような結論を下しても抗議できない。» ・『カトリック・ワールド』の編集長ジェームズ・M・ギリス神父が明言した。 «我々アメリカ合衆国民は・・・・・・キリスト教社会として、その道徳律に対して、いまだかつてなかったほどの激しい打撃をうけた。・・・・・・合衆国政府がとった行動は文明社会の根幹を成している情のすべて、罪の自覚のすべてをことごとく無視するものだ。» ・一九四六年(昭和二十一年)、カルホーン委員会が報告書を公表した。 «広島と長崎への突然の原爆投下は倫理的に弁護の余地はない・・・・・・長崎への投下は、原爆の威力が示された後だったにもかかわらず、日本政府と最高司令部が降伏の結論に達するだけの十分な時間を与えられないまま、警告もなく実施された。さらに、どちらの原爆投下も戦争に勝つためには不要であったと判断せざるをえない・・・・・・こういった状況下で史上初の原爆投下を行った国家として、我々は神の法においても、そして日本国民にたいしても、取り返しのつかない罪を犯した。» ・戦後、多くの日本人留学生をアメリカに招き、支援したフルブライト上院議員は、フルブライト留学生制度は原爆投下に対する懺悔のしるしとして行ったと語っている。 ・一九四六年六月九日には、第三艦隊司令官のウィリアム・ハルゼー大将が、原爆が使用されたのは、指導者層が科学者たちの持っている「おもちゃを実際に試したかったから」だと発言し、次のように続けたのである。 «史上初の原爆投下は全く必要のない実験だった・・・・・・そもそもあれを落とすこと自体が間違いだった。» ・この直後、『サタデー・レビュー』の編集長ノーマン・カズンズは、原爆投下という犯罪を真っ向から非難した。 «海軍のスポークスマンによると、日本は広島に原爆が投下される前に降伏の用意があったという。となると、何千何万という数えきれないほどのアメリカ人の命が救われたという主張は、どうなってしまうのだろう。» ・これらの一連の発言は、原爆製造に関与し、また投下の決定に関係した政府関係者たちの神経を大いに逆なでした。原爆投下を正当化するための逆襲が始まった。 ■「原爆投下は不必要だった」(アイゼンハワー司令官) ・ウィリアム・リーヒ海軍大将が、一九五〇年(昭和二十五年)公言たした。 «私の意見では、広島と長崎に対してこの残忍な兵器を使用したことは対日戦争で何の重要な助けにもならなかった。日本はすでに打ちのめされており、降伏寸前だった。・・・・・・ あれを最初に使うことによって、われわれは暗黒時代の野蛮人並みの倫理基準を選んだことになると感じた。あのように戦争を遂行するようには教えられなかったし、女、子供を殺すようでは戦争に勝利したとは言えない。» ・アメリカ大統領をつとめたD・アイゼンハワーが一九六三年(昭和三十八年)述べた。 «日本の敗色は濃厚で、原爆の使用はまったく不必要だという信念をもっていた。第二に、アメリカ人の命を救うために、もはや不可欠ではなくなっていた兵器を使用することによって世界の世論に波紋を広げることは避けるべきだと考えていた。» 一九九〇年(平成二年)、保守系のアメリカ原子力規制委員会で主席歴史記述者を務めるJ・サミュエル・ウォーカーは、権威ある学術雑誌『外交史』にその最新の成果を発表した。 «原爆に代わる選択肢があったことは明白であり、そのことをトルーマンとその側近が知っていたことに議論の余地はない。・・・・・・原爆は五〇万人のアメリカ戦闘部隊の命を救ったというカビの生えそうな主張にまったく根拠のないことは、疑いの余地はない。» ・メリーランド大学研究員で、全米経済代替案センター代表ガー・アルペロビッツも、次のように結論を下している。 «いかなる事情があったにせよ、警告もせずに原子爆弾を都市部に投下するという行為は正当化できるのだろうか。専門家の間では原爆投下がほぼ確実に不必要であったという見解が、おおむねまとまっていること、また、いずれにせよ[昭和二十年]十一月までに日本は降伏していた確率が高いということを、知って驚く人は多い。» ・一九九三年(平成五年)、ワシントンのスミソニアン博物館は、原爆が戦争終結を早め、多くの命を救ったとする「神話」を考え直そうとの意図をこめて、「原爆展」を計画した。 ・この「神話」を考え直そうとするスミソニアン博物館の提案は、原爆投下を正当化する元軍人たちや政治家たちによってたたき潰され、ついにこの「原爆展」は中止に追い込まれてしまった。 ・その一因は、実は日本側の姿勢にある。 ・スミソニアン博物館の「原爆展」反対運動を主導した同博物館のガイド、フランク・ラビットは次のように語った。 «大統領は原爆の投下で失われる命より、上陸作戦で失われる命の方が多いと説明していた。・・・・・・あれが戦争犯罪だというのか? 記憶にある限り、日本政府はアメリカが戦争犯罪を犯したと非難したことなど一度もなかったではないか» ・投下された側の日本が原爆投下の非をアメリカに訴えたことがなかったからである。「自分たちが侵略戦争を始めなければ、原爆投下もなかったはずだ」として、アメリカの非を追及するよりも自らの責任を問うことばかりに熱中していたからである。 ■「無差別爆撃」を非難した中立国スイスの新聞 ・戦争は国際法上合法なので、ひとたび戦争状態に入るや、平時には認められない交戦権の発動も認められているが、その攻撃対象はあくまで戦闘員と軍事施設とに限られていた。ところが、連合国側は民間人への攻撃をも総力戦という概念で正当化した。 ・今次の戦争は諸国の総力戦で、例えば靴下屋米の生産であっても、兵士がその靴下をはき、その米を食糧とするのであれば、民間人が軍事力に寄与しているといえるのだから、攻撃にあたって軍隊と民間人、軍事施設と民間物を区別する必要がないという言い方をしたのである。 ・イギリスの戦史家リデル・ハートによれば、この総力戦という考え方につついていえば、これはドイツよりも連合国の方が遥かに徹底した考え方を持っていたという。 ・しかもこの無差別爆撃は国策として遂行された。チャーチル英首相は、日本人を粉砕し、その町を破壊し、あるいは市街地を焼き払うという構想に、何度も積極的な賛意を表している。 ・アメリカ・カリフォルニア大学のジョン・W・ダワー教授によれば、日本の都市を火の海に化すという考え方は、真珠湾攻撃の少し前(!)から米軍内部では台頭していたという。 ・当時、マーシャル陸軍参謀総長は、「日本の人口密集都市の木と紙でできた家屋を焼き払う、無差別焼夷弾攻撃」を想定した計画を立てるように部下に命じている。 ・マッカーサーの右腕の一人、ボナ・フェラーズ准将は、米軍の日本に対する空襲を「史上最も冷酷、野蛮な非戦闘員殺戮の一つ」と、極秘覚書に記している。 ・この米軍による日本都市無差別爆撃は中立国たるスイスに異常な反響を巻き起こした。スイスの新聞『ガゼット・ローザンヌ』紙は八月六日の社説で、次のように主張した。 «米国の日本都市無差別爆撃はドイツのブーチェンワルド・マヌーゼン収容所の残虐にも比較するべきものであり、スイスは米国のこの暴挙の停止を勧告すべきだ» «木造建築の多い日本の都市で特に多数の婦女子が爆撃によって生命を奪はれてゐることを我々は忘却する権利はないはずだ» ・アメリカの無差別爆撃によって殺された我が国の同胞たちは、「アメリカの無法によって殺された被害者」ではなく、「戦争という犯罪を犯した罪を連合国から受けた、哀れな敗戦国民」としてしか記憶には留められていないのである。 ■「米ソによる共同謀議」を批判したプライス法務官 ・キーナン検事が中心になって起草した「起訴状」を読んで最も奇異に感じる部分は、日本が「ソ連」に対する侵攻戦争を計画・実行した罪で問われていることである。 ・連合国との停戦の仲立ちを日本政府から依頼され、日本が早期停戦を求めていたことを知りながら、ソ連は当時有効であった日ソ中立条約を一方的に破り、終戦直前の八月九日、満州、千島、北方領土に侵攻し、そのままそれらの地域を不法に占拠した。 ・日ソ関係に限定すれば、侵攻戦争を仕掛けたのはソ連の側であり、侵攻戦争の罪に問われるべきはソ連であることは誰の目にも明らかだった。 ・一九四七年(昭和二十二年)五月十六日、アメリカ人のA・G・ザラス弁護人は冒頭陳述で、日ソ不可侵条約に違反したソ連を強く批判し、日本の「ソ連に対する侵攻」を否定した。 ・一九四五年(昭和二十年)二月の「ヤルタ会談」で、ルーズベルト大統領はソ連の早期参戦の見返りとして、南満州鉄道の経営権及び、樺太と日本固有の領土を含む千島列島の領有権をソ連に引き渡すことをスターリンに密約した。 ・共和党議員曰く、「民主党のルーズベルト大統領は、国民を欺瞞して、ヤルタ会談におけるヤミ取引において、スターリンに大きな譲歩を与えた。ポーランドをタダでくれてやり、必要もないのに満州の利権と南樺太、千島を、これもタダ同然でスターリンにくれてやった」と。 ・マイニア教授は、一九四五年(昭和二十年)七月十七日から開催された「ポツダム会談」において、米ソ両国がいかにして日本侵攻のための共同謀議を謀ったかを、次のように描いている。 «ジェイムズ・F・バーンズ国務長官の言によれば、「ソ連政府は、アメリカ、イギリスおよび他の連合諸国がソ連政府に参戦するよう公式の要請を提出することが、最上の策だと考えている、とモロトフ[ソ連外相]は述べた」。バーンズは続けた。「この要請はわれわれに対して問題を提起した。ソ連は日本側と不可侵条約を締結していた。われわれは、アメリカ政府が他国政府に対して、後者の締結した条約を正当かつ十分な理由もなく破るように要請すべきではない、と信じていた。 「正当かつ十分な理由もなく」――これは重要な一句だった。一、二時間たつうちに、バーンズ長官は二つの口実を思いついた。一九四三年一〇月三〇日のモスクワ宣言と国際連合憲章 トルーマン大統領はソ連の介入を要請した手紙のなかで、つぎのように結論した。「憲章はまだ批准されておりませんが、サンフランシスコにおいてソ連代表はソ連政府が安全保障理事会の常任理事国になることに同意されました。したがって、モスクワ宣言および憲章の規定に鑑みて・・・・・・ソ連が、国際社会を代表して平和と安全を維持する共同行動のために、日本と現在戦争中の諸大国と協議、協力する意図を表明されることは、適切であろうと存じます。 アメリカ政府は、ソ連政府に対して根拠薄弱な理由付けを用意してやり、未批准の条約のために既存の条約を一方的に廃棄させたのであった。 バーンズ曰く、「ソ連の歴史家はソ連の対日宣戦布告が国際的な義務を忠実に履行したものである、と都合の良い主張をできることになった」» ・ソ連は、まだ批准もされていない国連憲章の草案によって、条約違反も、対日侵攻も、そして今なお続く北方領土の不法占拠も正当化した。その結果、満州・樺太・千島列島に在住した日本、韓国、中国のきわめて多数の民間人が殺害され、日本政府の財産ばかりか、多数の民間企業、数十万の民間人の財産のすべてが奪われたが、それらの行為の一切は東京裁判で訴追されるどころか、「国際連合」の名において正当化されたのである。 ・GHQが東京裁判の準備を進めつつあった一九四五年(昭和二十年)十二月、アメリカのプライス陸軍法務官は『ニューヨーク・タイムズ』紙で、強く批判した。 «東京裁判は、日本が侵略戦争をやったことを、懲罰する裁判だが、無意味に帰するからやめたらよかろう。なぜならそれを訴追する原告アメリカが、明らかに責任があるからである。ソ連は日ソ不可侵条約を破って参戦したが、これはスターリンだけの責任ではなく、戦後に千島、樺太を譲ることを条件として、日本攻撃を依頼し、これを共同謀議したもので、これはやはり侵略者であるから、日本を侵略者呼ばわりして懲罰しても精神的効果はない» ■「戦勝国の判事だけによる裁判は公平ではない」(ファーネス弁護人) ・公判でアメリカ人のジョージ・ファーネス弁護人は全被告に代わって訴えた。 «此の裁判所の判事は総べて斯う云う[戦勝国の]国家の代表であり、是が原告国家の代表であり、又検察官も其の国家を代表して居るのであります。我々は此の裁判所の各判事が明かに公正であるに拘らず、任命の事情に依って決して公正であり得ないことを主張するのであります。でありますから此の裁判は今日に於ても又今後の歴史に於ても、公正でなかった、合法的でなかったと云う疑いを免れることが出来ないのであります。» ・イギリスの元内閣官房長官ハンキー卿も批判している。 «未来に対して極めて重要な裁判を行う法廷を偏見の度合の少い連合国の構成国、もしくは、もっと公平な中立国の判事を参加させずに、戦争の矢おもてに立った連合国の構成国の指名した判事だけで構成することに決定したことは、果して正しく賢明だっただろうか。 われわれはいま少しで負けるところだったが、かりに負けたとしたら、われわれは日・独・伊三国だけによる裁判に納得しただろうか。また、歴史がそのような裁判の結果を受けいれると期待されるだろうか。» ・そもそも個々の裁判官の適格性にも疑問があった。アメリカに限らず法治国家の多くは、係争中の事件に事前に関係した人物は、その事件の裁判官になる資格はないとしている。 ・ところが、アメリカ代表マイロン・H・クレーマー少将は真珠湾攻撃の責任に関する法書簡を大統領に提出していた。フィリピン代表のハラニーヨ判事も日本軍の捕虜の経験があった。両者とも不適格である。裁判長を務めたオーストラリアのウェッブ裁判長もまた、戦争中、オーストラリアの戦争犯罪委員として、ニューギニアにおける日本軍の行為を調査した経験があった。 ・このため、オーストラリア高等裁判所ブレナン判事は、東京裁判が開廷される二ヵ月前の一九四六年(昭和二十一年)三月二十二日付『シドニー・モーニング・ヘラルド』紙において、 «ここに、犯罪捜査を担当し、ある犯罪人の証拠集めにたずさわった刑事がいるとする。英国の法廷は、この判事を、同類の犯罪人を裁く判事に任命するであろうか? この問題は、必ずや提起されるであろう。» ・当然のことながら、法廷で弁護側は、ウェッブ裁判長をはじめとする適格性を持たない裁判官に対する忌避を申し立てたが、その申し立てはすべて理由を明示されることなく却下された。 ・一九四八年(昭和二十三年)十一月、ジョン・G・ブラナン弁護人らはアメリカ連邦最高裁判所に対して「人身保護令適用のための訴願」を提出し、 «五、裁判所の判事たちは全部日本と戦争をした国の国民であり、各国政府が日本は侵略戦争をした罪があるとの政治的決定を宣言している以上、判事たちは公平無私の見解をとる事はできない。 六、審理の冒頭、原告達は裁判官忌避を申し立てしようとしたが、法廷は各裁判官はマッカーサー元帥の任命に基づくとの理由で、この申立を却下した。公訴に対して判事の忌避を申し立てる権利は、米国法廷で審理される全被告が持っている。・・・・・・ 八、よって原告は、次の事を嘆願する。・・・・・・ (2) この訴願をするに至った、米行政・軍両当局の行為と執った処置は[米国]憲法違反であり、無効である事を宣言すること» といった趣旨のことを訴えた。 ・この訴えは、最終的に却下されてしまった。 ■一部グループによる判決に抗議したブレイクニー弁護人 ・半数の判事が欠席しても法廷は続行され、その判決に際してもわずか一票差で死刑の判決が下されるなど、審理規則も通例を大幅に逸脱していた。 ・死刑の宣告には裁判官の全員一致を通例とする近代国家の裁判所ではあり得ない。 ・裁判終了後の一九四八年(昭和二十三年)十一月、全弁護団を代表してベン・ブルース・ブレイクニー弁護人は、減刑権を有している連合国最高司令官マッカーサーに対し、減刑嘆願のための覚書を提出、次のように訴えた。 «大部分の文明国では、死刑を科するには全員一致を必要とし、普通は単なる有罪の判定についても同様である。われわれアメリカ人は十一名中、六名または七名のものが有罪と判定し、死刑を宣告することを言語道断と考えるし、文明社会もまた、これを言語道断と見るにちがいない。有罪は、容疑の余地があるということ以上にはなんら立証されなかった。» ・東京裁判は近代法治国家の裁判としての要件を著しく欠いていた。はっきり言えば、裁判と呼べるシロモノではなかったのだ。 ■裁判の公正さを疑うベルナール判事 ・ニュルンベルク条例を踏襲した極東国際軍事裁判所条例において、「証拠規則」は次のように規定された。 «第13条 証拠 (イ) 証拠能力 本裁判所は、証拠に関する技術的法則に拘束されない。本裁判所は、迅速且機宜の手続を最大限度に採用し、かつ、適用し、本裁判所において証明力があると認めるいかなる証拠をも採用するのとする。・・・・・・» ・これらの規定の運用次第では、裁判長は、 ①証拠に関する専門技術的規則に拘束されず、通例ならば伝聞証拠として却下されうるような材料も受理することができる上、 ②提出されてくる証拠文書の採否を関連性の有無を口実に甚だ恣意的に決定することができ、 ③その決定に際しては予め証拠の内容を検討し、裁判長にとって都合が悪い証拠は事前検閲をなすがごとく、法廷に提出される前に却下する、 ことができた。 ・平たく言えば、証拠が採用されるかどうかは、すべて裁判長の判断次第となった。そして実際に裁判長の恣意的な判断で証拠の採否は左右された。 ・当時の日本政府の公式声明がすべて却下ということは、証拠規則においても「裁判を敗戦国の言い分を宣伝する場としてはならないし、戦勝国の戦争責任も追及されてはならない」という連合国の当初からの原則が冷厳に貫かれたことを物語っている。 ・フランスのアンリ・ベルナール判事は、特に「審理の手続についての意見」を提出し、 «条例は被告に弁護のために十分な保障を与えることを許していると自分は考えるが、実際にはこの保障は被告に与えられなかったと自分は考える。 多くの文明国家でそれに違反すれば全手続きの向こうとなるような重大な諸原則と、被告に対する訴訟を却下する法廷の権利が尊重されなかった。» ・オランダのベルト・レーリンク判事も、 «手続き上にも問題がいくつかあり、不公平な点がありました。 一例をあげると、中国における共産主義の脅威があったことを立証する機会を与えてほしい、との求めが被告側から出されました。そうした脅威があったために、日本は行動を起こしたと立証しようとしたのです。ドイツの場合は、ヨーロッパ大陸での大国になろうとして戦争に突入していったのですが、日本は、これとは違います。結局、裁判では、立証の機会は認められませんでしたが、アンフェア(不公平)だったと思っています。» ■「弁護側に不利な証拠規則だった」(プリチャード博士) ・インド代表のパール判事は、弁護側が提出し却下された文書類を次のように分類している。 «(1)日本軍が行動を開始した以前における中国本土の状態に関する証拠 (2)在中国の日本軍が中国に平和を恢復し、静謐をもたらしたことを示す証拠 (4)満州が日本の生命線であるという日本国民の輿論を示す証拠 (6)原子爆弾決定に関する証拠 (10)中国における共産主義に関する証拠» ・かくして、これらの視点に基づく証拠文書をすべて排除することによって事実認定がなされ、東京裁判の判決が下されたのである。 ・ブレイクニー弁護人は全弁護団を代表して、一九四八年(昭和二十三年)十一月、減刑権を有している連合国最高司令官マッカーサーに対し、減刑嘆願のための覚書を提出したが、その中で証拠採用の不公正さについても次のように訴えた。 « 裁判は不公正である ・・・・・・裁判所は、ある種の弁護の申立をきくことを拒絶したが、判決のなかでは、これらの弁護は「根拠とすべき証拠がないから」受理できないといっている。裁判所は検察側の「証拠」は新聞報道、二次的・三次的の噂、伝聞証拠、自称「専門家」の意見のかたちのものまで受理し、かかる「証拠」に基いて事実を認定し、有罪無罪を決定した。そして、日本人証人の証拠は不満であり、信頼できないとして、一切の弁護側証拠を、その判定に当って無視した。 » ・同年十一月、ディビッド・スミス弁護人らがアメリカ連邦最高裁判所に対して人身保護令の適用を次のように申し立てた。 «東京の国際法廷は、なんとしても米国の一市民であるマッカーサー元帥によって設置されたものである。マ元帥は、米国の行政部門(大統領)の命令によって設置したのだが、アメリカの立法府はこのような新規の裁判所の設置を、遣外司令官に委任したことはない。これは明らかに憲法違反である。--したがって、その被告たちに、人身保護令の手続きがとられるべきである。» ・スミス弁護人は、法手続きの不備、不公正さを指摘し、次のような激烈な東京法廷攻撃を行った。 «東京法廷は、真の国際法廷ではない。あれはマッカーサー元帥個人の裁判所である。元帥は、彼自身を国際的代表者と呼ぶことによって、米国の法律と縁を切ることはできない。東京法廷は、マ元帥のための事実審議機関であって、判決は、直接マ元帥のところに移されたし、最終の決定は、マ元帥にかかっていた。――訴願者[日本人の被告たち]は、今までどんな文化的、現代的法廷も直面したことがないような弛緩した証拠と手続きに関する規則にさらされたのである。法廷は、反対と、例外とにかまわず、署名されていない口述書、宣誓されていない声明、新聞報道、二流、三流の伝聞証拠を受理した» ・しかし、連邦最高裁は、「訴願受理の管轄権なし」として訴願を却下してしまう。 ・かくして日本の「言い分」を排除してかろうじて成り立った「戦勝国による事実認定」は、連合国=国際連合公認の歴史観として流布されることになった。 ・一九八八年(昭和六十三年)イギリスで、ロンドン・スクール・オブ・エコノミックス(LSE)から英語版『極東国際軍事裁判記録』が発行されたが、その編集責任者でロンドン大学のジョン・プリチャード研究員は、裁判は真実の解明よりも最初から日本側旧指導層の処罰と国民の再教育(正確に言えば「洗脳」であろう)を目的とする勝者の裁きだったとして、東京裁判の問題点を次のように列挙している。 «①検察は真実の解明よりもとにかく日本側の指導者たちをきびしく処罰して、日本国民を再教育することを目的としていた。判事たちは検察側の主張をうのみにして弁護側の証拠とか主張は一方的に却下した明確な形跡が多い。 ②一般に戦争犯罪とされる捕虜や民間人への残虐行為に関する記録は全体の五 ― 一〇%で、ニュルンベルク裁判よりずっと比率が低い。残りの「戦争についての政策」の部分は戦争を侵略と自衛に分けることは難しいし、日本の歴代指導層が一致して侵略戦争を企図したともいえないから「戦争に関する共同謀議」とか「不法戦争による殺人」という訴因にも法的根拠をほとんどみいだせない。 ③戦争後までは存在しなかった「平和に対する罪」を過去にさかのぼって適用する点やその「罪」の根拠を一九二八年のパリ不戦条約に求める点にも無のがある。 ・「勝者の言い分」とその言い分を裏付ける証拠によってのみ歴史認定を日本人に強いてきた「東京裁判」は、近現代史に関する公平かつ客観的な研究を五十年もの間、不当に妨げてきたのだ。その「罪」は途方もなく重いといわなければならない。» 【第4章】 蹂躙された国際法 ――国際法学者による「極東国際軍事裁判所条例」批判 ■「共同謀議」史観を批判したミアーズ女史 ・マイニア教授が一九七一年(昭和四十六年)曰く、 «戦争まえの日本の歴史を書こうとした極東国際軍事裁判所の試みは、見事に失敗した。最大の原因は、東京裁判の背後にあって東京裁判の進路を支配した基本的な誤謬であった。それは日本の歴史が共同謀議によって説明できるという考えであり、かつこの共同謀議が侵略的性格を持っていたという考えであった。» ・残念なことに東京裁判の判決を盲目的に受け入れた、いわゆる "進歩的文化人" と言われる人々によって、我が国の近現代史は「軍国主義者たちによる "共同謀議" の歴史であった」と喧伝されることになったのである。 ■イプセン教授の「個人責任論」批判 ・これまで戦争は国際法上の人格を持つ国家の相互間の事件で、敗戦国は通常、賠償金の支払いや領土の割譲という代償は支払ったが、戦争遂行自体が犯罪であるとして、その指導者が個人的刑事責任を追及されるようなことはなかっのである。 ■「不作為犯」理論に反対だったランシング米国務長官 ・連合国は、戦前・戦時中、日本軍が中国大陸、ジャワ、シンガポール、マニラ、香港などその戦闘地域及び占領地域において、略奪、暴行、凌辱、殺人、俘虜虐待などの非道の限りを尽くしたとして、それら戦争の法規・慣例(交戦法規)違反の残虐行為を命令したり、あるいは手掛けたとする日本人将兵(戦時中日本国籍を有していた朝鮮人、台湾人も含む)をB・C級戦犯として訴追し、アジア各地に設けた軍事裁判所で裁判にかけ、一千余名を処刑した。 ・更に東京裁判においても、日本人吏員に対し、戦争の法規・慣例の違反行為を「頻繁にして常習的に」なすことを「命令し授権し且つ許可すること」を共謀し、それらの違反行為を現実に「命令し授権し且つ許可し」たか、あるいは、戦争の法規・慣例の「遵守を確保しその違反を防止するに適当なる手段を執るべき法律上の義務を故意又は注意に無視した」として、それら交戦法規違反の行為が日本人将兵によって行なわれた時期に責任ある立場にあった指導者たちを、「通例の戦争犯罪及び人道に対する罪」を犯したA級戦犯として訴追した。 ・この「通例の戦争犯罪及び人道に対する罪」について、パール判事は「全員無罪」とした。 ・たしかに日本軍による残虐行為はあったが、ドイツと違って日本の場合は一般市民の虐待に関する「命令、授権または許可が与えられたという証拠は皆無」であり、捕虜虐待が政府の政策であったことを示す証拠もない。 ・アメリカのロバート・ランシング国務長官は痛烈に攻撃していた。 «犯罪を構成する行為をなした個人や自己の権限に基づいて他人に犯罪行為をなすように命じた個人を処罰することと、戦争の法規・慣例の違反を防止しなかったり、停止しなかったり、あるいは抑止しなかった個人を処罰することは、まったく別の問題である。 前者の場合には、当該個人は自ら行為したり他人に行為するように命じたりするのであって、自ら犯罪行為をなしているのである。だが後者の場合には、当該個人は他人の行為について処罰されるのであって、しかもそれは、かれが問題の行為がなされるのを知っていたか、または知っておればその行為を止めえたことが証明されない場合においてである。» ・「共同謀議」理論といい、「個人責任」理論といい、「不作為犯」理論といい、米欧戦勝国は国際法をねじ曲げるだけでは飽き足らず、当時国際法では認知されていなかった理論までも持ち出して、日本の指導者を裁き処罰したのである。 ・アメリカ連邦最高裁判所のダグラス判事らは、「東京裁判は司法的な法廷ではなかった。政治権力の道具に過ぎなかった」と批判した。 ■「合法的手続きの仮面をかぶった復讐」(マーフィー連邦最高裁判事) ・B級戦犯は、軍隊の上級指揮官を対象とする裁判、指揮、命令、あるいはその不作為責任を問われている裁判。 ・C級戦犯は、残虐行為、俘虜虐待などの直接責任者、実行者などの裁判。 ■「インド政府はパール判決を支持する」(チョプラ教育省事務次官) ・アジア近隣諸国に配慮して、日本政府は東京裁判の歴史観(いわゆる日本侵略史観)を認めるべきだとの主張をよく耳にするが、アジア諸国の歴史観は決して同一ではない。少なくともインドは反東京裁判史観に立脚している。アジアへの配慮を言うのであるならば、インドの歴史観をも日本政府は尊重すべきではないだろうか。 【第5章】 ‹東京裁判› は平和探求に寄与したか ――残された禍根と教訓 ■「アメリカの正義を疑え」(マイニア教授) ・我が国では、社会民主党(旧社会党)など革新系政党は表面上はアメリカを批判する。しかし、実際にやっていることは、日本のナショナリズムを抑圧し、東京裁判に示された「アメリカの正義」を認め、例えば改憲志向に示される日本の自立路線に反対することで、結果的にアメリカの属国化を促進し、もってアメリカ中心の国際体制を補完しているにほかならない。 ・一方、自民党もまた、米ソの冷戦構造の中で、東京裁判に示された「アメリカの正義」を認め、国際正義=アメリカの正義というイデオロギーを進んで容認すること――それはつまりアメリカの不正義、アメリカの外交の失敗には敢えて目をつぶり、アメリカを補完する存在に甘んじることだが――によって自国の安全保障を図る道を選択してきた。 ・武装解除された敗戦国家として戦後しばらくはそれもやむを得ない選択だったと思うが、その選択を五十年経った今も同じかたちで続けていることについて、対米追従と世界から揶揄・批判・憫笑されている事実に目を ・今や私たちは新たな選択を迫られている。即ち、アメリカとの関係を重視しつつも、アメリカの主観的正義のみによる国際秩序ではなく、我が国の主体的正義をも国際秩序に反映させることを望む、あるいは自由と平和と繁栄を尊重する諸国とともに、アメリカが政策を誤った場合には時にはそれを糺すことも辞さない、そのような国家として歩むことが求められているのである。 ・それはマイニア教授が指摘するように、現在の国際秩序の諸前提にある、東京裁判に示された「アメリカの正義」そのものを検証するところから始めなければならない。東京裁判の再検討は、現在の国際秩序のあり方とともに、これからの我が国の進路選択をも迫る問題として、私たちの前に立ちはだかっているのである。 【第6章】 戦後政治の原点としての‹東京裁判›批判 ――独立国家日本の「もう一つの戦後史」 ■講和会議で東京裁判を批判したメキシコ大使 ・国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって戦争が正式に終結するものとされる。それまで法的には「戦争状態が継続していると見なされる。 ・いわゆるA級戦犯を裁いた東京裁判や、アジア太平洋の各地で開廷されたB・C級戦犯裁判も、連合国軍による軍事行動(戦争行為)の一種と理解されている。しかし、軍事行動は講和条約の発効と共に終結し、効力を失う。 ・つまり、昭和二十七年(一九五二年)四月二十八日のサンフランシスコ講和条約の発効とともに、国際法的には日本と連合国の間に継続していた「戦争状態」は終焉し、独立を回復した日本政府は、講和に伴う(国際法上の大赦」を規定する国際慣習法に従って、戦争裁判判決の執行を承認した上で、連合国が戦犯として拘禁していた人々すべて釈放することができたはずなのである。 ところが、そうはならなかった。 ・本来ならば、日本政府は講和条約の発効とともに、戦犯として拘禁されていた者を釈放していいはずだが、アメリカは、講和独立後も、アメリカの「審判」に従った刑の執行を日本政府に要求したのである。 ・一九五一年(昭和二十六年)九月五日、サンフランシスコ講和会議が開かれた。この会議で、スリランカ代表のJ・R・ジャヤワルダナ蔵相(のち首相、大統領)は、 「私は、前大戦中のいろいろな出来事を思い出させるが、当時、アジア共栄のスローガンは、従属諸民族に強く訴えるものがあり、ビルマ、インド、インドネシアの指導者たちの中には、最愛の祖国が解放されることを希望して、日本に協力した者がいたのである」 として、日本の独立回復を支持する格調高い演説をした。 ・ラファエル・デ・ラ・コリナ駐米メキシコ大使はメキシコ代表として、 «あの裁判の結果は、法の諸原則と必ずしも調和せず、特に法なければ罪なく、法なければ罰なしという近代文明の最も重要な原則、世界の全文明諸国の刑法典に採用されている原則と調和ないと、われわれは信ずる» と東京裁判を批判した。 ・アルゼンチン代表のイポリト・ヘスス・パス駐米アルゼンチン大使も、 «法廷[東京裁判]に関しては、わが国の憲法は、何人といえども正当な法律上の手続きをふまずに処罰されない事を規定しています。» と語った。 ■四千万人を越えた「戦犯」釈放署名 ・かくして一九五一年(昭和二十六年)九月八日、サンフランシスコにおいて日本と四十八ヵ国の連合国とが講和条約に調印し、翌一九五二年(昭和二十七年)四月二十八日に発効した。 ・日本は晴れて独立を回復したが、講和条約第十一条に、関係国の同意なくして日本政府は独自に戦争受刑者(戦犯)を釈放してはならないと規定されていたため、引き続き千二百二十四名もの日本人および戦時中日本国籍を有していた朝鮮人・台湾人がA級及びB・C級戦犯として服役しなければならなかった。 ■可決された「戦争犯罪」否定の国会決議 ・平成五年(一九九三年)、細川護熙首相は「東京裁判の判決を受け入れることで日本は国際社会に復帰した」と述べたが、事実は全く違っていた。 ・総理大臣としては恐ろしく無知にして無見識なものであった。 ・講和独立後の日本の政治家たちは、「勝者の裁き」を敢然と拒否することこそが「わが国の完全独立」と「世界平和」につながると信じた。勝者の裁きを否定して、連合国によって奪われた「歴史解釈権」を晴れて取り戻した「完全な独立国家」として国際親交に努めたい――これが紛れもなく戦後の日本政治の原点であったと言えよう。 ・なお、A級戦犯は昭和三十一年(一九五六年)三月三十一日までに関係各国の同意を得て全員出所したが、B・C級の最後の十八名の仮出所が許され全員出所したのは昭和三十三年(一九五八年)五月三十日のことであった。 ■日本は東京裁判史観を強制されていない ・東京裁判否定の熱意を受け継ぐべき保守政治家たちは、米国との協調・友好を重視するあまり、米国の戦争責任追及=反米につながりかねない東京裁判否定論をトーンダウンさせてゆく。 ・一方、革新勢力は、ソ連・中国のマルクス主義史観に強い影響を受けながらマスコミや日教組と手を組み、 “東京裁判史観” の普及に、これ努めることになったのである。 ・かくしてマスコミや革新勢力の支援の中で、GHQの協力を得て結成した日本教職員組合(日教組)が、GHQの「戦争犯罪周知宣伝計画」に基づいて作成された「歴史教科書」を使って行う歴史授業によって、アメリカの「審判と慈悲に絶対的に従う」従属政権の樹立を促進しようとしたGHQの意図は、徐々に日本の若い世代の間で実現していくこととなった。 ・昭和五十七年(1982年)、歴史教科書の記述を文部省が検定で「侵略」から「進出」に書き換えさせたとして(これは後に誤報であることが判明した)、中・韓両国から大きな反発を招いた、いわゆる「教科書事件」が起こった。 ・近隣諸国から厳しく批判され、時の宮澤喜一官房長官(自民党)は、事実関係をろくに調べないまま、批判を全面的に受け入れた上、「わが国としては、アジアの近隣諸国との友好、親善を進める上でこれらの批判(韓国、中国からの批判)に十分耳を傾け、政府の責任において是正する」という談話を発表するに至った。 ・近隣諸国との友好のためには、東京裁判の判決に示された歴史観を受け入れるという、独立回復後の国会決議とまるで正反対の趣旨の談話が表明されたことになる。 ・以後今日に至るまで、残念ながらこの談話が追認される方向で進んでいるのである。 ・敵国によって “A級戦犯” とされた人々を靖国神社に合祀したことをめぐって再び近隣諸国を巻き込んだ形での問題が起こり、そのさなかの一九八五年(昭和六十年)十一月八日、衆議院外務委員会で土井たか子議員(社会党)は「戦犯は日本も受け入れた東京裁判によって “平和に対する罪” で処刑されたのであり、戦没者とは違う。どうして戦犯を祀っている靖国に参拝するのか」と質問した。 ・同じ社会党の先輩女性議員が、戦犯とされた人々が靖国神社にお祀りされていないことを嘆く遺族の人々の心情を代弁して、戦犯釈放運動を熱心に推進していたことなど、知りもしなかったのであろう。 ・この時期、サンフランシスコ講和会議でも問題とされた講和条約第十一条に「裁判を受諾し」との一節があることから、日本政府は第十一条のゆえに講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」の部分に示された、いわゆる「東京裁判史観」の正当性を認め続けるべき義務があると、一部学者たちが強硬に主張していた。 ・この主張の論拠の一つが、第十一条の日本文に「裁判を受諾し」とあることである。しかし、日本政府が「受諾」したのは「裁判」ではなく、「判決」であった。 ・そうである以上、日本は「東京裁判史観」まで受け入れたことにはならないのである。 ・国際法の専門家である佐藤和男教授は、 «第十一条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止を阻止することを狙ったものに過ぎず、それ以上の何ものでもなかった。日本政府は第十一条の故に講和成立後も、東京裁判野「判決」中の「判決理由」の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)の正当性を認め続けるべき義務があるという一部の人々の主張には、まったく根拠がない。 議論し得た限りすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはあり得ない」と語った。これが、世界の国際法学界の常識である» ・独立回復後の日本の政治家たちは、「勝者の裁き」を敢然と拒否することこそが「わが国の完全独立」と「国際親交」につながると信じたが、それは「自己解釈権」を取り戻した独立国家として、極めて当然かつ正当な行動であった。 ・こうした戦後政治の原点を踏まえ、私たちは、国際法上、敵国の軍事行動の一環であった「東京裁判」の判決にとらわれることなく、歴史の再検証と東京裁判の克服を堂々と世界に訴えていくべきなのである。 ・そうすれば、いわゆる東京裁判史観を日本に強要したいと考えている中・韓両国などは猛然と反発するだろうが、その一方で世界の国際法学者や識者たちが、あるいは反東京裁判史観を奉じるインドをはじめとするアジアの識者たちが、必ずや私たちの主張を断固支持・支援してくれるに違いない。 ■第二次東京裁判の開廷を提唱するセント・ジョン弁護士 ・なぜ戦後、全人類は核兵器の恐怖に脅えなければならなかったのか。アメリカが東京裁判において、原爆投下の罪を免罪にしたばかりか、侵略国日本を懲罰するために原爆は必要だったという悪質なデマを流し、原爆投下を正当化したからだ。 ・とするならば、核軍縮そして全廃へという国際政治の潮流を生み出すためには、東京裁判が不問にした連合国側の戦争責任を国際法に照らしてもう一度追及すべきではないか。 【私見 : どんな場面であれ、原爆投下の正当性が一度容認されれば、核拡散は防げない。日本の立場というより、原爆の使用そのものが間違いであることを世界の共通認識にする必要がある。その為には、一般論として原爆投下は間違いであったと認めさせる必要がある。日本人が原爆使用を是認することは、世界に対して誤ったメッセージを送り、かつ、核使用の正当化に道を開いたことになり、この罪は大きい】 ・連合国の戦犯裁判で殺された一千余名の日本人の名誉回復と、誤った歴史観の払拭のためばかりではない。国際正義の観点から、私たちは東京裁判の全面的な見直しを世界に訴える時を迎えているのである。 日本は東京裁判史観により拘束されない ――サンフランシスコ平和条約十一条の正しい解釈 ・国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって、戦争が正式に終結するものとされます。つまり、講和の成立(平和条約の効力発生)によって、国際法上の戦争状態が終了するのです。 ・日本の場合、昭和二十年九月二日に米艦ミズリー号上で連合国との間で「降伏文書」(連合国側の命名)の調印を行いましたが、この文書はポツダム宣言の内容を条約化して、日本の条件付終戦――日本政府が無条件降伏したというのは大きな間違いです――を正式に実現したもので、法的には「休戦協定」の性質を持ちます。 ・連合国占領軍は、日本が戦争終結の条件として受諾した事柄(ポツダム宣言六項~十三項に)を、日本に履行させるために、およそ七年間駐留して軍事占領行政を実施します。 ・が、サンフランシスコ対連合国平和条約が発効する昭和二十七年四月二十八日までは、国際法的には日本と連合国の間に「戦争状態」が継続しており、いわゆるA級戦犯を裁いた東京裁判と、B・C級戦犯裁判とは、連合国が軍事行動(戦争行為)として遂行したものであることを、よく理解する必要があります。 ・日本国民の中には、大東亜戦争は昭和二十年八月十五日に終ったと思い込んでいる人が多いのですが、国際法の観点からいえばこれは間違いで、戦闘期間が終わっても軍事占領期間中は「戦争」は継続されていたと見るのが正しく、事実、連合国側は平和条約発効の時まで、戦争行為として軍事占領を行うという意識を堅持して、連合国の目的にかなった日本変造に力を注いだのです。 あとがき ■東京裁判批判という国際正義を日本は掲げよ ・欧米諸国には、東京裁判を批判し、或いは連合国の戦争責任を追及する識者が意外なほど多い。また、パール判事の出身国インドでも東京裁判研究は盛んである。 ‹東京裁判› 批判論は日本でしか通用しないというのは勝手な思い込みに過ぎない。 ・連合国側がなぜ東京裁判を行なおうとしたのか。敵国の哲学(民族精神)を粉砕し、連合国の意のままになるように "精神的" 国家改造を行なうことが占領政策の目的であり、東京裁判はその目的達成の手段の一つであった。 ・国際正義に基づいた「国際裁判」と称したが、その実態は連合国による "武器なき" 軍事作戦の一環であった。連合国は停戦後も、東京裁判という軍事作戦を行ない、日本人の民族精神を抹殺しようとしたのである。 ・こうした政策が国際法上許されるはずもない。そこで連合国側は、日本政府が「ポツダム宣言」を受諾し、 "条件付終戦" に応じたのにも拘わらず、「無条件降伏したのだから日本は連合国の政策を受け入れよ」と虚偽の政治宣伝を行ない、自らの行動を正当化したのである。 ・その意味で、東京裁判を克服するためには、「日本は無条件降伏をした」という連合国側の悪質な宣伝を批判するところから始めるべきであろう。 ・世界の識者の ‹東京裁判› 批判のポイントは大別して二つある。 ・一つは、極東国際軍事裁判所は日本だけを裁き、連合国側の戦争犯罪を不問に付したという意味で、不公平な裁判所であったということである。 ・そもそも欧米諸国がアジア諸国を次々と支配し、排他的な経済ブロックを形成しなければ、日本は戦争に訴えてまで資源を確保しなくてもよかった。戦争責任は、連合国側にも求められるべきであったのである。 ・批判のもう一つのポイントは、東京裁判は実定国際法に反していたということである。 ・裁判が成立するためには法律が必要であり、東京裁判の場合、その法律にあたるものは連合国の委任を受けてマッカーサー司令官が制定した「極東軍事裁判所条例」であった。 ・この「条例」は、不戦条約を曲解することで事後に新しい罪をでっち上げ、国際法上なじみのない理論を導入するなど実定国際法に大きく反したものであった。東京裁判は、連合国による許しがたい不法行為であったのである。 ・このことは、日本の加害責任なるものを ・しかし、東京裁判は結局のところ、「敗者は戦争犯罪人として処刑され、戦勝国側の戦争犯罪は免罪される」という悪例をのこしたに過ぎず、国際法を退歩させただけであった。 ・国際法の漸進的発達による世界平和を願うならば、私たちはむしろ ‹東京裁判› を積極的に批判するべきなのである。 ・敵国によって「戦争犯罪人」という不当な烙印を押されたわが国の人々の名誉回復を図ろうとすると、往々にして「過去の反省が不足している」などと非難されがちだ。しかし、ひるむことはない。 ・「戦犯」の名誉回復は、東京裁判によって損なわれた国際法の権威の回復でもある。世界平和を願い、国際法を擁護するからこそ、私たちは「戦犯」の名誉回復に立ち上がるべきなのである。 ・実は、講和独立直後の我が国の政治家たちはそう考えていた。現在、「我が国は、東京裁判を受け入れることで国際社会に復帰した」というマスコミの宣伝を信じ込んでしまっている人が多いが、当時の国会論議などを丁寧に追っていくと、意外なことに社会党代議士でさえ東京裁判を敢然と批判している。 ・勝者の裁きを否定し、「戦犯」の名誉回復を図り、連合国によって奪われた「歴史解釈権」を晴れて取り戻した「完全な独立国家」として国際親交に努めたい――これも紛れもなく戦後政治の原点の一つであった。 |