
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年05月17日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
94 |
16/11 |
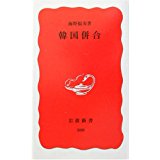 |
韓国併合 |
海野福寿 |
岩波新書 |
◎ |
第一章 朝鮮の開国 一 外交慣例をめぐる紛糾 江華島に刻まれた戦いのあと ・高麗時代の一三世紀、高麗全土がモンゴル軍の馬蹄に蹂躙された。 ・一七世紀には、朝鮮の臣属を求めて侵入してきた清の大軍によって江華島が占領された。 ・フランス人神父殺害の責任追及を名目としたフランス艦隊の侵入(一八六六年)。 ・アメリカ商船焼き打ち事件の調査・報復を理由としたアメリカ艦隊の攻撃(一八七一年)。 ・ともに真の目的は、朝鮮の開国強要であった。 ・清国・日本についで、朝鮮も開国させようという列強の飢えた波がひたひたと島に打ち寄せ、海辺を洗っていた。 鎖国攘夷政策の強化 ・フランス・アメリカの侵略行為をしりぞけたことは、実権を把握していた大院君に自信をあたえた。 ・危機を回避することができたのは排外攘夷主義の正しさによる、と理解した彼は、中華世界のもとでの朝鮮国家を外圧から守るためには鎖国攘夷政策の強化こそ唯一の道である、と誤信した。 ・欧米諸国を夷狄として排斥し、伝統的な朝鮮支配体制と朱子学的道徳を堅持することを強調した「衛正斥邪」思想がおこり、それを主張する一派の政治的影響力もつよまった。 慣例無視の外交文書 ・日本では維新政府が成立した。不平等条約の重荷をせおって誕生した新政府は、早々に対外親和・開国進取・万国対峙・国権拡張を国是にかかげた。 ・そのひとつは文明開化・富国強兵の線にそいながら条約改正事業にむかい、もうひとつは、その裏返しとしてアジア近隣諸国に対する国権外交へ走った。 ・特に朝鮮にたいしては、当初から侵略の志向をのぞかせていた。 【私見 : 地球規模で見て、日本はペリーの開国要求以前から、欧米のアジアに対する植民地政策に脅威を抱き、清国、朝鮮半島が力を付けないと日本も蹂躙されてしまうことを恐れ、朝鮮半島に進出していかざるを得なかったのではないだろうか。朝鮮そのものは侵略の対象ではなかったと思う】 ・外交通の木戸孝允は一八六八年(明治元)末以来、ことごとに征韓を主張していた。その根底にあるのは、江戸時代に醸成された朝鮮蔑視にまみれた歴史観である。 ・新政府は、王政復古を通告するための使節を朝鮮に派遣することにした。 ・六八年、対馬藩が持参した書契(外交文書)に、「 ・また、署名・印章も従来とことなったものを使用しており、慣例を無視した形式・表現であった。朝鮮側は、「規外」であり「違格」であるとして反発する。 ・釜山での交渉は一年余におよんだが、交隣(隣国との対等の通交)の慣例についていっさいの変更を認めない大院君政権下の朝鮮政府は、終始、書契受理と交渉をこばみとおした。 ・このような朝鮮の措置を「無礼」「侮日」と受けとめた木戸や外務当局は、征韓熱をかきたてる口実とする。 アジア朝貢体制とは ・前近代のアジアには歴史的に形成された ・李氏朝鮮(一三九二 ― 一九一〇年)はその典型であり、清国に臣属する藩属国として清国を宗主国として仰いでいた。 ・日本政府は条約改正のために小西洋をめざして出発したが、この朝貢体制の伝統的秩序にいかに対応していくか、というぬきさしならない問題に当面せざるをえなかった。朝貢体制を前提にして国家対等の関係を再編していくか。それとも朝貢体制を否定してアジア的世界から離脱し、これに挑戦するか。 ・歴史的事実としては、後者の道を歩んだことになる。 ・欧米諸国は朝鮮との開国に際して、一方で理念としての朝貢体制、清朝宗属関係を認めながら、他方では近代的な国家間関係を規定する条約をむすんでいる。西欧世界の論理をもって一方的にアジア的秩序に変革を迫るのではなく、まずはアジア的世界に参入する順序を踏んだのである。 ・日本もまた、清国とのあいだに七一年九月、日清修好条規を調印していたが、総じて「対等」な内容の条約であった。 ・これを清国側からみれば、従来の中華的秩序における「対等」性を近代的条約形式になぞらえて承認したのである。 対朝鮮政策の基本姿勢 ・一八七〇年四月、外務省から太政官あてに出された「対朝鮮政策三箇条」 第一の策は、「御国力充実迄」朝鮮との交際を廃止しよう、というもの。 第二の策は、まず皇使として木戸孝允を派遣し、王政復古通告の国書受理拒否を責め、通商条約締結をもちかけ、これを朝鮮側が拒否するならば武力発動におよぶ、というもの。 第三の策は、朝鮮「懐撫」のため、宗主国である清国と「比肩同等」の条約締結を先行させ、ついで朝鮮を「一等を下し候礼典」で扱い、「遠く和して近く攻る」の方策をとろう、というもの。 ・「日清修好条規」締結は、この第三の策を実行する手はじめである。 対朝鮮外交の一元化 ・一八七一年八月、廃藩置県により統一的中央集権国家の確立をはかった政府は、その機に、対馬藩宗氏の世襲政権である対朝鮮外交権を接収した。 ・翌七二年九月には、釜山の草梁倭館を外務省の管轄下に移し、日本公館と改称する。のちの日本領事館である。 ・草梁倭館とは日本からの使客を接待するために設けられた客館で、費用は朝鮮側が負担し、対馬藩がその使用を認められて、公私貿易もそこでおこなわれてきた。 ・こうした新政府の外交権一元化を朝鮮政府は認めなかった。 ・旧慣の礼を尊ぶ朝鮮側は、対馬藩吏以外の外交使節を「規外」としてしりぞけ、折衝をこばんでいた。 一方的な交渉放棄 ・朝鮮政府が固陋というわけにはいかない。従来どおりの宴享、しかも今回にかぎって旧例にもとづきおこない、書契を受理しよう、という柔軟な対応を示していたのである。 ・むしろ非妥協的な態度は森山理事官の側にあった。一八七五年四月、軍事的威嚇を背景にした交渉の必要を政府に請訓していた森山は、服装についてとやかくいうのは日本の内政にたいする干渉であり、「無礼」「侮蔑」である、という口述書を送った。最後通牒に等しい。 二 江華島事件――軍事力による開国強要 軍艦派遣を決定する ・交渉のゆきづまりを打開するため、 “軍艦一、二隻を派遣して朝鮮を威圧し、国論をゆさぶるのがよい” という主張である。 ・予告なしの入港に対し、東莱府は国交開始交渉中の突然の来航に抗議した。 ・許可を求めることもなしに、国交のない異国船が内国河川に侵入し、しかも要塞に接近することは歴然たる挑発行為である。これは日本政府が了解した計画的なものであった。 三 砲艦外交――「修交条規」の締結 黒田清隆の特派 ・一八七六年(明治九)一月、黒田特派大使は、品川沖を出港した。総員八〇〇人をこえる大集団である。 江華府にのりこむ ・日本側の態度は高圧的だった。 条約交渉の開始 ・交渉開始直前の正午に、停泊艦はいっせいに礼砲を打った。つまりは示威である。 【私見 : ペリー来航時と一緒や!】 ・朝鮮には全権委任の前例がなく、近代国家間の条約締結に必要な全権委任の意味が通じかねた。そればかりか締結すべき条約そのものの必要性さえ認めなかった。国交再会を中断していた交隣関係の修復と考える朝鮮にとっては、それらは慣例にないことである。 ・二月一二日の第二回会談で、済物浦へ来航した補給船「品川丸」を増援部隊の到着といつわり、さらに日本政府には後続の増派計画もある、とつけくわえて威嚇した。 条約交渉の展開 ・日本側が、朝鮮国は国際法上の主体として外交権をもつ独立国であるとして、清朝宗属関係の否定的表明としたのにたいし、朝鮮側は、逆に宗属関係 ― アジア朝貢体制の原理である「自主」と「平等」を表わしたものと解した。このズレが日清戦争にいたる日朝清関係のすきまを広げることになる。 ・朝鮮側が公使の首都常駐を拒否した理由は、 “江戸時代の通信使のように、慶弔時などに随時使節を派遣すればよい” とするもので、近代的外交関係からすれば異例であり、問題をあとにのこす。 ・日本の最大目標は、旧来の交隣関係を条約にもとづく国家間関係にあらためることだった。 批准書の親署問題 ・日本側は、国王の親署と玉璽捺印を要求した。これにたいし、朝鮮側は、国法に国王親署の規定がないとし、また、国王名を刻した玉璽もなく、「為政以徳」の印章をもって裁可のしるしとしていることを理由に、断然拒否して、結論をうるにいたらない。 ・黒田全権は、批准書に国家元首が親署するのは国際的慣例であることをかさねて説いた。 ・しかし、接見大官・副官ともに “臣下が国王に署名を乞うことは礼にそむくのでできない” とかたく拒否してゆずらず、平行線をたどった。 ・なぜ黒田は固執したのか。伝統にこだわる朝鮮の外交手法を近代的条約形式と国際法的ルールで打破したいと考えたためとしか思えない。 ・二二日、黒田は江華府から撤収することを通告した。交渉決裂を意味する。だが、これはポーズにすぎない。 ・軍事力をちらつかせながら危機状況をつくりだし、我意を通すという、拙劣ではあるが常套の外交手段である。 修交条規の調印 ・条約書を国王が裁可し、その調印式は二月二七日ときまった。 ・両国全権が記名捺印した「修交条規」を交換した。 ・日本天皇の批准は三月二二日。このとき、「修交条規」が発効した。 ・二月一一日にはじまった「日朝修交条規」交渉は、こうして終わった。近代朝鮮の悲劇の幕開けである。 四 解釈をめぐる対立 修交条規付録をめぐって ・さきに調印された「日朝修交条規」は、あたらしい日朝関係の、いわば総論で、具体的な外交・通商事項のとりきめは、「日朝修交条規付録」の協定であり、もうひとつが「朝鮮国議定諸港に於て日本国人民貿易規則」の締結である。 ・日本公使の首都駐在問題は、国書を朝鮮国王に奉呈したことを機に、朝鮮政府が日本公使の駐京を黙認したため、なしくずしに解決された。 ・漢城西大門外の清水館に日本公使館が開設されたのは、八〇年一二月とされている。 ・要するに、朝鮮政府はアジア朝貢体制下の日朝交隣関係の維持につとめ、その崩壊につながる異質な部分を排除したのである。このため、三〇〇年の歴史をもつ草梁倭館の日本人専住区域への転換は抵抗なく受け入れられた。 ・しかし、あらたに日本側の地代あるいは地租負担を明記することにより、それまでの「客館」としての性格は失われ、日本専管の居留地(租界)になりかわる。居留地では広範な自治権が認められ、それが領事裁判権とむすびついて朝鮮内における日本領土にひとしく機能し、朝鮮の主権を侵害することになるのだが。 ・交渉結果は日本の要求どおりにはいかなかったとはいえ、朝鮮政府の無知につけこんで、開港場における日本貨幣の使用と朝鮮銅貨の輸出入自由、朝鮮沿海測量の自由活動などの条項をしのびこませていた。 第二章 「軍乱」とクーデター 一 不平等条約の成立 日朝不平等条約の定着 ・「日朝修交条規」は、まぎれもなく不平等条約であり、朝鮮を近代的外交関係にひきずりこむ重大な契機となった。 ・「日朝修交条規」は鎖国朝鮮の重い扉をこじあけたとはいえ、朝鮮の巧妙な対応によって形骸化されようとしていた。 ・朝鮮政府が認めたのは、旧来のアジア朝貢体制に決定的な亀裂をもたらさない範囲で「近代」の部分をつつみこむことだった。 ・朝鮮にたいする各國不平等条約が大勢として成立するなかで、その一環として日朝不平等条約が定着する。 アメリカの朝鮮接近 ・一八八〇年(明治一三)五月、アメリカのシュウフェルト提督と李鴻章は朝米通商条約の交渉に入る。 ・李鴻章がシュウフェルトの要請にすぐ応じたのは、すでに朝鮮にたいし開国を勧告する政策をとっていたからである。 ・それは、朝鮮と東三省(中国東北部の奉天省・吉林省・黒竜江省)をうかがうロシアの南下政策と朝鮮への勢力拡大を企てる日本の侵略政策に対抗するため、欧米諸国をひきいれてロ日勢力を牽制しよう、という意図にもくづく。 ・朝鮮の危急はすなわち清国の危急ととらえる、自国本位の戦略である。 ・日本は一八七九年、沖縄県設置(琉球処分)を強行し、清国を刺激していた。日清両属の歴史を有する琉球の日本への併合は、中華的アジア伝統世界の崩壊につながる。 ・清国政府は李鴻章に、朝鮮政府にたいして開国するよう説得することを命じた。 ・「敵を以て敵を制する」、この李鴻章戦略の手のひらで、東アジアをめぐる列国の対立と同盟の組み合わせの歴史が展開することになる。そのるつぼのなかで朝鮮は従属の苦しみを受けなければならなかった。 朝鮮開国論の形成 ・一八八〇年八月、二回目の修信使が来日した。修信使とは修好条規第二款により、朝鮮が日本に派遣する使節である。 ・このときの修信使は礼曹参議 ・東京滞在中に彼は、駐日清国公使 ・何如璋が金弘集に贈った「朝鮮策略」の要点は、ロシアの侵略を防ぐため、朝鮮が “中国と親しみ、日本とむすび、アメリカとつらなり、以て自強を図る” ことを説いたものである。 【私見 : この時点でも朝鮮政府の主体性は全くなく、宗主国とは言いながら中国に蹂躙されるがままの状態になっている】 ・つまり李鴻章の方針が、対ロシア政策を増幅させながら、駐日公使館をへて朝鮮に伝えられることになったのである。 ・ついに朝鮮政府は開国の方針をえらび、八一年三月、李鴻章にそれを伝えた。 ・これにより李鴻章は、朝鮮政府にかわって対米条約交渉をおこなうことになる。だが、これはそれまでたびたび表明してきた「属国自主」の原則をくつがえしたのではない。「自主」のたてまえを保ちつつ、実質的に介入にふみだしたのである。 アメリカとの修好通商条約締結 ・八二年五月、「朝米修好通商条約」は仁川で調印される。 不平等条約体制の成立 ・八三年一一月に調印された「朝英修好通商条約」(京城条約)は、前年調印の条約とうってかわて、低い関税率、朝鮮全土への内地通商権など、不平等条項をふんだんに盛り込んだものだった。 ・朝鮮政府は日本と「日朝修交条規続約」等を結んでいたから、パークスらの要求を拒否することはできなかったのだろう。 ・パークスが「イギリスの東アジア諸国とむすぶ条約のモデル」と誇称したとおり、新条約はアジア不平等条約の決定版だった。 ・以後、各国との修好通商条約がこれにならう。ロシア(一八八四年)、イタリア(一八八四年)、そしてフランス(一八八六年)とつづいた。アメリカと日本も、最恵国待遇により、朝英・朝独条約が朝鮮からえた貿易上の特権にあずかったのはもちろんである。ここに朝鮮をめぐる列国の不平等条約体制が成立した。 二 壬午軍乱――清国の影響力が強まる 朝鮮の内部葛藤 ・開国の衝撃をうけた清朝宗属関係のあり方をめぐって、朝鮮宮廷・政府官僚は大揺れに揺れ、あい対立する派閥を生んでいた。 ・第一は、清朝宗属関係の維持に重きをおき、事大(大国に ・第二は、すでに崩壊の危機にさらされている清朝宗属関係に依存するのでなく、これを打破し、みずからも近代国家形成をはからねばならない、とする急進開化派である。 ・第三は、二者併存のもとでみずからの近代化を求めようとする親清開化派である。 軍乱と大院君の政権復帰 ・一八八二年(明治一五、壬午の年)七月二三日、漢城で兵士・市民の抗日暴動がおきた。 ・ことのおこりは、兵士にたいする給米の不正支給である。 ・この暴動を失脚中の大院君が利用し、閔氏政権の転覆を企て、日本公使館襲撃を教唆扇動する。 ・国王 日本政府の対応 ・政府はとりあえず事実経過の調査、謝罪・賠償要求と、居留民保護のため軍艦派遣を決定した。 ・朝鮮政府との交渉を命ぜられた花房公使にあたえられた訓令は、 (1)朝鮮政府の公式謝罪 (2)被害者遺族への扶助料支給 (3)犯人および責任者処罰 (4)損害賠償 (5)朝鮮軍による公使館警備 (6)朝鮮政府に重大な責任ある場合は (7)朝鮮政府が誠意を示さないばあいは仁川を占領し後命を待つこと などである。 ・そして、陸軍は熊本鎮台の一個大隊派遣、海軍は軍艦四隻、輸送船二、三隻の派遣をきめた。 ・迅速な対応をはかったのは、清国の干渉をおそれたためである。 ・外務卿代理吉田清成は、再三、「自主の国」朝鮮と日本との問題は条約にもとづき解決する、として介入を謝絶したが、清国側は、 “朝鮮は清国の属国であるから、清国が処理にあたるのは当然” として日本側の要請をはねつけた。 馬建忠の干渉 ・一八八二年(明治一五、壬午の年)八月二十六日、大院君拉致事件がおこる。大院君排斥・国王復権の基本方針は、北洋大臣代理の ・ "清国皇帝が冊封した朝鮮国王をしりぞけて政権をとるのは、国王をあざむき皇帝を軽んずるもので、その罪は許されない" というのが拉致の理由である。 ・高宗・閔氏政権が復活した。 済物浦条約と修交条規続約 ・復権した高宗・閔氏政権は、外交面ではまったく馬建忠に依存せざるをえなかった。 ・交渉結果はふたつの条約にまとめられ、三〇日に調印される。 ・ひとつは、壬午軍乱の善後処置としての「済物浦条約」、もう一つは、「日朝修交条規」の追加条項としての同条規続約である。 清国宗主権の強化 ・「大満足」の成果は、日本政府が嫌ったはずの清国の介入によりもたらされた。結果的には清朝宗属関係の頑強な存在をあらためて印象づけることになったのである。 ・清国が軍事力を背景に宗主権強化政策を採用したのである。もともと宗属関係は藩属国の内治外交に干渉しない原則であったから、強化というより権力的再編といったほうがよい。変質である。 ・清国にすがって国を守ろうとする閔氏政権の親清政策もこれをうながした。 ・ 「水陸貿易章程」の調印 ・一八八二年一〇月四日、「中国朝鮮商民水陸貿易章程」が調印された。 ・清朝間にむすばれた近代的形式をふんだ最初の条約である。 ・章程の「属邦優待」とは、清国が朝鮮貿易上の特権を排他的に独占することを意味する。 ・章程は、宗属関係をたてに、清国の朝鮮貿易独占、内地通商支配を基礎づけるものであった。 ・それは、もはや理念的な伝統的宗属関係とは異質のものである。清朝宗属関係の特殊性の強調とはうらはらに、内容は近代的支配隷属関係への質的移行を示していた。 第三章 日清戦争前夜 一 東学と甲午農民戦争 東学とは何か ・ ・基本教理の「人 ・民族的・民衆的性格をもつ東学が忠清道・全羅道・慶尚道地方に広がると、政府は社会不安を醸成する邪教とみなし、六四年崔済愚を処刑してきびしい弾圧をくわえた。 ・東学教団の幹部たちは、弾圧に抗しながら、教組の ・彼らの要求はもはや「教組伸冤」をこえて、日本や西洋諸国勢力の侵入を拝し大義達成をとなえる「斥倭洋倡義」(日本・西洋を斥け、義を唱える)を掲げ、他方では貪欲で暴虐な地方官吏の粛正を求めていた。 全璋準の蜂起 ・この農民戦争を、当時は、反国家的秘密結社である東学教団が指導した反乱という意味で「東学党の乱」とよんだが、最近では日清戦争下の第二次蜂起をふくめ、甲午農民戦争という。 執綱所コンミューン ・李王家本貫の地である全州を農民軍に制圧された政府は、袁世凱に清国軍の「借兵」を要請する。 ・政治的・軍事的・社会的権力として農村コンミューンを形成した農民軍は、政府中央・地方権力と対立を深めざるをえない。このような国家機構の分裂・二重化は、権力の移行過程にあらわれる権力の二重化である。 ・深刻な危機におちいった政府は反革命的な弾圧にのりだし、外国軍隊を誘いこんでいく。 二 日清戦争への道 日清両国が出兵 ・農民軍の全州占領にあわてた朝鮮政府は一八九四年(明治二七)六月一日、袁世凱に非公式に清国軍の出動を要請、三日には公式に出兵を要請した。 ・清国出兵のしらせは、同時出兵の機をうかがっていた日本政府に迅速な対応をうながした。駐日清国公使からの正式出兵通告があったのは七日である。 ・そして出兵通告を受けた七日には、日本政府も八五年の「天津条約」第三款の「行文知照(事前通告)」の規定にもとづいて、清国政府に出兵を通告した。 ・しかし、一一日には「全州和議」が成立し、日清両軍は朝鮮出兵の理由を失っていた。「天津条約」には変乱などが解決したら、ただちに兵を「撤回」し、ふたたび「留防せず」という規定がある。 ・大鳥公使と袁世凱のあいだで一二日から始められた共同撤兵交渉では、一五日の時点で日本軍の四分の三、清国軍五分の四は即時撤兵、民乱静穏化ののち全部撤兵で意見が一致した。だが、日本政府は駐兵と兵員増派計画をかえようとしなかった。 駐兵の口実づくり ・閣議は、朝鮮駐兵の口実づくりに腐心し、農民軍の日清両軍による鎮圧と朝鮮内政の日清共同改革を清国に申し入れる案をこねあげた。 ・清国に提案した共同改革案は、朝鮮の内政干渉になるという理由で清国から拒否された。 ・そのうえ朝鮮政府およびロシア・イギリスをはじめとする各国公使から日清同時撤兵の要求あるいは勧告が出され、清国側は撤兵に応ずる意向を示していた。しかし、日本側はこれを拒否、またしても同時撤兵の機は失われる。 ・このとき日清両国の撤兵が実現していたら、日清戦争はおこらなかったはずである。だが、賽は投げられた。 【私見 : ホンマやろか? 「たられば」は史実とは異なる。一個人の見解に過ぎない】 ・大量出兵した以上、無成果のまま撤兵することは国内世論の点からもできなかった。 【私見 : 日中戦争が泥沼化していった原因も、軍の暴走だけではなく、その軍の後押しをしたメディアと国民世論が背景にあった! 曰く、「今まで血を流した英霊に申し訳が立たない」「イケイケドンドン」】 ・大鳥は七月三日、外務督弁に改革要領を提示したのについで、一〇日には内政改革案を朝鮮政府にわたした。 ・十六日、朝鮮政府は日本側提示の改革案にたいし、日本軍の撤退が実施の前提であると回答した。 王宮占領事件 ・二二日を回答期限とした日本側公文による要求(清国軍の撤退、清朝宗属関係を反映する清朝間諸条約の廃棄など)にたいし、朝鮮政府が回答を渋るとみるや、軍事行動にうつった。王宮の ・この王宮占領事件は、参謀本部の公式戦史などでは、先に発砲した王宮守備兵との偶発的衝突から日本軍が応戦、王宮に進入した、とされている。 ・しかし、実態があきらかにされつつある。すなわち、あらかじめ計画された筋書きどおりに、景福宮に侵入、国王を ・この事件は、八月二〇日調印の「暫定合同条款」で「両国兵員 ・が、平時、外国軍隊が王宮に侵入し、国王を捕えるということは、空前の暴挙というほかない。 ・そのうえ清国から送還されて蟄居中の大院君をかつぎだし、日本軍制圧下の景福宮で国王と会見させ、大院君をまたまた執政に任じて政務を統括させることにした。閔氏政権の追放をはかったのである(甲午政変)。 日清戦争はじまる ・周到な計画のもとに実行された王宮占領は、開戦の ・豊島沖海戦中、「浪速」艦長東郷平八郎大佐は、清国艦に護衛されイギリス国旗を掲げ、清国将兵一〇〇〇人を乗せた輸送船「高陞」が降伏を拒否したため、「浪速」はこれを撃沈した。 ・「浪速」は救命ボートで船長ら四人の西洋人を救助したが、清国兵を見捨て、銃撃をくわえて現場を去った。国際法違反の疑いがある「高陞」撃沈はイギリスの世論を刺激した。 ・大鳥公使は属邦条項をふくむ清朝条約は「貴国自主独立の権利を侵害」するとして、廃棄すべきことを朝鮮政府に強要していた。 ・八月一日、天皇は宣戦の詔勅を ・戦争遂行の名分としての朝鮮の「独立自主」扶助は、日清戦争の全段階でくり返し叫ばれる。ただしそれは親日独立であって、反日独立であってはならないのである。 【私見 : 日本側から見れば当然のことであり、このことで朝鮮と対立したのだろう】 日本側に立つことを強要 ・対清宣戦布告から十二日後の八月十三日、陸奥外相は大鳥公使に訓令し、朝鮮が清国に宣戦布告するか、さもなければ宣戦にかわるべき日本との同盟を公表するよう、朝鮮政府と交渉することを命じた。 ・陸奥は戦争が日清間の交戦にとどまり、朝鮮が「中立国の如き有様」となれば、「第一には他各国の干渉を招く恐あり、第二には日本政府が大兵を同国内に派遣するの名義なく、遂に他の非難を受くるの ・八月二〇日には「暫定合同条款」が、そして二六日には「大日本大朝鮮両国盟約」がむすばれた。これにより朝鮮は日本側に立つことを義務づけられ、親清行動はもちろん、第三国への調停要請もできなくなった。 ・侵略の事実を覆い隠すかのように、条款の前文には、「朝鮮国の自由独立を 【私見 : 侵略を前提と決めつけているが、裏にそういう狙いがあったとしても条約の公文が事実としては正の解釈になるのではないか】 ・盟約の第二条では「日本国は清国に対し攻守の戦争に任じ、朝鮮国は日兵の進退及び其糧食準備の為め、及ぶ ・朝鮮を日本の同盟国に擬して、国際的批判の目をそらさせようという狙いである。 ・攻守同盟により日本軍は朝鮮で思いのままの人馬・糧食の挑発をおこない、朝鮮民衆の反発をかった。 第二次農民戦争 ・日清開戦による日本の朝鮮侵略に憤激した農民軍は、ふたたび決起した。 ・農民軍は南下した朝鮮政府軍・日本軍と交戦したが、近代的兵器による集中射撃と包囲戦で敗退せざるをえなかった。 ・農民軍が蜂起した各地では、政府軍・日本軍による大量殺戮がおこなわれ、財産が没収され、家屋が焼かれた。 ・こうして甲午農民戦争は鎮圧され、農民革命の灯は消された。 三 日清講和条約と王妃殺害事件 大勢が決する ・一八九四年(明治二十七)九月十六日の ・平壌占領の翌十七日には、連合艦隊が清国北洋艦隊に勝利して(黄海海戦)、朝鮮から清国軍を駆逐するとともに黄海の制海権をほぼ掌中に収めた。 ・そしてあらたに編成された第二軍(司令官大山巌大将)は、遼東半島占領(十一月二一日旅順占領)についで、翌九五年一月には山東半島威海衛作戦に転じ、二月一二日北洋艦隊を降伏させる。 ・勢いに乗る日本は清国の講和申し入れを拒絶、講和条件を有利に導くため南進を開始して 講和条約の調印 ・「日清講和条約」(下関講和条約)が調印されたのは四月一七日である。その第一条にいう。 【清国は朝鮮国の完全無欠なる独立自主の国たることを確認す。 ・日本が開戦の理由とした清朝宗属関係の廃棄を明文化し、「独立自主の国」朝鮮の保障を宣言したのである。 ・思えば、日清戦争とは朝鮮支配をめぐる日本と清国の争いであった。 ・そして、その勝者日本が帝国主義へ転化し、敗者清国と戦争の犠牲となった朝鮮が反植民地に転落した。 ・講和条約にいう朝鮮の「独立自主」とは、清国の影響を排除したことの宣言であり、日本が朝鮮を支配することの宣言であった。 閔氏派のまきかえし ・「日清講和条約」が締結されたときの内閣は、第二次金弘集内閣(九四年十二月成立)である。 ・井上馨は急進開化派を中軸にすえるとともに、改革資金として一三万円、さらに三〇〇万円という巨額の借款をあたえ、改革の促進をはかった。 ・しかし、日清講和条約締結直後におきた三国干渉の衝撃のなかで、井上の構想は頓挫する。 ・「日清講和条約」は、遼東半島・澎湖島・台湾の割譲、賠償金二億両の支払い、清国における通商上の特権付与などをふくんでいたが、批准書が交換されるまえに、ロシア・フランス・ドイツが遼東半島を返還するよう勧告し、日本はそれを受け入れざるをえなかった。 ・日本はあらためて、清国にまさる強大国ロシアの圧力が頭上にのしかかるのを自覚しなければならなかったのである。井上の改革構想が崩れるなか、第二次金弘集内閣は崩壊した。 ・八月に成立した第三次金弘集内閣では、日本の干渉に反発していた支配層である閔氏派が権力奪還をこころみ、ロシアの後援をえて開化派の抑制に成功した。 三浦梧楼の陰謀 ・井上公使にかわって駐朝公使になったのは三浦 ・着任は一八九五年九月一日。彼が親露米派を排除するため、国王高宗の妃(閔氏)の殺害計画を練ったのは、それからまもなくである。 ・一〇月八日未明、景福宮を占拠する。 ・壮士の一群は王妃を求めて探しまわり、常殿で王妃を斬殺し、領事館警部の指示で遺体を松林にはこび、焼きすてた。 事件はどう処理されたか ・三浦公使は、事件は解散命令をうけた訓練隊が大院君と結託しておこなったクーデターであるとし、事件そのものは日本人には無関係である、という筋書きでおしとおそうとした。 ・事実の隠蔽工作が破産してもなお、大院君の要請で参加した、と強弁した。 ・国際的に苦境に立たされた日本政府は、帰国した軍人八人を第五師団の軍法会議に、四八人を広島地裁の予審に付した。 ・被告のひとり杉村濬元書記官は、予審の陳述で、朝鮮内政改革は「尋常の手段」では不可能であることは日本政府も知っており、軍事クーデター計画は政府により「黙認せられたることと推測」して実行した、という。 ・たびたびの暴挙で道義心を失った、朝鮮通の外交官杉村に罪障感はない。 ・三浦にも日本国民にも罪責の意識が欠けていた。 四 開化派のたどった運命 復活した開化派 ・王妃殺害事件のあと、大幅な内閣改造がおこなわれ、第四次金弘集内閣が成立した。 ・だが、朝鮮の人びとはこの内閣を信用しなかった。 ・乙未事変の処理にあたって、日本側の責任を追及しなかった。 甲午改革をめぐって ・わずか一年半ほどの間に四たび組織された金弘集内閣のもとに参加した開化派の人びとは、それぞれの理由から海外で近代的事物を見聞した知識人である。 ・彼らは祖国の近代国家への転換をみずからの課題とした。自己利益のために親日家だったのではない。 ・親日的であったとすれば、心ならずも強制されたか、朝鮮独立と近代化のために必要な日本の勢力を利用しようとしただけである。 ・しかし、開化派政権の成立そのものが自前の政治的力量によるものではなく、日本の軍事力による閔氏の政治的権力の制御を前提にしていた。生まれながらに親日の母斑をつけた、反民族的な政権を民衆は支持しなかった。 ・一八九四年一二月に廃止されるまでに二〇八件の改革項目を議決、翌年にかけて実施した改革をふくめて甲午改革とよぶ。 ・甲午改革の主なもの 〔政治〕 宮中と府中との分離、清朝宗属関係の廃止、近代的内閣制度の導入と官庁機構改正、科挙制度(科挙試験による官吏任用)の廃止、教学としての儒教の排除、軍隊・警察制度の改革、郵便制度の確立、地方制度改革。 〔財政・経済〕 財政の度支衙門への一元化、予算制度の採用、幣制改革、租税金納化、度量衡の統一。 〔司法〕 司法権の確立、近代的裁判制度の導入、縁坐法の廃止。 〔教育〕 近代的学校制度の導入、実業教育の重視、外国語学校の設立、留学生の海外派遣。 〔社会〕 封建的身分制度の廃止、太陽暦の採用、女子の再婚自由、早婚禁止、断髪令。 ・これらのなかには農民軍が求めた幣制改革を吸収、反映させたものもみられ、封建社会を制度的に否定する近代的な改革内容にあふれていた。そのような意味で画期的な「上からの」ブルジョア革命を志向していた、ということができる。 ・しかし、政府と民衆とのよじれた関係のもとでは、改革は民衆の支持をとりつけることができなかった。その理由のひとつは、開化派政権成立の自主的基盤の欠如であり、もうひとつは、日本軍の朝鮮軍事占領下で改革がおこなわれたことである。 【私見 : 結果として近代化を実現しようとしたことについては、時の政府や日本への評価がどうあれ、事実として認識してよいのではないだろうか】 ・何よりも王妃殺害事件に関して、政府が日本の責任を不問に付そうとする屈辱的な姿勢である以上、怒りと憎悪の対象となるのは当然であった。 開化派が一掃される ・「母国 ・ロシア人カルネイェフ大佐とハイロフ中尉は、断髪令が「彼らの伝統的な神聖観を侵したのみならず、朝鮮人の外観を、彼らが軽蔑して止まない僧侶にも似させる結果となり、日本人にたいする歴史的な敵意は、民衆をして次のように考えることを余儀なくさせていた。即ち、日本人は ・義兵闘争が高揚する九六年二月一一日、親露派は、ロシア軍艦の将兵の助力をえてクーデターを強行、金弘集政権を倒して、国王をロシア公使館に移した。「俄(露)館 ・こうして開化派は一掃され、改革は流産した。 【私見 : 結局、近代化政策を進めようとした開化派を、親露派がつぶすという自滅の方向へ進んでしまった】 五 大韓帝国の成立と中立化構想の挫折 初期義兵の展開 ・開化派政権による改革の進行に ・王妃殺害のしらせがまず、彼らに決起をうながす。乙未事変直後から儒者たちの反日 【私見 : この一派は人数にして朝鮮人全体の何パーセントだったのだろうか。主流派だったのだろうか】 ・一八九六年の義兵闘争は、初期義兵とよばれる。日本の侵略にたいする反対と侵略者に追従する金弘集政権にたいする糾弾を掲げた義兵の先頭に立ったのは、「衛生斥邪」の思想的伝統を守る儒者たちだった。 ・九六年二月政変で政権を握った親露派を背景に、国王は断髪令中止、金弘集らの国賊断罪の詔勅を出して撤兵を命じたが、親露派政権に満足しなかった義兵は、その後も闘争を広げた。 独立教会のナショナリズム運動 ・そのような政治的空白期に登場したのが独立教会の自主独立・自由民権・自強改革を掲げた運動である。 ・独立教会は、ナショナリズムを鼓吹したが、やがて大衆討議を通じて認識された現実の政治のあり方について発言する政治団体へと成長した。 ・政治的にも財政的にも弱体な政府は、当時、ロシアや日本に多くの利権を供与していたが、独立教会はこれに反対し、日露の干渉侵略政策に対抗した。 ・独立教会の急進化をおそれる守旧派は、独立教会の政治目標が共和制樹立にあると皇帝に ・皇帝は、独立教会と万民共同会を強制解散させた。 ・独立教会を弾圧した政府は、民衆がめざした民権の伸長と国権の強化を受容し、民衆のエネルギーを汲みとって外圧に対する民族的防壁を築く最後の機会を失ったのである。 【私見 : 一連の流れを見て共通するのは、朝鮮政府の弱体的側面が出て国の方向を定められず、日本と関係なく自壊していくパターンに見える】 大韓帝国の成立 ・これより先、ロシア公使館に「播遷」していた国王高宗は、一八九七年二月、年号を ・独立教会などの市民的改革路線を切り捨てて政権を担当した守旧派は、九九年八月、憲法にあたる「大韓帝国国制」を制定した。 ・国制は、大韓帝国が五〇〇年の歴史をふんだ専制君主国であることを明示し、絶対主義君主支配の国家統治体制の基本法である。三権分立や国民の市民的諸権利の保障はなかった。 光武改革の内容 ・清朝宗属関係を廃棄した韓国が国際状況に対応していくためには、強大な専制権力を国内的に確立する必要があった。それは旧来の封建王朝体制の反動的再編ではなく、近代国家体制への転換でなければならない。 ・大韓帝国成立から日露戦争、そして「第二次日韓協約」締結までの数年間に支配層によっておこなわれた近代的改革を光武改革という。 ・植民地支配をはかる外国にたいし、鉱山と鉄道に関する利権を譲渡しないことを宣言した。 ・また、日清戦争期に日本の円銀の朝鮮国内自由流通を容認して以来、侵害されていた通貨主権の奪還をめざし、一八九八年二月に刻印付円銀の通用禁止令、一九〇一年に韓国政府の貨幣製造発行権を明記した「貨幣条例」を公布した。 ・しかし、鉱山・鉄道利権は日本・ロシア・イギリス・アメリカ・ドイツ・フランスの資本につぎつぎに奪われたし、通貨主権奪還もできず、かえって日本の第一銀行による銀行券発行でますます後退することを避けられなかった。 中立化構想をめぐる動き ・大韓帝国の外交方針は、東アジアに集中した帝国主義列国相互の対立、牽制を利用しながら侵略をおさえ、「自強」によって独立維持を追及することだった。 【私見 : これは無理。よほど国力、政治力がないといいようにされる。結局朝鮮半島はそうなった】 ・そのころイギリスが韓国の永世中立国化を提唱した。 ・それ以前にも、日本・清国・アメリカ・イギリス・ドイツの五ヵ国が共同で朝鮮の独立・中立を担保しよう、という井上 ・それらはいずれも提唱国の利害関係からロシアの朝鮮侵略を抑止するとか、清国の朝鮮独占支配を牽制するとかの意図にもとづいて考えられた国際政治的道具にすぎなかった。 ・韓国の主体的な中立化構想を軸とした外交戦略が胎動する。 ・一九〇〇年八月頃、ロシアがこの韓国の中立化構想に便乗した。 ・一九〇一年一月七日、日露は列国の共同保障による韓国の永世中立国化計画について提議した。 ・韓国にたいする独占的支配を構想する日本側は、韓国中立化を不利とみてロシア提案を拒否した。 満韓交換論の登場 ・三国干渉によって日本に遼東半島を放棄させたロシアは、不凍港獲得と南満州鉄道建設構想の実現にむかう。 ・南下を阻止しようとするイギリスの妨害にあいながらも、ロシアは一八九八年までに、東清鉄道建設と、南満州支線の敷設権を獲得し、旅順港と大連湾を二五年間租借した。 ・朝鮮政府とも秘密協約をむすび、朝鮮支配の意図をのぞかせた。 ・その勢いを脅威と感じながらも政治的後退を余儀なくされていた日本は、朝鮮をめぐる日露間の利害調整に応じなければならなかった。 ・守勢にあった日本が巻き返しをはかるべく案出されたのが満韓交換論である。 ・つまりロシアの満州支配とひきかえに日本の朝鮮支配を認めさせる提案である。ロシア側はこれを拒否した。 ・結局、一九〇二年一月三〇日「日英同盟協約」が調印され、対露交渉はうちきられる。 日露協商 ・しかし、一九〇三年におこなわれた対露交渉も実は満韓交換論の延長線上にあった。 ・閣議は、「日露両国は互に其韓国又は満州に於て現に保有する正当の利益を認め、之が保護上必要の措置を執り得ること」を骨格とする、小村外相提出の「日露協商案要領」を決定した。 ・韓国あるいは清国領土である満州の内政について日露両国が協定すること自体不当であるが、韓国には一片の通告すらない。 ・ロシアの対案は、日本の満州進出拒否、韓国の独立尊重と領土の軍事的使用禁止、北緯三九度以北の中立地帯化などで、日本側提案とは大きなへだたりがあった。 ・侵略者同士の話し合いが決裂したとき、日露戦争がはじまる。 局外中立宣言の試み ・日露の緊張がたかまるなかで、一九〇三年八月、韓国政府も戦時局外中立論の方針をとりたい外交策を開始した。諸国の承認をうるためである。 ・韓国政府の中立声明にたいしイギリス・フランス・ドイツ・イタリア・デンマーク・清が承認を与えた。 ・日本政府は、中立を承認しなかった。 ・中立国が国際的に認知されれば、交戦国はその国の中立を尊重しなければならない。同時に中立国は交戦国にたいし不偏不党であらねばならない。 ・中立国が有する領土主権にもとづく権利には、領土・領水内における作戦行動の禁止、交戦国軍隊の通過禁止、交戦国の港湾使用禁止、交戦国の自国内への避難防止などがふくまれる。したがって韓国が中立国となることは、対露戦を準備中の日本にとって作戦計画のすべてを失うことを意味した。 ・韓国の局外中立声明を黙殺した日本は、日本軍の韓国駐屯と韓国の協力を規定する「日韓議定書」を強制調印する。韓国は中立国としての不偏不党義務を放棄させられた。 【私見 : 強制調印とはどういう意味なのか? 不満があったとしても結果調印したら成立するのが条約ではないのか。】 ・中立国が中立を維持できる条件は、他国による領土侵犯を排除しうる防衛力をみずからもつか、中立を保障した担保国が中立国を援助し、中立侵害を許さないか、にかかる。 ・韓国の局外中立を承認したヨーロッパ諸国は、日露開戦にともなう日本の韓国中立侵犯を黙認した。ロシアだけが日本を非難したが。 ・中立を宣言した清国にたいしても日露両国は、その領土である満州を主戦場とするのである。 第四章 日露戦争下の韓国侵略 一 日韓議定書の締結 日韓秘密協定締結工作 ・韓国の局外中立は何としても阻止しなければならない、と小村外相は考えた。対ロシア戦の陸軍作戦は、朝鮮半島南部に上陸、北上して北部挑戦でロシア軍と戦う、とされていたからである。 保護国化方針の登場 ・日本政府が韓国保護国化を政策として掲げたのは、一九〇一年(明治三十四)六月成立の第一次桂太郎内閣の「政綱」が最初であろう。 ・日清戦後も対露戦にそなえて軍拡を続けた政府は、韓国支配を確保することが、ロシアの満州進出にたいする規制弁になると考えはじめた。韓国の中立化は日本の地位、威信の喪失につながる、というのが小村外相の主張だった。 ・小村が駐日ロシア公使ローゼンとのあいだに交渉した、満州におけるロシアの権益承認とひきかえに韓国における日本の優位、すなわち、「満韓交換」案が失敗に帰したとき、日露戦争による軍事的決着が不可避となる。 保護国とは何か ・歴史学のうえでいう保護国は、ある国による他国の政治的保護関係を示す用語として広く使用されている。そのため、宗属関係にある宗主国と藩属国との関係についても用いられるばあいもある。 ・一般に近代帝国主義の保護国支配は、伝統的な宗属関係の否定のうえに成立する。 ・保護国は、ここでは帝国主義国の植民地獲得過程での支配の一手段、すなわち隷属国の統治機能の一部を行使する保護関係を条約により設定する国家関係に限定して用いる。 ・外交用語としての保護関係は、第三国から独立を脅かされる状態にある国家の独立を保障するため、ある特定の国が保護をあたえる関係である。 ・国際法上の用語としてのそれは、保護をあたえる国が被保護国の外交権の一部あるいは全部を奪い、外交機能を代行する関係である。 ・外交権は、国家が国際法上の権利能力、法的人格を有することを示す最大の主権であるから、外交権を失えば、その他の主権を保持していようとも、その国家は国際法上の主体ではなくなる。 ・宗属関係のもとでの藩属国は独立国であるが、近代的保護関係のもとでの隷属国家は独立国とはいえないのは、そのような意味である。 ・保護国化は被保護国の外交権を侵害することによって成立するから独立の否定につながる。 ・一方で独立を保障しながら、他方で独立を否定する保護関係は本来的な矛盾をかかえもっていた。 日露開戦 ・対露宣戦の詔勅が発せられたのは一九〇四年二月一〇日である。 ・旅順では連合艦隊が停泊中のロシア艦隊に奇襲攻撃をかけ、仁川では臨時派遣隊が上陸、漢城へ入り、護衛艦隊は、仁川沖でロシアの軍艦二隻を撃沈した。 ・臨時派遣隊の先遣部隊の漢城入京は、韓国皇帝、政府や漢城駐在の外国外交団にたいして軍事的威圧をくわえ、伝えられていた漢城中立地帯化計画を阻止する目的でおこなわれた。 日韓交渉再開 ・一九〇四年二月一三日から林公使と交渉が再開される。 ・再開といっても継続ではない。 ・日本案は、形式的には相互協力協定だった前案とはことなり、日本が韓国にたいし保護、指導の立場にあることを明文化した。 ・また、前案にはなかった軍事協力条項をあらたに設け、日本軍の不当な軍事占領を合法化するとともに、以後の戦略展開にたいする韓国の協力を義務づける項目である。 ・さらに日本政府は、林案第四条に「大日本帝国政府は、前項の目的を達成する為め、軍略上必要の地点を占有することを得べし」をつけくわえ、修正した。 ・韓国皇帝・政府内外の反対のたかまりと外国の干渉をおそれる日本政府は、即時調印を韓国側に求めた。 ・二二日、「日韓議定書」にただちに調印した。 日韓議定書 ・調印に反対した李容翊は、この日の夜、日本軍に拉致され、「遊覧」の名目で日本に移送されて、約一〇ヵ月の軟禁を強いられる。 ・韓国内では反対の声が高まり、漢城の街は騒然とした空気につつまれた。 ・三月一七日、枢密院議長伊藤博文が特派大使として漢城にのりこんだ。 ・伊藤は、「日韓議定書」の履行と、それを妨害するものの排除を強要した。 ・通達には、韓国兵の反抗があれば敵国とみなすとか、韓国の態度が不鮮明であれば兵力を数倍にするとか、威嚇する言辞がある。 ・天皇への伝言をうながした伊藤にたいし、皇帝は「今や日韓両国の関係は、議定書に由って確定せり。我国の執るべき主義方針も亦之に一致するを要す。朕は我臣僚を率いて此主義の下に日韓提携の実を挙げんことを期す」と、屈辱的なことばを呈さなければならなかった。 二 植民地経営のマスタープラン 対韓施設綱領 ・日本政府は「日韓議定書」を拡張し「保護の実権を確立」するため、一九〇四年五月三十一日閣議決定した方針が、対韓施設綱領である。 〔軍事〕戦争終了後の日本軍の韓国常駐、軍用地収用は、韓国の独立および領土保全を保障した「日韓議定書」第三条による日本の権利である、とする。 〔外交〕韓国政府がおこなう外国との条約締結などの重要案件の処理を日本政府の事前承認制とし、そのために外交業務と外国人への特権譲与業務を外部衙門に集中し、そこに日本公使が監督する外国人顧問官を入れ、外交政務の実権を掌握する。 〔財政〕日本人顧問官を入れ、徴税法や幣制改革、財政再建をおこない、財務の実権を掌握する。 〔交通〕主として軍事的観点から建設中の京釜鉄道と京義鉄道の完成をはじめ、鉄道敷設権を獲得する。 〔通信〕韓国政府から日本政府に郵便電信、電話事業の管理を委託させ、日本の通信事業との合同をはかる。 〔産業〕韓国内の日本人の土地所有権、用地建、豆満江・鴨緑江沿岸の森林伐採権、鉱山採掘権、全道の漁業権朱徳などによる産業開発をおこなう。 ・韓国の独立保障とはうらはらに、韓国の主権を完全に無視したこの植民地化計画は、順次実行にうつされていく。 【私見 : ヨーロッパ諸国のアフリカ、アジアの植民地政策(資源の搾取、奴隷市場化)と比べて、日本が採った併合政策は全く内容が異なる。又、朝鮮半島はロシアの南下政策に対処するための橋頭堡であり、朝鮮半島は植民地対象ではなかったと思う】 ・開戦からまだ半年とたたない七月、小村外相ははやくも戦後処理の方針を進言した。彼は、戦争に勝利したとしてもロシアから賠償金を獲得できないことを想定し、満韓および沿海州方面での利権拡張に主眼をおき、後日、清国分割に有利に参加しうる態勢をつくるべきだ、と述べたうえで、韓国については「事実上に於て我主権範囲」とし、「保護の実権を確立し、益々我利権の発達を計る」ことを主張した。 ・「文明を平和に求め、列国と友誼を 【私見 : 仮面とは? 日露戦争の大義は方針の通りではなかったかと思う。手段の善悪は後付けの評論にすぎない。】 韓国駐剳軍への改編 ・開戦時、漢城付近に集結していた第一軍主力は北進を開始し、一九〇四年三月下旬には、鴨緑江左岸に達した。兵力四万。対岸はロシアの大軍が待ちうける満州である。 ・鴨緑江渡河作戦は五月一日に決行された。 ・日本軍主力は主戦場の満州に踏みこみ、国境を越えた。 ・韓国内の日本軍は、「日韓議定書」第四条にもとづき戦時占領軍として増強された。 ・一九〇四年三月一〇日、韓国駐箚隊から韓国駐箚軍へ改編された。 ・国内五六ヵ所に分遣所をおいた。韓国駐箚軍が対露戦兵力としてだけでなく、韓国内民衆の弾圧装置であったことを示している。 ・しかも、日本軍は日露戦後も二個師団程度の韓国常駐を計画、韓国駐箚軍の諸部隊の帰還といれかわりに第一三・一五師団が進駐し、一九〇六年八月には常置部隊となった。一九〇七年度からは常駐軍のための永久兵舎の建設も開始される。 抵抗と弾圧 ・韓国民にとっての日露戦争は、ロシア軍とのたたかいではなく、日本軍とのたたかいであった。鉄道用地・軍用地の強制収用をはじめ、人馬・食糧徴発が民衆に植民地化の危機を実感させた。 【私見 : 韓国人から見たらこう感じざるを得ないだろう。歴史的に朝鮮半島はロシアの南下政策の砦になってきた。日本は、朝鮮半島の安定化が絶対条件で、そのため韓国の自立、独立を願ってきたが、結局朝鮮半島は主体性を発揮できないまま中国、ロシア、アメリカに振り回されてしまった。日本は自国を守るために朝鮮半島へ出て行かざるを得なかったと考える。】 ・反日蜂起に手を焼いた駐箚軍司令官は、一九〇四年七月二日軍律を公布した。軍律とは占領軍が公布する一般住民に対する取り締まり令である。 ・咸鏡道については、反日活動や軍事妨害を封ずるため、一九〇四年一〇月八日、占領地内に軍政を施行した。 ・韓国軍歩兵大隊を解散させた。 ・また一九〇五年一月、駐箚軍司令官は漢城とその付近の治安警察権を韓国警察から奪い、言論・出版・結社・集会を統制して反日世論を封じた。 ・日本軍の横暴な軍事制圧のまえに、韓国政府はなすすべがなかった。 保護国実質化がすすむ ・「日韓議定書」締結にあたり、具体的な個別事項の交渉にてまどって調印を遅らせるよりも、第一条で韓国にたいする日本の指導的立場を示し、さりげなく挿入した第六条の「 ・第六条は堤を崩すありの穴であった。 ・軍事的制圧のもとで、さきの「対韓施設綱領」に示された侵略計画は日本の思いどおりに実現されて行く。 ・一九〇四年五月十八日には、韓国皇帝の「韓露条約廃棄勅宣書」により、それまで両国間にむすばれていたすべての条約の廃棄と、森林伐採特許権の無効宣言がおこなわれた。 ・韓国内政への介入もいちじるしく進行した。 軍事警察制施行(七月)、韓国在外公館廃止要求(十二月)、一九〇五年になると、貨幣条例公布、韓国軍隊の整理縮小(四月)などである。 第一次日韓協約をめぐって ・韓国植民地化が着々と進行するなかで、外交上の画期をなすのが、一九〇四年(明治三七)八月二十二日調印とされる「第一次日韓協約」である。 三 列強の合意をとりつける 「惨憺たる勝利」 ・一九〇四年、日本軍を迎えうつロシア軍と対決したのが八月下旬からはじまる遼陽海戦である。日本軍は激戦のすえ、クロポトキンの率いるロシア軍を九月三日、遼陽から退却させることに成功した。 ・第三軍(乃木希典大将)の旅順要塞攻撃も、一九〇五年一月一日に終わった。 ・日本軍二五万、ロシア軍三二万。二〇世紀に入って世界最大規模の奉天会戦は三月一日に開始され、九~一〇日のロシア軍総退却で決着した。 ・奉天会戦の日本軍死傷者約七万、ロシア軍死傷者約九万、俘虜二万二〇〇〇という。 韓国保護権確立方針の決定 ・一九〇五年(明治三八)四月八日の閣議で決定し、一〇日に天皇が裁可した「韓国保護権確立の件」は、戦後の韓国支配のあり方として保護国とすることを具体的に示した方針書である。 ・外交権の奪取を第一にあげ、「此際一歩を進めて韓国に対する保護権を確立し、該国の対外関係を挙げて我の掌裡に収めざるべからず」とした。 ・ここでいう保護権の設定は、国家間のあいまいな保護関係ではなく、近代的保護関係として韓国の外交権を全面的に日本が奪いとることである。つまり韓国の国際法上の独立を否定することを意味する。 ・しかしそれは、諸外国の承認がなければならない。 ・その「適等の時期」こそ日露戦争勝利のときである。 日英同盟協約の改定 ・「韓国保護権確立の件」を決定した同じ日の閣議は、「日英同盟協約」の継続と改定の方針を決定し、その交渉を開始することとした。 ・日英同盟は、極東におけるロシアの進出に対抗して日英両国の利益確保のため、一八九八年(明治三一)以降、対露強硬・日英提携の方針を固めた小村外相が推進した協定である。 ・日露戦争は、日本の侵略主義を隠蔽するために、ロシアを侵略者に仕立て、日本は韓国の独立と領土保全のために戦う、と戦争目的を正当化したが、もはやこのたてまえの論理は、韓国保護国化の方針を決定した日本政府には邪魔にこそなれ、必要ではなくなった。 【私見 : この史観は初めて聞いた。隠蔽とは? ロシアは侵略者ではないのか? たてまえだったのかどうか? 】 ・一九〇五年八月十二日調印の「第二回日英同盟協約」は、イギリスのインド領有と国境防衛措置を日本が承認することとひきかえに、日本の韓国支配をイギリスが承認するとともに、両国の軍事「攻守同盟」関係を明確にした。 ポーツマス条約 ・日露講和交渉は一九〇五年八月一〇日からアメリカのポーツマスでひらかれた。 ・九月五日調印の「日露講和条約」第二条には、日本の韓国支配が明記された。 ・前段では「日英同盟協約」と同じく、「指導、保護及監理」という文言を用いて日本の韓国支配を定義づけ、それにたいしてロシアは妨害、干渉しないことを約した。後段では、あたかも日本が韓国の主権者であるかのように、韓国領土内のロシア国民の地位を規定し、ここでも重大な韓国主権を侵害した。 アメリカの了承 ・日露講和交渉開始直前の一九〇五年七月二九日、「桂 = タフト協定」をむすんだ。それは、アメリカのフィリピン統治と日本の韓国にたいする保護権設定を相互に認め合う内容だった。 ・イギリス・アメリカ・ロシアの承認をとりつけた政府は、他国もこれにならうとみた。 ・ロシアのツケを韓国に転嫁することによって日露戦争に決着をつけ、平和を回復することを帝国主義列強も望むものとよんだ。 ・日本政府にとって、日韓保護条約の締結は、この機をおいてほかにないのである。 第五章 保護国化をめぐる葛藤 一 外交権を奪う――第二次日韓協約 第二次日韓協約の内容 ・「第二次日韓協約」は、韓国側の要求の一部をいれて終生、確定された。 第六章 韓国併合への道 一 保護か併合か――伊藤博文の「改宗」 併合論の台頭 ・ハーグ密使事件を契機として、新聞・雑誌も事件を好機ととらえ、対韓強硬措置を説く論説や伊藤統監の軟弱な懐柔政策の責任を問う意見であふれた。 ・西園寺首相は、韓国へ派遣した林 伊藤の保護国論 ・しかし、伊藤統監は強硬論に耳をかたむけず、合併論をしりぞけた。伊藤は統治の実権を掌握しながらも、韓国閣僚に日本人を送りこむようなことはせず、 ・伊藤は統監就任以来、しばしば韓国の「独立富強」を口にした。保護の名における韓国内外政の主権侵奪と韓国の独立とが矛盾なくむすびついているのは、韓国は自力では独立することはできないので、日本が韓国に保護をあたえ独立させている、という思い上った考えによる。 【私見 : 思い上った考えとは思わない。日清戦争以降の国際情勢とロシアの動き等を踏まえると、朝鮮半島が自立していないと間違いなくやられてしまうだろう。日本は生命線を守るのに必死だった。朝鮮半島は何としてもしっかりして貰わなければならない。日本が口出ししてでもやらないと韓国は自力では何もできなかった】 ・韓国の独立をおびやかし主権を蚕食しているのが、ほかならぬ日本であることの自覚をもたない伊藤は、「独立富強」の名分をふりかざすことによって限りなく侵略をしつづけた。したがって名分を捨てる併合は避けたいのである。伊藤はそのような保護国論者だった。 【私見 : 同上】 統監政治への批判 ・伊藤の甘い見通しを裏切って義兵闘争はますます激化する一方で、日本人のあいだからその保護国経営を「韓国本位」と論評する声があがった。 一進会の動向 ・韓国で併合推進を唱える一進会も伊藤にゆさぶりをかけた。 ・伊藤は一進会との絶縁を決意した。たとえ「親日」にせよ「韓日合邦」を高唱する一進会は保護国経営の妨害になる。 伊藤の統監辞任 ・保護国経営をめざした統監政治が思わぬ障害に遭遇して、伊藤は韓国統治にたいする意欲を喪失した。 ・最大の理由は、弾圧をかさねても、かえってそれによって鍛えられるかのように成長する義兵闘争の高揚であった。 二 併合の条件づくりがすすむ 一進会の合邦運動 ・一進会が求めた合邦とは、日本との対等合併ないしは連邦形式の連合国家であり、日本政府が意図する併合の内容形式とは天と地ほどのへだたりがあった。 ・ ・曽禰は、一進会に演説・集会を禁じ、さらに一進会と大韓協会の日本人顧問に諭旨退去を命じて両派の活動を弾圧した。併合反対であれ賛成であれ、併合を既定方針とした日本政府にとって、議論が沸騰すること自体が障害と映ったのである。 ロシアの併合承認 ・韓国併合直前の一九一〇年七月四日に調印された「第二回日露協約」は、アメリカの満州進出に対抗して「第一回日露協約」の内容を強化し、日露両国の地位確保のために締結された条約である。 ・交渉にさきだって、併合問題を打診したところ、 “時機はともかく、日本の韓国併合についてロシアが反対する理由も権利もない” という回答を引き出すことに成功した。 ・満蒙地域における利権の拡大を狙うロシアもまた、日本との宥和でより有利な立場に立つことを欲していた。 ・韓国併合承認の対価としてロシアの清国侵略に日本の協力を期待した。日露両国は韓国、清国を材料に取引したのである。 イギリスの併合同意 ・イギリス政府は併合に反対ではないが、韓国とむすんだ条約によってえていた既得権を併合後の日本がどのように保障するかに関心をもっていた。その最大関心は関税問題である。 ・関税自主権を欠く韓国の対欧米条約が併合により消滅し、日本なみの関税率が適用されれば、日英同盟の友好関係維持にも悪影響をおよぼすだろう、というのである。 ・日本政府閣議は、はやばやと関税は「当分の内現行の 寺内正毅の統監就任 ・国称は「朝鮮」と決定した。 ・朝鮮は古い呼称で、「朝日が鮮明なところ」に由来するといわれ、一部の人が誤解しているような蔑称ではない。いずれにしても、併合後になお一国が存続しているような印象を残す「韓国」だけは避けなければならなかった。 三 「韓国併合条約」の論理 韓国併合に関する条約 ・一九一〇年(明治四十三)、「韓国併合条約」は『官報』号外で公示され、同時に天皇の詔勅と併合にともなう諸勅令が公布された。 併合の世論 ・韓国併合にたいして日本人のなかに反対や異論の声はあがらなかった。 ・いくらかなりと韓国植民地化を批判していた社会主義者もまた、併合を既成事実として是認する論説を掲げた。 ・たとえば片山 歴史家と日朝関係史 ・新聞・雑誌にもまして国民に大きな影響をあたえたのは、国民教育を通じての朝鮮蔑視観と朝鮮民族抹殺日朝一体化論の注入である。その先頭に立ったのが歴史学者だった。 ・日本の朝鮮植民地政策の理念である「同化主義」を歴史的に裏打ちする日韓「同種」論に立つ 【私見 : この類の説には全く同意しない。そもそも、国内でどの程度の割合で存在した意見なのだろうか?】 ・このような民族史観にもとづく併合の正当化は、喜田にかぎらず多くの歴史家に共通した。 ・一九二〇~二一年発行の第三期国定歴史教科書『尋常小学国史』上下(文部省)においても、日本と朝鮮との関係項目は、「 ・韓国併合は韓国の「国利民福」のため、韓国側の申し出でおこなわれたことだけが強調されている。 ・支配民族である日本人と被支配民族である朝鮮人との民族的矛盾の存在を観念的に否定した同化主義植民地政策は、支配と収奪を朝鮮にたいする日本の恩恵におきかえた。 ・今日求められている日朝国交正常化問題にしても、補償問題にしても、戦後処理の正しい解決をするためには、正しい歴史認識をもたなければならない。いいかえれば、誤った歴史認識からは誤った回答しかえられないのである。 ・消し去ることのできない過去の「清算」は難しい。しかし、それができるとすれば、まず、日本と朝鮮との関係史を直視し、正しい歴史認識にもとづいた意識の「清算」から始めねばならない、と切に思う。 【私見 : 氏の言われる「正しい歴史認識」とは何か。歴史には史実しかないと思うが、韓国の言う正しい歴史認識は政治的に見て正しいかどうかということで、史実に基づかない議論が多い。故に、どちら側から見た政治的歴史認識かで、見解が全く異なる。少なくとも韓国の言う正しい歴史認識という言い方は正しくない。】 【私見 : 「侵略」と「併合」は異なる。】 【私見 : 条約を締結してから、「これは朝鮮の意思ではない」から無効だというのか。反対派は完全に抹殺されたが、当時は日本と手を組んで近代化を進めようとしていた意見もあったのではないか。】 あとがき ・「植民地」支配そのものが正当性・道義性を欠いていた。 【私見 : 正当性・道義性で歴史を評価するのはおかしい。政治的出来事の結果として併合という事実があったということだけではないのか。】 ・日本が謝罪を求められているのは個々の不法行為にたいしてではなく、朝鮮民族をまるごと支配した愚劣な行為にたいしてであり、問われているのは日本人のモラルの再生状況なのである。 【私見 : 政治的所産をモラルで捉えるようとする意見は賛成しかねる。】 ・わたしたちが歴史的事実として自明のことのように思ってきた日本の朝鮮「植民地」支配は、その成立に合法的根拠がなく、不法・不当な強占(軍事占領)が一九四五年の解放までつづいたのだ、と彼らは主張する。 ・しかし、韓国併合は形式的適法性を有していた。つまり国際法上合法であり、日本の朝鮮支配は国際的に承認された植民地である。 ・だが、合法であることは、日本の韓国併合や植民地支配が正当であることをいささかも意味しない。 【私見 : 併合の事実を正当性で評価する考えには賛成できない。】 ・わたしたちにとって考えるべき問題の本質は、併合にいたる過程の合法性如何ではなく、隣国にたいする日本と日本人の道義性の問題ではないか、と思う。 【私見 : 道義性で歴史をみるのはいかがなものか。いささか感情的過ぎるきらいがする。当時の国際情勢、自国の置かれている立場等々、クールに見る必要がある】 |