
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年03月07日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
1 |
17/01 |
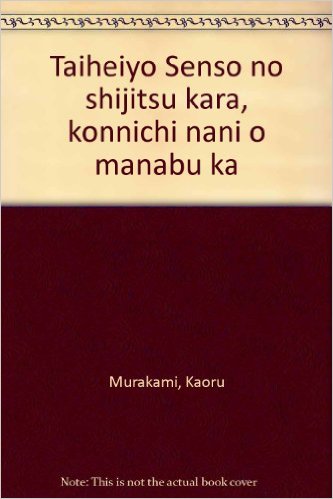 |
太平洋戦争の史実から何を学ぶのか |
村上 薫 |
実業之日本社 |
◎ |
リーダーシップ ビルマ作戦にみる二つの軍団 証言 特攻隊生き残りとして考えた 指導者の「責任」 河野洋平事務所 石川達男 “神がかり的愛国心”には反対 ・敗れたとはいえ、太平洋戦争で当時の若者たちが特攻隊で戦ったことは、民族の不滅の歴史の中に、永遠に語り継がれていくと思います。またそうしなければなりません。 ・国を守る気概を持つということは、教育上大事なことだと思います。しかし戦前のように若者を死に追いやることを強制する「神がかり的愛国心」には絶対反対です。上から押しつけるのではなく、若者たちが自分自身で考えて祖国防衛に立ち上がる。アメリカやイギリスやフィンランドでは皆そうやっている。 ・戦争をするかしないかをきめるのは政治だ。 ・戦前の政治家が軍部や右翼の圧力に押され、満州事変から支那事変、そして、ついに太平洋戦争へと追い詰められていった歴史を振り返ると、政治家の責任がいかに重大なものであるかがよくわかります。 ・あの悲惨な戦争体験の上に立って、日本は二度と戦争をやってはいけない。そういう政治をやるんだということを絶対の基本にしていきたい。 ・ただ、戦争にならないようにするということは、国の誇りと固い面まで傷つけて、相手の言うことに屈従するのとは、おのずからわけが違います。そういうことにならないようリードしていく政治が必要です。そのためには歴史をもう一度振り返って、よく整理すべきだと思います。 日本型人事 ノモンハン敗退を招いたエリート偏重主義 ソ連軍の輸送力を見誤る ・第二十三師団付少佐参謀 扇 廣 氏は、ノモンハン事件について証言した。 ・第六団司令部は、全滅の危機にある第二十三師団を撤退させなければいけないと、皆考えていた。しかし軍司令官も師団長も参謀も、誰もそれを口に出す勇気がなかった。これはその背景に『絶対敵に後ろを見せてはならない』という日本陸軍独特の神がかり的伝統精神が存在していたからである。 ・この信念はノモンハンだけでなく、太平洋戦争の全期間を通じて生き続け、銃剣による破れかぶれの "バンザイ攻撃" となって表れている。 上級は責任回避、下には厳しい処罰 ・当時の陸軍人事の風潮は、本当に処罰すべき人を処罰しないで、下の者ばかりやっていた。大物や参謀などエリート階級には手をつけず、温情主義で臨んでいた。こうした点こそが、まさに日本陸軍の最大の欠点だった。 ・積極論者が過失を犯した場合、人事当局は大目に見た。処罰しても、その多くは申し訳的だった。一方、自重論者は卑きょう者扱いにされ勝ちで、その上もし過失を犯せば手厳しく責任を追及される場合がすくなくなかった。このような陸軍人事行政は、つぎつぎに平地に波瀾をまきおこしていく猪突性を助長していった。 陸軍上層部は兵隊を軽視した ・あれだけ決定的な敗北をこうむりながら、陸軍はその後それを教訓に生かせなかったのは、日露戦争で大国ロシアに勝った、これは精神主義のおかげだ。今回ノモンハンで負けたが、これはたまたま運が悪かったんだ。従来とってきた精神教育は決して間違ってはいなかった。こう考えたのではないか。 ・たとえばソ連の戦車に対し火焔ビンで立ち向かう、地雷を抱えて飛び込む。まさに神がかり的、独善的なものだ。 ・ノモンハン後、陸軍の一部に表面化しようとした合理主義的改革の動きをいっさい許そうとしなかった。 時代の変化 ミッドウェー失敗と大企業病の共通点 短期決戦主義者だった山本長官 ・ミッドウェー敗戦の原因は、情報軽視と慢心が重なり合ってもたらされたものである。しかし太平洋戦争で日本海軍が敗れた最大の原因は、戦艦に替わって空母が新しい時代の戦いの主役になりつつあったにもかかわらず、それを見抜けなかった海軍指導部の保守的体質にあったといってよい。 もう一時間早く敵を発見していたら ・ミッドウェー作戦が完敗に終わったのは、日本海軍の暗号が完全に米側に漏れていたからです。ミッドウェー海戦の時、米海軍はわれわれの動向を全部事前に察知していた。それに対し、日本側は米側の動きについて何も知らず、ミッドウェー近海には敵空母はいないはず――と最後まで信じて疑わなかった。 "兵力集中" 無視の作戦構想 ・ミッドウェー敗戦の最大の原因は、 "兵力集中" を欠いた作戦構想にあった。 ・連合艦隊の主要部隊は、この作戦において二つの作戦目的を与えられていた。一つはミッドウェー占領、もう一つは敵機動部隊を誘い出し、これを撃滅することです。 ・敵がよほど弱兵でないかぎり、一つの作戦に二つの大きな目的を同時に与えることは、失敗を招く原因となる。 ・それからもう一つ、なぜあの時ミッドウェー作戦と並行してアリューシャン作戦を実施したか。これも兵力の集中使用の原則に反する。 ・ハワイ攻撃の時のような徹底した兵力集中はそこに見られないし、旧来の戦艦至上主義の考え方を捨て切れなかった陣型です。 証言 日本の国民性から見た 貿易摩擦問題 神戸製鋼会長 元通産省事務次官 小松勇五郎 日本人は早めに手を打つことが不得手 ・総対的に言ってわが国では、政治家も、関係各省もとらえ方が甘すぎるし、したがって早めに手を打つことが不得手です。 景気対策にしても、地震対策にしても、日本の場合は実際に不況が深刻になる、あるいは地震が起こってからでないと動かない。私はそれが日本人の国民性のような気がします。 ・日本人は本土決戦を本気でやるつもりだった。これは欧米人の常識では考えられないことです。 ・もしあの時、本土決戦をやっていたら、今日の日本はなかったでしょう。ソ連は必ず北海道を取っていたはずだ。本土決戦を思いとどまらせたのは原爆投下です。 ・私は広島県出身で、原爆でずいぶん親せきの人達も死にましたが、個人的感情を離れて言えば、原爆投下についてはこれが日本を永久破滅から救ったと考えています。 【私見 : 原爆が日本を救ったとの意見には与しない。きっかにはなったかもしれないが、終戦対策は原爆投下以前から検討されていたし、広島、長崎の一般市民が他の日本人の犠牲になって日本が助かったという考え方は余りにも自虐的であり、加害者はあくまでも戦争当事国のアメリカでなければならないと思う。】 ・明治の政治家と軍人は軍事力は政治の “手段” であって “主体” でないことを明確に認識していたし、外国語を習ったこともないにもかかわらず、日露戦争の時の日英同盟締結に示されるように、外交的判断も非常によかった。 ・これは明治の祖先達が国際的に孤立化しては大変だと、外国のことを一生懸命に謙虚に学んだおかげである。 ・ところが日露戦争に勝ってからの日本は次第に慢心し、昭和に入ってからは、軍事力についての傲りと過信から日本を誤った大陸政策に駆り立て、ついに世界中を相手とする無謀な戦争へと突入させてしまった。 ・天皇を神格化し、神州不滅、八紘一宇、一億玉砕など精神主義を振りかざし、それに反対する者は国賊として片っぱしから弾圧した。 ・日本人は個性的な欧米人と違って、このように言葉、ムード、錦の御旗に弱い。戦後も経済競争で強くなるにつれ、自分たちはジャパン・アズ・ナンバーワンと傲り出した。これまた日本人の国民性の欠陥です。 ・心が傲っている国民は、なんでも自己中心的に考えがちで、他国に対する配慮を欠きがちです。太平洋戦争以前の日本がまさしくそうだった。が、こんなことをしていると必ず相手からごつんとやられます。今、米議会を中心に起こっている厳しい “日本たたき” はその象徴です。 選択眼不在 情報戦で敗れた太平洋戦争 唯一の成功例を除いて完敗 ・「すぐれた情報の価値は、十二個師団の兵力に相当する」――かつて日露戦争の時、明石元二郎大佐が語った有名な言葉である。 ・しかし太平洋戦争では、情報は極めて軽視されていた。 ・たとえば同じ参謀でも、情報参謀は常に作戦参謀の下位にランクされていた。 ・太平洋戦争中の日本軍は、情報をあまり重要視せず、精神力至上主義、もっぱら戦闘による勝利のみを追求してきた。 ・太平洋戦争中の日本を振り返ってみると、情報面では完敗に近かったといってよい。 ・成功した唯一例は、緒戦の真珠湾攻撃に必要な事前情報を、完璧に近いほど収集したことだけだった。 ・注目されるのは、暗号が解読されていることを戦争が終わるまで誰も気がついていなかったことである。 ・絶対に解読されていないと信じ込んでいた海軍のD暗号が解読され、山本司令長官の搭乗機が狙い撃ちされたことも、日米開戦の直前、日本の外交暗号がすでに解読され、野村吉三郎大使がハル国務長官に真珠湾攻撃の最後通牒を手渡した時、相手側は先刻それを知っていたことも、戦後初めて知ったくらいである。 ・戦力差で圧倒的に優勢だった南雲機動部隊がミッドウェー海戦で敗れたのも、米側は日本側の行動をことごとくキャッチしていたのに対し、日本側は「敵空母はいないはず」とかたくなに信じ込み、形式的な索敵を行ったからである。 ・第二次、第三次ソロモン海戦以後、日本海軍得意の夜戦が封じ込められ、せっかくの航空攻撃の戦果がほとんどあがらなかったのは、このころから米軍に配備されたレーダーが大きな威力を発揮し始めたからである。 ・四十キロ以上離れた敵を発見し、夜間でも霧、雨に関係なく、レーダーに連動して射撃する米軍と、むやみやたらに特効出撃する日本軍とでは、誰の目にも勝敗は明らかだった。 握りつぶされた「日米開戦不可なり」の小野寺電 ・昭和十六(一九四一)年十二月八日、日本が無謀な太平洋戦争に突入したのは、当時の日本の政治、軍事指導者が国際情勢に対する判断を誤ったからである。 ・彼らの判断とは何か。ひと口でいってそれはドイツの戦力を過信し、ずるずると戦争に引きずり込まれていったことである。 ・日本の指導者たちは、ドイツの国力を過大評価し、昭和十五(一九四〇)年九月二十七日、ついに日独伊三国同盟に調印した。 ・ルーズベルトにとって、ヒトラーに率いられたドイツは、 “悪魔” であり、そのドイツと同盟を結んだことで日本は “悪魔の片われ” になってしまった。 ・かてて加えて日本はもう一つ重大な外交的ミスをやってしまった。それは昭和十六年七月の南部仏印進駐である。それに対してアメリカは石油の全面禁輸で報復を加えた。 ・日米開戦の約半年前の六月二十二日、ドイツ軍は突如国境線を突破し、ソ連領に攻め入った。 ・小野寺信駐在武官は、開戦までの二カ月間、日米開戦反対の電報を東京の参謀本部あてに打ち続けた。 ・独ソ戦戦でドイツ軍戦力に ・「日本はドイツの優勢を信じ切って、開戦に踏み切ろうとしている」――そう読みとった小野寺は、懸命に開戦反対の意見具申を東京へ送り続けた。電報の数は合計三十何通に達した。 ・小野寺が掲げた反対の理由――それは「独ソ戦においてドイツはやがて敗れる。日本がドイツの戦力を当てにして、英米と戦うことは危険である」――というものだ。 ・だが、それを信じる者はいなかった。独ソ戦が始まった当初、ドイツ軍は素晴らしい早さでソ連内部へ快進撃していたし、ヒトラーは「三ヵ月でソ連を打倒できる」と言明していた。 ・当時、ベルリンにいた大島浩駐独大使はもとより陸海軍駐在武官全員がドイツ軍当局の発表を鵜呑みにし、ドイツ軍優勢を信じ込み、その旨、東京に打電し続けていたからである。 ・しかしヒトラーは、ことソ連攻撃作戦に関してだけは、その機密を保持するため、同盟国の日本にすら、「ドイツ軍はむしろ英本土上陸をねらっている」と “情報操作” したのである。 ・そんなことは露知らぬ大島大使は独ソ開戦二ヵ月前の昭和十六年四月、英本土上陸作戦を信じ切った電報を打っていたのである。 ・しかし小野寺武官の予言はみごとに的中する。十二月八日の日米開戦のその日、ドイツ軍はモスクワから猛吹雪の中、退却を開始した。 ・小野寺武官がスウェーデン公使館付駐在武官として赴任したのは、昭和十五年十月だったが、極めて信頼度の高い優秀な情報機関づくりに成功していたので、ドイツやソ連の動きに関して、絶対の確信を持っていた。 ・情勢判断をする場合、あらかじめ先入観を持つことはぜさったいタブーである。ところがベルリン駐在の大島大使以下、武官たちは頭からドイツの勝利を確信し、その他の否定情報を一歳受けつけようとしなかった。 ・独ソ戦におけるドイツ軍の劣勢は、ドイツ当局の発表には少しも表れないので、大島大使等はその時点においても「モスクワの命運はもはや尽きたといってよい。ドイツ軍は計画どおり厳冬期前にソ連軍に殲滅的打撃を与えるだろう」という超楽観的な電報を東京あて打っている。 ヤルタ密約まで打電したが、中央は無視 ・それに先立つ昭和十六年四月、松岡洋右外相がベルリンを訪問した。 ・松岡はこの後、モスクワへ向かい、ソ連と日ソ中立条約を結ぶつもりだった。 ・日独伊三国同盟成立以来、これにソ連を加えた四国同盟に発展させたい――そう松岡は考えていた。 ・もし四国同盟ができれば当面の主敵、英米を牽制することができる。現に独ソは不可侵条約を結んでいる。ドイツ空軍はロンドン大空襲でイギリスを悩ましている。ドイツはまもなく英本土に上陸作戦を開始する。そうなればアジアにおけるイギリスの防衛力は手薄になる。その時、日本は石油資源豊かな東南アジアに南進すればよい――これが当時、開戦派の政治家、軍人たちが考えていた戦略判断だった。 ・したがって、このころ中央の参謀本部の最大関心事は、「いつドイツ軍が英本土に上陸するのか」だけだった。六月、ドイツ軍がソ連に攻め込むなど誰も夢想だにしていなかった。 ・ところがその中で、ストックホルムの小野寺武官だけが「ドイツは英本土上陸の意図なし。むしろソ連に向かって開戦準備中」の意見具申を打電していたのである。 ・松岡外相がベルリン滞在中、同地で在欧陸軍武官会議が開かれ、今後のドイツ軍の行動について分析が行われた。全員が英本土上陸を主張する中で、独り小野寺だけがソ連に向かうと確信のほどを主張したが、誰からも相手にされなかった。 ・小野寺武官は英米の宣伝に惑わされているとまで言う者もあった。 ・ドイツ側はソ連進攻計画の最高機密については、同盟国の日本の松岡外相にも明かそうとしなかった。 ・しかし、独ソ間の仲が最近険悪であり、ソ連からの攻撃に備え百五十個師団を配置しているとほのめかした。これは同盟国日本に対するせめてもの好意だった。しかし、ドイツ軍の英本土上陸作戦の情報ばかり聞かされていた松岡の耳には、貴重なヒントも入り込む余地がなかった。 ・四月十三日、日ソ中立条約調印。駅頭まで松岡外相を送ったスターリン首相は、「これで日本は安心して南進できる」と言ったという。 ・ところがその二ヵ月後の六月二十二日、独ソ開戦となったので、松岡らは強いショックを受けた。 ・それにもかかわらず、日本が開戦に踏み切ったのは、開戦直前の十月、ベルリンから送られた「ドイツ軍は計画どおり厳冬期前にソ連に殲滅的打撃を与えるだろう」という大島駐独大使の電報を信じ続けていたからである。 ・小野寺情報を無視し続けた結果、日本はついに日ソ中立条約という取り返しのつかない条約を結んでしまうことになる。これが当時の日本の政・軍指導者たちに日米開戦を決意させ、また終戦前、この条約を信じてソ連に停戦の仲介を頼んだため、日本の運命がどれほど大きく狂わされたかを考えれば、当時の大島駐独大使や駐在武官、それに中央で彼らと直結していた人々の責任は、万死に値する。 ・日本が終戦決意をするうえで決定的に重要だったヤルタの密約(ドイツ降伏後三ヵ月でソ連は対日参戦する)に関する情報も小野寺武官は握っていた。 ・周知のようにヤルタ会談は昭和二十年二月初め、ソ連のクリミアで米英ソ三国首脳が会談、対独戦後処理、ソ連の対日参戦などを決定したものである。 ・そんなことは露知らぬ重光外相らはソ連に米英との和平の仲介を依頼する。 ・その打診のため、二月二十二日クレムリンを訪れた佐藤尚武中ソ大使に対し、愛想よく迎えたモロトフ外相は、「ヤルタ会談の内容はコミュニケに発表されたとおりで、日本に関しては少しも話題にのぼりませんでした。ソ連の対日方針には何の変更もない」と空とぼけてみせた。 ・ほっとした佐藤大使は、いまがチャンスだと考え、期限切れが迫っている日ソ中立条約を持ち出した。モロトフは機嫌よく「中立条約の存続については多忙のためまだ研究していないので、追って話をしたい」と語った。 ・小野寺機関は、ヤルタ会談の期間中、スターリンがチャーチル英首相よりも、ルーズベルト米大統領と頻繁に会っていたこと、ドイツ降伏後三カ月以内に対日参戦の密約を交わしていたこと等をことごとくキャッチした。もちろんこれはすべて暗号電報で送ったが、これもまた無視されてしまった。 ・ストックホルムから打電された一連の重要情報は、中央の参謀本部の誰かによって、故意に握り潰されていたわけである。 ・戦局は日を追って逼迫し、六月に入るとストックホルムの新聞紙上に、日本がソ連に和平の仲介を依頼していると大見出しで報ぜられた。東京からそれについて一言も言ってこなかったが、小野寺武官はすぐに参謀総長あてに電報を打った。 ・内容は「モスクワを仲介として和平工作を行うのは危険。もしその必要があるなら、あらゆる場合に応ずる路線を用意するから、それを利用されたい」というものだった。 ・すでに小野寺武官はいざという時に備え、国王の甥、プリンス・カール等を通じ、終戦への道を求めて活動していた。それに対し偏見を抱いた岡本公使らが、中央に中傷電報を打ち妨害工作を行った。 ・その間、七月二十六日にポツダム宣言が出され、八月六日広島に原爆投下、八日ソ連の対日宣戦、個々のか長崎へ原爆投下と事態は急転した。 ・東京から十日付で参謀総長からの電報が到着した。内容は、初めて小野寺武官の終戦工作を認知したものだった。 NHKが海外取材で信ぴょう性を裏付け ・ドイツの外務省資料館からは、ゲシュタポ隊長ヒムラーから外務大臣リッペンドロップにあてた手紙が出てきた。その中には「日本の駐スウェーデン武官、小野寺のもとで働くメジャーRは、世界で最も危険なスパイの一人である」と書かれていた。 ・日本にさえ隠したいドイツの内情をすべて小野寺に伝えるこのメジャーRをドイツは憎み、何とか捕らえようとしていたのである。頭文字Rとは誰のことか? ・かつてスパイとして活躍したポーランド人、その名はリビコフスキー、日本武官室ではペーター・イワノフと名乗ったという。 ・小野寺武官の情報源はこのほか、前のラトビア駐在武官時代に親密だったエストニア軍の優秀な将校たちだった。 ・情報活動の重要な要素の一つは、誠実な人間関係に結ばれた仲間と協力者を得ることである。 「戦略情報」具眼の士の不在 ・小野寺武官がストックホルムから送り続けた「ドイツ軍は英本土上陸の意図なし。むしろソ連に向かって開戦準備中」といった情報、さらにヤルタの密約に関する貴重な情報が中央に送られながら、それが無視されたのはかえすがえすも残念なことである。 ・これらの情報を中央がまともに取り上げていれば、日米開戦はあるいは回避されたかもしれないし、原爆が落ちる前の早い段階で終戦に持ち込まれていたかもしれないのである。 ・多くのシベリア抑留者、中国残留孤児の悲劇も生れなかったはずである。 ・その根本原因は、中央に戦略情報を的確に読む具眼の士がいなかったためである。太平洋戦争で日本が敗れた最大の原因の一つに、情報戦があげられるゆえんがここにある。 山本長官戦死――暗号漏れにまったく気づかず ・最前線であることを全く無視した山本長官の詳細な行動予定日程が電報で打たれたのである。細心の注意を欠く宇垣参謀長が発信を命じたといわれている。 ・これでは、ラバウルの連合艦隊司令部内に敵のスパイを務める通信兵がいて、わざとこんなとんでもない電報を打ったと言われても仕方がないくらいだ。 ・海軍の場合、通信士は鉛の錘のついた鎖で暗号帳を体にしばりつけ、官庁と一緒に運命を共にしなければならなかった。 ・日本の潜水艦から発見した暗号帳によって、アメリカは山本長官機の行動計画を全部知り抜いていた。いくつかの海戦を通じ、日本の船がだいぶ沈められたし、捕獲された船もあった。 ・その結果、暗号は当然新しいものに変更されてしかるべきなのに、海軍上層部ではそこまで長期的な展望を持たず、暗号更新の準備が遅れていたのではないか。 ・当時の海軍は大鑑巨砲の威力で敵を全滅させるという考え方を基本にしており、無電や暗号を軽視していた。 真珠湾奇襲――盗まれていた日本の外交暗号 ・十二月六日夜、日本の対米最終回答の暗号電十四部のうち十三部までのマジック情報を詠んだ大統領は、「これは戦争を意味する」と側近のホプキンズに語ったといわれている。翌七日午前十時(ワシントン時間)、日本が同日午後一時に最後通牒を出すことも米側は知っていた。 ・ところがたまたまこの日は日曜日だったためタイピストが休んでいた。書記官が人差し指で懸命にタイプを打ったが書類作成が間に合わず、野村大使がハル国務長官に最後通牒を手渡したのは真珠湾攻撃開始後の午後二時二十分(ハワイ攻撃は午後一時十九分)だった。 ・受け取ったハルは、怒りを込めて野村吉三郎(大使)と 「私の公職生活五十年のあいだ、いまだかつてこのような恥ずべき偽りと歪曲に満たされた文書を見たことがない」 ・日本の空母機動部隊が一時間ほど前に、真珠湾の米艦隊に攻撃を仕掛けてきたと、聞かされたばかりだったからである。 ・ルーズベルト大統領やハル国務長官ら政府首脳は、すでに日本外務省の最後通告文の暗号電報の解読文を読んでいて、その内容も、野村大使らが午後一時に持ってくることも知っていた。 ・しかし彼らはそのことを一切伏せ、米国民に「日本は国際条約を破り、卑劣な騙し討ちを仕掛けた。真珠湾を忘れるな(リメンバー・パールハーバー)と呼びかけた。これを見て「ジャップが騙し討ちした」と米国民はいきり立ち、それまで孤立主義的世論がまだ強く残っていたアメリカは、ここに一挙に対日戦争に踏み切ることとなった。 ・真珠湾攻撃に臨んだ山本五十六連合艦隊司令長官の狙いは、真珠湾を奇襲して米主力艦隊を撃破すれば、米国海軍と米国民は士気を沮喪し、日米戦を断念するだろうというものであったが、この狙いは全く逆効果になってしまったのである。 ・真珠湾奇襲をめぐって、「あれはルーズベルトがあらかじめ知っていたにもかかわらず、ヨーロッパ戦争に介入するため、日本に一発先制攻撃をさせたんだ」という “大統領謀略説” が、今なお米国内で根強くささやかれている。 ・それに対してアメリカは公式に否定(上下院合同調査委員会の結論)、「攻撃は日本軍による一方的な侵略行為だった」と言っている。 ・最後通告の手交が遅れた直接の原因は、野村、来栖大使の監督不行き届き、書記官らの怠慢のためだった。しかし実は、もっと根本的な問題が、日本陸海軍の中にあった。 ・生手寿著『勝負と決断』は、次のように述べている。 ‹開戦四日前の十二月四日、大本営、政府連絡会議で、東郷茂徳外相が最後通告を米政府に渡す必要があると提議した。› ‹永野軍令部総長と杉山元参謀総長は、「開戦劈頭、奇襲によって米国に打撃を与えることが絶対に必要である」として、攻撃開始前に最後通告を米政府に手交することに反対した。› ‹東郷外相は、重ねて「戦争終結の機会をとらえるためには、攻撃に先立って交渉打ち切りの理由を正式に通告しておく必要がある」と強調した。› ‹永野、杉山両氏はやむなくそれに同意した。真珠湾攻撃開始の予定時刻は十二月八日午前三時三十分、ワシントン地方時の七日午後一時三十分である。軍令部と参謀本部は、その一時間前、ワシントン地方時の午後零時三十分に最後通告をしてもらうことに意見が一致し、それを東郷外相に申し入れた。> ‹ところが翌五日、軍令部次長の伊藤整一中将と参謀次長塚田攻中将が、東郷外相を訪ね、手交時間の三十分繰り下げを頼んだ。それに対し、東郷が「攻撃と最後通告との間に十分時間があるか」と質問したのに対し、二人は「十分ある」と答えた。› ‹大規模作戦では実施が二十分前後遅れるのが普通なので、最後通告の時刻を三十分遅らせ、敵に対応準備の余裕を与えないようにしたという。› ‹ところが東郷は、最後通告手交時刻の三十分後に攻撃開始されることは知らされていなかったし、それが真珠湾攻撃だということも全く知らされなかった。そのため外務省、駐米大使館も、それほど緊急なものと思わず、文書作成が遅れたのである。› ‹海軍中枢は、奇襲成功を最優先に考えていたため、最後通告手交時刻を第二義と考え、最後通告が遅れた場合に、米国その他世界各国でどのような事態が発生するかについて考えようともしなかった。› ‹最後通告が遅れないよう万全の処置をとらなかったために、奇襲は成功したが、戦果よりはるかに大きなマイナスを生じさせてしまったのである。› ‹せめて東郷外相には、「三十分後には真珠湾攻撃が開始されますから、最後通告は絶対に遅れないようにしてください」と、打ち明けておくべきであったろう。› 最高機密文書さえ敵の手に ・古賀長官を乗せた一番機は、行方不明となった。 参謀長福留繁中将らの二番機は、ミンダナオ島北方のセブ島沖の海上に不時着し、乗員六人はフィリピン・ゲリラの捕虜となった。 ・飛行機が不時着した時、福留の手提鞄の中には「Z作戦」の詳細な機密書類と暗号書が入っていた。 ・「Z作戦計画」とは三月初め、パラオ港に在泊していた連合艦隊旗艦「武蔵」艦内で作られたもので、「あ号作戦」(昭和十九年六月のマリアナ沖海戦)と「捷一号作戦」(同年十月のフィリピン沖海戦)の原案である。 ・その中には作戦計画を作成した三月十日現在の連合艦隊の実兵力のほか、四月末までにおける兵力増強の詳細、攻撃目標、攻撃方法など作戦指導の腹案が一切含まれていた。もちろん最高機密に指定されていた。 ・したがって、この連合艦隊の死命を制する機密文書が敵方に渡れば、米海軍は赤子の手をねじるように、簡単に日本海軍をノックアウトしてしまうだろう。 ・福留は、「機密書類はフィリピン漁民の手に渡ったが、彼らはそれに関心を持たなかったようだ」と言った。だが、実際には、その夜のうちに極秘書類は米軍の手に渡っていたのである。 機密紛失責任より名誉問題が優先 ・米海軍は福留参謀長遭難時、機密作戦計画書を入手した事実を日本側に悟られまいと、文書のコピーを元のケースに入れてセブ島海域に流すなど、情報戦に細心の気配りを示している。 ・それに対しわが方では、福留参謀長が虜囚のはずかしめを受けたか否かという名誉問題が、機密文書紛失より優先して扱われ、事件直後、暗号の更改、作戦計画変更などの措置が全然とられなかった。 ・のみならず福留さんは六月十五日付で大航空艦隊司令長官に発令されている。 【私見 : 福留の所業は万死に値する! 東京裁判ならばさしずめ米側から褒められるのだろう。マリアナ沖、フィリピン沖海戦で死んでいった多くの兵士は、米軍ではなく日本人に殺されたようなものだ。日本人による日本人の裁判が改めて必要と感じる。】 ・その直後の六月「あ号作戦」(マリアナ沖海戦」を仕掛けた小沢機動艦隊に対し、スプルーアンス提督は日本側の実兵力、攻撃目標の手順などすべて知り尽くしていた。これはミッドウェーの場合と全く同じで、これでは戦う前に日本側の敗北は決まっていたといってよい。 ・海軍中央ではフィリピン・ゲリラの捕虜になっていた福留中将らを四月十七日、大臣官邸に出頭させて事情を聴取したが、福留らは作戦計画書や暗号書についてはひと言も話さなかったし、六人の委員もそれについての究明を少しもしなかった。 ・軍法会議にかけず、臭いものにはフタをしたのは、真相が海軍部内に知れわたれば、上層部の威信が地に堕ちることを恐れたためとみられている。 【私見 : 六人の委員を初めとして、海軍上層部は日本人による戦争裁判にかけるべきだ】 零戦敗退を招いたもの ・昭和十九年六月以降、無敵零戦の王座は米海軍艦上戦闘機グラマンF6F「ヘルキャット」によって奪われることとなる。 ・昭和十七年六月四日、一機の零戦が小さな島に不時着した。 ・アメリカ軍はさっそく同機を本国に持ち帰り、徹底的に弱点を洗い出した。当時、「零戦を撃墜できる戦闘機」開発に躍起になっていた米軍はこの「神からのプレゼント」に感謝した。そして作り上げたのが、ヘルキャットだったのである。 情報氾濫時代の真の選択眼 ・昭和十五年一月から二年半、米国事情の調査のため渡米した実松実氏(後、軍令部第三部第五課長、海軍大佐)は、イタリアの駐在海軍武官から「イギリス海軍が暗夜でも敵の方位と距離を測ることができる電波を利用した秘密兵器を備えている」という話を聞き、英国が持っているなら米海軍は必ず持っているはず――と判断、予算教書その他の公開情報から、アメリカがレーダーと呼ばれる新兵器の整備に躍起になっていることを知り、「早急に対策を立てなければ、帝国海軍伝統の夜戦も無意味になるだろう」との意見を付けて東京に報告した。しかし海軍中央はこの情報を重視しなかった。 ・ガダルカナルで海軍の設営隊はつるはしとシャベルで二ヵ月かかって飛行場をつくったが、それを奪ったアメリカは二日間でそれ以上の飛行場にしてしまった。ブルドーザーの力だった。アメリカはブルドーザーの生産を隠してなんかいない。 ・もし当時の日本に、せめて海軍士官にでも、こうした技術情報とそれを評価する “眼” があったら、ブルドーザーぐらいいくらでも入手できていたはずである。 ・藤原肇氏は共著『情報戦争』の中で、次のように述べている。 ‹日本の情報収集能力はどうか。勝者が情報網を誇っているといっても、それはテレックスとか電話などのネットワークが出来ているというにすぎない。その先端に立っている人たちに本当に問題意識があり、海外のそれぞれのコミュニティーでトップの人たちと交渉し、生きた情報をとっているかというと、甚だ疑問だ。これは大使館でも同様だ。› ・現在は情報氾濫時代といわれているが、その中から真偽を選び出す “眼力” のないことは、太平洋戦争時代とあまり変わっていない。 ・数年前から次第にエスカレートしていた日米経済摩擦は、六十二年春、東芝機械のココム違反事件発覚後、米議会による激しいジャパン・バッシング(日本たたき)が繰り返され、日米関係は戦後最悪の対決状態に立ち至っている。 ・ココム違反事件に関するすべての情報は、米CIAが二年前から衛星を使い、通産省の電話を盗聴していたというから恐ろしい。 証言 日米情報戦争 学徒出身、海軍特信士官奮戦記 元連合艦隊司令部通信諜報班長、海軍大尉、東陽テクニカ社長 野村 日米の圧倒的な意識ギャップ ・太平洋戦争の戦局全般を通じて感じたことは、情報の重要性に対する日米の圧倒的な意識ギャップです。米軍の場合は、艦隊司令長官など上級職から末端に至るまで、 "情報マインド" になっている。 ・ところが日本軍では「通信兵が兵隊ならば、電信柱に花が咲く」と軽んぜられていた。海軍ですら、魚雷や大砲専門の兵科は重視され、尊敬されるが、主計や通信関係は軽んぜられるという風潮がかなりありました。それに反し米軍は、作戦と情報は渾然一体のものとしてとらえられていた。 ・わが日本海軍も開戦直前、情報が重要だということがわかって、予備学生制度を発足させ、語学に堪能な大学高専出身者を集めて対敵通信諜報士官を養成したことは、当時の状況のもとでは画期的な英断だったといってよい。 ・しかし米国に比べて対応があまりにも遅すぎた。太平洋戦争はまさにその情報戦によって、大きく左右されたといってよい。 証言 マスコミが放棄した 真実報道への努力 内外ニュース社長 清宮 龍 ・昭和十六年ころ、すでに新聞は、対米強硬論一色にぬりつぶされ、紙面には「見よ米反日の数々、帝国に確信あり、今ぞ一億国民団結せよ」(十一月三日付朝日新聞』――といった勇ましい見出しが連日のように踊っていた。 【私見 : メディアは今でも、当時は軍の検閲等が厳しく言論の自由が拘束されていたというが、実はメディア自身がイケイケだったのだ! 特に朝日新聞は最右翼だったようだ】 ・マスコミのこうした世論誘導と、軍部の強い圧力の前に "言論の府" たる議会もまた無力と化した。 ・昭和十六年十一月十六日から始まった臨時議会には「国策完遂に関する決議案」が上程され、総額三十八億円という当時としては膨大な臨時軍事費の追加予算はあっという間に成立してしまう。 ・一方新聞は、「一億国民熱火の意気、聖戦完遂に善用せよ」――とますます宣戦気分をあおりたてたのである。 大本営発表の伝達機関へ ・日本の新聞は、はるかにさかのぼって昭和六年の満州事変前後から、軍部の圧力に妥協、屈服し始めていた。 ・世論を誤った方面に誘導し、戦争熱をあおり立てたマスコミの責任は極めて大きいといわねばならない。 ・ジャーナリズムは、ただただ時の勢いに流されるだけで、真実を報道するための努力をいち早く放棄してしまった。 ・国民だけではない。最高指導者である東条英機首相さえも、戦争の実体を正確には把握していなかったようだ。 情勢判断 開戦に引きずり込まれた指導者たちの責任 知米派追い出しの陸軍人事 ・昭和前期・日本は、なぜあの無謀な「十五年戦争」に突入していったのか。 ・最大の原因は、軍人が大きな力を持ち、軍閥化したことがあげられる。軍人は外国のことを知らない。特に陸軍はひどかった。アメリカのこともドイツのことも誤解した。 軍部ファッショを招いた原因 ・昭和前期、軍部ファッショを招いた最大の原因の一つに明治建軍以来の統帥権の独立という制度があげられる。 ・当時の日本の権力構造は、法制的には天皇を主権者とし、政務を総理以下の各国務大臣が輔弼し、軍務を陸海軍の統帥部長(陸軍参謀総長、海軍軍令部長)が輔翼して行うことになっていた。陸海軍の作戦、用兵など統帥権は天皇に直属する。 ・したがってこと作戦、用兵に関しては陸軍大臣、海軍大臣はもちろん、総理大臣のコントロールさえ受けなくてよい――というものである。 昔も今も "四面楚歌" の日本 ・日本人はよく戦術的判断にはすぐれているが、戦略的判断に不得手であるといわれているが、これは今も昔も変わっていない。 ・もう一つは、相手の立場に立って考えず、自分の都合だけで物事を押し通そうとする型の人間が多いということである。そのため戦前も世界から孤立したが、現在も経済摩擦で世界中から四面楚歌の状態に陥っている。その背景には、ややムシがよすぎる日本人のものの考え方に問題があるのではなかろうか。 憲兵使っての迫害の数々 ・東条が今なお日本国民に嫌われている大きな理由は、憲兵を使い、政界、言論界、お膝元の陸軍部内のアラ探しに至るまで、執拗な恐怖政治を布いたことである。 証言 東條内閣の権力政治に抵抗した戦争秘話 懲罰人事で二等兵にされた「勅任官」 東海大学総長 松前重義 歴史を動かす本当の力 ・終戦当時のことを振り返って考えると「あの当時、東条内閣がつぶれていなかったらどんなことになったろうか」とぞっとする。 ・当時アメリカは九州、遠州灘、相模湾、駿河湾などから日本本土に上陸することを考えていたが、アメリカが太平洋岸からの上陸を考えていた裏では、ソ連が主として日本海側から秋田その他に上陸を考えていたのである。 ・つまり東条内閣が無益に抵抗を続けていたら日本は米ソに占領されて、おそらくドイツと同じような分裂国家になっていたであろう。 ・それにつけても私は終戦に踏み切った鈴木貫太郎内閣は英断だったと思わずにはおられない。 ・もう一つ私が痛感するのは皇室の存在の有難さである。 ・日本国民には東条内閣はつぶせなかった。 ・それを押さえて東条を退陣させ、日本を終戦に導き、国民を破滅から救ったのには、やはり陛下というご存在がなくては考えられないことである。 証言 東条退陣にとどめを刺した 岸信介氏の行動 自民党代議士 元官房長官、元農相、元防衛庁長官 赤城宗徳 ・東条首相には「戦術」はあってもアメリカのような「戦略」はない。首相のほかに陸軍大臣、軍需大臣、さらに天皇の統帥権の下で参謀総長も兼任して戦っているが、やっていることといえば、 "一億一心" の精神論で国民を叱咤激励するのみ。 ・それに対しアメリカは緒戦の真珠湾で一敗を喫したが、それ以来 "島伝い戦略" の下で戦力を増強、一つずつ島を占領し、ついにサイパン島までアメリカの手に帰した。 サイパンが陥落した以上、当然、米軍はここにB29の基地を設け、日本本土爆撃を開始するだろう。 ・とすればここで東条独裁政権を退陣させ、人心一新によって危機を乗り切るよりほかにない。そのためここ一番、岸さんに東条内閣退陣のため頑張っていただきたい旨、強く進言した。それに対し岸さんは、われわれの進言をまつまでもなく、当然やらねばならぬことと言明された。 ・岸さんが辞表提出を拒み、これが東条首相を退陣に追い込む契機となった。 ・敗戦後、東条内閣の国務大臣だったということでA級戦犯容疑として巣鴨に収容されていた岸さんが、無罪として釈放されることになったのは、あの時の岸さんの行動が大きな原因あったかと思う。 国家の責任 在満邦人の根こそぎ動員 ・関東軍の戦力は南方や本土決戦に備えた内地への転用で著しく低下していた。そのため満州の四分の三を放棄し、南満に立て籠もって持久戦略をとることが、七月五日、関東軍首脳と大本営の間で決定されていた。 ・しかし満州の大半を放棄するからには、当然のことながら、そこに住む開拓団や都市居留日本人を避難させることを考えなくてはならない。だが、事前にそういう動きを少しでも示そうものなら、敵に企図を察知されるという意見が関東軍参謀部内を支配した。 ・それが今なお批判のマトになっている。「関東軍は民間人を見殺しにした」という非難と、敵中に残された「在満邦人の悲劇」へと発展していったのである。 ・ちなみに敗戦時の混乱の中で、ソ連軍と中国人暴民の襲撃で、在満邦人は十九万人の犠牲者を出している。四十年後の今、中国残留孤児の悲劇が続いているのも、原因はそこにある。 ・が、もちろんそういった関東軍のおえら方が決めたことを一般部隊、まして下級の将校、下士官、兵士たちが知るはずがない。 ・関東軍は大幅に減った欠員補充のため昭和二十年に入ってから、在満邦人の根こそぎ動員を行った。 ・しかし兵員は徴集したものの装備は間に合わず、各部隊に配属された初年兵は竹製の水筒に、三、四人に一丁の帯剣といった状況だった。勃利陸軍病院の近くにある青山堡飛行場には、敵の目をごまかすため模型飛行機が並べられていた。 ・しかしソ連も対独戦で大きな打撃を受けており、満州に侵攻してくるとしてもおそらく来年以降――というのが、関東軍の情勢判断だった。それだけに、八月九日、ソ連軍が日ソ不可侵条約を踏みにじり、侵攻してきた時には、皆、衝撃を受けたものである。 |