
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年02月12日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
11 |
17/01 |
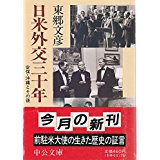 |
日米外交三十年 |
東郷文彦 |
中公新書 |
◎ |
第一章 終戦、憲法、そして安保 一、終戦 ・ポツダム宣言は日本の中の問題とは別のところで作られたものであるが、七月二十六日にそれが公にされるまでには、スターリンから日本の戦争終結に対する意図はトルーマンとチャーチルには伝えられている。 ・それでもポツダム宣言だけでは日本政府は未だ動けない。これを「コメントなしに国内に流す」と云うのが「黙殺」すると云う総理の発言となり、英語で「イグノア」すると訳されて日本は宣言を拒否したと云うこととなり、原爆投下、ソ連参戦と続く。 【私見 : 言葉の壁が誤解を招いたとしたら、もし、日本の意志が正しく伝わっていたら原爆投下はなかったかもしれないし、そもそも原爆投下が終戦を早めたという意見も成り立たなくなる。】 ・戦争終結と云うことが如何にむつかしいことであったかと云うことは、「無条件降伏に非ざる戦争終結」の条件としてのポツダム宣言、原爆投下、ソ連参戦、と重なっても、なお終戦までに一週間の時間と二つの聖断を必要としたと云うことに如実に示されている。 ・ポツダム宣言は、「無条件降伏に非ざる戦争終結」の条件であった。 ・米国による直接軍政を引っ込ませることが出来たのも、無条件降伏ではないからである。ところがこの頃から日本人の間には、折角の有条件降伏をことさらに無条件降伏、無条件降伏と言うようになって行った。 【私見 : 何でやろか? 又、未だに歴史教科書で無条件降伏と教えているのはおかしい。】 三、安保条約 ・日米安全保障条約は、占領下に準備され、米国が占領という地位を平和条約発効後もそのまま維持できるよう、米国によって日本に押し付けられたものであり、内容は一方的片務的であり、日本を米国の世界戦略に組み込み日本をその欲せざる戦争に捲き込むものであると、国内で非難されるようになる。 ・しかしその成立の経緯を見れば、その淵源は、武装を解除され、戦争を抛棄し陸海空軍を持たない日本が、冷戦の世界に如何にしてその安全を図って行くかと云う命題に対する自らの回答に発している。 ・平和条約に関しては国内に全面講和論があり、また安全保障問題については非武装中立論があった。しかしこれらの議論は国民多数の採るところとならず、自由と民主主義に則り、米国との協議を軸として国の安全と再建を図ると云う日本政府の政策が支持されたのであった。 ・いわゆる「西側の一員」と云うことは、その後三十年近く経って漸く一般に云われるようになったが、実は国の行き方としてはこの時既に確立していたのである。 ・いわゆる米国の「押し付け」と云うことについては、新憲法については余り触れられることなく、安保条約についてのみ押し付けであり一方的であると極めつける声が高くなって行った政治の動きと云うものは、誠に不思議なものである。 第二章 安保改訂 四、新条約の交渉 ・集団的自衛権というのは、利害を共にする相手の国が武力攻撃を受けた場合に、自分の国が直接武力攻撃を受けていなくても、相手の国に対する武力攻撃を自分の国に対する危険であると認め、この攻撃を排除するために武力を行使しても違法性を阻却される、という権利である。 七、安保論争 ・安保問題に関する与野党間の論争は、安保体制そのものに関する基本問題と、安保条約の実施上の問題との二つに類別することが出来ると思う。 ・安保体制そのものについては、日本の敗戦後極東に生じた力の空白をアメリカの力によって埋め、アメリカを与国として民主主義と自由経済の体制の下に国の生存と繁栄を図ろうとする立場と、アメリカと手を組んでいてはその世界戦略の一齣に組み込まれ、わが国をその欲せざる戦争に捲き込むものであるとする考え方や、日本を別の体制に持って行こうとする立場との間の対立であり、これは平和条約に関する多数講和と全面講和の対立と同じく、世界観を異にし、共通の土俵のない論争であって、議論はどうしても平行線を辿るしかない性質のものである。 ・他の種類の議論は条約の実施上の問題に関するものであり、これが戦闘作戦行動のための基地使用及び核兵器の持込みに関する事前協議の問題に集約される。 第三章 沖縄返還 日米間の諸問題について(一九六八・五・二〇) ・日米友好関係は固よりそれ自身が目的であるのではなく、個人の尊重と自由民主主義を国是としてその安全と繁栄を図る立場から、日米間の友好関係を最も有利かつ必要とするが故に、これをわが外交の一つの基本政策としているのである。 ・日本の中には、日本政府は米国に遠慮するのあまりいうべきことも満足にいいえないと論ずる者もあるが、このような議論は、当該個人の考えをそのまま政府が米国にいわないが故に日本政府が卑屈であると錯覚するものが多く、むしろ米国側こそ諸般の考慮からいいたいこともいわないこともあるという事実に思いをいたすべきであろう。 ・一般に日本の安全保障という場合、日本の安全に対していかなる脅威ありや、しかしてこの脅威にいかに対処すべきやということが問題となるが、その前に、まず日本はいかなる国是に立ち、今日の世界にいかに国として活きて行くかという問題があるのである。 ・さればこそ、自由民主主義を国是とする立場に立つ安全保障の考え方と、反体制的立場からする安全保障論とが互いに相容れないのは当然であって、単に中共に日本侵攻の意図がないから日本の防衛は必要ないとか、米国のアジアにおける軍事的プレゼンスが極東緊張の原因であるから米国がアジアから手を引けば日本が憲法の文字どおり活きて行ける環境ができるとかの議論は、安全保障問題の前提である基本問題を明らかにしない限り、意味のない議論である。 ・日本の安全保障についての議論は、またとかく四囲の国際環境から遊離した、いわば抽象的な日本の安全という形で論ぜられる傾向がある。戦後の国際環境を顧みるならば、極東もまた世界の権力政治の一つの場であって、一方が退いて力の空白をもたらせば、即時に立ほうが進出してこれを埋めるという事例がいくつか挙げられるであろう。 ・いずれの国といえどもこの世界の権力政治の埒外に立っているものではなく、その一環として自己に最も有利な安全保障の方途を求めざるをえないのである。 ・米国のアジアにおけるプレゼンスは、往々にして「米国の核戦略」とか、「米帝国主義の侵略」と称せられる。それならば、もし米国がアジアからそのプレゼンスを消した場合を想定するならば、朝鮮半島は北朝鮮政権が統一するところとなり、台湾は中共の一州となるであろうし、爾余の中共周辺諸国においても、いわゆる民族解放戦争は思いのままに遂行されるであろう。 ・重要なことは、わが国にとって右いずれの状態をより有利とするかということである。 ・安保体制の功罪は、わが国の利益を図る立場から、わが国の国是と国際環境という以上二つの観点を検討して判断されなければならない。 ・これが基本問題であって、米国の核抑止力とか、極東の安全のための米軍の在日基地使用というような問題は、すべて方法論にすぎない。安保体制をとるかとらないかは、基本的には、自由民主主義に立脚する国是の下に我が国の繁栄を図るか、あるいは日米友好関係のきずなを断って太平洋戦争前のごとく我が国の生存を他の連帯関係に求めるかの選択の問題であって、その間に自己に有利な要素のみを抽出して政策を具現しようとしてもそれは机上の空論の域を出ないのである。 ・よってもし前者を我が国の利益に合致すると認めるならば、それに従って国の政策を指導して行くことが必要であり、方法論上派生する問題の故に事の基本を損なうことがあってはならない。 ・またもし後者がわが国の利益であるというならば、単に安保体制の一方的批判に止まらず、わが国がいかなる国是に立ち、いかなる姿でその安全と繁栄を図ることができるかが、すべての国民の前に明らかにされなければならない。 ・安保体制を前提とする方法論上の問題として米国の核の抑止力という問題がある。 ・核兵器の抑止力という観念は、相手方が攻撃を仕かけようとしても核攻撃の可能性を計算に入れなければならないということから、攻撃を思いとどまらせる力ということであって、相手方の考える攻撃は核攻撃には限らないのである。 ・核兵器は今日の時代において確かに抑止力をその機能とし、現実にこれを行使するという可能性はほとんどないということができようが、問題は、核兵器保有国にとっては、核・非核両兵器が併せて一体としての兵器体系をなしているところにあると思われる。 ・少なくとも米国の立場からすれば、関係諸国に対する極東の安全についての条約上の約束を果たすためには、いかなる攻撃にたいしても必要ならば核兵器を使用して対抗しうる状態にあるということが抑止力たるに必要である、ということは認識してかからなければならない。 ・次に、米軍が安全のためのみならず、極東の安全と平和のために日本にある基地を使用するという問題がある。 ・わが国では、米軍が日本の安全のために基地を使用するのは差支えないが、日本と関係のない極東の安全のために日本の基地を使用し、特に戦闘行動のため発進することは、日本を戦争に捲き込むことになるから許すべきでないという議論がある。 ・この考え方は、米国が一方的に日本を防衛する義務を負うことが当然であるという前提に立っていること、また日本の安全が極東情勢から遊離して観念されていること、の二つの点において合理的ではない。 ・安保条約は一方において米国は日本防衛の義務を負い、他方において米国が極東の平和と安全のために日本の基地を使用することを認めるということで成り立っているものである。 ・もし後者を拒否するなら、対等な二国間の条約として前者のみを存続させるということはできない相談である。 ・外国軍隊の駐留ということも方法論上の問題である。 ・二十余年外国軍隊の駐留が続き、また今後も続くであろうという現在の態勢がそのままでよいかどうかも等閑に付されてよいことではない。 ・もし外国軍隊の駐留を好ましからざるとするならば、その引き揚げを可能ならしめるよう、わが自衛隊を充実して有事に際して必要な軍事施設はすべてその手で平時から確保するような準備が必要である。 ・これらの問題は沖縄返還に関しては最もはっきり現われてくるところである。沖縄返還はこの意味においては米国が決めるところではなく、日本が決めるべき問題である。 ・一九六七年を通じ、沖縄の施政権返還と云うことはそれほど現実的の課題であるとして扱われてはいなかった。ところが同年十一月の首脳会談で、両三年以内に返還の時期の目途をつけると云うことになって以来、様相は著しく変わってきた。 ・すなわちジャーナリズムは、忽ち施政権返還は恰も既成の事実であるかの如くこれを前提とし、専ら「核抜き、本土並み」の主張が展開されることとなった。 ・「核抜き、本土並み」は結構であるが、沖縄返還は所詮極東の国際環境のなかでその一環として運ばれるところである。そこで「核抜き、本土並み」の前に、 ・また折角安保条約を改訂しながら沖縄は日米双方で防衛する条約地域には含ませず、沖縄が「核付き」ならば返還されない方がいい、と云うのでは、沖縄の人達から見れば本土の方は余りに身勝手ではないか。 ・言うまでもなく沖縄を本土と差別してはならないと云うことは、誰が見ても当然であるし、核の問題も本土でも沖縄でも同じ問題である。 ・ただ沖縄に核は必要でないと云う日本側の議論は、必要でないと云う結論から出発してこれを正当化する、と云う性質の議論であり、それでアメリカを納得させ得ると云うものではなかった。 ・アメリカ側は日本が返還後の沖縄にどの程度の抑止力を期待し、どの程度の支持を与え得るかについて日本側の考えが示されることが先決で、アメリカはこの日本の判断に適応していかなければならない立場である。 ・沖縄返還の話合いについては、国内では直ちに繊維との取引であったなどと言う向きがあった。しかし、一九六九年の共同声明に至る三年の足どりを見れば決して左様なものではない。 ・六九年会談の後、繊維問題が紛糾したのは残念なことであるが、これは長い日米経済摩擦の歴史の一頁であり、繊維が沖縄との取引材料にされたなどと云うのは、言葉は悪いが下世話に云う何とかの勘繰りと云うものであった。 ・交渉の実質を顧みれば、わが方は沖縄は返還して正常の姿に復すべきであり、また返還の故に極東における安全保障に支障を来たさしめることなきよう意図している旨を説き、アメリカ側においてある程度のリスクをとるよう要請したのである。 ・これに対してアメリカ側が日本政府を信頼してそのリスクをとったことにより、会談が成功裡に終わったのである。 ・その背景にあるものは、国力の向上した日本と、内外に難問を抱えている米国の相対的関係の変化であった。 ・ニクソン大統領が日米相携えて太平洋地域の安定と繁栄のために協力していかなければならない、としてわが国に対する期待を示したのも、こうした変化の反映である。 ・佐藤総理は一九六五年に、沖縄の祖国復帰が実現されるまでは戦後は終わらないと述べたが、日米関係における「戦後の終わり」とは、ただ沖縄が祖国に復帰すると云うことだけではなく、わが方が両国の相対的関係の変化をよく認識し、日米関係をわが国の利益に則して健全に発展させて行くか、と云う時代の出発点であるわけである。 第四章 「戦後」以後 一、ベトナム ・ベトナム戦争は悲劇の裡に終わったが、自由の体制の下に北ベトナムの干渉なしに生存を図ろうとした南ベトナムと云うものの存在を認める限り、これを援けようとしたアメリカの立場は世界の権力政治の仕組みの中で評価されなければならないところである。 三、韓国 ・金大中事件と云い、朴大統領暗殺未遂事件と云い、誠に遺憾な不祥事であった。それでなくともむずかしい事件の処理を一層むずかしくするのは、入り組んだ歴史を背景とした日韓双方に存在する強いコンプレックスである。 ・右いずれの事件についても、韓国側の反応は往々にして感情的に過ぎ、度を越したものであったと思う。しかしコンプレックスは韓国側だけではなく、わが方においても事韓国となると喧嘩腰になり易く、韓国が独立国であることを忘れたような言辞を聞くことは少しも珍しくない。 四、外交の重点 ・敗戦後わが国は多数講和の道を選び、極東に生じた力の空白は安保条約によって米国の軍事力を以て埋め、民主主義体制の下に国の再建復興に立ち向かった。 ・この間世界はいわゆる二極構造で東西冷戦の時代であり、わが国の対外関係も自ら対米関係が大部分を占めていた。 ・明治の開国以来、日本の対外政策の課題は一貫して朝鮮半島と支那大陸の問題、いわゆる大陸政策の問題であった。 ・帝国主義時代の末期にわが国は挙国一致して極東の一角にその地歩を確立したのであるが、歳月を経て終に大陸問題の故に英米と戦端を開くに至り、折角培ったわが国力は、灰燼に帰することとなった。 ・戦争の主たる相手方であったアメリカと手を携えることによって国力を再建し、「対米関係は日本外交の基軸である」と云うことが一般に受け容れられていると云うことは、歴史の面白さであるかも知れない。 ・国際政治が多極化し、複雑の度を加えれば加える程、わが国もその中における己れの立場を明確にすることを迫られる。 ・確かに日本の外交は対米関係を基軸として来たが、それもわが国がアジアにおいてしっかりした立場と自らの政策を持っていて初めて意味をなすのである。 第五章 日米関係の流れ ・安保条約は日本の敗北により極東に生じた力の空白を米国の力によって埋め、そうすることによって日本が灰燼の中から自由世界の一員として復交再建の途を進むことを可能にする環境を作ったものである。 ・これからの日米関係 【安全保障の分野】 ・「諸国民の公正と信義に信頼して」安全と生存を保持して行くと言っても、国際社会に生きることがそれほど甘いものでないことは明らかであり、列国の中にも、わが国の立場からして味方であるものとそうでないものとの区別はしなければならない。 ・我が国の安全保障も世界の他の地域と遊離して考えうるものではなく、西側全体としての安全保障の一環である。 ・現に南西アジアが多端であってわが国周辺における米国の軍事力が手薄になるならば、これを補って極東の力の均衡を保って行く力はわが国自身も自分のこととして対処しなければならないところであり、わが国がそうした気構えを持つことによって初めて安全保障の信憑性は保たれるのである。 【世界的規模における経済問題】 ・資源の争奪は過去において戦争の原因となってきたが、対立抗争の道を選ばず、人類生存のため共に叡智を活かして行くということは、これからの日米関係においてきわめて大きい新しい課題である。 【両国間の多岐にわたる経済問題】 ・過去において日本側は経済問題について屡々「日本の特殊事情」を掲げて米国の説得に努めたが、今やこちらが米国の「特殊事情」に理解を示すことも必要になってきていると言えようか。 【米国の世界戦略】 ・とくに安保論争時代には、これは日本が巻き込まれてはならない悪いものであるとの意味合いで使われたのであるが、事実は日本も欧州も米国の世界戦略に支えられて世界の均衡が保たれていることによって、今日の発展まで達することができたのである。 ・現在でも日本の防衛力増強は米国の世界戦略支援の立場が色濃く出るので宜しくない、などという向きがあるが、こういう惰性的な表現はもうそろそろ清算してもよいのではないか。 ・わが国は一方の極端から他の極端に走ることなきよう心する必要がある。 ・米国の世界戦略は、実は西側の世界戦略の重要な一環なのであり、これが健在であることが自由諸国にとっても必要なのである。 ・わが国は世界政治的のことは、とかく何もしないというふうで今日まで来たが、一方、米国の相対的地位が下がったのであるならば、米国もその世界戦略を策定するに当たってそれだけ多く与国の考えに耳を傾けるのである。 ・わが国も自らの世界戦略を持ち、それによって米国の世界戦略が西側全体の安全と繁栄に、ひいては世界平和に資するよう動かして行くという気構えが、これからの日米関係にとって最も必要なことであると思う。 |