
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年02月16日 木曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
12 |
17/02 |
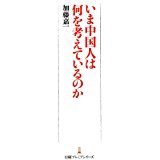 |
いま中国人は何を考えているか |
加藤嘉一 |
日経プレミアシリーズ |
◎ |
第1章 日本人があまり知らない中国人マインド 見栄を大切にする中国、実利を取る日本 ――スタバでわかる日中の違い 上海万博は中国で大盛況 ・地方の政府はとことん面子にこだわる。中央政府や外国人から「どう見られるか」を異様に気にするのである。 ・中国の大学生はすぎらしい。向上心があるし、何より、すべての機会を生かして経験値を積み重ね、それをキャリアアップの土台にしようというハングリー精神にあふれている。気合がみなぎっている。 日本に来ると軍国主義でない姿に驚く 規制緩和の三つの効果 ・日本政府の一連の規制緩和措置は、日本に三つの効果をもたらす ・一つに、消費・内需の拡大である。 ・二つ目に、中国人の対日感情である。 国内で近現代史に偏った日本観を植えつけられた中国人が、自らの目で等身大の日本社会・日本人を体験すると、90%以上が驚く。「日本は軍国主義じゃなかったんだ」と。この効果は抜群である。 ・最後に、少子高齢化という爆弾を抱える日本社会にとって、先行投資としての効果が期待できる。 将来的に、旅行者だけでなく、大量の中国人労働者が必然的に日本に押し寄せると考える。 第2章 確実に育ちつつある市民革命の萌芽 中国高速鉄道衝突事故 ――人民が週刊誌の記者のように ・インターネット、特に3億人を超えると言われる中国版ツイッター(ウェイボー)が社会の影の部分を24時間体制で「監視」し、ネット上で次々に暴露していく。 ・監視されるのは人民だけではなくなった。共産党も人民から監視されているのである。 ・インターネットという武器を手に入れた中国人は、すでに一方的に統治される愚民としての人民では決してない。「物言う市民」になってきたのだ。 ネットとマスコミではこんなにも違う ――毒ギョーザ事件に中国国民はどう反応したか? 突然の事件解決 ・容疑者逮捕のニュースに対し、日本の鳩山首相や岡田外務大臣は「感謝」「評価」のコメントを返した。中国メディアは「待っていました」とのごとく、「日本の首相が中国側に謝意表明」「日本側が中国政府の努力に敬意を表した!」などのタイトルで、トップページの目立つ位置を飾った。 【私見 : 本来は、事件発生当初からずっと日本側を非難してきた中国に対し、非礼も含めてモノ申すべきだったが、一言も反論しなかった日本。濡れ衣と分かっていながら、相手を慮り(但し、相手は何とも思っていない)結局、犯人を輩出した側が褒められるという、笑えないジョーク! 日本はそこまで統治能力を欠いていたのだ!】 沈黙を破るワンミン ・毒ギョーザ事件は2008年1月の段階で表面化し、刑事事件から外交問題に発展した。 ・中国国民は当初からギョーザ事件に関するニュースをほとんど知らされていない。 ・事件直後に公安省幹部が「中国国内で混入された可能性は極めて小さい」と言い切ったシーンのみがクローズアップされ、「日本人はどうしても中国を犯人に仕立て上げたいのか!」という「日本けしからん論」だけが蔓延した。 映画『南京! 南京!』にこめられた中国人監督の本音 少しずつ変わりつつある民衆の歴史観 ・中国の人はとにかく「南京大虐殺30万」にこだわる。家庭内で、学校でそう教えられるのだ。さもなければ「政治的に不合格」になり、中国では生きられなくなってしまう。中国人にとって、歴史認識とは「保身」の意味も含んでいるのだ。 ・中国人にとって、南京や自国史(たとえば文化大革命、天安門事件)を含めた「歴史観」とは、歴史にどう向き合うかではなく、今をどう生き抜くかという起点なのだ。 歴史認識を超えた世界 ・中国では映画も含めたすべての媒体作品は共産党当局の厳格な審査を通過しなければならない。チェックの要はもちろん、「政治的に合格かどうか」である。 限られた環境でリスクを背負う中国人 ・私たち日本人は知る必要がある。限られた政治環境、特殊な政治体制の中で、リスクを背負ってでも、戦う中国人がいる。 ・仮に日本人が「日本にも平和を願い、歴史認識を乗り越えて中国人と友好関係を築きたいと思っている人がたくさんいる」ことを中国人に知ってほしければ、日本人自身も中国国内で起きている真実に目を向けるべきではないだろうか。 第3章 実はとても日本が気になる中国人 日本の首相がころころ替わるのはなぜ? ――高校生がつぶやいた一言 アジア各国は日本の一挙手一投足を見ている ・ほぼ全員の記者に聞かれる質問、「日本の首相はなぜここまで頻繁に替わるのか?」 ・中国世論は日本を「頻繁換相」の国家だと表現する。文字通り、首相が頻繁に交換する、という意味だ。 ・私たち日本人はこの質問に的確な答えを見出せるだろうか。そもそも、日本の首相が1年前後という周期で替わるという趨勢に、海外の人たちが関心を持ち、疑問を抱いているという現状をまともに認識できているのだろうか。「日本は変わった国だ」と外国人から思われていることを日本人はそもそも自覚しているのだろうか。 「頻繁換相」から抜け出すには ・中国の日本専門家たちは、「首相は1年以内に替わるけれども、国民の政治生活は何も変わらない。独立した官僚システムが安定しているからだ」と、自国の国民に説明している。 ・「日本が政治主導になることはあり得ない。政治家が無能すぎて、官僚が狡猾すぎるからだ」、長年日本政治を研究してきた政府系シンクタンクの専門家は筆者に本音を漏らした。 国際社会から「同情」される海洋国家日本の外交 ソフトランディングを目指した日本 ・「胡錦濤国家主席がロシアを訪問した際にロシアサイドと交わした合意には、対日政策に関して歴史・領土問題で歩調を合わせていくことが含まれている」(中国共産党関係者) 第4章 世界第2位経済国の自信と苦悩 舞い上がる中国 ・中国人は縁起やゲン担ぎを日本人以上に大切にする。 北京事務所撤退の大号令 ――中央のご機嫌取りに躍起な地方機関 積極的に民衆のガス抜きを行う ・外国人が中国をウォッチするとき、「中国はひとつ」と思ってはならない。形式上は中央集権国家であることは間違いない。しかしながら、色んな場所、価値観、利害関係がある。土地政策、教育政策、戸籍政策、不動産市場など含め、中央政府が地方の状況を100%把握し、制御できていると思ったら大間違いだ。 ・昨今の共産党が、別れを告げたはずの「階級闘争」の時代に後戻りしている気がしてならない。党が設定したルールに従う者は「仲間」であり、背く者は全員「敵」と判断され、公の場で吊るし上げられる。 「敵」「仲間」というイデオロギー闘争 ・北京で生活していると、北京事務所の横暴ぶりが、目に見える形で浮き彫りになっていることを感じる。その典型が、物価高騰と交通渋滞である。土産になるような商品の値段は、地方役人が買い漁っていくおかげで一気に上がる。中央政府機関が位置する付近では、地方からの公用車が日々列を成しているため、渋滞が止まらない。 ・これらの行為を粛清するという一点において、中央指導者と国民の利害関係は高度に一致しているのだ。 腐敗は数千年の歴史に根ざしている ・「中国の腐敗は数千年の封建社会に根ざしている。結局は現行の体制が根本的に変わらない限り(北京事務所の)完全撤退はあり得ないのだ。あらゆる名義で北京に潜伏を続けるにちがいない。中途半端に管理を強化することで、状況はかえって悪化するだろう」、中央政府の幹部は筆者に対して力強く語った。 対日デモは実は中国政府にとって痛手だった 中国はもはや中央集権国家ではない! ・「反日」を装ったデモは本質的には中国の内政問題である。このことを一番理解しているのは中国政府自身なのだ。 ・日本のメディアでは、「中国共産党は反日を煽り、それをカードに日本に圧力をかけようとしている」という論調が蔓延している。 ・このロジックもあまりに中国共産党を過大評価している。 ・昨今の中国共産党は毛沢東時代の「革命党」ではなく、正真正銘の「執政党」である。社会主義というイデオロギーは保ちつつも、市場経済で国家運営を進める「与党」なのだ。 ・選挙という「手続」さえ踏めば、結果を保証する必要のない民主主義とは異なり、自らのパフォーマンスをもって結果を示さなければ、政権自体が崩壊するシステムなのである。 ・経済が発展し、生活水準が向上しさえすれば、中国人民は沈黙し、我慢する。しかし、その前提が崩れれば、彼ら・彼女らは暴れる権利を授かる。 ・中国4千年の偉大なる歴史を見れば、明らかである。常に統一と崩壊の繰り返しなのだ。中華民族・文明の根本は何も変わっていないようにみえる。 ・共産党の統治形式は、世代を追うごとに、コレクティブ、つまり、集団主義的になっていく。ひとりのリーダーのカリスマ性で国家をまとめあげる、まとめられる時代は終わった。国家主席の鶴の一声で物事は決まらないし、進まない。 ・中央と地方、党と軍、富裕層と貧困層、市民と農民、役人と学生、様々なファクターが複雑に絡み合い、13億人という対外的には圧倒的優位を誇る外交カードが、体内的には圧倒的劣位としての不安要素と化していく。 ・中国を中央集権国家と認識する事大はとうに過ぎ去った。 ・2010年下半期、日本との関係をめぐって勃発した一連のデモは、北京という中央が5中総会という「政治の季節」に突入した矢先に、地方で勃発したのだ。この事実を重く受け止めるべきだ。 ・四川省の成都、陝西省の西安、河南省の鄭州、いずれも省都であり、内陸部の大都市である。警備は厳重に敷かれていたにもかかわらず、デモの発生を逃れられなかった。 第5章 歩いてみてわかる中国の真実 自分の言葉を話さなくなった人もいるチベット チベットには漢化しかないのか ・世界中の人々から尊重される神秘性が、あの土地には存在する。 ・問題は、国際社会における国家のイメージという意味で、対チベット強行政策を続けることによって、世界中の政府や人民から冷ややかな目で見られているという現状を、中央政府がどう認識するかであろう。 ・中国には特殊な国情がある。「台湾問題が解決して初めて祖国統一」と考える当局にとって、チベット独立を容認するなんていうことはあり得ない。 ・ただ、独立は容認しない、祖国統一を前提としたうえで、より柔軟で、国際社会からの理解を得られるような「第三の道」は考慮に値しないのか。そこに尽力せず、ただ「チベット人民の生活レベルは確実に向上している」などと叫んでも、説得力に欠ける気がしてならない。 |