
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年09月24日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |||||||||||||||
17 |
17/02 |
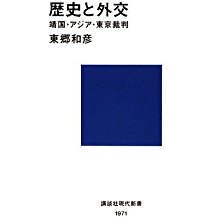 |
歴史と外交 |
東郷和彦 |
講談社現代新書 |
☆ |
第一章 靖国神社と歴史認識 2 A級戦犯の合祀と戦争責任 政府としての責任はまぬがれない ・靖国神社にA級戦犯を合祀したのは、靖国に祀られるべき候補者が、「祭神名票」というかたちで、政府から靖国神社に提出されたことを、出発点としている。 ・政府がこの名票をつくった以上、「靖国神社さえよろしければ、このかたがたは、神として祀るにふさわしいかたがたです」という判断があったと考えねばならないし、そういう判断をしたことに対する政府としての責任はまぬがれない。 ・国のために命を捧げた人がいったい誰であるかということは、本来、国が、堂々と判断すべきことではないのだろうか。 ・自分が「国に命を捧げる」という立場に立ったとして、自分が国のために死んだかどうかについての認定をするのが、国ではないなどというのは、あまりにも変ではないか。 ・このもっとも政治的な問題についての政治的な判断を、法的な「擬制」によって、宗教法人たる靖国神社に委ねてしまって、ほんとうによいのか。 3 遊就館から “国民的な歴史博物館” へ 私の歴史観 ・西欧帝国主義列強に囲まれた日本は、アジアのなかでほぼ唯一、植民地支配に屈することなく、富国強兵・脱亜入欧・和魂洋才をもって近代化をなしとげた。 ・日清戦争でアジアの超大国清を破り台湾を獲得、日英同盟を背景として欧米列強の雄ロシアを破り、中国・韓国の改革者を含め、アジアと世界の被植民地や世界の列強に深い感銘をあたえた。 三つの部屋を ・昭和の戦争にいたる原点 ①日露戦争における日本の勝利を絶賛した孫文が、やがて抗日の先鋒となったのはなぜか。 ②同じく韓国で、日露戦争の日本の勝利を、わがことのように喜んだ安重根がその五年後に伊藤博文を暗殺したのはなぜか。 ③日露戦争時にはロシア兵捕虜に対する国際法に則った人道的な取り扱いが絶賛されながら、太平洋戦争における捕虜の取り扱いについては、いまだに元連合国兵士の根深い怨恨があるのはなぜか。 4 憲法二十条をどうするか 私的な訪問という議論は意味をなさない ・総理大臣の靖国参拝が、かくも問題となるのは、総理大臣が、職責上、行政府の長として、英霊を死にいたらしめた国家を代表して、祈るからである。 ・靖国神社に英霊が眠っており、その死に対して彼らを死にいたらしめたものを代表して感謝する以上、その行為は公のものであり、わが国憲法のどこを読んでも、世界の常識のどこを叩いても、それを禁ずるという考えはないと思う。 ・総理大臣について、個人としての私的な訪問という議論は意味をなさないと思うのである。 ・もうひとつは、憲法第二十条に示された政教分離の規定に従い、「国がおこなってはならない宗教活動」はなにで、それに抵触せずに、靖国という民間の宗教法人で祈りを捧げるには、どうしたらよいかということである。 靖国を置き去りにするなかれ ・靖国神社問題が抱える矛盾を解決し、国民と世界からもっと広汎に受け容れられる状況になっていたら、戦後六十年余の今日に於て、堂々と靖国での慰霊を続けられるのではないか。 ・中国にあれこれ言われたからではなく、日本がみずからの手で、日本の内部の矛盾を解決することができれば、結果として、中国との関係も、より強固なものになる。 第二章 国家の矜持としての慰安婦問題 1 性奴隷なのか、公娼なのか 慰安婦問題の、他にない特徴 ・日本内部における主な立場 (1)制度的レイプ派 (2)公娼派 (3)河野談話派 の三つに分けられると私は考える。 いわば“制度的レイプ” ・主張の根幹は、慰安婦制度が、国際的な犯罪行為であり、いわば “制度的レイプ” であるということにある。日本政府は、犯罪としてこれに対する補償を支払うべきだというものであった。 ・青柳敦子氏、高木健一弁護士、吉見義明氏などの名前がまず浮かぶ。 慰安所=レイプ・センター ・朝日新聞の記事がひきがねとなり、宮澤喜一首相の一九九二年一月十六日からの韓国訪問は、宮澤首相が謝罪をくりかえし、真相究明を約束する旅となった。 ・一九九二年二月十七日、戸塚悦郎氏がジュネーヴの国連人権委員会で慰安婦を「性奴隷」として告発、日本政府の補償と国連の調停を求めたことがこの動きを強めることとなった。 ・国連では、一九九六年二月五日付で人権委員会に、『クマラスワミ報告書』が提出され、四月十九日、「この作業を歓迎し、報告書に留意する」という決議が採択された。 ・国連人権委員会では、さらに、一九九八年六月二十二日、人権委員会差別防止・少数者保護委員会で、『マクドゥーガル報告書』が受理され、八月二十一日、前文で、「報告書を、重大な関心をもって歓迎する」という決議が採択された。 ・ジェンダー(性)の観点から、慰安婦制度を法的に糾弾する動きは、さらに大きなものとなった。 ・二〇〇〇年一二月八日から十二日まで、東京で「日本軍性奴隷制を裁く女性国際法廷」が開催、「『戦争と女性への暴力』日本ネットワーク」の松井やより代表以下多くのメンバーが積極的な役割を果たした。 「慰安婦は公娼と同じだ」 ・慰安婦制度は、大陸に進出した日本軍のために設置された。一九三二年、上海事変の際にはじめて設置され、基本目的は、一般婦女子への強姦、性病、情報漏洩の予防にあった。 ・慰安所の運営は、主に、民間の業者がおこなったが、いろいろな意味で、軍の関与があったことは、否定されていない。いわゆる ・しかし、軍は、どちらかといえば、慰安所の規律を守る側にいた。 ・とくに、慰安婦を集める過程で、軍・官憲などによる、「強制連行」を示す証拠は基本的に残っていないことが、強く主張された。 ・要するに、個々のケースで、悲惨な運命にあった女性がいたことは否定しないが、慰安婦制度自体が、軍という組織が責任を追及されるべき犯罪行為といわれる理由はないというのが、 "公娼派" の根本的な考え方である。 ・櫻井よし子氏、古森義久氏、西岡力氏、渡辺昇一氏そのほか多くのオピニオン・リーダーが、このグループに属している。 河野談話と「アジア女性基金」 ・内閣退陣の五日前、河野洋平官房長官より、「慰安婦関係調査結果発表に関する内閣官房長官談話」を発表した。 ・ポイントは、四つあった。 第一に、「慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した」として、慰安所に対する軍の関与を認めたことである。 第二に、「慰安婦の募集については、軍の要請をうけた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに関与したこともあった」と判断されている。 第三に、「慰安所における生活は、強制的で痛ましいものであった」とし、特に朝鮮半島について言葉が割かれ、「その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行なわれた」と、指摘されている。 第四に、このような認識にもとづき、「政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる」とし、国としてその気持ちをどう表現するかは、今後真剣に検討したいと述べている。 ・河野談話にもとづいた政府としての活動は、一九九五年、村山富市総理の下で、「女性のためのアジア平和国民基金」の活動として開始された。 ・基金の事務局経費は予算で、女性に対する償い金は、民間からの寄付によってまかなうというのが、この基金のコンセプトとなった。 ・戦争に関する請求権問題は、戦後日本が結んだ条約によって決着済みであり、政府予算で償い金まで拠出することは、いわゆる道義的な責任を認めているだけでなく、法的な責任まで認めることにならないかという懸念から、このような枠組みがつくられた。 越えがたい溝 ・河野談話とそれにもとづくアジア女性基金の活動は、 "制度的レイプ派" からも、 "公娼派" からも、強い批判を浴びる結果となった。 ・ "制度的レイプ派" からは、河野談話で日本政府が「法的な責任」を認めず、不法行為に対する国家補償の体制をとっていないとして、強い批判がおこなわれた。韓国市民団体、国連人権委員会や、女性国際法廷における議論もまったく、この方向にしたがっている。 ・ "公娼派" からは、河野談話の事実認定について、猛烈な反論が展開された。とくに、募集に関して、「官憲等が直接これに加担した」との表現が、いわゆる "強制連行" (いやがって泣き叫ぶ人を、暴力をもって連れ去る)を示唆している。また、朝鮮については、「総じて」という一言をもって、あたかも、朝鮮人の慰安婦全体(もしくは、その圧倒的多数)が、レイプ状況だったというイメージを作り出したと批判された。 ・私自身は、明確に、 "河野談話派" だった。私の年代の外務官僚としては、それは、一般的な立場だった。 2 共通認識を求めても 強烈な論争の結果 ・吉見義明氏と秦郁彦氏の著作を中心に勉強をしていくと、当初思ったよりも、じつは、双方のものの見かたに共通点がある。 (a)軍の関与自体については、三つのグループのあいだにコンセンサスに近いものが形成されている。 (b)「強制連行」についても、驚くべきことに、相当の接近がある。 当初、強制連行のイメージづくりに大きな影響をあたえた吉田清治「私の戦争犯罪」で描写された済州島城山浦での強制連行がでっちあげとしか言いようのない事件であったことは、秦郁彦氏のその後の現地調査に加え、吉見義明氏も、吉田氏への直接確認を試みた結果として「吉田さんのこの回想は証言としては使えない」と確認している。 二十万人算出の根拠 (c)強制連行の有無については、日本の植民地だった朝鮮・台湾と、その他のアジアの占領地域では、実態は大きく異なっていた。 (d)慰安婦の総数と出身地について、さまざまな数字があるが、吉見義明氏も秦郁彦氏も、確実な史料が存在せず、推定でしか議論できないという点については、完全に見解が一致している。 「欺瞞」をめぐる対立 ・ "制度的レイプ派" の視点からは、「欺瞞」によって女性を調達するケースは、暴力的に拉致するケースと、法的にも実態的にも、同じように悪質だと議論される。 ・吉見義明氏によると、朝鮮からの徴集でもっとも多いのは、だまされて連れて行かれたケースだったと述べている。 ・ "公娼派" も、「欺瞞」によって慰安婦となった人がいたことは、否定してはいない。 ・秦郁彦氏は、一九四四年夏、テニアン島で米軍の捕虜になった三人の朝鮮人による「太平洋の戦場で会った朝鮮人慰安婦は、すべて志願者か、両親に売られた者ばかりである」という証言を、有力な反証として提起している。 ・どのくらいの女性が慰安所で、広い意味で、「本人たちの意思に反して」働いていたのかという点で、 "制度的レイプ派" と "公娼派" の、最も決定的な認識のギャップがあらわれる。 かつての兵士たちは・・・・・・ ・ "制度的レイプ派" は、主に、一九九〇年以降の元慰安婦の証言にもとづき、慰安所は性奴隷制を敷くレイプ・センターだと主張する。 ・ "公娼派" は、当時の兵士その他の証言も勘案し、慰安所が当時社会的に受け容れられていた、公娼制度を軍との関係でつくったものだと主張する。非常に多くの兵士の意識がその裏づけとなる。 ・一九九二年三月、かつての兵士ら百三十二名の電話が寄せられ、慰安所の雰囲気について語った。 ・しかし、慰安所が「レイプ・センター」だと認識している人は、ひとりもいなかった。 ・小野田寛郎氏も、自身の経験をもとに、公娼制度下の慰安所がけっして、レイプ・センターでなかったことを書いている。 ・一九四四年八月十日、ビルマのミートキナで米軍が二十名の朝鮮人慰安婦を尋問した貴重な調書が残っているが、これを読めば、おおむね、慰安婦たちが、どういう仕事につくか承知のうえで、朝鮮からビルマに来ており、相当程度の収入を得て、兵士たちと一定限度、生き生きとした関係をつくっていたようすがうかがえる。 ・多くの慰安婦が、「欺瞞」によって連れてこられ、以後、本人の意思に反してセックスを強要され、制度自体を、「レイプ・センター」とみなさざるをえないような実態であったのか。 ・それとも、慰安所は当時合法的だった公娼制度の一環であり、慰安婦は主に、自発的志願、親との契約にもとづいて働くことになったのか。時に逸脱があり、規律が完全には守られなかったことは遺憾であるが、これをもって、国際法上の責任を追及され、犯罪者として処罰されなければならないのか。溝は、深い。 ・河野談話は、いわば、両者のあいだに立っている。軍の関与の下で活動した慰安婦のなかに、苦しんだ人がいたこと、そのことに、謝罪と償いを表明した。 "制度的レイプ派" と認識を一にする面があるが、彼らのいうところの、国家賠償を必要とする犯罪という認識とは、一線を画したのである。 下院決議案と安倍発言 ・下院外交委員会ではこの七年間、慰安婦決議案が検討されてきた。戦前の日本がいわゆる従軍慰安婦に対してとった対応を非難し、日本政府の公式の謝罪を要求する決議案は、二〇〇六年九月十三日下院外交委員会を全会一致で通過したが、本会議の議決にいたらなかった。この決議案を支持した米国の評論家は、日本大使館が多額の資金を注入し、元共和党有力議員を使って下院本会議での決議案の採択をブロックしたと非難した。 論点は七つ ①慰安婦制度は、一般婦女子へのレイプ、性病、情報漏洩を抑止するために、設置された。多くの兵士が、慰安所は、軍のための遊郭という認識でここに通った。 ②軍が直接運営した例外的な場合を除き、大部分の慰安所は、民間の業者によって運営された。 ③軍は、直接間接に、慰安所の設置、管理、および慰安婦の移送に関与した。 ④一般的な慣行として、強制連行は、朝鮮ではおこなわれなかった。そういう場合があったとしても、それは、例外的な場合であったが、相当数の朝鮮慰安婦が「欺瞞」によって慰安所に送られたと推定される。 ⑤中国やフィリピンなどの占領地域では、レイプの結果として性的なサービスが強要された場合がある。インドネシアにおけるオランダ人慰安婦については、地域の軍が強制行動に関与したことが明らかになっている。 ⑥以上のような事態の結果として、精神的・肉体的に非情な苦痛を感受した女性たちがいた。 ⑦河野談話は、慰安婦が受けた苦しみを認識し、政府の責任を認め、反省と謝罪を表明した。この立場から、アジア女性基金の活動が始まった。アジア女性基金の活動に協力した政府もいるし、その活動を拒否した政府もいる。基金は、二〇〇七年三月、その活動を終了させた。 あなたは納得できないかもしれないが ・女性の権利の問題はアメリカではきわめてセンシティヴな政治問題なので、日本は慎重なうえにも慎重に対応したほうがよい、アメリカを挑発したと受けとめられるような行動をとったときに、それを支持するアメリカ人はいないということに、尽きていた。 ・婦人の尊厳と権利を踏みにじることについては、過去のことであれ、現在のことであれ、少しでもこれを正当化しようとしたら、文字どおり社会から総反撃を受けることになる。 ・これは、非歴史的すなわち、六十年前の視点でものを見ているのではなく、現在の視点でものを見た議論と言ってもよいと思っている。『それはひどいではないか』と言っても、それがいまのアメリカをはじめとする世界の圧倒的な大勢である。 3 情報戦には勝たねばならない 『ワシントン・ポスト』紙に載った意見広告 ・六月十四日の『ワシントン・ポスト』紙に日本の政治家とオピニオン・リーダーの、慰安婦問題に関して、「強制連行はなかった」とする意見広告が掲載されたという。これによって、しばらく表面に出ていなかった下院外交委員会の決議案がまた急浮上するだろう。 ・日本の報道や雑誌記事のなかに、慰安婦問題が、アメリカでこのように大きな問題になっているのは、在米の中国や韓国のロビー活動が原因であるという指摘が目立つ。貴重な情報だと思う。しかし、そうであればこそ、その活動に乗せられないような、アメリカ全体を動かす効果的なメッセージを出さねばならない。 決議案は採択された ・「議員の多くは、自分の選挙区のアジア(韓国・中国)系の豹を得るために、決議案に賛成する機会をうかがっているのだよ。」 ・「日米関係は大事だが、慰安婦問題で、旧日本軍の慰安婦制度を支持するアメリカ人はひとりもいない。」 ・「成立する以上、拘束力もないし、日本側が過剰反応しないことが大事だと思う」 ・「日本では、河野談話とそれに対する批判派のあいだで激しい議論をおこなっているあいだに、外の世界がどう変わってきたか、わからなくなってしまったのではないか」 ・七月三十日、下院本会議は、歴史上はじめて、慰安婦問題に対する公式謝罪要求を内容とする決議案を採択した。この動きは、オランダ(十一月八日)、EU(十二月十三日)の各議会における決議議案採択へと発展した。 ・慰安婦に関する対日批判は、これからも、続くであろう。「過去を反省しない国」「女性の尊厳を踏みにじる日本」というイメージは、そのたびに少しずつ強まるであろう。 ・六月十四日の広告のなかで述べられた “事実” については、個別に正しいものがあっても、広告の主目的が、慰安婦制度自体の正当性を訴えようとしていると受けとめられるなら、世界がこれを受け容れることは、まず予見されない。 ・欧米、韓国、中国はそれぞれの立場から対日批判を強め、努力すればするほど、日本は国際的に孤立化する。六十年前に軍事的に叩きのめされた事態が、こんどは、文化的な次元で起きかねないように見えるのである。 玉砕に近い事態 ・岡崎久彦氏曰く、日本が、アメリカの国力とその国民の性向を把握し、それに即応した対応をとっていたならば、おのずと違った戦いかたがあった、「真の敗因は情報の軽視にあった」と指摘する。 ・「真珠湾攻撃という戦術的大成功は、戦略的大失敗と断ぜざるをえない」 ・今回の慰安婦問題をめぐる対応は、日本が、情報戦で、きわめて深刻な立ち遅れに至っているかもしれないことを、示している。 ・相手国、世界の心理が把握できていないがゆえに、みずから正しいと信ずる心理をそのままのかたちでぶつける。結果として、玉砕に近い事態が起きる。情報戦において決定的に敗北しているからとしか、言いようがない。 矜持を保つ道 ・世界のなかで日本が孤立化し、尊敬に値しない存在ということになれば、 ・だが、私の見るところ、この問題に日本が勝つ方法がひとつだけある。 ①まず、慰安婦問題にたいする世界の世論がどう動いているかについての正確な情報を蓄積する。日本が発するメッセージは、世界の世論が「なるほど」と思うかたちで発せられねばならない。 ②メッセージの中核は、「日本が過去に他者に与えた痛みを感じ取る国であること」におく。それは、河野談話の中核にある考え方だし、また、『ワシントン・ポスト』紙への意見広告のなかにも、目立たないかたちではあるが、述べられている思想である。 ③メッセージには、行動をともなわせる。二〇〇七年四月二十七日の最高裁判決によって、いかなる国の慰安婦からの個別訴訟によっても、国は敗訴することはなくなった。この事態をむしろ「チャンス」ととらえて、国として、道義的な観点から出来ることを考える。 ④以上の対応は、「慰安所は『レイプ・センター』であり、日本は、二十万人の性奴隷をつくりだした」という認識にもとづく必要はまったくない。むしろ、以上のようなメッセージと行動の基礎として、秦郁彦氏や吉見義明氏のおこなった地道な事実調査を位置づける、日本としての歴史認識をきちんと添付する。 ・少なくとも、政治家からもオピニオン・リーダーからも、日本から発するメッセージは、他者の痛みを理解するものとなっていることが、ぜひとも、必要である。 ・そこを基礎とするならば、いずれ慰安婦に関する歴史的事実を国際的に、明らかにしていくことが可能だと思う。 ・これが、明治以降の日本の名誉と、敗戦から学んだ戦後の日本のもつ道徳観の双方を生かし、世界のなかで日本が矜持を保ち、尊敬を 第三章 日韓の “失われた時” を求めて 1 恨みが残らぬはずがない 祖父そして美山 ・東郷茂徳は、鹿児島市から車で約一時間ほどの距離にある ・美山は、慶長三(一五九八)年、朝鮮戦役の最後に、半島から撤退する豊臣秀吉軍に拉致された朝鮮の陶工たちが、居を構えた場所である。この村で、朝鮮の陶工たちは、薩摩藩の独特の保護と隔離の政策の下で、当時の世界の最先端技術による陶器を製産、世に知られる薩摩焼となった。 ・茂徳の父寿勝はこの村の陶工のひとりであり、明治維新のとき、旧姓の朴を捨て、東郷姓を名乗った。 【私見 : だからなのか、氏の対韓国観は、寛容に見える。】 すべてが微妙にくいちがった ・十九世紀なかば、朝鮮(李朝)も、日本も、ほぼ同じくらいの歴史をもち、中華秩序のなかでそれぞれの立場を有し、ともに高度に発展した文化に誇りをもつ国だった。 ・日本における「尊皇攘夷」、朝鮮における、 ・明治天皇とほぼ同じ時期に朝鮮に君臨した ・しかし、一方が、日清・日露の戦いを経て、列強に伍す、アジア唯一の近代国家となったのに比し、他方は、韓国併合により、国家としてのかたちを失った。 ・この差はどこから生まれたのだろうか。 ・徳川幕府は黒船来航を端緒として、一連の不平等条約を結び、一挙に開国政策を進めた。一方、当初は攘夷を唱えていた薩摩藩および長州藩が、一八六三年の薩英戦争と翌年の英米仏蘭四ヵ国連合艦隊の下関砲撃で、それぞれ列強の力を実感する。また、いずれの勢力も、特定の外国勢力と結ぶことはなかった。 ・幕府は、錦の御旗のもとに ・朝鮮では、すべてが、一歩ずつ遅れ、くいちがった。フランス艦隊およびアメリカ艦隊の排撃は、列強恐れるに足らずという感慨を生んだのかもしれない。 ・開国は、けっきよく、日本艦隊の砲艦外交の結果としての、江華島条約を待たねばならない。日本に遅れること約二十年。 韓国併合 ・一八八〇年代以降、朝鮮は江華島条約締結後の日本、宗主国として天津条約締結以降ふたたび巻き返しに転じた清、そして南下政策をとる帝政ロシアの三国の角逐に捲き込まれる。 ・改革にも、宮廷内の勢力争い(高宗、父君の大院君、 ・一八九四年・・・・・・東学党の乱、日清戦争勃発 一八九五年・・・・・・下関条約、三国干渉、閔妃暗殺 一八九七年・・・・・・国号を朝鮮から大韓帝国に変更 ・入れかわり立ちかわり、朝鮮国内政治と外国勢力との結びつきが生じ、ついに、朝鮮の近代化は実現しなかったのである。 ・他方、一九〇五年、日露戦争において勝利し、名実ともに近代国家の一員に列した日本は、それからわずか五年にして韓国を併合した。 ・江華島条約によって、いわば、恫喝的に開国を強いられた後、朝鮮で志をもってその近代化を実現しようとした改革の志士たちは、どちらかといえば、日本を見、日本をその範としようとしていたのである。 ・開国後の開明政策、親日改革派による ・それが、である。 日清戦争で清の勢力を朝鮮半島から駆逐した日本が、日露戦争でロシアの勢力を駆逐したあと、韓国の希求する「日本型の独立近代化」実現を補佐するどころか、列強帝国主義の一員として、韓国の独立を完全に否定し、これを併合したのである。 ・韓国人の心情からすれば、心に恨みが残らなかったといえばうそになろう。 安重根の提起する問題 ・欧米の列強の圧力のなかで独立と近代化を希求し、日本に期待し、そして、日本に裏切られた当時の韓国の人びとの心情を、もっとも ・安自身の著述になる『東洋平和論』という書のなかに、日露戦争緒戦における日本の勝利について「快なるかな、壮なるかな、数百年来、悪をおこないつづけてきた白人種の先鋒が、鼓を一打しただけで大破してしまったのであり、千古に稀な事業として万国に記念すべき功績であった。このとき、韓清両国の有志は、はからずも同じように、自分たちが勝ったように喜んだ」という意味の記述がある。 ・伊藤博文を暗殺した人間が、日本の勝利について、これほどの言辞を用いて絶賛・驚喜したのはなぜなのだろう。 ・『東洋平和論』が、一九〇九年十月、ハルビンで伊藤博文を暗殺した後に旅順の刑務所で書かれた未完の論考であったこと、 韓国の独立を保障すると思った日本が逆にそれを奪う方向に出たことに対し安が抑えがたい怒りをもち、それが、暗殺行為につながったこと、 旅順の獄中で安の監視にあたった憲兵の千葉十七が安の人柄に打たれ、二人のあいだに稀有の交流が生まれたこと、 一九一〇年三月二十六日処刑の朝、安は千葉に「為国献身軍人本分」というみごとな書を残し、「親切にしていただいたことを心から感謝します。東洋に平和が訪れ、韓日の有向がみがえったとき、生まれかわってお会いしたいと思います」と述べたということを知った。 ・彼自身の言葉 「いま韓日は非常に不幸なかたちで袂をわかってしまった。しかし、いずれの日か、韓日清(中国)はともに手を携えて、北東アジアの平和と繁栄をつくっていかねばならない。そのためには、三国共通の銀行をつくることも有益だろう。三国の若人が集まって、地域の安全保障を担う部隊をつくることも考えられる」 【私見 : このような思いは誰でも持つことはできるだろうが、政治外交的に考えると無理がある。日本も大東亜共栄圏構想を持ったが、白人世界に粉砕されてしまった。少なくとも、朝鮮がリーダーにはなれないだろうし、中国は独裁的な考えを持っているだろうから、夢話にしかすぎないと思う】 ・安重根は、伊藤博文という明治の元勲を暗殺した人物であり、結果においては、この暗殺が韓国併合のプロセスを加速し、不可逆的にした。 ・にもかかわらず、安重根の人生、千葉十七との友情、安の抱いた日中韓の未来像は、多くの日本人をなごませ、往時の「やりすぎ」を反省させ、韓国には立派な人がいたという謙虚な気持ちにさせ、未来の北東アジアについて、楽観的な気持ちにすらさせるのである。 ファクト・シートをつくってみた ・植民統治の歴史を勉強すればするほど、三十六年の植民地時代に、朝鮮の近代化が進んだ側面は、否定しようがないものがある。そこを、まったく無視して、この時代の歴史を教えることはできない。 ・そこで、自分は、植民地時代の朝鮮について、データとして客観性があると思われるものを選んで、一枚紙の「ファクト・シート」をつくった。
・しかし、当時、起きたことを、できるかぎり、客観的に理解するひとつのよすがにはなるのではないかと、私は思ったのであ。 もっと大きな苦しみが ・そのうえで、講義にあたっては、以下の三点を述べた。 ・第一に、誰が たとえば、耕地の拡大については、厳格な土地の調査を実施し、結果として、朝鮮人が耕作していた土地が日本人の入植者に渡ったという側面もあった。 一般論としても、朝鮮経済の発展は、日本帝国の発展の一部となったわけであり、日本が裨益したことは、疑いがない。 ・第二に、当時朝鮮側で、独立の喪失と日本統治に不満をもつ広汎な人たちがいたこともまったく、否定できない。 「三・一抗日運動」は、そのもっとも象徴的な動きであった。 ・第三に、一口に植民統治といっても、時期により、政策のちがいがあった。 併合当初の武断統治、「三・一抗日運動」以降の文化統治、日中戦争以降の総力戦における完全日本化への動きという三つの大きなうねりがあったと思う。 ・植民地下の教育で当初ハングル文字はそれまでよりも積極的に教えられたが、総力戦の時期に入ると、朝鮮語を学校教育で教えること自体が禁止されたのは、その振幅を物語る例であろう。 ・結論として、朝鮮の人たちが、もっとも苦しんだこと、日本の植民統治によって、もっとも傷ついたことは、日本側が強制した、「日本化」政策ではなかったか。 ・いまふりかえり、この点に、明らかに「ゆきすぎ」があったのではないか。 ・まず、植民地化とともに始まった、いわゆる、日本との、同化政策があった。 ・これが、一九三〇年代後半、総力戦の開始とともに、いわゆる皇民化政策の徹底に連なる。戦争の遂行のなかで、朝鮮人は、日本人と同じように、否、日本人よりももっと苦しい条件下で、日本人として、戦争の遂行に協力させられた。 ・一九三八年に始まった朝鮮からの志願兵の採用、同年の第三次朝鮮教育令(朝鮮語教育の禁止)、一九四〇年の創氏改名、一九四四年からの徴兵制など、みな総力戦のなかの徹底した日本化政策ということであろう。 ・日本からすれば、当時日本帝国の一部となっていた朝鮮のもてる力を、国運をかけた太平洋戦争に投入する、そのために、朝鮮を徹底的に日本精神で固めていくということは、疑うべくもない当然の政策だったのかもしれない。 ・しかし、独立民族の誇りを心にもつ人たちとして、自国のアイデンティティを壊滅させられることが、心の痛みにならないわけはない。 ・日本帝国が、朝鮮に敷いた日本化政策は、朝鮮の人たちのアイデンティティに筆舌に尽くしがたい苦しみをあたえた。しかし、もっと大きな苦しみがあるとすれば、それは、当時の朝鮮人の少なくとも一部の人たちが、日本人として、立派に戦ったことにあるのではないか・・・・・・。 ・黒田勝弘氏は、韓国人の記憶の本質は、「かつて危うく日本人になりかかり、共にあの戦争を戦った忌まわしさ」にあると喝破している。 2 戦後六十年間の振幅 独立国としてのアイデンティティ――日本の全否定 ・日本の敗戦によって、朝鮮統治は終わりを告げた。朝鮮人は、もはや日本人であることをやめた。 朴正煕、全斗煥、盧泰愚――三人の軍人出身大統領 ・第一期は 朴大統領は、軍事独裁的な政治手法によって、韓国社会を統御しつつ、外交的には、親米路線を堅持、日本との関係も正常化し、韓国経済復興に導いた。「 ・しかし、朴大統領時代の韓国社会全体の反日ムードには強烈なものがあり、知日派ともいうべき朴大統領の対日観は、複雑なものがあったと思う。 ・一九七九年の朴大統領の暗殺後、韓国は ・一九八〇年代は、韓国経済が躍進した時代であり、一九八八年のソウル・オリンピックは、韓国高度成長の象徴となった。 ・さらに、冷戦の終了とともに韓国外交は、ソ連との外交関係設定(一九九二年八月)と、めざましい展開をみせた。 ・政治・経済・外交と力がついてくれば、当然、自負の気持ちも強くなろう。教科書問題(一九八二年)、靖国問題(一九八五年)とこの時代、歴史問題が、はじめて本格的な懸案として、両国間に登場する。 3 教科書と竹島 お互いのちがいを前提として ・日韓間の火種となりかねない歴史問題は、靖国、慰安婦、教科書、竹島問題の4つである。 ・わが国の名誉をまもりつつ、今後ともに、「近隣諸国条項」を堅持し、アジアの心をも離散させずに(歴史教科書)記述することは可能だ、私は信じている。 【私見 : そう思いたいが、近隣諸国条項自体が、双方の解釈が同床異夢のように見え、もとは政治的解決手段としての言葉として出されたもののように思う。中国と韓国の一方的主張にのみ配慮することが近隣諸国条項の役割だとしたら、わが国の名誉を守ることには決してならない】 第四章 トーゴー先生は台湾独立を支持しますか? 1 "現状維持" というコンセンサス 日本統治時代の記憶――なぜ韓国とはちがうのか ・双方の歴史の記憶がくいちがう、もっとも大きな原因は、朝鮮においては、日本を上回る歴史・文化・国際的な地位をもつと自負する一方で、一時は範をとって、近代化を実現せんとした、その日本に裏切られたという民族の誇りの蹂躙の気持ちがあった。 ・台湾には、少なくともそれに比べるほどに、踏みにじられた埃の苦渋はなかった。 ・そこに、最大の要因があるのではないかと思われる。 台湾の戦後史――白色テロから民主化・台湾化へ ・朝鮮は、南北の分断と朝鮮戦争という悲劇に見舞われ、李承晩大統領の反日、反共政策から、民主的な市民国家としての発展をとげた。この過程において、新生韓国のアイデンティティは、戦前の日本統治の全否定におかれた。 ・民主化と台湾化の過程は、台湾のなかにおける、中国的なものとの戦いでもあった。 ・そして、歴史的な記憶としてそこで対置されることになったのが、五十年の日本の植民統治のあいだに蓄積された、非中国的なものであった。植民地時代の善を生かすことが、台湾化を進めようとする人たちの政治の要請となった。 ・植民統治時代の全否定に現在の建国のすべてをかける韓国と、植民統治時代の日本的なものに今後の建国の精神を探求する台湾本省人と、双方のあいだに、大きな差異が生まれるのは、けだし、当然のことと考えねばならない。 2 ギリギリの答え 「上海コミュニケ」 ・アメリカの台湾政策のひとつは、アメリカは理念の国であって、アメリカ自身のアイデンティティは、自由・民主・人権の尊重にあり、この理念を共有し、アメリカに支援を求める国に対しては、これを助けようとする内在的な力があるということである。 ・もうひとつは、アメリカは、現実主義の国であって、アメリカの利益になることであれば、善悪というリベラルな価値基準に依拠することなく、いかなる国とも提携する可能性があるということである。 ・一九五〇年十月の朝鮮戦争への中国の介入は、冷戦の主敵が、ソ連だけではなく中国だという認識を米国に植えつけ、台湾は、アメリカの防衛圏のなかに、明確に組みこまれた。 ・一九五三年七月の朝鮮戦争休戦協定の後、一九五四年十二月に「米華相互防衛条約」が締結されたのである。 ・一九六九年大統領に就任したニクソン氏とキッシンジャー補佐官は、デタントという大きな政策転換を図った。 ・折からの中ソ対立を最大限に利用し、中国との関係を再構築することにより、自国に対する包囲網の形成を恐れるソ連をもひきこみ、「ベトナム戦争からの名誉ある撤退とアメリカにとっていっそう有利な国際関係の再構築」にのりだしたのである。 ・その決定的な成果が、一九七二年二月の「上海コミュニケ」での、「アメリカは、台湾海峡両岸の中国人がみな中国はひとつしかなく、台湾は中国の一部分であると考えていることを認識した。アメリカ政府はこの立場に対し、異議を唱えない」という内容の米中間の合意だった。 ・こんどは、アメリカの国内法である「台湾関係法」において、「アメリカの中華人民共和国との外交樹立の決定は、台湾の将来が平和的手段によって解決されるとの期待にもとづくものであることを明確に表明する」という、重要な規定が置かれたのである。 3 日本のなすべきこと 「東洋平和」という理念 ・「台湾は中国の内政問題」という中国の立場は明確に承知しつつも、日本は、いま台湾でなにが起きているかを十分にフォローし、そのなかで日本としてとるべき立場をほんとうに真剣に模索すべきではないか。 ・日本がそのように真剣に考えることは、中国の現下の政策にそのまま順応することにはならなくても、中国からのほんとうの尊敬を獲ちうるうえで必要なプロセスであり、真の日中間の信頼関係をつくる礎になるのではないか。 【私見 : 台湾が勝ち取ってきた民主的政治基盤を日本が支持することに対して、中国本土(共産党政権)はどこまで理解を示すだろうか。日本が真剣に立ち向かえば向かうほど中国は苛立つだろう。むろん、日本はそれに屈してはいけないのだが。】 アジアの国々は注意深く見守っている ・日本は、一八九五年から五十年間、台湾を統治してきたという歴史がある。もしも、その統治にいささかなりとも誇る点があると思うなら、その統治を経て形成されてきた台湾というもの、その台湾の民主化と台湾化の問題に、日本全体として、もう少し関心をもつべきではないか。 ・日本が、台湾に対してどのような出処進退を示すのか、アジアの国々は注意深く見守っていると思うのである。 ・私は、台湾人がほんとうにみずからの意思にもとづいて中国回帰を選択するのであれば、日本はそれに反対する立場にはないと考えている。 ・台湾の将来に関しては、その歴史的背景の重みを考えるのであれば、台湾みずからが自由な意思で選択した結果を日本は謙虚に受けとめるべきだと、私は思う。 ・中国の断固たる政策の下でなお、台湾が、東アジア共同体の下に静かに着地していくように、日本が、知恵を出し、汗をかくこと、そこにいまの時点における日本としての積極的な外交の場所があると思うのである。 第五章 原爆投下をアメリカに抗議すべきか 1 三つの見かた 原爆投下は必要だった――“正統派” ・長谷川毅氏は、原爆投下に対する見方を "正統派" "修正派" "新正統派" の三つに分けて分析している。 ・ "正統派" の議論は、「原爆投下は必要であり、正当な行為だった。原爆の投下は、戦争を直接的に即刻終わらせるためにおこなわれ、意図したとおりの結果が生じ、数百万のアメリカ人および日本人の命を救った」というものである。 原爆は戦争早期終結のために落されたわけではない――"修正派" ・ "修正派" の議論は、この対極に立つ。 ・ひとつは、原爆投下がなくても、また、ソ連の参戦がなくても、終戦を企図していた日本は一九四五年の秋には降伏していたという見方。 ・もうひとつは、トルーマン大統領は、戦争の早期終結のために原爆を投下したのではなく、別の目的のために投下した。 ・たとえば、冷戦構造が顕在化する過程で、ソ連に米国の力を見せつける、ないしは、原爆の投下によって、ソ連の参戦を未然に防止しようとしたという見方である。 ・ "修正派" の議論の、もっとも有力な根拠のひとつになっているのが、一九四六年七月の戦略爆撃調査報告の「原爆の投下、および、ソ連の参戦のいずれがなくても、日本は、四五年十二月一日までには確実に、十一月一日までにはすべての蓋然性をもって、降伏していたであろう」というものである。 ・ガール・アルペロヴィッツは、一九六五年、『原子力外交 ― 広島とポツダム』を出版、、 「一九四五年夏には日本は、天皇制の維持を許されれば降伏していた、トルーマン大統領とその側近は、そのことを知っており、意図的にその条件を示さず、代わりに、日本がそのままはのめない条件を提示した」という衝撃的な論述をおこなった。 ・鳥居民が日本には基本的降伏の意思があったことを述べたうえで、「トルーマンとバーンズ(国務長官)は、原爆投下の大公開を終えたら、ソ連軍が満州に侵攻する前に日本を降伏させてしまいたいと望んでいた」と記した。 多様な見方の組み合わせ――"新正統派" ・ "新正統派" は、 "正統派" と "修正派" のあいだに位置づけられることになるが、その考えかたは、多様である。 ・新正統派の考えかたを検討するために、この問題に関するすべての理論的可能性を整理すると、以下のようなことになる。 Ⅰ 日本の降伏については ①日本は、いずれにせよ、降伏する状況になっていた ②基本的には、原爆投下のみによって降伏を決断した ③原爆の投下よりも、ソ連の参戦によって、降伏する決断をした ④すみやかな降伏のためには、原爆投下とソ連参戦が双方あいまって効果を発揮した という四つの見方が成り立ちうる。 Ⅱ 原爆を投下したトルーマンの意図については、 ①日本の早急な降伏を主眼として原爆を投下した ②なんらかの別の目的のために原爆を投下した という見方の二つに大別される。 議論白熱中 ・太平洋戦争終結の時点で、自国兵士の命を救うために、敵国非戦闘員の命を奪った論理が、今後ともに、正当化されるのか。 ・原爆という兵器に内在する、非人道性を最初に指摘したのは、投下直後の日本政府であり、また、東京裁判で「日本指導部の殺人の責任を追及するなら、まさに、米国指導部の殺人の責任を追及すべきではないか」との論陣を張った、ベン・ブルース・ブレークニーである。 なぜスターリンの思惑を容認したのか ・【アメリカの原子爆弾製造計画は、一九四一年秋、ルーズヴェルト大統領の命令によってマンハッタン計画として開始された】 ・原爆完成の暁には、日本に対して使用されるべきだという決定が米英間でなされた。 ・【原爆投下の最終決断は、一九四五年七月十八日から八月二日までおこなわれたポツダム米英ソ三ヵ国首脳会談を背景として下された】 ・まず、七月十八日朝、ポツダム滞在中のトルーマン大統領に、原子爆弾の実験成功の最初の報告が届けられた。大統領は、このニュースをチャーチル首相にのみ伝えた。 ・七月十八日午後の米ソ首脳会談で、トルーマンはスターリンに、原爆実験成功のニュースを伝えなかった。 ・逆にスターリンは、トルーマンに対し、天皇が終戦を企図しソ連に仲介を求めてきたという正確な情報を伝達した。 ・そこで両者は、日本がソ連の斡旋に脈があると信じるように対応することに合意した。 ・講和を求める日本に対し「時間かせぎをする」ことが米ソ最高レベルで合意されたのである。 ・第一の疑問 スターリンにとって、日露戦争でロシア帝国が失ったものを日本および中国からとりかえすために、なんとしてでも日本の降伏の前に参戦することが必要であり、二月のヤルタ会談と七月~八月のポツダム会談がそのための壮大な権謀術数の場となった。 ・日本の降伏前に参戦することが、ポツダム会談の時点で、スターリンにとって至上の課題になっており、したがって、スターリンの立場からすれば、近衛文麿特使派遣に対して「時間かせぎをする」のが、当然の要請だった。 ・しかし、なぜトルーマンが、スターリンのこの「時間かせぎ提案」に賛成したのか。 ・第二に、当時のアメリカの指導部の知日派は、一致して国体護持を条件として、日本を降伏させるという案を献策していた。なぜ、トルーマン大統領は、「知日派の国体護持条件案を採用」しなかったのか。 なぜ「原爆投下なしには戦争が終わらない」と考えたのか ・【七月二十五日、スティムソン陸軍長官とマーシャル陸軍参謀総長によって原爆投下の命令が承認された】 ・この命令が、ポツダム宣言発出の前日に出されていることは、注目に値する。 ・すなわち、日本の降伏自体は、原爆の投下によるショックを経ずには実現しえないという見とおしがあり、ポツダム宣言は、日本の降伏意思が確定したときに、同意すべき条件を明示したものであるということになる。 ・なぜ、トルーマンは、「原爆投下なしには戦争が終わらない」と考えたのか。 ・これが、第三の根本的な疑問である。 ・この点は、多くの日本人が、これまで十分に理解してこなかったことであり、 "正統派" "修正派" "新正統派" の論争の大きな焦点も、まさにここにあるといってよいように思われる。 トルーマンの胸中は…… ・トルーマンの考えをさぐる、二つの見かた ・ひとつは、この決定的に重要な意思決定の時期、すなわち、七月十八日午後の「時間かせぎ決定」、七月二十四日のポツダム宣言最終案の決定、七月二十五日の原爆投下命令発出の時点で、トルーマンは、日本の戦略企図をまったく信用していなかったという説である。 ・無条件降伏をめぐる東郷外務大臣と佐藤尚武駐ソ大使とのあいだの外交電報の解読(マジック)が、日本政府には早急な降伏意思なしという印象を与えたというものである。 ・もうひとつは、トルーマンは、原爆投下のショックによる強制降伏シナリオという確定シナリオを、すでにもっていたという見かたである。 ・いずれにせよ、事態は、このあと、アメリカ指導部にとって、ほぼ想定どおりに進む。 ・日本政府は、ポツダム宣言の受諾をめぐってもたつき、八月六日と八月九日、予定どおり、二発の原爆が広島と長崎に投下された。 2 無条件降伏と国体護持のあいだで 近衛特使派遣をめぐって ・一九四五年四月七日、鈴木貫太郎内閣が成立した。茂徳は、戦争終結を目的として、外務大臣として入閣、終戦への意思統一の場として、総理、外務大臣、陸軍大臣、海軍大臣、陸軍参謀総長、軍令部総長からなる最高戦争指導会議構成員会議(いわゆる六者協議)を主導。 ・議題としては、 ①ソ連の参戦防止 ②ソ連の好意的な態度への誘致 ③和平への誘導 の三点を核とする、対ソ政策がとりあげられた。 ・世界の大国のなかで、唯一日本と中立関係にあったソ連との関係を有利に使おうという軍の思惑を活用し、和平にもちこもうと考えたのであった。 【私見 : 裏話を知らない日本は、ソ連や米英にいいようにされていたのだ】 ・交渉は、マリク駐日大使と広田弘毅元首相とのあいだで進められることとなったが、二月のヤルタ会談で、独ソ戦終了後二、三ヵ月で対日戦に参加することを約束していたソ連は、引き延ばし戦術をとった。 ・けっきょく、日本の指導部は、七月十二日、天皇自身が、「戦争が速やかに終結せられんことを念願せられ」ており、そのメッセージを伝えるために、特使として近衛文麿公爵を派遣するという電報がモスクワの佐藤尚武大使に伝達された。 ・この時点で、特使派遣にいたった直接の契機は、ポツダムで開催されることになった、英米ソ首脳会談の前に、日本側の講和意思を明確に伝えることにあった。 ・次に、特使派遣提案においては、戦争終結の条件は、なにも述べられていない。 ・事前に訪れた東郷外務大臣に、近衛公自身が、「自分が向ふに行くやうになれば ・しかし、現地の佐藤大使からは、七月十五日初の電報第一三九二号で、「戦争終結の具体的提案を ・特使派遣にこぎつけるだけでも非常な努力を要した、具体的な条件を決めるとなれば、議論が百出し、そうなれば、和平の敷居は高くなるばかりとなる。 ・それよりも、特使に事実上一任のかたちをとり、もって、落としどころを探らざるをえないと考えた東京と、はっきりした和平の条件も提示せずに、和平が実現できるはずがないという現地の意見と、それぞれの立場から、理解しうるということだろうか。 ・だが、電報第一三九二号は、具体的な終結条件として、きわめて重要なもうひとつのポイントを含んでいた。戦局の不利なことと、連合国が、終戦の条件を日本側と交渉する意図がないことを論述したあと、佐藤大使は、「結局帝国において真実戦争終結を欲する以上無条件又はこれに近き講和を為すの他なきことを真に巳むを得ざる所なり」と述べたのである。 ・ここに、近衛特使派遣をめぐるもっとも大きな問題として、無条件降伏の問題が、真正面に登場する。 バーンズ回答 ・二十八日、鈴木首相は、強硬派の意見に動かされ、「政府としては、重大な価値あるものとしては認めず、黙殺し、断固戦争遂行に邁進する」とと発言、そのむね、二十九日の各紙が報じた。ロイター、APは、ただちにこれをreject(拒否)と報道した。 ・ここから事態は、八月六日と九日の原爆投下、九日のソ連参戦と、一気に暗転する。 ・けっきょく九日深夜から開催された御前会議で、国体の護持のみを条件としてポツダム宣言を受け容れるべしという和平派と、占領地域の限定、自主武装解除、日本自身による戦争犯罪人処罰の三条件をも要求すべきとするいわゆる継戦派との見解が対立、鈴木総理より、陛下の御聖断が求められ、国体の護持一条件によるポツダム宣言受諾に至った。 ・茂徳は、ソ連の参戦については、強い警戒感をもって対応していた。にもかかわらず、実際のソ連の参戦時期を見抜けなかった後悔については、七月十三日にモスクワの佐藤大使が「戦争終末に関する大御心」を伝えるために近衛特使を派遣したいと申し入れた際のソ連側の消極的な反応について、「日本に対し既に開戦の決意を為し……たと迄は想像し得なかったのは甚だ迂闊の次第であった」と述べている。 ・ソ連を通ずる終戦工作が、一億玉砕をとなえる軍部を説得して終戦を実現するための不可欠の方策だったとしても、最後の局面でなおかつスターリンの意図を見抜けなかったことに対する茂徳の痛切な反省と後悔の言葉であろう。 無条件降伏を支持していた人は誰もいなかった ・いわゆる「継戦派」が無条件降伏を受け容れた最低限の条件は、この和平派の提示した、国体護持が担保されるという理解にあった。 3 核の傘の下にいる “唯一の被爆国” 原爆投下の原因究明はなぜ遅れたのか ・おそらくそれは、戦後の国際秩序を形成した戦勝国アメリカ政府が「日本を終戦にもっていくためには、原子爆弾の投下が必要だった」という歴史認識を明らかにしていたことが、大きな原因だったのではないかと思う。 ・そういう状況下では、政府系、ないしは、日米同盟を大事に考える右派の研究者に、アメリカにとってきわめてセンシティヴな原爆投下の問題について、研究を深めるインセンティヴは、湧かなかったのかもしれない。 ・戦後つとに反米的な立場を強めた左派の研究者がなぜこの点を十分に研究してこなかったかは、それ自体考えさせる問題である。戦争については、まずもって、日本帝国主義への批判が先行したこと、米国史料を駆使した実証的な研究を不得手としたなどが原因なのかもしれない。 ・これが、原爆投下をめぐる議論における第一のねじれ現象と見る。 米国の核兵器には正面きって反対しにくい ・原爆投下をめぐる第二のねじれ現象 戦後ただちに始まった冷戦が米ソの核均衡によって維持され、わが国が、自国の安全保障を米国の核の傘の下に置いた結果、日本政府にとって、米国の核兵器には正面きって反対しにくい状況が生じたことによる。 ・冷戦下の米ソ対立の下で、日米安保をわが国安全保障の根幹に置いた日本政府にとって、対立する歴史認識の問題を日米両国間の政治問題として浮上させることの危険性は、あまりにも大きかったのである。 とにかく核は許さない? ・戦後一貫して反米の立場をとってきた野党、左派の市民団体、オピニオン・リーダーは、第三のねじれ現象といえるのではなかろうか。 ・冷戦下で日本の左の勢力は、理想主義的な平和主義に走り、現実主義的な対応のなかで米国の核をどうするかと考えることに不得手であったことが、絶対的な核兵器反対思想に結実したのであろうか。 ・実際に原爆の被害をこうむった人たちへの救済への要求は、原爆を投下した米国政府に対してではなく、日本政府に対して向けられてきたことと関連する。 ・日本政府がサンフランシスコ講和条約によって対米請求権を放棄した以上、必要な救済は、国みずからがおこなうべしというものである。 ・「とにかく核は悪いことだ」という理想主義的な価値観に立脚した立場を正面に押し立て、または、被害の救済を国から求めようとすることは、歴史認識としての広島・長崎への原爆投下をどう考えるかという問題に向きあうことにはならない。 ・「核の全面廃絶」という主張は、「核は必要悪」という現実主義の立場とは、正面衝突しかねないものがある。 綻びと転機と ・驚くべきことに、わが国は、この一見解決不可能なねじれをなんとか乗り越え、全体が破綻しない方式を見つけながら、すごしてきた。 ・その方式とは、 ◉歴史認識の問題は、語らない ◉目前の政策としては、日米安保のもとでの米国の核と世界の核均衡を支持 ◉長期目標としては核廃絶を主張し、その手始めとしてNPT体制を支持 というものだった。 長期的視点に立った日米和解に向けて ・原爆投下をめぐる歴史認識の問題について、日本がいま必要としていることは、この問題についての日本内部の分裂を克服し、日本としてのおおむねの方向性を打ち出すことである。 ・さらにこの問題をもっとも深刻なかたちで提起している中国と韓国とのあいだに共通の基盤を見出し、東アジアにおける和解を推進し、この問題が、日本と東アジアの外交の障害とならない合意をつくりあげることである。 ・エネルギーをまさにそこに注入すべきときに、アメリカとのあいだで新たな戦端を開くことほど、愚かな政策はない。 ・この問題で正面からアメリカ政府を叩くならば、今の時点では、アメリカのよって立つ正義への挑戦と受けとめられ、そのことは、同盟への根本的な挑戦と見なされかねない。これは、わが国の国益に裨益しない。 ・二〇〇七年七月十日、政府が、「(今の時点で)米国に抗議するよりも、核兵器のない平和で安全な世界の実現を目指して、現実的かつ着実な核軍縮努力を積み重ねていくことが重要である」と述べたのは、正しい方向を示していると考える。 ・三つのねじれを解消し、原爆投下問題に正面から向きあうためには、日本政府と日本国民は、いままでよりもはるかに大きな外交力を必要としているといえよう。 第六章 私のなかの東京裁判 「共同謀議」と「侵略」 ・東京裁判でとりあげられた論点で、自分として、無理なく賛成しうる議論。 ・第一に、歴史的な事実関係として、一九二八年から四五年まで「侵略戦争を企図し、計画し、準備し、主導した」共同謀議が存在したかという点についてである。 私は、このような「共同謀議」はなかったと思う。 ・第二に、かりにこの間の日本の行動全体が、中国から東南アジアにいたる「侵略」であったと認定したとしても、そのような行為を、国際法上違法性を追及しうる「侵略戦争」と認定しうるのか、かりに、そういう認定が成り立ちうるとしても、特定の個人に対して、その責任を刑事的に追求しうるかという問題である。この問題こそ、東京裁判の核心をなす「平和に対する罪」の法的正当性を問うものである。 私は、「平和に対する罪」を追及する法的な正当性は、なかったと思う。 「残虐行為」 ・第三に、東京裁判で裁かれた日本軍による残虐行為、ないしは、その防止業務を怠ったという問題である。 この点については、日本軍の行動の一部において「残虐行為」と言われてもしかたのない行動があったことは、否定しがたい事実のように私は思う。 ただし、パル判事の主張にように、東京裁判で処断された二十五名の被告が、その責任を負うべき立場にいたのかという問題は、別途の問題として存在しており、この関連で看過できないのは、およそ一国を国際法上の犯罪者として処断するのであれば、適用する法的な基準は、公正なものでなければならないということである。 戦後条約秩序のなかで ・敗戦国日本は、連合国によって、A・B・Cの三つの領域で戦争犯罪を追及され、判決をうけ、その判決を受諾した。判決の受諾は、サンフランシスコ条約第十一条に法的義務として規定された。 ・「平和に対する罪」によって処断されたことが、いかに納得できなくても、東京裁判の判決を日本政府が条約によって受諾している以上、日本政府は、もはやこのことに対して、異議を申し立てる立場にはない。 ・戦後秩序の根本をになう、サンフランシスコ条約第十一条に政府が異議を申し立てることは、日本が懸命につくのあげてきた、戦後の条約秩序を壊すことになる。正気の沙汰ではないとしか言いようがない。 ・現時点のいかなる責任ある政治家も、官僚も、オピニオン・リーダーも、けっして賛成すべきでない道だと思う。 日本は無条件降伏したわけではない ・誰しもが、日本を残すとき、国体の護持を条件として、と考えた。 ・皇室の安泰、天皇制の保持、国体の護持、表現の違いはあるものの、原爆とソ連の参戦という絶体絶命の状況下で、この点だけは守り抜こうというのが、終戦を主導した指導部の見解であり、ギリギリであっても、それを確保しえたという考えが、十四日の二回目の御聖断の背景となった。 東京裁判の隠れた意義 ・被告全体にとって、天皇陛下をお守りすること、すなわち、訴追はおろか、天皇を証言台に引きだすことも、肯んじないということが、東京裁判の隠れた意義だったのだと思う。 ・国体の護持を条件として戦争を終結した人たちの一致した気持ちが、東京裁判で絶対に天皇に累を及ぼさないという点に結集していたこと、このことのもつ重みを理解せずに、東京裁判を理解することはできないと思う。 ・そして、その観点から考えるなら、米国側の考慮がなんであれ、天皇を訴追の対象からはずしたことが、どんなに、適切な措置であったかわからない。 ・連合国の一部に、天皇訴追の考えかたは、たしかに存在した。そして、その力を抑えこみ、ポツダム宣言受諾に至る日本との約束が守られたこと、そこに、東京裁判がもった、重い政治的な意味合いがあったと思う。 反対意見の存在 ・東京裁判がもつもうひとつの特質は、「平和に対する罪」を訴追の根幹に据えながらも、この点に対する徹底的な反論を含めて、裁判所の構成自体のなかに、反対意見を活かす構造が存在していたことである。 ・ひとつには、米国から派遣された、米国人弁護士の役割がある。私の知るかぎり、被告側は、みな、自国の立場を離れて被告と国際法の真の適用の視点に立ち、歯に衣を着せない論陣を張った。これら弁護人の勇気に感動し、感謝している。 判事のなかの少数意見 ・もうひとつは、裁判官のなかの、少数意見であり、もっともひろく知られているのは、パル判事の「全員無罪」の見解である。勝者の側が、敗者を処罰する目的で設立された裁判で、「被告全員無罪」の判決を出す少数意見が表明されたということは、まことに驚くべき事態であると言わざるをえない。 ・かりにそれが裁判所の設立者の意図ではなかったとしても、また、それが裁判全体の基調にならなかったとしても、そういうことを可能とした裁判のしくみには、一定の評価があたえられてしかるべきではないか。 ・パル判事の見解について、清瀬氏は、「いわゆる『侵略戦争を準備し、またはこれを遂行するということは、太平洋戦争当時、 ・パル判事とは立場を異にするが、国際法の適用という観点から、勝者・敗者の立場を超えて独自の判断にいたり、広田弘毅被告に対する無罪を主張した、オランダのレーリンク判事の立場を評価する見解も多い。 被告人の考えを述べえたこと ・「平和に対する罪」という事後法により、勝者の立場から敗者を断罪した東京裁判の論理は、受け容れられない。 ・しかし、太平洋戦争の終結という、国際政治上の稀有の困難さをともなう事業を成し遂げるにあたって、その法的な構成要件が誤ったものであったとしても、裁判という形式をとったことにより、すべての被告は、おのれの信ずることを述べえた。 ・民主主義と言論の自由を標榜する米国の占領政策が、占領下で、激しい言論統制をおこなったことは、いまや、公知の事実である。しかし、裁判という形式があったがゆえに、その場所だけは、完全な言論の自由が保たれた。 【私見 : 他書では、戦勝国に不利な弁論や証拠採用が抑え込まれたという話はある。故に完全な言論の自由があったとは思えない。あくまでも限定された枠の中での自由ではなかったのか】 ・清瀬一郎弁護人が、東京裁判を回顧して、「当時、日本国内で、自由率直の発言ができたのはこの法廷だけであった」「法廷なればこそ連合国の違法も、わが国の自衛権も、正々堂々、だれはばからず主張することができた。いかに耳ざわりでも、とにかく、これを許さねば道理が立たぬ。法廷以外では、その半分の主張も許されぬ。そのことは当時の占領政策の実際としてわかっている」と述べていることの意義を、軽んじることはできない。 ・裁判という形式があったがゆえに、戦争に臨んだ人たちの考えかたが、敗戦と占領という異常事態のなかで、もっとも凝縮されたかたちで、歴史に残ったとするならば、そこに、この裁判の今日的な意義の一端があるのではないか。 ・このことは、「平和に対する罪」の事後法的不当性をなんら正当化するものではない。 ・しかし、東京裁判が、日本とアジアの歴史のなかでもった多面的な意味を考え、それが歴史のなかでもった意義をそれなりに位置づけることができるなら、心を平らかにして、この裁判の意義と不当性について、時間をかけた学術的な論考を積み重ねることができるのではないだろうか。 重い問いかけ ・アメリカ要路の大部分は、アメリカは、中国に対する侵略国日本から真珠湾攻撃という恥ずべき不意打ちをくらい、正義の名によって、日本を叩き潰したと、認識している。 ・政府レベルで、あるいは国会を含む公のレベルで、私は、この問題をいまけっしてアメリカに提起すべきではないと思う。それは、まったく不要な過去の亡霊をもって、未来の日本外交の立ち位置を脆弱化させることになる。わが国の国益に、けっして、プラスになることではない。 ・だが、日本として、なにもしないのか。 ・民間における研究と議論は、今後も、続けていったらよいと思う。 ・その際、東京裁判のもつ多面的な側面には、十全の注意を払ったらよいと思う。 ・平和に対する罪への批判は、私は、揺るぎがないと思う。 ・しかし、無条件降伏を拒否して降伏した日本が、東京裁判という過程を通じて、昭和天皇を守りえたこと、それは、二十五名の被告団の総意であると同時に、米国占領行政の結果であったことも、忘れてはいけないと思う。 ・日本人として、そこには、日本民族とはなにか、皇室とはどういう意味をもつかという、今日的な、重い問いかけが発生する。 オール・ジャパンとして――あとがきにかえて ・歴史に関心を寄せない民族に、大きな将来性があるとは思えない。 ・だが、わが民族の、歴史に対する関心を見ていると、もうひとつ、そこに、猛烈な内部対立があり、巨大なエネルギーが、その内部対立に割かれていることを感じざるをえない。 ・歴史と民族のアイデンティティに関するわが国内の議論は、相互尊重にもとづく対話というよりも、人格攻撃を含む、猛烈な相互攻撃の渦のように感ぜられるのである。 ・多数の国民が、左右の思想家の論述を、自分の頭で整理し、考え、自分の考えかたをつくっていく。それが、社会や国家としてのコンセンサスづくりにつながっていく、そういう動きこそ、いまのわが国は、必要としているのではなかろうか。 ・わが日本は、明治維新から太平洋戦争までの七十七年の栄光を敗戦によって失った後、六十三年のあいだ、どうやって民族の誇りを回復しつつ世界のなかで尊敬される日本になるかという課題を実現すべく、漂流を続けてきた。 ・もうそろそろ、歴史問題について、オール・ジャパンとしての大きな方向性を見出し、それを、日本社会のコンセンサスのなかに着地させ、世界との調和を実現する時期にきたのではないか。 * ・異なった意見をもつ相手を尊敬しながら議論を展開する力を身につけ、人格的相互攻撃で空費されるエネルギーを抑制すること、そして、民族のエネルギーを、日本社会の力と日本人の創造性を開化させる積極的な方向に向けること――意思と、指導力があれば、それは、実現できるはずである。 ・一人ひとりの日本人が、そういう認識を強めることが、オール・ジャパンとしての共通なメッセージになり、それが、世界全体に受け容れられるものになっていく。遠回りのようでも、そういう道筋をめざすことが、この問題を乗り越えていく、王道だと思う。 ―― 完 ―― |
||||||||||||||