
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年05月16日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |||||
26 |
17/03 |
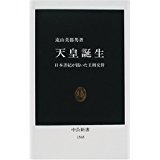 |
天皇誕生 |
遠山美都男 |
中公新書 |
◎ |
序章 万世一系と王朝交替と 「日本国は万世一系」 ・『宋史』日本伝によれば、僧 「わが国王は、王をもって姓となし、世襲して今の王に至るまで六十四世になります。また、文武の官僚もみな世襲となっております」 と、奝然は告げたという。 ・――島国の夷人にすぎない日本には王朝の交替がない、そればかりか大臣や臣下の世襲も実に簡単に実現を見ている。それはまるで、中国で伝えられている、はるか古の聖人の世のようではないか。わが中国も日本のようでありたいものだ。 太宗は長いため息とともに一気に喋った。 ・中国では、天(天帝)という絶対的・超越的な存在の指名と命令(いわゆる天命)をうけた者が皇帝となり、その子孫がその地位を継承していくのであるが、この皇帝を出す一族、さらには歴代の皇帝を中心に形成された支配組織を総じて王朝とよぶ。 ・天が皇帝にもとめたものは、全世界の民をわが子のように愛し慈しむことのできる徳(人徳)の質と量であった。 ・したがって、天によってそれがなくなったと判断された時には、皇帝の座は別の一族に移動せざるをえない。 ・王朝が交替するということは、天命が替わる(革まる)こと(革命)、それも天命が別の人物、別の一族に替わること(易姓)、すなわち易姓革命とよばれていた。 ・日本の天皇は古より同じ一族からえらばれ続けている、すなわち万世一系であるという主義・主張が、平安前期の日本人のなかにすでに明確にあった。 王朝とは何か? 王朝交替とは? ・六世紀以前は、王位が血統によって継承されておらず、王にふさわしい人格・資質の持ち主を求め、王位が複数の血族集団のあいだを移動していた段階なのである。 ・特定の一族から倭国王が選出されたとしても、わずか数代なのであるから、これではとても世襲とはいえない。 ・ともかく、血統による世襲という観念が未成立であった以上、そこに王朝の概念を適用することは不可能なのである。 本書の課題――二つの物語=世界の発掘 ・『日本書紀』の記述をそのまま素直に読めば、そこに万世一系の皇位継承の歴史が描かれていると考えられるかといえば、かならずしもそうはいえないと思われる。 ・なぜならば、『日本書紀』の記述、とくに六世紀初頭の継体天皇以前の部分を子細に読むならば、そこに天皇を中軸としながらもそれぞれに主題を異にする二つの物語、あるいは二つの世界が存在することに気づくからである。 ・この二つの物語=世界にそれぞれの王朝の名を冠することもゆるされるのではあるまいか。 Ⅰ 律令制国家と天皇――その誕生の物語 1 イワレヒコの東征――神武天皇 始祖王、イワレヒコ――神々の聖なる混血 ・神武天皇といった場合の神武とは、推古・天智・天武といった歴代天皇の漢字二字より成る名前と同様に、奈良時代の終わり頃、 ・また、天皇という称号が用いられるようになったのも、七世紀後半に下ると考えられる。 ・イワレヒコが神々の聖なる結婚の所産であるという設定は、神武に始まるとされる天皇(あるいは天皇家)が、この日本列島を領有・支配するいわれを説明しようとして考え出されたものであろう。 ・日本列島のうち山や海を領有・支配していた神々の血筋を婚姻を通じて取り込むことによって、列島内の山海という特殊領域の領有権や支配権まで手に入れることになった。 ・イワレヒコが実在の人物であったか否かを議論するよりも前に、初代天皇となる彼が、天皇による日本列島統治の起源や正当性を説明する必要から、いろいろな神々の混血という系譜的位置をあたえられていたとする設定のほうを重視すべきであろう。 東征の起点――なぜ日向なのか? ・日向の高千穂の峰というが、実際にそのような高峰があったわけではない。高天原という天上の世界から降り立つには、そのような高峰がふさわしいだろうということで、考え出された空想上の地名にすぎないのである。 ・天神=日神の子孫であるニニギノミコトが降り立つにふさわしい場所を日本列島の内部に探すならば、やはり天や日(太陽)に関係の深い場所やそのような地名のある場所がよいということになる。 ・日向国は南九州の東端に位置し、九州島のなかで太陽が上る方角に位置しているということで、古くから「日に向かう(場所)」 → 「日向(ヒムカ)」とよばれていた。 ・「日に向かう場所」ということでヒムカという名をもった土地は日本列島の各地にあったであろう。しかし、ある時期以降は、南九州の日向が最もポピュラーなヒムカだったということである。 ・ニニギノミコトの降臨地は、このようにしてえらばれ、決定したと考えてよいであろう。 ・いわゆる天孫降臨神話は、天皇家の先祖がかつて南九州の地にあったことを物語るものではありえないのである。 なぜ東征するのか?――イワレヒコのたたかい(一) ・南九州にあった勢力が、かつて大挙して東に向かって攻め上ったことがあったという、そのような歴史的な記憶が神武東征説話(神話)に結実しているのだという見方があるが、それは妥当とはいえない。 ・太陽がのぼる方角である東に向かう、東に向かってたたかうというのは、天神=日神の子孫の採るべき行動として最もふさわしいと考えられた結果であろう。 ・天神=日神の子孫であるニニギノミコトが高天原から降り立った日向国から、そのニニギノミコトの子孫とされる実在の天皇たちが政治的拠点としていた大和国までの物理的な移動を、できるだけ合理的に説明する必要があったのである。 ・イワレヒコの東征とは、そのようにして生み出された壮大な虚構なのであって、九州にあった勢力が大挙して東に攻め上ったなどという歴史的事実がいくらかでも投影されているとは考えがたい。 大和を制圧せよ――イワレヒコのたたかい(二) ・天皇は日本列島のみならず朝鮮半島をも領有・支配する大国の君主と見なされていた。その初代である神武が日本列島全体を制圧したのではなく、あくまでも大和の中心部のみを制圧したことが強調して語られているということは、これに続く物語は、神武に始まって天皇の地位と権力が変化・発展していくさまを描こうとしているのだと予告しているのに等しいといえよう。 2 神々のむすめとの密月――綏靖天皇~開化天皇(欠史八代) 欠史八代は実在の天皇? ・ 欠史八代の名前とその正体 ・欠史八代の天皇とは、その名前から分析する限り、おそらく大和やその周辺で祭られていた神々あるいは精霊であった。そのような神々や精霊の名前に、後世の天皇の地位に関わる尊称や称号を冠することにより、いかにも実在した天皇の国風の諡号のようにみせかけ、八代の天皇を創造しようとしたものと考えられる。 ・欠史八代の天皇とは、実在した天皇よりも数多くの天皇の存在が必要になったために、急拵えで創造された天皇たちであったということができるだろう。 なぜ父子直系で、しかも長寿なのか? ・七世紀末になって、皇位の継承は父子直系で行なおうということになったことは間違いない。 ・天皇家の系譜を実際よりも古く、威厳のあるものに見せかけようとして、系譜を古い時代に向かって思い切り延長しようと試みた。 ・その結果、その伸び切った長い長い系譜を埋めるため、幾人かの天皇の創出が急務になる。 ・父子直系の虚構と長寿という虚構とは、同一の目的達成のために、お互いに助け合い、そして補い合う関係にあったと考えるべきなのである。 なぜ、県主のむすめと結婚したのか? ・欠史八代の天皇のみが (※)県主 = 天皇家の直轄領である県の中心に祭られている神々の祭祀を統括する役目を世襲した、いわば神官的な氏族。 ・大和の在地の神々を祭る県主一族との姻戚関係の積み重ねによって、天皇家は大和とその周辺に着実に根を下ろしていったのだと描き、印象づけることが、この虚構を創出した一番のねらいであろう。 3 ハツクニシラス天皇――崇神天皇・垂仁天皇 祭祀・葬礼に関わる王たち ・崇神天皇はミマキイリヒコイニエといった。 ・垂仁天皇の名前は、イクメイリヒコイサチという。
・崇神天皇の名前は「特定の墳墓を祭る御方」という意味ではないか。 ・この「特定の墳墓」とは箸墓、すなわち、最近になって卑弥呼の墓ではないかとの声がますます高まっている箸墓古墳を指す可能性が十分にあるだろう。 ・ノミノスクネの話は ・つぎの殉死を禁止する話が、葬礼に関わるものであることはいうまでもあるまい。ノミノスクネを始祖とする土師連が大王・天皇の葬礼に奉仕する氏族であったことも、そのことを裏書きしている。 ・崇神や垂仁の名前は、神々の祭祀や葬礼に関わる特別な人格であることをあらわすものであった。 ・もちろん、崇神・垂仁の名前は、天皇の固有名として伝承されてはきたが、もともとは、特別な霊力をそなえている貴人、あるいは、特別な場や空間で霊的能力を発揮する高貴な人を指してよんだ普通名詞と考えたほうが妥当であろう。 4 疾風、ヤマトタケル――景行天皇・成務天皇 景行天皇――それは、顔のない巨人 ・垂仁天皇の後を継いだ景行天皇は、日本列島の軍事的平定を果たした天皇とされる。 ・たしかに景行自身、九州に出征し、熊襲を平定した物語が伝えられているのである。熊襲とは南九州の在地勢力の総称であり、 ・東奔西走して日本列島の平定に尽力した最大の功労者は景行の皇子、ヤマトタケルノミコト(日本武尊)である。 ・景行天皇の名前は、オオタラシヒコオシロワケと伝えられている。 ・オオタラシヒコとは、偉大なる天皇であることをあらわす称号にすぎないのであって、ひとり景行のみの固有の名前ではありえない。 無名の武人たちの墓碑銘――ヤマトタケルのたたかい(一) ・景行天皇の命をうけ、景行に代わって日本列島の軍事的平定にあたったのが、景行の皇子、ヤマトタケルであった。彼の活躍なくして日本列島の統一は実現しえなかったかのように描かれている。 ・ヤマトタケルという名前は彼の実名ではなく、彼が天皇の命を奉じて討ち取った熊襲の首領、カワカミノタケルから献上されたものということになっている。 ・ヤマトタケルという名前は「ヤマトに住むタケル(勇者、勇猛な武人)」の意味であり、あくまでも普通名詞である。 ・タケルの上に地名を冠すれば、幾人もの勇者の名前が出来上がるわけであり、ヤマトタケルという名前も、決してひとりの人間に占有されるものではなかったと考えられる。 ・『日本書紀』におけるヤマトタケルは、景行天皇の息子で、父の命をうけて独り各地を転戦したことになっているが、実際には、大勢の名もなきヤマトタケルがいたはずである。 ・ヤマトタケルとは、かれら名もなき武人たちの集合霊的な存在と見なしてよい。 ・景行天皇に代わって日本列島の軍事的な閉廷を遂行したヤマトタケルが、景行の皇子であったとされたのは、一体どうしてであろうか。 ・それは、天皇に代わって日本列島の平定を遂行したのが天皇と血縁的にまったく無縁の人間であってはならず、むしろ、できるだけ天皇に近い血縁者でなければならないと考えられたからであろう。 5 皇后、海をわたる――仲哀天皇・神功皇后 夫は英雄の遺児、妻は巫女…… ・仲哀の皇后はオキナガタラシヒメノミコトといった。いわゆる、神功皇后である。 ・タラシヒメというのはタラシヒコの女性版であって、女性の天皇(女帝)を意味する普通名詞と考えてよい。 ・神功皇后の身にはたびたび神々が憑依しており、彼女は神の意志やことばを口にしている。彼女は、憑依・脱魂の状態で神霊の意志を告げる能力をもった女性、即ち ・彼女は巫女としての能力をそなえている上に、皇后であり、後にはその子応神天皇の摂政をつとめたというから、日本列島を代表する最高首長の地位にあった女性といってよい。 なぜ、新羅征伐なのか?――神功皇后のたたかい(一)
・朝鮮半島に形成された諸王権と倭国とよばれていた日本との本格的な交渉の歴史は四世紀にさかのぼる。 ・倭国はまず、朝鮮半島西南部を領していた百済とのあいだに軍事同盟を結んだ。奈良県天理市にある ・倭国は七世紀、中国的な国家形成を急速に推し進め、その結果、七世紀の末から八世紀初頭にかけて律令制を根幹とした中央集権国家を出現させた。 ・天皇を中心とした日本の律令制国家は、大唐帝国と同様の大国という認識をもっていた。というよりも、唐と対等の世界帝国であるという独善的な思想が、その国家体制の支柱にほかならなかったのである。 ・そのため、倭国改め日本は唐を「隣国」と限定した。そして、朝鮮半島を統一し、支配している新羅を「諸蕃」と称して、天皇に朝貢する異民族の国家と見なしたのである。 ・『日本書紀』が編纂された八世紀の前半、朝鮮半島を統一的に支配していたのは新羅であり、日本はその新羅を天皇に服属し、朝貢を行なうべき異民族の国家と見なしていた。 ・そのような日羅関係の歴史的な起源を説くために、神功皇后の物語は創造されたと考えられる。 「神功皇后は卑弥呼である」? ・『日本書記』は、オキナガタラシヒメこと神功皇后が、『魏志』倭人伝に見える女王・ ・『日本書記』の編纂者はたしかに『魏志』倭人伝を読んでおり、そこに見える女王・卑弥呼の生存年代が、『日本書記』のなかで設定された神功皇后の生存年代と大体において合致すること、それに加えて、『魏志』倭人伝に記された卑弥呼が「鬼道」という呪術・祭祀に関わる女性であり、神功皇后も巫女としての能力をもっていたと伝えられていたことなどから、「卑弥呼=神功皇后説」を確信するに至ったようである。 ・また、『日本書記』編纂者がわざわざ『魏志』倭人伝を持ち出してきて、神功皇后が卑弥呼であるなどと主張したのは、『魏志』倭人伝を書いた中国や中国人というものを過剰に意識していたためではないか、と思われる。 ・しかし、まず、卑弥呼とは一般的にいわれているような邪馬台国の女王ではなく、『魏志』倭人伝のなかでは、邪馬台国をはじめとした数十の国々より成る倭国の女王とされていた。 ・つぎに、卑弥呼というのは女王の個人名というよりは、特定の女性が就任する地位・身分の呼称と考えるべきである。 ・卑弥呼という地位・身分は、女王の地位・身分をあらわす呼称ではなく、倭国王(男性)の近親女性でシャーマンとしての資質にすぐれた者が就任し、倭国王の正当性を宗教的に保証した地位・身分のことなのではないかと考える。 ・『魏志』倭人伝に描かれた卑弥呼は、倭国内部の行政に関与できるような立場にはなく、彼女はあくまでも「鬼道」という祭儀にのみ奉仕する巫女だったようである。 ・この卑弥呼という地位・身分は、二世紀の後半に起きた最初の倭国大乱の後に、統一が成った西日本一帯を支配する倭国王(邪馬台国王が選ばれた)の地位を宗教的に支えるために創出されたものであった。 ・そして、三世紀半ば頃の二度目の倭国大乱の後、西日本に加えて東海・中部地方が新たに倭国王の統合に加わるようになると、卑弥呼とよばれる役職はその姿を消し、新たな政治的統合のシンボルとして創造された前方後円墳をはじめとした巨大な墳墓(古墳)とその祭儀に代わられることになった、と考えられる。 ・要するに卑弥呼とは、第一次倭国大乱と第二次倭国大乱のはざまにのみ存在し、その間の倭国王の政治的支配を支えた、この時期に固有の地位・身分であったということである。 ・これまで、卑弥呼を女王、それも巫女王と信じて、だれもが微塵も疑わなかったのは、『魏志』倭人伝にそのように明記してあることに加えて、『日本書記』がその叙述のなかで数少ない巫女王として描いていた神功皇后こそ、『魏志』倭人伝に見える卑弥呼であるという独自の解釈を示していたことに原因があると思われる。 ・卑弥呼の巫女王としての風貌が強調されてきたのは、『魏志』倭人伝に対する史料批判の不徹底に加えて、正真正銘の巫女王、神功皇后の存在(ただし、実在の人物とはいえない)が卑弥呼のイメージを固定し、さらに増幅する役割を果たしてきたからであるといえよう。 応神朝は渡来ブーム? ・古代において、日本列島に中国大陸や朝鮮半島などから、実に多くの人びとが渡来してきた。 ・列島各地に居住している秦氏のすべてが同一の血族から構成されていたわけではなかった。 ・おそらくは朝鮮半島の南部から、時機を異にして列島の各地に渡来した諸集団が、ある時期に治天下大王に対して同一の奉仕を負うことになった。秦氏の場合、その機織りの技術が買われて、大王に献上する調布を製造する職務があたえられたようである。 ・それを契機に成立したのが秦氏であり、日本列島に到来した、いわばアカの他人どうしが王権に対する奉仕の共通性によって擬制的な同族としてまとまったというのが秦氏の実態であった。 ・アチノオミ・ツカノオミ父子に始まる ・秦氏や東漢氏などの有力渡来系氏族は、その氏族としての成り立ちから「諸蕃」とよばれていた。 ・ちなみに、天皇・皇族を始祖とする氏族は「皇別」、神々の後裔氏族は「神別」とされたのに対し、渡来系氏族は「蕃別」ではなく「諸蕃」とされたのである。 ・「諸蕃」とは、当時の法制用語であり、日本列島外部にあって天皇に従属・朝貢する異民族の国家のことで、現実には新羅や ・秦氏や東漢氏などを構成した諸集団が日本列島にやって来た時期は個々バラバラなのであって、かれらが「胎中天皇」=応神の時代に一族うち揃って渡来・帰化したというのは、『日本書記』が創造した歴史的な幻想にすぎないのである。 Ⅱ 中国的王朝――その興亡の物語 2 反乱、また反乱――履中・反正・允恭・安康天皇 二人で一人前?――イザホワケとミツハワケ ・『宋書』倭国伝は、多少の誤解や偏見もふくまれているとはいえ、ノンフィクションとして書かれている。 ・他方『日本書記』は、一定の主題・構想のもとに書き下ろされたフィクションと考えるべきである。 ・したがって、前者に見える人物が後者にあらわれる人物とまったく同一人物である、という断定のしかたは不正確であり、みとめられない。 ・せいぜい、前者(ノンフィクション)のなかに見える人物は、後者(フィクション)に登場する人物の実在のモデルの可能性がある、といえる程度であろう。 ・讃や珍という名前は、倭国王の名前を漢語に翻訳したもの、すなわち、倭国王の名前の本質に相当する部分を取り出し、それと同じ意味をもった漢字を当てはめたものと考えられる。 オアサツマワクゴノスクネ――存在感ゼロ、なのに偉大な天皇 ・允恭天皇は、あくまでも仁徳に始まる王朝の興亡・盛衰物語というフィクションの一登場人物にすぎない。 ・ウジ・カバネ制度について ウジとは、大王(天皇)に奉仕する政治的な地位を父系で相続していく一族を意味する。 他方、カバネとは、その政治組織内部における各豪族のランキングを示した称号である。 ・ウジの標識であるウジナ(たとえば、 ・ウジ・カバネ制度が成立する条件が出揃うのは、やはり六世紀の前半を待たねばならないと考える。 ・『日本書記』などに見える天皇の血縁関係をたよりに、倭の五王が『日本書記』の何天皇に相当するかを論議すること自体、大きな疑問と限界がある。 3 大いに悪しき天皇――雄略天皇 鉄剣銘文のワカタケルノ大王 ・埼玉県 ・「辛亥年」は、古墳の築造年代( ・ワカタケルノ大王は『宋書』倭国伝に見える倭王の武と同一人物と考えられる。 ・当時、中国から倭国とよばれていた日本は、二世紀初頭以来、中国の王朝に従属・朝貢し、その ・しかし、この倭王武の時代に、従来どおりの朝貢を行ない冊封はうけながら、中国の王朝(この場合は南朝の宋)からは自立の途を歩み始めることになった。 ・すなわち、中国の皇帝の支配がおよぶ範囲を天下といったが、倭王武は、その支配領域(彼のいい分によれば、日本列島と朝鮮半島の南部)が中国皇帝の天下の一隅に位置するにもかかわらず、それを指して大胆にも天下と称するに至ったのである。 ・『日本書記』に見える雄略天皇は、あくまでも仁徳に始まる中国的な王朝の興亡・盛衰物語というフィクションのなかの一登場人物にすぎない。 ・それに対して、辛亥銘鉄剣に見えるワカタケルノ大王は、明らかに五世紀後半に実在した倭国王である。 4 繰り返される断絶と再生――清寧・顕宗・仁賢・武烈天皇 継体は応神五世孫? ・継体は、六、七世紀に実在した大王(正確には治天下大王)の直接の起点となった欽明天皇の実父とされているから、その実在性をことさらに疑う必要はないと思われる。 ・『日本書記』が描く皇位継承の上では、たしかに武烈と継体は連続しているが、武烈と継体のあいだには大きな断絶が横たわっていることを見のがしてはならない。 ・武烈は仁徳天皇に始まる物語=世界の一登場人物であるが、他方、継体はそのような虚構のなかの人物ではなく、間違いなく実在の人物だったのである。 終章 再び、万世一系と王朝交替と 二つの物語、二つの世界 ・七二〇(養老四)年に完成した『日本書記』の継体天皇以前の叙述(神代紀はのぞく)には、大きく分けて二つのまとまりが存在した。二つのまとまりには、それぞれに明確な主題があって、それぞれの主題にもとづいて独特の物語が構成されていた。 ・最初のまとまりは、神武天皇に始まり応神天皇に終わる物語であり、実際には七世紀末から八世紀初頭にかけて成立した律令制国家とその最高首長である天皇の地位と権力が、どのようなプロセスをたどって形成されたかを解き明かそうとする主題に貫かれた部分である。 ・そして、もう一つのまとまりは仁徳天皇に始まり武烈天皇に終わる物語である。それは、日本にもかつて中国的な王朝が存在したことを主張し、その興亡と盛衰のさまを具体的に描こうとするものであった。 天皇、および日本の誕生 ・『日本書記』が出来上がったのは、日本という国号が誕生してから、わずか二十年足らず後のことで、日本の国号は七〇一年に施行された大宝律令において正式に採用されたのである。『日本書記』はできて間もない国号をその書名に冠したことになる。 ・そして、日本国号と関係の深い天皇という君主号が、従来の治天下大王の称号に代わって採用されたのは、六八九年施行の ・天皇号および日本という国号は、いずれも世界帝国としての唐という国家を強烈に意識して形成されたものであった。 ・まず、天皇という称号についてであるが、天皇とは、中国の儒教においては天皇大帝あるいは ・唐の第三代皇帝である高宗は、六七四年(わが国の天武天皇三年)に皇帝の称号に代わり天皇号を採用していた。 ・天皇号についで成立した日本国号は、倭国がかつて、隋やその後を継いだ唐から「 ・「日出処」や「日出国」といえば、所詮、隋・唐から見て東方に位置する国家という意味合いにすぎなかった。 ・だが、それに対し日本というのは、隋や唐の東方にある国家という意味にとどまらず、天空に昇りきった太陽の真下(それはすなわち、世界の中心ということになる)という意味をもふくむことになる、実に大胆不敵な自称なのであった。 ・このように日本の国号は、それまでの「日出処」「日出国」とは決定的に異なって、やや先行して成立を見た天皇号と同様に、大唐帝国と同質の世界帝国としての自国を表現しようとした呼称だったのである。 なぜ、書名が『日本書記』なのか? ・『日本書記』は、その叙述の前半部分において、天皇という地位と権力、その天皇を中核にした国家の成り立ちを問題にし、書名には日本の国号を堂々と冠した。 ・そのような『日本書記』のなかで、倭国の実際の歴史過程は起こりえなかった王朝交替をあえて描き出そうと試みたのは、ひとえに、日本という国家が大唐帝国と同じ世界帝国であることを自国史において検証しようとしたため、といえるであろう。 ・それは、中国に天命をうけて成り立つ王朝があり、その王朝が頻繁に後退するという長期にわたる歴史があるのならば、わが国にだって同様の長い長い歴史があるのだという、実に単純素朴な政治的主張であった。 ・『日本書記』は、日本という作られて間もない国号を書名に冠したことからも明らかなように、中国を、大唐帝国を強烈に意識し、それに対して発信しようとする内容を備えていたのである。 ・中国における天(天帝)とは、世界を支配する皇帝(天子)を選択・任命する絶対的・超越的な存在であって、中国の歴史に於て王朝交替を支える理論的な根拠となったのが天という思想であった。 ・それに対して日本は、中国の天の思想を導入・摂取したものの、そのさいそれに大幅なアレンジを加え、天とは ・そして、その高天原の最高神であるアマテラスの血脈を継承するがゆえに天皇は尊く、日本列島を統治する資格をもつのであり、この血脈を相承する者のみが天皇として推戴されうるという論理を創り出したのであった。 中国の文化・思想という磁力 ・わたしは、『日本書記』のなかにも多数収録されている神話や伝承の古さやその価値までまったく否定し去ろうというのではない。バラバラの状態で存在したそれらの古伝承を吸い上げ、整然と並べ上げる強力な磁石の役割を果したのが中国の政治的な文化・思想であったことを改めて強調したいのである。 ・最近の研究では、『日本書記』の実際の書き手が渡来・帰化した中国人であったことが解明されつつある。 ・『日本書記』が何世紀にもわたる中国からの文化・思想の摂取・継受をベースにして、当時の大唐帝国に向けて発信された歴史書であったということは、今後、『日本書記』自体を研究する場合でも、また、『日本書記』を使って歴史の研究を行う場合でも、押さえておかねばならない基本的な視点と結論して間違いないであろう。 あとがき ・「実在のたしかな最初の天皇はだれ?」 「古代天皇の実在はどのあたりから確実なのでしょう?」 ・このような問いかけに対し、研究者は沈黙を守ってきたわけではありませんが、それは、『古事記』『日本書記』に見える神話をふくめた古い時代の天皇に関する叙述を歴史学の立場からどのように理解・評価するかについて、研究者個々人がふみ込んだ追及を避けてきたためではないか。 ・「実在の初代天皇は一体だれなのか?」、また、「崇神が実在したのか否か?」といった質問の設定のしかたにこだわっていては、いつまでたっても問題は解決しないのではないかと思われます。 ・そもそも、「崇神が実在した」とはどのような意味なのでしょう。それは、ミマキイリヒコイニエという名の王者が実在したということなのか、神祇祭祀制度を確立し、都の四方に将軍を派遣したという事績をもつ王がいたということなのか、はたまた、『日本書記』の年代観に検討を加えて算出された崇神の時代に日本列島を支配した王がいたということなのか。 ・特定の天皇を指して「実在か否か?」を議論することに、どれほどの意味合いが見いだせるでしょうか、はなはだ疑問です。 ・そのような単純な二者択一論を超えて、歴史的事実に接近するより有効な枠組みを模索することが急務であり、それこそが意義のある仕事なのではないでしょうか。 |
||||