
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年09月10日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
32 |
17/04 |
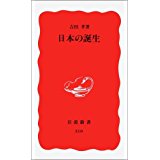 |
日本の誕生 |
吉田 孝 |
岩波新書 |
◎ |
一 東アジア世界と「倭」の出現 日本列島と農耕社会の成立 ・日本列島は、地球の中緯度に位置する地域のなかでは、農耕・牧畜社会への移行が、はるかに遅い地域に入る。しかし高度な水稲耕作技術が継受されると、人類史的にも異例な速いスピードで、政治的統合、初期国家の形成へと進む。 ・それを準備したのは、縄文文化の水準の高さ、縄文時代の社会組織の発達であったと考えられている。 ・農耕社会が成立すると、やがて各地に拠点的な集落を核とする統一体が現れてきた。「ムラ」をいくつか統合した「クニ」の首長の出現である。 秦漢帝国の出現と東アジア ・秦から漢への激動のなかで、中国からたくさんの人びとが、大挙して東方へ移動してきた。 ・前一九五年ころ、部下千人あまりと東方の朝鮮に亡命してきた衛満は、秦~漢の激動期に流入して住みついていた中国移流民を掌握し、やがて朝鮮王準を滅ぼして衛氏朝鮮を立て、王険城(現在のピョンヤン)を都とする。 ・衛氏朝鮮の支配層のなかで重要な役割を果たしたのは土着化した中国人である。 ・衛氏朝鮮の支配層は、土着化した中国人と、在地の首長層とによって構成されていたのである。 ・漢の武帝は、衛氏朝鮮を滅ぼして楽浪郡など四郡を置いた。 倭人のクニの登場 ・楽浪郡は、郡県制による直接支配とともに、周辺の諸族を慰撫する拠点でもあった。日本列島、とくに西日本の各地に生まれてきたたくさんのクニの首長のなかには、楽浪郡に朝貢する者があらわれたことを、中国の歴史書は記録している。『漢書』地理志の有名な紀事である。 ・西日本に成長してきたたくさんのクニの首長も、みずからの権力・権威を補強する有力な手段として、漢帝国、具体的にはその出先の楽浪郡に朝貢して、その地位を認めてもらおうとしたのではないか。 二 倭の女王と交易 失われた記録 ・一九〇年、遼東郡の太守であった ・帯方郡が設置されると、これまで楽浪郡が管轄していた ・このとき倭国では卑弥呼がすでに王になっていたと推定されるので、卑弥呼は使者を帯方郡に送って朝貢し、邪馬台国を盟主とする倭国統合の状況も詳しく報告したのであろう。 卑弥呼を親魏倭王に冊封 ・公孫氏政権が滅亡した翌二三九年(景初三年)の六月、卑弥呼は ・その年の一二月、魏の皇帝が卑弥呼に与えた詔書が『魏志』倭人伝に収録されている。 ・この詔書は、 “卑弥呼を親魏倭王とし、金印紫綬を仮する” 、卑弥呼が献じた貢物に対するお返しと、特別に卑弥呼に与えるもの、の二項からなる。 ・卑弥呼が任じられた「親魏倭王」の称号は、西方の「親魏大月氏王」とならぶものであろう。 ・魏は、敵対する蜀・呉を牽制するため、それぞれの背後にある中央アジアの大月氏と倭を厚遇したのである。 ・魏は、公孫氏を平定すると、韓の諸国の 三 大王(天皇)にも姓があった 広開土王碑のなかの「倭」 ・碑文がみずからの論理に組み入れた歴史的事件は存在した。誇張はあっても架空ではない。 ・倭が百済を支援して、朝鮮半島の広い範囲で高句麗と戦ったこと、加耶諸国のなかの任那加羅・安羅が、倭とともに百済を支援したことは、ほぼ動かない事実と推定される。 倭の五王、中国南朝へ遣使 ・三七一年には百済が高句麗を攻め、四七五年には、高句麗が百済の都、漢城を陥落させている。 ・このような経過のなかで、倭は中国の南朝に朝貢し、朝鮮半島における軍事指揮官に任命されることによって、軍事行動を補強しようとした。 ・四一三年、倭国は南朝の東晋に貢物を献じた。 ・次いで四二一年には、倭王の ・四年後、讃は司馬(安東将軍府の官人)の ・讃のあと ・四七八年、武が宋に遣使する。 ・倭・新羅の次の「 倭王の武 ・倭の五王のうち、最初の讃・珍が『古事記』『日本書記』の応神・仁徳・ ・なかでも武は、記紀の雄略、すなわちワカタケルにあたることは確実である。 四 東海の帝国への道 転換期に立つワカタケル大王 ・中国の冊封体制から離脱した倭は、朝鮮諸国の国制を継受しながら、独自の国制の形成へと向かう。それは、中国の帝国にならって、周辺の民族をも支配する帝国――中国の東海に浮かぶ小さな帝国――の形成をめざす長い道であった。そして、そのわかれ道に立っていたのが、倭王の武、ワカタケル大王である。 朝鮮半島から渡来した人びと ・朝鮮半島からたくさんの渡来人によって、水稲耕作と金属器の文化が伝えられ、日本列島の社会が大きく変動した。 ・とくに四世紀後半から活発となった。 ・『古事記』『日本書記』は四世紀から五世紀初めと推定される応神朝のころに、渡来人のなかでも古い歴史をもつ ・渡来者のなかには、朝鮮半島に進出した倭軍が、連れもどった者もいたかもしれない。 ・渡来人のなかでも、 ・また、倭の五王が中国の宋と通交した時期には、中国から直接に渡来する人びともいた。 ・渡来の波は、五世紀後半の雄略(ワカタケル、倭王の武)のころから六世紀にかけて、さらに活発になり、 ・このような日本列島への渡来の背景には、中国大陸における大規模な人口移動があった。このころ、中国内に移住してきた胡族(異民族)の王朝が次々に建てられたが、 ・東方の大移動の余波が、日本列島にまで及んできたのかもしれない。 ・時を同じくして、西方ではゲルマンの大移動がおこなわれていた。 渡来人が伝えた文化 ・渡来人が伝えた文化は他方面にわたるが、なかでも「文字」を読み書きする技術は、倭の王権の発展に大きな役割を果した。 ・渡来人は鉄の生産技術を伝え、農具・武器など鉄器の製造技術も革新した。 ・五~六世紀に、日本列島で鉄の生産が本格化し、朝鮮半島の鉄への依存度が低くなったと推定されることは、倭王権が中国王朝の冊封体制から離脱して東海の帝国への道を進むうえで、重要な背景となったであろう。 ・大規模な灌漑水路の工事も可能となり、台地上などに生産力の高い乾田(冬には水を落とす)が開発された。また高温で焼く固い ・倭王権は、これらの渡来人を組織することによって、勢力を強めていった。ヤマト朝廷の組織の骨格となる「 「任那」とは何か ・「任那」は、近代の大日本帝国が植民地支配の正当化に利用したので、近年の概説書や教科書では、避けて通ることが多い。しかしそれでは、かえって歴史を歪めてしまう。 ・朝鮮半島からたくさんの人びとが日本列島に渡来してきたころ、日本列島からも朝鮮半島へ移住する人びとがいた。なかでも半島南端の任那加羅(金官国。現在の ・百済・新羅にはさまれたかつての弁韓の地域には小国が分立していたが、そのなかで南方の任那加羅と、やや遅れて北方の大加羅(現在の ・南方の任那加羅は倭と結び、倭の軍事力を利用して政治的統合をめざしたと考えられる。 ・当時の「倭」の実体は、ヤマトの王権とは限らず、倭人の各地の豪族も独自に行動していたらしい。王権とは直接の関係のない、以前からの移住者をふくめて、倭系の人びとがたくさん集住した。 ・かれらの多くは現地の女性と結婚し、政治的社会を形成していた可能性が強い。 ・近年、全羅南道のこれらの地域にほぼ該当する地域から、十余の前方後円形の古墳が発見されていることも、倭系の土着豪族(その子孫をふくむ)と関係があるかもしれない。 倭と任那 ・大加羅王は、新羅の進出をおそれて百済と結び、百済の聖王(聖明王)が新羅との戦いで敗死して間もなく、五六二年に新羅によって滅ぼされるという運命をたどった。 ・『日本書記』が「任那滅ぶ」と記したのは、大加羅(とその連合国)が滅亡したときである。 ・『日本書記』の「任那」を構成した加耶諸国が、滅亡あるいは統合され、倭の朝鮮半島への足がかりを失われたとき、倭にとっての「任那」がまさに滅んだのであった。 仏教の伝来 ・倭にも渡来人によって個別に仏教が伝えられていた可能性がある。 ・五三八年(または五五二年)に、百済の聖王から朝廷に仏像(おそらく小金銅仏)・仏具・経典などが送られてきた。 ・仏教にはインド ― 西域 ― 中国 ― 朝鮮と、さまざまな国や社会に伝来してきた世界宗教としての性格があり、クニやムラの習俗や信仰を越えた普遍的な教理・哲学がその基礎にあった。 ・日本列島に伝えられた仏教も、やがて、クニやムラを越えた古代国家の形成の過程で、大きな思想的役割を果すことになる。 「飛鳥は日本の文化のふるさと」 ・高松塚のある ・有名な飛鳥寺は、百済王がおくってきた僧や寺工・ ・その鍍金用の黄金三百二十両は、高句麗王が贈ってきたものだった。倭と高句麗は六世紀の中ごろから親密な関係になっていた。 ・朝鮮半島からの渡来人は、筑紫や吉備など各地に住み、また七世紀後半、百済・高句麗滅亡の際に移住してきた人びとのなかには、東国に送られた人びとも多かった。 ・渡来人の多く、とくに高い技能を持った人びとや、百済・高句麗からの亡命王族・貴族は、内つ国(機内)に定住する者が多かった。 ・平安時代初期に撰述された『新撰姓氏録』は、京・機内の氏族のリストを掲げているが、そのなかで渡来人の氏族は三六二氏で、全体のほぼ三〇%を占めている。 ・飛鳥時代~奈良時代に渡来人がたくさん住んでいたのは、機内でもとくに河内・大和であるが、なかでも大和の飛鳥は渡来人の集住する地域で、飛鳥文化は、渡来人が生み出した文化であった。 日出づる処の天子 ・かつて倭の五王は、中国の宋の皇帝から「倭王(倭国王)」に冊封(任命)されることを願い、宋の皇帝の天下を拡げる役割を荷っていた。 ・それに対して、推古朝の倭王は、隋の皇帝と同じように天子と称したために激怒され、天皇(または大王、天王など)と改めたとはいえ、終始一貫して冊封を受けようとはしなかった。倭王は、朝貢はするが、隋の皇帝の正式の臣下になることは拒んだのである。 ・なぜ隋は倭が冊封を受けない(すなわち臣下にならない)のを容認したのか。このころ隋は高句麗と戦争状態にあったので、敵対する高句麗の背後に倭があることを重視したのだろう。 ・かつての三国時代の魏と倭の関係と同じように、ここにも国際情勢と地理的環境が大きく影響している。 ウヂ名と姓の萌芽 ・冠位とともに「姓」の制度も中国王朝との外交が端緒となった可能性が強い。 ・しかし冊封体制から離脱していた大王は、「姓」の制度からも超越していた。 ・かつての倭の五王と異なり、推古朝の大王が中国の皇帝から倭国王に冊封されなかったこと、そしてのちの朝廷も、朝貢はするが冊封は受けないという基本的立場を守り続けたことは、この列島の古代国家のあり方を大きく方向づけることとなる。 ・律令国家の形成過程で、中国の「姓」の制度を庶民にまで拡大していくが、大王(天皇)がみずからは姓をもたず、ウヂ名・カバネを民にあたえるという国制は、もし倭王が中国の皇帝から冊封を受けていたら、おそらく不可能であったろう。 ・現在まで天皇が姓をもたないのは、ここにその淵源がある。 五 クーデターと「革命」 戦争と内乱の世紀の幕開け ・隋が中国を統一して(五八九)年、東アジア世界の大帝国として登場した。 ・そのなかで、隋と高句麗の対立・紛争が発生する。 ・六一八年、隋は滅亡し、唐帝国が成立する。 ・倭が最初の遣隋使を派遣した六〇〇年は、そのような状況のときであった。 ・倭が当時の外交的常識からいえば「非礼」をおかしたにもかかわらず(だからこそ煬帝は激怒した)、朝貢はするが冊封を受けない(臣下とはならない)という特別な位置を得たのは、国際的・地理的条件が関係していたのである。 ・倭は高句麗の背後にあるという有利な立場をフルに利用する。 ・唐が隋にかわって帝国を再建すると、高句麗・百済・新羅は唐から冊封を受けて、国際関係がひとまず回復する。 ・六三〇年(舒明二)、第一回の遣唐使が派遣されることになった。このときも倭は冊封を受けず、唐との国交を開くことになる。 譲位のはじまり ・入鹿が暗殺された翌日、入鹿の父、 ・これまで朝廷では ・ところが、この大王位の継承が、朝廷の群臣の推戴によってではなく、皇極や中大兄など大王家の意志によっておこなわれたのである。 ・この「乙巳の変」における譲位は、王権の歴史において、王権が朝廷を構成する豪族たちから制度的に自立するという、画期的な出来事であった。 ・これ以後は、有力な豪族の意向によって皇位継承が事実上、左右されることはあっても、制度的には(不文法をふくむ広義の制度としては)、王権の意志によって、王位継承がおこなわれる。 ・先に、「乙巳の変」の物語によって、大王の血統が大王となる必要条件と観念されたことに注目したが、続いておこなわれた譲位は、大王の地位の自律性が制度として成立したことを示すものとなったのである。 改新政権の発足 ・中大兄は孝徳天皇のもとで皇太子として実権を握る道を選び、鎌足は皇太子の腹心として内臣となった。 ・改新政府が打ち出した、「 新羅の金春秋の選択 ・六四五年(大化元)六月の蘇我入鹿暗殺の場として利用された三韓の朝貢の儀式は、実際には翌七月におこなわれたが、その際、朝廷は「任那の ・六世紀前半に金官国(任那加羅)は新羅の勢力下に入ったので、ヤマト王権は新羅に「任那の調」を納めることを要求していたが、大化のころには百済が西方から勢力を伸ばしてきていたので、百済に「任那の調」を納めさせようとしたのである。 ・しかし百済に納めさせる政策もうまくいかなかったらしく、翌大化二年七月、改新政府は国博士の高向玄理を新羅に派遣し、「 ・新羅が送ってきたのは王族の金春秋(のちの武烈王)である。新羅王の孫で、母も王の娘である。 ・金春秋の ・唐に渡った翌年、春秋は唐を去るが、帰国した春秋は、新羅の服制を唐の服制に改め、年号も唐の年号を用い始める。唐の年号を用い、唐の衣服を着ることは、新羅が唐の属国になることを示している。 ・高句麗に使いして囚われの身となり、倭には「質」として赴き、唐に使いした金春秋は、唐の属国として生き残る道を選んだ。 ・この春秋の選択は、その後の東アジア諸国の運命に大きな影響を及ぼすことになる。 百済の滅亡 ・六五五年、高句麗・百済が連合して新羅の北部に侵入すると、新羅は唐に救援を求め、それに応じて唐は高句麗に出兵する。 ・六五九年、新羅は、百済の征討を唐に強く要請した。百済が高句麗の威を借りて新羅の領域を侵すという理由である。 ・六六〇年三月、唐の高宗は水陸一三万の大軍をもって百済を攻撃する。 ・また高宗の命令で、新羅の武烈王(金春秋)は、王子や将軍金 ・各地に残っていた百済の遺将らは、使者を倭に送り、援軍の派遣と、 ・豊璋は義慈王が三〇年前に「質」として倭に送ってきた百済の王子で、倭に滞在していた。その豊璋を王に立てて百済を復興しようというのである。 白村江の戦と高句麗の滅亡 ・六六〇年の暮、斉明女帝は難波宮に移り、出兵の準備を整え、翌年正月、中大兄皇子・大海人皇子らとともに難波を出発し、八月、救援軍がやっと編成され、餘豊璋を百済に衛送する。 ・倭の水軍は錦江の江口( ・八月二七日、倭の水軍と唐の水軍が戦闘の火蓋を切り、翌日、決戦となるが、またたく間に倭軍は大敗する。 ・逃れた倭の軍は朝鮮南部に集結し、亡命を希望する百済の将軍や兵士とともに、帰国の途についた。 ・六六四年の二月には、早くも弟の大海人皇子が宣して国制の改革に着手し、並行して、国土防衛のための施策が次々に打ち出される。 ・六六七年(天智六)、中大兄は都を近江の大津宮に遷し、翌年正月、正式に即位する(天智天皇)。 ・その年、唐・新羅連合軍は高句麗の都を攻め、一か月にわたる攻防戦の末、王都は陥落し、高句麗はついに滅びた。 ・白村江の戦いにおける倭と百済の連合軍の決定的敗戦は、その後の日本の歩みに重大な刻印を与えることになった。 ・朝鮮半島から倭の影響力が最終的に失われたことにくわえ、古代最後の、そしておそらくは最大の渡来人の集団的移住の契機になったことである。 ・百済の王族・貴族をはじめ、四、五千人以上と推測される人びとが大挙して倭に亡命してきた。 ・また高句麗が滅亡したときにも、王族をふくむかなりの数の亡命者があった。 ・これら百済・高句麗からの亡命者のうち、庶民の多くは、東国に入植していった。 国際情勢の変化と倭の朝廷 ・天智天皇は、全国にわたる戸籍( ・一方、朝鮮半島では、宿敵の百済、つづいて高句麗を、唐と結んで滅ぼした新羅が、目的を達すると一転して、唐の軍隊の追い出しにかかっていた。 ・唐の朝鮮半島の支配体制は、重大な危機を迎える。 壬申の乱 ・六七二年(壬申)五月、大海人の ・壬申の乱は、代替わりごとに祭式のようにくりかえされてきた皇位継承の争いの一つでもあった。しかし大海人にとっては、近江朝廷を滅ぼすことは、やはり「革命」だったのだろう。 天武・持統朝と古代官僚制 ・壬申の乱後の厳戒体制が終わるころ、天武は恒常的な軍事体制の構築を始め、官僚制の形成に着手した。 ・六八一年(天武一〇)、天武は律令の編纂を命じ、没後、あとを継いだ皇后(持統天皇)に継承され、六八九年(持統三)、 ・倭が百済・新羅と異なり、体系的な律令法典を編纂したのは、倭が中国から冊封されていなかったこととも密接な関係がある。 ・中国の律令法典は、周辺の蛮夷をも支配する帝国法であったので、中国から冊封されている国が独自の律令法典を編纂することはできなかったからである。 文字の世界へ ・中国の漢字文化圏の東端にいた倭人にとって、文字との出会いは、漢字との出会いであった。 ・日本列島に住む人びとが、文字を書き始めたのがいつかは、まだはっきりとわかっていない。おそらく渡来人がまず外交文書として漢文(中国文)を書き始め、やがて他の分野にもひろまったのであろう。 ・七世紀になると、漢文の文章構造をくずし、やまと言葉(日本語)の語の配列に合わせて漢字をならべた和風のまじった文章が書かれるようになる。 ・六七五年(天武四)、畿内と周辺の諸国から「 ・人麻呂は、助詞・助動詞を文字化する新しい表現法を開発した。 ・人麻呂が開発した「やまと歌」の表記法は、散文にも利用され、のちの漢字・仮名まじりの日本語表記法の基礎となる。 六 「日本」国号の成立 「日本」の国号はいつ成立したか ・「日本」の国号を中国に対して用いたのは、七〇一年(大宝元)の遣唐使であるが、「日本」の国号が正式に定められたのは、六七四年(天武三)以後と推定されている。 ・「日本」の国号が正式に定められたのは、史料的に確認されるかぎりでは、六七四年から七〇一年の間である。 ・制度的には、おそらくは、飛鳥浄御原令(六八九年施行)で「日本」が国号とされていたのではないだろうか(なお朝鮮の『三国史記』巻六が、六七〇年‹文武王十年、倭の天智九年›に倭から日本へ改めたと記すのは、『新唐書』日本伝の記事についての誤解による)。 日の出と「日本」 ・仏典などの知識によって、西の「日没する処」の中国に対する、東の「日出づる処」として、みずからの国号を定めたのであろう。 ・そこには当然、「日」のイデオロギーの高揚が背景にある。小さくとも東海の帝国をめざした倭の朝廷は、中国の「東」であることを前提として、「日の御子」の ・倭は、みずからの国号を定める時、中国との関係――すなわち「西」の中国に対する「東」の日本――を基軸にして、国号を定めたのであった。 ・唐の皇帝から冊封を受けない、すなわち「日本の国王」に任命されることを求めない、あるいは任命されることを拒んできた独立国「日本」の朝廷も、中国との関係を基軸として世界をみつめていたのである。 「天皇」号の成立 ・「日本」の国号とほぼ同じころ、「天皇」号が成立したいうのが、近年の学界の有力な説である。 ・しかし、「天皇」号がいつから正式に用いられるようになったのかは、実は明確でない。 ・「天皇」号の始用は天武朝末年、制度的には飛鳥浄御原令(六八九年)において制定されたとする説が有力となっており、この説によれば、「天皇」号と「日本」号はほぼ同じ時期に制定されたことになる。 銀と銀銭 ・記録によれば、初めて銀が産出したのは、六七四年(天武三)(対馬)である。 ・天武朝には最初の銀の産出から十年もたたないうちに、「銀銭」「銅銭」が鋳造されたのであった。 ・中国以外では、東アジアの最初の鋳造貨幣であった。 ・そして七〇八年(和銅元)の「和同開珎」から約二百五十年にわたって十二種の鋳貨を発行しつづける。 古代日本の国際的環境 ・鉄器や文字を入手したのは朝鮮半島からであったが、それらを伝えた渡来人の有力氏族が「秦」・「漢」氏と表記されたように、その背後にはつねに中国の文明が意識されていた。 ・朝鮮諸国はいずれも、日本と同じように、漢字と中国の儒教・仏教を摂取し、中国の統治技術を継受しながら国家を形成した。ただ日本と異なり、「律令」法典は編纂しなかったらしい。 七 大仏開眼と金 平城京と和同開珎 ・元明天皇が即位した翌七〇八年正月、武蔵国から和銅(自然銅)を献じた祥瑞を機に、「和銅」と改元された。 ・銅・銀・金など鉱物の出現が祥瑞とされるのは、中国には例がなく、日本の祥瑞の特色といわれる。 ・改元の翌月、貨幣の鋳造と都城の建設が開始される。律令国家を象徴する「 ・平城京は、中国の都城を手本としたにもかかわらず、藤原京と同じように城壁がなかった。 ・地方の都市にいたるまで高い城壁に囲まれた中国、戦時に逃げ込む山城が広く分布する朝鮮の人びとにとって、城壁に囲まれない都は、異様な光景でであったに違いない。 ・集落を濠や柵で防衛したのも、一般には弥生時代と戦国時代の戦乱の時代だけだ。 内外に高まる緊張 ・七二七年(神亀四)、渤海がはじめて日本に使節を送ってきた。渤海は、滅亡した高句麗の遺民が、配下の ・渤海は、高句麗の旧領域の大部分を領有したため、唐や新羅との軍事的緊張が高まっていた。 ・七三二年(天平四)、渤海と唐との戦争が始まり、新羅は唐の命令で渤海へ出兵する。 ・七三七年(天平九)、朝廷は諸国に釈迦三尊像の造立と大般若経の書写を命じる。これはのちに諸国の国分寺へと発展する。 廬舎那仏の造立と黄金の出現 ・聖武天皇は、七四三年(天平十五)、 ・かつて天武天皇は、「大君は神にしませば」とうたわれ、「神」とたたえられたが、聖武は「三宝の奴」と宣言したのである。「三宝」とは本来、仏・法・僧をさすが、仏(または仏法)をさすことが多い。 ・神話や系譜によってその正当性が裏付けられた天皇から、仏教や儒教によって王権の正当性が裏付けられる天皇への転換が始まる。 天平文化と墾田永年私財法 ・大仏造立の詔が出された七四三年(天平十五)、墾田永年私財法が出された。 藤原仲麻呂の儒教政治 ・七五八年(天平宝字二)、仲麻呂の傀儡の淳仁天皇が即位する。 ・仲麻呂は鋳銭(貨幣発行)の特権を得る。二年後、仲麻呂は最高位の太政大臣(太師)にまで上りつめた。 ・七六〇年(天平宝字四)、金銭の開基勝宝、銀銭の太平元宝、銅銭の万年通宝を新鋳する。 僧、道鏡の進出 ・七六一年(天平宝字五)、近江の保良宮に淳仁天皇と孝謙上皇が行幸する。 ・滞在中に孝謙上皇が病気になり、宮中の内道場の禅師、道鏡の漢語を受ける。 ・それを契機に、孝謙は道鏡を寵愛するようになった。 ・孝謙と道鏡の接近をみて若い淳仁天皇は苦言を呈する。孝謙は激怒し、平城宮に帰ると、法華寺に入って出家し、淳仁から国家の大事の決定権を奪い取ってしまう。 ・この事件を契機に仲麻呂の没落が始まり、追いつめられた仲麻呂は反乱を起こして近江へ脱出する。 ・しかし激戦の末、琵琶湖の船上で捕らえられ、首を斬られる。 ・乱を鎮圧した孝謙上皇は、淳仁天皇を淡路国に幽閉し、再び皇位に即いた(称徳天皇)。 ・称徳女帝の出現とともに、道鏡が急速に進出し、「法王」の地位につく。 天皇と儒教・仏教 ・仲麻呂が太師(太政大臣)になったのに対して、道鏡は太政大臣禅師、さらに法王となった。 ・また仲麻呂が領国の近江国に保良宮を造営して「北京」と称したのに対して、道鏡は出身地の河内国の ・古墳時代、ヤマト朝廷を構成していた豪族たちは、特異な霊威を血縁で世襲する大王を共立し、大王を核として朝廷を構成していた。しかし律令国家の天皇は、そのような氏族制的な原理だけでは、その正当性を十分に主張することができなかった。 ・仲麻呂が儒教の仁政の思想によって、また称徳・道鏡が仏教によって、王権を基礎づけようとしたのは、大陸の文明によって、天皇の正当性を新しく構築しようとする模索の過程でもあった。 八 ヤマトの古典的国制の成立 天皇の制度の確立 ・八世紀後半ころから皇位継承をめぐる争いは、立太子・廃太子をめぐって展開してきた。それは天皇の生前譲位が制度として成立することと表裏の関係にある。 ・かつてヤマト王権の時代の王権は、大王だけでなく、妃や王子たちによっても担われていたが、それは王権が一人の王に収斂しないという、未開社会によくみられる王権の一形態であった。王権が制度上、天皇一人によって代表され、皇太子が皇位継承者としての地位を確立し、生前譲位の制が習慣化したとき、天皇の制度が確立したのである。 源・平の出現と名前の唐風化 ・嵯峨天皇は子だくさんで、五〇人におよぶ皇子・皇女がいた。天皇は八一四年(弘仁五)、皇后・妃・ ・こののちに仁明・文徳・清和をはじめ、代々の天皇の皇子・皇女が源朝臣の姓を賜わる。 ・また八二五年(天長二)には、桓武天皇の孫の ・源・平両氏のなかでも、とくに清和源氏・桓武平氏は、のちに武家の棟梁として活躍することになるが、源・平・藤・橘という伝統的な姓がこの時代に出そろう。 摂政・関白の出現 ・摂政・関白はいわゆる ・摂政・関白は天皇の制度の一環として、その後の国制の重要な要素となるが、院や征夷大将軍と同じように、平安前期に出現してくることに注目したい。 ・この後、後醍醐天皇のように自ら権力を行使する天皇も出現するが、摂政・関白、院、征夷大将軍が、天皇の権力を代行することが一般化する。 家の相続の萌芽 ・伝統的な「イエ」の制度も、平安時代に成立したと考えられる。 神仏習合への道 ・神道の源流は、弥生~古墳時代の共同体的な呪術的宗教である。 ・大陸から流入していた民間道教の要素が、この古来の ・仏教と神道との交流は、奈良時代に、苦しむ神を救うため、神社の近くに神宮寺を建てることから始まった。 ・神は輪廻の世界に苦しむ存在で、仏に救いを求めたのである。 ・土着の神が仏を助け、仏法を守護するというのは、インドの梵天・帝釈天をはじめとする護法神の思想で、八幡神は仏教徒の関係が深かった。八幡神は、平安初期には「八幡大菩薩」と呼ばれるようになる。 ・仏教と神道の交流のなかから、伝統的な宗教意識の基層が生み出されてくる過程で、最澄と空海が果たした役割は非常に大きかった。 ・密教はインドの古来の神々を吸収しながら成立したもので、日本に摂取された密教も、古来の神々を吸収し、いわゆる神仏習合を生み出していく。 ・密教の呪術的な修法は、人びとの恐れる怨霊を鎮めるのに大きな力を発揮し、密教は朝廷や貴族社会に急速にひろまっていった。 ・修験道も密教の山林修行を母胎とする。 ・平安中期には、仏がこの世に神の姿で現われるという、本地垂迹の思想が生まれてくる。 ・仏教は神道を吸収して神仏習合を生み出したが、神道を解体しないで包摂しながら並存していった。 ウメからサクラへ ・花のなかでサクラがとくに愛好されるようになるのは、平安前期である。 ・もちろん奈良時代の『万葉集』にもサクラがうたわれているが、桜花の宴を楽しむことは、平安貴族から盛んなった。 ・サクラが日本列島に自生した植物であるのに対して、ウメは中国原産で、中国文化の摂取の過程で、日本にもたらされた。 ・ウメは七~八世紀に急速に広がり、天平びとは、中国風のウメをサクラよりも愛でたのである。 ・平安時代になると、ウメとサクラの地位はゆるやかに逆転していく。 ・ウメからサクラへの推移を象徴するのは、内裏の かな文字の創造 ・固有の文字をもたなかったこの列島の人びとは、漢字をそのまま用い、漢字の意味とは無関係にその音を用いて日本語を表記した。いわゆる万葉仮名である。 ・万葉仮名は奈良時代の終わりには、しだいに崩した字形となり、画数も少ない文字が多く用いられるようになったが、平安時代に入ると、ますます簡略化した草書体が用いられ、「ひら仮名」が生まれてくる。 ・平安時代には、漢文を日本語風に訓読することが盛んになり、仏典や漢籍に訓点を書きこむことが始まる。 ・狭いスペースに傍訓や送り仮名を記すには、万葉仮名をそのまま書いていたのでは、時間もスペースもとても足りない。そこで漢字を極度に省略した字形が考えだされ、「カタ仮名」が成立してくる。 日本語の音韻の変化 ・「いろはにほへど ちりぬるを……」という「いろは歌」が成立したのは『古今集』よりも後とされている。 王土王臣思想とケガレ ・律令国家は小さくとも、蕃夷を従える帝国であることを建前とした。 ・中国の王土王臣思想を継承し、新羅へも臣属を要求し、隼人・蝦夷にも王化に従うことを要求して征服した。 ・しかし、実際には、中国周辺の小帝国にすぎなかったので、国の境の外にひろがる空間は、天皇が徳化を及ぼすべき対象、すなわち「王化」の対象から切り棄てられていく。 ・ケガレ(穢)の観念は、インドのカーストをはじめ、人類史には広くみられ、『魏志』倭人伝にも、人が死ぬと、墓に葬ってから、家じゅうの者が水に浴して ・人の死、出産・月経、家畜の死・産、失火などが、ケガレのおもな発生源とされる。 ・ケガレの観念は、平安前期に急速に肥大、・・・ケガレは伝染すると観念され、・・・ケガレ意識の肥大化は、大八州の境外はケガレた空間とする恐怖を生み出してくる。 ・蝦夷や南島の人びとも、・・・ケガレにみちた恐怖の対象へと変貌していった。 ・大八州は、神仏の加護する領域であり、その外の蝦夷ヶ島(北海道)や琉球、さらに朝鮮半島や大陸はケガレた空間とされたのである。 ・大八州は閉ざされた空間となり、そのなかの人びとは、言語と文化を共有するという観念が、しだいに形成されていった。 ・境界外のエゾ(アイヌ)は、はっきり異種族として差別されるようになる。 ・ケガレの観念は、一方に、ケガレからもっとも隔離された天皇像を生み出す。 ・そしてもう一方に、ケガレを世襲的に負わされ、差別される人びとを、やがて制度として生み出していくことになる。 終章 ヤマトと「日本」 「日本」は王朝名 ・大宝の遣唐使以来、現在にいたるまで、対外的に国号として機能してきた「日本」とは、本来は、「 ―― 完 ―― |