
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年05月31日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
39 |
17/04 |
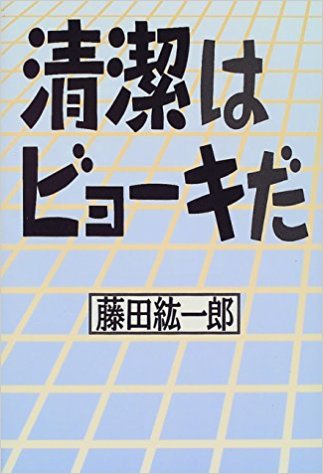 |
清潔はビョーキだ |
藤田紘一郎 |
朝日新聞社 |
◎ |
はじめに ・完璧な衛生環境、抗生物質や消毒剤といった薬によって完全に守られていた私たちが、なぜ、病原性大腸菌 ・私は戦後、日本人が進めてきた「清潔志向」とそれによる日本国内の「無菌化」が関係しているように思う。 ・一九六〇年代半ばから日本人に多発してきた花粉症やアトピー性皮膚炎、気管支ぜんそくなどのアレルギー性疾患が、この日本の「無菌化」と実は密接な関係をもっていた。 ・戦後の日本人の清潔志向は、次第にその度合いを強めてきて、最近では身の回りの、人が生きていくために必要な「共生菌」まで排除しはじめたのだ。 ・共生菌の排除が新しい感染症、病原性大腸菌О157を生み、それの犠牲になる日本人を生んだ。すなわち、「共生菌」の排除が新しい病原体を生み、一方では人間の免疫力を低下させるよう働いたのだった。 第一章 アレルギー性疾患はなぜ増えたか し尿の有機肥料還元 町美化しつつ回虫運ぶ ・日本民族は弥生時代後期という大変昔の時代に、糞便を有機肥料としてリサイクルさせることを考えついた、大変頭のいい民族ではないか。 抗アレルギー物質 がん発生を見落とす体質に ・寄生虫の分泌液や排泄液中にある分子量約二万の糖タンパクがアレルギー反応を抑える物質であることがわかった。 ・この物質は確かに強力な抗アレルギー作用をもつのだが、同時に重大な副作用もあることがわかってきた。 大量に使用すると、がん細胞の発生を見落とす体質にしてしまうことがわかったのだ。 ・人間の免疫反応は、ヘルパーT細胞の一種、Th1細胞とTh2細胞という二種類のタイプのバランスによって調節されている。 ・私たちの体内には、絶えずがん細胞が出現しているのだが、一方でその細胞をすばやく見つけて殺してしまう免疫の仕組みがあり、その主役がこのTh1細胞の系統なのである。 ・しかし、寄生虫そのものはTh1細胞とTh2細胞のバランスをうまくとって、がんの発生を抑えているが、分子量約二万の糖タンパクだけを大量に人間に与えたとすると、Th2細胞のほうだけが活発に働くようになる。 ・肝心のがん細胞を殺すTh1細胞の系統は完全に働きが抑えられてしまい、がん細胞が出現しても、見逃ししてしまう状態になることがわかった。 寄生虫の功罪 「治療目的」の感染は非現実的 ・寄生虫の中には、人に害を与えないものが少なくない。 そうかといって、すべての寄生虫が安全かというと、もちろんそうではない。 ・アレルギー性疾患の治療のためにわざわざ寄生虫に感染するという発想はあまり現実的ではない。 ・現在は有機農業がブームで、人糞を有機肥料として使っている人も少なからず存在する。そのおかげで知らないうちに回虫に感染している人も増えてきた。 ・自然食でアトピーや花粉症が治った人の多くが、自然食と共に感染した回虫がアレルギー反応を抑え、その結果、アレルギー性疾患が治ってしまったのではないだろうか。 共生の妙 細菌感染も花粉症抑制 ・結核などの細菌に感染すると、Th1型のヘルパーT細胞が刺激され、その結果、人間が花粉アレルギーを引き起こす抗体(IgE抗体)をつくり出しにくい状況となり、花粉症の発症を抑える。 ・つまり、寄生虫であれ、結核などの細菌類であれ、人間がこれらに感染することが花粉症などの発症を抑えている。 ・微生物と人間との間に培われてきた「共生」の見事な現象で、まさに「共生の妙」といえるだろう。 ・日本人の「超清潔志向」とそれによる日本国内の「無菌化」が、アレルギー性疾患の多発に間違いなく関係している。 ・あまりに清潔第一で生活していると、免疫力は低下し、弱毒菌でも病気を起こしたり、アレルギーを発症したりするようになる。 第二章 日本人はなぜバイ菌に弱くなったか 崩れた共生 なぜ先進国にだけO157? ・発展途上国では、病原性大腸菌O157の集団感染は見られない。なぜ、先進国にだけ、このような大腸菌が出現したのだろうか。 ・私たちの腸の中には、腸内細菌 ・このうち、大腸菌は、一般には「悪玉菌」として扱われてきた。確かに、腸の調子が悪い時に、腸内細菌叢を調べてみると、乳酸菌やビフィズス菌が減っていて、大腸菌は逆に増えている。 ・しかし、大腸菌は、人間が正常な健康状態の時には、消化を助けたり、ビタミンを合成したり、むしろ人間に良いこともしているのだ。 ・このように、もともと人間と「共生」している大腸菌の一部がなぜ、凶悪なO157になってしまったのか。 ・その理由の一つが、日本人をはじめとする先進国の人たちの「清潔志向」と、その延長である抗生物質や消毒剤の乱用である。 ・これらの物質の乱用によって、大腸菌が平穏に生きる環境が奪われ、変質へと追い込まれたのではなかろうか。 ・人は生まれた直後から、微生物と共に生きている。清潔にするのは悪いことではないが、われわれの敵か仲間化を見極めず、すべてを敵視するのは、いきすぎだ。 ・腸の内部には、長い歴史の中で人類と共生するようになった「常在菌」が約一〇〇種類、計一〇〇兆個も棲んでいる。一平方センチあたり数千万個という莫大な数になる。 ・ほぼ無菌状態で生まれる赤ちゃんも、親と触れたり、母乳を飲んだりしているうちに、生後数時間すると、腸の中にこうした細菌がしっかり棲みつく。 ・常在菌にびっしりと覆われていれば、腸の中に病原菌が入ってきても、「空き家」がないため棲みにくい。人はこうして生まれた直後に、感染症に対する「武器」を身につけるのだ。 ・あらかじめ抗生物質を与えて腸内細菌を殺してしまったネズミは、抵抗力が一万分の一程度にまで落ちることがわかった。 ・抗生物質の投与で腸内細菌の生態系が乱されると、抗生物質に比較的強いディフィシール菌だけが生き延び、異常増殖する。その結果、腸の粘膜に薄い膜のようなものができ、偽膜性大腸炎という病気になることがある。 ・この病気の一番の治療法は、腸内細菌の生態系を元に戻してやることだ。 ・微生物の専門家の間では、「腸内細菌は臓器のひとつ」とさえいわれている。腸内細菌はそれほど人が生きていくのに欠かせないもの、という意味なのだ。 ・大腸菌は、多くは無害というよりむしろ人間に必須のビタミンをつくったりして、有益な細菌といえる。 ・しかし、なかには下痢などを起こすものがあり、病原性大腸菌とよばれている。 乗り移り 人体に入ると毒素放出 ・文明社会は、多くの環境汚染物質を地球上に放出してきた。その中には、先進国の人々の「きれい好き」に由来する不必要な抗菌物質や消毒剤、殺虫剤などが含まれている。 ・大腸菌も、人間と同じ生物だ。棲みにくくなった先進国でも、なんとか生き延びようと努力をしているのである。その結果、大腸菌にもいろいろなタイプができ上がった。 ・そんな中で現れたのが、赤痢菌の毒素と同じものをつくり出すウイルスと結合した大腸菌――O157である。 ・私たちの腸の中には「腸内細菌叢」といって、乳酸菌、ビフィズス菌、大腸菌、ウェルシュ菌などがたくさん棲んでいる。 ・このうち、乳酸菌やビフィズス菌などは「善玉腸内細菌」といわれ比較的大事にされてきた。 ・しかし、ヒトの腸は、これらの「善玉腸内細菌」だけではうまく機能しない。「悪玉」の大腸菌をすべて駆逐した場合には私たちの腸は正常に働かないことがわかったのだ。 ・つまり、あくまでも腸内細菌類の間の「バランス」が必要だ、ということだ。 ・日本人は「悪玉」ということで大腸菌を徹底的にいじめた。その結果生まれてきたのが、大腸菌の「奇形種」O157だったというわけだ。 ・この「奇形種」のO157は実はきわめて「 ・細菌類がわんさといる、「汚い場所」では生存できない。他の細菌類にやられてしまうからだ。 ・世界で最も清潔な「学校給食の場」が最も騒動を起こしやすい。 ・そして、この「 ・腸の中にわんさと細菌を飼っているような「汚い日本人」はにがてのようである。 免疫力の低下 外で遊び抵抗力を養おう ・東京医大の中村明子客員教授曰く、 「子どもたちは抵抗力がまだ弱いが、全員がO157で発病するわけではない。むやみに消毒したり、抗菌の製品ばかりそろえたりして、神経質になり過ぎると、かえって腸内の有用な菌が少なくなり、菌に対する抵抗力が弱まることになりかねない。衛生管理は当然のことだが、無菌状態がいいとは言い切れない」 ・中村教授は、子どもをできるだけ外で遊ばせることを勧める。 ・外でいろいろな菌に少しずつ触れることは、免疫力を高めるうえでも、感染症への抵抗力を養う意味でも必要だと思う。 ・岡山県邑久町におけるO157集団中毒の際には、感染者の児童のうち、重症になった一割の子どもはすべて神経質で、「超清潔志向」に育てられた子どもたちであった。 ・興味深い点は、浦和市の場合も堺市の場合も、邑久町と同じように菌が検出された人の約三〇%は全く無症状、約六〇%が下痢のみ、約一〇%が重症になったということだろう。 ・同じメニューの給食を食べても、まったく感染しない人、感染しても症状の出ない人(健康保菌者)、軽い下痢ですむ人、合併症で死の淵をさまよう人などさまざまいる。 ・なんともない人と、重症になる人との差はいったいどこからくるのだろうか。 ・腸内細菌叢の研究者は、「健康な腸内細菌叢をもっている」人の腸の中では、病原菌が増殖しにくい、というのだ。 ・「超清潔志向」で腸内細菌叢の種類や数の少なくなった人や、抗生物質や抗菌剤の乱用などで腸内の細菌が少なくなった人たちのお腹では、腸内細菌たちが棲んでいるアパートに「空き家」が増える。この時O157がお腹に入ってくると、O157はその「空き家」に棲んでしまうようになる。 ・ビフィズス菌などの嫌気性細菌による発酵物質で腸内が酸性に保たれると病原菌の活動や増殖が抑えられるので、嫌気性細菌の栄養となるでんぷん、食物繊維、オリゴ糖などを食べると、O157などの感染の予防になる。 ・でんぷんは米、オリゴ糖は大豆、食物繊維は根菜類や海草に含まれているから、もっと和食を見直すべきだ。 ・最近、アメリカの学者たちが「健康のためにはアジア式食生活を」ということで、「食事ピラミッド」を提示している。 ・毎日食べるべきである食べ物として、米、麺類、パン、キビ、アワ、トウモロコシなどの穀類、果物、野菜、豆類、ナッツをあげている。 ・つまり、これらはすべて腸内細菌の「エサ」となり、腸内細菌類の種類や数を増やすような食べ物なのだ。 ・それと同時に、これらの植物性の食べ物は、多かれ少なかれすべて抗がん作用を有している。豊富な腸内細菌が免疫力を高めることがわかってきているので、「正常な腸内細菌を育てる」ことと、「がんの発生を抑える」ことが案外連動しているのかも知れない。 コレラ・ミステリー 休眠中の菌が国内定着 ・現在のコレラはエルトール小川型がほとんどで、この種のコレラは多少下痢を起こす程度で病原性はきわめて低い。 ・コレラ菌は正常の胃の中では約一万分の一にまで減少することがわかっている。 ・病原性大腸菌O157はコレラ菌にくらべて、胃酸に対する抵抗力が強いといわれている。しかし、それでも胃酸によって、一〇分の一程度にまで減少することがわかっている。 ・つまり、O157やコレラなど腸管感染症の場合、その第一のバリアーとなるのは間違いなく「胃」ということだ。 ・健康な人では、食べ物と一緒に多少の細菌が口から侵入しても、胃の中で分泌される胃酸によって細菌は殺され、感染からまぬがれるというわけだ。 ・ストレス、胃炎などのため胃酸の分泌が悪くなっている人や清涼飲料水などの飲み過ぎで胃酸が薄まっている人などでは、O157やコレラ菌が殺されないまま胃を通過し、小腸や大腸に到達する。そしてそこでこれらの菌は増殖する。 ・O157やコレラ菌を小腸や大腸で増やさないためには、「腸内細菌叢」を正常に保つことであろう。これが第二のバリアーである。 ・正常な「腸内細菌叢」を保つには、細菌類の「エサ」になるような食品を含む、バランスのとれた食事と抵抗力のある体力づくりが大切なのだ。 ・私たちが日ごろから「細菌たちと仲よく」共生していれば、何も恐れることはない。 再興寄生虫症 制圧一転、先進国で流行 ・一度制圧されたはずの感染症が再び私たちの前に出現してきた。これらを再興感染症という。 ・人類は感染症と戦い続けて来た。そしてワクチンや抗生物質の開発で感染症を克服したかに見えた。しかし、現在また、感染症が猛威をふるいはじめている。 ・世界で最も衛生環境が整備され「無菌国家」とまでいわれる日本に生活していると、世界人口の三分の一が結核菌に感染し、毎年三〇〇万人が死亡しているということをどうしても忘れがちになるようだ。 ・現実には、結核は「世界最大の成人感染症」であり、今、地球始まって以来の蔓延時代を迎えているのだ。東南アジア、サハラ以南のアフリカ諸国では、五歳以上の感染症死亡の第一位となっている。 MRSA 抗菌薬使用を最小限に ・院内感染の原因であるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)の特効薬として使われてきた抗生物質のバンコマイシンにも、効果のない例が出てきている。 ・だが、免疫力が落ちた人を襲うMRSAも、細菌自体の毒性は決して強くはない。 ・黄色ブドウ球菌は、もともと私たちの皮膚や鼻の粘膜にいて、健康な人には悪さをしない「常在菌」の一つだ。 ・常在菌は人間の皮膚や粘膜で増え、外からやってきた病原菌が皮膚や粘膜で繁殖するのを防ぐ、いわば、人間との共生関係を築いた細菌なのだ。 ・MRSAの毒性は、普通の黄色ブドウ球菌と変わらない。健康な人が保菌していても問題はない。 ・手術を受けた人や免疫力の落ちた人にMRSAがうつった時に問題となるのだ。 ・薬の効かない耐性菌は、「したたかで強い菌」というイメージがあるが、実態は違うようだ。 ・耐性菌は、菌が生きるために必要なエネルギーを犠牲にし、薬に耐える特別な力を獲得している。結果的に、普通の環境で生きる力は弱くなっている場合が多い・ ・抗菌薬の使用を最小限に抑え、常在菌や体の自然回復力を借りる知恵がMRSAの治療と対策に行かされるべきだ。 ・MRSAは老人や手術後の人などの免疫の働きが弱った人が感染すると、重い場合は肺炎や敗血症を起こして死亡することもある。 ・これまで、このMRSAには特効薬としてバンコマイシンという抗生物質が使われてきた。 ・ところが、このバンコマイシンが効かないMRSAが最近増加していることがわかった。 ・ペストや赤痢、結核などの細菌感染症は有史以来、人類にとって逃れられない災厄だった。ペニシリンをはじめとする抗菌薬ほど、多くの患者の命を確実に救った薬はない。 ・しかし、切れ味のよい抗菌薬が乱用された結果、「薬剤耐性菌」が蔓延したのだ。 ・抗生物質の大量使用による耐性菌の増加を食い止めるため、アメリカ疾病管理予防センター(CDC)は九七年から無駄な使用を減らす対策に乗り出した。 ・抗生物質はウイルスには効かないのに、かぜなどのウイルス性の病気に使っているケースが目立つ。 ・抗生物質を使うと弱い細菌は死ぬが、生き残った細菌が薬に対する抵抗力をつけ増殖してしまう。抗生物質の使用量に比例するように耐性菌が増える。 ・抗菌薬の服用を続けると腸に細菌がいなくなるが、薬をやめると約一週間で菌が元通りに戻る。MRSAの治療と対策には、菌や体の自然回復力を借りる知恵が必要だ。 ・人間と微生物は、微妙なバランスの上で暮らしている。微生物を恐がるのではなく、共存するという意識が大切だ。 第三章 日本人はペット病や海外病になぜかかるのか ペット 潔癖志向と逆の溺愛 ・ことペットに関する限り、日本人のこの極端な清潔志向がどこかに飛んでしまっている。 ・日ごろ、清潔・潔癖主義を通している日本人が、電車のつり革や他人の使ったボールペンなどを「きたない」といって持たない一方で、おしりをなめたペットと平気でキスをするという極端な現象を私は不思議に感じる。 ・ペットが原因で起こる病気には、大きく分けて二種類ある。ペットからうつる病気とペットの毛や乾燥した糞などが原因となって起こるアレルギー病の二種類だ。 ・ペットなど動物からヒトに感染する病気を「人畜共通感染症」という。 ・最近、日本ではこのペットからうつる「人畜共通感染症」が増加している。 ・ヒト側の要因もたくさんある。 第一に、日本人の「超清潔志向」が人畜共通感染症にかかりやすくしているように思う。最近の日本人の「清潔志向」は明らかに「行き過ぎ」ている。このことが日本人の免疫力の低下を誘導し、感染症にかかりやすくしているようだ。 ・第二に、現代の先進国の文明が「ヒトが生物として生きる」基盤を失うように働いている事であろう。 便利すぎる社会が、ヒトが「体を動かす」機会を奪い、いつでもどこでも食べられる「調理済みの食品」の増加も、ヒトの免疫力低下につながっている。 ・さらに、高度に発展した機械化文明がいろいろなストレスを生んでいる。物質文明は多量の汚染物質を環境中に放出している。それらのストレスや環境汚染物質が現代人が生物として、まともに成長していく過程を妨害しているのは明らかである。 ・医学の進歩によって昔なら助からなかった病気が治療できるようになった結果、逆に抵抗力の弱い人が多くなってきた事も原因の一つであろう。普通の人には無害な菌でも抵抗力の弱い人には感染して発病してしまうからで、これを「 ・ペット病は確かに恐ろしい病気がいくつかあるが、ヒトにかかる率はそれほど高いものではない。 トキソプラズマ 成人の二割以上が感染 ・トキソプラズマは日本人の成人の二〇%以上に感染しているありふれた原虫で、成人がトキソプラズマにかかっていても、ほとんどの場合、症状が出ない。トキソプラズマは、成人に感染した場合には、筋肉中で「ふくろ」に包まれて、本当に静かにしているからだ。 海外病 「無菌国家」が重傷招く ・無菌国家日本で育った若者が「あぶない」。 ・日本では「はしか」「みずぼうそう」「おたふくかぜ」「風疹」など子どものうちにかかっておくべき感染症にかからないで青年期にまで達する若者が増えてきた。これらの若者が「病原菌がいっぱい」の発展途上国に出かけたり、生活すると「あぶない」のだ。 第四章 「超清潔志向」日本人の行きつく先 抗菌グッズ 皮膚を守る菌まで攻撃 ・人間の皮膚には表皮ブドウ球菌や黄色ブドウ球菌をはじめとするたくさんの皮膚常在菌が存在して、皮膚を守っている。それらが抗菌グッズで常に攻撃され、皮膚常在菌が弱ってくると、体の中の白血球がそれらを攻撃して多量の活性酸素を生じ、その結果、皮膚が障害されるという。 ・「抗菌」は、菌類に対する抵抗性の総称として最近、頻繁に使われている。 ・しかし、抗菌に統一の表示やマークなどはなく、抗菌の定義も明確でない。 ・日本リーバでは「抗菌は『抗菌性物質、抗菌作用』から取られている言葉で、はっきりした基準がない。どれくらい効果があり、どれくらいの期間有効なのかもはっきりしない」と話している。 ・抗菌加工された繊維を肌につけること自体が問題であると私は思う。 ・皮膚の上に棲みついている常在菌も、中性脂肪を分解して酸をつくることで、他の細菌がとりつくのを防いでいると考えられている。抗菌防臭加工した衣服ばかりを着ていたらこうした常在菌がどうなるか、きちんと調べていくべきだ。 ・病原菌にむやみに侵されないようにするためにも、少なくとも幼児や、同様に抵抗力が落ちた高齢者には、常在菌の助けが必要だろう。 ・「殺虫剤に耐性が生じるのと同様に、抗菌剤に抵抗する菌をつくる可能性もある。微生物と『共生』しなければいけないのに、『抗菌』だけを強調するのはどうだろうか」という声もある。 ・抗菌加工商品のはんらんには「売れるからつくる」という側面がつよいようだ。 洗い過ぎ 肌弱くカサカサに ・皮膚は真皮と表皮の二層からできている。この二層が体内の水分を一定に保ち、病原菌や有害物質の侵入を防いでいる。 ・さらに、外敵から身を守っている二種類のものがある。一つは、毛穴から分泌される皮脂。これが皮膚を薄く覆い、外敵の侵入を防ぐ第一のバリアーになっている。 ・もう一つは、「常在菌叢」。人間の皮膚には、表皮ブドウ球菌やニキビ菌、新菌類など約一〇種類ほどの細菌類が棲みついている。これらの細菌叢が病原菌を寄付けないにしているらしい。これらの常在菌叢は、体を洗った後では一時的に九割はなくなるという。 ・また、体を洗い過ぎると、当然「皮脂」も失う結果となる。皮脂を失うと、「ドライスキン」といってカサカサの肌になってしまう。 ・ドライスキンになると、皮膚が過敏になる。ほこりや紫外線、汗のような弱い刺激でも、湿疹や炎症の引き金となり得る。 ・日本人はきれい好きだ。しかし、洗い過ぎると皮脂や常在菌にとって、悪い影響が出るのは当然だ。 ・過ぎたるはなお及ばざるがごとし、ともいうではないか。 ・皮膚の構造 皮膚の外側は表皮と呼ばれている。この表皮は四つの層に分かれている。最も内側にある「基底層」では、絶えず新たな細胞が分裂している。これらが次々に表面に向けて押し上げられ、二週間ほどで外界に接する「角質層」に届く。 細胞はさらに約二週間、角質層にとどまった後、やがて「あか」になって自然にはがれ落ちる。肌のみずみずしさは、こうしたメカニズムに支えられている。 ・「表皮」は〇・一ミリの厚さ、これが暑さ二ミリの「真皮」の上に重なってできている。 この二層が体内の水分を一定に保ち、病原菌や有害物質の侵入を防いでいる。そして、その他に外敵から身を守る、二種類の「助っ人」たちがいる。表面を覆う皮脂と常在菌だ。 共生菌の排除 洗い過ぎで炎症になる ・人間の体には、私たちを守ってくれる細菌も棲みついている。 ・皮膚には表皮ブドウ球菌をはじめとする皮膚常在菌がいて、皮膚を病原菌から守り、異物の侵入をふせいでいる。 ・腸の中にはビフィズス菌や乳酸菌がいて、食べ物の消化を助け、免疫力をつけるように働いている。 ・行き過ぎた清潔志向が共生菌を排除し、健康を障害するように思えてならない。 ・健康な人の皮膚にいる表皮ブドウ球菌などの常在菌は、病原体やアレルギーの原因物質が皮膚に付くのを防ぐ役割も果たしている。人間も、微生物と共生して健康を維持していることを忘れないで欲しい。 自己臭症 「個」を消す奇妙な病理 ・動物学専攻の女子栄養大学の小原秀雄教授 「動物にとっては、においは大切な自己主張のサイン。消臭というのは、自分を見せたくないとすること。におい消しでみんな同一化するようになったという傾向に、『個』の行き詰まりを感ずる。においをなくして個の主張をなくし、仲間外れにならないようにする。におうことが『いじめ』の理由になるなど、おだやかなファシズムになっている」 おわりに ・アトピー性皮膚炎、気管支ぜんそく、アレルギー性鼻炎といった、いわゆるアレルギー性疾患が日本に出現したのは、たかだか三〇年前のことだ。 ・一方、日本人が現在のような「超清潔」な環境の中で生活しだしたのも、最近の三〇年というわずかな期間にすぎない。 ・現在の日本人の「超清潔志向」は、常軌を逸したものになっているのではないかと思う。 ・健康至上主義者は寄生虫はともかくとして、自分の身を守っている共生菌などを異物として小心翼々と忌避、排除し、極端なまでの清潔を心がけている。 ・そして、ついに消毒され、清められた「無菌室」のような空間に入り、自らを「家畜化」して、反自然的状態を現出しているのではなかろうか。 ・反自然とはもちろん、生に反していることである。そして生に反するものは、いずれ生と自然の側から報復を受けずにはすまないと私は思う。 |