
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年05月24日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
40 |
17/04 |
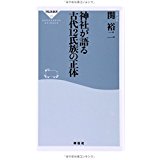 |
神社が語る古代12氏族の正体 |
関 裕二 |
祥伝社新書 |
◎ |
序編 「神道」と日本人 よくわからない ・「神道」を日本固有の宗教と位置づけ、しきりに喧伝したのは、江戸時代の国学者、 源流は、中国から ・「神道」の二文字がはじめて文書のなかに登場するのは、 ・また、 ・そもそも「神道」という言葉も、日本で生まれたのではない。紀元前四~三世紀ごろ、すでに中国で使われはじめた言葉だ。 ・それが、前一世紀の漢代には、墓に通じる道を「神道」と呼び、後漢には、道術を意味するようになった。つまり、呪術宗教的な真理をさしていた。 ・おそらく『日本書記』の編者の手によって、この「神道」という言葉が「 ・神道の骨格をなしている ・ 道教の影響をうけた「天武・持統朝」 ・天皇の和風諡号にも、道教の思想が見受けられる。 ・およそ伊勢神宮が、いまのような形に整えられたのは、「天武・持統朝」のこととされている。そしてこの時期、急速に道教的発想が神祇祭祀のなかに組みこまれていった。 ・大嘗祭も、伊勢神宮も、北極星と関わりが深い。 ・古代中国哲学は、北極星を神霊化し、宇宙神「 ・天皇にとっても、もっとも大切な大嘗祭と伊勢神宮には、古代中国の思考が混じり、信仰の柱になっていたことがわかる。 ・いっぽう、太古の日本人は、東から西のライン、すなわち「太陽の道」を重視した。ここに大きな差がある。 前方後円墳の誕生と終焉 ・大嘗祭も、伊勢神宮も、ともに七世紀から八世紀にかけて、本格的に整備されたことだ。そして、この前と後では、信仰の内容も、その祭祀支配者も、大きく入れかわっていた可能性が高い。つまり、この頃、「神道」は大きく性格を変えてしまったのではあるまいか。 ・まず、ヤマト建国以来続いてきた「前方後円墳体制」が、約三〇〇年後の七世紀初頭に終焉を迎えた。 ・三世紀初頭、奈良盆地の東南の隅に、政治と宗教に特化した、前代未聞ともいえる形態の都市が造営された。これが、 ・ここに、日本じゅうの地域から、人びとが集まってくると、彼らがそれぞれに持ちよった埋葬文化が組みあわされることで、前方後円墳は生まれる。 ・ヤマトの地で誕生した前方後円墳は、各地に伝播し、埋葬文化を共有する「ゆるやかな連合体」が生まれた。これが、ヤマト建国の実態である。 ・前方後円墳は、もっとも「王や首長のお墓の個性的な形」であったが、それよりも大切なことは、「新たな宗教観」を提示し、共有した事であろう。 ・墳丘上で祭祀が執りおこなわれ、埋葬する先代の王や首長の霊(魂)を新たな王や首長が継承した。これが、ヤマトの「神祇祭祀=神道」の原型であった。 ・つまり、三世紀後半、あるいは四世紀から七世紀初頭まで続いた前方後円墳体制は、ヤマトの神祇祭祀の本質だったことになる。すなわち「神道」の原型である。 ・だからこそ、七世紀初頭に前方後円墳の造営が終わったことに、注目せざるをえない。 祭政一致の時代 ・男王(ヒコ)の親族の女性(ヒメ)が祭祀に専念し、神と結ばれ、その力を王に照射する・・・・・・これが「ヒメヒコ制」と呼ばれている、古代日本の政治システムである。 ・もっともわかりやすい例は、邪馬台国の卑弥呼だろう。 ・卑弥呼は ・邪馬台国、神武東征(ヤマト建国)当時、すでにヒメヒコ制は確立していて、ヤマト朝廷も、やはり邪馬台国の卑弥呼の時代と同じように、「神と結ばれた巫女」、「王を守るミコ」によって、民を統治していたことがわかる。 ・「政」と書いて「マツリゴト」と読むのは、このような古代社会の祭政一致があったからである。 七世紀の大きな変化 ・六世紀末~七世紀以降、ヤマト朝廷は大変身する。 ・飛鳥の法興寺(飛鳥寺)、斑鳩の法隆寺など、蘇我氏主導で、本格的な大寺院がつぎつぎと建立されていく。 ・ ・前方後円墳がつくられなくなるのは七世紀の初頭で、ヤマト朝廷が新たな体制に向かって走りだす時代と、ほぼ重なっている。 ・やはり、七世紀に何かが起きていたのであり、このときにまた、神道が大きく改変された可能性は高いのである。 ・『日本書記』は、西暦七二〇年に編纂され、また大宝律令(七〇一)によって、律令制度は、ほぼ完成したと考えられている。 ・伊勢神宮の整備も、この「新体制づくり」の過程で進んだが、とくに天武天皇の時代、急激な変化があったと見られている。 ・最初に『日本書記』編纂を「命じた」のも天武天皇だった(と、その紀事から読み取れる)。新たな時代を築くために、過去の清算を行おうとしたのだろう。 改変された神道 ・神道を支配していったのは、藤原氏から枝分かれした中臣氏である。 ・「神道」とは、八世紀に生まれた新たな信仰形態であって、ヤマト建国以来続いてきた前方後円墳体制やヒメヒコ制とは、まったく別物だった可能性が出てくる。 多神教と一神教 ・江戸時代の国学者、 ・神とは、善悪を超越し、「人智を超えた力を発揮するもの」とみなした。 ・「カミ」は、人間の力ではどうすることもできない、偉大で恐ろしい目にみえない力、すなわち「大自然そのもの」、神道の起源は、「アニミズムと多神教」だった。 ・一般的に、神というものは、「正義の味方」とは限らない。じつに人間くさく、悪さもする。時には、人びとを恐怖のどん底に突き落とす。天変地異や疫病を振りまき、人びとを殺していく。そうかと思うと、幸や豊穣をもたらす。それはなぜかといえば、「カミは大自然そのもの」だからだ。 ・そして神は、「 ・アニミズムは、ありとあらゆるものに精霊や神は宿るという発想で、その延長線上に、 「自覚のない信仰心」の源流 ・久保田展弘氏曰く、 「私は、アイヌの人々が生活感覚の中に持ちつづけて来た縄文的思考原理と呼べるその精神世界に、むしろ自分の記憶の底にある筈の、感性のルーツが求められる気がしてならないのだ。 そして宗教というものを、その教理が文字によってきちんと整えられたものととらえがちな、多くの認識から見れば、アイヌの本来的な宗教は、宗教以前の宗教ということになるだろう。しかしだからこそ、これが宗教のルーツなんだということができる。」 ・そのとおりであろう。日本人は自覚のない信仰心を抱いているのであって、それは、意識できないほど、深い心理に焼きつけられているからにちがいない。おそらく、遠い縄文時代の記憶ではあるまいか。 「 ・早々に「弥生化」していった地域の多くも、「弥生系集団」がたちどころに征服したのではなく、土着の「縄文系集団」が「弥生化の主体」となっていた可能性が高くなっている。 ・祭器具の流行を見ると、「縄文的なもの」と「弥生的なもの」が反復、回帰、揺りもどしと、循環しながら盛衰を繰りかえし、縄文的な文化を内在しつつ、しだいに弥生的なものに変化したと考えられるようになった。 ・弥生時代の到来とともに、土着の縄文人や縄文文化はいっせいに駆逐されたわけではなく、「弥生化」は「縄文集団が主体」だったのであり、縄文的な祭祀形態も、弥生化の過程で消滅したのではなく、根強く生き残っていったことがわかる。 縄文人も祖先を祀っていた ・祖霊を敬う祭祀は、すでに縄文人が始めていた。 縄文時代前期に、集団墓が形成され、しだいに死者を「あの世」に送る儀礼が発達し、体系化されていく。 ・前方後円墳に、大量の銅鏡が副葬されていたことは、中国から伝わった文化のあらわれであり、日本の伝統とはかけ離れている。しかしその一方で、「祖神を祀る」という宗教観は、縄文時代から連綿と引き継がれた信仰であり、これに道教などの新しい「意味づけ」が加わって、新たな埋葬文化が生まれたと読みとくことができる。 ・中国や朝鮮半島からつぎつぎと押し寄せる文物を前に、われわれ日本人の先祖たちは圧倒されつつも、「揺らぐことの無い核(コア)」が、守られつづけたのではなかったか。 ・これが、日本人の「神祇祭祀」(あえてここでは「神道」とはいわない)の、深層を流れる伏流水ではなかろうか。 ・そして、この「自覚のない信仰心」は、現代人の潜在意識のなかにも、しっかりと刻まれている。 生き残った「神道的発想」 ・伊勢神宮は新しく道教的な思想によって組み立てられ、しかも、 ・奈良時代以降、「 ・神仏習合の ・『 「経典を拝見すると、仏法を衛尊敬しているのは神々であることがわかる。だから、出家した僧も ・天皇、神道、どちらにとっても、もっとも大切な行事である大嘗祭に、はじめて仏僧が参加することになった。 ・ここに、神道をめぐる大きな謎がある。もし、これまでの常識どおり、神道が「天皇の神聖性を証明するための宗教」、「天皇の統治を正当化するための宗教」の意味を担っていたとしたら、なぜ天皇みずから、神道の根幹を揺るがすような行動に出たのだろう。しかもこののち、神道と仏教は実際に融合していってしまうわけである。 ・称徳天皇といえば、怪僧と伝えられる 神祇祭祀と「神道」 ・日本人の民俗信仰の深層には、縄文以来継承されてきた、アニミズム的発想が隠されている。国家の体裁が整い、支配者が、「国を統治するための宗教」を形づくり、その儀礼が日本各地で認知され、同じような信仰形態が共有されていった。 ・その後、律令制度の完成とほぼ同時に、神祇祭祀は藤原(中臣)一族に支配され、古き伝統は破壊された。こうして作られたのが「神道」の正体であり、伊勢神宮を見れば、伝統的な信仰の上に、非日本的な様式が重ねられているのがわかる。 ・また、「新たな神道」に対する違和感から、神仏習合が進み、一見すれば、日本は仏教的な思想に彩られていったかのように思えるが、実際にはそれは「形だけ」であり、仏教でも神道でもない「三つ子の魂」が、脈々と生きつづけてきたということであろう。 ・藤原氏が表向きで神道を改変しようとも、神仏習合が進もうとも、日本人は日本人の信仰を捨て去ることはできなかったのである。 第一編 ヤマト建国の立役者となった氏族たち 第二章 天皇家の祭祀を支えた「物部の力」 ・物部氏のもののべは、朝廷の軍事をつかさどり、「もののふ」(武士)の語源になった。 なぜ物部氏は、カハチの地を選んだのか ・ヤマト建国時、祭祀形態をつくりあげていく、その中心に物部氏が立っていたが、前方後円墳の原型を編みだしたのも、物部氏だった可能性が高い。 瀬戸内海の覇者 ・四世紀以降六世紀にいたるまで、ヤマト朝廷の外交方針は、「親百済」で、大坂→瀬戸内海→関門海峡→北部九州→ ・石上神宮に 第二編 ヤマト建国の秘密を知る氏族たち 第六章 水先案内人として登場 ・浦島太郎は、『日本書記』や『万葉集』、『風土記』に登場する実在の人物なのである。 第八章 「女装する天皇」の意味 ・正史『日本書記』といえば、これまで「天武天皇のために書かれた」と信じられてきた。天武天皇の時代に編纂が命じられ、天武の王家のなかで完成したからだ。 ・しかし正確には、『日本書記』は、「天武天皇崩御後の政権にとって都合のよい正史」である。誰にとって都合がよいのかといえば、編纂時の権力者・藤原不比等である。 第十章 祭祀場としての古墳 ・古代人は、神域の樹木に神が宿ると信じていた。だから、仏教伝来以前には、人工的な建造物のなかに神を呼ぶという発想そのものが、なかったのではあるまいか。 ・巫女や祭司王が神を祀る館は用意されていたかもしれないが、これは、神社の社殿とは性格が異なる。 ・古い豪族たちは、社殿を建てて、いわゆる氏社を立てるのではなく、古墳を築き、先祖や氏神を祀っていた。 ・そこには、亡者を供養するというよりも、積極的に神として祀ることの意識のほうが強かったように思われる。 ・したがって、のちの時代に見られるような、「仏教風」の、あるいは「道教風」の、巨大壮麗な神社社殿を必要としなかったということではなかろうか。 おわりに ・天皇は万世一系でないとしても、「ヤマトの王家」そのものは、ヤマト建国以来、続いてきたのではないか・・・・・・。 ・そもそも古代の「天皇家」に実体はなく、蘇我、物部、尾張氏ら、ヤマト建国に活躍し、裏切り、裏切られた者たちが、恩讐を乗り越え、血の交流を進め、多くの血が集まって王家を形成していたのではないか、と思える。 ・ヤマト政権そのものが、いくつもの地域の首長たちの寄せ集めであり、その合議によって、政権は成り立っていた。 ・また、「魏志倭人伝」に描かれた卑弥呼のように、それぞれの首長が王を「共立」していたのだろう。 ・天皇とは何か・・・・・・。 日本人の信仰とは何か・・・・・・。 ・いたる場所に神々は ・われわれの御先祖様たち、ヤマトを構成した豪族たちは、「共存」する体制を大切にしていたのだ。 ・日本人の信仰と正体を知るには、『日本書記』編纂以前のわれわれの先祖の歴史を知ることが早道と気づかされる。 |