
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年07月25日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
43 |
17/05 |
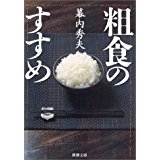 |
粗食のすすめ |
幕内秀夫 |
新潮文庫 |
☆ |
第2章 「栄養素信仰」の大罪 欧米式「栄養素」なんて忘れるべし 「栄養のバランス」の本当の意味 栄養素やカロリー計算は時間の無駄 ・一キロカロリーとは、水一リットルの温度を一度上昇させるのに必要な熱量をさす。 ・しかし、食品成分表を見ると、育ちざかりの一〇歳の子どもも、七〇歳の老人も、ご飯一杯は一七七キロカロリーということになってしまう。 ・食物は体内で吸収されてはじめて熱量になるのだが、消化吸収能力は人によって違うはず。同じものを同じ量食べたからといって、子どもと老人が同じカロリーになるはずがないのだ。 ・また、同じ人でも精神状態や体調によって、消化吸収率がかなり違ってくるものなのだ。 ・こういった人それぞれの違い(個人差)を考慮せず、「何グラムで何キロカロリー、だから多い、少ない」と計算するのは、あまりにも人間のからだを単純にとらえすぎていないだろうか。 ・こうした点から考えても、「カロリー」という数字は、あまりにもあやふやなものだ。 「栄養のバランス」とは何か ・ご飯を食べて太るのが本当なら、明治、大正時代は街中、肥満の人だらけだったことになる。しかし、太った人は今よりずっと少なかった。 ・その理由は、「伝統食」を食べていたため、食べたものの利用効率がとても良かったからで、からだの新陳代謝が非常に良かったからなのである。 不足しない食べ方こそ重要 ・日本人にとって、一番利用効率のいい食事、つまり新陳代謝のいい食事は、米を中心とした食事である。 ・「副食の種類を多く、ご飯は少なめに」という現代風の食生活はやめ、「副食は少なく、ご飯は多めに食べる」戦前の日本人の食生活を試してみていただきたい。太るどころか、むしろスマートになっていくはずである。 ・燃料を上手に燃やすために必要なのが酸素だ。酸素が上手く取り入れられなければ、からだは不完全燃焼を起こしてしまう。からだにとっての酸素、それは「微量栄養素」といわれる各種ビタミンやミネラルのこと。 ・微量栄養素が不足しない食べ方とはいったいどんな食べ方かというと、「ムダのない食べ方」だ。皮をムダにしない、内臓をムダにしない。 栄養素理論と実際の問題点 栄養素は本当に科学的か ・子どもたちの体格が向上したことにどれほどのメリットがあるというのだろう。「体格」よりも「体質」でこそ健康問題は語られるべきだと思う。 ・そして、八〇歳、九〇歳になっても元気な人たちは明治生まれの人たちであり、現代の食生活で育った人たちではないのだ。 第3章 食原病時代の食事法 カタカナ食品からひらがな食品へ転換せよ 口から入る「食原病」が急増 ガンと食事療法 ・一品健康法や健康食品を追い廻す患者さんは、日々の食生活を見直すことをしない。ビタミン類やミネラル類の不足した食生活をしながら、せっせと高価なビタミン、ミネラルの錠剤を胃袋に詰め込んでいるのだ。そのために、いつまでたっても病気は治らない。 ・食生活そのものを見直した上で、健康食品の利用を考えるべきなのである。 ・日々の食生活にふれずして「これさえ食べれば病気は治る」などという食品は選ぶべきではない。そのような健康食品に、効果は期待できないと思うべきであろう。 「万能の食物」なんてない ・「現代人はビタミンCが不足しています。ビタミンCの補給は〇〇で」といったコマーシャルを耳にするが、不足を何かで補うことよりも、不足しないように毎日の食生活を心がける、その方が大切だ。 ・「これさえ飲めば、これさえ食べれば」という特別な食物や栄養素、魔法の食物を追い求めるよりも、身近な毎日の食生活に問題はないか――そのことに目を向けてほしい。 「カタカナ食品」から「ひらがな食品」へ転換 国籍も季節も失われた食生活 ・日本人は古い時代から動物性食品の少ない食生活をしてきたが、だからといって、世界の民族の中で特別にからだが弱いとか、骨がもろいということはなかった。 ・どの民族も気候風土の条件のなかで食べられるものを食べてきた結果で、「バランスよく何でも食べる」という食生活ではなくても、そのために民族が絶えることはなかった。 ・「多品目の食品をバランスよく食べることが健康の秘訣」という考え方に惑わされる必要がないことを、あえて強調したい。 「食原病」を防ぐ一〇箇条 ①ご飯はきちんと食べる ②穀類は未精製のものに 胚芽米、 ③副食は野菜中心にする 野菜、海草類、芋類、キノコ類。 ④発酵食品を食べる みそ汁、漬物、納豆など。 ⑤肉類を減らす ⑥揚げ物は控えめに ⑦白砂糖の入った食品はさける ⑧砂糖や塩は未精製の物を使う ⑨できるかぎり安全な食品を選ぶ ⑩食事はゆっくりよく噛んで 第4章 現代型栄養失調の改善策 今の食生活は不完全燃焼を起こしている 一億総 "現代型栄養失調" の時代 エントツが詰まる「便秘」は万病のもと ・食物繊維が不足すると、糖尿病や胆石、大腸ガンなどのリスクも高くなると指摘されている。 慢性病が急増している原因 ・最大の原因は、継続的な微量栄養素の欠乏である。各種ビタミン、ミネラル類である。 ・この「微量栄養素」というのは、食べたものを円滑に代謝させるために必要なもので、人間に不可欠で特別なもののことである。 ・なぜ、複雑な "複合栄養失調" になっているのだろうか。 ・なんといっても大きいのは、精白食品の増加だ。 ・精白食品とは、白米、真っ白く精白された麦でできたパン、うどん、菓子類、スパゲティ、マカロニなど、そして、白砂糖、精製塩などである。 ・これらの食物はいずれの場合も、精製、精白されたことによって捨てられるのは、各種ビタミン、ミネラル類、食物繊維などだ。 精製食品が起こす恐い現代型栄養失調 新しいタイプの栄養失調が急増 ・ビタミンやミネラルといった微量栄養素は、食べたものを円滑に代謝させるためになくてはならない栄養素である。 ・例えば、カルシウムが骨に沈着するためには、ビタミンDと筋肉の運動が必要だし、ご飯を分解してエネルギーに変えるためにはビタミンB1が必要といったように、微量栄養素が不足していると、いくら食物を食べても、体内で有効に使われず、栄養失調になってしまう。 ・微量栄養素にはどんな種類のものがあるのか、何が不足しているのかといったことは、まだ完全には分かっていない。 ・微量栄養素が何種類あるかが解明されていないのに、不足している栄養素を知ることなど無理。 ・だから、不足したものを補うのではなく、微量栄養素が不足しないような、食品や調理法を選ぶことが大切なのである。 第5章 FOODは風土が決める 今こそ「伝統食」を見直せ 「粗食」には欠かせないこの伝統食 「丸ごと食べる」のが粗食の本質 ・蕎麦、米(玄米)、小麦粉 塩(にがり入り)、黒砂糖 魚 ・真っ白な米、真っ白な小麦粉、真っ白な塩、真っ白な砂糖・・・・・・。不完全な食べ物をいくら組み合わせても、不完全でしかない。 ・「もったいない」こそ、食生活の最高の知恵である。そのことを理解しなければ、現代の食生活の問題点は見えてこないのである。 ・「丸ごと食べる」ことこそ、素材を生かした食物、「素食」――これが「粗食」の本来の意味である。 みそ汁は医者殺し ・国立がんセンター研究所の平山雄博士の調査「みそ汁と胃がんの関係」によると、 胃ガンで死亡する率は、「毎日飲む」人が一番低く、「ときどき飲む」から「あまり飲まない」「ほとんど飲まない」人となるほど高くなり、「みそ汁ゼロ」の人の胃ガン死亡率は「毎日」の人より五〇%も高いと発表している。 ・さらにこの調査では、味噌汁が胃潰瘍、虚血性心臓病、肝硬変などの死亡率も下げていることを明らかにしている。 ・理由 ①みそ汁の原料である大豆に抗ガン作用がある。 ②みそは良質の栄養源として、からだの抵抗力を高める。 ③みそ汁の具の野菜類に、胃ガンを減らす作用がある。 漬物は最上の整腸財 ・塩さえ減らせば健康になれると考えている栄養士の人たちは、減塩運動に、伝統食の崩壊、食文化の否定につながる側面があることに気付いているのだろうか。 ・日本には、日本酒、みそ、醤油、酢といった醗酵食品があり、四季折々の野菜が豊富にある。そのため漬物の歴史は古い。 ・その中で是非見直したいのが糠漬けだ。糠には、ビタミン、ミネラルなどの微量栄養素が豊富に含まれている。 ・そして、もっとも大切なことは、わずか二グラム程度の糠に二億以上もの乳酸菌が生きているということだ。 ・私たちの腸内には約一〇〇種類、一〇〇兆以上もの細菌が住みついているといわれる。 ・それらの細菌を働きの面で大きく分類すると、乳酸菌と腐敗菌、病原菌と非病原菌、ビタミン生成菌と消費菌に分けられる。腐敗菌が増えると、腸の内容物は腐敗し、インドール、スカトール、アンモノアなどの有害物質が増えることになる。また、これらの物質が腸で吸収されることによって、ガンをはじめとしたさまざまな病気の原因になっていると考えられている。 ・しかし、乳酸菌をしっかりとっていると、腸内の酸性度が高まるため、酸に弱い腐敗菌は抑制される。そのため、昔からお腹を壊したときなど、糠床の糠をお湯に溶いて飲む習慣があった。素晴らしい知恵である。地方によっては、クサヤの漬け汁を飲むなどという話も耳にする。 ・一見「粗食」に見える食生活でも日本人が元気に働いてきたのは、小さな小さな微生物の助けがあったからである。それらの微生物と共存し、多くの醗酵食品を利用してきた祖先の知恵の深さには驚くばかりである。 第6章 食生活改善の主役はご飯 主食の米と旬の野菜が「粗食」の原点 米こそ「粗食」を支える原動力 “地球の健康” のためにも主食は米 ・以前、ローマでの世界食糧会議で開発途上国から「先進国が国内の食糧生産をおろそかにし、世界の食料を買いあさり、国際価格を上昇させ、外貨準備のない国を苦しめている」という非難が出た。 ・私たち日本人は、米という素晴らしい主食がありながらそれを食べず、国家レベルでコメの生産を制限し、飢えに苦しむ人たちを尻目に金にものをいわせ、穀物を買いあさって家畜に与え、その肉や牛乳、乳製品をむさぼり食べているのだ。 いまこそ主食――米を見直す ・必要な栄養を摂るためには、副食なしでは一日茶碗一〇杯ぐらいご飯を食べる必要がある。それがあまりにも少ないと、自然にお菓子や油ものを食べたくなってしまうのである。 玄米の食物繊維の効力 ・食物繊維の働きの中で最も注目されているのは、抱水能(水を吸収してゲル状になる性質の強さ)だ。 ・便は小腸から大腸へ入っていく液状の内容物が結腸で水分が適度に取り除かれ、密度の高い状態になったもの。なんらかの理由で水分の吸収がうまくいかない場合が下痢だ。 ・逆に、腸の内容物に食物繊維が不足すると、内容物中の水分は取り除かれ過ぎて、便は小さく固いものになる。このことが直接的には便秘の原因になっている。 ・食物繊維のこの抱水能という働きがあってはじめて腸内容物の容積を保ち、便のやわらかさを保つことができるわけである。 ・この便のやわらかさというのは、水を飲んだりしても役には立たない。食物繊維が十分にない限り、飲んだ水は腸から吸収されて、尿中に排泄されるだけだ。 ・実際に玄米食にしてみると、速い人では数日間で快適な便通を経験できる。 第7章 今、子どもと若い女性の「食生活」が危ない! 学校給食、カタカナ食品は「造病食」 若い女性に「慢性病五点セット」が急増 子どもの「食生活」が危ない 子どもの食生活改善一〇箇条 ①ご飯をしっかり食べる ②飲み物で満腹にしてはいけない 飲ませるなら、水や麦茶、番茶、ほうじ茶、野草茶など食事に影響を与えないものに。 ③パンの常食はやめる ④おやつは主食に近いものを優先する 穀類や芋類などがベスト。甘い菓子類は極力避ける。 ⑤未精製の穀類にする ⑥副食は季節の野菜を中心にする ⑦発酵食品をきちんと食べる ⑧肉類よりも魚介類にしよう ⑨揚げ物は控えめにする ⑩食事はゆっくりと噛んで 若い女性の「食生活」が危ない "五点セット" は現代型栄養失調症 ・食生活が原因とみられる病気、症状をもつのは、その八〇パーセント以上が女性である。 ・「慢性病五点セット」(生理不順、冷え性、便秘、貧血、肌荒れ)、この "現代型栄養失調症" が若い女性に非常に増えている。 第8章 間違いだらけの食事常識 食事健康法、食事、食生活のウソ、ホント 「〇〇を食べて健康になる」は本当か 食事療法は心理的効果も期待 ・塩分のとり過ぎで高血圧になったのは、冷蔵庫のなかった昔のことで、今の高血圧の原因は別のところにあると思う。 間違いだらけの食事法、食生活常識 牛乳で骨粗しょう症が予防できるか? ・結論からいえば、牛乳を飲んで骨が丈夫になることはないし、また牛乳を飲まなければ骨が脆くなるということもない。むしろ、乳糖不耐症のことを考えると、逆なのではないかと考えられる。 ・すきっ腹で牛乳を飲んだりすると、下痢をしたりお腹にガスがたまったり、あるいは「便通がよくなる」などという人、これが乳糖不耐症である。 ・昔から牛乳を飲む習慣のない民族は、牛乳の主成分である乳糖を消化するための酵素・ラクターゼの活性が低い。 ・上手く消化できず便がゆるくなったり、下痢をしてしまうのだ。そのため、他の植物からカルシウムを摂取しても、一緒に排泄されてしまう危険性があるのである。 ・骨粗しょう症が増加しているのは、カルシウム不足ではなく、カルシウムを上手く利用(消化)できないライフ・スタイルに原因がある。 ・極度の運動不足。筋肉を使わなければ、いくらカルシウムを摂取しても骨には沈着しない。 ・次に挙げられるのが暗闇生活である。 ・カルシウムは十分に日光を浴びないと吸収されない(ビタミンD)。 ・その上、ストレスの増加によってカルシウムを溶かすための胃酸の分泌が悪くなっていることも考えられる。 ・骨粗しょう症は、牛乳を飲めばよいという話ではない。まさに現代人のライフ・スタイルへの警告なのである。 ―― 完 ―― |